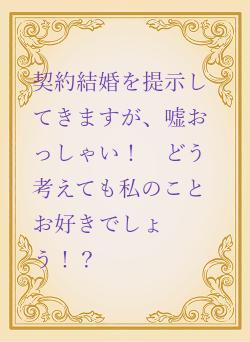別の日に、お守り用の布を買いに行って、ちくちく縫い合わせました。裁縫は萩原の家ではやらせてもらえず、女中たちの目を盗んで、月のものの時に使う当て布を作るだけで精一杯だったので、人に売るようなものを作るのに、しばし練習を重ねましたが、やはり椎名の家では自分の着物はすべて自分で縫っていましたので、勘を取り戻すことができれば、難しくはありません。
芙蓉さんに踊りの練習を見てもらい、身体を休めながら裁縫をし、身体が回復すれば一人で踊りの練習をするのを、ひたすらに繰り返します。ちっとも心身共に休まないわたくしを心配して、躑躅さんに叱られたり、蘿月様に膝枕を名目に休むように指示されたりすることもありましたが、やはりと言うべきかなんと言うべきか、熱を出してしまい、この稽古も改めなくてはならないと思いました。
「無理をするのに慣れすぎているのも、困りものだな」
「自分の身体は、こんなに脆いのだと驚きました。ずっと前は、こんなに根を詰めても、風邪ひとつ引かなかったものですから」
病み上がりで、汗をかいたわたくしの頭を撫でながら、彼は淡く微笑みます。彼はわたくしがまた高熱に何日も苦しむのではないか、と心配して、よく様子を見てくれましたが、幸い、高熱というほど熱も出なかったので、彼は様子を見るたびに、ほっとしていました。そうすると、この身体はもうわたくしのものだけではない、というのは前々から変わりはしませんが、大切にするためにそれぞれ分け合って抱えているような気がして、自分の身体をよくよく大切にしなければならないと、初めて感じたのです。
「芙蓉は、お前が寝込んでいる間、振り付けを考えてくれているそうだ」
「それは、とてもありがたいです」
さ、少し水を浴びてきなさい。そう勧められて、裏で水を浴び、嫌な汗を洗い流します。するとどろりと足の間から血が垂れてきて、また月のものがはじまったと気が付きます。子が出来てしまえば良いのに、と思ってしまうのは、お母様が子どもが出来ないばかりに冷遇されたためでしょう。子が出来ないのは、世が江戸から明治から変わっても、女の責任です。男の子が欲しい家で女しか生まれなかったとしたら、それも女が責められます。子は男と女で作るというのに、すべてすべて、女が悪いことになります。最初は男の子を生んでくれと願ったところで、生まれる子の性別を決めるのは、神様と呼ばれるような存在でありますから、女がどれほど望んでも変わることはないのです。しかし、世の中はそういうものですから、お母様はあのような扱いを受けたのでしょう。
蘿月様は、子を作るための母体を欲しがっているわけではありませんし、わたくしという人間を愛してくださっているわけですから、子の有無はわたくしへ注がれる愛に変わりはしないと分かっているのですが、やはり未だに、お母様が生家で冷たく扱われてきたことが、深い傷として、わたくしの中に残っているようでした。
そもそも、神様と人間の間に子は出来るものなのでしょうか。これまでのわたくしがどうだったのか、聞くにはいくらか勇気が要りますが、機を見つけて聞いてみようと思いました。十四のお前にはまだ子は早いよ、もう少し大人になってからにしよう、と言われるであろうことも分かっているのですが、やはり子のいない家庭というのは、明治に変わった世でも哀れみを向けられてしまいますので、もし子ができるのであれば、いずれは欲しいと思いました。
じくりじくりと痛みを持ち始める下腹部を抑えながら、湯あみを済ませ、新しい浴衣を着ます。月のものの痛みに効くものが何かないか、躑躅さんに尋ねたところ、芍薬が効くらしいとのことでしたので、薬屋で芍薬を買ってきてもらうことにしました。躑躅さんが慌てふためいて帰ってきたのは、それからすぐのことでした。
「大変よ、大変。芙蓉が住んでる長屋一体が火事よっ」
「なんだって」
「芙蓉さんは?」
「探してもいないの!」
躑躅さんの綺麗な着物は煤だらけで、燃えている長屋の中に入って、芙蓉さんが中で逃げ遅れていないか確かめてくれたようでした。辺り一帯を探したようですが、それでも見つからず、それで一度蘭麝神社に戻ってきたようでした。わたくしも腹痛をおして、芙蓉さんのいる長屋の方に向かい、燃え盛る長屋と、泣き叫ぶ人々と、崩れ落ちていく人と言えを見たのですが、その光景は恐ろしく、芙蓉さん、芙蓉さん、と呼ぶだけで精一杯でした。
「きっと買い物に行っているんだよ」
そう結論づけたのは、蘿月様でした。火を広げないために、街の人や消防組を名乗る人たちが動き回っている最中のことです。わたくしは、女は役に立たないからどいてくれと、あちこちから水を運んでくる人たちに押しのけられ、呆然と、火のまだ回っていない道端に座り込んでいたものですが、彼に支えられ、立つように促されます。
「きっとそうだよ」
きっと、安全なところにいると、信じる他ないのですが、無事な様子を見るまでは安心できない、というのが本音です。しかし蘿月様が、一生懸命わたくしを励ましてくれているのは分かりましたから、わたくしはただ静かに頷きました。
「やっぱり、いないわ。どこ探してもいない。ついでに逃げ遅れた男の子助けちゃったんだけど、そしたらお団子たくさん買ってもらったわ」
躑躅さんはまだ芙蓉さんを探してくれたようで、はやり煤だらけでした。うつくしい服のところどころが黒焦げになっていましたが、男の子を助けたという彼女の横顔は凛々しく、汚らしさはありません。なんて格好いいのだろうとは思いましたが、わたくしは無力な人間な女ですので、やはり待つしかないようでした。
「住むところがなくなったら、きっと神社に来るさ」
「そうよ。あの子、強かに生きてるもの。そう簡単に死にやしないわよ」
「そう、ですね」
火事、というものは珍しくありません。江戸の時も火事が多かったという話ですし、家々が木造である限りは、一度火がつけば燃え広がるものでしょう。未だに子供も大人も、病や事故ですぐに死んでしまいますし、仇討ちもなくなりませんし、人の死というものは、あまり恐れすぎると、生きづらいのかもしれません。ですが、どうか生きていてと、誰も死なないでと、願わざるを得ないのでした。
帰りに芍薬を買ってもらい、屋敷に帰ってから煎じて飲み、団子を食べました。わたくしが熱がぶり返して横になっている間に、ふすまを一つ挟んだ向こう側で、躑躅さんと蘿月様の話す声が聞こえます。二人とも小声ではありましたが、耳を澄ませれば聞こえる声量がありました。
「あの火事、志貴が噛んでなければいいんだけれどな」
「あたしは椎名のガキんちょが関わってそうだと思ってるけど」
「そうだな。あの家は父親も義母も悪どいことをするのだろう。子たちは見事に善悪が分からぬまま育ったようだ。十分、あり得るな」
「芙蓉が巻き込まれていなければ、良いのだけれど」
「巻き込まれていたら琥珀が気にする」
躑躅さんが、彼女の怨敵に舌打ちをします。きっと怖い顔をしているのだろうと思いましたが、躑躅さんの怖い顔を、わたくしの頭の中で作ることが出来ませんでした。
「俺は明日の夜にでも、志貴を殺しにいくつもりだ」
「調整は十分?」
「かろうじて、な。本当はもう少し、やりたいのだが。待っていては琥珀が危なくなる」
「あんまり先延ばしにすると、琥珀と出来ないもんね」
躑躅さんの揶揄う声に、ぶっと蘿月様がお茶を噴き出したようでした。げほげほ、咽る声が聞こえます。わたくしの顔からも湯気が出そうになりますが、起きていると知られたくないため、じたばた転がりたくなるのを耐えます。
「いや、あれは、志貴にまたとられないためであって、その。本当は、身体の負担を考えると、その」
「あーはいはい。二千年経っても初心だったのねごめんねー」
「とにかく、明日の夜に向かうからな。俺は今から少し、山で鬼やら怨霊やらを狩ってくる。琥珀を頼んだ。あれは今までの我が妻の中で、一番脆い」
「分かってるわよ」
蘿月様が立ち上がる音がして、きっと躑躅さんがじきに様子を見に来ると思い、わたくしは寝ているふりをするべく目を閉じます。すると、疲労を訴えていた身体が、やっと眠れると喜んで、わたくしはそのまま、眠りの世界に落ちました。
芙蓉さんに踊りの練習を見てもらい、身体を休めながら裁縫をし、身体が回復すれば一人で踊りの練習をするのを、ひたすらに繰り返します。ちっとも心身共に休まないわたくしを心配して、躑躅さんに叱られたり、蘿月様に膝枕を名目に休むように指示されたりすることもありましたが、やはりと言うべきかなんと言うべきか、熱を出してしまい、この稽古も改めなくてはならないと思いました。
「無理をするのに慣れすぎているのも、困りものだな」
「自分の身体は、こんなに脆いのだと驚きました。ずっと前は、こんなに根を詰めても、風邪ひとつ引かなかったものですから」
病み上がりで、汗をかいたわたくしの頭を撫でながら、彼は淡く微笑みます。彼はわたくしがまた高熱に何日も苦しむのではないか、と心配して、よく様子を見てくれましたが、幸い、高熱というほど熱も出なかったので、彼は様子を見るたびに、ほっとしていました。そうすると、この身体はもうわたくしのものだけではない、というのは前々から変わりはしませんが、大切にするためにそれぞれ分け合って抱えているような気がして、自分の身体をよくよく大切にしなければならないと、初めて感じたのです。
「芙蓉は、お前が寝込んでいる間、振り付けを考えてくれているそうだ」
「それは、とてもありがたいです」
さ、少し水を浴びてきなさい。そう勧められて、裏で水を浴び、嫌な汗を洗い流します。するとどろりと足の間から血が垂れてきて、また月のものがはじまったと気が付きます。子が出来てしまえば良いのに、と思ってしまうのは、お母様が子どもが出来ないばかりに冷遇されたためでしょう。子が出来ないのは、世が江戸から明治から変わっても、女の責任です。男の子が欲しい家で女しか生まれなかったとしたら、それも女が責められます。子は男と女で作るというのに、すべてすべて、女が悪いことになります。最初は男の子を生んでくれと願ったところで、生まれる子の性別を決めるのは、神様と呼ばれるような存在でありますから、女がどれほど望んでも変わることはないのです。しかし、世の中はそういうものですから、お母様はあのような扱いを受けたのでしょう。
蘿月様は、子を作るための母体を欲しがっているわけではありませんし、わたくしという人間を愛してくださっているわけですから、子の有無はわたくしへ注がれる愛に変わりはしないと分かっているのですが、やはり未だに、お母様が生家で冷たく扱われてきたことが、深い傷として、わたくしの中に残っているようでした。
そもそも、神様と人間の間に子は出来るものなのでしょうか。これまでのわたくしがどうだったのか、聞くにはいくらか勇気が要りますが、機を見つけて聞いてみようと思いました。十四のお前にはまだ子は早いよ、もう少し大人になってからにしよう、と言われるであろうことも分かっているのですが、やはり子のいない家庭というのは、明治に変わった世でも哀れみを向けられてしまいますので、もし子ができるのであれば、いずれは欲しいと思いました。
じくりじくりと痛みを持ち始める下腹部を抑えながら、湯あみを済ませ、新しい浴衣を着ます。月のものの痛みに効くものが何かないか、躑躅さんに尋ねたところ、芍薬が効くらしいとのことでしたので、薬屋で芍薬を買ってきてもらうことにしました。躑躅さんが慌てふためいて帰ってきたのは、それからすぐのことでした。
「大変よ、大変。芙蓉が住んでる長屋一体が火事よっ」
「なんだって」
「芙蓉さんは?」
「探してもいないの!」
躑躅さんの綺麗な着物は煤だらけで、燃えている長屋の中に入って、芙蓉さんが中で逃げ遅れていないか確かめてくれたようでした。辺り一帯を探したようですが、それでも見つからず、それで一度蘭麝神社に戻ってきたようでした。わたくしも腹痛をおして、芙蓉さんのいる長屋の方に向かい、燃え盛る長屋と、泣き叫ぶ人々と、崩れ落ちていく人と言えを見たのですが、その光景は恐ろしく、芙蓉さん、芙蓉さん、と呼ぶだけで精一杯でした。
「きっと買い物に行っているんだよ」
そう結論づけたのは、蘿月様でした。火を広げないために、街の人や消防組を名乗る人たちが動き回っている最中のことです。わたくしは、女は役に立たないからどいてくれと、あちこちから水を運んでくる人たちに押しのけられ、呆然と、火のまだ回っていない道端に座り込んでいたものですが、彼に支えられ、立つように促されます。
「きっとそうだよ」
きっと、安全なところにいると、信じる他ないのですが、無事な様子を見るまでは安心できない、というのが本音です。しかし蘿月様が、一生懸命わたくしを励ましてくれているのは分かりましたから、わたくしはただ静かに頷きました。
「やっぱり、いないわ。どこ探してもいない。ついでに逃げ遅れた男の子助けちゃったんだけど、そしたらお団子たくさん買ってもらったわ」
躑躅さんはまだ芙蓉さんを探してくれたようで、はやり煤だらけでした。うつくしい服のところどころが黒焦げになっていましたが、男の子を助けたという彼女の横顔は凛々しく、汚らしさはありません。なんて格好いいのだろうとは思いましたが、わたくしは無力な人間な女ですので、やはり待つしかないようでした。
「住むところがなくなったら、きっと神社に来るさ」
「そうよ。あの子、強かに生きてるもの。そう簡単に死にやしないわよ」
「そう、ですね」
火事、というものは珍しくありません。江戸の時も火事が多かったという話ですし、家々が木造である限りは、一度火がつけば燃え広がるものでしょう。未だに子供も大人も、病や事故ですぐに死んでしまいますし、仇討ちもなくなりませんし、人の死というものは、あまり恐れすぎると、生きづらいのかもしれません。ですが、どうか生きていてと、誰も死なないでと、願わざるを得ないのでした。
帰りに芍薬を買ってもらい、屋敷に帰ってから煎じて飲み、団子を食べました。わたくしが熱がぶり返して横になっている間に、ふすまを一つ挟んだ向こう側で、躑躅さんと蘿月様の話す声が聞こえます。二人とも小声ではありましたが、耳を澄ませれば聞こえる声量がありました。
「あの火事、志貴が噛んでなければいいんだけれどな」
「あたしは椎名のガキんちょが関わってそうだと思ってるけど」
「そうだな。あの家は父親も義母も悪どいことをするのだろう。子たちは見事に善悪が分からぬまま育ったようだ。十分、あり得るな」
「芙蓉が巻き込まれていなければ、良いのだけれど」
「巻き込まれていたら琥珀が気にする」
躑躅さんが、彼女の怨敵に舌打ちをします。きっと怖い顔をしているのだろうと思いましたが、躑躅さんの怖い顔を、わたくしの頭の中で作ることが出来ませんでした。
「俺は明日の夜にでも、志貴を殺しにいくつもりだ」
「調整は十分?」
「かろうじて、な。本当はもう少し、やりたいのだが。待っていては琥珀が危なくなる」
「あんまり先延ばしにすると、琥珀と出来ないもんね」
躑躅さんの揶揄う声に、ぶっと蘿月様がお茶を噴き出したようでした。げほげほ、咽る声が聞こえます。わたくしの顔からも湯気が出そうになりますが、起きていると知られたくないため、じたばた転がりたくなるのを耐えます。
「いや、あれは、志貴にまたとられないためであって、その。本当は、身体の負担を考えると、その」
「あーはいはい。二千年経っても初心だったのねごめんねー」
「とにかく、明日の夜に向かうからな。俺は今から少し、山で鬼やら怨霊やらを狩ってくる。琥珀を頼んだ。あれは今までの我が妻の中で、一番脆い」
「分かってるわよ」
蘿月様が立ち上がる音がして、きっと躑躅さんがじきに様子を見に来ると思い、わたくしは寝ているふりをするべく目を閉じます。すると、疲労を訴えていた身体が、やっと眠れると喜んで、わたくしはそのまま、眠りの世界に落ちました。