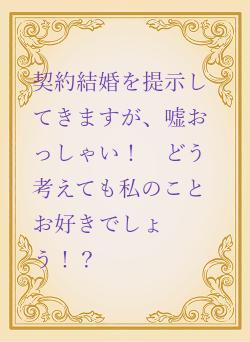一週間もすると、少しずつ身体が動くようになってきまして、ぎこちない動きではありますが、だんだん踊りらしくなってきました。巫女服の変わりに男物の袴を纏い、練習を続け、芙蓉さんが帰った後も、ひたすらに続けます。わたくしがあまりにも自分の身体の限界を無視するので、よく躑躅さんや蘿月様に両脇を抱えられて、居間に座らされることもしばしばありましたが、目標があって、そのために取り組んでいることがあるということも、充実していましたし、何を始めるにも遅くない、という芙蓉さんの言葉は、わたくしの背を押してくれました。
わたくしがこうして踊りの練習に明け暮れていると、志貴様がお義母さんやほたるを使って、わたくしを取り戻しに来ようとしていることを、少しだけ、忘れることが出来ました。舞が上手になるたびに、これを街の人に披露して、蘭麝神社にいる舞のうつくしい巫女として認識されれば、少しは志貴様や椎名の家の者たちにとって、手を出しにくい存在になれるのではないかと思えて、安心し、そしてまた、踊りにのめり込みました。
「筋肉痛も、もうほどんどならなくなりました」
「良かったわね」
だけど、本当に無理はしないでね。躑躅さんはそう言って、ご飯を多くよそってくれます。今日は芙蓉さんと踊りの稽古をする日ではないのですが、今日も踊りをするつもりで、一生懸命食べていると、蘿月様に、「今日は踊りは休んで、お守りの布を買いに行かないか」と言われました。
「布屋に行って、合う布を探してくるんだ。お守りも作りたい、と言っていただろう」
「良いのですか」
「お前はそうでもしないと、休まないだろう」
で、でも、と言い淀みましたが、休むのも踊りのうち、と言われてしまいまして、身体の節々が疲れて、悲鳴を上げていることに気が付いてしまうのでした。
「蘿月もね、ここんところずっと山に籠っているでしょう。あんたと一緒に出掛けたいんですって」
蘿月様が照れながら頷きますので、なんだかわたくしまで照れくさくなってしまいまして、小さく頷きました。ここしばらく、わたくしも蘿月様も、己の鍛錬ばかりしていましたので、共に話し、共に歩く時間が減っていたようにも思います。それは寂しいことでありましたから、一緒にいる時間を作ってくれたことを、嬉しく思いました。
朝食の後、出かけるために身支度をしていた時でした。お祓いを受けたいのです、という声が神社の中に響き、わたくしの髪を結っていた躑躅さんが、さっと顔を上げました。嫌な臭いがする、そんな呟きが聞こえます。
声に聞き覚えがあり、わたくしは決して表には出ず、お屋敷の押し入れの中に隠れることにしましたが、蘿月様も何か嫌な気配を感じたようでした。耳ばかり澄ませていると、かすかに、叫び声をあげるお客様の懺悔が聞こえてきます。
懺悔です、これは、懺悔です。私は椎名という、横浜の男爵家で雇われていた女中のあやでございます。ええ、きっと、ご子息様たちがいらしたでしょうね。彼らの代わりにお詫び申し上げます。お詫び申し上げます。私は彼らに遣わされたのではなく、ええ、もう、首を飛ばされてしまいましたので、こうして、己の罪を洗いざらい、話に来た次第にございます。
何かと思い、そっと押し入れを這い出て、声の聞こえるところに寄ってみると、今度はくっきりと、懺悔の言葉が聞こえるようになりました。
ああ、神主様、それとも神様でしょうか。私をそのような目で見ないでください。蔑まれる覚悟はしてまいりましたが、やはり辛うございます。いえ、蔑まれて当然ではあるのですが。私はもとより、琥珀様のお母上の嫁入りの際に、共に遣わされた女中ですので、彼女を守らなければならなかったのですが、私は椎名の旦那様にお金を握らされ、琥珀様を虐げるように命じられました。私は本来、彼女を守らなくてはならない立場であったのに関わらず、彼女が泣き声をあげ、縋るような目でこちらを見てくる度に、庭の隅に隠れて泣いている度に、心の中が喜びでざわめくようになりました。私も椎名の家では、奥様側の人間だったため、それまではひどい扱いを受けていたのですが、一変して優遇されるようになり、自分より可愛そうな人間を見ることで、自分が少しばかり、ましな人間であるように思いました。そうして、いつの間にか、お嬢様を虐げることを日々の喜びとしました。ですから、ええ、お嬢様が嫁いだ時は、ひどく悲しくなったものです。ほたる様も、新しい奥様も、皆つまらなそうでした。その退屈の矛先は私に向き、今度は私が、殴られ蹴られと、同じ扱いを受けたのです。そうして私は私の罪を自覚し、琥珀様のことを思い浮かべました。
椎名の家が滅びるのは、自らの行いのためです。しかし琥珀様、私はあなたに、とても酷いことをしました。懺悔、懺悔させていただきたく――。
「言いたいことはそれだけか」
蘿月様の低い声が、懺悔を遮りました。ああ、これは酷く怒っている。そう分かるには十分すぎるほどの棘を含むそれは、あやを静かにさせました。
「貴様、自分の行いが自分に返ってきただけだろう。ここに琥珀という人間はいない。あのガキどもにも伝えておけ。だが、まあ、椎名の家とやらはよほど汚い場所だったのだろう、お前の身体には醜い鬼や悪霊やらが大量にひっついている。ふん、それだけはとってやろうじゃないか」
「私の残り少ない財産ですが、皆あなたにお渡しします。私が人生をやり直せるよう、すべてすべて、落としてくださいませ」
蘿月様はすぐにお祓いを始めるのだろうと思いましたが、その前に、屋敷の中に隠れているわたくしの姿を見に来ました。
「お前はよく耐えてきたな」
それだけ言い残して、彼は神職のような態度で戻っていき、躑躅さんが入れ替わりで入ってきます。躑躅さんはわたくしが泣き出すと思ったようで、隣に座って肩を抱きかかえながら、「ほんとに追い出されたみたい。随分大荷物だったし、ぼろぼろだったわ」と言いました。
「謝るくらいなら、最初から、わたくしの味方でいてくれれば良かったのに」
「仮にあんた、あいつの前に出るとしたら、謝罪を受ける?」
わたくしは曖昧に微笑みました。言うか言うまいか悩んで、それから、躑躅さんの耳に、口を寄せます。醜い言葉かもしれませんが、躑躅さんになら話して良いと思いました。
「わたくしはきっと、その場で謝られたら、許してしまうと思うのです。ですが、謝って、あやが気持ちよくなるだけです」
あやは、自分だけが許されるためにここに来ました。わたくしを必死に守って育ててきたお母様の意思をないがしろにし、己の欲に、己の保身のために、わたくしを虐げることを選びました。そのくせ、自分だけは許されて、新たな人生を歩もうとするのは、はっきりと言って、許せませんでした。胸の奥が苦いようで、熱いようで、冷たいようで、ああ、憎らしいと思いました。ただ、あまりの彼女の都合の良さに呆れかえってしまい、怒る気も湧いてきませんが、きっと後から、それこそ数か月数年経ってから、わたくしは彼女をひどく恨むのでしょう。ですが一度許してしまったら、その後も許さなければいけませんので、彼女を恨めしいと思う気持ちを、わたくしは責めることになるのだと思います。それでは、わたくしが生涯苦しむことが決まってしまいますから、仮にあやがわたくしを見つけて、地面に頭をこすりつけて謝ったとしても、許さない方がいいのだと思います。ですがわたくしはやっぱり弱いので、謝られたら許すと言ってしまいます。ですから、彼女には今後一切、会わない方がいいのだと思いました。
「恨むのも苦しいけれど、恨めないのも苦しいのよね。でも絶対、許したら苦しむのがあんただけになる。それで良いと思うのよ、あたし」
「ありがとうございます」
「それにしても、ろくでなしね、あいつ。どれだけろくでなしだったらあんなに悪いもの連れてくるのよ。あんたの妹弟たちも悪いもの下げてきてたけど、あの女中は最悪よ。これはお祓いもかかるわね」
今日出かけられなくて気の毒ねぇ、と躑躅さんがわたくしの頭を撫で、整えたもらったばかりの髪型を褒められました。よく似合ってるわね、と。リボンもいくつか揃えたらもっと良いわね、と。
「ねえ、躑躅さん。きっと蘿月様には難しいでしょうから、躑躅さんにお願いするのですが。わたくし、やっぱり生家の方々に縋りつかれたら、許してしまうと思うのです。もしそんなことになったら、わたくしを止めてくださいますか」
「ええ、もちろん。あんなやつら許してあげることなんてないわ、って連れて帰ってあげる。蘿月にぎゅってされたら、あんたも我に返るわよ。あんたは絶対、蘿月の元に帰りたいって願うはずだから」
あたしはね、あんたが蘿月と幸せに生きていくために、二千年も生きてんのよ。それくらいやってあげる。彼女はそう言って、ふわりと笑いました。そうしたらなんだか安心して、怖いことが少し減ったように思えます。
お昼ご飯どうしましょうかねぇ、と彼女と話していると、蘿月様が戻ってきて、すぐに悲しそうな目でわたくしを見下ろしました。ああ、なんだか、泣き出しそう。そう思った時には抱きしめられていて、わたくしは慌てて「お祓いは済んだのですか」と聞くと、彼はうんともいいやともつかない、曖昧な返事をします。
「嘘下手すぎ。おバカさんね」
「と、いうことは」
「お祓いは、した。俺の刀に相性の良い呪いは、吸い取った」
「他をやってないのよ。してないならしてないで、かっこつけなさいよ、琥珀に心配かけたいの?」
「すまない」
彼はぽつぽつと、せいぜい肩こりが長らく消えないくらいだとか、寝つきが悪いだとか、それくらいで、これまで生きてきたのなら生死には関りはしないだろう、と一生懸命言い訳していました。しかしその最中で、わたくしをそっと見下ろし、「怒るか?」と尋ねてきました。その目は子供のように、子犬のように、しおれて、落ち込んでいるように見えます。いじらしい、という気持ちが沸き上がってきて、彼の頭を抱き寄せました。
「わたくし、あやにはもう呆れすぎてしまって、怒る気も起きなかったのです。わたくしの代わりに、怒ってくださったのですよね。なんだか、かえって、落ち着きました」
「そういうことに、してくれるか」
「はい。そういうことに、しましょう。でも次は、なしですよ」
わたくしにきちんと隠してくださいね。そう言うと、彼はこくこくと頷いて、わたくしの頭を撫でるのでした。
「案外、蘿月でも出来そうじゃない?」
「そうですね、そうかもしれません」
「何の話だ?」
「何でもありません。ね、躑躅さん」
「ねー」
微笑むと、蘿月様が首を傾げます。わたくしの頭を撫でる彼の手を触れて、ああ、愛おしいと思いました。
わたくしがこうして踊りの練習に明け暮れていると、志貴様がお義母さんやほたるを使って、わたくしを取り戻しに来ようとしていることを、少しだけ、忘れることが出来ました。舞が上手になるたびに、これを街の人に披露して、蘭麝神社にいる舞のうつくしい巫女として認識されれば、少しは志貴様や椎名の家の者たちにとって、手を出しにくい存在になれるのではないかと思えて、安心し、そしてまた、踊りにのめり込みました。
「筋肉痛も、もうほどんどならなくなりました」
「良かったわね」
だけど、本当に無理はしないでね。躑躅さんはそう言って、ご飯を多くよそってくれます。今日は芙蓉さんと踊りの稽古をする日ではないのですが、今日も踊りをするつもりで、一生懸命食べていると、蘿月様に、「今日は踊りは休んで、お守りの布を買いに行かないか」と言われました。
「布屋に行って、合う布を探してくるんだ。お守りも作りたい、と言っていただろう」
「良いのですか」
「お前はそうでもしないと、休まないだろう」
で、でも、と言い淀みましたが、休むのも踊りのうち、と言われてしまいまして、身体の節々が疲れて、悲鳴を上げていることに気が付いてしまうのでした。
「蘿月もね、ここんところずっと山に籠っているでしょう。あんたと一緒に出掛けたいんですって」
蘿月様が照れながら頷きますので、なんだかわたくしまで照れくさくなってしまいまして、小さく頷きました。ここしばらく、わたくしも蘿月様も、己の鍛錬ばかりしていましたので、共に話し、共に歩く時間が減っていたようにも思います。それは寂しいことでありましたから、一緒にいる時間を作ってくれたことを、嬉しく思いました。
朝食の後、出かけるために身支度をしていた時でした。お祓いを受けたいのです、という声が神社の中に響き、わたくしの髪を結っていた躑躅さんが、さっと顔を上げました。嫌な臭いがする、そんな呟きが聞こえます。
声に聞き覚えがあり、わたくしは決して表には出ず、お屋敷の押し入れの中に隠れることにしましたが、蘿月様も何か嫌な気配を感じたようでした。耳ばかり澄ませていると、かすかに、叫び声をあげるお客様の懺悔が聞こえてきます。
懺悔です、これは、懺悔です。私は椎名という、横浜の男爵家で雇われていた女中のあやでございます。ええ、きっと、ご子息様たちがいらしたでしょうね。彼らの代わりにお詫び申し上げます。お詫び申し上げます。私は彼らに遣わされたのではなく、ええ、もう、首を飛ばされてしまいましたので、こうして、己の罪を洗いざらい、話に来た次第にございます。
何かと思い、そっと押し入れを這い出て、声の聞こえるところに寄ってみると、今度はくっきりと、懺悔の言葉が聞こえるようになりました。
ああ、神主様、それとも神様でしょうか。私をそのような目で見ないでください。蔑まれる覚悟はしてまいりましたが、やはり辛うございます。いえ、蔑まれて当然ではあるのですが。私はもとより、琥珀様のお母上の嫁入りの際に、共に遣わされた女中ですので、彼女を守らなければならなかったのですが、私は椎名の旦那様にお金を握らされ、琥珀様を虐げるように命じられました。私は本来、彼女を守らなくてはならない立場であったのに関わらず、彼女が泣き声をあげ、縋るような目でこちらを見てくる度に、庭の隅に隠れて泣いている度に、心の中が喜びでざわめくようになりました。私も椎名の家では、奥様側の人間だったため、それまではひどい扱いを受けていたのですが、一変して優遇されるようになり、自分より可愛そうな人間を見ることで、自分が少しばかり、ましな人間であるように思いました。そうして、いつの間にか、お嬢様を虐げることを日々の喜びとしました。ですから、ええ、お嬢様が嫁いだ時は、ひどく悲しくなったものです。ほたる様も、新しい奥様も、皆つまらなそうでした。その退屈の矛先は私に向き、今度は私が、殴られ蹴られと、同じ扱いを受けたのです。そうして私は私の罪を自覚し、琥珀様のことを思い浮かべました。
椎名の家が滅びるのは、自らの行いのためです。しかし琥珀様、私はあなたに、とても酷いことをしました。懺悔、懺悔させていただきたく――。
「言いたいことはそれだけか」
蘿月様の低い声が、懺悔を遮りました。ああ、これは酷く怒っている。そう分かるには十分すぎるほどの棘を含むそれは、あやを静かにさせました。
「貴様、自分の行いが自分に返ってきただけだろう。ここに琥珀という人間はいない。あのガキどもにも伝えておけ。だが、まあ、椎名の家とやらはよほど汚い場所だったのだろう、お前の身体には醜い鬼や悪霊やらが大量にひっついている。ふん、それだけはとってやろうじゃないか」
「私の残り少ない財産ですが、皆あなたにお渡しします。私が人生をやり直せるよう、すべてすべて、落としてくださいませ」
蘿月様はすぐにお祓いを始めるのだろうと思いましたが、その前に、屋敷の中に隠れているわたくしの姿を見に来ました。
「お前はよく耐えてきたな」
それだけ言い残して、彼は神職のような態度で戻っていき、躑躅さんが入れ替わりで入ってきます。躑躅さんはわたくしが泣き出すと思ったようで、隣に座って肩を抱きかかえながら、「ほんとに追い出されたみたい。随分大荷物だったし、ぼろぼろだったわ」と言いました。
「謝るくらいなら、最初から、わたくしの味方でいてくれれば良かったのに」
「仮にあんた、あいつの前に出るとしたら、謝罪を受ける?」
わたくしは曖昧に微笑みました。言うか言うまいか悩んで、それから、躑躅さんの耳に、口を寄せます。醜い言葉かもしれませんが、躑躅さんになら話して良いと思いました。
「わたくしはきっと、その場で謝られたら、許してしまうと思うのです。ですが、謝って、あやが気持ちよくなるだけです」
あやは、自分だけが許されるためにここに来ました。わたくしを必死に守って育ててきたお母様の意思をないがしろにし、己の欲に、己の保身のために、わたくしを虐げることを選びました。そのくせ、自分だけは許されて、新たな人生を歩もうとするのは、はっきりと言って、許せませんでした。胸の奥が苦いようで、熱いようで、冷たいようで、ああ、憎らしいと思いました。ただ、あまりの彼女の都合の良さに呆れかえってしまい、怒る気も湧いてきませんが、きっと後から、それこそ数か月数年経ってから、わたくしは彼女をひどく恨むのでしょう。ですが一度許してしまったら、その後も許さなければいけませんので、彼女を恨めしいと思う気持ちを、わたくしは責めることになるのだと思います。それでは、わたくしが生涯苦しむことが決まってしまいますから、仮にあやがわたくしを見つけて、地面に頭をこすりつけて謝ったとしても、許さない方がいいのだと思います。ですがわたくしはやっぱり弱いので、謝られたら許すと言ってしまいます。ですから、彼女には今後一切、会わない方がいいのだと思いました。
「恨むのも苦しいけれど、恨めないのも苦しいのよね。でも絶対、許したら苦しむのがあんただけになる。それで良いと思うのよ、あたし」
「ありがとうございます」
「それにしても、ろくでなしね、あいつ。どれだけろくでなしだったらあんなに悪いもの連れてくるのよ。あんたの妹弟たちも悪いもの下げてきてたけど、あの女中は最悪よ。これはお祓いもかかるわね」
今日出かけられなくて気の毒ねぇ、と躑躅さんがわたくしの頭を撫で、整えたもらったばかりの髪型を褒められました。よく似合ってるわね、と。リボンもいくつか揃えたらもっと良いわね、と。
「ねえ、躑躅さん。きっと蘿月様には難しいでしょうから、躑躅さんにお願いするのですが。わたくし、やっぱり生家の方々に縋りつかれたら、許してしまうと思うのです。もしそんなことになったら、わたくしを止めてくださいますか」
「ええ、もちろん。あんなやつら許してあげることなんてないわ、って連れて帰ってあげる。蘿月にぎゅってされたら、あんたも我に返るわよ。あんたは絶対、蘿月の元に帰りたいって願うはずだから」
あたしはね、あんたが蘿月と幸せに生きていくために、二千年も生きてんのよ。それくらいやってあげる。彼女はそう言って、ふわりと笑いました。そうしたらなんだか安心して、怖いことが少し減ったように思えます。
お昼ご飯どうしましょうかねぇ、と彼女と話していると、蘿月様が戻ってきて、すぐに悲しそうな目でわたくしを見下ろしました。ああ、なんだか、泣き出しそう。そう思った時には抱きしめられていて、わたくしは慌てて「お祓いは済んだのですか」と聞くと、彼はうんともいいやともつかない、曖昧な返事をします。
「嘘下手すぎ。おバカさんね」
「と、いうことは」
「お祓いは、した。俺の刀に相性の良い呪いは、吸い取った」
「他をやってないのよ。してないならしてないで、かっこつけなさいよ、琥珀に心配かけたいの?」
「すまない」
彼はぽつぽつと、せいぜい肩こりが長らく消えないくらいだとか、寝つきが悪いだとか、それくらいで、これまで生きてきたのなら生死には関りはしないだろう、と一生懸命言い訳していました。しかしその最中で、わたくしをそっと見下ろし、「怒るか?」と尋ねてきました。その目は子供のように、子犬のように、しおれて、落ち込んでいるように見えます。いじらしい、という気持ちが沸き上がってきて、彼の頭を抱き寄せました。
「わたくし、あやにはもう呆れすぎてしまって、怒る気も起きなかったのです。わたくしの代わりに、怒ってくださったのですよね。なんだか、かえって、落ち着きました」
「そういうことに、してくれるか」
「はい。そういうことに、しましょう。でも次は、なしですよ」
わたくしにきちんと隠してくださいね。そう言うと、彼はこくこくと頷いて、わたくしの頭を撫でるのでした。
「案外、蘿月でも出来そうじゃない?」
「そうですね、そうかもしれません」
「何の話だ?」
「何でもありません。ね、躑躅さん」
「ねー」
微笑むと、蘿月様が首を傾げます。わたくしの頭を撫でる彼の手を触れて、ああ、愛おしいと思いました。