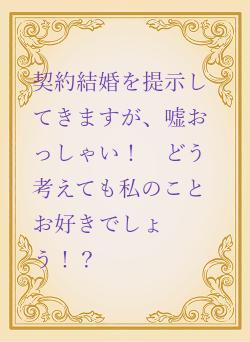翌朝の朝食の時間、志貴様に夜中に泣いていたのか、と聞かれました。咄嗟に、お母様が死んだ時の夢を見たと返したのですが、彼はそれでは納得しなかったようで、訝し気にわたくしを見ます。彼の切れ長の瞳が細くなると、また彼の気を損ねて、叩かれるのではないかと、身体がすっと冷えていくような思いがするのですが、今朝の彼は声を荒らげることも手をあげることもなく、ただ「本当かい」と聞き返しただけでした。
彼と出会った時は、彼が恐ろしいことなど、少しも知りませんでした。唯一わたくしを守り、愛してくれたお母様を喪い、悲しさと心細さでただ泣いて過ごしていた、八歳の頃に彼に出会ったものですから、わたくしに差し伸べられる手のすべてが救いであるように感じてしまったのです。
彼は薄汚れた着物を纏うわたくしを見て、まず「可哀そうな子だね」と言いました。確かその日は横浜まで妖魔退治に来ていたようで、勇ましい恰好をしていたことを、ぼんやりと覚えています。彼はわたくしより十年上ですから、当時は十八歳でありましょうか。綺麗で格好いいお兄さんが、泣いているところに声を掛けてくれたものですから、それこそおとぎ話の主人公が、わたくしを助けに来てくれたように錯覚しました。お腹いっぱい食べさせてあげよう、綺麗な着物を着せてあげよう。きっと寂しい想いはさせないよ。だからうちにおいで、もう少し大きくなったらうちにお嫁さんにおいで――。子どもにも分かりやすく利のある、子どもにとって、甘く優しい言葉を吐かれ、わたくしは縋るような気持ちで頷きました。尋常小学校を卒業したら、女学校には行かせずに、萩原――志貴様の家に棲ませるように。そう椎名の家と彼の間に約束が成立し、わたくしはその日から志貴様の婚約者になりました。
真冬の庭でほたるに冷水をかけられ、弟の金剛に気晴らしに蹴られ叩かれ、妾だったお義母様には、お茶が不味いと、淹れたばかりのお茶をかけられます。お父様にはまるで存在しないように扱われ、お母様付きだった女中ですらわたくしを嘲笑うようになり、わたくしは心も身体もいつも傷だらけでした。火傷や痣の痕が常に身体のどこかに存在し、蝶が舞うように浮かんでは消えていき、また現れます。その繰り返しです。わたくしの身体の斑な色に、尋常小学校の先生は気が付いていたようでしたが、学校自体、素行の悪い生徒は水をたっぷりいれた桶を持って立たされたり、叩かれたりするのがごく普通に行われていましたので、わたくしは素行の悪いなんてことはない、「良い子」であったのに関わらず、躾が厳しい家なのだろう程度にしか思われなかったようで、特に目をかけてもらえることはありませんでした。ただ、同じ教室にいる子どもたちからはずっと、汚らしい女子として、親しくしてもらえることはありませんでした。女のくせに身体にたくさんの傷痕があると。傷物と。卒業が近づくと、志貴様の家に綺麗な身体で向かわせるために、椎名の家での暴力はぴたりと止みましたが、それでも何でもないことで声を荒らげられるようなことは続きましたので、わたくしは次第に、人前で言葉を話すことのできない子どもになっていきました。
「どうしてつらい時、すぐに僕を頼ってくれなかったんだ」
えっと。言葉に困りました。志貴様のご機嫌を損ねるのが怖かったから、とは言えません。そのまま告げれば、きっとひどく叩かれるでしょう。えっと、あっと、何度か繰り返した末に、「志貴様を起こしてしまうのが申し訳なくて」と言ったのですが、彼にとって満点の回答ではなかったようです。切れ長の目がぐっと細くなって、わたくしは少々身を強張らせたのですが、幸い、これ以上機嫌を損ねることはありませんでした。
「まあ、良い。昨日君の家から招待状が来たんだ」
「招待状、ですか」
「なんとも、家を西洋館に造りなおしたそうだ。パーティーを行えるような広い部屋も作ったそうだから、お披露目したいと」
「はあ、そうですか」
彼の言葉にぼんやりと頷きます。江戸から続くわたくしの生家は、確かにあちこちが古くなっていました。世の中の上流階級の流行りは半洋式の家だったと記憶していますが、横浜が西洋人が多い場所ですから、また違うのかもしれません。そう思いながら箸を進めましたが、「君もドレスを着て来いと手紙に書いてあった」と言われ、箸で摘まんでいた煮物を危うく落とすところでした。
「ど、ドレス、ですか」
「もっと喜べよ、つまらないじゃないか。僕がドレスを作ってやろうとしているのに」
「も、申し訳ありません」
慌てて言うと、彼は午後に横浜に行くと言って、さっさと席を立ってしまいました。
お義母様とほたるのことですから、上等なドレスとうつくしい西洋館を見せびらかして鼻高々にいようと考えているのでしょう。御国がお金をたくさんかけて造った鹿鳴館ですら、西洋人に猿真似として笑われていて、終焉は近いと噂されているのですから、ただの下級貴族がドレスを着て西洋館で暮らそうなど、誰に笑われるか分かりません。きっと日本中の笑いものです。しかしそういった恥を考えもせず、高価なものを身に着けたいだけ身に着けたがるのは、椎名の家の者たちらしいと思い、とても気が重くなりました。
午前の間を、わたくしが住まわされている屋敷にまで聞こえる、神社でのお祓いの儀式の音や声を聞きながら過ごし、午後に志貴様に連れられて横浜に行きました。横浜は江戸の終わりから居留外国人がいた都合で、西洋人が営む婦人洋裁店があるのですが、彼はそこまでまっすぐに馬車を走らせます。わたくしはいかにも日本人らしい、まっすぐな黒髪に黒い目を持った小娘でしかなく、少々睫毛は長くはありますが、まあ所謂、地味な顔立ちをしていますので、西洋人に、こんなに貧相な日本人の女子が、ドレスなんかを着たがっていると笑われるのではないかと終始びくびくし、何度も日本人の営む洋裁店が良いと、控えめでありますが主張したのですが、志貴様は、「まだ日本人は洋裁が下手だから」と聞き入れてくれませんでした。
「彼女に今流行りのドレスを」
「そうすると、バッスル・ドレスだな。クリノレット・ドレスの流行はとうに終わってるよ、どこ見てるんだいお嬢さん」
わたくしは見本に置かれていた絵の、くりのれっとどれす、とやらを綺麗だと思ったのですが、志貴様が流行りのものと言った以上は流行りのものにしかならないので、店の隅で小さくなりながら、レエスの場所がどう、なんて話を聞いていました。わたくしは志貴様の従順なお人形であることで、やっと彼から最低限の価値を与えられるのですから、意匠をどうしてほしいと伝えることすら、何の意味も持たない、下手を打てば彼の機嫌をひどく損ねるものでしかありません。ただ採寸のために連れて来られたのだと思い、ぼんやりと待ち、わたくしの棲まされている神社はどうやら、困っている人からお祓いのために高いお金を巻き上げているようですから、それが高級品であるドレスに使われること、それがわたくしのものになることを、申し訳なく思いました。
彼と出会った時は、彼が恐ろしいことなど、少しも知りませんでした。唯一わたくしを守り、愛してくれたお母様を喪い、悲しさと心細さでただ泣いて過ごしていた、八歳の頃に彼に出会ったものですから、わたくしに差し伸べられる手のすべてが救いであるように感じてしまったのです。
彼は薄汚れた着物を纏うわたくしを見て、まず「可哀そうな子だね」と言いました。確かその日は横浜まで妖魔退治に来ていたようで、勇ましい恰好をしていたことを、ぼんやりと覚えています。彼はわたくしより十年上ですから、当時は十八歳でありましょうか。綺麗で格好いいお兄さんが、泣いているところに声を掛けてくれたものですから、それこそおとぎ話の主人公が、わたくしを助けに来てくれたように錯覚しました。お腹いっぱい食べさせてあげよう、綺麗な着物を着せてあげよう。きっと寂しい想いはさせないよ。だからうちにおいで、もう少し大きくなったらうちにお嫁さんにおいで――。子どもにも分かりやすく利のある、子どもにとって、甘く優しい言葉を吐かれ、わたくしは縋るような気持ちで頷きました。尋常小学校を卒業したら、女学校には行かせずに、萩原――志貴様の家に棲ませるように。そう椎名の家と彼の間に約束が成立し、わたくしはその日から志貴様の婚約者になりました。
真冬の庭でほたるに冷水をかけられ、弟の金剛に気晴らしに蹴られ叩かれ、妾だったお義母様には、お茶が不味いと、淹れたばかりのお茶をかけられます。お父様にはまるで存在しないように扱われ、お母様付きだった女中ですらわたくしを嘲笑うようになり、わたくしは心も身体もいつも傷だらけでした。火傷や痣の痕が常に身体のどこかに存在し、蝶が舞うように浮かんでは消えていき、また現れます。その繰り返しです。わたくしの身体の斑な色に、尋常小学校の先生は気が付いていたようでしたが、学校自体、素行の悪い生徒は水をたっぷりいれた桶を持って立たされたり、叩かれたりするのがごく普通に行われていましたので、わたくしは素行の悪いなんてことはない、「良い子」であったのに関わらず、躾が厳しい家なのだろう程度にしか思われなかったようで、特に目をかけてもらえることはありませんでした。ただ、同じ教室にいる子どもたちからはずっと、汚らしい女子として、親しくしてもらえることはありませんでした。女のくせに身体にたくさんの傷痕があると。傷物と。卒業が近づくと、志貴様の家に綺麗な身体で向かわせるために、椎名の家での暴力はぴたりと止みましたが、それでも何でもないことで声を荒らげられるようなことは続きましたので、わたくしは次第に、人前で言葉を話すことのできない子どもになっていきました。
「どうしてつらい時、すぐに僕を頼ってくれなかったんだ」
えっと。言葉に困りました。志貴様のご機嫌を損ねるのが怖かったから、とは言えません。そのまま告げれば、きっとひどく叩かれるでしょう。えっと、あっと、何度か繰り返した末に、「志貴様を起こしてしまうのが申し訳なくて」と言ったのですが、彼にとって満点の回答ではなかったようです。切れ長の目がぐっと細くなって、わたくしは少々身を強張らせたのですが、幸い、これ以上機嫌を損ねることはありませんでした。
「まあ、良い。昨日君の家から招待状が来たんだ」
「招待状、ですか」
「なんとも、家を西洋館に造りなおしたそうだ。パーティーを行えるような広い部屋も作ったそうだから、お披露目したいと」
「はあ、そうですか」
彼の言葉にぼんやりと頷きます。江戸から続くわたくしの生家は、確かにあちこちが古くなっていました。世の中の上流階級の流行りは半洋式の家だったと記憶していますが、横浜が西洋人が多い場所ですから、また違うのかもしれません。そう思いながら箸を進めましたが、「君もドレスを着て来いと手紙に書いてあった」と言われ、箸で摘まんでいた煮物を危うく落とすところでした。
「ど、ドレス、ですか」
「もっと喜べよ、つまらないじゃないか。僕がドレスを作ってやろうとしているのに」
「も、申し訳ありません」
慌てて言うと、彼は午後に横浜に行くと言って、さっさと席を立ってしまいました。
お義母様とほたるのことですから、上等なドレスとうつくしい西洋館を見せびらかして鼻高々にいようと考えているのでしょう。御国がお金をたくさんかけて造った鹿鳴館ですら、西洋人に猿真似として笑われていて、終焉は近いと噂されているのですから、ただの下級貴族がドレスを着て西洋館で暮らそうなど、誰に笑われるか分かりません。きっと日本中の笑いものです。しかしそういった恥を考えもせず、高価なものを身に着けたいだけ身に着けたがるのは、椎名の家の者たちらしいと思い、とても気が重くなりました。
午前の間を、わたくしが住まわされている屋敷にまで聞こえる、神社でのお祓いの儀式の音や声を聞きながら過ごし、午後に志貴様に連れられて横浜に行きました。横浜は江戸の終わりから居留外国人がいた都合で、西洋人が営む婦人洋裁店があるのですが、彼はそこまでまっすぐに馬車を走らせます。わたくしはいかにも日本人らしい、まっすぐな黒髪に黒い目を持った小娘でしかなく、少々睫毛は長くはありますが、まあ所謂、地味な顔立ちをしていますので、西洋人に、こんなに貧相な日本人の女子が、ドレスなんかを着たがっていると笑われるのではないかと終始びくびくし、何度も日本人の営む洋裁店が良いと、控えめでありますが主張したのですが、志貴様は、「まだ日本人は洋裁が下手だから」と聞き入れてくれませんでした。
「彼女に今流行りのドレスを」
「そうすると、バッスル・ドレスだな。クリノレット・ドレスの流行はとうに終わってるよ、どこ見てるんだいお嬢さん」
わたくしは見本に置かれていた絵の、くりのれっとどれす、とやらを綺麗だと思ったのですが、志貴様が流行りのものと言った以上は流行りのものにしかならないので、店の隅で小さくなりながら、レエスの場所がどう、なんて話を聞いていました。わたくしは志貴様の従順なお人形であることで、やっと彼から最低限の価値を与えられるのですから、意匠をどうしてほしいと伝えることすら、何の意味も持たない、下手を打てば彼の機嫌をひどく損ねるものでしかありません。ただ採寸のために連れて来られたのだと思い、ぼんやりと待ち、わたくしの棲まされている神社はどうやら、困っている人からお祓いのために高いお金を巻き上げているようですから、それが高級品であるドレスに使われること、それがわたくしのものになることを、申し訳なく思いました。