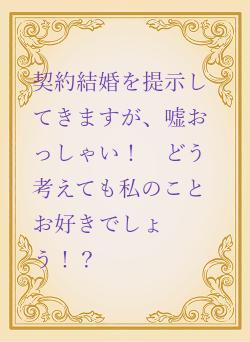次に目が覚めたのは、夜中でした。円に近づいた月が空高く昇り、障子の隙間から、わたくしを見下ろしていました。わたくしはまだ涙の痕が残っているであろう頬をこすり、夢の残滓を追い払うために、首を振りました。
嫌な夢を、見ていました。ほたると金剛がわたくしの両手を握り、うきうきと歩いている夢でした。暴れようとすれば、後ろにいたお義母様に叩かれ、わたくしの前を歩くお父様が、お母様の遺品を人質に、わたくしにまっすぐ歩くように言ってくるのです。お母様は、冷遇されているわたくしを少しでもまっすぐに育てるため、嫁入り道具であった琴や上等な着物や装飾品などのほとんどを売ってしまいましたので、それこそ、彼女が亡くなった頃には、最後に身に着けていた着物一着ばかりしか残っていませんでした。遺品、にあたるものはそんな具合に、着物一着しかないのですが、志貴様の家に持っていってしまいましたので、お父様が持っているはずがないのですが、志貴様が見つけ出して、お父様に渡したのだろうと思いました。
まるで葬式の列のようだ、と思いました。棺こそありませんが、わたくしは死人でした。死んだまま歩いていました。そして志貴様という、わたくしの前世を衰弱死させ、今世のわたくしを手籠めにしようと企む彼の元で、再び殺されるのです。そのために早々に葬式を行っているような気がしました。
夢では志貴様の元にたどり着くことはなく、ただ真っ白な道を歩いている最中に目が覚めましたが、このままだと本当に死んでしまうという恐怖で、何とか意識を浮上させたようで、目覚めきれなかった身体が、怠さを訴えて、また夢に沈もうとしています。わたくしは己の身体を叱咤し、起き上がり、隣で眠っている蘿月様を見下ろしました。彼はきっと、途中までわたくしを抱きしめていたのでしょう。同じ部屋に二枚布団は敷かれているのに、わたくし側の布団で、彼は眠っていました。わたくしはほとんど布団から落ちそうになっていましたので、夢に魘されている間に彼の腕から逃れてしまったようでしたが、彼の腕がすぐそこにあることに安心して、彼の片腕を持ち上げて、もう片腕に頭を乗せ、彼の胸元に額を押し付けました。神様なのに、彼は人の身体のぬくもりを思い出させてくれます。躑躅さんもそうです。彼女は他の部屋を片付けて以降、わたくしたち夫婦を気遣って、別の部屋で眠るようになっていましたが、きっと彼女も、寝る前にわたくしの頭を撫でてから自分の部屋の布団に潜ったのでしょう。
どうしたら、いつまでもこの二人の温もりに触れて生きられるのでしょうか。志貴様は化け物となり、人の定めを捻じ曲げて生き永らえている者ですから、討伐されるのだとしても諦めがつきますが、椎名の者たちは、今を生きる者たちです。彼らはきっと誰がどう見てもクズと呼ばれる者たちでしょうし、わたくしたちが何もしなくても、自らが抱えた借金で破滅するのは確実ですが、破滅を逃れるために藻掻いている間は、きっとわたくしの目に何度も入るのでしょう。その度にわたくしは何度も苦しむのは分かり切っていますから、何か策を講じなくてはならないと思いました。それに、わたくしは本来蘿月様にお仕えし、彼の呪いを浄化するために作られた存在、少々大げさに表現しますが、まあ、守るために生まれてきましたので、ただ守られているだけ、というのも性に合わないようです。かといって、瘦せ細ったこの腕では、刀ひとつ、銃ひとつまともに扱うことが出来ないでしょうから、どうすればいいのか、分からなくなってしまいました。
「蘿月様。わたくし、いつまでもあなたのお傍にいたいです」
何か策を、何か策を。そう考えている間に、薄っすら目を覚ましたらしい彼がわたくしを抱き寄せて、それから再び穏やかな寝息を立て始めました。その柔らかな息を感じていると、思考が溶けていくように思えましたが、夜中まですっかり寝ていましたから、目は冴えています。決して手を出せない存在、手を出すと、手を出した方が白い目で見られるような存在。偉い人、有名な人、必要とされる人、うつくしい人、人脈がある人。ああ、だめです。今のわたくしには、何もありません。これからそのどれか一つでも手に入れようと思うと、途方もないことのように思いましたが、幸い、神社で舞を行うことは決めていて、その準備も少しずつ進めています。地域で注目を浴びる、神社で舞を披露した巫女になるのが、美貌も持ち合わせていなければ人としての力も持たない、ただの女には手っ取り早く、そして確実であるように思いました。
舞の練習、頑張らなくちゃ。それから、舞を見に来てもらうためのものを考えなくちゃいけないわ。やっぱりお祭りかしら。お祭りだわ――。そう考えているうちに、再びわたくしは眠りにつき、再び悪夢に魘されそうになりましたが、蘿月様の優しい手のひらの感触を思い出して、日の昇る朝に、柔らかく包まれるようにして目を覚ましたのでした。
嫌な夢を、見ていました。ほたると金剛がわたくしの両手を握り、うきうきと歩いている夢でした。暴れようとすれば、後ろにいたお義母様に叩かれ、わたくしの前を歩くお父様が、お母様の遺品を人質に、わたくしにまっすぐ歩くように言ってくるのです。お母様は、冷遇されているわたくしを少しでもまっすぐに育てるため、嫁入り道具であった琴や上等な着物や装飾品などのほとんどを売ってしまいましたので、それこそ、彼女が亡くなった頃には、最後に身に着けていた着物一着ばかりしか残っていませんでした。遺品、にあたるものはそんな具合に、着物一着しかないのですが、志貴様の家に持っていってしまいましたので、お父様が持っているはずがないのですが、志貴様が見つけ出して、お父様に渡したのだろうと思いました。
まるで葬式の列のようだ、と思いました。棺こそありませんが、わたくしは死人でした。死んだまま歩いていました。そして志貴様という、わたくしの前世を衰弱死させ、今世のわたくしを手籠めにしようと企む彼の元で、再び殺されるのです。そのために早々に葬式を行っているような気がしました。
夢では志貴様の元にたどり着くことはなく、ただ真っ白な道を歩いている最中に目が覚めましたが、このままだと本当に死んでしまうという恐怖で、何とか意識を浮上させたようで、目覚めきれなかった身体が、怠さを訴えて、また夢に沈もうとしています。わたくしは己の身体を叱咤し、起き上がり、隣で眠っている蘿月様を見下ろしました。彼はきっと、途中までわたくしを抱きしめていたのでしょう。同じ部屋に二枚布団は敷かれているのに、わたくし側の布団で、彼は眠っていました。わたくしはほとんど布団から落ちそうになっていましたので、夢に魘されている間に彼の腕から逃れてしまったようでしたが、彼の腕がすぐそこにあることに安心して、彼の片腕を持ち上げて、もう片腕に頭を乗せ、彼の胸元に額を押し付けました。神様なのに、彼は人の身体のぬくもりを思い出させてくれます。躑躅さんもそうです。彼女は他の部屋を片付けて以降、わたくしたち夫婦を気遣って、別の部屋で眠るようになっていましたが、きっと彼女も、寝る前にわたくしの頭を撫でてから自分の部屋の布団に潜ったのでしょう。
どうしたら、いつまでもこの二人の温もりに触れて生きられるのでしょうか。志貴様は化け物となり、人の定めを捻じ曲げて生き永らえている者ですから、討伐されるのだとしても諦めがつきますが、椎名の者たちは、今を生きる者たちです。彼らはきっと誰がどう見てもクズと呼ばれる者たちでしょうし、わたくしたちが何もしなくても、自らが抱えた借金で破滅するのは確実ですが、破滅を逃れるために藻掻いている間は、きっとわたくしの目に何度も入るのでしょう。その度にわたくしは何度も苦しむのは分かり切っていますから、何か策を講じなくてはならないと思いました。それに、わたくしは本来蘿月様にお仕えし、彼の呪いを浄化するために作られた存在、少々大げさに表現しますが、まあ、守るために生まれてきましたので、ただ守られているだけ、というのも性に合わないようです。かといって、瘦せ細ったこの腕では、刀ひとつ、銃ひとつまともに扱うことが出来ないでしょうから、どうすればいいのか、分からなくなってしまいました。
「蘿月様。わたくし、いつまでもあなたのお傍にいたいです」
何か策を、何か策を。そう考えている間に、薄っすら目を覚ましたらしい彼がわたくしを抱き寄せて、それから再び穏やかな寝息を立て始めました。その柔らかな息を感じていると、思考が溶けていくように思えましたが、夜中まですっかり寝ていましたから、目は冴えています。決して手を出せない存在、手を出すと、手を出した方が白い目で見られるような存在。偉い人、有名な人、必要とされる人、うつくしい人、人脈がある人。ああ、だめです。今のわたくしには、何もありません。これからそのどれか一つでも手に入れようと思うと、途方もないことのように思いましたが、幸い、神社で舞を行うことは決めていて、その準備も少しずつ進めています。地域で注目を浴びる、神社で舞を披露した巫女になるのが、美貌も持ち合わせていなければ人としての力も持たない、ただの女には手っ取り早く、そして確実であるように思いました。
舞の練習、頑張らなくちゃ。それから、舞を見に来てもらうためのものを考えなくちゃいけないわ。やっぱりお祭りかしら。お祭りだわ――。そう考えているうちに、再びわたくしは眠りにつき、再び悪夢に魘されそうになりましたが、蘿月様の優しい手のひらの感触を思い出して、日の昇る朝に、柔らかく包まれるようにして目を覚ましたのでした。