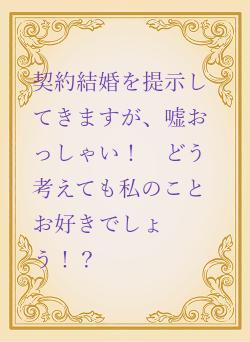舞を教えてくれることになったのは、元は神社の娘だという女性でした。駆け落ち同然に家から逃げ出してしまったとのことなのですが、その旦那様が亡くなってしまい、得意の舞を披露してなんとか食いつないでいるようなのですが、正直に言って、彼女の身なりは荒んでいました。黒の付け襟は確か東京の下町での流行りであったと記憶していますが、彼女の場合、きっと着物の衿を出来るだけ汚さないためでしょう。着物自体も継ぎはぎだらけで、替えすら用意出来ていないのだろう、というのが容易に想像できました。きっと太一さんたちがこの女性をわたくしに紹介しようと思ったのは、純粋に生活に苦心している人を助けたいという気持ちがあったからでしょうけれど、おそらく、この女性は身なりさえ整って、生活が豊かでさえあれば、とても美しい女性なのでしょう。目鼻立ちははっきりしている上に、睫毛は長く、頬ももう少しふっくらして赤みが差せば、儚げな美女であるように思えました。なんだか彼女には放っておけないような魅力があって、それに太一さんたちは吸い寄せられたのではないか、と思いました。
「芙蓉、と名乗らせていただいております」
ぼろぼろの家の中で、彼女は丁寧に頭を下げました。さすが舞の名手というべきか、指先から背の動きまでが整っています。
「私が舞を披露していたといっても、いつ身売りしなければならないか分からないようなところでしたので、生きるためと言っても、恐ろしく。生家にも縁を切られていますから、助けを求めはしたのですが、追い出されてしまいまして」
「そうでしたか」
大変でしたのね。そう呟くと、彼女が静かに静かに涙を流し始めます。幸いというべきか何というべきか、子どもはいないようでしたので、どこかの家のお妾さんになるか、女中として奉公するかすれば生きていけるのかもしれませんが、今の世の中ではまだ、女という生き物は、どこかの家に属さなければ生きていけないものです。芙蓉さんはまだ、舞という技術を持っていますから、一人で生きていけるのかもしれませんが、その道がとても険しいことは、誰の目から見ても明らかでした。
「蘿月の旦那、この子に悪いもの憑いてたり、しませんかね」
「いんや、この子にはお前に憑いていたようなものはいやせんよ。ただ、まあ、多少お祈りすれば、楽になるかもしれないが」
「お賽銭を入れるお金がなく、申し訳ありません」
芙蓉さんはすっかり項垂れていましたが、わたくしと蘿月様はそっと顔を見合わせました。多分、同じことを考えていると思いました。
「稽古代をこちらが支払うのだ。お前はお賽銭を入れなくても構わないよ。当分、うちで琥珀に稽古をつけ、昼飯を食べていきなさい」
「お夕飯もご一緒にどうですか」
「良いな。琥珀は賑やかなのは、好きか」
「どうでしょう。ただ、蘿月様と躑躅さんと囲む食事は楽しいので、もしかしたら、そうかもしれません」
「だ、そうだ。生徒が他に見つかるまでは、琥珀にみっちり稽古をつけてもらおうか」
みっちり、ですか。そう言うと、太一さんと喜助さんがわっと笑って、蘿月様がふふと笑みを浮かべました。わたくしは、体力的に自信がない、という言葉が先に浮かびましたが、でもすぐに、この目の前にいる困っている人に、頻繁に食事を分け与えられるのだと気が付いて、すぐに胸の奥が温かくなります。
こんな風に、見ず知らずの人を簡単に信じて、救いの手を差し伸べてしまう蘿月様は、甘いのでしょう。ですが彼は神様ですし、武力をさほど持たないといっても、人間の女なんて、本当にそうするかはともかく、やろうと思えば赤子の手を捻るよりも簡単に仕留めることが出来ましょうから、甘くても特に彼は困りはしないのでしょう。きっとその甘さは、何か悪いことを引き寄せることもあるかとは思いますが、もしそうなったら、きっとこの中で一番、人の悪意に敏感であるであろうわたくしが、止めて見せようと、そう思いました。それに、人助けというのは、例え偽善であったとしても、わたくしの醜い部分が覆い隠され、うつくしく生まれ変わっていくような気すらしますので、これから蘿月様が誰彼構わず救いの手を差し伸べたとしても、わたくしたちに害のない限りは手伝いたいとも思いました。
「相場、というのは分からないのだが。月謝はこれで足りるか?」
「ええ、ええ。これで十分にございます。これで家賃が支払えます」
「それから、高くなくていいから、着物を買いなさい。銭湯に行って、悪いものを流してきなさい。運気の上がるようなことは大事だよ」
そうさせていただきます。彼女は深々と頭を下げて、明日から週に五日稽古をつけに通うと約束してくれました。わたくしは、この方が明日きちんと来てくれるか、ほんの少し不安に思いましたが、食事のために来るだろうと、思うことにしました。
「芙蓉、と名乗らせていただいております」
ぼろぼろの家の中で、彼女は丁寧に頭を下げました。さすが舞の名手というべきか、指先から背の動きまでが整っています。
「私が舞を披露していたといっても、いつ身売りしなければならないか分からないようなところでしたので、生きるためと言っても、恐ろしく。生家にも縁を切られていますから、助けを求めはしたのですが、追い出されてしまいまして」
「そうでしたか」
大変でしたのね。そう呟くと、彼女が静かに静かに涙を流し始めます。幸いというべきか何というべきか、子どもはいないようでしたので、どこかの家のお妾さんになるか、女中として奉公するかすれば生きていけるのかもしれませんが、今の世の中ではまだ、女という生き物は、どこかの家に属さなければ生きていけないものです。芙蓉さんはまだ、舞という技術を持っていますから、一人で生きていけるのかもしれませんが、その道がとても険しいことは、誰の目から見ても明らかでした。
「蘿月の旦那、この子に悪いもの憑いてたり、しませんかね」
「いんや、この子にはお前に憑いていたようなものはいやせんよ。ただ、まあ、多少お祈りすれば、楽になるかもしれないが」
「お賽銭を入れるお金がなく、申し訳ありません」
芙蓉さんはすっかり項垂れていましたが、わたくしと蘿月様はそっと顔を見合わせました。多分、同じことを考えていると思いました。
「稽古代をこちらが支払うのだ。お前はお賽銭を入れなくても構わないよ。当分、うちで琥珀に稽古をつけ、昼飯を食べていきなさい」
「お夕飯もご一緒にどうですか」
「良いな。琥珀は賑やかなのは、好きか」
「どうでしょう。ただ、蘿月様と躑躅さんと囲む食事は楽しいので、もしかしたら、そうかもしれません」
「だ、そうだ。生徒が他に見つかるまでは、琥珀にみっちり稽古をつけてもらおうか」
みっちり、ですか。そう言うと、太一さんと喜助さんがわっと笑って、蘿月様がふふと笑みを浮かべました。わたくしは、体力的に自信がない、という言葉が先に浮かびましたが、でもすぐに、この目の前にいる困っている人に、頻繁に食事を分け与えられるのだと気が付いて、すぐに胸の奥が温かくなります。
こんな風に、見ず知らずの人を簡単に信じて、救いの手を差し伸べてしまう蘿月様は、甘いのでしょう。ですが彼は神様ですし、武力をさほど持たないといっても、人間の女なんて、本当にそうするかはともかく、やろうと思えば赤子の手を捻るよりも簡単に仕留めることが出来ましょうから、甘くても特に彼は困りはしないのでしょう。きっとその甘さは、何か悪いことを引き寄せることもあるかとは思いますが、もしそうなったら、きっとこの中で一番、人の悪意に敏感であるであろうわたくしが、止めて見せようと、そう思いました。それに、人助けというのは、例え偽善であったとしても、わたくしの醜い部分が覆い隠され、うつくしく生まれ変わっていくような気すらしますので、これから蘿月様が誰彼構わず救いの手を差し伸べたとしても、わたくしたちに害のない限りは手伝いたいとも思いました。
「相場、というのは分からないのだが。月謝はこれで足りるか?」
「ええ、ええ。これで十分にございます。これで家賃が支払えます」
「それから、高くなくていいから、着物を買いなさい。銭湯に行って、悪いものを流してきなさい。運気の上がるようなことは大事だよ」
そうさせていただきます。彼女は深々と頭を下げて、明日から週に五日稽古をつけに通うと約束してくれました。わたくしは、この方が明日きちんと来てくれるか、ほんの少し不安に思いましたが、食事のために来るだろうと、思うことにしました。