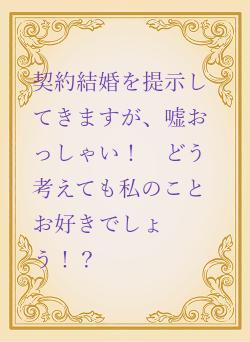お祓い、という名目ではありますが、蘿月様の場合、人に取りついた怨霊であったり鬼であったりを吸い取り、飲み込むことを指すようで、神職の方がされるように、祝詞を唱える必要はないようでしたが、祝詞を唱えるほうが人々がお祓いをされている気分になるとのことで、何か自分で考えた呪文のようなものを唱えながら、腕羅さんが作った刀を時折振り、祓串を振りと、それらしい恰好をしているようでした。太一さんたちは、蘿月様が神様自身であることも、躑躅さんが妖狐であることも知りません。躑躅さんの尻尾は彼らには見えていないようですし、蘿月様がまだ身体に纏っている靄も、彼らには見えない様子でした。箱根の旅行の際も、道を歩く人の誰にも蘿月様の靄のことを気に留めている様子はありませんでしたので、見える者にしか見えないようです。
「わたくしに何か出来ることは、ないのでしょうか」
昼餉のおにぎりを食べながら、躑躅さんに問うてみます。躑躅さんはおにぎりの具を何にするか、まだ悩んでいたようでしたが、わたくしの問いに顔を上げ、うーんと首を捻ります。
「祓うのはね、特殊な力なのよ。あんたの力は蘿月にしか使えないのよね。あいつが悪いもの貰ってきた後に、癒してあげることくらいしかないわね、残念ながら」
「そう、ですか」
頷いて、鮭の入ったおにぎりを齧ると、ふわりと塩の香りがします。美味しい、とつぶやくと、躑躅さんがにこりと笑いました。
わたくしも家事をやるようになったとはいえ、この家のことを回しているのは、主に躑躅さんです。例えば農家や織物をやっている家であれば、家事の他に農作業や糸を紡ぐようなことをするのでしょうけれど、ここはそんなに大きな神社ではありませんし、お祓いをしているだけであって、巫女や神職の方が何人も働くような場所ではないのです。わたくしに出来るのは、神社を綺麗に整えることくらいで、何か特別、お役に立てているようには思えません。わたくしが持つ浄化の力も、手を握るだけで効果を発揮するものですから、何か他に役に立ちたいと、思ってしまうのでした。
「琥珀はとっても『良い子』ね」
良い子にならざるを得なかったのだろう、というのは躑躅さんにも薄っすら分かっているようで、褒めるようなことは言われずに、少しほっとしました。
「ただ、まあ、そうね。お賽銭とお祓いをしないと、お金の心配をしなくちゃいけなくなるのよね。ここもう、ずっとぼろぼろだったから、お客もなかなか来ないだろうし」
「えっと、ということは、お客様が集まるようなことをすれば、良いのでしょうか」
そうね、と躑躅さんは頷きました。でも何したら集まるかしらねえ、と彼女が言いますので、わたくしもうんうん頭を捻ります。神社の中から叫ぶような声がしましたが、躑躅さんは特に動じることもなく、当たり前にあることなのだと気が付いて、わたくしにはそういう、人ならざる者の力で直接人々の役に立つことはできないのだと分かりました。そうなるとやはり、お客様を集めるような何かを計画する方が、よほど現実的なのでしょう。
「お祭り、ですかねぇ、やっぱり」
「あいつの『お祓い』は本物よ。お祓いとは違うけれど。悪いものは吸うけれど、それもあんたが蘿月と共に生きる限りは、気にしなくて良い」
「つまり、蘿月様のお祓いを受けたくなるような、何か、お祭りのようなものを考えれば良いのですよね」
悪霊退散ッ。そんな声が神社から聞こえてきます。陰陽師の真似なのでしょうか。そう思ったらなんだかおもしろくて、躑躅さんと顔を見合わせて笑いました。
詳しくはわたくしも知らないのですが、政府は神社合祀、というものを計画しているようで、神道国家の体制作りや見栄えやら何やらの都合で、複数の神社を一つに纏めてしまおうとしているようです。まだ神社が纏められたという話を聞いてはいないのですが、少し前まで寂れていたここが、その対象にならないとも限りませんので、早いうちにこの神社を、参拝客の多い立派な神社にしなければ、わたくしはやっと得た温かい場所を喪ってしまうことになります。それは何としても避けなければなりませんから、お客様にたくさん来てもらって、お祓いを受けてもらわねば困ります。
きっと躑躅さんは、お祓いを受けさせることで、蘿月様が抱える呪いや祟りの力を増やし、前世のわたくしの仇を早々に打たせようと思っているのでしょう。仇討ち、というものに気は進みませんが、それで二人の気が済むのなら、止めるつもりはありません。武士ならば仇討ちは当然企むでしょうし――わたくしたちの誰かが武士というわけではなく、ただ武士の国に生まれただけですが――、わたくしにとっても、志貴様は懸命に生きてほしいと願うほど、素敵な人でもありませんでしたから。そうやって、自分に言い聞かせます。
「あとお守りを売ってみるとか、ですかねぇ」
わたくしがそう呟いた時、神社から、「躑躅、躑躅、この二人に飯を用意してやってくれんか」という声が聞こえてきました。わたくしと躑躅さんが神社の中に向かうと、境内の石畳の上で太一さんがぐったりと横になっていて、その横で喜助さんがおろおろしています。目を凝らすと、太一さんの背に張り付いている鬼も疲れたように太一さんにのしかかっていて、そのせいで、彼は起き上がることが出来ない様子でした。
「はい、おにぎりどうぞ」
「お嬢ちゃん、俺の背中の鬼はどうだい?」
「太一さんを押しつぶしていますね」
「そうかァ、道理で重い。でも身体の中の気持ち悪さは随分楽なんだ、これでも」
おにぎりを持った躑躅さんがぺらと太一さんの袴の裾を捲り、「人面瘡もちっちゃくなったわね」と言います。
「最初に出来た人面瘡が余計なものを引き寄せたようだ。生霊も落ち武者の霊のみんな抱えていたよ。それらは俺が力だけ吸い取って、元の場所にお帰りいただいた」
「成仏させないんですかい」
「未練を晴らさねばあの世にはいけないのだ。未練を晴らすのは他のやつの方が詳しい。俺は人間の身体から追い出すのがせいぜいだよ」
そうかァ、と太一さんは寝転がったまま頷き、渡されたおにぎりを食べます。わたくしも喜助さんと蘿月様におにぎりを配ると、少し疲れたように座る蘿月様の横に腰掛けました。すると、彼がゆったりと目を細めます。
「心配いらないよ」
「ふふ、分かってしまうのですね」
「お前が生きている限りは、大丈夫だ」
「長生きしますね」
「そうしてくれ」
彼は喜助さんたちに聞こえないように、こっそりと、こうしている間にも、周辺に住む人の恨みつらみや呪いといったものを、少しずつ吸い取っているのだと話してくれました。直接神社にやってくる方が、対象を定めやすいために効果を感じやすいのだそうですが、彼は存在する限り、人々が生み出す負の気持ちというものを吸い取るとのことでした。
「俺が存在しても、戦も殺しも起こる。素晴らしい力というわけでは、ないのだがな」
「ですが、あなたに救われた人も、たくさんいるでしょう」
「そうだといいな」
ありがとう、と彼はちいさく笑いました。その頬に陽光が差し、なんだか神秘的に見えると思った時、わたくしの頭にきらりと光るものが走ります。
「そうだわ、舞をすればいいのだわ」
わたくしの普段より大きな声に、わたくしの企みを知らない蘿月様がぽかんと口を開けて、こちらを見てきます。太一さんも喜助さんもこちらを見て、躑躅さんがくすくすと笑いました。
「あう、蘭麝神社を、盛り上げよう作戦、です」
顔から湯気が出るのを感じましたが、すぐ隣で蘿月様が優しく微笑む気配を感じましたので、なんだか勇気が出ました。
「よく分からないが、作家の筋書きがいるのなら俺に任せなァ」
「先に締め切りなんとかしろよ、締め切り破り先生」
「そう言ってくれるな喜助。まあ、こうやって助けてもらってる礼ってやつよ」
舞ね、良いんじゃない。そう言って躑躅さんも笑いましたので、舞を披露するために行動するのが決まりました。
「わたくしに何か出来ることは、ないのでしょうか」
昼餉のおにぎりを食べながら、躑躅さんに問うてみます。躑躅さんはおにぎりの具を何にするか、まだ悩んでいたようでしたが、わたくしの問いに顔を上げ、うーんと首を捻ります。
「祓うのはね、特殊な力なのよ。あんたの力は蘿月にしか使えないのよね。あいつが悪いもの貰ってきた後に、癒してあげることくらいしかないわね、残念ながら」
「そう、ですか」
頷いて、鮭の入ったおにぎりを齧ると、ふわりと塩の香りがします。美味しい、とつぶやくと、躑躅さんがにこりと笑いました。
わたくしも家事をやるようになったとはいえ、この家のことを回しているのは、主に躑躅さんです。例えば農家や織物をやっている家であれば、家事の他に農作業や糸を紡ぐようなことをするのでしょうけれど、ここはそんなに大きな神社ではありませんし、お祓いをしているだけであって、巫女や神職の方が何人も働くような場所ではないのです。わたくしに出来るのは、神社を綺麗に整えることくらいで、何か特別、お役に立てているようには思えません。わたくしが持つ浄化の力も、手を握るだけで効果を発揮するものですから、何か他に役に立ちたいと、思ってしまうのでした。
「琥珀はとっても『良い子』ね」
良い子にならざるを得なかったのだろう、というのは躑躅さんにも薄っすら分かっているようで、褒めるようなことは言われずに、少しほっとしました。
「ただ、まあ、そうね。お賽銭とお祓いをしないと、お金の心配をしなくちゃいけなくなるのよね。ここもう、ずっとぼろぼろだったから、お客もなかなか来ないだろうし」
「えっと、ということは、お客様が集まるようなことをすれば、良いのでしょうか」
そうね、と躑躅さんは頷きました。でも何したら集まるかしらねえ、と彼女が言いますので、わたくしもうんうん頭を捻ります。神社の中から叫ぶような声がしましたが、躑躅さんは特に動じることもなく、当たり前にあることなのだと気が付いて、わたくしにはそういう、人ならざる者の力で直接人々の役に立つことはできないのだと分かりました。そうなるとやはり、お客様を集めるような何かを計画する方が、よほど現実的なのでしょう。
「お祭り、ですかねぇ、やっぱり」
「あいつの『お祓い』は本物よ。お祓いとは違うけれど。悪いものは吸うけれど、それもあんたが蘿月と共に生きる限りは、気にしなくて良い」
「つまり、蘿月様のお祓いを受けたくなるような、何か、お祭りのようなものを考えれば良いのですよね」
悪霊退散ッ。そんな声が神社から聞こえてきます。陰陽師の真似なのでしょうか。そう思ったらなんだかおもしろくて、躑躅さんと顔を見合わせて笑いました。
詳しくはわたくしも知らないのですが、政府は神社合祀、というものを計画しているようで、神道国家の体制作りや見栄えやら何やらの都合で、複数の神社を一つに纏めてしまおうとしているようです。まだ神社が纏められたという話を聞いてはいないのですが、少し前まで寂れていたここが、その対象にならないとも限りませんので、早いうちにこの神社を、参拝客の多い立派な神社にしなければ、わたくしはやっと得た温かい場所を喪ってしまうことになります。それは何としても避けなければなりませんから、お客様にたくさん来てもらって、お祓いを受けてもらわねば困ります。
きっと躑躅さんは、お祓いを受けさせることで、蘿月様が抱える呪いや祟りの力を増やし、前世のわたくしの仇を早々に打たせようと思っているのでしょう。仇討ち、というものに気は進みませんが、それで二人の気が済むのなら、止めるつもりはありません。武士ならば仇討ちは当然企むでしょうし――わたくしたちの誰かが武士というわけではなく、ただ武士の国に生まれただけですが――、わたくしにとっても、志貴様は懸命に生きてほしいと願うほど、素敵な人でもありませんでしたから。そうやって、自分に言い聞かせます。
「あとお守りを売ってみるとか、ですかねぇ」
わたくしがそう呟いた時、神社から、「躑躅、躑躅、この二人に飯を用意してやってくれんか」という声が聞こえてきました。わたくしと躑躅さんが神社の中に向かうと、境内の石畳の上で太一さんがぐったりと横になっていて、その横で喜助さんがおろおろしています。目を凝らすと、太一さんの背に張り付いている鬼も疲れたように太一さんにのしかかっていて、そのせいで、彼は起き上がることが出来ない様子でした。
「はい、おにぎりどうぞ」
「お嬢ちゃん、俺の背中の鬼はどうだい?」
「太一さんを押しつぶしていますね」
「そうかァ、道理で重い。でも身体の中の気持ち悪さは随分楽なんだ、これでも」
おにぎりを持った躑躅さんがぺらと太一さんの袴の裾を捲り、「人面瘡もちっちゃくなったわね」と言います。
「最初に出来た人面瘡が余計なものを引き寄せたようだ。生霊も落ち武者の霊のみんな抱えていたよ。それらは俺が力だけ吸い取って、元の場所にお帰りいただいた」
「成仏させないんですかい」
「未練を晴らさねばあの世にはいけないのだ。未練を晴らすのは他のやつの方が詳しい。俺は人間の身体から追い出すのがせいぜいだよ」
そうかァ、と太一さんは寝転がったまま頷き、渡されたおにぎりを食べます。わたくしも喜助さんと蘿月様におにぎりを配ると、少し疲れたように座る蘿月様の横に腰掛けました。すると、彼がゆったりと目を細めます。
「心配いらないよ」
「ふふ、分かってしまうのですね」
「お前が生きている限りは、大丈夫だ」
「長生きしますね」
「そうしてくれ」
彼は喜助さんたちに聞こえないように、こっそりと、こうしている間にも、周辺に住む人の恨みつらみや呪いといったものを、少しずつ吸い取っているのだと話してくれました。直接神社にやってくる方が、対象を定めやすいために効果を感じやすいのだそうですが、彼は存在する限り、人々が生み出す負の気持ちというものを吸い取るとのことでした。
「俺が存在しても、戦も殺しも起こる。素晴らしい力というわけでは、ないのだがな」
「ですが、あなたに救われた人も、たくさんいるでしょう」
「そうだといいな」
ありがとう、と彼はちいさく笑いました。その頬に陽光が差し、なんだか神秘的に見えると思った時、わたくしの頭にきらりと光るものが走ります。
「そうだわ、舞をすればいいのだわ」
わたくしの普段より大きな声に、わたくしの企みを知らない蘿月様がぽかんと口を開けて、こちらを見てきます。太一さんも喜助さんもこちらを見て、躑躅さんがくすくすと笑いました。
「あう、蘭麝神社を、盛り上げよう作戦、です」
顔から湯気が出るのを感じましたが、すぐ隣で蘿月様が優しく微笑む気配を感じましたので、なんだか勇気が出ました。
「よく分からないが、作家の筋書きがいるのなら俺に任せなァ」
「先に締め切りなんとかしろよ、締め切り破り先生」
「そう言ってくれるな喜助。まあ、こうやって助けてもらってる礼ってやつよ」
舞ね、良いんじゃない。そう言って躑躅さんも笑いましたので、舞を披露するために行動するのが決まりました。