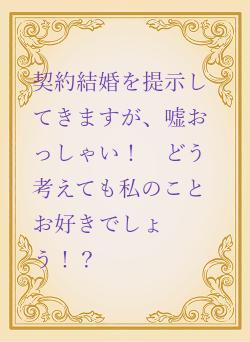躑躅さんと一緒に屋敷を整え、神社を綺麗にしている最中に、最初の参拝客は現れました。
今まで旅行や牛鍋を食べられていたのは、躑躅さんが以前にわたくしの墓の様子を見に来た際に、蘿月様がぐったりとしているのを見て、何かあってもいいように、神社が持ち合わせていたお金を金に変えて隠し持っていたからだそうです。時代によって貨幣制度が変わってきたのを、彼らは何度も目にしていますから、価値の大きく変動しないもの、つまり金や銀といった金属そのものにお金を換えるようにしているようで、おかげで、しばらく分の贅沢が出来、わたくしも瘦せ細った身体にほんの少し肉がついたものですが、やはり神社を立て直さなくては、収入がなくなってしまいます。蘿月様には刀との特訓を続けてもらい、わたくしと躑躅さんで神社を綺麗にしていたのですが、やっと、観光客がふらりと立ち寄るようになったようでした。
「はぁ、蘭麝神社、か。鎌倉の観光案内書にはなかった神社だなぁ」
やっと神社の鳥居も綺麗になったところだったのですが、案の定というべきか、江戸の中頃から流行した鎌倉巡りの、それに関わる書物には、蘿月様の神社のことは書かれていないようでした。蘿月様が打たせた刀すら取りに行けず、日々寝込むようにして過ごしていた頃でしょうから。
「昔からあったのですが、やっと復活しまして」
復活ねぇ、と言って、彼は境内の中を眺めまわしましたが、お賽銭を入れていこうという気分になったのか、拝殿の方に歩いていきます。手を合わせてお祈りしていると、彼の背からすっと黒い靄が立って、蘿月様が籠っている山の方に吸い込まれていきます。あれが蘿月様の守り神としての力なのでしょう。わたくしが驚いてそれを見ていると、彼の身体から立つ靄はなくなり、黒い靄が山に向かっていくだけとなりました。
「どう? 少し、身体が軽くなったんじゃないの?」
箒を持ったまま躑躅さんが問いますと、男は肩をぐるりぐるり回して、なんだか、すっきりしたと言って軽く笑います。憑き物が落ちたようです。
「でしょう? ここのお祓い、もっと凄いわよ」
躑躅さんは尻尾を隠してはいましたが、微笑む姿の妖艶さはそのままでした。身内にお祓いが必要な人がいたら連れてらっしゃい。なあに、他の神社ほど高くないわよ。そう語り掛けると、男はぽうと顔を赤らめて、「周りに様子がおかしいやつがいるんだ、連れてくるよ」と言いました。また来てね、と躑躅さんが言うと、彼はこくこくと頷いて、帰っていきました。
「あいつにたんと食べさせないとね」
そう小さく呟く躑躅さんの目が、ひどく澱んでいたのは、気が付かないふりをしました。
やがて男は本当に、ご友人を連れてやってきました。男の名は喜助、書生風の恰好をしたご友人の名は太一と言うのですが、喜助さんが生き生きとした様子でいるのに対し、太一さんは顔色が悪く、げっそりとやつれているように見えました。わたくしも昨日まで月のもののために横になっていたものですが、それでも、彼のほうがよほど不健康に見えます。蘿月様はわたくしに屋敷に休んでいるように言いましたが、何か彼のお役に立てれば良いという気持ちと、ちょっとした好奇心のために、お茶を淹れる係に自ら手を挙げて、彼らのやりとりに耳を澄ませます。
どうやら、太一さんは小説家として生活しているそうなのですが、怪異が出てくる娯楽小説を書こうと思い、怪異の噂が立つ場所に向かったそうなのですが、その日以降、膝に人面瘡が出来てしまったというのです。わたくしがお茶を置きがてらこっそりそれを盗みみると、なるほど、まくり上げた裾から、膝に人の顔に見える、皺のようなものが見えました。人面瘡というものは初めて見ましたが、好奇心で見るものではなかったと、後悔しました。
「バカねえ、だめよ、行ったらだめってところには行ったらだめな理由があるんだから」
「躑躅、やめてやれ。この者も大いに反省しているようだ。して、いったい何を見にいったんだ」
太一さんは、「腹切りやぐら」や「曼荼羅堂」などの、知る人はよく知っているであろう、武士や落ち武者の霊が出ると噂の場所を上げ、とにかく怪異であれば何でも良かったと言ったのですが、彼が最後に挙げた場所に、蘿月様は眉を顰めました。
「蘇芳診療所、とは何だ」
「五年くらい前に、借金取りに追われて亡くなった男がやっていた診療所でして、あはは、借金をしていたのは、妻の方だったようなのですが、まあ、ともかく、借金取りに殴り殺されてから、頻繁に夜中に男の叫び声がそこから聞こえてくるようになったのだそうで。へえ、で、牛鬼やら姑獲鳥が出るとか言うもんで、行ってみたんでさァ」
身振り手振りで太一さんが話をしますと、躑躅さんが傍に座るわたくしに、そっと耳打ちし、「目を凝らして御覧なさい、あんたにも見えるはずよ」と言いました。わたくしにも何か見えるのかはわかりませんが、ひとまず言われた通りに目を凝らし、じっと彼の背を見つめますと、何かぼやけた輪郭がわたくしにも見えるようになってきました。くっきりとは見えませんでしたが、彼の背にしがみつき、舌を垂らし、唾液をたらたらと垂らした、角のある生き物が、そこにいました。
「お、鬼、鬼だわ」
わたくしが座ったままじりと下がると、鬼の目がぎょろりとわたくしを見ます。その目が一つしかないのが異様に恐ろしく、慌てて蘿月様の首にしがみつきますと、太一さんは慌てて背後を振り返りました。しかし彼には何も見えないようで、ただ羽織の裾が翻っただけです。
「琥珀は見なくていいぞ」
蘿月様は怖がるわたくしを笑うことはせず、だから言ったのにとばかりに躑躅さんを見たのですが、躑躅さんは途端にしおれて、ほんの少しうつむきました。
「ごめんね、怖がらせちゃったわね」
「鬼って、腕羅さんのような者ばかりだと思っていました」
「あれが例外だ。たいていの鬼はこのように醜い」
わたくしがぽんぽんと頭を撫でられている間に、すっかり太一さんは顔の色をなくし、喜助さんもまた、理由が分からないまま腰を抜かしていました。見えないのだとしても、それを見て、恐れている人間がいることが、彼らの得体のしれない恐怖を増しているようでした。太一さんは早く祓ってくれと頭を下げ、喜助さんもまた、それに倣いました。金なら出す、なんて言葉を聞く日が来るとは思いませんでしたが、人間というもの、困ったときはお金に頼るしかないようです。
「これは祓うのにかかる。何日泊まれる?」
「締め切りが、明日で」
「遅らせなさい」
「は、はい」
慌てて文を編集の方宛てに出させ、こうして最初のお客様のお祓いをすることになりました。
今まで旅行や牛鍋を食べられていたのは、躑躅さんが以前にわたくしの墓の様子を見に来た際に、蘿月様がぐったりとしているのを見て、何かあってもいいように、神社が持ち合わせていたお金を金に変えて隠し持っていたからだそうです。時代によって貨幣制度が変わってきたのを、彼らは何度も目にしていますから、価値の大きく変動しないもの、つまり金や銀といった金属そのものにお金を換えるようにしているようで、おかげで、しばらく分の贅沢が出来、わたくしも瘦せ細った身体にほんの少し肉がついたものですが、やはり神社を立て直さなくては、収入がなくなってしまいます。蘿月様には刀との特訓を続けてもらい、わたくしと躑躅さんで神社を綺麗にしていたのですが、やっと、観光客がふらりと立ち寄るようになったようでした。
「はぁ、蘭麝神社、か。鎌倉の観光案内書にはなかった神社だなぁ」
やっと神社の鳥居も綺麗になったところだったのですが、案の定というべきか、江戸の中頃から流行した鎌倉巡りの、それに関わる書物には、蘿月様の神社のことは書かれていないようでした。蘿月様が打たせた刀すら取りに行けず、日々寝込むようにして過ごしていた頃でしょうから。
「昔からあったのですが、やっと復活しまして」
復活ねぇ、と言って、彼は境内の中を眺めまわしましたが、お賽銭を入れていこうという気分になったのか、拝殿の方に歩いていきます。手を合わせてお祈りしていると、彼の背からすっと黒い靄が立って、蘿月様が籠っている山の方に吸い込まれていきます。あれが蘿月様の守り神としての力なのでしょう。わたくしが驚いてそれを見ていると、彼の身体から立つ靄はなくなり、黒い靄が山に向かっていくだけとなりました。
「どう? 少し、身体が軽くなったんじゃないの?」
箒を持ったまま躑躅さんが問いますと、男は肩をぐるりぐるり回して、なんだか、すっきりしたと言って軽く笑います。憑き物が落ちたようです。
「でしょう? ここのお祓い、もっと凄いわよ」
躑躅さんは尻尾を隠してはいましたが、微笑む姿の妖艶さはそのままでした。身内にお祓いが必要な人がいたら連れてらっしゃい。なあに、他の神社ほど高くないわよ。そう語り掛けると、男はぽうと顔を赤らめて、「周りに様子がおかしいやつがいるんだ、連れてくるよ」と言いました。また来てね、と躑躅さんが言うと、彼はこくこくと頷いて、帰っていきました。
「あいつにたんと食べさせないとね」
そう小さく呟く躑躅さんの目が、ひどく澱んでいたのは、気が付かないふりをしました。
やがて男は本当に、ご友人を連れてやってきました。男の名は喜助、書生風の恰好をしたご友人の名は太一と言うのですが、喜助さんが生き生きとした様子でいるのに対し、太一さんは顔色が悪く、げっそりとやつれているように見えました。わたくしも昨日まで月のもののために横になっていたものですが、それでも、彼のほうがよほど不健康に見えます。蘿月様はわたくしに屋敷に休んでいるように言いましたが、何か彼のお役に立てれば良いという気持ちと、ちょっとした好奇心のために、お茶を淹れる係に自ら手を挙げて、彼らのやりとりに耳を澄ませます。
どうやら、太一さんは小説家として生活しているそうなのですが、怪異が出てくる娯楽小説を書こうと思い、怪異の噂が立つ場所に向かったそうなのですが、その日以降、膝に人面瘡が出来てしまったというのです。わたくしがお茶を置きがてらこっそりそれを盗みみると、なるほど、まくり上げた裾から、膝に人の顔に見える、皺のようなものが見えました。人面瘡というものは初めて見ましたが、好奇心で見るものではなかったと、後悔しました。
「バカねえ、だめよ、行ったらだめってところには行ったらだめな理由があるんだから」
「躑躅、やめてやれ。この者も大いに反省しているようだ。して、いったい何を見にいったんだ」
太一さんは、「腹切りやぐら」や「曼荼羅堂」などの、知る人はよく知っているであろう、武士や落ち武者の霊が出ると噂の場所を上げ、とにかく怪異であれば何でも良かったと言ったのですが、彼が最後に挙げた場所に、蘿月様は眉を顰めました。
「蘇芳診療所、とは何だ」
「五年くらい前に、借金取りに追われて亡くなった男がやっていた診療所でして、あはは、借金をしていたのは、妻の方だったようなのですが、まあ、ともかく、借金取りに殴り殺されてから、頻繁に夜中に男の叫び声がそこから聞こえてくるようになったのだそうで。へえ、で、牛鬼やら姑獲鳥が出るとか言うもんで、行ってみたんでさァ」
身振り手振りで太一さんが話をしますと、躑躅さんが傍に座るわたくしに、そっと耳打ちし、「目を凝らして御覧なさい、あんたにも見えるはずよ」と言いました。わたくしにも何か見えるのかはわかりませんが、ひとまず言われた通りに目を凝らし、じっと彼の背を見つめますと、何かぼやけた輪郭がわたくしにも見えるようになってきました。くっきりとは見えませんでしたが、彼の背にしがみつき、舌を垂らし、唾液をたらたらと垂らした、角のある生き物が、そこにいました。
「お、鬼、鬼だわ」
わたくしが座ったままじりと下がると、鬼の目がぎょろりとわたくしを見ます。その目が一つしかないのが異様に恐ろしく、慌てて蘿月様の首にしがみつきますと、太一さんは慌てて背後を振り返りました。しかし彼には何も見えないようで、ただ羽織の裾が翻っただけです。
「琥珀は見なくていいぞ」
蘿月様は怖がるわたくしを笑うことはせず、だから言ったのにとばかりに躑躅さんを見たのですが、躑躅さんは途端にしおれて、ほんの少しうつむきました。
「ごめんね、怖がらせちゃったわね」
「鬼って、腕羅さんのような者ばかりだと思っていました」
「あれが例外だ。たいていの鬼はこのように醜い」
わたくしがぽんぽんと頭を撫でられている間に、すっかり太一さんは顔の色をなくし、喜助さんもまた、理由が分からないまま腰を抜かしていました。見えないのだとしても、それを見て、恐れている人間がいることが、彼らの得体のしれない恐怖を増しているようでした。太一さんは早く祓ってくれと頭を下げ、喜助さんもまた、それに倣いました。金なら出す、なんて言葉を聞く日が来るとは思いませんでしたが、人間というもの、困ったときはお金に頼るしかないようです。
「これは祓うのにかかる。何日泊まれる?」
「締め切りが、明日で」
「遅らせなさい」
「は、はい」
慌てて文を編集の方宛てに出させ、こうして最初のお客様のお祓いをすることになりました。