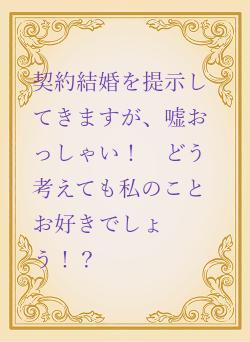箱根から鎌倉に帰ってくると、随分神社もお屋敷も綺麗になっていました。神社もこれなら人が安心して参拝しに来るのだろうと思うほど、ぴかぴかになっていましたし、奥の住処も、中に机やら箪笥やらが見えるほど蘇っていて、思わず「わぁ」と声を上げてしまいます。
「あらぁ、お帰りなさい」
足音と声に気が付いたのか、躑躅さんが飛び出してきます。着物は豪奢なままでしたが、上から割烹着を着ていて、抱きとめられると、野菜や醤油の香りが混ざったような、良い匂いがしました。
「やっぱり、あんたがいないと寂しいわァ。どう、楽しかった?」
「なんだか、躑躅さんの顔を見たら、安心しました」
「んもう、可愛いわねえ」
旅行はとても楽しかったです、と付け足すと、躑躅さんは「あっお鍋見てこなくちゃ」と慌てて家の中に戻っていきました。蘿月様に「俺たちも入ろう」と言われて、屋敷に足を踏み入れ、少々迷いながら、「ただいま戻りました」と言ってみました。
「おかえりおかえり」
躑躅さんも、おかえり、と言える人がいるのが嬉しいようで、九つの尻尾がうきうきと揺れています。こんな可愛らしくてうつくしい方が、わたくしの仇のために刀を打たせようとしたことがあったのだと思うと、なんだか苦しいような気がして、少し、泣きたくなりました。ただ、ここで突然泣くのも変だと思い、目元を覆いますと、躑躅さんも蘿月様も気が付いて、慌ててわたくしの顔を覗き込むのでした。
「蘿月になんかされた? あっ、分かった、腕羅に変なこと吹き込まれたでしょ」
「俺は変なことは」
「んもーっ、そうやって顔赤くしてもーっ、察しちゃうじゃないのよもうっ」
「す、すまん」
「琥珀が思い出して照れてるでしょッ、蘿月あんた責任取りなさいよ」
そう言われても、と蘿月様が半ば困ったような声色で言うので、なんだかおかしくなって、躑躅さんに突かれるまま、腕羅さんに言われたことを、洗いざらい話してしまいました。すると二人は顔を見合わせて、まず蘿月様がわたくしの頭を撫で、それから躑躅さんがわたくしをぎゅうと抱きしめました。
「あんたは気にしなくていいのよ、そんなこと。あたしらは人間じゃないし、特にあたしはもう、怒ったらとことんやるの。妖狐だもの、そうやって生きてきてるの」
「で、でも」
「お前は優しいな、ずっと変わらず」
「あたしたち、あんたのそういうところが大好きでしょうがないのよ。だからあんたが傷つけられるがどうしてもだめなの。許してね」
牛鍋ってやつ作ってるところなの、食べましょ、人間って食べたら元気出るって聞いたのよ。躑躅さんはそう言ってぱんと手を叩き、厨房に戻っていきました。わたくしがそれを目で追うと、今度は蘿月様がわたくしを抱き寄せ、何か祈るように、わたくしの背を撫で続けるのでした。
牛鍋、というのは、志貴様と共に食べたことはあったのですが、こんなに美味しいものだということは、知りませんでした。牛肉はまだ高いものですから、一生懸命美味しいと言ってみたのですが、今日のように心が躍りはしませんでした。
「あーんお肉硬くなっちゃったわぁ、ごめんねぇ」
「しばらくやっていなかったようだが、躑躅は料理が上手い。すぐに美味しいものを食べさせてもらえるようになるぞ」
確かに牛鍋は醤油の味が濃く、肉も煮込みすぎたのか、柔らかく食べる肉にしては、随分硬いように思いました。しかし、三人で囲む料理はあまりにも美味しく、これまでの生活では、美味しさを感じる余裕を失っていたのだと気が付いてしまいます。もちろん、旅行の時も美味しいものを食べさせてもらいましたけれど、旅行という特別感がありましたから、家というものに戻ってきてやっと気が付いたのでした。
「あたしが知らないうちに、ビフテキなんてものも出来てたのよね」
「日本人が肉を堂々食べるようになったのだな」
琥珀が美味しそうに食べるから、もう張り切っちゃうわね。期待しているぞ。あんたも何かしなさいよ。じゃあ釣りでもするかな。良いわね、大きいの釣ってきてちょうだい。二人の会話が心地よく胸に染みて、わたくしはこれから、きっと穏やかに生きていけるのだと、安心しました。
食事が終わると、蘿月様は裏の山に籠り、刀を扱えるようになるべく、鍛錬をしにいきました。わたくしが何か呆然と、出来ることはないか考えたものですが、思いつかず、先に躑躅さんにお土産を渡すことにしました。
躑躅さんのお土産に選んだのは、珠の形をした飾りの部分が開け閉めできる簪でした。洋装化の進む今の時代、きっといつか躑躅さんもハイカラな恰好をする時が来るでしょうから、夜会挿しの出来る形の簪にしてみたのです。躑躅さんはわたくしが差し出した簪をしげしげと眺め、それから少女のように顔を綻ばせて笑いました。
「とっても素敵」
「ここが開いて、中には躑躅の花の飾りが」
「まあ」
躑躅さんが簪を髪に挿し、ぎゅうとわたくしを抱きしめます。それはやっと、わたくしと落ち着いて暮らせることの喜びであるように思えました。
「あんたね、今度は長生きするのよ。あたしたちみたいに何百年何千年生きてとは言わないから」
「ええ」
「これまで歯食いしばって生きてきたでしょう」
「あ、いえ、自分が苦しんでいる自覚も持てなくて」
わたくしが曖昧に答えると、躑躅さんはほんの少し、目を伏せました。その睫毛が震えるのを、思わず見つめてしまいます。
「蘿月はあたしみたいに口数が多くないから、あいつの分も言っておくわ。長生きしてね」
今度は、必ず。そう答えると、躑躅さんは何度も頷いて、わたくしの頭を撫でました。
その日はまだ寝るための部屋が一つしか準備できていないということで、わたくしを挟んで、三人で川の字になって眠りました。もし、お母様が生きていて、お父様がわたくしとお母様を愛してくれたのなら、こうして眠ることもあったのでしょうか。そう思ったら、お母様が恋しく、またあのような死に際を悲しく思えてなりませんでした。そうして、志貴様の家に、お母様の形見である着物が置き去りになっていたことを思い出し、そこでの暮らしは着物も髪飾りも、すべて志貴様の用意したものである必要があったため、着ることも出来なかったことも思い出しました。もし、骨と共に取り戻すことが出来たのなら、この二人に、その着物を着た姿を見てほしいと、そう思いました。
「あらぁ、お帰りなさい」
足音と声に気が付いたのか、躑躅さんが飛び出してきます。着物は豪奢なままでしたが、上から割烹着を着ていて、抱きとめられると、野菜や醤油の香りが混ざったような、良い匂いがしました。
「やっぱり、あんたがいないと寂しいわァ。どう、楽しかった?」
「なんだか、躑躅さんの顔を見たら、安心しました」
「んもう、可愛いわねえ」
旅行はとても楽しかったです、と付け足すと、躑躅さんは「あっお鍋見てこなくちゃ」と慌てて家の中に戻っていきました。蘿月様に「俺たちも入ろう」と言われて、屋敷に足を踏み入れ、少々迷いながら、「ただいま戻りました」と言ってみました。
「おかえりおかえり」
躑躅さんも、おかえり、と言える人がいるのが嬉しいようで、九つの尻尾がうきうきと揺れています。こんな可愛らしくてうつくしい方が、わたくしの仇のために刀を打たせようとしたことがあったのだと思うと、なんだか苦しいような気がして、少し、泣きたくなりました。ただ、ここで突然泣くのも変だと思い、目元を覆いますと、躑躅さんも蘿月様も気が付いて、慌ててわたくしの顔を覗き込むのでした。
「蘿月になんかされた? あっ、分かった、腕羅に変なこと吹き込まれたでしょ」
「俺は変なことは」
「んもーっ、そうやって顔赤くしてもーっ、察しちゃうじゃないのよもうっ」
「す、すまん」
「琥珀が思い出して照れてるでしょッ、蘿月あんた責任取りなさいよ」
そう言われても、と蘿月様が半ば困ったような声色で言うので、なんだかおかしくなって、躑躅さんに突かれるまま、腕羅さんに言われたことを、洗いざらい話してしまいました。すると二人は顔を見合わせて、まず蘿月様がわたくしの頭を撫で、それから躑躅さんがわたくしをぎゅうと抱きしめました。
「あんたは気にしなくていいのよ、そんなこと。あたしらは人間じゃないし、特にあたしはもう、怒ったらとことんやるの。妖狐だもの、そうやって生きてきてるの」
「で、でも」
「お前は優しいな、ずっと変わらず」
「あたしたち、あんたのそういうところが大好きでしょうがないのよ。だからあんたが傷つけられるがどうしてもだめなの。許してね」
牛鍋ってやつ作ってるところなの、食べましょ、人間って食べたら元気出るって聞いたのよ。躑躅さんはそう言ってぱんと手を叩き、厨房に戻っていきました。わたくしがそれを目で追うと、今度は蘿月様がわたくしを抱き寄せ、何か祈るように、わたくしの背を撫で続けるのでした。
牛鍋、というのは、志貴様と共に食べたことはあったのですが、こんなに美味しいものだということは、知りませんでした。牛肉はまだ高いものですから、一生懸命美味しいと言ってみたのですが、今日のように心が躍りはしませんでした。
「あーんお肉硬くなっちゃったわぁ、ごめんねぇ」
「しばらくやっていなかったようだが、躑躅は料理が上手い。すぐに美味しいものを食べさせてもらえるようになるぞ」
確かに牛鍋は醤油の味が濃く、肉も煮込みすぎたのか、柔らかく食べる肉にしては、随分硬いように思いました。しかし、三人で囲む料理はあまりにも美味しく、これまでの生活では、美味しさを感じる余裕を失っていたのだと気が付いてしまいます。もちろん、旅行の時も美味しいものを食べさせてもらいましたけれど、旅行という特別感がありましたから、家というものに戻ってきてやっと気が付いたのでした。
「あたしが知らないうちに、ビフテキなんてものも出来てたのよね」
「日本人が肉を堂々食べるようになったのだな」
琥珀が美味しそうに食べるから、もう張り切っちゃうわね。期待しているぞ。あんたも何かしなさいよ。じゃあ釣りでもするかな。良いわね、大きいの釣ってきてちょうだい。二人の会話が心地よく胸に染みて、わたくしはこれから、きっと穏やかに生きていけるのだと、安心しました。
食事が終わると、蘿月様は裏の山に籠り、刀を扱えるようになるべく、鍛錬をしにいきました。わたくしが何か呆然と、出来ることはないか考えたものですが、思いつかず、先に躑躅さんにお土産を渡すことにしました。
躑躅さんのお土産に選んだのは、珠の形をした飾りの部分が開け閉めできる簪でした。洋装化の進む今の時代、きっといつか躑躅さんもハイカラな恰好をする時が来るでしょうから、夜会挿しの出来る形の簪にしてみたのです。躑躅さんはわたくしが差し出した簪をしげしげと眺め、それから少女のように顔を綻ばせて笑いました。
「とっても素敵」
「ここが開いて、中には躑躅の花の飾りが」
「まあ」
躑躅さんが簪を髪に挿し、ぎゅうとわたくしを抱きしめます。それはやっと、わたくしと落ち着いて暮らせることの喜びであるように思えました。
「あんたね、今度は長生きするのよ。あたしたちみたいに何百年何千年生きてとは言わないから」
「ええ」
「これまで歯食いしばって生きてきたでしょう」
「あ、いえ、自分が苦しんでいる自覚も持てなくて」
わたくしが曖昧に答えると、躑躅さんはほんの少し、目を伏せました。その睫毛が震えるのを、思わず見つめてしまいます。
「蘿月はあたしみたいに口数が多くないから、あいつの分も言っておくわ。長生きしてね」
今度は、必ず。そう答えると、躑躅さんは何度も頷いて、わたくしの頭を撫でました。
その日はまだ寝るための部屋が一つしか準備できていないということで、わたくしを挟んで、三人で川の字になって眠りました。もし、お母様が生きていて、お父様がわたくしとお母様を愛してくれたのなら、こうして眠ることもあったのでしょうか。そう思ったら、お母様が恋しく、またあのような死に際を悲しく思えてなりませんでした。そうして、志貴様の家に、お母様の形見である着物が置き去りになっていたことを思い出し、そこでの暮らしは着物も髪飾りも、すべて志貴様の用意したものである必要があったため、着ることも出来なかったことも思い出しました。もし、骨と共に取り戻すことが出来たのなら、この二人に、その着物を着た姿を見てほしいと、そう思いました。