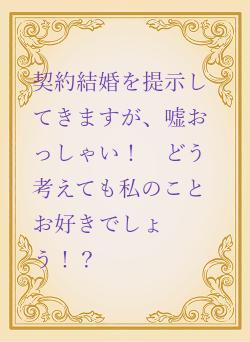途中途中で蘿月様に抱えられていたとはいえ、山に入るとやはり疲れますので、帰りは団子だけ途中で食べて、すぐに宿に戻りました。二人してぐったりと横たわり、それから、声を上げて笑いました。
「律儀な方でしたね」
「半端にな。騙されるなよ、本当に律儀なやつは依頼の刀を溶かしなんかしないんだ」
「でも、騙したり、気にしたりしない方なら、もう引っ越していますもの」
だから怒り切れないのだよな、と蘿月様はぼやきます。だから嫌いではないのだよな、とも。
「腕羅さんとは、どこで知り合ったのですか」
尋ねると、三百年前だったか、と彼が呟いて、それからはっとしたように言います。先ほどは、お前を置いて盛り上がってしまってすまないと。
「お気になさることはありません。人というもの、そのようなこといくらでもあります」
わたくしはそう笑って答えましたが、不思議と胸が痛むのです。しかしこの胸の痛みの理由は、あの時あの場で、わたくしだけ話に混ざれなかったことだけではなく、他にもあるような気がして、わたくしはじっと考え込み、やがて気が付きました。
どうやらわたくしは、皆の記憶は何百年以上、二千年以上と続いていますのに、わたくしだけが、十四年分の記憶しか持っていないことが、悔しくて、そして悲しいようでした。蘿月様はさくやであった頃のわたくしを知っているのに、わたくしは知りません。躑躅様は、どうもわたくしに恩を受けたようなのに、わたくしはその恩が何であったのかを覚えていません。志貴様のことはあまり思い出したくはないのですが、志貴様もまた、わたくしを五百年、狂うほど愛していることになりますのに、わたくしは前世で彼にされた恐ろしいことも、ちっとも覚えていないのです。蘿月様に対しては、なんとなく、魂に慈しみや愛おしさというのが刻み込まれていましたが、ずっとわたくしと共にいたもう一人の、躑躅様のことを覚えていないばかりか、蘿月様へも、そんな、ぼんやりとした気持ちしか抱えてこられなかったのです。蘿月様に拾われてから、少しずつ言葉を重ねてきて、わたくしと魂を同じくする四人が、神とその贄である以上に、蘿月様を恋い慕い、愛しみ、日々を大切に過ごしてきたことも、蘿月様に穏やかに愛されて来たことも分かってしまいますので、彼らが抱えて来た記憶が、わたくしにないために彼らに悲しい想いをさせているのではないかと考えてしまいますし、何より、わたくしは、このことが悲しく、悔しく、寂しいのでした。それを、先ほどのお互いのことを知っている二人の、まるで親友のようなやり取りを見て、自覚しただけに過ぎないのですが、一度自覚してしまうと、涙を堪えることが難しくなります。
蘿月様は突然涙を滲ませたわたくしに驚いたようでしたが、やはりというべきかなんというべきか、わたくしがこのような理由で泣き出すのも分かっていたようで、優しい笑みを浮かべて、そっと目尻に指先を寄せてくるのでした。きっと、翡翠も同じように泣いたのだと、思いました。
「忘れるのは、悪いことではないのだ」
「でもわたくし、せめて、ひとつくらい、覚えていたかったです」
彼はわたくしの耳を撫でながら、「この世の魂は輪廻を繰り返すのに、皆前世のことを覚えていないか分かるか」と尋ねてきました。わたくしが首を振ると、彼はまた少し悩んで、幼子に言い聞かせるような優しさを持ちながらも、大人を扱うような丁寧さで、神様の持つ感性の話をしてくれるのでした。
曰く、この世の魂は皆、天の世界で浄化を受けてから、新しい身体に宿るのだそうですが、その際に、魂に染みついた汚れと呼ぶべきものをそぎ落とす時に、記憶というものも一緒に零れ落ちてしまうのだそうです。新たな魂として生まれるには、生前のしがらみというものが災いをすることがしばしばあるからなのですが、彼曰く、人の魂を扱う神様は少々乱暴で、浄化というものをすぐに終わらせるために、すべての記憶を抜き取ってしまうのだそうで。わたくしの場合、お役目というものを忘れないようにしつつ、吸い取った穢れを浄化するのに必要な年数が、五百年近い、ということなのだそうです。記憶を全て留めようと思えば千年近く必要になるとのことなので、それでは蘿月様が祟り神になってもおかしくありませんから、仕方なく、ほとんどのことを覚えていない状態で、かんなぎとして送り出されるのだそうです。
「俺は、お前が翡翠だった時にされたことを、覚えていなくて良かったと思っている。あまりにも惨いことをされたから」
「確かにそう、なのですが」
「お前が覚えていなくても、俺は覚えているし、躑躅も覚えている。忘れて生まれてきてしまったとしても、知りたい分は俺たちが教える。いくらでも、語って聞かせよう」
わたくしの耳をまだ撫でる彼が、あんまりにも優しい顔をして言うものですから、わたくしは、「じゃあ」と口に出しました。
「わたくしが最初に、さくやの時に蘿月様にお会いした時、わたくしは、何て言ったのでしょうか」
「うむ。『お初にお目にかかります。わたくしが、貴方様のかんなぎだそうで、導く声に従って、やってまいりました。神官の家の巫女ではありますが、名を持ちませんので、どうかお好きに呼んでくださいませ』だな、今の言葉に直すと」
「じゃあ、じゃあ、翡翠のわたくしが――」
わたくしは夜遅くまで、過去の話をねだりました。彼は様々な出来事を事細かく覚えているようで、時折悩みはしましたが、たいていのことを、淀みなく答えるのでした。話を聞くほどに、もっと知りたい、もっと知りたいと思うようになり、あれもこれもと、聞き分けのない子どものようにせがんでいたのですが、ずいぶん久しぶりに我儘を言っていると気が付き、でも、わたくしの我儘を少しも咎めようとしない彼に、甘えました。そうしている間に、抱えていた寂しさが埋まるようにも、どんどん深くなるような気もして、やめられませんでした。
「そんな、都合よく頭の上に柿が落ちるなんて」
「躑躅が慌ててなぁ。俺も焦ったのだが、躑躅がお前を抱えて、町医者のところまで走っていってしまったのだ。俺も追いかけたら、こぶはできているが大事はないと言われていたよ。帰りは俺が抱えて歩いた」
話は続き、わたくしはいつの間にか眠っていたのですが、朝起きて、彼が穏やかに眠っているのを見て、不思議なことに、泣きたくなるほど安心しました。こうして彼のことを見つめるわたくしがいたことに、ほっとしたのかもしれません。
その日も二人で箱根を歩いて、また昔の話をねだり、夜になって、今度こそ抱いて欲しいと頭を下げました。こういったことにお願いをするのは、変なのかもしれませんが、やはり翡翠だったわたくしの死に方を思うと、早く手を出してもらうに越したことはありません。本来愛する人が、愛を確かめ合うために行うものなのでしょうけれど、わたくしは蘿月様の贄として生きてられるという安寧を、早く得たかったのです。それは蘿月様にも伝わってしまったようで、彼はわたくしの背を撫で、決心したように、わたくしの浴衣の帯をほどき、腰ひもを解き、身体を露わにしました。本当は、身体がきちんと成長してからの方が、お前に負担がなくて良いのだと彼は言いましたが、この一回だけは急いでほしいと思い、彼の首に腕を回します。
彼はわたくしの背中の傷の、呪いを断ち切るための噛み痕をしばらく気にしていましたが、やがて優しいやさしい口づけが降ってきます。彼はわたくしの身体を終始気遣って、できるだけ痛くないように、苦しくないようにと、慎重に事を進めてくるのが、愛おしく、切なく、寂しく、嬉しく、二人の身体の奥が同じ温度になった時、ああ、幸せなのだと思いました。そして、すべてが終わった後、これで志貴様にあのような目を向けられなくて済むのだと思い、安心して、ぽろぽろと涙をこぼし続けました。彼のまだほんのり熱を帯びた肌に顔をうずめて、これからはきっと、この優しくてもろい人のお傍にいられるのだと思ったら、心の奥で積み上げてきた、自分を守るための壁が、用をなくして崩れていったのです。
「わたくしのこと、大事にしてくれているのに、ごめんなさい」
「何を謝ることがあるのだ。ほら、冷える前に服を着なさい」
「あとは、もっと大人になってからで、良いですから」
彼はわたくしの頭を撫で、畳に散らかった浴衣で、包んでくれました。ゆっくり大人になりなさい、俺は急がないから。そんな彼の言葉に、わたくしが愛されているという実感を、やっと持ったのでした。
「律儀な方でしたね」
「半端にな。騙されるなよ、本当に律儀なやつは依頼の刀を溶かしなんかしないんだ」
「でも、騙したり、気にしたりしない方なら、もう引っ越していますもの」
だから怒り切れないのだよな、と蘿月様はぼやきます。だから嫌いではないのだよな、とも。
「腕羅さんとは、どこで知り合ったのですか」
尋ねると、三百年前だったか、と彼が呟いて、それからはっとしたように言います。先ほどは、お前を置いて盛り上がってしまってすまないと。
「お気になさることはありません。人というもの、そのようなこといくらでもあります」
わたくしはそう笑って答えましたが、不思議と胸が痛むのです。しかしこの胸の痛みの理由は、あの時あの場で、わたくしだけ話に混ざれなかったことだけではなく、他にもあるような気がして、わたくしはじっと考え込み、やがて気が付きました。
どうやらわたくしは、皆の記憶は何百年以上、二千年以上と続いていますのに、わたくしだけが、十四年分の記憶しか持っていないことが、悔しくて、そして悲しいようでした。蘿月様はさくやであった頃のわたくしを知っているのに、わたくしは知りません。躑躅様は、どうもわたくしに恩を受けたようなのに、わたくしはその恩が何であったのかを覚えていません。志貴様のことはあまり思い出したくはないのですが、志貴様もまた、わたくしを五百年、狂うほど愛していることになりますのに、わたくしは前世で彼にされた恐ろしいことも、ちっとも覚えていないのです。蘿月様に対しては、なんとなく、魂に慈しみや愛おしさというのが刻み込まれていましたが、ずっとわたくしと共にいたもう一人の、躑躅様のことを覚えていないばかりか、蘿月様へも、そんな、ぼんやりとした気持ちしか抱えてこられなかったのです。蘿月様に拾われてから、少しずつ言葉を重ねてきて、わたくしと魂を同じくする四人が、神とその贄である以上に、蘿月様を恋い慕い、愛しみ、日々を大切に過ごしてきたことも、蘿月様に穏やかに愛されて来たことも分かってしまいますので、彼らが抱えて来た記憶が、わたくしにないために彼らに悲しい想いをさせているのではないかと考えてしまいますし、何より、わたくしは、このことが悲しく、悔しく、寂しいのでした。それを、先ほどのお互いのことを知っている二人の、まるで親友のようなやり取りを見て、自覚しただけに過ぎないのですが、一度自覚してしまうと、涙を堪えることが難しくなります。
蘿月様は突然涙を滲ませたわたくしに驚いたようでしたが、やはりというべきかなんというべきか、わたくしがこのような理由で泣き出すのも分かっていたようで、優しい笑みを浮かべて、そっと目尻に指先を寄せてくるのでした。きっと、翡翠も同じように泣いたのだと、思いました。
「忘れるのは、悪いことではないのだ」
「でもわたくし、せめて、ひとつくらい、覚えていたかったです」
彼はわたくしの耳を撫でながら、「この世の魂は輪廻を繰り返すのに、皆前世のことを覚えていないか分かるか」と尋ねてきました。わたくしが首を振ると、彼はまた少し悩んで、幼子に言い聞かせるような優しさを持ちながらも、大人を扱うような丁寧さで、神様の持つ感性の話をしてくれるのでした。
曰く、この世の魂は皆、天の世界で浄化を受けてから、新しい身体に宿るのだそうですが、その際に、魂に染みついた汚れと呼ぶべきものをそぎ落とす時に、記憶というものも一緒に零れ落ちてしまうのだそうです。新たな魂として生まれるには、生前のしがらみというものが災いをすることがしばしばあるからなのですが、彼曰く、人の魂を扱う神様は少々乱暴で、浄化というものをすぐに終わらせるために、すべての記憶を抜き取ってしまうのだそうで。わたくしの場合、お役目というものを忘れないようにしつつ、吸い取った穢れを浄化するのに必要な年数が、五百年近い、ということなのだそうです。記憶を全て留めようと思えば千年近く必要になるとのことなので、それでは蘿月様が祟り神になってもおかしくありませんから、仕方なく、ほとんどのことを覚えていない状態で、かんなぎとして送り出されるのだそうです。
「俺は、お前が翡翠だった時にされたことを、覚えていなくて良かったと思っている。あまりにも惨いことをされたから」
「確かにそう、なのですが」
「お前が覚えていなくても、俺は覚えているし、躑躅も覚えている。忘れて生まれてきてしまったとしても、知りたい分は俺たちが教える。いくらでも、語って聞かせよう」
わたくしの耳をまだ撫でる彼が、あんまりにも優しい顔をして言うものですから、わたくしは、「じゃあ」と口に出しました。
「わたくしが最初に、さくやの時に蘿月様にお会いした時、わたくしは、何て言ったのでしょうか」
「うむ。『お初にお目にかかります。わたくしが、貴方様のかんなぎだそうで、導く声に従って、やってまいりました。神官の家の巫女ではありますが、名を持ちませんので、どうかお好きに呼んでくださいませ』だな、今の言葉に直すと」
「じゃあ、じゃあ、翡翠のわたくしが――」
わたくしは夜遅くまで、過去の話をねだりました。彼は様々な出来事を事細かく覚えているようで、時折悩みはしましたが、たいていのことを、淀みなく答えるのでした。話を聞くほどに、もっと知りたい、もっと知りたいと思うようになり、あれもこれもと、聞き分けのない子どものようにせがんでいたのですが、ずいぶん久しぶりに我儘を言っていると気が付き、でも、わたくしの我儘を少しも咎めようとしない彼に、甘えました。そうしている間に、抱えていた寂しさが埋まるようにも、どんどん深くなるような気もして、やめられませんでした。
「そんな、都合よく頭の上に柿が落ちるなんて」
「躑躅が慌ててなぁ。俺も焦ったのだが、躑躅がお前を抱えて、町医者のところまで走っていってしまったのだ。俺も追いかけたら、こぶはできているが大事はないと言われていたよ。帰りは俺が抱えて歩いた」
話は続き、わたくしはいつの間にか眠っていたのですが、朝起きて、彼が穏やかに眠っているのを見て、不思議なことに、泣きたくなるほど安心しました。こうして彼のことを見つめるわたくしがいたことに、ほっとしたのかもしれません。
その日も二人で箱根を歩いて、また昔の話をねだり、夜になって、今度こそ抱いて欲しいと頭を下げました。こういったことにお願いをするのは、変なのかもしれませんが、やはり翡翠だったわたくしの死に方を思うと、早く手を出してもらうに越したことはありません。本来愛する人が、愛を確かめ合うために行うものなのでしょうけれど、わたくしは蘿月様の贄として生きてられるという安寧を、早く得たかったのです。それは蘿月様にも伝わってしまったようで、彼はわたくしの背を撫で、決心したように、わたくしの浴衣の帯をほどき、腰ひもを解き、身体を露わにしました。本当は、身体がきちんと成長してからの方が、お前に負担がなくて良いのだと彼は言いましたが、この一回だけは急いでほしいと思い、彼の首に腕を回します。
彼はわたくしの背中の傷の、呪いを断ち切るための噛み痕をしばらく気にしていましたが、やがて優しいやさしい口づけが降ってきます。彼はわたくしの身体を終始気遣って、できるだけ痛くないように、苦しくないようにと、慎重に事を進めてくるのが、愛おしく、切なく、寂しく、嬉しく、二人の身体の奥が同じ温度になった時、ああ、幸せなのだと思いました。そして、すべてが終わった後、これで志貴様にあのような目を向けられなくて済むのだと思い、安心して、ぽろぽろと涙をこぼし続けました。彼のまだほんのり熱を帯びた肌に顔をうずめて、これからはきっと、この優しくてもろい人のお傍にいられるのだと思ったら、心の奥で積み上げてきた、自分を守るための壁が、用をなくして崩れていったのです。
「わたくしのこと、大事にしてくれているのに、ごめんなさい」
「何を謝ることがあるのだ。ほら、冷える前に服を着なさい」
「あとは、もっと大人になってからで、良いですから」
彼はわたくしの頭を撫で、畳に散らかった浴衣で、包んでくれました。ゆっくり大人になりなさい、俺は急がないから。そんな彼の言葉に、わたくしが愛されているという実感を、やっと持ったのでした。