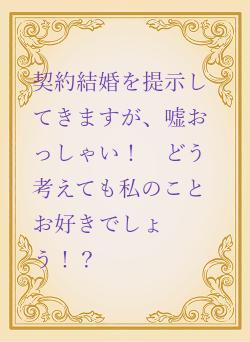これは、時を超えて紡がれる愛の物語。そして、虐げられた少女が、己の運命を知り、優しく愛され、慈しまれることを知る物語でございます。
それは揺り籠に揺られているような、穏やかな、温かな夢でした。しかし不思議と切なく、目が覚めた後はいつも、泣きたいような気持ちになるのです。
誰かがわたくしの名を呼んでいます。琥珀、と呼ばれているわけではないのですが、どうしてか、彼が呼んでいるのは私だと分かります。夢はいつだって朧気で、目が覚めた後は、名前を呼ばれていることしか思い出せないのですが、その声には、慈しみが籠められているような気がしてならないのです。
目が覚めると、障子の隙間から差し込んだ月が、わたくしの顔を照らしていました。月と視線が絡むと、目が反らされるように雲に隠れます。部屋に落ちるのは暗闇のみになり、わたくしはひとつ、息を吐きました。目尻から零れた涙がぽとりぽとり、褥の上に落ちます。そうやって涙を零してようやく、わたくしは曖昧な揺籃のような夢から現実に引き上げられ、またあの夢を見ていたのだと、ぼんやりと知るのでした。
わたくしが不思議な夢を見るようになったのは、月のものがはじまってからでした。まだそれから一月経っていない頃でしょうか。わたくしは月のものが始まらないように、始まらないように、とずっと祈っていたのですが、身体の成長は残酷で、少しずつ少しずつ、身体の内側も外側も構わず、女に変えられていきました。もっとも、わたくしが身体から血が流れるのを恐れていたのは、夢を見ると知っていたからではありません。それはわたくしの生まれとお母様の死に方に関係があります。
わたくしは横浜にある、椎名という男爵の家に生まれました。お父様の一家は明治維新にいくらか政略の面で貢献したようで、それから男爵の地位を授かりました。それからお母様を結婚相手に貰い受け、子を為そうとしたそうですが、何年も子に恵まれなかったようで、お父様は妾を家に囲い、そちらにも子を求めるようになりました。不運だったのは、わたくしと腹違いの妹が、ほとんど同時に胎に宿ったことでしょうか。わたくしが男に生まれなかったことでしょうか。わたくしが春のはじめに生まれ落ち、妹が春の終わりに産声を上げたのですが、妾は女子が生まれたのを喜ばれたのに関わらず、わたくしは男子でなかったことを悲しまれたようです。それから二年後、お母様が子を成すことがなかったのに関わらず、妾が男子を産んだことで、お母様とわたくしは冷遇されるようになりました。
日本に限らない話だと思うのですが、女という生き物は、その家に嫁ぎ、その家の子を産むことで価値がつけられます。子が出来なければ実家に帰される、なんてことは当たり前にありますので、お母様が生家に返される前にわたくしが胎に宿ったのは、幸運であったのかもしれませんし、不幸であったのかもしれません。お父様とお母様が政略結婚であったのに対し、お父様と妾は恋愛関係にあったそうですから、そもそも、何か理由を見つけて、妾の方を大切にしたかったのでしょう。お母様が男子を作れなかったのが、都合が良かっただけなのでしょう。わたくしが尋常小学校に通っている間にお母様が死んだのは、肺の病のせいなのですが、お父様と妾、そしてその子たちに冷遇されたために命を短くしてしまったのではないかと、そう思ってしまうのです。それらの出来事は子が出来なければ嫁入り先に捨てられる、という恐怖心を植え付けるには十分でした。わたくしがお母様に似たとすれば、子が出来にくい身体かもしれませんから、月のものが来て、子が産める身体になり、婚約者である志貴様に求められるようになるのが恐ろしかったのです。
志貴様は立派な呪術師として、この辺りの者だけでなく、遠くに住む者たちからも頼りにされているようですので、きっと彼に夢のことを聞けば何か分かるのかもしれませんが、夢のことを話すとなると、月のものが来たことを話さなくてはなりません。そうなった時、わたくしはいよいよ志貴様と夫婦の契りを結ぶことになります。まだわたくしは十四ですから、あともう少しの間は、月のものが来なくてもおかしくない歳でいられますので、女として価値がないと断じられるかもしれない時を先延ばしにしたいと思っていました。
褥に零れ落ち続ける涙を拭い、起き上がって障子を閉めました。こういう時、妹のほたるならば、寂しいとか悲しいとか、そんな理由を並べて婚約者に甘えて可愛がられるのでしょうけれど、生憎わたくしは、愛らしい甘え方を知りません。志貴様の部屋とわたくしの部屋は壁ひとつで遮られているだけですので、きっと、壁越しに何かささやくだけでも彼に届くのかもしれませんが、彼はわたくしが従順な人形でいなければひどく怒る性質です。彼の操り人形でありながらも可愛がられる女でいるような器用さは持ち合わせていないと、悲しいことにわたくしは知っていますので、ひとり、寂寥感とも郷愁とも慈しみともつかないこの感情を持て余し、ただ眠りにつくことを祈るのでした。
それは揺り籠に揺られているような、穏やかな、温かな夢でした。しかし不思議と切なく、目が覚めた後はいつも、泣きたいような気持ちになるのです。
誰かがわたくしの名を呼んでいます。琥珀、と呼ばれているわけではないのですが、どうしてか、彼が呼んでいるのは私だと分かります。夢はいつだって朧気で、目が覚めた後は、名前を呼ばれていることしか思い出せないのですが、その声には、慈しみが籠められているような気がしてならないのです。
目が覚めると、障子の隙間から差し込んだ月が、わたくしの顔を照らしていました。月と視線が絡むと、目が反らされるように雲に隠れます。部屋に落ちるのは暗闇のみになり、わたくしはひとつ、息を吐きました。目尻から零れた涙がぽとりぽとり、褥の上に落ちます。そうやって涙を零してようやく、わたくしは曖昧な揺籃のような夢から現実に引き上げられ、またあの夢を見ていたのだと、ぼんやりと知るのでした。
わたくしが不思議な夢を見るようになったのは、月のものがはじまってからでした。まだそれから一月経っていない頃でしょうか。わたくしは月のものが始まらないように、始まらないように、とずっと祈っていたのですが、身体の成長は残酷で、少しずつ少しずつ、身体の内側も外側も構わず、女に変えられていきました。もっとも、わたくしが身体から血が流れるのを恐れていたのは、夢を見ると知っていたからではありません。それはわたくしの生まれとお母様の死に方に関係があります。
わたくしは横浜にある、椎名という男爵の家に生まれました。お父様の一家は明治維新にいくらか政略の面で貢献したようで、それから男爵の地位を授かりました。それからお母様を結婚相手に貰い受け、子を為そうとしたそうですが、何年も子に恵まれなかったようで、お父様は妾を家に囲い、そちらにも子を求めるようになりました。不運だったのは、わたくしと腹違いの妹が、ほとんど同時に胎に宿ったことでしょうか。わたくしが男に生まれなかったことでしょうか。わたくしが春のはじめに生まれ落ち、妹が春の終わりに産声を上げたのですが、妾は女子が生まれたのを喜ばれたのに関わらず、わたくしは男子でなかったことを悲しまれたようです。それから二年後、お母様が子を成すことがなかったのに関わらず、妾が男子を産んだことで、お母様とわたくしは冷遇されるようになりました。
日本に限らない話だと思うのですが、女という生き物は、その家に嫁ぎ、その家の子を産むことで価値がつけられます。子が出来なければ実家に帰される、なんてことは当たり前にありますので、お母様が生家に返される前にわたくしが胎に宿ったのは、幸運であったのかもしれませんし、不幸であったのかもしれません。お父様とお母様が政略結婚であったのに対し、お父様と妾は恋愛関係にあったそうですから、そもそも、何か理由を見つけて、妾の方を大切にしたかったのでしょう。お母様が男子を作れなかったのが、都合が良かっただけなのでしょう。わたくしが尋常小学校に通っている間にお母様が死んだのは、肺の病のせいなのですが、お父様と妾、そしてその子たちに冷遇されたために命を短くしてしまったのではないかと、そう思ってしまうのです。それらの出来事は子が出来なければ嫁入り先に捨てられる、という恐怖心を植え付けるには十分でした。わたくしがお母様に似たとすれば、子が出来にくい身体かもしれませんから、月のものが来て、子が産める身体になり、婚約者である志貴様に求められるようになるのが恐ろしかったのです。
志貴様は立派な呪術師として、この辺りの者だけでなく、遠くに住む者たちからも頼りにされているようですので、きっと彼に夢のことを聞けば何か分かるのかもしれませんが、夢のことを話すとなると、月のものが来たことを話さなくてはなりません。そうなった時、わたくしはいよいよ志貴様と夫婦の契りを結ぶことになります。まだわたくしは十四ですから、あともう少しの間は、月のものが来なくてもおかしくない歳でいられますので、女として価値がないと断じられるかもしれない時を先延ばしにしたいと思っていました。
褥に零れ落ち続ける涙を拭い、起き上がって障子を閉めました。こういう時、妹のほたるならば、寂しいとか悲しいとか、そんな理由を並べて婚約者に甘えて可愛がられるのでしょうけれど、生憎わたくしは、愛らしい甘え方を知りません。志貴様の部屋とわたくしの部屋は壁ひとつで遮られているだけですので、きっと、壁越しに何かささやくだけでも彼に届くのかもしれませんが、彼はわたくしが従順な人形でいなければひどく怒る性質です。彼の操り人形でありながらも可愛がられる女でいるような器用さは持ち合わせていないと、悲しいことにわたくしは知っていますので、ひとり、寂寥感とも郷愁とも慈しみともつかないこの感情を持て余し、ただ眠りにつくことを祈るのでした。