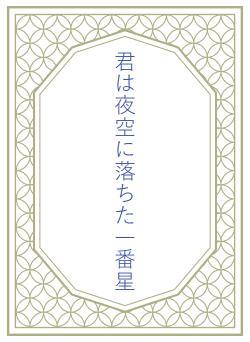翌朝、王城の正殿にて緊急の評議が開かれた。
夜明けの陽は鈍く、広間の障子越しに射し込む光も、どこか冷たさを帯びている。
霊障事件――そして、火見久遠による龍の鎮魂。
この一件はもはや噂の域を超え、宮廷の重職たちの耳にまで届いていた。
その結果、かつてなき異例の場が設けられることとなった。
『二人の巫女』が並び立つ、真贋を問う裁きの席である。
白張りの間に、鈴の音が響く。
端然と並んだ文官と祭官たちが、静かに目を閉じ、裁定の時を待っていた。
中央に進み出たのは、火見家の長女・千早。
純白の神衣に身を包み、真珠をあしらった髪飾りが、彼女の凛然たる美貌を際立たせていた。
誰が見ても『理想の巫女』そのもの――ただし、表面だけを見ればの話だ。
そのすぐ後ろに、ひとりの少女が歩み出る――妹・久遠だった。
彼女の衣は、粗末とはいかぬまでも、千早に比べれば質素だった。
けれど、背筋は真っすぐに伸び、指先まで緊張のない所作で整っていた。
それは、与えられたものではない、自身で得た立ちの『姿』だった。
▽
「火見千早殿、あなたが王家の巫女としてこれまで多くの儀式を司ってきたことは、記録に明らかである」
「だが、昨夜の霊障において、龍の加護が応じたのは、あなたではなかった」
年配の官僚の声が、室内に静かに響いた。
千早は微笑を崩さず、深く一礼する。
「……確かに、霊障は私の祈祷中に治まりました。ですが、それが私でない誰かによるものとは、判断しかねます」
言葉遣いは丁寧で、声にも迷いはなかった。
だが、それは事実を認めたくないと言う考えだと、聞く者には映っていた。
「では、龍が応じたというこの者――火見久遠の存在について、どうお考えですか」
「……あの者は、かつて霊力を示すことなく、正統な巫女候補から外された者です……そのような者が、龍と契りを交わすなど……いささか信じ難い話かと」
ざわ、と静かな波紋が広がった。
誰もが思っていたことを、あえて口にした――だが、今はそれが『言ってはならないこと』になりつつある空気があった。
久遠は何も言わない。
ただ、静かに立ち尽くし、視線を落としたまま木札を取り出した。
それは、黒龍の霊紋が淡く輝く、契約の証。
祭官のひとりが、木札を受け取り、慎重に霊視を行った。
沈黙し、そして――震える声が、告げた。
「これは……確かに、黒龍の直霊による加護……火見久遠殿は、龍と正しく契りを交わしておられます」
その場にいた全員が、わずかに息を呑んだ。
「……そんな……っ」
千早の声が、微かに掠れた。
その顔から血の気が引き、目元に見えないひびが入っていく。
「久遠は……何もできなかったはず……!封じられていたはずなのに……っ」
その言葉に、会場がざわつく。
重ねるように、老臣の一人が口を開いた。
「封じられていた……とな?」
沈黙――千早の唇が動きかけ、言葉が出ない。
久遠のまなざしが、姉を見つめていた。何の怒りも、軽蔑もなかった。
ただ、まっすぐに――そのまなざしに千早は耐えられなかった。
その眼差しは、姉として自分が決して与えようとしなかった『瞳』だったから。
▽
調査の結果、かつて火見家内で久遠に対し、不当な処置――霊脈封じの施術が無断で行われていた記録が確認された。
それは、正統な巫女候補から遠ざけるための手段であり、そして、その命令を出したのが、他ならぬ千早だったことも明るみに出る。
「火見千早。そなたの行為は、巫女の名に泥を塗るもの」
「もはや、王家の龍を託すには相応しくない」
静かに、そして確かに。
裁定が下される。
火見千早、巫女の資格剥奪。火見宗家、しばらくの間、祭職を停止。
一方――火見久遠、黒龍との契約者として、新たに『暁巫女』の位を授与。
▽
久遠が暁巫女として王城に迎えられた日、都の空には薄く霞がかかっていた。春の兆しは確かにあったが、風はまだ肌寒く、冬の名残を引きずっていた。
それでも、都の人々は広場へと集まった。
誰もが『選ばれし巫女』の姿を一目見ようと、静かに息をひそめていた。
緋の装束を纏った久遠が、舞台の中央に進み出たとき、場にいた誰もが息をのむ。
彼女の動きは派手ではなかった。
それでも、風と音と大地が、彼女に呼応するようにゆっくりと満ちていくのが感じられた。
その胸元には、黒龍の契りの証が静かに輝いていた。
鈴の音が一つ。
そのとき、空を滑るように黒龍の影が現れた。
雄大で、しかし威圧することなく。
風が広場をめぐり、花の香りを運び、すべてが静かに祝福へと移っていった。
誰もが理解した。
龍が応えたのは、この少女の声だったのだと。
そして、囁きがひとつ、またひとつと伝わっていく。
「黒龍が選んだのは、火見家の長女ではない」
「名も呼ばれなかった『影』の妹だったのだ」と。
▽
式が終わり、人の波が引いていったあと、城の裏庭にただひとり立つ久遠の姿があった。
春を待つ桜の枝はまだ裸木で、けれどその枝先には小さく膨らんだ蕾が見えた。
「……ここまで、来たんですね」
久遠の声は静かだった。
けれど、胸の奥には重く澱のように沈んでいたものが、少しずつほどけていく感覚があった。
ずっと、自分は何者でもなかった。
霊力がないと言われ、名も立場も与えられず、姉の影として扱われて、誰かの役に立つことでしか、ここにいてよい理由を見出せなかった。
けれど、黒龍は応えてくれた。
『おまえの声を聞いている』と、確かに言ってくれた。
その声が、久遠をここまで連れてきたのだ。
「……お前が歩いてきたからだ」
背後から響いた声に、久遠ははっと振り返る。
朔真が、そこに立っていた。
以前と変わらない黒の衣に身を包み、無表情に近い顔で、けれど目だけはまっすぐに彼女を見ていた。
「式を見ていましたか?」
「……見てた」
「どう、でしたか?」
久遠は、冗談めかした口調で問うた。
けれどその声はほんの少し、震えていた。
朔真は答えず、しばらく風に耳を澄ませていた。
「巫女の姿でも、あの山で木を折って転んでたときのままだな」
思わず久遠は吹き出す。
それは、緊張が少しだけほどけた証だった。
「朔真さんって、たまにひどいこと言いますね」
「事実だ」
どちらからともなく笑みが浮かんだ。
けれど、沈黙のあとの風が通り抜けたとき、久遠はふと声を落とした。
「……怖かったんです」
そのひと言に、朔真が静かに目を向ける。
「今も、時々思ってしまうんです。私はまだ、『影』のままなんじゃないかって……名前を呼ばれなかった日々が、心に刻まれすぎていて……」
朔真は答えなかった。
久遠もそれ以上、何も言わずに、ただ空を仰いだ。
ふたりの間を、風が一筋通り過ぎた。
それから、久遠はほんの少しだけ勇気を振り絞って、言った。
「……私、あなたに会いたかったんです……この式が終わったら、真っ先に、朔真さんのところへ行こうって、そう思ってました」
朔真の目が、ほんのわずかに驚きを見せた。
けれどその奥には、やわらかなものが灯っていた。
「俺も、お前の声をずっと聞いてた……言葉にしなくても、そばにいるだけで伝わる気がした。でも……それじゃ、足りない気もしていた」
朔真がゆっくりと近づいてくる。
久遠の視線が、彼の目を真っ直ぐに捉えた。
「私は……もう、『選ばれる』のを待ちたくない……私から、選びたい。あなたを、選びたいんです」
その言葉に、朔真の手がそっと久遠の指に触れた。
その手は温かく、けれど震えていた。
きっと彼も、同じように迷い、恐れていたのだと、久遠は思った。
「……俺も、そう思っていた」
ふたりの手が静かに絡む。
月が、空の高みから光を注いでいた。
その光の中、黒龍の影がゆっくりと空を巡っていく。
――影に咲いた花は、やがて暁を導く
久遠は、黒龍の声を胸の奥に感じた。
(ああ、そうか――私は、もうひとりじゃないんだ)
『影』として歩んできた日々は、私を消すためのものじゃなかった。
そこにこそ、私自身があったのだ。
そして今、その隣に朔真がいる。
「……これからも、そばにいてくれますか?私が影だったことを、忘れずにいてくれますか?」
「忘れない。影だったお前が、俺にとっては最初の“光”だったから」
ふたりの手は、離れなかった。
▽
春の風が吹いている。
桜の枝先には、小さな蕾が、確かに春を待っていた。
そして夜空には、黒龍の影が静かに輪を描き、月のまわりをひとめぐりする。
それはまるで、ふたりの未来を祝福するように、やさしく、永く続いていた。