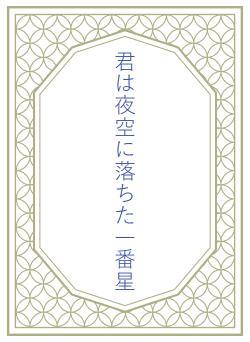その日、都は朝から清めの霧に包まれていた。
春の大祭『霊祀』が執り行われる日。王城の内庭には幾重もの白布が張られ、選ばれし巫女が、龍へと五穀の実りと民の安寧を祈る――
それは、火見家が代々担ってきた最も重要な儀式のひとつであった。
今、その舞台の中心に立つのは、長女・千早。
金糸で縫われた神衣が風に揺れ、白粉の肌が日差しに淡く照らされ、彼女の一挙手一投足は、誰の目にも優雅で、完璧に見えた。
けれど、舞が始まった瞬間。
白砂を敷き詰めた神域の中心――その足元に、細く深い亀裂が走った。
風が止み、鳥の声が遠ざかる。
空を覆う雲が、音もなく垂れこめていく。
千早は、舞の型を保ちながらもわずかに膝を緊張させた。
装束の袖がひとつ、乱れ、整えたはずの微笑は、気づかぬうちに消えていた。
舞の終わりを告げる鈴の音が鳴った時、空気はどこか、乾いたように冷えていた。
誰もが、確かに感じている。
――何かが、ほんの少し、噛み合っていない。
「……巫女様の霊脈が、鈍いのでは?」
「あれでは、龍が応じぬ。まるで、どこか別の……」
「火見家も、もう終わりかしら?」
声を潜めたささやきが、観客席の奥から漏れ、それが波紋のように広がり、辺りの空気をざらつかせる。
千早の耳にも、その言葉は届いていた。
髪飾りを外す手がふと止まり、鏡越しに映る自分の瞳を、じっと見つめる。
あれほど修練を積み、完璧を保ち続けてきたのに、なぜ――龍は自分に応えてくれないのか。
記憶の底で、妹の久遠の顔が浮かぶ。
久遠――母の違うあの娘。
力のない、影のような存在だったはずの妹。
けれど、噂がある。
黒龍が封じられた神域で、彼女が何かを『得た』という噂。
久遠が黒龍と契りを交わしたなどという、まさか――千早は思わず身震いする。
「……久遠……」
声に出した瞬間、千早の指先がかすかに震えた。
焦りが、胸をきつく締めつける。
▽
そのころ、山奥の小屋では、久遠が朔真の導きで霊力の基本を学んでいた。
「霊力とは、力そのものではない」
朔真はそう言って、掌をひらりと開く。
「それは、世界との響きだ。心の静けさがなければ、龍はお前に応えない」
その掌から、黒く細い光がふわりと立ち上がった。
風の気配に似たやわらかな揺らぎ、久遠は目を凝らしながら、それを見つめた。
「怒りや恐れで無理に扱えば、龍は暴れる。……そして、扱う者自身を蝕む」
「……姉さまは、ずっと堂々と力を使っていました」
「彼女は元々、『与えられた力』を借りているにすぎない」
朔真の声は淡々としていたが、その奥には確かな違和感と批判があった。
「だが、お前は……『呼ばれた』んだ。龍とお前の間に、確かな契りがある」
「それは、ただ与えられる力とは違う。お前自身が、望まれている」
久遠は、静かに視線を落とす。
胸の奥にいつもある黒龍の気配は、確かにここにあり――それは熱くも冷たくもなく、ただ静かで深い。
まるで、底の知れない湖、自分の中にそんな場所があるとは、想像したこともなかった。
「……怖いです」
ぽつりと漏らした言葉に、朔真はふと顔を向けた。
「でも、それ以上に……確かなんです……『黒龍』が、私の声を聴いてくれている気がするんです。姉さまの声よりも、ずっと……」
沈黙が落ちる。
朔真はその言葉を否定も肯定もせず、ただ湯を注ぎ、その穏やかな所作に、久遠はふと肩の力を抜いた。
▽
一方、王城では、千早が火見家の長老たちと向かい合っていた。
「霊祭の失敗は看過できぬ」
「巫女としての在り方を、改めて問い直さねばならぬ」
「このままでは、火見家の名も危うい」
厳しい言葉の応酬に、千早は頭を下げて答える。
けれどその心は静まり返るどころか、かき乱されていた。
なぜ、こんなにも危うくなってしまったのか?
あれほど完璧であったはずの舞も、姿勢も、声も、何ひとつ乱してはいないはずだった。
それなのに――千早の頭に、再度妹の久遠の顔が浮かぶ。
「まさか、久遠が……」
その囁きを誰かが洩らす。
千早は、その言葉に立ち上がりかけた自分の膝を必死に押さえつけた。
自室へ戻ると、鏡を見つめたまま、低く吐き捨てる。
「……影の妹が、龍と契りを? そんなもの、誰が信じるものですか」
けれど、その誰も信じない事が、次第に揺らぎはじめている。
▽
夜の山の稽古場――久遠は一人、黒龍の気配と向き合っていた。
両の掌を膝に置き、静かに目を閉じる。
心の奥へと意識を沈めていく。
呼吸と、思念と、鼓動が、深くひとつに溶け合う瞬間、ふいに、内から声が響く。
――……我が声に、耳を澄ませよ、久遠
久遠はゆっくりと息を吸い、吐いた。
龍の気配が、確かにそこにあった。
「姉さまが、わたしを『影』の中に閉じ込めていたのだとしても――わたしは、自分の光を見つけます……」
その呟きは、誰にも届かなかった。
けれど、山を吹き抜ける風が、わずかに優しくなったように感じた。
龍はきっと、孤独に沈んだ声を、誰よりもよく聴いている。
久遠の歩みは、まだ細く、頼りなかった。
けれど、それは確かに、真の巫女への道を踏み出した証だった。
▽
都に、異変が起きたのは、黄昏が空を染め始めた。
王城の東の空に、重く垂れこめた黒雲が湧き上がり、風が巻くようにして一帯を包みはじめる。
季節外れの冷たい空気が城下を吹き抜け、街の人々は口々に『龍が荒れている』と囁く者が多くなってきている。
白磁のように冷えた空。
誰もが何かを察していた――龍が、動いている。
やがて、龍封の神域に近い村で、霊障が発生した。
田畑の作物が萎れ、井戸の水が濁る。
原因は不明、ただ、龍の気が乱れているのは確かだった。
「『龍の巫女』を呼べ!」
宮中からの急報が火見家に届くと、千早はすぐに神衣をまとい、使い慣れた扇を手に向かった。
その姿は、誰が見ても立派だった。
けれど、心の奥では焦りが渦巻いていた。
何度も祈り、何度も舞ってきた。
だが、あの黒雲が、自分に応じている気配は、どこにもなかった。
神域の入り口に立ったとき、千早は空を見上げて、思わず足を止めた。
龍の気配――それが、自分ではない誰かを求めているように思えたのだ。
▽
久遠は、ゆっくりと歩いていた。
山を下り、村を抜け、城下へと向かうその道は、これまで何度も夢に見た光景だった。
けれど、今の彼女の足取りに迷いはなく、彼女の近くでは『黒龍』の気配が背中に寄り添っている。
それは、言葉にはならない力――それでも確かに、久遠の中にあった。
彼女の姿を見た村人たちは、最初は誰だかわからなかった。
袖のほころびた旅装束、控えめな立ち居振る舞い、そしてその静かな瞳。
だが、久遠が手をかざして風の乱れを鎮め、萎れた作物に微かな霊の息を吹き込むのを見たとき、誰かが小さくつぶやいた。
「……巫女?」
その言葉が、ゆっくりと広がっていく。
▽
王城の前庭――霊障の中心にある広場に、千早が降り立ったとき、彼女は明らかに動揺していた。
草木が黒く変色し、空気には不吉な音が混じっていた。
扇を広げ、祝詞を唱えても、風は逆らうばかりだった。
「……応じなさい。私は、火見家の巫女……あなたたちの主です……!」
声が震えた。額に汗が滲む。
その時――周囲の風が、まるで呼吸を止めるかのように静まり返り、そして、城門の奥から、ひとりの少女が姿を現した。
薄灰の衣に身を包み、長い黒髪を風にたなびかせる少女――久遠だった。
「……久遠……?」
千早の声が、風にかき消された。
久遠は何も言わなかった。
ただ、両の手を前に差し出し、そっと目を閉じる。
次の瞬間、黒い風が彼女の周囲に舞い、まるで龍がその身に巻きつくようにして光を放った。
空が震え、木々がざわめき、その場にいた誰もが、息を呑んだ。
「龍が……応えている……!」
誰かの叫びが広場に響いた。
千早の視線が、久遠の姿に釘付けになる。
嘘、ありえない、そんなはずはない――心の中で否定の声が渦を巻く。
けれど、現実は冷たく正確で――龍は、久遠に応えている。
巫女としてではなく、『龍に選ばれた者』として。
▽
その夜、王城では異例の会議が開かれた。
火見家の巫女としての正当性、そして黒龍と契りを交わした『少女』の正体について、重臣たちの間で議論が飛び交う。
「……龍が応えたのは事実。我らは、もはや目を逸らすことはできぬ」
「だが、あれは……『影』と呼ばれた久遠ではなかったか?」
重苦しい沈黙――その中で、ひとりの老臣がぽつりと呟いた。
「ならばこそ、龍が選んだのだろう」
▽
久遠はその夜、城の一室に通された。
そこには朔真の姿があった。
「よく来たな」
彼は、そう言ってただ一度、深く頭を下げた。
「黒龍の力は暴れてなどいなかった。ただ、導く者を待っていただけだ」
「……私が、その導き手になれたのなら、嬉しいです」
久遠の声は震えていたが、芯があった。
「……もう、あの時のように、戻れませんね」
「あの時、お前は決めた時から戻る場所は、最初からなかった……だが、これからは、進む場所ならある」
朔真の言葉に、久遠はふと微笑んだ。
その笑みは、小さく、控えめで、それでいて確かな強さをたたえていた。
――このとき、彼女の名はまだ正式には呼ばれていなかった。
『巫女』とも、『契約者』とも。
けれど、人々の記憶には、あの黒い風と共に舞い降りた姿が、深く刻まれていた。
影ではない。
選ばれた者、久遠としての物語が、いまようやく始まったのだ。