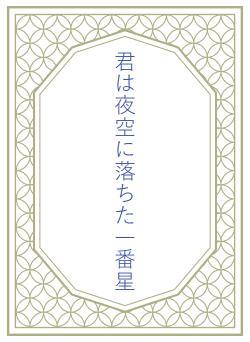この国には龍がいる――空を翔け、大地を揺らし、神々にさえ頭を垂れさせる存在だという。
けれど、火見家の次女として生まれた久遠にとって、龍とは物語の中でしか出会えぬ、遠い夢のようなものだった。
▽
姉の千早は、霊の気に満ちた空気をまとう少女だった。
幼い頃から龍の気配を感じ、祝詞を口ずさめば、風が舞い、鳥が鳴く。
人々は口を揃えて『巫女に選ばれるのは、あの子しかいない』と毎日のようにささやいた。
久遠もまた、火見家に生まれたが――けれど、誰も彼女に龍の血を見出さなかった。
礼儀を教えられることも、舞を学ぶ機会もなく、姉の陰で静かに息を潜めて育った。
その『静けさ』こそが、彼女に許された存在意義のようにさえ感じられていた。
ある日の夕暮れ、久遠は屋敷の廊下に膝をつき、柱の陰に身を隠していた。
姉が通ると知らされていたからだ。
「久遠様、頭をお下げください」
付き添いの侍女が声をかけ、そっと背を押す。
床板に額をつける瞬間、久遠の胸の内に、小さな痛みが走った。
けれど、それを表に出すことはできない。
火見家の娘である以上、その感情すらも余計なものとされるから。
足音が近づき、そして通り過ぎる。
白足袋の先、金糸の裾、結い上げられた髪。
姉は今日も美しく、完璧だった。
「……また掃除、忘れたの?」
廊下の向こうから、淡く響く声が聞こえる。
久遠が顔を上げると、千早が振り返っていた。表情には笑みが浮かんでいる。
けれど、その目の奥には冷たい硝子のような光があった。
「申し訳ありません。今日中に終わらせるつもりでした」
久遠が丁寧に頭を下げると、千早はわずかに眉を上げた。
「龍の加護を持たぬ者は、せめて勤めだけは果たさないと」
声音は柔らかいのに、その言葉は鋭く、突き刺さるようだった。
久遠はうなずき、声を返すことなく頭を下げ直す。
反論する理由も、立場もなかった。
火見家では、千早が『陽』で、久遠は『影』だった。
それは、当たり前のように染みついた役割。だれもが、それを疑わなかったのである。
その夜、久遠はひとりで裏山へと足を運んでいた。
神域――龍の魂が眠るとされる封印の地へ。
本来ならば、火見家の者すら無断では入ることを禁じられた場所だった。
けれど、風の流れが、空の匂いが、胸の奥で揺れる何かが、彼女を静かに誘っていた。
月は細く、空は澄んでいた。
木々の間を縫うように歩き、祠の前へと立つ。
そこには誰もいないはずだった。
それでも、久遠には『何か』が確かにそこにいると感じられた。
――目覚めよ。
「え……」
声とも思念ともつかぬ響きが、風の音に重なる。
祠の扉が、わずかにきしんだ。
その音に久遠の肩が震える。けれど、逃げ出す足は動かなかった。
――影に生きし者よ。拒まれし者よ。それでもなお、応じし者よ。
――我が契りを望むか?
胸の奥が熱い。
焼けるような痛み――けれどそれは、なぜか懐かしさを帯びているように感じた久遠は小さく、かすかに首を縦に振った。
「……あなたの声が……わかる」
次の瞬間、光が弾け、闇の中に、一条の黒い輝きが奔り、風が逆巻いた。
木々が揺れ、大地が微かに震える。
久遠の体を、何か大きなものが貫いたような気がした。
その時、自分の名を呼ぶ声が聞こえた。
「久遠――!」
鋭い声が響き、駆けてきたのは、千早だった。
祠の前に立つ妹の姿を見た姉の目が、大きく見開かれる。
「なにを……呪いを受けたの!?龍に触れるなんて……っ」
久遠の姿には、微かな霊紋の光が滲んでいた。
それを見た千早の顔が、怒りと恐怖とでゆがむ。
「姉さま……あなたには、聞こえなかったの?」
久遠が静かに問いかけると、千早の顔から色が消える。
「黙りなさい……呪われた娘が、巫女の真似事を……っ」
けれど、久遠は何も言い返さない。
祠の奥に漂う気配は、まだ静かに彼女の背を押していた。
ここにいてはいけない。
影のままでは、きっとこの声すらも奪われてしまう。
久遠はそっと目を伏せ、くるりと背を向けた。
「もう戻らないわ。……わたしは、わたしのために歩く」
その言葉だけを残して、久遠は闇の山道へと消えていく。
月が、雲の切れ間から彼女の背中を照らしていた。
▽
夜の山道は、想像よりも険しく、久遠は燃えるような胸の痛みを抱えたまま、細い足取りで、冷たい地を踏みしめていた。
背中で何かが脈打っている。祠で交わした『契り』が、彼女の身体の奥で、静かに目を覚ましつつあるのだ。
けれど、痛みよりも強かったのは、言葉にできぬ不思議な温かさだった。
――自分は今、確かに選ばれたのだ。
生まれて初めてそう感じた。
しかし、その確信も長くは保てなかった。
数十歩も歩かぬうちに、足元が崩れた。小石を踏み外し、転げ落ちるように斜面を滑り、久遠は下草の茂みに倒れ込んだ。
肩に痛みが走り、意識が遠のいていく中で、月が空で滲み、風の音が静かに聞こえる。
「――久遠」
誰かが、彼女の名を呼んだ気がした。
▽
目を覚ましたとき、久遠は藁の香りに包まれていた。
薄暗い木造の小屋の中。簡素だが清潔な布団の上に寝かされており、右の肩には、薬草の湿布が当てられていた。
「起きたか」
扉の向こうから、男の声がした。
ゆっくりと首を向けると、青年が一人、戸口に立っていた。
漆黒の装束に身を包み、顔立ちは鋭いが、どこか儚げな静けさを纏っている――そして、彼の手には、まだ湯気の立つ茶椀があった。
「……あなたが……?」
久遠がか細く声を出すと、青年は一歩、彼女のそばへと近づいた。
「お前が神域から落ちたと聞いて、迎えに行った。お前の身体には……奇妙な霊気が残っていた」
彼はそう言って、茶椀をそっと久遠の枕元に置く。
久遠はその視線の鋭さに、身をこわばらせた。
だが、青年はすぐに視線を外し、静かに息を吐いた。
「……名を朔真という。火見家には属していないが、龍を護る一族の末裔だ」
彼の言葉には、わずかな警戒と――それ以上に、困惑が滲んでいた。
「黒龍に、呼ばれたのか?」
その問いに、久遠は胸に手を当て、小さくうなずいた。
「声が……聞こえたんです。あの祠で。確かに……わたしを、選ぶと」
「黒龍が、選んだ?」
朔真の眉がわずかに動く。
龍神の加護を得る者は、選ばれた者。
だがそれは、本来、火見家の正統たる者――つまり姉・千早であるはずなのに、黒龍が久遠を選んだという事実は、この国の巫女制度に揺らぎをもたらしかねない。
「どうして……私なんかを、龍は……」
思わず漏らした問いに、朔真はしばらく答えなかった。
ただ、火を見つめるように、久遠の目をじっと見返していた。
「お前の気は……静かすぎるほど、澄んでいた」
「……え?」
「それは、満たされぬ静寂。龍はその奥にある想いを感じ取ったのだろう」
それは、久遠自身すら気づかぬほどに、長く深く沈んでいたモノで――久遠はずっと、姉の『影』として生きてきた。
しかしその中で、何も諦めてはおらず、ただ、自分の場を、声を、まだ見つけられずにいただけだった。
「……じゃあ……わたし……巫女に……なれるの……?」
つぶやくような声に、朔真はわずかに笑った。
「なれるかではない。もう、選ばれたのだ……ただし、その力を制御できねば、いずれ自身を壊す」
久遠は目を伏せ、小さく息を吐いた。
身体の中に、黒龍の気配がまだ確かにある。
それは、熱でも冷たさでもない。言葉にできない、『大きな存在』だった。
「……教えてくれますか? わたしが、何をすればいいか」
「……ああ。お前が望むのなら、力の扱いを教えよう」
朔真の声は、どこまでも静かだった。
その静けさが、久遠にはなにより安心だった。
火の揺らぎが、二人の間を照らす。
久遠は目を閉じ、小さく拳を握った。
もう、誰かの影にいるだけではいられない――この力は、確かに自分の中にある。
黒龍が、そう告げてくれたのだから。
夜は深まっていた。
けれど、久遠の胸の奥には、かすかな光が灯っていた。