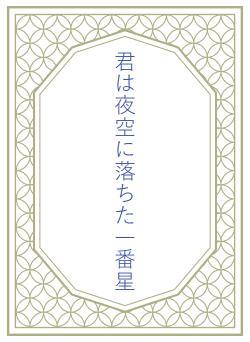花の香りが、風に乗って漂っていた。
田舎の教会の小さな庭で、春の陽射しを浴びながら、クラリスは純白のドレスの裾を整えていた。
鏡の前には、傷も、呪いも、もう“ない『彼女』が傍に居る。
その右頬には、かつての刻印の痕がかすかに残っている。
けれど、それを隠すショールは、もう身につけていなかった。
彼女は、もう隠さない。
そして、それを誰よりも先に褒めてくれた人が、これから隣に立つのだ。
「クラリス、準備できてる?」
扉の向こうから声がかかった。
あの、少し眠たげな声。いつもの調子。だけど――少し、照れた音色。
「……はい、すぐに」
彼女は深く息を吸い、扉を開けた。
外には、黒の礼服をきちんと着こなしたレオナールが、驚いたような顔で立っていた。
「……すごい、綺麗だ……いや、知ってたけど、なんか……うん、改めて……その……」
ぶつぶつと言葉が崩れていく。
「……あ、ありがとうございます……でも、私、ちょっと緊張していて……」
「僕も。めちゃくちゃしてる。今すぐ逃げたいくらい」
「……逃げないでください」
ふたりは顔を見合わせて、笑った。
そのすぐ先にある小さな祭壇には、
兄リヒトが堅い顔で書類の確認をしており、母オリヴィアが大声で「誰か泣く準備できてるか!?」と叫び、父ユリウスが花をいじりながら無言で立っていた。
「……なんて、にぎやかな家族なんでしょうね」
「僕も、昔はびっくりしてた」
「今は?」
「今は、誇りに思ってる……君もその一員になってくれるなら、もう言うことない」
クラリスは静かに頷いた。
震えることなく、迷うこともなく。
ただ、レオナールの手を取り、その隣に立つ。
春の陽が、二人の頭上に降り注ぐ。
痣と、傷と、呪いと、孤独と。
全部を越えて、彼女は今、『花嫁』になった。
そして魔術師の彼は、『守る者』になった。
その日、教会の扉が開くと、村の人々が小さな祝福を持ち寄っていた。
誰もが、『呪いの令嬢』ではなく――『幸せそうなクラリス』として、彼女を見ていた。
小さな教会の庭に、笑い声が響いた。
それは、春の訪れと、再生の音だった。
そして、その横で。
「……レオ、いい嫁もらったなぁ……」
「母さん、うるさい……」
「おねえさまぁぁああ!ドレス似合いすぎよぉぉぉ!」
「妹まで……はぁ、父さん、今日もしゃべらないの?」
「……綺麗だった」
「「「えっ!?」」」
思わず家族全員が父を二度見した。
その一言が、一番泣けるなんて、ずるい。
クラリスは――レオナールは、これから先、何度季節が巡っても、この日を、笑って思い出すのだろう。
あの日、森で出会った、ひとつの孤独が。
今、ようやく春を迎えた。