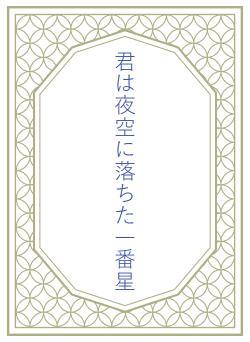クラリスがレオナールの『婚約者宣言』から数日。
村の空気は徐々に変わりはじめていた。
広場の八百屋では
「こんにちは、クラリスさん」
「こ、こんにちは……」
名前を呼ばれたので、返事を返す事を覚えた。
通りを歩けば
「もう『呪い』なんて言ってたのが恥ずかしいね」
そのように囁かれるようになった。
クラリスのそんな穏やかな変化の中――『彼』は現れた。
▽
日暮れ時の広場――帰り道、クラリスの足が止まった。
そこに立っていたのは、上質なマントに身を包んだ金髪の男。
かつて彼女の『婚約者』だった男。
男爵家の嫡男――カノン・グランフォード。
「……久しぶりだね、クラリス。元気そうでなによりだ」
変わらぬ笑顔。変わらぬ声色。
だがその奥にある『傲慢』を、彼女はもう見逃さない。
「……なぜ、ここにいらっしゃるのですか?」
「いや、ただ『懐かしくて』さ……噂で聞いたんだ。君がまだ、生きていたって」
その言葉に、クラリスの背中が強張る。
「『まだ』……?」
「てっきり、誰にも愛されず、ひとりで朽ちていったと思っていたよ……だが、どうやら『救ってくれた男』が現れたらしいな?」
その声の奥には、羨望と嘲笑が入り混じっていた。
彼の言葉を聞いた瞬間、胸の中から『何か』があふれ出そうだった。
「まあ、君は『使い道』がなかったわけじゃない。今さら戻ってきても、面倒は見てもいいと――」
「言葉を選べ」
突然、クラリスとカノンの間に割って入ったのは、落ち着いた低い声。
広場の角に立っていたのは、リヒトだった。
黒の燕尾服のような上衣に、重厚なマント。
胃薬を片手に持ち、握りしめながらも、その瞳は鋭く冷たい。
クラリスは、そんな兄、リヒトの姿を見たのは初めてだった。
静かな声で、リヒトは話を続ける。
「うちの弟の大事な婚約者に、無礼なことを言うな」
「……どちら様だ?」
「伯爵家リュミエール家長男、リヒト・リュミエールだ」
カノンの顔色が変わる。
伯爵家。
それも本家筋。
その名前が意味する力を、彼は知っていた。
だが、カノンはそれでも引かない。
「……婚約者、と言うが……それはそちらの勝手な――」
「正式に結婚の話も進んでいる。記録にも残す。君に『差し戻し』などできない。それでもまだクラリス嬢に関わろうとするなら、我が家は君の家に正式な抗議を申し入れる」
淡々と。静かに。
それでいて、逃げ道を一切残さないように。
カノンはわずかに歯噛みした。
「……面白くないな。たかが『傷物』一人に、随分と入れ込む」
カノン・グランフォードが『傷物』と口にした瞬間、空気が一変した。
静かだった広場に、ぱんっと乾いた音が響く。
頬を押さえ、よろめくカノンの姿を、クラリスは見つめる事しか出来ない。
「……っ、な、何を――!」
彼が振り返ったときには、すでにリヒトの拳が再び振り上げられていた。
二発目は、容赦のない真正面からの打ち抜きだった。
どさり、とカノンが地面に転がる。広場が凍りつく。
「えっと……リヒト、様……?」
クラリスが震えた声で名前を呼ぶ。
しかし、リヒトの表情は、冷たく、静かで、殺気に満ちていた。
「口を慎めと忠告しただろうが、聞こえなかったか?」
静かに、ぞくりとする声で、リヒトは言う。
「『傷物』?それがお前の語彙の限界か?人を飾りとしか見られないくせに、自分が捨てた相手に『まだ使える』とか……」
リヒトの足が、ぐっとセルヴィスの胸元を踏みつけた。
「『人間』をなんだと思ってる?」
「が……っ、ぐっ……!」
呻くカノンに、リヒトは構わず言葉を続ける。
そんな二人のやり取りを、クラリスは見つめる事しか出来ない。
と言うより、あのような顔をしたリヒトの姿を見たのは初めてだったので、その場で動くことが出来ない。
「てめぇみたいなやつが、『選ぶ側の人間』気取ってんじゃねぇよ」
怒気も叫びもない。
ただ、言葉の端々に滲む――本物の怒り。
「クラリス嬢は、もうお前が『傷つけていい女』じゃない。うちの『家族』だ……うちの弟の、大切な婚約者だ。だから――」
ぐっ、とリヒトは拳を握り直す。
「その口で彼女を汚すなら、その歯を全部へし折ってやる」
ざわり、と風が吹いた。
その場にいた誰もが、普段『胃痛で弱そうな兄』だと思っていた男の、本当の姿を知った。
「……立てよ、グランフォード家の出来損ない」
「……っ!」
「立てよ……俺はもう一発、正面から殴ってやらないと気が済まねぇんだよ」
だが、カノンは立てなかった。
顔を引きつらせ、這うようにしてその場を逃げ出す。
リヒトはそれを追わなかった。
ただ、足元の石を一つ蹴って――吐き捨てるように呟いた。
「クソが」
リヒトは追いすがることなく、その場に静かに立ち尽くしていた。
その横顔には怒りの名残もなく、代わりにどこか――疲労感が浮かんでいる。
「……はあ」
彼は深くため息をつくと、懐から常備している銀の小瓶を取り出し、手慣れた動作で蓋を開け、くいっと胃薬を一口。
「……また胃が痛くなった。なんでこう、毎回こうなるんだ……」
「リヒト兄様……!」
いつの間にかリヒトの近くに来ていた妹、アナスタシアに「服が乱れてますわ!」と袖をぴしぴし直されながら、
リヒトは仕方なく小声で呟いた。
「……殴るのは嫌いなんだがな……言わなきゃ伝わらないバカもいるんだ」
「兄さん、ありがとう」
アナスタシアと一緒にこちらに来たレオナールがぽつりと言った。
静かに、真っすぐに。
その言葉に、リヒトはほんの少しだけ、照れくさそうに視線を外した。
「……礼なんか、いらないよ」
クラリスが何か言おうとしたが、その前にレオナールがふっと笑って呟いた。
「……相変わらず、キレると怖いな、兄さん」
「うるさい」
「うちの家族で一番怖いのは、リヒト兄様なのだから……もう、誰に似たんでしょう?」
「父さんかな?口は悪くないけど、容赦ないからなぁ、父さん」
「確かに、そうですわね……大丈夫ですか、おねえさま?」
「……ええ、大丈夫です」
三人の兄弟の姿を見たクラリスは安心したかのように、笑みを零し、そのままレオナールの隣に立った彼女は静かに手を繋いでくる。
一瞬、驚いた顔をしたレオナールに対し、クラリスは頬を少し赤く染めながら、笑うだけだった。
(……大丈夫、この人なら、この人達なら)
クラリスは目を閉じ、彼らに感謝をしながら、強くレオナールの手を握りしめた。