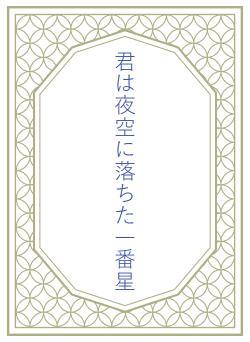扉の向こうにいたのは、見た事のない、『家族』だった。
いえ、あれは――『家族』だったのだと、今なら思える。
初めて踏み入れた屋敷の空気は、温かく、にぎやかで、うるさかった。
右からも左からも話しかけられ、頬が熱くなるほど注目され、気がつけば果実の皿を押し付けられていた。
なのに、誰も、私の顔を見て、眉をひそめなかった。
あの『傷』に、怯えも、蔑みも、なかった。
──お母様、素敵ですわ!
──この子、守りたくなる顔だよな!
驚いて、戸惑って、怖くて……でも、少し、嬉しかった。
レオナール様が黙って席を引いてくれた時、アナスタシアさんが私の手を取って笑顔で『お姉さま』と呼んだとき、誰も知らない胸の奥が、じんわりと温かくなった。
かつて、私は誰かの『所有物』だった。
綺麗で、従順で、誰かに見せられるような存在であることを望まれた。
そして、傷ついた私に彼は
「お前の事、もういらない」
と言ってきて、私を捨てた。
だからずっと、世界から閉ざされたまま、森の中で息を潜めていた。
――でも。
もし、あの場所に、もう一度行ってもいいのなら。
もし、あの笑い声を、また聞いてもいいのなら。
私は――もう少しだけ、この『あたたかさ』に触れてみたいと思った。
――その日の夜。
薄い毛布の中、微かに香るはちみつと果実の匂い。
私の右頬に触れたレオナール様の言葉が、ふとよみがえる。
「怖くないよ」
――私は、まだ生きていていいのかもしれない。
そんなことを、初めて思った夜だった。