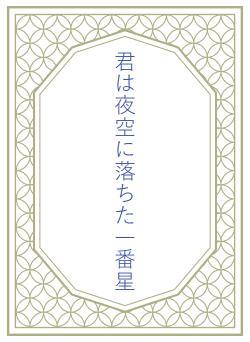彼女が去って行ったあの日――というには、まだ一日しか経っていない。けれどレオナールにとって、その背中は妙に深く印象に残っていた。
話しかけたのも束の間、彼女は怯えるように瞳を伏せ、何も言わず、ただ森の奥へと姿を消した。
名も、何も、聞けなかった。
――なのに。
翌朝になると、レオナールの足は自然と森へ向かっていた。
魔術の調整という建前を持ちながらも、内心では、もう一度だけ彼女に会えたらと――そんな期待を、どこかで抱いていた。
木々の間を抜ける風が、葉を揺らす。鳥が啼く声も、遠くから聞こえてくる。
昨日、彼女が現れたあの場所。小さな開けた空間に足を踏み入れると、そこには――いる。
彼女は、そこにいた。
そのまま声をかけていこうとしたのだが、声をかけられない。
倒れかけた切り株に腰をかけ、何かを見ているかのような姿で空を見つめている。
その姿が何処か綺麗で、思わず見惚れてしまい――次の瞬間、目線がこちらに向かったので、レオナールは体を反応させてしまう。
少女はレオナールを見て、静かに息を吐いた。
「……来ると思ってました」
少女は、そう言った。
声は昨日よりも少しだけ穏やかで、少しだけ震えていた。
「その……昨日は……ごめんなさい。あんなふうに、逃げるような真似をして」
「逃げるのは、悪いことじゃない。僕だって、森に来るときは少し逃げてる気持ちで来てるし……そもそも初対面で突然声をかけられたら誰だって警戒する」
レオナールは木の根元に腰を下ろす。
距離は、二人分ほど。これ以上近づくことは、彼女を傷つけてしまいそうで。
少女が、昨日と違う、静かに笑みを零しながら話しかけてきた。
「ここは、静かですね。都会より、ずっと」
「……そうだね。魔素の流れも穏やかで……君が、ここにいる理由が少しだけわかった気がするよ」
彼女は顔を上げた。
その右頬の『傷』が、木漏れ日に照らされて淡く揺れる。
「見えないようにしてるつもりだったのに……あなたには、見えたんですね」
「君も、僕の痣を見たろ?」
「……はい。ですが、怖くありませんでした」
「僕もだよ」
レオナールは静かに笑った。
彼女は少し驚いたように目を瞬かせ、そして――ほんのわずかに、唇の端を持ち上げた。
それは、微笑みと呼ぶにはあまりに小さなものだったけれど、彼にはそれで十分だった。
「そういえば……君の名前、まだ聞いてなかったよね」
名前を聞いていなかったので、せめて名前だけ聞いておこうかなとレオナールは声をかける。
すると少し迷う素振りを見せながら、彼女は答えた。
「……クラリス、といいます」
「クラリス。うん、いい名前だね」
その一言で、また彼女の表情が揺れた。
それでも、今度は逃げなかった。
木々の隙間から、ふわりと春の風が吹いた。彼女の銀の髪が揺れ、レオナールはそっと視線を落とす。
この森が、きっと彼女の『避難所』であることを、彼は強く感じた。
だからこそ――この静けさを壊さぬように。
ゆっくりと、彼女のそばに寄っていけたらと、そう思った。
▽
再び森で出会ったその日から、レオナールは何度か、彼女――クラリスのもとを訪れるようになった。
彼女が暮らしているのは、森のはずれにある古びた離れ屋敷。
木造の壁は雨風に晒され色褪せているが、窓辺には手入れされた花が咲いていて、彼女の静かな暮らしぶりを物語っていた。
クラリスは最初こそ警戒していたが、レオナールが“必要以上に踏み込まない『人間』だとわかると、少しずつ言葉を交わすようになった。
彼女の話し方は静かで、丁寧だった。
目を見て話すことが少なく、それでもときおり、魔力球の光に照らされる横顔は柔らかくて、どこか儚かった。
クラリスは自分の傷跡のことは話さなかった。
レオナールも聞かなかったし、そもそも聞くつもりなどなかった。
興味と言うものがなかったのである。
代わりに、彼はただ、穏やかに問いかけた。
「君は、森が好きなのか?」
「はい。音が優しいですから。風も、葉のささやきも。人の声よりも、ずっと」
「……それは、ちょっとわかるな」
ふたりの間には、沈黙が流れることもあった。でも、それが苦しくなかった。むしろ心地よいと、どちらともなく思っていた。
――そんなある日の事。
朝から妙に騒がしい屋敷の食卓で、レオナールはため息をつく。
原因は自分の家族だ。
「レオ、聞いたぞ?あんた最近、森に通っている、と?」
母のオリヴィアが両肘をついてニヤリと笑っている。
「……観察と実験のためだよ。魔素の研究の一環」
「ふーん……じゃあ、何故昨日、服に白い花粉ついてたんだ?あれは確か、森の奥の『祈り草』のやつよね?」
「観察の一環だって言ってるだろ」
「うちの子、ようやく春を迎えたのかぁぁああ!」
母、感涙。
妹、笑顔で拍手。
「レオお兄様、すごいです! 次はお茶会デートですわね!」
「うるさい」
妹が嬉しそうに話している間、兄のリヒトは腹部を抑え、頭を抱えている。
小食だが、相変わらず胃が痛いらしく、薬を握りしめている。
「……だから胃が痛いんだ。お願いだからこの家、もう少し落ち着いてくれ」
「……すまん、兄さん」
「いや、レオナールのせいじゃないから気にしないでくれ……」
男二人はそのような話をしていると、玄関の扉が、控えめにノックされた。
この家は大きいが、田舎の家で、使用人もいない。
一体誰だろうと。レオナールが立ち上がってドアを開けると、そこには、見慣れた銀髪の少女の姿があった。
「……クラリス?」
「こ、こんにちは……ごめんなさい、森で摘んだ果実……お礼に、と思って……」
彼女の手には、小さな布包みに入った果物。
まさか彼女が自分の家に来るとは思わなかったので、思わず呆然とクラリスに視線を向けてしまった。
それを黙っている母、妹ではない。
レオナールが何か返す間もなく、背後から轟音のような声が響いた。
「まっったくぅうう! こんな可愛い子を家に呼ぶとは、どうして教えてくれなかったレオナール!!」
「ええ!? えええええええ!? あ、あの、いえ、私は――!」
「嫁ですか!?これは嫁コースですか!?ちょっとレオお兄様!クラリスさんって呼び捨てにしてるってことは、もうそういう仲!? ねぇ!?」
「ちがっ、違うって!」
「父様!今夜の食卓、祝い膳にしましょう!!」
静かに食事していた父が目を向ける。
彼はそのまま無言で頷いた。
「頷くなぁぁああああああ!!!」
混乱の中で、クラリスは小さな声で言った。
「……あの、帰った方がいいでしょうか……」
「ごめんクラリス!待って、お願いだから帰らないで……!」
とりあえず帰ってしまったら絶対に彼らにしわくちゃにされるに違いない。
青ざめた顔をしながら、レオナールはクラリスを止め、食卓に招待するのだった。
数分後、彼女が持ってきた果実は食卓に並んだ。
そして、クラリスは考える――こんなに、うるさくて、あたたかい場所があるなんて。
最初こそ混乱していたクラリスだったが、食卓についたあとは、どこか不思議な空気に包まれていた。
それは、恐怖や緊張とは違う。
もっとこう――どう受け取ればいいのか分からない、という戸惑いだった。
「お口に合うといいけど、これ、アナスタシア特製のはちみつ漬け!クラリスさんの肌がもっとツヤツヤになるようにって!」
「つ、ツヤ……?」
アナスタシアは満面の笑みで果実を差し出す。
クラリスはおずおずとそれを受け取り、ひと口、口の中に入れる。
「……あまい」
「でしょ!?レオナール兄様の好物でもあるんですのよ!」
「やめてくれ……」
アナスタシアの特攻はやめられず、顔面真っ赤に染まったレオナールは先ほどのリヒトのように頭を抱えるが、母のオリヴィアはそれを見てますます調子に乗った。
「ふふっ、クラリスちゃん!うちの子はちょっと変人だが、根は真面目で優しい!どうかな?」
「お母様! 早いです! まだご挨拶の段階ですわ!」
クラリスの頬が見る見るうちに紅くなる。
だが、誰もそれを責める者はいなかった。
代わりに、みんなが笑っていた。賑やかに、自然に、あたたかく。
家族というものに囲まれた記憶が、クラリスにはあまりない。
貴族の家に生まれ、婚約者に『役目』として選ばれ、傷を刻まれて「呪われた」と呼ばれて、そして捨てられた。
父も母も、もういない。兄弟もいなかった。
だから――こんな光景が、眩しすぎた。
「……クラリス?」
レオナールの声に、ふと我に返る。
気づけば、目の端が熱を帯びていた。
嗚咽は飲み込む。
けれど、その代わりに言葉が溢れた。
「……こんな風に囲まれて、食事をしたの……いつ以来か、分かりません」
妹であるアナスタシアがそれを聞いて驚く。
そしてそのままそっと手を握る。
「じゃあ、これからは『思い出せるように』なってくださいね!うちの家族はみんなこんな感じですから」
アナスタシアの言葉を聞いたクラリスは、泣き笑いのような表情で、こくりと頷いた。
その夜、彼女は深く眠れた。
久しぶりに、『夢にうなされない夜』。
そして翌日から、森の中に咲く花がひとつ、ふたつと増えており――レオナールはそれを見つけるたびに、小さく微笑んで「明日も行ってみるか」と呟いた。