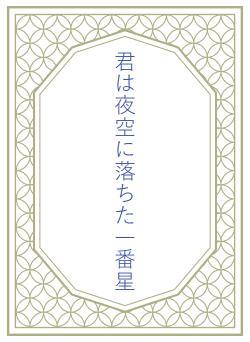移住から数日後の午後、レオナールはひとり森の中にいた。
目的は魔力の調整だ。田舎の魔素は首都と違い、濃度が素直で安定している。試してみたい術式がいくつもあった。けれどそれだけでなく、彼は時折こうして一人になりたくなる。
誰かに見られない場所で、自分の痣のことを忘れられる空間が、森の静けさにはあった。
膝をつき、地面に指先で陣を描く。魔術がすっと編まれていく。手のひらの中に浮かび上がるのは、小さな光――蛍火のような魔力球。
「……やっぱり、ここの魔素は応えてくれるな」
レオナールは魔力球を浮かべたまま、じっとその光の揺らぎを観察した。
魔素濃度は首都のそれより低いはずだが、流れが素直だ。変な混ざり気もなく、風や木々の生気と自然に馴染んでいる。
「動的な術式の反応速度は都市部の1.3倍……いや、下手すると1.5倍近い。魔素粒子が結合に対して柔らかく反応する分、融解率が高いのか?」
魔力球の中に、別の小さな術式を挿入する。熱伝導系の初歩魔法。通常であれば光は赤みを帯びるはずだが――レオナールは再度、集中する。
「……やっぱり、黄色が強い。ここの魔素は“守る”より“育む”方向に流れるのか。穏やかすぎて、少し拍子抜けだな」
観察ノートが欲しい、とつい思ってしまった。
けれど、この手応えを肌で感じることが何より大事だ。実地研究の本質は、紙の上では測れない。
「これは……魔術応用系、回復術式にも転用できるかも。もし、少し複雑な重ね書きをすれば――」
彼の脳内にはすでに、複数の術式構造が組み上がっていた。
研究者としての本能が静かに熱を帯びていく。その時――カサ、と背後の茂みで音がした。
レオナールは反射的に術式を中断し、肩越しに振り返った。森の静寂の中に、微かな気配。風に揺れる葉音とは異なる、確かな“誰か”の存在。
「……そこに誰かいるのか?」
応えはない。
しかし、気配がするのはわかる。
(……もしかして、魔物か?)
森の中なのだから、魔獣と言う存在がいてもおかしくない。
レオナールは詠唱をしながら視線を動かしていたのだが、その姿を見て思わず動きを止めてしまった。
木の陰から、ひとりの女性が現れた。
ゆるく巻かれた銀の髪。深い灰色の瞳。肩まで隠れる古びたショール。そして、何よりも印象に残ったのは――その右頬に刻まれた、大きな傷だった。
(右頬に傷……いや、、もしかすると、魔術印?)
傷というには、どこか不自然な形だった。
まるで何かの印のように、肌に焼きついている。
少女はレオナールと目があった瞬間、青ざめた顔をしながら顔を隠した。
「……見ないでください」
彼女は言った。
声は静かだったが、どこかに怯えと、刺すような鋭さが混じっていた。
レオナールは、ほんの一瞬だけ躊躇し――そのままゆっくりと自分のフードを外す。
右頬に浮かぶ、痣を隠さずに。
「……大丈夫。僕の顔にも傷はあるから、気にしなくていいよ。君のやつより酷いかもしれないし……」
笑みを浮かばせながら彼女に話しかけると、少女の瞳が見開かれた。
驚きと、わずかな混乱。そして、ほんの少しの――共鳴。
「……どうして、そんな風に」
「君と、同じだからかな。……いや、君より軽いかもしれないな、俺のは」
レオナールは痣に指を添えて、笑ってみせた。
「怖くないの、ですか?」
「別に。呪いだって、誰かの都合で決まるものだろ?僕は……たぶん、見た目より、声とか雰囲気とか、そっちのほうが怖い」
「……変な人、ですね」
「よく言われる」
彼女は少しだけ口元を緩めた。だがすぐに、それを消して俯く。
少女にとっては酷いトラウマの傷なのかもしれないが、レオナールにとってはどうでも良い事だ。
レオナールはそんな外形よりも、人間の心の方が怖い。
ただ、そのように考えるようになっているのは、自分の事をどんな事があっても味方でいる、家族たちの存在があるからなのかもしれない。
「えっと……君の名前は?」
「私は……名前を名乗るような者じゃ、ありません」
「じゃあ、俺が名乗る。レオナール……魔術師、兼、田舎暮らしの初心者。数日前に来たばっかなんだ」
「……レオナール、様」
その名前を、彼女は静かに繰り返した。
それだけで、なぜだろう――森の風が、少し柔らかくなった気がした。