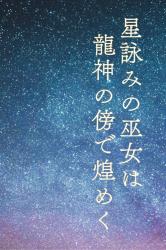十五分後。パンダの遊具に寄りかかりながら待っていると、制服姿の葛西がやって来た。
「熊谷!」
ダッシュで近付いてきたかと思うと、勢いよく抱きしめられる。普通に立っていたら後ろに倒れていたかもしれないが、パンダの遊具に寄りかかっていたおかげで体勢をキープできた。バネで揺れている俺の身体を、葛西はぎゅうぎゅうと抱きしめる。
「ごめん、本当ごめん」
「なんで謝るの?」
「俺のせいで、熊谷に寂しい思いをさせたから」
もしかして葛西は、教室で素っ気なくしたことを謝っているのか? そうだとしても、まだ納得できないことがある。
「なんで俺が寂しがっているって分かったの?」
「寂しいって呟いてたじゃん」
確かにインスタで『寂しい』と呟いた。だけどその投稿はすぐに削除したし、そもそも葛西には俺のアカウントは教えていない。
「なんで葛西が俺のアカウント知ってんの?」
追求すると、葛西は俺の背中に回していた腕を解く。顔を見合わせた後、葛西は「ああー」と呻きながら頭を抱えてしゃがみ込んだ。
「……ごめん、今の忘れて」
「いや、無理だから」
こんな不可思議なことを忘れられるはずがない。俺は葛西の隣にしゃがみ込んで、顔を覗き込んだ。
「ねえ、なんで知ってるの?」
じっと見つめて追及をすると、葛西は顔を手で覆いながら小さな声で白状した。
「……ずっと、見てたから」
「もしかしてフォロワーだった?」
葛西はこくんと頷く。まさかこんな身近にフォロワーがいるとは思わなかった。とはいえ、葛西なんてアカウントは今まで見たことがない。葛西、かさい、カサイ……と考え込んでいると、ある人物の存在を思い出す。
「saikaさん?」
葛西はもう一度、こくんと頷く。
「マジか……」
まさか葛西がsaikaさんだなんて思わなかった。だけどよくよく考えてみれば、サイカはカサイのアナグラムであることに気付く。
「なんだ、言ってくれれば良かったのに……」
なぜわざわざ正体を隠していたのか? 知り合いだと分かった時点で明かしてくれれば良かったのに。眉を顰めていると、葛西は真っ赤な顔で叫んだ。
「そんなこと言ったら、ストーカーだと思われてドン引きされるじゃん!」
別にSNSを見ていたからって、ストーカーにはならないだろう。ああ、だけど、投稿して二秒でいいねを送ってくる行為は、ちょっとストーカーっぽいかもしれない。
「SNSストーカー?」
「言うなって、恥ずかしい」
葛西はもう一度、両手で顔を覆う。普段はクールな葛西が、ここまで取り乱しているのはレアだ。意外な一面を見て、ちょっと得した気分になる。とはいえ、手放しには喜べない事実にも気付いてしまった。
「でも、フォロー外したよね? あれはなんで?」
さっき確認した時も、フォロワーにsaikaさんはいなかった。追求すると、葛西は顔を覆ったまま白状した。
「腹が立ったから」
「何に?」
腹が立つような投稿をしたっけ、と振り返る。すると意外な出来事をあげられた。
「知らない女と話してたじゃん」
それは昨日リプでやりとりした女性のことだろうか? いまいちピンとこないまま、こちらの言い分を伝える。
「リプ来たら普通返すでしょ? どこの店ですかって質問されてたし」
俺がおかしいのかと疑惑を抱きつつも弁解すると、葛西は蹲りながら拗ねた声で言う。
「好きって言われてたじゃん。熊谷も満更じゃなさそうだったし」
「それは写真の話じゃん」
別に俺が告られたわけではない。ただ写真を好きと言われただけだ。困惑していると、葛西はワックスで整った髪をくしゃっと握りしめながら本音を吐露した。
「それは分かってるけどさ、あんな簡単に好きって言ってるのが許せなくて……。俺の方がずっとずっと熊谷のこと好きなのに」
不意に「好き」という言葉が飛び出して、胸の奥がこそばゆくなる。葛西は俯きながら、言葉を続けた。
「このままだと嫉妬でどうにかなっちゃいそうだから、学校でも距離取って、フォローも外した。ホントごめん」
そこまで聞けば、葛西の言う「好き」がどういう意味なのか気付いてしまった。同性から特別な感情を向けられているものの、嫌悪感はない。むしろ嬉しくて舞い上がりそうだ。
もっと葛西と向き合いたい。葛西の気持ちをもっと知りたかった。
「ねえ、聞いていい?」
葛西はゆっくりと顔をあげる。その瞳には僅かに涙が滲んでいた。きっと向こうも、感情を吐き出してぐちゃぐちゃになっているのだろう。冷静とはほど遠い状況だったけど、きちんと聞いておきたかった。
「どうして俺のことを好きになってくれたの?」
好きになるのに理由なんかない。ドラマではそんな台詞も耳にしたけど、やっぱり気になってしまった。どうして何の取り柄のない俺に興味を持ってくれたのか?
じっと瞳の奥を見つめていると、葛西はゆっくりと立ち上がる。それにつられて俺も立ち上がった。互いに向き合うと、葛西は真剣な眼差しで話し始めた。
「俺さ、昔から周りの物事にあんまり興味が持てない人間だったんだ。何をしていても、一歩引いて見ているって言うのかな。夢中になれることとかないし、友達とか彼女にも興味が持てなくて……」
それは、付き合っても相手を好きになれないという話と通じるのかもしれない。一つひとつ言葉を飲み込みながら、続く言葉を待った。
「何をしても心が動かない俺は、人間として欠陥だと思っていたんだ」
そんなことはないでしょ、と否定しようと思ったが、続く言葉で阻まれた。
「そんな時、熊谷のインスタを見つけたんだ。『#キリトリセカイ』で何となく写真を眺めていたら、毎日上り下りしている坂道の写真が出て来て」
「え?」
坂道の写真と言われてもピンとこない。過去に撮った写真を頭の中で振り返っていると、葛西が話題にあげた写真を見せてくれた。
「これ。ぱっと見て、すぐに場所が分かった」
スマホに映し出されていたのは、学校から駅まで向かうまでの坂道だ。夕暮れ時の空が、橙色、黄色、桃色、紫色、紺色と移り変わっている。日没後の数十分間だけ見られるマジックアワーだ。
「この写真を見た時、見慣れた景色の中にこんなに綺麗なものがあるんだって気付かされた。他の写真も、綺麗なものや和むものばかりで、この人には世界がどんな風に見えているんだろうって興味が湧いた」
俺が切り取った世界は、些細なものばかりだ。日常の中に当たり前のように存在する景色で、珍しいものなんて何ひとつない。それでも葛西は、興味を持ってくれた。
「そしたらさ、その人が同じクラスにいることに気付いて驚いた。熊谷のことをもっと知りたくて、思い切って一緒に帰ろうって誘った。最初は友達になれれば十分だと思っていたけど、夕日に照らされた熊谷の横顔を見ていたらそれ以上の感情になって……」
そこまで聞くと、途端に恥ずかしくなる。初めて一緒に帰った日、葛西から綺麗だと言われたけど、あれはそういう意味だったのか。
「一緒に過ごすようになって、ころころ表情が変わる熊谷を見ていたらもっと好きになった。手を繋がれて困惑している熊谷も、ちょっと拗ねた熊谷も、カフェではしゃいでいる熊谷も、くすぐられて涙目になっている熊谷も、涎を垂らして寝てる熊谷も、抱きしめられてちょっとえっちな顔している熊谷も、全部切り取って保存したくなった」
「えっ……な顔は、してないと思うけど……」
教室で抱きしめられたことを思い出す。自覚はないものの、葛西の言っていたような顔をしていたとしたら最悪だ。葛西は一歩近づくと、俺の顎に手を添えて強引に顔を上げる。
「してたよ。あの顔見て、理性失いかけたから」
恥ずかしくて泣きそうなる。顎を掴まれているせいで、顔を背けることもできなかった。葛西は俺の瞳を見据えながら、真剣な声色で告げる。
「俺は、熊谷のことが好き。熊谷の全部が知りたい」
直球で告白されるとは思わなかった。恥ずかしいけど、それ以上に嬉しさが込み上げてくる。
葛西は、膨大な情報で溢れるネットの海から俺を見つけ出しくれた。それだけに留まらず、好きになってくれた。写真だけでなく俺自身のことも。葛西から好きと言ってもらえたことで、何の取り柄のない俺でも価値のある存在に思えた。
嬉しいと思っている時点で、俺の気持ちは決まっている。葛西がはっきりと伝えてくれたんだから、俺もきちんと伝えなければ。
「俺も、葛西のことが好きだよ」
心臓は破裂しそうなほど暴れている。それでも、この想いだけはきちんと伝えたかった。俺の顎から手を離した葛西は、驚いたようにこちらを凝視する。
「本当に? 俺の好きって、友達としての好きじゃないよ?」
「そんなの……分かってるよ」
いちいち言わなくたって分かっている。そこまで鈍感ではない。
「本当に分かってんの?」
「分かってるよ。俺だって、そういう意味で好きだって言ってるんだから。今日学校で素っ気なくされて寂しかったし、葛西が公園まで駆けつけてくれた時は嬉しくなった」
恥を忍んで伝えたというのに、葛西はまだ納得してくれない。
「いや、友達に素っ気なくされても寂しくなるでしょ。俺の好きはそういうんじゃない」
「はああ!?」
どうして分かってくれないんだ。確かに友達に素っ気なくされても寂しくなるけど、それとこれとは話が違う。
この感情をどうやって証明すればいいんだ? もどかしくなって頭を掻きむしっていると、葛西はもう一度俺の瞳を覗き込んだ。
「じゃあさ、熊谷は俺とキスできる?」
思いがけない言葉に目を瞠る。熱を帯びた瞳に見据えられると、呼吸すら忘れてしまった。
「俺の好きは、そういう好きだから」
分かってる。この感情の延長線上に、そういう欲があることも。だけど、俺は葛西に対してそういう欲を抱いたことがない。葛西への想いも、自覚したばかりだから。言葉に詰まらせていると、葛西は眉を下げながら微笑む。
「ごめん、困らせるようなことを言って。これからは友達として傍にいられればいいから」
このままでは葛西が離れていってしまう。そんなのは嫌だ。
「できるよ」
離れかけた葛西の手を掴んで、強く訴える。身体が熱くて仕方がない。それでも葛西を引き留めたい一心で、精一杯の強がりを言った。
キスをした後に、自分がどんな感情になるか分からない。もしかしたら心が追い付かなくて、嫌悪感を抱くかもしれない。それでも葛西を引き留めるには、この方法しか思い浮かばなかった。
本気であることが伝わるようにじっと見つめていると、葛西の瞳がギラリと光る。距離を縮め、今にも触れ合いそうな近さで迫られた。
「本当にするよ?」
「うん」
熱い眼差しを向けられて、頭が沸騰しそうになる。身を強張らせていると、葛西の大きな手が俺の後頭部を包み込んだ。
「目、閉じて」
言われた通りに目を閉じる。ドキドキしながら、その時を待った。数秒の間があった後、唇に柔らかいものが掠めた。
ほんの一瞬、触れただけだ。それでも確実にキスをしていた。
胸の奥がくすぐったくなる。頭がふわふわして仕方がない。心配していた嫌悪感は一切なくて、舞い上がりそうなほどの高揚感に満たされた。
「無理してない?」
目を開けると、葛西が心配そうにこちらを見下ろしている。気遣うようなことを言っているが、瞳の奥には明らかに興奮が滲んでいた。その眼差しに晒されるだけで、またしても胸の奥がむず痒くなる。
薄い唇に視線を向けると、先ほどの感触が鮮明に蘇る。どうやら俺にも欲はあったようだ。堪らなくなって、葛西の肩に手を回して求めた。
「もっとして良いよ」
磁石に引き寄せられるように、今度は俺からキスをする。すると、さっきよりも深く重なった。ふにっとした柔らかい感触や、湿った質感が伝わると、深い幸福感に包まれる。
やばい。こんなのを知ってしまったら中毒になりそうだ。離れようとしたものの、今度は葛西の方から唇を押し当ててきた。
「んっ……」
先ほどまでの軽く触れ合うだけのキスとは違う。欲望を剥き出しにした本気のキスだ。葛西は唇を食んだり軽く舐めたりしながら、夢中で貪っていた。
もっとして良いとは言ったけど、これは想像以上だ。ふわふわした気持ちのままされるがままになっていると、不意に自転車が迫ってくる音が聞こえた。そこで慌てて離れる。
自転車が通り過ぎるのをドキドキしながら見届ける。完全に姿が見えなくなったところで、二人して安堵の溜息をついた。顔を見合わせると、どちらともなく笑いだす。
「今のはマジで焦った。俺、制服だから見られたらヤバかったね」
「バレたら学校に通報とかされんのかな?」
「分かんないけど、万が一そんなことになったら学年集会になるかもね」
会話の内容は深刻だけど、俺達はどちらも笑っている。それくらい浮かれていた。
ひとしきり笑った後、葛西は穏やかに微笑みながら告げた。
「熊谷、付き合おう」
改まって言われるとは思わなかった。驚いたものの、嬉しいことには変わりない。
「うん」
微笑みながら返事をすると、葛西は蕩けきったような笑顔を浮かべた。
「じゃあこれからは、俺だけのものだね」
両手を広げた葛西に抱きしめられる。こんなに近付いたら、また心臓の音が聞こえてしまいそうだ。だけど離れたくはなかった。俺はおずおずと葛西の背中に手を回す。
「熊谷、可愛い」
耳元で甘く囁かれながら、さらに強く抱きしめられた。
離れる間際、葛西は俺の頬に軽くキスをする。再び向き合うと、葛西は心底幸せそうに微笑んでいた。その表情にときめいている自分がいる。
この景色を切り取っておきたい。俺はポケットからスマホを取り出して、葛西に向けた。
――カシャ
「え? なんで今撮った?」
半笑いで迫ってくる葛西に、俺は悪戯っぽく笑いながら伝えた。
「内緒」
好きだなぁ、と思ったからなんて恥ずかしくて言えない。俺の言葉を聞いた葛西は、声を抑えながら笑った。
「写真、インスタに上げんなよ」
「上げないよ。俺専用だから」
葛西の口癖を真似してみた。これまで何度も聞いた言葉だけど、葛西がどんな気持ちで言っているのか理解できたような気がした。
スマホで撮った写真を見返していると、思わず笑みが零れる。こんなに愛おしい景色は、誰にも見せたくない。
~おわり~
「熊谷!」
ダッシュで近付いてきたかと思うと、勢いよく抱きしめられる。普通に立っていたら後ろに倒れていたかもしれないが、パンダの遊具に寄りかかっていたおかげで体勢をキープできた。バネで揺れている俺の身体を、葛西はぎゅうぎゅうと抱きしめる。
「ごめん、本当ごめん」
「なんで謝るの?」
「俺のせいで、熊谷に寂しい思いをさせたから」
もしかして葛西は、教室で素っ気なくしたことを謝っているのか? そうだとしても、まだ納得できないことがある。
「なんで俺が寂しがっているって分かったの?」
「寂しいって呟いてたじゃん」
確かにインスタで『寂しい』と呟いた。だけどその投稿はすぐに削除したし、そもそも葛西には俺のアカウントは教えていない。
「なんで葛西が俺のアカウント知ってんの?」
追求すると、葛西は俺の背中に回していた腕を解く。顔を見合わせた後、葛西は「ああー」と呻きながら頭を抱えてしゃがみ込んだ。
「……ごめん、今の忘れて」
「いや、無理だから」
こんな不可思議なことを忘れられるはずがない。俺は葛西の隣にしゃがみ込んで、顔を覗き込んだ。
「ねえ、なんで知ってるの?」
じっと見つめて追及をすると、葛西は顔を手で覆いながら小さな声で白状した。
「……ずっと、見てたから」
「もしかしてフォロワーだった?」
葛西はこくんと頷く。まさかこんな身近にフォロワーがいるとは思わなかった。とはいえ、葛西なんてアカウントは今まで見たことがない。葛西、かさい、カサイ……と考え込んでいると、ある人物の存在を思い出す。
「saikaさん?」
葛西はもう一度、こくんと頷く。
「マジか……」
まさか葛西がsaikaさんだなんて思わなかった。だけどよくよく考えてみれば、サイカはカサイのアナグラムであることに気付く。
「なんだ、言ってくれれば良かったのに……」
なぜわざわざ正体を隠していたのか? 知り合いだと分かった時点で明かしてくれれば良かったのに。眉を顰めていると、葛西は真っ赤な顔で叫んだ。
「そんなこと言ったら、ストーカーだと思われてドン引きされるじゃん!」
別にSNSを見ていたからって、ストーカーにはならないだろう。ああ、だけど、投稿して二秒でいいねを送ってくる行為は、ちょっとストーカーっぽいかもしれない。
「SNSストーカー?」
「言うなって、恥ずかしい」
葛西はもう一度、両手で顔を覆う。普段はクールな葛西が、ここまで取り乱しているのはレアだ。意外な一面を見て、ちょっと得した気分になる。とはいえ、手放しには喜べない事実にも気付いてしまった。
「でも、フォロー外したよね? あれはなんで?」
さっき確認した時も、フォロワーにsaikaさんはいなかった。追求すると、葛西は顔を覆ったまま白状した。
「腹が立ったから」
「何に?」
腹が立つような投稿をしたっけ、と振り返る。すると意外な出来事をあげられた。
「知らない女と話してたじゃん」
それは昨日リプでやりとりした女性のことだろうか? いまいちピンとこないまま、こちらの言い分を伝える。
「リプ来たら普通返すでしょ? どこの店ですかって質問されてたし」
俺がおかしいのかと疑惑を抱きつつも弁解すると、葛西は蹲りながら拗ねた声で言う。
「好きって言われてたじゃん。熊谷も満更じゃなさそうだったし」
「それは写真の話じゃん」
別に俺が告られたわけではない。ただ写真を好きと言われただけだ。困惑していると、葛西はワックスで整った髪をくしゃっと握りしめながら本音を吐露した。
「それは分かってるけどさ、あんな簡単に好きって言ってるのが許せなくて……。俺の方がずっとずっと熊谷のこと好きなのに」
不意に「好き」という言葉が飛び出して、胸の奥がこそばゆくなる。葛西は俯きながら、言葉を続けた。
「このままだと嫉妬でどうにかなっちゃいそうだから、学校でも距離取って、フォローも外した。ホントごめん」
そこまで聞けば、葛西の言う「好き」がどういう意味なのか気付いてしまった。同性から特別な感情を向けられているものの、嫌悪感はない。むしろ嬉しくて舞い上がりそうだ。
もっと葛西と向き合いたい。葛西の気持ちをもっと知りたかった。
「ねえ、聞いていい?」
葛西はゆっくりと顔をあげる。その瞳には僅かに涙が滲んでいた。きっと向こうも、感情を吐き出してぐちゃぐちゃになっているのだろう。冷静とはほど遠い状況だったけど、きちんと聞いておきたかった。
「どうして俺のことを好きになってくれたの?」
好きになるのに理由なんかない。ドラマではそんな台詞も耳にしたけど、やっぱり気になってしまった。どうして何の取り柄のない俺に興味を持ってくれたのか?
じっと瞳の奥を見つめていると、葛西はゆっくりと立ち上がる。それにつられて俺も立ち上がった。互いに向き合うと、葛西は真剣な眼差しで話し始めた。
「俺さ、昔から周りの物事にあんまり興味が持てない人間だったんだ。何をしていても、一歩引いて見ているって言うのかな。夢中になれることとかないし、友達とか彼女にも興味が持てなくて……」
それは、付き合っても相手を好きになれないという話と通じるのかもしれない。一つひとつ言葉を飲み込みながら、続く言葉を待った。
「何をしても心が動かない俺は、人間として欠陥だと思っていたんだ」
そんなことはないでしょ、と否定しようと思ったが、続く言葉で阻まれた。
「そんな時、熊谷のインスタを見つけたんだ。『#キリトリセカイ』で何となく写真を眺めていたら、毎日上り下りしている坂道の写真が出て来て」
「え?」
坂道の写真と言われてもピンとこない。過去に撮った写真を頭の中で振り返っていると、葛西が話題にあげた写真を見せてくれた。
「これ。ぱっと見て、すぐに場所が分かった」
スマホに映し出されていたのは、学校から駅まで向かうまでの坂道だ。夕暮れ時の空が、橙色、黄色、桃色、紫色、紺色と移り変わっている。日没後の数十分間だけ見られるマジックアワーだ。
「この写真を見た時、見慣れた景色の中にこんなに綺麗なものがあるんだって気付かされた。他の写真も、綺麗なものや和むものばかりで、この人には世界がどんな風に見えているんだろうって興味が湧いた」
俺が切り取った世界は、些細なものばかりだ。日常の中に当たり前のように存在する景色で、珍しいものなんて何ひとつない。それでも葛西は、興味を持ってくれた。
「そしたらさ、その人が同じクラスにいることに気付いて驚いた。熊谷のことをもっと知りたくて、思い切って一緒に帰ろうって誘った。最初は友達になれれば十分だと思っていたけど、夕日に照らされた熊谷の横顔を見ていたらそれ以上の感情になって……」
そこまで聞くと、途端に恥ずかしくなる。初めて一緒に帰った日、葛西から綺麗だと言われたけど、あれはそういう意味だったのか。
「一緒に過ごすようになって、ころころ表情が変わる熊谷を見ていたらもっと好きになった。手を繋がれて困惑している熊谷も、ちょっと拗ねた熊谷も、カフェではしゃいでいる熊谷も、くすぐられて涙目になっている熊谷も、涎を垂らして寝てる熊谷も、抱きしめられてちょっとえっちな顔している熊谷も、全部切り取って保存したくなった」
「えっ……な顔は、してないと思うけど……」
教室で抱きしめられたことを思い出す。自覚はないものの、葛西の言っていたような顔をしていたとしたら最悪だ。葛西は一歩近づくと、俺の顎に手を添えて強引に顔を上げる。
「してたよ。あの顔見て、理性失いかけたから」
恥ずかしくて泣きそうなる。顎を掴まれているせいで、顔を背けることもできなかった。葛西は俺の瞳を見据えながら、真剣な声色で告げる。
「俺は、熊谷のことが好き。熊谷の全部が知りたい」
直球で告白されるとは思わなかった。恥ずかしいけど、それ以上に嬉しさが込み上げてくる。
葛西は、膨大な情報で溢れるネットの海から俺を見つけ出しくれた。それだけに留まらず、好きになってくれた。写真だけでなく俺自身のことも。葛西から好きと言ってもらえたことで、何の取り柄のない俺でも価値のある存在に思えた。
嬉しいと思っている時点で、俺の気持ちは決まっている。葛西がはっきりと伝えてくれたんだから、俺もきちんと伝えなければ。
「俺も、葛西のことが好きだよ」
心臓は破裂しそうなほど暴れている。それでも、この想いだけはきちんと伝えたかった。俺の顎から手を離した葛西は、驚いたようにこちらを凝視する。
「本当に? 俺の好きって、友達としての好きじゃないよ?」
「そんなの……分かってるよ」
いちいち言わなくたって分かっている。そこまで鈍感ではない。
「本当に分かってんの?」
「分かってるよ。俺だって、そういう意味で好きだって言ってるんだから。今日学校で素っ気なくされて寂しかったし、葛西が公園まで駆けつけてくれた時は嬉しくなった」
恥を忍んで伝えたというのに、葛西はまだ納得してくれない。
「いや、友達に素っ気なくされても寂しくなるでしょ。俺の好きはそういうんじゃない」
「はああ!?」
どうして分かってくれないんだ。確かに友達に素っ気なくされても寂しくなるけど、それとこれとは話が違う。
この感情をどうやって証明すればいいんだ? もどかしくなって頭を掻きむしっていると、葛西はもう一度俺の瞳を覗き込んだ。
「じゃあさ、熊谷は俺とキスできる?」
思いがけない言葉に目を瞠る。熱を帯びた瞳に見据えられると、呼吸すら忘れてしまった。
「俺の好きは、そういう好きだから」
分かってる。この感情の延長線上に、そういう欲があることも。だけど、俺は葛西に対してそういう欲を抱いたことがない。葛西への想いも、自覚したばかりだから。言葉に詰まらせていると、葛西は眉を下げながら微笑む。
「ごめん、困らせるようなことを言って。これからは友達として傍にいられればいいから」
このままでは葛西が離れていってしまう。そんなのは嫌だ。
「できるよ」
離れかけた葛西の手を掴んで、強く訴える。身体が熱くて仕方がない。それでも葛西を引き留めたい一心で、精一杯の強がりを言った。
キスをした後に、自分がどんな感情になるか分からない。もしかしたら心が追い付かなくて、嫌悪感を抱くかもしれない。それでも葛西を引き留めるには、この方法しか思い浮かばなかった。
本気であることが伝わるようにじっと見つめていると、葛西の瞳がギラリと光る。距離を縮め、今にも触れ合いそうな近さで迫られた。
「本当にするよ?」
「うん」
熱い眼差しを向けられて、頭が沸騰しそうになる。身を強張らせていると、葛西の大きな手が俺の後頭部を包み込んだ。
「目、閉じて」
言われた通りに目を閉じる。ドキドキしながら、その時を待った。数秒の間があった後、唇に柔らかいものが掠めた。
ほんの一瞬、触れただけだ。それでも確実にキスをしていた。
胸の奥がくすぐったくなる。頭がふわふわして仕方がない。心配していた嫌悪感は一切なくて、舞い上がりそうなほどの高揚感に満たされた。
「無理してない?」
目を開けると、葛西が心配そうにこちらを見下ろしている。気遣うようなことを言っているが、瞳の奥には明らかに興奮が滲んでいた。その眼差しに晒されるだけで、またしても胸の奥がむず痒くなる。
薄い唇に視線を向けると、先ほどの感触が鮮明に蘇る。どうやら俺にも欲はあったようだ。堪らなくなって、葛西の肩に手を回して求めた。
「もっとして良いよ」
磁石に引き寄せられるように、今度は俺からキスをする。すると、さっきよりも深く重なった。ふにっとした柔らかい感触や、湿った質感が伝わると、深い幸福感に包まれる。
やばい。こんなのを知ってしまったら中毒になりそうだ。離れようとしたものの、今度は葛西の方から唇を押し当ててきた。
「んっ……」
先ほどまでの軽く触れ合うだけのキスとは違う。欲望を剥き出しにした本気のキスだ。葛西は唇を食んだり軽く舐めたりしながら、夢中で貪っていた。
もっとして良いとは言ったけど、これは想像以上だ。ふわふわした気持ちのままされるがままになっていると、不意に自転車が迫ってくる音が聞こえた。そこで慌てて離れる。
自転車が通り過ぎるのをドキドキしながら見届ける。完全に姿が見えなくなったところで、二人して安堵の溜息をついた。顔を見合わせると、どちらともなく笑いだす。
「今のはマジで焦った。俺、制服だから見られたらヤバかったね」
「バレたら学校に通報とかされんのかな?」
「分かんないけど、万が一そんなことになったら学年集会になるかもね」
会話の内容は深刻だけど、俺達はどちらも笑っている。それくらい浮かれていた。
ひとしきり笑った後、葛西は穏やかに微笑みながら告げた。
「熊谷、付き合おう」
改まって言われるとは思わなかった。驚いたものの、嬉しいことには変わりない。
「うん」
微笑みながら返事をすると、葛西は蕩けきったような笑顔を浮かべた。
「じゃあこれからは、俺だけのものだね」
両手を広げた葛西に抱きしめられる。こんなに近付いたら、また心臓の音が聞こえてしまいそうだ。だけど離れたくはなかった。俺はおずおずと葛西の背中に手を回す。
「熊谷、可愛い」
耳元で甘く囁かれながら、さらに強く抱きしめられた。
離れる間際、葛西は俺の頬に軽くキスをする。再び向き合うと、葛西は心底幸せそうに微笑んでいた。その表情にときめいている自分がいる。
この景色を切り取っておきたい。俺はポケットからスマホを取り出して、葛西に向けた。
――カシャ
「え? なんで今撮った?」
半笑いで迫ってくる葛西に、俺は悪戯っぽく笑いながら伝えた。
「内緒」
好きだなぁ、と思ったからなんて恥ずかしくて言えない。俺の言葉を聞いた葛西は、声を抑えながら笑った。
「写真、インスタに上げんなよ」
「上げないよ。俺専用だから」
葛西の口癖を真似してみた。これまで何度も聞いた言葉だけど、葛西がどんな気持ちで言っているのか理解できたような気がした。
スマホで撮った写真を見返していると、思わず笑みが零れる。こんなに愛おしい景色は、誰にも見せたくない。
~おわり~