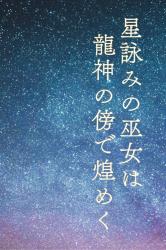満腹になると午後の授業で眠くなるという葛西の指摘は正しかった。六限の数学の授業で、俺はこくりこくりと船を漕いでいた。
黒板に書かれている数式が歪んで見える。眠気に抗うことができず、俺は机に突っ伏して眠りについた。
目を覚ました頃には、授業どころかホームルームすら終わっていた。教室はしんと静まり返っていて、グラウンドからは運動部の掛け声が聞こえてくる。
目を擦りながら机から顔を上げると、目の前に葛西の顔があった。机の上で頬杖をついていた葛西は、驚いたように目を見開く。
一歩間違えば、キスでもしてしまいそうな距離感だ。息遣いすら感じる近さに、心臓が跳ね上がる。俺は恥ずかしさを追い払うように、冗談めかして言った。
「俺はキスしても目を覚まさないよ」
「覚ましたじゃん」
冗談で言ったつもりだったのに、何食わぬ顔で肯定されてしまう。
まさか、本当にしたのか?
カアアッと顔が熱くなるのを感じながら口元を押さえていると、葛西は真顔を崩して笑い始めた。
「嘘、嘘、してないよ」
「な、なんだ、驚かせんなよ……」
寝ている間にファーストキスを奪われたらショックだ。するんだったら、ちゃんと意識のある時にしたい。そんなことを考えていると、葛西はやけに色気のある顔で言った。
「しようと思ったけど、やめた」
それも冗談だよな? どんなリアクションを取れば良いのか分からずにいると、葛西がポケットからスマホを取り出した。
「その代わりに寝顔を激写した」
ぽちぽちとスマホを操作すると、俺が涎を垂らしながら眠っている写真を突きつけられる。間抜けな姿を盗み撮りされて、死にたくなった。
「勝手に撮んなよ! 消せ!」
椅子から立ち上がって葛西のスマホを奪おうとしたものの、さらりとかわされてしまう。机から身を乗り出してもう一度手を伸ばしたが、葛西はスマホを持った手を高く掲げて届かないようにした。
「恥ずかしいから、消せって!」
「やだ」
それならと葛西の正面に回ろうとすると、教室の後ろ側まで逃げられてしまった。俺もダッシュで追いかける。
「早く消せって!」
「やだ。熊谷の寝顔とか激レアじゃん」
背伸びをして奪おうと試みたが、身長の高い葛西に手を伸ばされたら届かない。ぴょんぴょんとジャンプしても、空気を掴むばかりでスマホには届かなかった。必死に奪おうとする俺を見下ろしながら、葛西は悪戯っ子のように笑う。
「いいじゃん。俺専用なんだから」
またそれか。俺の写真なんて撮って、何の価値があるんだ。やっぱり葛西は、変な奴だ。
息切れしたところで、スマホを奪うのは諦める。あの感じだと、どうせ消してはくれないだろう。小さく溜息をついてから、俺は席に着こうと振り返った。
正面を向いた時、はっと息を飲んだ。
夕日に照らされた教室が、橙色に染まっている。秋風に煽られてカーテンが揺らめくと、整然と並んだ机に長い影を落とした。
綺麗なのは間違いないのだけれど、切なさが溢れかえってくる。胸の奥が締め付けられる感覚に耐えながら、目の前の景色を瞳の奥に焼き付けた。
「この雰囲気、結構好きかも。普段は騒がしい教室が、夕日に飲み込まれて消えていくような……」
もうしばらくすれば、窓の外は暗くなり、この教室も闇夜に飲まれていく。そうなってしまう前に、この景色を切り取っておきたかった。
俺はブレザーのポケットからスマホを取り出して、橙色の教室を画角に収める。シャッターを切ろうとした瞬間、ふっと背中に温もりを感じた。
最初は何が起こっているのか分からなかった。だけど腰に回された手を見て、葛西に後ろから抱きしめられていることに気付いた。
「葛西?」
急にどうしたんだろう? 振り返ろうとした時、耳元に吐息が触れた。
「熊谷のそういう感性、本当好き。俺にはないものだから」
耳元で囁かれると、くすぐったくて仕方がない。身をよじらせると、逃げられないようにぎゅっと抱きしめられた。
「熊谷の全部が知りたい」
肩に額をすり寄せながら、甘い声で囁かれる。背中から伝わる熱と、清涼感のあるワックスの香りに、身体の内側がくすぐられた。
熊谷の全部が知りたい。そんなことを言われたって、どうやって教えればいいのか分からない。それにさっき口にした「好き」は、どういう意味での「好き」なのか? こうして抱きしめられているということは、やっぱり……。
「熊谷、今何考えてるの?」
耳元で質問される。低い声と吐息が伝わった瞬間、またしてもくずぐったい刺激が駆け巡った。浅い呼吸を繰り返しながら振り返る。
「葛西のこと、考えてた」
取り繕う余裕すらなくて、正直に明かす。すると葛西の瞳の奥がギラリと光ったような気がした。
「ふーん」
目を細めながら笑ったかと思えば、腰に回された手が白いシャツの上を這う。骨ばった大きな手は、少しずつ上っていき、胸の位置で止まった。
「俺のこと考えながら、こんなに心臓バクバクさせてるんだ」
シャツ越しに心臓の音を聞かれている。緊張も、興奮も、何もかも見透かされてしまいそうだ。
こんなの駄目だ。頭がおかしくなる。泣きそうになっていると、さらに追い詰められる。
「ねえ、どうして?」
細い指先で胸をくすぐられる。淡い刺激に堪えられなくなり、「あっ」と声を漏らした。
咄嗟に口を塞ぐ。なんだ今の甘ったるい声は? このままではどうにかなってしまいそうだ。おかしな空気を断ち切るように、俺は葛西の腕から逃れた。
「わかんないよ。つーか、離せ」
恥ずかしくて、葛西の顔が見られない。俺はダッシュで自分の席まで戻ると、スクールバッグを掴んだ。
「今日は一人で帰る」
振り返ることなく素っ気なく伝えると、逃げるように教室から飛び出した。
黒板に書かれている数式が歪んで見える。眠気に抗うことができず、俺は机に突っ伏して眠りについた。
目を覚ました頃には、授業どころかホームルームすら終わっていた。教室はしんと静まり返っていて、グラウンドからは運動部の掛け声が聞こえてくる。
目を擦りながら机から顔を上げると、目の前に葛西の顔があった。机の上で頬杖をついていた葛西は、驚いたように目を見開く。
一歩間違えば、キスでもしてしまいそうな距離感だ。息遣いすら感じる近さに、心臓が跳ね上がる。俺は恥ずかしさを追い払うように、冗談めかして言った。
「俺はキスしても目を覚まさないよ」
「覚ましたじゃん」
冗談で言ったつもりだったのに、何食わぬ顔で肯定されてしまう。
まさか、本当にしたのか?
カアアッと顔が熱くなるのを感じながら口元を押さえていると、葛西は真顔を崩して笑い始めた。
「嘘、嘘、してないよ」
「な、なんだ、驚かせんなよ……」
寝ている間にファーストキスを奪われたらショックだ。するんだったら、ちゃんと意識のある時にしたい。そんなことを考えていると、葛西はやけに色気のある顔で言った。
「しようと思ったけど、やめた」
それも冗談だよな? どんなリアクションを取れば良いのか分からずにいると、葛西がポケットからスマホを取り出した。
「その代わりに寝顔を激写した」
ぽちぽちとスマホを操作すると、俺が涎を垂らしながら眠っている写真を突きつけられる。間抜けな姿を盗み撮りされて、死にたくなった。
「勝手に撮んなよ! 消せ!」
椅子から立ち上がって葛西のスマホを奪おうとしたものの、さらりとかわされてしまう。机から身を乗り出してもう一度手を伸ばしたが、葛西はスマホを持った手を高く掲げて届かないようにした。
「恥ずかしいから、消せって!」
「やだ」
それならと葛西の正面に回ろうとすると、教室の後ろ側まで逃げられてしまった。俺もダッシュで追いかける。
「早く消せって!」
「やだ。熊谷の寝顔とか激レアじゃん」
背伸びをして奪おうと試みたが、身長の高い葛西に手を伸ばされたら届かない。ぴょんぴょんとジャンプしても、空気を掴むばかりでスマホには届かなかった。必死に奪おうとする俺を見下ろしながら、葛西は悪戯っ子のように笑う。
「いいじゃん。俺専用なんだから」
またそれか。俺の写真なんて撮って、何の価値があるんだ。やっぱり葛西は、変な奴だ。
息切れしたところで、スマホを奪うのは諦める。あの感じだと、どうせ消してはくれないだろう。小さく溜息をついてから、俺は席に着こうと振り返った。
正面を向いた時、はっと息を飲んだ。
夕日に照らされた教室が、橙色に染まっている。秋風に煽られてカーテンが揺らめくと、整然と並んだ机に長い影を落とした。
綺麗なのは間違いないのだけれど、切なさが溢れかえってくる。胸の奥が締め付けられる感覚に耐えながら、目の前の景色を瞳の奥に焼き付けた。
「この雰囲気、結構好きかも。普段は騒がしい教室が、夕日に飲み込まれて消えていくような……」
もうしばらくすれば、窓の外は暗くなり、この教室も闇夜に飲まれていく。そうなってしまう前に、この景色を切り取っておきたかった。
俺はブレザーのポケットからスマホを取り出して、橙色の教室を画角に収める。シャッターを切ろうとした瞬間、ふっと背中に温もりを感じた。
最初は何が起こっているのか分からなかった。だけど腰に回された手を見て、葛西に後ろから抱きしめられていることに気付いた。
「葛西?」
急にどうしたんだろう? 振り返ろうとした時、耳元に吐息が触れた。
「熊谷のそういう感性、本当好き。俺にはないものだから」
耳元で囁かれると、くすぐったくて仕方がない。身をよじらせると、逃げられないようにぎゅっと抱きしめられた。
「熊谷の全部が知りたい」
肩に額をすり寄せながら、甘い声で囁かれる。背中から伝わる熱と、清涼感のあるワックスの香りに、身体の内側がくすぐられた。
熊谷の全部が知りたい。そんなことを言われたって、どうやって教えればいいのか分からない。それにさっき口にした「好き」は、どういう意味での「好き」なのか? こうして抱きしめられているということは、やっぱり……。
「熊谷、今何考えてるの?」
耳元で質問される。低い声と吐息が伝わった瞬間、またしてもくずぐったい刺激が駆け巡った。浅い呼吸を繰り返しながら振り返る。
「葛西のこと、考えてた」
取り繕う余裕すらなくて、正直に明かす。すると葛西の瞳の奥がギラリと光ったような気がした。
「ふーん」
目を細めながら笑ったかと思えば、腰に回された手が白いシャツの上を這う。骨ばった大きな手は、少しずつ上っていき、胸の位置で止まった。
「俺のこと考えながら、こんなに心臓バクバクさせてるんだ」
シャツ越しに心臓の音を聞かれている。緊張も、興奮も、何もかも見透かされてしまいそうだ。
こんなの駄目だ。頭がおかしくなる。泣きそうになっていると、さらに追い詰められる。
「ねえ、どうして?」
細い指先で胸をくすぐられる。淡い刺激に堪えられなくなり、「あっ」と声を漏らした。
咄嗟に口を塞ぐ。なんだ今の甘ったるい声は? このままではどうにかなってしまいそうだ。おかしな空気を断ち切るように、俺は葛西の腕から逃れた。
「わかんないよ。つーか、離せ」
恥ずかしくて、葛西の顔が見られない。俺はダッシュで自分の席まで戻ると、スクールバッグを掴んだ。
「今日は一人で帰る」
振り返ることなく素っ気なく伝えると、逃げるように教室から飛び出した。