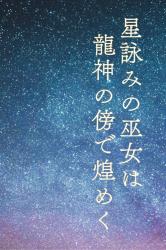葛西と関わるようになってから一週間が経過した。最初の二日間は放課後に一緒に帰るだけだったけど、カフェに行った翌日からは教室でもたびたび声をかけてくるようになった。
「熊谷、おはよう」
「熊谷、次、移動教室だよ」
「熊谷、英語の宿題やった?」
「熊谷、どこいくの? トイレ? なら俺も一緒に」
口を開けば、熊谷、熊谷、熊谷……。流石にちょっと構い過ぎじゃないか?
最近では陽キャグループから離れて、俺とばかりつるむようになっている。それでいいのかと心配したものの、本人は結構楽しそうだ。
もとのグループでは口数の少ない葛西だったが、俺といる時はよく喋るし、表情豊かだ。大口を開けて爆笑することはないけど、ふとしたタイミングで穏やかに微笑むことがある。その笑顔を見せつけられる度、胸の奥がむず痒くなった。イケメンの笑顔は、男にも効果てきめんらしい。
昼休みになると、コンビニの袋を下げた葛西が俺の席までやってきた。
「熊谷、昼飯食おう」
「ん」
端的に返事をしてから、俺はスクールバッグに入ったお弁当を取り出した。
ここ最近は、昼飯も一緒に食べるようになっている。場所は決まって中庭。ピクニック気分でのんびりできる場所だけど、陽キャの溜まり場だったから、これまでは使ったことがなかった。
だけど葛西と一緒なら、あまり浮くことはない。木陰に二人並んで、弁当を広げた。
ランチョンマットの上に、二段重ねのお弁当を広げていると、葛西が声を抑えながら笑う。
「前から思ってたけどさ、熊谷の弁当って量多いよね」
「そう?」
葛西につられてまじまじと弁当を見る。一段目には、ぎっちり詰め込まれた白米。二段目には、昨日の残り物のから揚げとほうれん草のおひたしと大学イモ、それに母さんが今朝作った玉子焼きとウインナーが入っている。いつも通りの弁当だ。
「普通じゃない?」
「多い方だと思うよ」
そう言われてもあまりピンとこない。参考までに葛西の昼飯を見ると、コンビニで買った玉子サンドと鶏むね肉のサラダだけだった。
「葛西こそ、それで足りんの?」
「まあ、足りるかな。満腹になると午後の授業で眠くなるから、これくらいでちょうどいい」
午後の授業で寝ないために、昼飯の量を調整するという発想はなかった。俺なんて昼は腹一杯食べて、午後の授業では睡魔と戦っている。改めて格の違いを見せつけられると、葛西が二つ入りの玉子サンドのうち一つを俺に差し出した。
「玉子サンド、一個食べる?」
「葛西の分が少なくなるじゃん」
「いいよ。美味しそうに飯食ってる熊谷を見てるだけで満たされるから」
意味がわからない。俺なんか見たって腹の足しにはならないだろう。
「変なの」
疑問に思いつつも、差し出された玉子サンドはありがたく頂いた。代わりにから揚げをあげると、嬉しそうに表情を綻ばせた。
普段からそうやって笑っていれば、もっとモテそうなのに……なんてお節介極まりないことを考えていると、不意に目が合う。
「なに? 熊谷」
「いや、葛西ってさ、俺といる時はよく笑うなって」
指摘をしてみると、葛西は目を丸くしながら頬を押さえた。
「俺、笑ってた?」
「え? 自覚なかったの?」
自覚がないとは驚きだ。二人してきょとんとした顔をしていると、葛西がじわじわと嬉しさが滲みだすように笑いだした。
「熊谷といると、感情が忙しい」
「なんだよそれ……」
褒められているのか、ディスられているのか、よく分からない。首を捻りながらも、最後のひとつの玉子焼きを口に放り込んだ。弁当箱が空になると、葛西がまじまじと覗き込む。
「本当に完食した。その細い身体のどこに、そんなに入るの?」
「細い? そうかな?」
俺はシャツをめくって腹回りを見る。自分では普通だと思っているけど、他の男子から見れば細く見えるのか? 第三者の意見を聞こうと思ったものの、葛西は手の甲で口元を押さえながら視線を彷徨わせていた。
「そういうこと、軽率にすんなよ」
「そういうことって?」
「肌見せるとか……」
俺は、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。腹を見せただけで、なんでそんなに赤くなっているんだ? 相手が女子なら分かるけど。
「早くしまって。他の人も見てるかもしれないし」
まるで露出狂みたいな扱いだ。軽くショックを受けていると、葛西は俺のシャツを掴む。
「ほら、早く」
強引にシャツを下ろそうとした瞬間、葛西の手の甲が俺の脇腹を掠めた。
「ふあっ」
くすぐったくて、おかしな声を出してしまった。恥ずかしくて俯いていると、葛西が目を丸くしながら俺の顔を覗き込んだ。
「なに、今の声?」
そんな目で見るな。俺は視線を逸らしながら弁解した。
「……脇腹、弱いんだよ」
恥を忍んで弱点を教えると、葛西の瞳の奥がギラリと光ったような気がした。
「ふーん」
葛西はにやりと口元を歪めたかと思うと、じりじりと距離を詰めてくる。
「そう言われると、もっと触りたくなる」
「おい、やめろ。来んな」
正面まで迫ってくると、細い指先で脇腹をくすぐり始めた。
「ぎゃーー! やめろーー!」
こそばゆい刺激に襲われて力が入らなくなる。芝生に倒れこむと、葛西は俺を見下ろしながらくすぐりを続行した。
「やめっ……力入んない」
「激よわじゃん」
じたばたと悶える俺を、楽しそうに見下ろす葛西。あのクールな葛西がこんな子供っぽい悪戯をしてくるとは思わなかった。意外な一面に驚かされたものの、今はそれどころじゃない。
「ほんと、やめろ!」
笑いすぎて涙目になってきたところで、ようやく脇腹から手が離れる。ぜえぜえと息を切らしながら顔を上げると、ちょっとおかしな状態になっていることに気付いた。
俺の肩の真横に手を置いて、こちらを見下ろす葛西。これではまるで、押し倒されているみたいだ。したり顔をしていた葛西も、徐々に真顔に戻っていく。
「ごめん、やりすぎた」
こんな姿を他の人に見られたら変に思われる。俺は慌てて身体を起こした。
「本当ごめん。変な意味でやったわけじゃないから」
頭を下げて謝る葛西は、耳まで真っ赤に染めていた。
変な意味ってなんだよ。そんな反応をされると余計に恥ずかしくなる。俺は急いで弁当箱を片付けて、立ち上がった。
「そろそろ教室に戻ろう」
「うん」
恥ずかしさに苛まれながら、俺達は教室に戻った。
「熊谷、おはよう」
「熊谷、次、移動教室だよ」
「熊谷、英語の宿題やった?」
「熊谷、どこいくの? トイレ? なら俺も一緒に」
口を開けば、熊谷、熊谷、熊谷……。流石にちょっと構い過ぎじゃないか?
最近では陽キャグループから離れて、俺とばかりつるむようになっている。それでいいのかと心配したものの、本人は結構楽しそうだ。
もとのグループでは口数の少ない葛西だったが、俺といる時はよく喋るし、表情豊かだ。大口を開けて爆笑することはないけど、ふとしたタイミングで穏やかに微笑むことがある。その笑顔を見せつけられる度、胸の奥がむず痒くなった。イケメンの笑顔は、男にも効果てきめんらしい。
昼休みになると、コンビニの袋を下げた葛西が俺の席までやってきた。
「熊谷、昼飯食おう」
「ん」
端的に返事をしてから、俺はスクールバッグに入ったお弁当を取り出した。
ここ最近は、昼飯も一緒に食べるようになっている。場所は決まって中庭。ピクニック気分でのんびりできる場所だけど、陽キャの溜まり場だったから、これまでは使ったことがなかった。
だけど葛西と一緒なら、あまり浮くことはない。木陰に二人並んで、弁当を広げた。
ランチョンマットの上に、二段重ねのお弁当を広げていると、葛西が声を抑えながら笑う。
「前から思ってたけどさ、熊谷の弁当って量多いよね」
「そう?」
葛西につられてまじまじと弁当を見る。一段目には、ぎっちり詰め込まれた白米。二段目には、昨日の残り物のから揚げとほうれん草のおひたしと大学イモ、それに母さんが今朝作った玉子焼きとウインナーが入っている。いつも通りの弁当だ。
「普通じゃない?」
「多い方だと思うよ」
そう言われてもあまりピンとこない。参考までに葛西の昼飯を見ると、コンビニで買った玉子サンドと鶏むね肉のサラダだけだった。
「葛西こそ、それで足りんの?」
「まあ、足りるかな。満腹になると午後の授業で眠くなるから、これくらいでちょうどいい」
午後の授業で寝ないために、昼飯の量を調整するという発想はなかった。俺なんて昼は腹一杯食べて、午後の授業では睡魔と戦っている。改めて格の違いを見せつけられると、葛西が二つ入りの玉子サンドのうち一つを俺に差し出した。
「玉子サンド、一個食べる?」
「葛西の分が少なくなるじゃん」
「いいよ。美味しそうに飯食ってる熊谷を見てるだけで満たされるから」
意味がわからない。俺なんか見たって腹の足しにはならないだろう。
「変なの」
疑問に思いつつも、差し出された玉子サンドはありがたく頂いた。代わりにから揚げをあげると、嬉しそうに表情を綻ばせた。
普段からそうやって笑っていれば、もっとモテそうなのに……なんてお節介極まりないことを考えていると、不意に目が合う。
「なに? 熊谷」
「いや、葛西ってさ、俺といる時はよく笑うなって」
指摘をしてみると、葛西は目を丸くしながら頬を押さえた。
「俺、笑ってた?」
「え? 自覚なかったの?」
自覚がないとは驚きだ。二人してきょとんとした顔をしていると、葛西がじわじわと嬉しさが滲みだすように笑いだした。
「熊谷といると、感情が忙しい」
「なんだよそれ……」
褒められているのか、ディスられているのか、よく分からない。首を捻りながらも、最後のひとつの玉子焼きを口に放り込んだ。弁当箱が空になると、葛西がまじまじと覗き込む。
「本当に完食した。その細い身体のどこに、そんなに入るの?」
「細い? そうかな?」
俺はシャツをめくって腹回りを見る。自分では普通だと思っているけど、他の男子から見れば細く見えるのか? 第三者の意見を聞こうと思ったものの、葛西は手の甲で口元を押さえながら視線を彷徨わせていた。
「そういうこと、軽率にすんなよ」
「そういうことって?」
「肌見せるとか……」
俺は、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。腹を見せただけで、なんでそんなに赤くなっているんだ? 相手が女子なら分かるけど。
「早くしまって。他の人も見てるかもしれないし」
まるで露出狂みたいな扱いだ。軽くショックを受けていると、葛西は俺のシャツを掴む。
「ほら、早く」
強引にシャツを下ろそうとした瞬間、葛西の手の甲が俺の脇腹を掠めた。
「ふあっ」
くすぐったくて、おかしな声を出してしまった。恥ずかしくて俯いていると、葛西が目を丸くしながら俺の顔を覗き込んだ。
「なに、今の声?」
そんな目で見るな。俺は視線を逸らしながら弁解した。
「……脇腹、弱いんだよ」
恥を忍んで弱点を教えると、葛西の瞳の奥がギラリと光ったような気がした。
「ふーん」
葛西はにやりと口元を歪めたかと思うと、じりじりと距離を詰めてくる。
「そう言われると、もっと触りたくなる」
「おい、やめろ。来んな」
正面まで迫ってくると、細い指先で脇腹をくすぐり始めた。
「ぎゃーー! やめろーー!」
こそばゆい刺激に襲われて力が入らなくなる。芝生に倒れこむと、葛西は俺を見下ろしながらくすぐりを続行した。
「やめっ……力入んない」
「激よわじゃん」
じたばたと悶える俺を、楽しそうに見下ろす葛西。あのクールな葛西がこんな子供っぽい悪戯をしてくるとは思わなかった。意外な一面に驚かされたものの、今はそれどころじゃない。
「ほんと、やめろ!」
笑いすぎて涙目になってきたところで、ようやく脇腹から手が離れる。ぜえぜえと息を切らしながら顔を上げると、ちょっとおかしな状態になっていることに気付いた。
俺の肩の真横に手を置いて、こちらを見下ろす葛西。これではまるで、押し倒されているみたいだ。したり顔をしていた葛西も、徐々に真顔に戻っていく。
「ごめん、やりすぎた」
こんな姿を他の人に見られたら変に思われる。俺は慌てて身体を起こした。
「本当ごめん。変な意味でやったわけじゃないから」
頭を下げて謝る葛西は、耳まで真っ赤に染めていた。
変な意味ってなんだよ。そんな反応をされると余計に恥ずかしくなる。俺は急いで弁当箱を片付けて、立ち上がった。
「そろそろ教室に戻ろう」
「うん」
恥ずかしさに苛まれながら、俺達は教室に戻った。