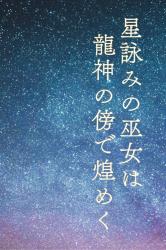翌日。帰りのホームルームが終わると、葛西が俺の席にやって来た。
「熊谷、帰ろう」
クラスメイトからの注目が集まる中、俺は小さく頷く。
「うん」
承諾すると、葛西の頬が僅かに緩んだ。その笑顔に、ドキッとしている自分がいる。
葛西の後に続いて教室から出ようとしたところで、いつも葛西とつるんでいるムードメーカーの佐藤に道を塞がれた。
「え? なになに? 葛西と熊谷って仲良かったっけ?」
佐藤は俺達の顔を交互に見比べる。興味津々とばかりに注目されると、少し居心地が悪くなった。背中を丸めて小さくなっていると、葛西が佐藤を押しのけて俺の腕を掴む。
「じろじろ見んな。熊谷が怯えてんだろ」
「悪い、悪い。なんか面白い組み合わせだったから。俺も熊谷と話したいし、一緒に帰っても」
「駄目」
屈託のない笑顔で同行しようとする佐藤を、葛西が一蹴する。そんなに冷たく突き放さなくたっていいじゃないか。断られた佐藤が哀れに思えてきた。
すると葛西がおもむろに俺の肩に手を伸ばし、ぐいっと引き寄せる。バランスを崩した俺は、葛西の胸にすっぽり収まった。あまりの急展開についていけずに固まっていると、信じられない言葉が飛んでくる。
「俺達これからデートなんだよ。邪魔すんな」
デート。デート。デート……。あれ、デートってなんだっけ? デートがゲシュタルト崩壊していると、今度は手を繋がれる。
「行こう、熊谷」
おい、なんでナチュラルに手を繋いでるんだよ! なんて文句を言いたかったけど、葛西が不機嫌そうだから言い出せない。成すすべなく、俺は葛西に連行された。
◇
「おい、なんでナチュラルに手を繋いでるんだよ!」
正門を出てから、ようやくツッコミを入れられた。俺が大声を出したせいで、周りの生徒も一斉にこちらに注目する。そこでやっと左手が解放された。
「ごめん」
一言、そう謝るだけだった。先ほどのデート発言といい、さっきから何なんだ?
「つーか、なんでデートなんて言ったんだよ? あんなん言ったら誤解されるじゃん」
むっとしながらぶっきらぼうに抗議すると、葛西は手の甲を口元に添えながら吹き出す。
「もしかして熊谷、デートするの初めて?」
「初めてだけど、今それはどうでもよくて、男同士で出掛けることをデートなんて言わないだろ」
「気になる人と出掛けるのは、デートじゃない?」
さも当然と言わんばかりに告げられる。確かにその理屈は正しいとは思うけど、すぐには飲み込めない。
「葛西って、俺のこと気になってんの?」
「……うん」
一瞬間があった後、肯定される。葛西は、俺からの視線から逃れるように俯いていた。心なしか耳まで赤くなっているような気がする。
葛西の言っている「気になる」は、友達としてという解釈でいいのか? 真実を追及するのは、ちょっと怖かった。
恥ずかしさを振り払うように、葛西の隣を通りすぎて早足で坂道を下る。すると、後から走ってきた葛西が隣に並んだ。
「せっかくだし、どっか寄ってく?」
「どっかって?」
「こっから三駅先の本町駅の西口に、良い感じのカフェがあるんだけど」
「カフェ?」
思わず立ち止まって、葛西の顔を覗き込む。放課後にお洒落なカフェに立ち寄る。それは密かに憧れていたことだ。
「行く」
嬉しいけど、あんまりはしゃいだら子供っぽく思われそうだ。ここはクールに振舞おう。
視線を落としながら意思を伝えると、葛西は表情を緩ませた。
「うん、じゃあ行こっか」
◇
葛西に案内されたのは、お洒落なハワイアンカフェだ。店の外にはヤシの木が植えられていて、壁一面は大きなガラス窓になっている。大通りから少し覗いただけでも、お洒落な空間であることが伝わってきた。
「ここに入るの?」
俺一人だったら、まず入らない店だ。怖気づいていると、パステルイエローの木製扉に手をかけた葛西が振り返る。
「やだ? 別の場所にする?」
「そういうわけじゃないけど、お洒落空間過ぎて俺には場違いな気が……」
店内にいるのは、綺麗な女性やお洒落なカップルばかり。葛西ならまだしも、俺には場違いな気がしてならない。そろりそろりと後退りしていると、葛西に腕を掴まれて捕獲される。
「大丈夫。熊谷、可愛いから」
綺麗の次は、可愛いときた。葛西の目には、一体俺はどんな風に映っているのか?
心の準備ができないまま、葛西に手を引かれながら店に入った。
「いらっしゃいませ~」
カランコロンという軽やかなベルの音と共に、黒いキャップを被ったお姉さんに出迎えられる。ハワイアンカフェということもあり、内装もリゾート風だ。入口に立てかけられたライトブルーのサーフボード、壁に吊るされた色鮮やかなレイ、テーブルとテーブルの仕切りの上にはハイビスカスの造花が飾られている。まじまじと店内を観察していると、お姉さんに声をかけられた。
「二名様ですね。ご案内いたします」
俺は葛西を盾にしながら、おっかなびっくり店内を歩く。案内されたのは、四人は座れそうな窓際のソファー席だ。ソファの端にはウミガメのイラストがプリントされたクッションがある。
「熊谷、奥座りな」
「うん」
俺は葛西に促されるまま、奥の席に腰掛けた。その瞬間、柔らかいソファーにお尻が埋まる。
「わっ! ソファーふかふか」
柔らかさを確かめるように腰を上下に浮かせていると、正面に座った葛西に笑われた。そこで慌てて姿勢を正す。
油断すると、すぐコレだ。子供っぽく思われないように、大人しく過ごそう。
そう決意したのも束の間、葛西からメニューを差し出されると、好奇心を刺激された。
「食べ物もめっちゃお洒落じゃん! どれも美味そう。あっ、これインスタで見たことあるやつだ」
イラスト付きのメニューには、ハワイアンバーガーやガーリックシュリンプなどのフードが載っている。それにいつぞやsaikaさんがインスタにあげていたパンとベーコンに黄色いソースがかかったフードもあった。インスタで見た時から美味しそうだと思っていたんだ。これを食べてみたい。
「熊谷はそれにする?」
願望が駄々洩れだったのか、葛西に言い当てられる。恥ずかしさを感じたものの、俺は素直に頷いた。
「うん」
「飲み物は? 最後のページに載ってるよ」
「えーっと、じゃあ、カフェラテで」
フードとドリンクが決まると、葛西が手を挙げて店員を呼ぶ。すると、最初に案内してくれたお姉さんがにこやかにやって来た。
「ご注文お伺いします」
眩しい笑顔に圧倒される。しどろもどろになりながらも、どうにか注文を口にした。
「この、ベーコンベックエネディクトで……」
「ベーコンエッグベネディクトな」
葛西にしれっと訂正される。緊張しすぎてカタカナも読めなくなってしまった。恥ずかしくて背中を丸めていると、葛西が他の注文も済ませた。
「あとは、サーモンサラダパンケーキとカフェラテ、それとクラフトレモネードで」
「かしこまりました」
黒いキャップのお姉さんが、にこやかに去っていく。結局、俺のドリンクまで注文させてしまった。なんだか申し訳ない。
「なんか、ごめん」
「え? 何が?」
葛西は驚いたように瞬きを繰り返す。気にしていないなら、いいか。
「ううん、何でもない」
俺は首を振ってから、ウミガメのクッションを膝に乗せた。
葛西は格好いいだけでなく、気遣いもできる。だからモテるんだろうなぁと納得していた。なんだか人間としての格の違いを見せつけられたような気分だ。視線を落としながらクッションを抱き寄せていると、正面に座った葛西が肩を竦めながらはにかんだ。
「なんか、緊張する」
俺は目を丸くして、葛西の顔を凝視する。葛西はこういう場所に慣れていそうだから意外だった。
「ここ、何度か来たことがあるんでしょ? なんで緊張するの?」
率直に尋ねると、葛西は「違う違う」とはにかみながら首を振った。
「熊谷と二人でカフェにいる状況に緊張してる」
「なんで?」
少し大きな声で聞き返してしまう。女子と二人きりならまだしも、俺といるだけで緊張するなんて意味が分からない。ぱちぱちと瞬きを繰り返していると、葛西は目を細めながら微笑んだ。
「そりゃあ、気になる人といれば、緊張もするでしょう」
またしても「気になる人」発言が飛び出す。葛西が言うと、どうにも色恋沙汰のように聞こえてしまうから良くない。さらりと思わせぶりな発言ができるのも、モテる所以なのかもしれない。俯きながらクッションをぎゅうぎゅうと抱きしめていると、葛西に声をかけられる。
「熊谷、今何考えてるの?」
視線を上げると、葛西はテーブルから身を乗り出して、俺の顔を覗き込んでいた。不意に距離が近くなって、心臓が跳ね上がる。
「えっ……そのー……葛西はモテそうだなーって」
嘘ではない。実際にモテそうだと思っていた。
俺の言葉を聞くと、葛西はテーブルから離れて、ソファーの背もたれに身体を預ける。
「別にモテないし」
「嘘つけ。一年前くらい? 先輩と付き合ってたじゃん」
高一の秋頃、葛西が美人な先輩と付き合っていると噂で聞いたことがある。一年の頃はクラスが違ったから顔すら知らなかったけど、クラスの女子が「先輩に取られた~」と大泣きしていたのは覚えている。
先輩の話を持ち出すと、葛西はいじけたように視線を落とした。
「……付き合ってたけど、あんまり好きになれなくて別れた」
これはあまり深堀してはいけない案件な気がする。別の話題に切り替えようとしたものの、葛西は視線を落としたまま話を続けた。
「俺さ、いつもそうなんだよね。告られて、付き合っても、相手のことをあんまり好きになれなくて別れるの。先輩の時もさ、今度こそ好きになれるかもって思ったんだけど、やっぱり駄目で……。そんなこと繰り返してきたから、きっと俺は人を好きになることすらできないドライな人間なんだって思ってた」
深刻なトーンで打ち明けられて面食らう。俺は俯く葛西をまじまじと見つめていた。
交際経験のない俺からすれば、彼女がいるだけでも眩しい。だけど葛西にとっての「付き合う」は後ろめたさも孕んでいるように思えた。モテるっていうのも、案外大変なのかもしれない。
どうフォローをすればいいのか分からずにいると、俯いていた葛西の口元がほんの少しだけ緩む。
「だけど最近は、そうじゃないかもって気付いたから、嬉しいんだ」
それはどういうことだ? 追求しようとしたものの、白い皿を両手に持ったお姉さんがやって来て阻まれた。
「お待たせしました。ベーコンエッグベネディクトとサーモンサラダパンケーキです」
「ありがとうございます。エッグベネディクトがあっちで、サーモンサラダがこっちです」
葛西がメニューを片付けてテキパキと置き場所を指示すると、目の前にプレートが置かれた。料理が揃うと、葛西は穏やかに微笑みながら、カトラリーケースを差し出す。
「食べよ」
銀のナイフとフォークを取り出してから、もう一度葛西を盗み見る。
「ん?」
葛西は目を細めながら、こくりと首を傾ける。そんな些細な仕草すら格好良いのだから、なんだかズルイ。複雑な心持ちのまま、俺はベーコンなんちゃらにナイフを入れた。
すると、玉子の黄味がとろーっと溢れ出して、ベーコンの上に広がる。ベーコンの端まで流れると、白い皿の上まで流れ落ちた。その芸術的ともいえる光景を見て、俺は声を弾ませる。
「玉子じゃん。しかもとろとろのやつ」
「え? 今気付いたの? メニューにもエッグって書いてあったじゃん」
葛西は驚いたように俺の顔を見る。お恥ずかしながら、今の今までエッグの存在には気付かなかった。メニューに書かれていたイラストから、黄色いソースのかかったベーコンマフィンだと思っていた。
「もしかして、玉子苦手だった? アレルギーとか?」
葛西が心配そうに尋ねてきたが、俺はぶんぶんと首を振って否定する。
「違う。むしろ好き。玉子全般大好き」
玉子は好物だ。中でもとろとろの玉子は、食べ物の中で一番好きかもしれない。嫌いでないことをアピールすると、葛西は安心したように頬を緩めた。
「それなら良かった」
さっそくマフィンとベーコンを一口大に切り、ソースと黄味をたっぷり付けて口に運ぶ。コクのあるソースと滑らかな黄味の食感が合わさると、口の中がパラダイスになった。
「んまっ! なにこれ、めっちゃ美味い!」
こんなに美味い食べ物が世の中に存在するなんて知らなかった。ベーコンは厚みがあって食べ応えがあるし、下に敷かれたマフィンはふわふわだ。なによりソースが美味い。バターのようなまろやかな味わいの中にレモンの酸味が混じっている。そこに滑らかな黄味が混ざると、さらに濃厚になった。
目を輝かせながら感動に浸っていると、葛西は俯きながらプルプルと肩を震わせた。
「……っとに熊谷は……」
その姿を見て、緩んだ表情を引き締める。
やばい。はしゃぎ過ぎだ。俺はナイフとフォークを握りしめたまま背中を丸めた。
「ごめん、今の忘れて」
「忘れられるわけないじゃん。あー、ミスったー。さっきの動画に収めておけば良かった……」
葛西は、悔しそうに顔を顰めている。俺が飯を食っているだけの動画を撮って何が面白いんだ? ひとまずは、恥を拡散されるリスクがなくなって安堵した。しかし動画という単語が出たことで、重大な失態に気付いてしまった。
「写真撮るの忘れた」
せっかくの映える料理だったのに、写真に収めることなく食べてしまった。もったいないことをしたなぁと悔いていると、再び葛西に笑われた。
「次来た時に撮ればいいじゃん」
次来た時、ということはまた一緒に来てくれるのか? 驚いていると、輪切りのゆで卵を刺したフォークが目の前に差し出される。
「こっちのサラダにゆで卵あるけど、食べる?」
俺がさっき玉子が好きと言ったから、気を使ってくれたのかもしれない。恥ずかしかったけど、せっかくの厚意を無駄にするのは忍びない。
「……食べる」
俺は差し出されたゆで卵を口にした。
「ありがとう」
端的に礼を伝えると、葛西は嬉しそうに頬を緩めた。
「どういたしまして」
その後も、特に会話が弾むわけでもなく、黙々と食事を続ける。早々に完食してしまった俺は、プレートに乗ったハイビスカスを指先でくるくると弄っていた。
これも食べられるのかなぁ、なんて考えながら店内に流れる洋楽に耳を傾けていると、不意に葛西からスマホを向けられた。
「え? なに? 写真?」
「違う、動画」
「はあ? 勝手に撮んなし」
レンズを手で覆って撮影を中断させると、葛西が声を潜めながら笑った。
「ごめん、ごめん。花で遊んでいる熊谷が可愛かったから」
「なんだよそれ……」
またしても可愛いと言われてしまった。本当に、葛西には俺がどう見えているんだ。
葛西は撮影した動画を見返しながら、「可愛い」と呟く。その姿に首をかしげてしまった。
「俺なんか撮って楽しい?」
「楽しい」
即答されてしまった。やっぱり理解不能だ。
「どうでもいいけどさ、ストーリーにあげたりしないでね」
俺の動画が世間に晒されるのはごめんだ。念のため忠告をすると、葛西は頬を緩めながら首を振った。
「あげないよ。俺専用だから」
またしても「俺専用」が飛び出した。拡散されないのは良いのだけれど、葛西のスマホに俺の動画があるという事実も恥ずかしい。昨日も撮られたから、写真と動画が両方あるということになる。
こうなったら、いつか隙を見て葛西の写真も撮ってやろうと、密かに対抗意識を燃やしていた。
◇
その日の晩、俺はベッドでうつ伏せになりながら、今日撮った写真を見返していた。
料理の写真も、葛西の写真も撮り損ねたけど、食後に出てきたカフェラテは撮影できた。それも普通のカフェラテではない。表面に立体的なしろくまのラテアートが施されたカフェラテだ。
飲んでしまうのがもったいないくらい可愛かったけど、飲まないのはもっともったいない。モコモコのしろくまを写真に収めてから、ありがたく頂いた。
カフェでのやりとりを思い出しながら、インスタを開く。慣れた手つきで『#キリトリセカイ』と添えて、ラテアートの写真を投稿した。すると、二秒後に「いいね」が飛んでくる。
「はっや……」
反応してくれたのは、saikaさんだ。いつも反応は早いけど、今回は最速記録かもしれない。
「もしかしてsaikaさんって、暇人?」
なんて失礼な想像をしながら、俺はスマホを手放した。
「熊谷、帰ろう」
クラスメイトからの注目が集まる中、俺は小さく頷く。
「うん」
承諾すると、葛西の頬が僅かに緩んだ。その笑顔に、ドキッとしている自分がいる。
葛西の後に続いて教室から出ようとしたところで、いつも葛西とつるんでいるムードメーカーの佐藤に道を塞がれた。
「え? なになに? 葛西と熊谷って仲良かったっけ?」
佐藤は俺達の顔を交互に見比べる。興味津々とばかりに注目されると、少し居心地が悪くなった。背中を丸めて小さくなっていると、葛西が佐藤を押しのけて俺の腕を掴む。
「じろじろ見んな。熊谷が怯えてんだろ」
「悪い、悪い。なんか面白い組み合わせだったから。俺も熊谷と話したいし、一緒に帰っても」
「駄目」
屈託のない笑顔で同行しようとする佐藤を、葛西が一蹴する。そんなに冷たく突き放さなくたっていいじゃないか。断られた佐藤が哀れに思えてきた。
すると葛西がおもむろに俺の肩に手を伸ばし、ぐいっと引き寄せる。バランスを崩した俺は、葛西の胸にすっぽり収まった。あまりの急展開についていけずに固まっていると、信じられない言葉が飛んでくる。
「俺達これからデートなんだよ。邪魔すんな」
デート。デート。デート……。あれ、デートってなんだっけ? デートがゲシュタルト崩壊していると、今度は手を繋がれる。
「行こう、熊谷」
おい、なんでナチュラルに手を繋いでるんだよ! なんて文句を言いたかったけど、葛西が不機嫌そうだから言い出せない。成すすべなく、俺は葛西に連行された。
◇
「おい、なんでナチュラルに手を繋いでるんだよ!」
正門を出てから、ようやくツッコミを入れられた。俺が大声を出したせいで、周りの生徒も一斉にこちらに注目する。そこでやっと左手が解放された。
「ごめん」
一言、そう謝るだけだった。先ほどのデート発言といい、さっきから何なんだ?
「つーか、なんでデートなんて言ったんだよ? あんなん言ったら誤解されるじゃん」
むっとしながらぶっきらぼうに抗議すると、葛西は手の甲を口元に添えながら吹き出す。
「もしかして熊谷、デートするの初めて?」
「初めてだけど、今それはどうでもよくて、男同士で出掛けることをデートなんて言わないだろ」
「気になる人と出掛けるのは、デートじゃない?」
さも当然と言わんばかりに告げられる。確かにその理屈は正しいとは思うけど、すぐには飲み込めない。
「葛西って、俺のこと気になってんの?」
「……うん」
一瞬間があった後、肯定される。葛西は、俺からの視線から逃れるように俯いていた。心なしか耳まで赤くなっているような気がする。
葛西の言っている「気になる」は、友達としてという解釈でいいのか? 真実を追及するのは、ちょっと怖かった。
恥ずかしさを振り払うように、葛西の隣を通りすぎて早足で坂道を下る。すると、後から走ってきた葛西が隣に並んだ。
「せっかくだし、どっか寄ってく?」
「どっかって?」
「こっから三駅先の本町駅の西口に、良い感じのカフェがあるんだけど」
「カフェ?」
思わず立ち止まって、葛西の顔を覗き込む。放課後にお洒落なカフェに立ち寄る。それは密かに憧れていたことだ。
「行く」
嬉しいけど、あんまりはしゃいだら子供っぽく思われそうだ。ここはクールに振舞おう。
視線を落としながら意思を伝えると、葛西は表情を緩ませた。
「うん、じゃあ行こっか」
◇
葛西に案内されたのは、お洒落なハワイアンカフェだ。店の外にはヤシの木が植えられていて、壁一面は大きなガラス窓になっている。大通りから少し覗いただけでも、お洒落な空間であることが伝わってきた。
「ここに入るの?」
俺一人だったら、まず入らない店だ。怖気づいていると、パステルイエローの木製扉に手をかけた葛西が振り返る。
「やだ? 別の場所にする?」
「そういうわけじゃないけど、お洒落空間過ぎて俺には場違いな気が……」
店内にいるのは、綺麗な女性やお洒落なカップルばかり。葛西ならまだしも、俺には場違いな気がしてならない。そろりそろりと後退りしていると、葛西に腕を掴まれて捕獲される。
「大丈夫。熊谷、可愛いから」
綺麗の次は、可愛いときた。葛西の目には、一体俺はどんな風に映っているのか?
心の準備ができないまま、葛西に手を引かれながら店に入った。
「いらっしゃいませ~」
カランコロンという軽やかなベルの音と共に、黒いキャップを被ったお姉さんに出迎えられる。ハワイアンカフェということもあり、内装もリゾート風だ。入口に立てかけられたライトブルーのサーフボード、壁に吊るされた色鮮やかなレイ、テーブルとテーブルの仕切りの上にはハイビスカスの造花が飾られている。まじまじと店内を観察していると、お姉さんに声をかけられた。
「二名様ですね。ご案内いたします」
俺は葛西を盾にしながら、おっかなびっくり店内を歩く。案内されたのは、四人は座れそうな窓際のソファー席だ。ソファの端にはウミガメのイラストがプリントされたクッションがある。
「熊谷、奥座りな」
「うん」
俺は葛西に促されるまま、奥の席に腰掛けた。その瞬間、柔らかいソファーにお尻が埋まる。
「わっ! ソファーふかふか」
柔らかさを確かめるように腰を上下に浮かせていると、正面に座った葛西に笑われた。そこで慌てて姿勢を正す。
油断すると、すぐコレだ。子供っぽく思われないように、大人しく過ごそう。
そう決意したのも束の間、葛西からメニューを差し出されると、好奇心を刺激された。
「食べ物もめっちゃお洒落じゃん! どれも美味そう。あっ、これインスタで見たことあるやつだ」
イラスト付きのメニューには、ハワイアンバーガーやガーリックシュリンプなどのフードが載っている。それにいつぞやsaikaさんがインスタにあげていたパンとベーコンに黄色いソースがかかったフードもあった。インスタで見た時から美味しそうだと思っていたんだ。これを食べてみたい。
「熊谷はそれにする?」
願望が駄々洩れだったのか、葛西に言い当てられる。恥ずかしさを感じたものの、俺は素直に頷いた。
「うん」
「飲み物は? 最後のページに載ってるよ」
「えーっと、じゃあ、カフェラテで」
フードとドリンクが決まると、葛西が手を挙げて店員を呼ぶ。すると、最初に案内してくれたお姉さんがにこやかにやって来た。
「ご注文お伺いします」
眩しい笑顔に圧倒される。しどろもどろになりながらも、どうにか注文を口にした。
「この、ベーコンベックエネディクトで……」
「ベーコンエッグベネディクトな」
葛西にしれっと訂正される。緊張しすぎてカタカナも読めなくなってしまった。恥ずかしくて背中を丸めていると、葛西が他の注文も済ませた。
「あとは、サーモンサラダパンケーキとカフェラテ、それとクラフトレモネードで」
「かしこまりました」
黒いキャップのお姉さんが、にこやかに去っていく。結局、俺のドリンクまで注文させてしまった。なんだか申し訳ない。
「なんか、ごめん」
「え? 何が?」
葛西は驚いたように瞬きを繰り返す。気にしていないなら、いいか。
「ううん、何でもない」
俺は首を振ってから、ウミガメのクッションを膝に乗せた。
葛西は格好いいだけでなく、気遣いもできる。だからモテるんだろうなぁと納得していた。なんだか人間としての格の違いを見せつけられたような気分だ。視線を落としながらクッションを抱き寄せていると、正面に座った葛西が肩を竦めながらはにかんだ。
「なんか、緊張する」
俺は目を丸くして、葛西の顔を凝視する。葛西はこういう場所に慣れていそうだから意外だった。
「ここ、何度か来たことがあるんでしょ? なんで緊張するの?」
率直に尋ねると、葛西は「違う違う」とはにかみながら首を振った。
「熊谷と二人でカフェにいる状況に緊張してる」
「なんで?」
少し大きな声で聞き返してしまう。女子と二人きりならまだしも、俺といるだけで緊張するなんて意味が分からない。ぱちぱちと瞬きを繰り返していると、葛西は目を細めながら微笑んだ。
「そりゃあ、気になる人といれば、緊張もするでしょう」
またしても「気になる人」発言が飛び出す。葛西が言うと、どうにも色恋沙汰のように聞こえてしまうから良くない。さらりと思わせぶりな発言ができるのも、モテる所以なのかもしれない。俯きながらクッションをぎゅうぎゅうと抱きしめていると、葛西に声をかけられる。
「熊谷、今何考えてるの?」
視線を上げると、葛西はテーブルから身を乗り出して、俺の顔を覗き込んでいた。不意に距離が近くなって、心臓が跳ね上がる。
「えっ……そのー……葛西はモテそうだなーって」
嘘ではない。実際にモテそうだと思っていた。
俺の言葉を聞くと、葛西はテーブルから離れて、ソファーの背もたれに身体を預ける。
「別にモテないし」
「嘘つけ。一年前くらい? 先輩と付き合ってたじゃん」
高一の秋頃、葛西が美人な先輩と付き合っていると噂で聞いたことがある。一年の頃はクラスが違ったから顔すら知らなかったけど、クラスの女子が「先輩に取られた~」と大泣きしていたのは覚えている。
先輩の話を持ち出すと、葛西はいじけたように視線を落とした。
「……付き合ってたけど、あんまり好きになれなくて別れた」
これはあまり深堀してはいけない案件な気がする。別の話題に切り替えようとしたものの、葛西は視線を落としたまま話を続けた。
「俺さ、いつもそうなんだよね。告られて、付き合っても、相手のことをあんまり好きになれなくて別れるの。先輩の時もさ、今度こそ好きになれるかもって思ったんだけど、やっぱり駄目で……。そんなこと繰り返してきたから、きっと俺は人を好きになることすらできないドライな人間なんだって思ってた」
深刻なトーンで打ち明けられて面食らう。俺は俯く葛西をまじまじと見つめていた。
交際経験のない俺からすれば、彼女がいるだけでも眩しい。だけど葛西にとっての「付き合う」は後ろめたさも孕んでいるように思えた。モテるっていうのも、案外大変なのかもしれない。
どうフォローをすればいいのか分からずにいると、俯いていた葛西の口元がほんの少しだけ緩む。
「だけど最近は、そうじゃないかもって気付いたから、嬉しいんだ」
それはどういうことだ? 追求しようとしたものの、白い皿を両手に持ったお姉さんがやって来て阻まれた。
「お待たせしました。ベーコンエッグベネディクトとサーモンサラダパンケーキです」
「ありがとうございます。エッグベネディクトがあっちで、サーモンサラダがこっちです」
葛西がメニューを片付けてテキパキと置き場所を指示すると、目の前にプレートが置かれた。料理が揃うと、葛西は穏やかに微笑みながら、カトラリーケースを差し出す。
「食べよ」
銀のナイフとフォークを取り出してから、もう一度葛西を盗み見る。
「ん?」
葛西は目を細めながら、こくりと首を傾ける。そんな些細な仕草すら格好良いのだから、なんだかズルイ。複雑な心持ちのまま、俺はベーコンなんちゃらにナイフを入れた。
すると、玉子の黄味がとろーっと溢れ出して、ベーコンの上に広がる。ベーコンの端まで流れると、白い皿の上まで流れ落ちた。その芸術的ともいえる光景を見て、俺は声を弾ませる。
「玉子じゃん。しかもとろとろのやつ」
「え? 今気付いたの? メニューにもエッグって書いてあったじゃん」
葛西は驚いたように俺の顔を見る。お恥ずかしながら、今の今までエッグの存在には気付かなかった。メニューに書かれていたイラストから、黄色いソースのかかったベーコンマフィンだと思っていた。
「もしかして、玉子苦手だった? アレルギーとか?」
葛西が心配そうに尋ねてきたが、俺はぶんぶんと首を振って否定する。
「違う。むしろ好き。玉子全般大好き」
玉子は好物だ。中でもとろとろの玉子は、食べ物の中で一番好きかもしれない。嫌いでないことをアピールすると、葛西は安心したように頬を緩めた。
「それなら良かった」
さっそくマフィンとベーコンを一口大に切り、ソースと黄味をたっぷり付けて口に運ぶ。コクのあるソースと滑らかな黄味の食感が合わさると、口の中がパラダイスになった。
「んまっ! なにこれ、めっちゃ美味い!」
こんなに美味い食べ物が世の中に存在するなんて知らなかった。ベーコンは厚みがあって食べ応えがあるし、下に敷かれたマフィンはふわふわだ。なによりソースが美味い。バターのようなまろやかな味わいの中にレモンの酸味が混じっている。そこに滑らかな黄味が混ざると、さらに濃厚になった。
目を輝かせながら感動に浸っていると、葛西は俯きながらプルプルと肩を震わせた。
「……っとに熊谷は……」
その姿を見て、緩んだ表情を引き締める。
やばい。はしゃぎ過ぎだ。俺はナイフとフォークを握りしめたまま背中を丸めた。
「ごめん、今の忘れて」
「忘れられるわけないじゃん。あー、ミスったー。さっきの動画に収めておけば良かった……」
葛西は、悔しそうに顔を顰めている。俺が飯を食っているだけの動画を撮って何が面白いんだ? ひとまずは、恥を拡散されるリスクがなくなって安堵した。しかし動画という単語が出たことで、重大な失態に気付いてしまった。
「写真撮るの忘れた」
せっかくの映える料理だったのに、写真に収めることなく食べてしまった。もったいないことをしたなぁと悔いていると、再び葛西に笑われた。
「次来た時に撮ればいいじゃん」
次来た時、ということはまた一緒に来てくれるのか? 驚いていると、輪切りのゆで卵を刺したフォークが目の前に差し出される。
「こっちのサラダにゆで卵あるけど、食べる?」
俺がさっき玉子が好きと言ったから、気を使ってくれたのかもしれない。恥ずかしかったけど、せっかくの厚意を無駄にするのは忍びない。
「……食べる」
俺は差し出されたゆで卵を口にした。
「ありがとう」
端的に礼を伝えると、葛西は嬉しそうに頬を緩めた。
「どういたしまして」
その後も、特に会話が弾むわけでもなく、黙々と食事を続ける。早々に完食してしまった俺は、プレートに乗ったハイビスカスを指先でくるくると弄っていた。
これも食べられるのかなぁ、なんて考えながら店内に流れる洋楽に耳を傾けていると、不意に葛西からスマホを向けられた。
「え? なに? 写真?」
「違う、動画」
「はあ? 勝手に撮んなし」
レンズを手で覆って撮影を中断させると、葛西が声を潜めながら笑った。
「ごめん、ごめん。花で遊んでいる熊谷が可愛かったから」
「なんだよそれ……」
またしても可愛いと言われてしまった。本当に、葛西には俺がどう見えているんだ。
葛西は撮影した動画を見返しながら、「可愛い」と呟く。その姿に首をかしげてしまった。
「俺なんか撮って楽しい?」
「楽しい」
即答されてしまった。やっぱり理解不能だ。
「どうでもいいけどさ、ストーリーにあげたりしないでね」
俺の動画が世間に晒されるのはごめんだ。念のため忠告をすると、葛西は頬を緩めながら首を振った。
「あげないよ。俺専用だから」
またしても「俺専用」が飛び出した。拡散されないのは良いのだけれど、葛西のスマホに俺の動画があるという事実も恥ずかしい。昨日も撮られたから、写真と動画が両方あるということになる。
こうなったら、いつか隙を見て葛西の写真も撮ってやろうと、密かに対抗意識を燃やしていた。
◇
その日の晩、俺はベッドでうつ伏せになりながら、今日撮った写真を見返していた。
料理の写真も、葛西の写真も撮り損ねたけど、食後に出てきたカフェラテは撮影できた。それも普通のカフェラテではない。表面に立体的なしろくまのラテアートが施されたカフェラテだ。
飲んでしまうのがもったいないくらい可愛かったけど、飲まないのはもっともったいない。モコモコのしろくまを写真に収めてから、ありがたく頂いた。
カフェでのやりとりを思い出しながら、インスタを開く。慣れた手つきで『#キリトリセカイ』と添えて、ラテアートの写真を投稿した。すると、二秒後に「いいね」が飛んでくる。
「はっや……」
反応してくれたのは、saikaさんだ。いつも反応は早いけど、今回は最速記録かもしれない。
「もしかしてsaikaさんって、暇人?」
なんて失礼な想像をしながら、俺はスマホを手放した。