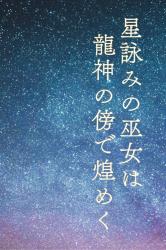二年三組の葛西颯斗。クールイケメンと評判の一軍男子だ。
口数は多くないが、陽キャグループの中ではツッコミ役を担っている。その言葉選びが絶妙で、周囲からも気に入られていた。
成績も優秀。本人はテストの点数をひけらかすタイプではないが、一学期の成績票が配られた時に陽キャグループで「三位、三位」と騒がれていた。
イケメンの上に、コミュ力も高く、頭もいい。天は彼に二物も三物も与え過ぎだと思う。
葛西は男の俺から見ても格好良い。落ち着きがあって、何事にも動じなくて、冷静に物事を対処できる。自分もあんな性格だったらなぁと密かに憧れていた。
そんな葛西から、一緒に帰ろうと誘われた。なぜだ?
これまで一緒に帰ったことなんてないし、教室でもほとんど話したことがない。何なら昨日初めて話したくらいだ。それなのに、誘ってくる意味が分からなかった。
遠慮しようにも、腕を掴まれて逃げられない。じっとこちらを見つめる眼差しからは、逃がさないという意思すら感じさせた。
葛西の顔と掴まれた腕を交互に見ていると、真剣な眼差しで尋ねられる。
「迷惑? それとも他と約束してる?」
「いや……迷惑じゃないし、約束もしていないけど……」
「じゃあ一緒に帰ろう」
拒絶しているわけではないと分かると、有無を言わさず連行される。教室の後方のドアに辿り着くまでの数秒間で、クラスメイトからの注目が集まった。そんな反応になるのも無理はない。
手を引かれながら、さりげなく葛西を観察する。学校指定の白シャツの上からグレーのカーディガンを羽織っている。制服を適度に着崩しているせいか垢抜けた印象だった。ストレートの黒髪もワックスで動きを付けてアレンジしている。昨日チラッと見た限り、スニーカーも格好良かった。もとの顔が良いだけでなく、お洒落にも気遣っているのだから、モテるのは当然だ。
対する俺は至って平凡。学校指定の制服を校則通りに着ているだけで、お洒落とは無縁だ。髪型も無難な黒髪ショートで、ワックスなんて使ったことがない。童顔なせいで、時々中学生に間違えられることもコンプレックスだった。
葛西と俺とでは、キャラもビジュも釣り合っていない。セットでいるのは傍から見てもおかしかった。クラスメイトからの好奇の視線に耐え切れず、俺は俯きながら教室を出た。
◇
「あの、そろそろ腕を離してもらえると……」
正門を出てから恐る恐る申し出る。目立つし恥ずかしいから、そろそろやめていただきたい。すると葛西はあっさり解放してくれた。
「ああ、悪い」
なんだ。すぐに離してくれるなら、もっと早く言えば良かった。
掴まれていた腕をさすりながら、葛西の隣を歩く。チラッと横目で伺うと、綺麗な顔立ちをしているなぁと感じた。今まではあまり意識したことがなかったけど背も高い。167cmの俺とは握りこぶし一つ分は差がありそうだ。横目でまじまじと観察していると、葛西がこちらに視線を向ける。
「なに?」
「いや、なんでも……」
会話終了。葛西は無表情のまま視線を前方に戻す。
いやホント、なんで一緒に帰ろうなんて誘った?
そっちから誘ったんだったら、もっと会話を盛り上げようという気概があってもいいだろう。何かしら話題を振ってくれたら、俺だってちゃんと乗っかる。それくらいのコミュ力は持ち合わせているはずだ。
それなのに葛西は、表情一つ変えず、無言で隣を歩き続けている。ここまで興味を示されていないと、俺と一緒に帰っていること自体が罰ゲームなんじゃないかと邪推してしまった。
……無くはない話だ。罰ゲーム説が濃厚になると、ずーんと気分が沈んでいく。
なんだ、俺に興味があるわけじゃないのか。納得しつつも、どこかがっかりしている自分がいた。
無言のまま駅まで続く下り坂を歩く。俺達の通う高校は高台に建っているため、通学時には曲がりくねった急こう配を上り下りしなければならない。おかげで足腰はかなり鍛えられた。
大半の生徒は坂の上り下りを「だるい」と言っているが、悪いことばかりでもない。ヘアピンカーブをぐるっと回ったところで、視界が開けた場所にやってくる。そこで俺は足を止めた。
「あっ」
坂の下には、ミニチュア模型のように市街地が広がっている。昔ながらの住宅街も、真新しい高層マンションも、大型商業施設のロゴも、すべてが見渡せた。この景色を見ると、いつも清々しい気分になる。
それに今の時間帯は最高だ。空の色が、綺麗なグラデーションになっている。遠くにある山の頂上は橙色に染まっていて、そこから視線を上げると黄色、桃色、紫色、紺色に移り変わっていった。
日没後の数十分間に見られる空は、一日の中でもっとも美しい。帰り道に運よくこの景色を見られると、得した気分になった。
綺麗な景色を前にすると、写真を撮りたくなってくる。ブレザーのポケットからスマホを取り出そうとしたものの、隣に葛西がいることを思い出した。
人といる時に撮影を始めたら失礼かもしれない。やめておこうと諦めた時、思いがけない言葉が飛んできた。
「いいよ、撮っても」
顔を上げて葛西の顔を見る。まるで俺が写真を撮りたがっているのを見越したような発言だ。なんだこいつ、エスパーなのか?
疑問は残るものの、お許しを貰えたのなら遠慮なく撮らせてもらおう。スマホを取り出すと、夕空と市街地を画角に収めた。
――カシャ
一枚撮影してから、そそくさとスマホをポケットにしまう。隣から視線が突き刺さる。気まずさを振り払うように、俺はたどたどしく雑談を始めた。
「日の出前とか日の入り後の空が薄明るい時間帯のことを、マジックアワーって言うんだよ。空気の澄んだ晴れた日には空がグラデーションになるんだけど、昼と夜が溶け合ったみたいな感じが俺は結構好きで……」
話しているだけなのに、顔がどんどん熱くなる。急にこんな話をしたら、おかしな奴だと思われるだろうか。失敗したなぁと思いながら俯いていると、穏やかな声が届く。
「やっぱり好きだな」
顔を上げると、葛西は口元を緩めて微笑んでいた。
教室では滅多に笑わない葛西が、笑っている。俺は大きく目を見開きながら、その顔を目に焼き付けていた。
俺が凝視していることに気付くと、葛西ははっと我に返る。頭を掻きながら、たどたどしく言葉を続けた。
「なんだっけ……。マジックアワー? 俺も好きだなって」
「え? ああ、へぇー、そうなんだー……」
驚き過ぎて、さっき話していたことすら忘れてしまった。ふわふわした気持ちのまま立ち尽くしていると、葛西はポケットからスマホを取り出す。
「俺も撮って良い?」
「ああ、うん、どうぞ」
写真に写り込まないように一歩横にズレたものの、葛西はスマホのレンズをこちらに向ける。
――カシャ。
「え? 今、俺を撮らなかった?」
「うん、撮った」
「なんで?」
「……綺麗だったから」
一瞬の間があった後、葛西は視線を落としながら小さな声で白状した。
「変なの……」
訳が分からないまま、俺はスマホをポケットに突っ込んで歩き出した。早足で坂を下っていると、葛西が追いかけて来る。
「怒った?」
「別に怒ってはないけど……。あー、でも、写真、SNSにはあげないでね」
「あげないよ。俺専用だから」
足を止めて振り返ると、葛西は猫でも愛でるような蕩けきった表情を浮かべていた。
やっぱり変な奴だ。
無言でずんずん坂を下っていると、隣まで走ってきた葛西がスマホを突き出す。
「熊谷、ライン交換しよう」
「いいけど」
ポケットからスマホを取り出すと、QRコードを表示して連絡先を交換した。
坂を下りきって駅前までやって来ると、俺は駅の反対側を指さす。
「じゃあ、俺、家あっちだから」
電車通学ではないことを伝えると、葛西はきゅっと口を結んで視線を落とした。微妙な間があった後、葛西は顔を上げた。
「じゃあね、熊谷、また明日」
軽く手を挙げてから、葛西は駅の階段を登った。あっさりと去って行く背中を、俺はぼんやりと眺めていた。
「また、明日……」
そう返事をしたものの、俺の声は駅前の雑踏に埋もれた。
◇
自宅のマンションに帰宅して、制服からスウェットに着替える。ブレザーのポケットからスマホを取り出すと、葛西からラインがきていることに気付いた。駅からマンションまでの移動中はスマホを弄っていなかったから、気付くのが遅くなってしまった。急いでトーク画面を開くと、あっさりとしたメッセージが目に飛び込んだ。
[明日も一緒に帰ろう]
まさか連日で誘いを受けるとは思わなかった。驚きはしたものの、断る理由はない。俺はベッドに腰掛けながら、ぽちぽちと返事を打った。
[いいけど]
送信してから、素っ気なさすぎたかと反省した。だけど送ってしまったものは仕方がない。トーク画面を閉じようとすると、すぐに既読がついて、返事が届いた。
[楽しみにしてる]
なんだそれ? 一緒に帰るだけなのに?
訳が分からなかったが、それ以上なんと返していいのか分からなくて、ラインを閉じた。ひとつのアプリを閉じると、習性とも言えるような流れで別のアプリを開く。
インスタを開くと、先ほど撮影した夕空の写真を選択した。テキスト欄に「#キリトリセカイ」とタグを添えてから、投稿ボタンを押す。すると、三十秒足らずで「いいね」がついた。
「はっや……」
反応してくれたのは、saikaさんだ。驚きつつも、反応してもらえたのはやっぱり嬉しい。遠くにいながらも、あの景色を分かち合えた気分ような気がした。にしし、と頬を緩ませながら、俺はベッドに倒れ込んだ。
口数は多くないが、陽キャグループの中ではツッコミ役を担っている。その言葉選びが絶妙で、周囲からも気に入られていた。
成績も優秀。本人はテストの点数をひけらかすタイプではないが、一学期の成績票が配られた時に陽キャグループで「三位、三位」と騒がれていた。
イケメンの上に、コミュ力も高く、頭もいい。天は彼に二物も三物も与え過ぎだと思う。
葛西は男の俺から見ても格好良い。落ち着きがあって、何事にも動じなくて、冷静に物事を対処できる。自分もあんな性格だったらなぁと密かに憧れていた。
そんな葛西から、一緒に帰ろうと誘われた。なぜだ?
これまで一緒に帰ったことなんてないし、教室でもほとんど話したことがない。何なら昨日初めて話したくらいだ。それなのに、誘ってくる意味が分からなかった。
遠慮しようにも、腕を掴まれて逃げられない。じっとこちらを見つめる眼差しからは、逃がさないという意思すら感じさせた。
葛西の顔と掴まれた腕を交互に見ていると、真剣な眼差しで尋ねられる。
「迷惑? それとも他と約束してる?」
「いや……迷惑じゃないし、約束もしていないけど……」
「じゃあ一緒に帰ろう」
拒絶しているわけではないと分かると、有無を言わさず連行される。教室の後方のドアに辿り着くまでの数秒間で、クラスメイトからの注目が集まった。そんな反応になるのも無理はない。
手を引かれながら、さりげなく葛西を観察する。学校指定の白シャツの上からグレーのカーディガンを羽織っている。制服を適度に着崩しているせいか垢抜けた印象だった。ストレートの黒髪もワックスで動きを付けてアレンジしている。昨日チラッと見た限り、スニーカーも格好良かった。もとの顔が良いだけでなく、お洒落にも気遣っているのだから、モテるのは当然だ。
対する俺は至って平凡。学校指定の制服を校則通りに着ているだけで、お洒落とは無縁だ。髪型も無難な黒髪ショートで、ワックスなんて使ったことがない。童顔なせいで、時々中学生に間違えられることもコンプレックスだった。
葛西と俺とでは、キャラもビジュも釣り合っていない。セットでいるのは傍から見てもおかしかった。クラスメイトからの好奇の視線に耐え切れず、俺は俯きながら教室を出た。
◇
「あの、そろそろ腕を離してもらえると……」
正門を出てから恐る恐る申し出る。目立つし恥ずかしいから、そろそろやめていただきたい。すると葛西はあっさり解放してくれた。
「ああ、悪い」
なんだ。すぐに離してくれるなら、もっと早く言えば良かった。
掴まれていた腕をさすりながら、葛西の隣を歩く。チラッと横目で伺うと、綺麗な顔立ちをしているなぁと感じた。今まではあまり意識したことがなかったけど背も高い。167cmの俺とは握りこぶし一つ分は差がありそうだ。横目でまじまじと観察していると、葛西がこちらに視線を向ける。
「なに?」
「いや、なんでも……」
会話終了。葛西は無表情のまま視線を前方に戻す。
いやホント、なんで一緒に帰ろうなんて誘った?
そっちから誘ったんだったら、もっと会話を盛り上げようという気概があってもいいだろう。何かしら話題を振ってくれたら、俺だってちゃんと乗っかる。それくらいのコミュ力は持ち合わせているはずだ。
それなのに葛西は、表情一つ変えず、無言で隣を歩き続けている。ここまで興味を示されていないと、俺と一緒に帰っていること自体が罰ゲームなんじゃないかと邪推してしまった。
……無くはない話だ。罰ゲーム説が濃厚になると、ずーんと気分が沈んでいく。
なんだ、俺に興味があるわけじゃないのか。納得しつつも、どこかがっかりしている自分がいた。
無言のまま駅まで続く下り坂を歩く。俺達の通う高校は高台に建っているため、通学時には曲がりくねった急こう配を上り下りしなければならない。おかげで足腰はかなり鍛えられた。
大半の生徒は坂の上り下りを「だるい」と言っているが、悪いことばかりでもない。ヘアピンカーブをぐるっと回ったところで、視界が開けた場所にやってくる。そこで俺は足を止めた。
「あっ」
坂の下には、ミニチュア模型のように市街地が広がっている。昔ながらの住宅街も、真新しい高層マンションも、大型商業施設のロゴも、すべてが見渡せた。この景色を見ると、いつも清々しい気分になる。
それに今の時間帯は最高だ。空の色が、綺麗なグラデーションになっている。遠くにある山の頂上は橙色に染まっていて、そこから視線を上げると黄色、桃色、紫色、紺色に移り変わっていった。
日没後の数十分間に見られる空は、一日の中でもっとも美しい。帰り道に運よくこの景色を見られると、得した気分になった。
綺麗な景色を前にすると、写真を撮りたくなってくる。ブレザーのポケットからスマホを取り出そうとしたものの、隣に葛西がいることを思い出した。
人といる時に撮影を始めたら失礼かもしれない。やめておこうと諦めた時、思いがけない言葉が飛んできた。
「いいよ、撮っても」
顔を上げて葛西の顔を見る。まるで俺が写真を撮りたがっているのを見越したような発言だ。なんだこいつ、エスパーなのか?
疑問は残るものの、お許しを貰えたのなら遠慮なく撮らせてもらおう。スマホを取り出すと、夕空と市街地を画角に収めた。
――カシャ
一枚撮影してから、そそくさとスマホをポケットにしまう。隣から視線が突き刺さる。気まずさを振り払うように、俺はたどたどしく雑談を始めた。
「日の出前とか日の入り後の空が薄明るい時間帯のことを、マジックアワーって言うんだよ。空気の澄んだ晴れた日には空がグラデーションになるんだけど、昼と夜が溶け合ったみたいな感じが俺は結構好きで……」
話しているだけなのに、顔がどんどん熱くなる。急にこんな話をしたら、おかしな奴だと思われるだろうか。失敗したなぁと思いながら俯いていると、穏やかな声が届く。
「やっぱり好きだな」
顔を上げると、葛西は口元を緩めて微笑んでいた。
教室では滅多に笑わない葛西が、笑っている。俺は大きく目を見開きながら、その顔を目に焼き付けていた。
俺が凝視していることに気付くと、葛西ははっと我に返る。頭を掻きながら、たどたどしく言葉を続けた。
「なんだっけ……。マジックアワー? 俺も好きだなって」
「え? ああ、へぇー、そうなんだー……」
驚き過ぎて、さっき話していたことすら忘れてしまった。ふわふわした気持ちのまま立ち尽くしていると、葛西はポケットからスマホを取り出す。
「俺も撮って良い?」
「ああ、うん、どうぞ」
写真に写り込まないように一歩横にズレたものの、葛西はスマホのレンズをこちらに向ける。
――カシャ。
「え? 今、俺を撮らなかった?」
「うん、撮った」
「なんで?」
「……綺麗だったから」
一瞬の間があった後、葛西は視線を落としながら小さな声で白状した。
「変なの……」
訳が分からないまま、俺はスマホをポケットに突っ込んで歩き出した。早足で坂を下っていると、葛西が追いかけて来る。
「怒った?」
「別に怒ってはないけど……。あー、でも、写真、SNSにはあげないでね」
「あげないよ。俺専用だから」
足を止めて振り返ると、葛西は猫でも愛でるような蕩けきった表情を浮かべていた。
やっぱり変な奴だ。
無言でずんずん坂を下っていると、隣まで走ってきた葛西がスマホを突き出す。
「熊谷、ライン交換しよう」
「いいけど」
ポケットからスマホを取り出すと、QRコードを表示して連絡先を交換した。
坂を下りきって駅前までやって来ると、俺は駅の反対側を指さす。
「じゃあ、俺、家あっちだから」
電車通学ではないことを伝えると、葛西はきゅっと口を結んで視線を落とした。微妙な間があった後、葛西は顔を上げた。
「じゃあね、熊谷、また明日」
軽く手を挙げてから、葛西は駅の階段を登った。あっさりと去って行く背中を、俺はぼんやりと眺めていた。
「また、明日……」
そう返事をしたものの、俺の声は駅前の雑踏に埋もれた。
◇
自宅のマンションに帰宅して、制服からスウェットに着替える。ブレザーのポケットからスマホを取り出すと、葛西からラインがきていることに気付いた。駅からマンションまでの移動中はスマホを弄っていなかったから、気付くのが遅くなってしまった。急いでトーク画面を開くと、あっさりとしたメッセージが目に飛び込んだ。
[明日も一緒に帰ろう]
まさか連日で誘いを受けるとは思わなかった。驚きはしたものの、断る理由はない。俺はベッドに腰掛けながら、ぽちぽちと返事を打った。
[いいけど]
送信してから、素っ気なさすぎたかと反省した。だけど送ってしまったものは仕方がない。トーク画面を閉じようとすると、すぐに既読がついて、返事が届いた。
[楽しみにしてる]
なんだそれ? 一緒に帰るだけなのに?
訳が分からなかったが、それ以上なんと返していいのか分からなくて、ラインを閉じた。ひとつのアプリを閉じると、習性とも言えるような流れで別のアプリを開く。
インスタを開くと、先ほど撮影した夕空の写真を選択した。テキスト欄に「#キリトリセカイ」とタグを添えてから、投稿ボタンを押す。すると、三十秒足らずで「いいね」がついた。
「はっや……」
反応してくれたのは、saikaさんだ。驚きつつも、反応してもらえたのはやっぱり嬉しい。遠くにいながらも、あの景色を分かち合えた気分ような気がした。にしし、と頬を緩ませながら、俺はベッドに倒れ込んだ。