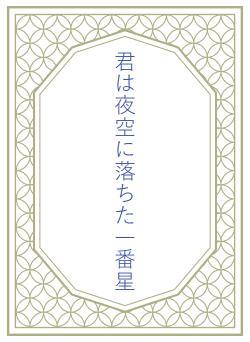(僕にとって、プロムは良き存在で、良き相手で、そして何より尊い存在だった)
そんな事を考えながら、ある人物は静かに目を閉じ、大好きな家族の事を考える。
しかし、そんな事を考えている余裕など全くないのだ。
「プロム!お前との婚約を破棄させ――」
「……王子、大変申し訳ございませんが僕の妹はただいま体調不良のため、家におりますが……もう一度、そしてはっきりと言ってくれませんか?」
「うっ……ア、アレク……」
アレクと呼ばれた青年の姿を見た王太子である第二王子、ジュディスは青ざめた顔をしながら辺りを見回し、お目当ての少女の姿が見つからないと、青い顔がますます青く染まっていく。
その姿を見ながら、アレクと呼ばれた青年はクスっと笑みを零しながら、睨みつけるようにジュディスを見た後、ジュディスの隣にいる女性に視線を向ける。
(確か、聖女候補の伯爵家の女……確か名前は――)
「王子、お聞きいたしますが、まさか婚約者がいるにも関わらず浮気なんてしておりませんよね?しかも浮気相手は聖女候補の貴族の女性ではありませんか……僕の可愛らしい妹を放っておいて?」
「う、五月蠅い!五月蠅い!そ、そもそも彼女から聞いたぞ!なんでもお前の妹は勤めを怠り、サリーナに仕事を全て押しつけていたらしいではないか!それをどう証言するのだ!」
「へぇ、そんな事が……」
(んなわけねーだろうが)
震えながら必死に恐怖を隠すようにしながら答えるバカな王子と、その隣でニヤニヤと笑いながらこちらに視線を向けている聖女候補の女性。明らかにバカにしているような態度に苛立ちを覚えさせられる。
(まぁ、婚約破棄になった方が、こちらとしても都合がいいのだが……)
頭を悩ませるようにしながら、静かにため息を吐く。
そもそも王太子との婚約も、妹が王宮を訪れた際に目の前の王太子が一目惚れをしたからと言う話で出来てしまった婚約だ。
もちろん家族一同反対したのだが、今後の事を考えて婚約を成立させたのである――結果、このような事態になってしまったので、責任を取ってもらといけないのだが。
しかも、今回、アレクがいる場所は国王主催の舞踏会だ。
その舞踏会でまさか第二王子であるジュディスが婚約破棄の為に公の場で叫び、そしてアレクの妹であるプロムを陥れようとしている。
それだけ考えると腹が立って仕方がない。
(……これは、僕にとっては宣戦布告と言う事だろうか?)
ニヤっと悪人のような笑みを見せるアレクの姿を見たジュディスは再度、恐怖を感じたのか震えている。しかし、話を終わらせる気はないらしい。
「と、とにかく!聖女の仕事を怠り、可愛らしいサリーナを虐める聖女など聖女ではない!お前の妹は聖女と言う名を剥奪し、そして追放にする!アレク、それで良いな!」
「……まぁ、僕としては別に構いません。妹の婚約破棄、追放、全て承りましょう。しかし、本当にそれでよいのですね、王子?」
「ああ、構わん!」
「――では、皆様申し訳ございませんがこのまま失礼いたします」
アレクは笑みを浮かべたまま、静かに舞台から離れていく。
周りが静寂している中で、ジュディスとサリーナの二人が二人の世界に入っている事など、全く興味もないかのように。
(とりあえず、教会に行かないといけないな)
アレクは教会にいる家族を迎えに行く為、すぐに馬車を呼びつけ、向かうのだった。
▽ ▽ ▽
「プロム、この国の為に祈るはもうよせ」
「え、ど、どうしたのですかね……いえ、兄さま?めちゃくちゃ機嫌悪そうな顔をして!」
「機嫌が悪いんだからこんな顔をしているんだ……こんばんは、良い夜ですね、大司教様」
「どうかなさいましたかアレク様!す、すごく不機嫌な顔を、まるでこの国を滅ぼしかねんぐらいの顔をしているではありませんか?」
「出来ればしたいです。とりあえずあの王子、ぶん殴りたい」
教会の中に入ると、幼い姿をした小さな少年がアレクの顔を見て驚いた顔をしている。その隣にいる大司教と呼ばれている老人も。
中に入ると同時に、近くにある椅子に座り、そのまま指先を鳴らす。
指先を鳴らした瞬間、突然アレクの体を氷のようなモノを包み込み、そして砕けた瞬間、アレクと言う青年の姿はなく、アレクと同じ服装をした一人の女性の姿が現れる。
女性は舌打ちをしながら話を続ける。
「舞踏会に出てみると、まさかの公の場で婚約破棄と来た!ああ、笑える!」
「……姉さま、一応今は淑女なのですから、そのように豪快に笑ってはいけません」
「だっておかしいではないかプロム!幼い私の姿に惚れて婚約をしたはずなのに、二年程顔を合わせなければ、どこぞの聖女候補の伯爵令嬢に乗り換えたと来た!」
「え、聖女候補の伯爵令嬢ですか……名前を知っておりますか?」
「ああ、サリーナと言っていたなぁ……まぁ、もう何者かはどうでも良いので聞く気にもなれんが」
「……サリーナ様、ですね。確かに今年聖女候補を何名か見つけましたが……その中のお一人かどうか、確認してみますね」
大司教の老人が笑顔でそのように言いながら、そのまま後ろに下がってしまう。
残された二人の少年と女性。
少年は再度ため息を吐きながら、そのまま近づき、女性の隣に座る。
「……えっと、姉さま。それならば、私はもう、この国の為にお祈りをしなくても良いと言う事なのでしょうか?」
「お祈りもお勤めの一つ、だったんだろう。するなするな……ついでに国を囲っている結界の一部のお前のだろう?もう壊してしまえ」
「姉さま、容赦ないなぁ……」
「当たり前だ。僕はお前の事を一番愛し、守らなければならないんだ……お前が、『身代わり』になった時から」
女性――アレクがそのように呟き、唇を噛みしめた後、そのまま少年を優しく抱きしめる。
微かに感じる温もりに、少年――プロムは嬉しそうに笑った。
アレクの性別は男性ではなく、女性だ。ただ、それにはちゃんとした理由がある。
それは、数年前、突然『光魔法』と言うモノを覚醒させた人物がいた――それは、アレクではなく、弟であるプロムだった。
光魔法は本来癒しや守りを中心とした力であり、その力を扱える存在はこの世界では『聖女』と言われている女性にしか宿せないとこの国では言われている。
『聖女』としての力を持つ存在はこの国にも何人もいたのだが、その中で強い力を持っていたのは、この国では何故か弟であるプロムだった。
何故弟にそのような力が存在し、覚醒してしまったのか、家族はわからなかった。数日考えた結果、アレクが『聖女プロム』として弟の名を借りて名乗り、そして弟は影ながら力を使ってもらおうと言う形になった。
しかし、家族にはもう一つ、難点があった。
アレクは女性らしくない女性であったのである。
彼女の祖父は勇敢な騎士だった。
その祖父に憧れてしまったアレクは祖父の後をついて回るようになり、一緒に狩りをしたり、冒険したりなどなど――それを止める人たちもいなかったので、アレクは男らしく育ってしまったのである。
そんな彼女に女らしい、『聖女』など勤まるわけがない。
アレクの弟であるプロムは一番それを心配したのだ。
「……姉さま、ちゃんと出来る?大丈夫?」
「う、うーん……とりあえず、しゃべらない人形のようにしていれば大丈夫だろうか?」
「まぁ、姉さま顔は良いからね。顔は」
プロムの言う通り、アレクの顔は母親譲りの綺麗な顔立ちをしていたので、何とか誤魔化す事に成功した。
数年ほど、聖女として表舞台に立つ事もあった。
しかし、アレクはそれでも我慢出来なかった。
十六歳になろうとしている時、アレクに待ち受けていたのは三年間の学園生活である。もちろんアレクの事を聖女として知っている者も多数居る――暴れん坊のアレクが我慢出来るはずがない。
そこで考えたのが、性別を入れ替える魔法である。
お抱えの魔道具専門店で性別を入れ替える魔道具を売っていると父親から情報をもらったので即購入。そして、アレクは『男性』として、そして聖女の双子の兄として学園で三年間過ごすことが出来たのである。
同時に、プロムは完全に表舞台から姿を消してしまった。
アレクはそれが一番嫌だった。
父も母も、そしてアレクも、そのような扱いをする事がとても嫌だったのだが、プロムは笑いながらそれを受け入れた。
「僕も家族は大好きだから。家族を守るためにこの力をこの国に捧げても平気だよ」
そのように笑った弟の姿を、アレクは今でも忘れる事が出来ない。
まるで、『生贄』のように、プロムはアレクの代わりとして、聖女としての力を発揮し、全ての人々を助け、救う事を。
しかし、今日でそれも全てなくなった。
王族の言う事は絶対なこの国にはもう用はない。聖女の役目も終わりだ。
アレクは弟の頭を優しく撫でながら、考える。
「問題はこれからなんだよなぁ……とりあえずおじい様の辺境に行くか、それとも行った事のない国に行くか……」
「どうせならカルスラーン様の所に行くのはどうですか?姉さま」
「…………カルスラーンねぇ」
プロムは嬉しそうにそのように言いながら答えるが、アレクはまさかその名が出てくるとは思わなかったので、一瞬言葉が詰まりそうになったのだが、とりあえず飲み込むことにした。
カルスラーン・アルフィンーー一年だけ、アレクが通っていた学園に留学と言う形で現れた、隣国の第一王子。
アレクにとって、カルスラーンと言う人物は正直苦手であった。
苦手と同時に、アレクの姿を見て一目散に『彼』ではなく、『彼女』に気づいた人物なのである。
男の姿をしているアレクに向かってこのような言葉を口にした。
「お前、どうして女なのに男の姿をしてるんだ?すごい魔法だな」
「は――」
真顔でそのように言ってきたあの男――カルスラーン・アルフィンの姿を絶対に忘れる事が出来ない。
アレクが男性の姿になっているのには、ちゃんとした理由があるからこそ、周りに知られては困る。
その時は周りに人が居なかった為何とかばれる事はしなかったのだが、ばれてしまったのは仕方がないため、アレクはカルスラーンに対し、自分は聖女と呼ばれているが聖女ではなく、聖女の仕事をしているのはプロムと言う弟だと言う事。ごく一部しか知らない話をカルスラーンに話すと、カルスラーンは面白い顔をしながら、アレクに告げた。
「なんだそれ、面白いな……で、お前、もし聖女ではなくなったらどうなるんだ?」
「聖女ではなくなる……ああ、大体予想している。クソ王子の女の件か」
「ぶっ……く、クソ……口悪いなお前」
「昔からこういう性格なんだ……まぁ、こっちとしては好都合だが、プロムが悲しむなぁ……」
「……弟、大好きなんだな」
「弟は僕の大切な家族だからな」
――そして、僕の為に影ながら犠牲になってしまっている存在でもある。
そのような発言は流石に言えなかった。
唇を噛みしめるようにしながらアレクは空を静かに見上げながら、呟く。
「……このまま婚約破棄になれば、この国を守るモノなんてないから、弟を……家族を連れて国を出ていきたいんだがなァ」
「出ていけばいいじゃないか」
「そんな事が出来たら苦労しないさ」
ハッと笑うようにしながら答えるアレクの顔を見たカルスラーンは、ふと何かを思いついたかのように突然笑顔を見せる。
その笑顔がちょっと気持ち悪く、思わず嫌そうな顔をしながら引いてしまうと、カルスラーンはとんでもない事を言い出した。
「じゃあ、もし婚約破棄になって、聖女でなくなったら俺のモノになってくれるか?」
「…………はい?」
突然言い出したカルスラーンの言葉に呆然としながらアレクが視線を向けると、アレクは笑いながら話を続ける。
「だって、婚約破棄をされて、聖女でなくなるなら、もう弟を守る必要はないだろう?だったら俺の国に来て俺の婚約者になって、妻になってくれ。王位は大丈夫だ。国王になるのはうちの兄貴だから」
「いや、だから……そもそも僕とお前は出会ってまだ数日だし、お前の事は知らないし――」
「一目惚れってあるんだなぁ~」
「ま、マジでいっているのか、おまえ……」
「で、どうするアレク嬢?受けるか受けないか?」
「……とりあえず、本当にそのようになったら考えさえてほしい……」
その時、まさかそのような発言を言われるとは知らず――それから一年過ぎ、カルスラーンは国に戻ってしまったが、一応文通としての交流は続いている。恋人ではなく、友人として。
一応弟にはそのような出来事を話した事はあり、本人は乗り気らしい。
プロムはカルスラーンに会った事はないのだが、半年前から手紙を書くようになったので、アレクと同様文通相手になっている。
話は戻るが、婚約破棄され、そして聖女も剥奪された。
これからどうするかは実の所まだ考えていない――プロムの頭を撫でる。
「姉さま?」
「……お前は、僕が示した選択に後悔しない?」
「なぜ後悔しないといけないんですか?」
「だって……」
「僕は姉さまが行く道ならどんな道で行きます!だって、これからもずっとそばに居てくれるのでしょう?」
「プロム……本当、愛い奴め!」
フフっと笑いながらプロムの体を強く抱きしめるようにしながら、優しく頭を撫でる。プロムも嬉しそうに笑いながら、アレクの体を強く抱きしめた。
大好きな弟の事を考えながら、アレクは頭の中でこれからの事を考える。
(……私が奴の婚約者になれば、プロムも影ではなく、光でのびのびと暮らしていけるのだろうか?)
そんな事を考えながら、アレクはカルスラーンに連絡をしなければならないなと思いながら、弟の体を強く抱きしめるのだった。
▽ ▽ ▽
「よう、アレク嬢!久しぶりだな!」
「は……」
プロムと一緒に教会に泊まった後、家に戻らなければと男の姿にチェンジしたアレクは、教会から出ようとした瞬間、笑顔で挨拶をしてきたカルスラーンの姿に驚いた。
まだ連絡も何もしていないのに、なぜ目の前に隣国の王子が居るのか、理解が出来ない。
呆然としてその場に立っているアレクの姿に、カルスラーンは不思議そうな顔をしながら首を傾げる。
「なんだ、そのような顔をして?もしかして、俺が目の前にいるのが予想外だったのか?」
「…………ああ、予想外すぎて頭が痛くてたまらん。カルスラーン、なぜ目の前にお前が居る?」
「なぜって、迎えに来たんだ。だって、婚約破棄され、聖女剥奪されたんだろう?」
「なぜ知っているんだお前は!」
どうしてその情報を知っているのか、驚いたアレクに対し、カルスラーンは軽く口笛を吹くと、突然カルスラーンの背後に黒服の小さい少女が立っており、膝をついている。
呆然としているアレクに対し、カルスラーンは話を続ける。
「俺が国に帰った後、お前とお前の弟の近くに密偵のような奴を一人置いておいた。気づかれないようにしていたんだが……時々目が合っていたって言ってたぞ」
「……誰かに見られているって言う感じはしていたんだが、あのクソ王子の手先かなぁと思ってたんだよ」
「じゃあ見当違いだな。うちの手先だ」
「……それで、情報を与えて、魔道具を使ってこちらに来たと言うワケか」
「ああ、魔力を溜めるのに一週間はかかるがな。ちょうど満タンだったんで、来てみた」
笑いながらそのように答えるカルスラーンの姿は相変わらず変わらない。一年前と同じ顔をしている。
久々の数少ない友人に安堵しながら、アレクは静かに息を吐く。
そんな彼女の息を吐く姿を見ながら、カルスラーンは笑顔を絶やさず聞いてみる。
「で、考えたか?」
「考えるって?」
「俺のモノになるかって事」
「……」
その発言を聞いた瞬間、一気に重みが増したような感覚だった。
そもそも婚約破棄をされている身であり、聖女としての力があるのは自分ではなく弟。その弟の力を犠牲にして自分は聖女としての身代わりの『プロム』と言う弟の名前を借りた女性を作っただけだ。
『アレク』に戻ってしまったら、女らしさの欠片のない、口の悪い、暴力的の女に戻る事になる。カルスラーンはそれでも良いのだろうか?
「……カルスラーン、一つ聞いても良いか?」
「ん?」
「――お前が僕を求めているのは、僕の弟の力のためか?弟の『力』が欲しいから、僕を求めるのか?」
アレクを一緒に国に連れていくと言う事は、当然弟のプロムも一緒に行くことになる。
同時に、カルスラーンの国はある意味、『聖女』と言う存在を手に入れることになる。そうなればその国も安泰なのかもしれない。
カルスラーンが求めるのは、自分ではなく、弟だとしたら、自分はおまけと言う存在になる。
何も言わずに見つめているアレクに対し、カルスラーンはそのまま首を傾げるようにしながら答えた。
「アレク嬢、何を言っているんだ?」
「いや、僕は正論を――」
「一目惚れってあの時言ったではないか?」
「…………」
「姉さま、カルスラーン様は本心を言っていますよ」
何をわけのわからぬ事を言っているのだろうかと言う顔をしながら、カルスラーンはアレクに視線を向けている。
驚いた顔をしているアレクに対し、カルスラーンは本当にワケのわからない顔をしている。
そんな二人のやり取りを、プロムは楽しそうに見つめながら呟いたのだった。
アレクはしばらく頭を整理した後、そのまま額を抑えるようにしながら呟く。
「……一目惚れ、本当にあるんだな?」
「あるに決まっているだろう!で、アレク嬢、どうする?婚約破棄されていく場所はあるのか?」
「……」
家族は多分既にこの国を出る準備をしているであろう。文は寝る前に魔術を使って出している。
行く先はまだ決めていなかったのだが――アレクはプロムに視線を向けると、弟は両手を握りしめ、ガッツポーズを見せる。
「……カルスラーン、約束をしてほしい」
「なんだ、言ってみろ?」
「必ずプロムの安全は確保してほしい。もし、『聖女』と言う存在がプロムだとバレてしまったら……プロムは自分で守れるぐらいの力はない。だから、僕が『聖女』として人前に出ていた。僕なら、自分で守れるぐらいの力はあるし、鍛えている」
「もちろんそのつもりだ!父上や母上には既に了承済みだ!」
「……それと、一目惚れって言う話だが、僕はその言葉を信頼していない」
「え、な、なぜだ!?」
「あのクソ王子は僕に一目惚れをしたと言う事で、婚約者になったんだ……裏切られるのは嫌なんでね」
鼻で笑うようにして答えるアレクの姿を見ても、カルスラーンの表情は変わらなかった。
そのまま手を握りしめ、カルスラーンは笑顔で答える。
「何を言っているのだアレク嬢!」
「うわっ!ちょ……」
「俺はあなたのそういう強気の所も好きだし、女の姿の時も可憐で美しい……俺はそういうところに惚れたのだ。もっと、あなたの事を知りたくなった!」
「な……」
「だから父上と母上に無理いって色々な事もした!」
「……色々な事の内容はちょっと聞きたくないな」
一体どんなことをしたのか、正直それは聞きたくない。
しかし、カルスラーンは彼女の肩を強くつかみ、引き寄せるような形をとる。
耳元で囁くように。
「――俺は欲しいと思ったモノがあれば、どんな手を使ってでも手に入れたい。例えば……女を使ったり、とか」
「……ッ!」
小さな囁きで聞こえた言葉に驚いたアレクは視線を向けると、上機嫌な顔でアレクを見ているカルスラーンの姿が。
同時に、どうやら自分たちはカルスラーンに踊らされていたのだろうと言う事を理解したのである。
「……サリーナと言う女はお前の手引きした女か?」
「はは!何のことだが!」
「え、そうなんですか!?カルスラーン様!」
笑いながら誤魔化している様子が見られるが、どうやらサリーナを使ってあのバカ王子を落としたのはカルスラーンの手引きらしい。
呆れて何も言えなかった事と、そして自分がそれに見抜けなかったことに呆れながら、アレクはため息を吐く。
同時に隣にいる男は食えない男だと自覚しながら――寒気を覚えた。
「……やっぱり、一緒に行くのやめようかな?」
「ははは!アレク嬢、あきらめよ!」
「……もしかして僕たち、いけない人に捕まってしまったんでしょうか、姉さま」
「すまんプロム……ふがいない姉で……」
「別に良いんですけど……それより姉さま、女性の姿に戻りませんか?」
どこか恥ずかしそうに、頬を赤く染めながら答えるプロムに対し、アレクは首を傾げる。
どうしてそのような事を言うのだろうかと思った瞬間、自分が女性ではなく、男性の姿になっている事を思い出し、顔を真っ赤に染める。
続けてプロムが言った。
「……なんか、男同士でそのような距離感だと、イケナイ関係のように見えますよ……ね」
プロムの言葉通り、今の距離感だと明らかにイケナイ関係のように見える。
「ん?別に俺は構わないぞ?どんな姿であれ、アレク嬢はアレク嬢だ!」
「……いや、誰もいないけど、周りの視線が気になりそうなので、プロムの提案にのる」
甲高い声が響き渡りそうな事を想像しながら、アレクは女性の姿に戻り、息を吸う。
同時に、これからの未来が少しだけ心配なるのであった。
後日、アレクとプロムは家族と共に隣国へ。
隣国では、プロムは張り切って『聖女』としての仕事をしており、同時に姉の為に、そしてカルスラーンの為にと強い結界を国中に貼ってくれた為、隣国で魔獣などの出現などはなくなった。
反対にアレク達が去ってしまった国では、『聖女』の結界は解かれ、魔獣たちが襲ってくるようになる。
全ては王太子であるジュディスに責任が向き、彼が信頼していたサリーナはいつの間にか何処かへ行ってしまい、残されたジュディスはそのまま胸を患うようになり、部屋に引きこもるようになり、そのままその国は数年後、国が亡びる事になり、ジュディス達は民の反乱により、命を落としていったのだと言う事を風の噂で聞いた。
現在、アレクは前の国と変わらない一日を過ごしている。
プロムは相変わらず表舞台に出る事はないが、『聖女』として影ながら国を支えてくれている。それと同時に、『聖女』と言う事を隠しながら、隣国の学園に通わせてもらえる事になった。
最近その学園で気になる相手がいる、と言う事を嬉しそうに話してくれている。
そしてアレクは――。
「相変わらずだな、俺の可愛らしい奥さんは……いや、かっこいい旦那様と言うべきか?」
「やめてくれ、カルスラーン」
大剣を片手に握りしめながら、足元には瀕死したドラゴンが転がっている。
先ほどカルスラーンと協力しながら対峙したドラゴンであり、そのドラゴンの上に乗りながら嬉しそうにしている男性の姿をしたアレク。
アレクのうれしそうな表情を見ながら、カルスラーンも嬉しそうに笑っていた。
ドラゴンから降りた後、男の姿から女の姿に戻り、生き生きとした表情を見せながら話す。
「まさかドラゴンを狩れる事が出来るなんて、夢みたいだ!おじいさまがいつも言っていたお話と同じ事が出来るとは……本当にありがとうカルスラーン!」
「いやはや、まさかここまで喜んでもらえるとは……向こうにいるときよりとても良い笑顔をしているぞ、アレク」
「まぁ、向こうでは顔を作っていたからな……さて、次は何をしよう!そういえば近くにゴブリンの巣があると聞いていたな……よし、次はゴブリン退治でもするかカルスラーン!」
「ああ、それも構わないが、奥さん」
興奮している顔を抑えきれないかのようにしているアレクの姿を見ながら、カルスラーンは笑顔で彼女の肩に手を置く。
「――そろそろ夫婦の時間も作るのはどうだろうか?俺はちょっとさみしくて泣いてしまいそうだ」
寂しそうな顔をしながらそのように呟くカルスラーンの姿を見たアレクの表情は固まる。
確かにここ最近魔獣退治ばかりしていたため、そのような時間をとっていなかったような気がする。
それと同時に、夫婦の時間と言うものは慣れないのでアレクはあまり好きではなかった。
少しだけ頬を染めながら、アレクは呟く。
「…………そ、それならば、そ、その……一緒にお茶を飲んでのんびりするのは、どうだろうか?」
「うん!よい!それならば善は急げだ!」
「うわっ!?」
その言葉を聞いた瞬間、カルスラーンはアレクの体を抱き上げ、素早い動きで走り出す。目指す先は自分たちが暮らしている屋敷だ。
楽しそうに笑うカルスラーンの姿を見たアレクは聞こえないように、小声で呟く。
「……本当、お前には感謝しかないよ、カルスラーン」
「ん、何か言ったか俺の奥さん?」
「いいや、なんでもないよ、僕の旦那様」
カルスラーンの言葉に対し、アレクは笑いながら返事をしたのだった。