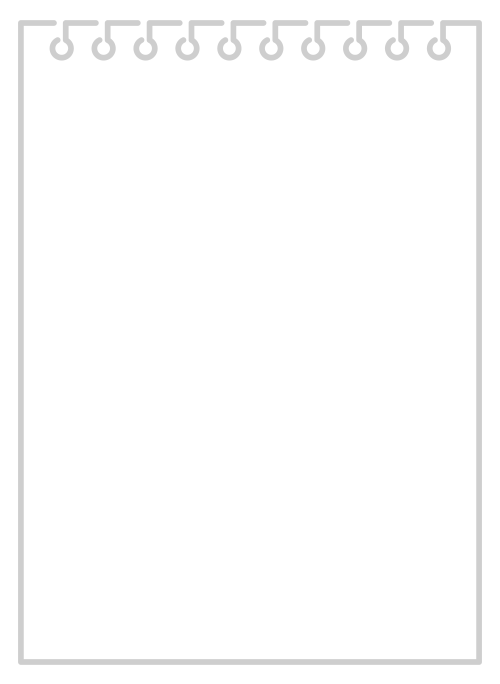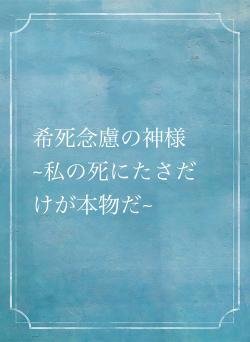自己中心の塊みたいな彼女――ハルのことが、ずっと苦手だった。
時間にルーズで、なくし物が多くて、社会性の欠片もない。そんな彼女との同棲は大学時代に始まり、もう十年目になる。
きっかけは、「お願い、今から泊めて!」という切実な言葉だった。泣き縋るような声音に抗えなかった記憶がある。
あの時は確か、深夜三時を回っていた。私は枕もとのスマホから発される耳障りなコール音に、気分の悪い目覚めを経験した。
暗い部屋で淡白な光を放つ画面には、「ハル」の名前。
うんざりしながら、いやいや緊急事態かもしれないじゃないか、と無理に自分を納得させてから電話に出た。
「あの、もしもし?」
「やっと出たー! 遅いよ、もう」
掴みどころのない、ふわふわした甘い声。
どうしてこちらが責められているのかは全くもって分からない。
「ねえ、今の時間分かってる? 私になんの用?」
一瞬間が空く。通話越しに車の走行音が響く。それで、ハルはこんな夜中にもかかわらず、外にいるのだと気づく。
「ちょっと返事してよ! まさか馬鹿なこと考えてないよね、ねえ?」
「志乃さん……」
ハルが妙に深刻そうな調子で私を呼ぶ。
「お願い、今から泊めて!」
続けて、彼女の口から紡がれたのは、何ともふざけた要求だった。
途端、私に連絡を寄越してきたのはそういうことか、と合点がいった。この付近に一人暮らしをしている人間は、学内でも限られている。
「そんな急に言われても、私だって困る。とりあえず事情を説明して」
私が強めの口調で返すと、ハルは怒られた子どもみたいに「うん、そだよね」と、あからさまに落ち込んで見せる。計算し尽くされたやり口だ。
「家、なくなっちゃって……志乃さんしか頼れないの」
「はあ? なくなった?」
訳が分からずに聞き返す。
長い話になりそうな予感があって、私は眠たい目を擦りながら体を起こし、布団の上で胡座をかく。
「彼氏と喧嘩して、家から追いだされちゃった」
「こんな夜中に? でも、そんなの一時的なもんでしょ?」
ハルは社会人の年上男性と交際していて、少し前に同棲を始めていた。あれだけ愛の深さを語っておいてこのざまかよ。
「とりあえず、泊めてってば! 志乃さんはあたしが路上で野垂れ死んでもいいんだ?」
「別にいいけど。なにを大袈裟な」
「嘘だよ! ぜったい後悔するんだから!」
「はあ……」
「可愛い友達の頼みでしょ? 今晩だけでいいよ、ね?」
私はため息を吐いた。通話越しにもちゃんと聞こえるように。
でもそれはまあ、形式上のものであって、内心は受け入れてあげてもいいか、とは思っている。大事なのはあくまで、私は嫌がっているんですよ、というスタンスであって、そういう私の本質まで見抜かれているのだとしたら、こちらは白旗をあげるしかない。
「分かったよ。ほんと今晩だけだからね」
「ありがと。志乃さん、大好きだよ」
量産されているであろう大好きをもらって、通話は途切れた。
ちなみにハルは私のことを名前にさん付けするかたちで志乃さんと呼ぶけれど、同じ年の生まれであり、学年も変わらない。たぶん甘えん坊キャラを死守するために、日頃から誰にでもさん付けをしているのだと思われる。
五分後、アパートの部屋のベルが鳴った。まさかと思ってドアスコープをのぞくと、派手なピンクのハーフツインが見える。ハルだった。
いくら何でも早すぎる。こいつ、確認を取る前から私の家に向かっていたに違いない。
ロックを外して扉を開けてやるなり、ハルは私に向かって突進してきた。抱きつかれて、そのまま玄関に二人して倒れ込む。ガチャン、と扉の閉まる音がする。
「ねえ、重い。最悪」
「ひどいこと言わないでよー」
「声でかい。響くから」
「あ、ごめん……」
私は自分に被さるハルの体を押し退ける。
彼女は腕にコンビニのレジ袋を提げていて、それを私の前に掲げた。
「軽く飲もう、付き合って。そんで話聞いて」
「仕方ないな」
「待って! その前にシャワー浴びたい」
「え、あー、うん」
ハルに促されるまま、私はカラーボックスから高校時代のジャージ上下を取りだし、彼女に手渡す。私はこれと今身につけているグレーのスウェットを、交互に着回している。
「ありがと。あたしがお風呂入ってる間に寝るのナシね!」
「うん。分かったから、早く行け」
「ぜったいね!」
嵐のような、という比喩はきっと彼女のためにあるのだろう。
私はハルが脱衣所に姿を消すと、ささやかな晩酌のための準備に取りかかった。
補強したダンボール箱に布地をかけただけの粗末なテーブルに、買い溜めてあったスナック菓子を広げる。次に、彼女から受け取ったビニール袋をのぞくと、フルーツの絵が載った缶パッケージが目につく。
甘いのばっかだな、とラインナップに独りで愚痴を零しながら、とりあえず互いの分を一本ずつ用意して並べた。
「ごめんごめん、あがったー」
ようやくハルがお風呂からあがってきた時、私は壁にスクリーンを映しだすために、投影機の設定をいじっていた。
通販サイトでセール時に購入した安物だ。開封が面倒で放置していたのだけれど、せっかくなのでこの際に使ってみることにした。
「志乃さん、なにしてんの?」
「これ買ったんだ。宅飲みしながら、大きな画面で映画観るのってちょっと夢じゃない?」
「ふーん」
「え、てかなにその格好」
「下、サイズ合わんかったー」
濡れた髪から水滴を垂らし、私にもたれかかってくるハルは、小柄な体に上着だけを纏っている。露出した生足が、何というか、目に毒だ。
私は意識を他に追いやろうとして、ひとまず彼女から視線を外す。
「もしかして志乃さん、照れてんの?」
「なわけない」
ハルは一向に髪を乾かそうとしない。それどころか、鬱陶しくらいこちらに頭を擦り寄せてくる。そのせいで、グレーのスウェットに染みができる。
彼女はいよいよ、私の膝の上に頭を乗せてきた。寝転がったまま缶チューハイに手を伸ばして、私にクレームをつけてくる。
「余計な買い物ばっかしてさあ、いい加減テーブルくらい買いなよ」
「うるさいな」
ハルが寝そべったままの姿勢で、缶のプルタブを開け、口もとに持っていく。「危ないよ」という私の忠告も虚しく、彼女の口の端からお酒が伝って零れる。
「なんかどうでもよくなっちゃったなあ」
不意に、ハルが天井をじっと見つめながら呟いた。
「なにが?」
「ここ向かってる時はさ、志乃さんにいっぱい喋りたいことあって、全部受け止めてもらおうと思ってたのに、今はもう言葉が出ないの。志乃さんの傍にいるとさ、誰に傷つけられたとか、裏切られたとか、そういうの全部大したことじゃないんだなって思うよ」
熱い何かが、喉もとに込みあげた。それで私は、今この瞬間に泣きだしたいような、笑いだしたいような、相反する感情に冒された。
「ねえ、志乃さん」
「ん?」
「あたし、いつも大事な人に捨てられちゃうの。でも、志乃さんだけはいなくならないもんね?」
ずるいな、と思う。頼むから、そんなふうに私に縋らないでくれ。
「まあ、そうね」
たちまち、間違った優越感が私を満たす。
平静を装ったはずの声はいやに掠れていて、自分が情けなかった。
明くる日、私たちは講義をサボって、一日中家で映画を観ながら過ごした。
恋愛映画の途中で突然ハルが号泣し、それがいつまでもやみそうにないから、わりと焦って、気分転換にホラー映画を再生して、あまりの怖さに二人して本気でビビって、一つの布団に身を寄せあって。たぶん、幸せってこういうことをいうのだと思う。
次の日もハルは家に泊まった。その次の日も、また次の日も。
そうやって一日ずつ、たくさんの言い訳を並べながら、彼女の滞在を許容していって。気がつけば、長い月日が経っていた。
二十歳に出会った私たちは、今年で三十になる。
***
「ねえ、志乃さん! あたし犬飼いたい」
平日の朝はとにかく時間がない。出勤までの道のりを、どれだけ短縮できるかが勝負となる。
すっかり昼夜逆転した生活を送っているハルは、毎朝飽きもせずにだる絡みしてくる。もはやルーティンの一部となりつつあるそのイベントを、私は華麗に無視して、せっせとタスクをこなしていく。
キッチンに立って、棚からマグカップを取りだし、天然水を注いだそれにビタミンCの錠剤を溶かす。無理にご飯を詰め込むと、通勤の列車のなかで吐き気を催すことは目に見えているから、朝はこれだけで済ませるのが習慣になっている。
堅苦しいスーツを着るのは最後にして、次にメイクとヘアセット。
ドレッサーの前に腰かけたところに、隣からハルの腕が伸びてくる。
「見てよこれ! めっちゃ可愛くない?」
彼女の手に握られたスマホの画面に映るのは、ポメラニアンが飼い主とじゃれあっている様子を撮った、ショートムービー。
「動画で見るぶんにはね」
「そんなことないって! こんな子が家にいたらさ、すっごく癒されると思わない? 志乃さんだって、もっと仕事頑張れるかもだよ」
私は大仰にため息を吐く。ハルの衝動性には、幾度となく振り回されてきた。
少なくとも、一時の感情に踊らされて選択するべきことではないと思うし、どうせ毎日の散歩は私の役目になることだろう。
「うちのマンションはペット駄目でしょ?」
私は苛つきながら、もっともな指摘をする。忘れたとは言わせない。
「なら、また引っ越せばいいじゃない」
ハルは臆する様子もなく、当然のようにそう言った。軽薄な態度が、さらに私の苛立ちに拍車をかける。
「そう簡単に言わないでよ。今のところ予定はないし、次に引っ越す時があったなら、それはあんたとの別離を示してる」
「つまんない冗談やめてよね。もう何度も聞いたって、それ」
そうだ、これも。もう何度も交わしたやり取り。ハルからすれば、私が示す拒絶は、わざわざ気に留める必要もないくらい日常に浸透してしまったのだ。
「次の休みはさ、ペットショップに行こうよ。とりあえず見るだけでいいから! ね?」
ハルがめげずに話しかけてくる。
私は「ん、そうね」と適当にあしらって、鏡に映る憂鬱な顔をした自分を見つめた。
下地を塗って、ファンデーションを叩いて、ペンシルで眉毛を描く。簡潔に化粧を済ませると、最後に着替えをする。いつも着ているシンプルなスーツ。指先で摘んだストッキングをみじめに引きあげているこの時間が、何よりも億劫だと思う。
全ての身支度を終えた私は、玄関でパンプスを履きながら、これまた定型になった台詞を吐いた。
「じゃあ行ってくるから、留守番お願いね」
「はーい」と間延びした返事を受けて、私は扉の外に出た。
最寄り駅まで徒歩十五分。プラットホームで列車を待つ。四月の生温い風が肌を撫でる。
数分後に到着した列車に乗り込む。通勤の満員電車は何年経験しようが慣れないし、慣れたくもない。
車体が揺れて、誰かの靴を思わず踏んでしまって、「すみません」と小声で謝る。車内を満たす熱気。伝わる他人の憂鬱。抑鬱気分。最低な一日の始まり。
息苦しいな、と私は思う。
そうして次に、家で寛いでいるだろうハルのことを思う。
彼女は今まで一度も働いたことがない。大学四年時に就活で挫折したらしく、それ以来バイトも何もしていない。
私がさり気なく就職について促す度、「今は少し、難しい時期なの」とハルは言った。案の定、その難しい時期とやらは十年経っても続いている。
そういえば、私の学生時代の夢は専業主婦だった。早くに結婚して、社会から距離を置いて、家庭のことに専念したかった。
むろん家事を軽んじているわけではないけれど、それでも他人の心情を図りながら、社会のなかで生きていく方がよほど難儀に感じていた。
なんでこうなってしまったのだろう。どうして、ハルのポジションにいるのが私でないのだろう。
途中駅で列車の扉が開いて、多くの人が乗り込んできた。車内はより圧迫し、他人の体に触れざるを得ないほどになる。
ああ、息苦しいな。また一つ、私の胸中のわだかまりが増えていく。毎日、毎日毎日毎日毎日毎日。同じことの繰り返しで。憂鬱で、気怠い。水で薄めたような、漠然とした死にたさがいつまでも消えない。
***
日曜日。
私とハルは、大型モールの一角にあるペットショップの前にいた。
ハルがガラス越しの子犬に駆け寄っていく。まるで子どもみたいに。ウェーブをかけたピンク髪がゆらゆらと揺れる。彼女は週一で美容院に通い、綺麗なハイトーンを維持している。
改めて外でハルのことを見ていると、彼女は本当に老けないなと思う。制服を着れば、余裕で高校生に見えそうなくらい。幼い顔の造形も、滑らかな肌も、出会った頃から何も変わらない。それに比べて私は……。
「わぁー、かわいいー!」
ハルが感嘆の声をあげて、私に手招きする。周りの視線が痛い。仕方なく重い足を動かす。
「なあに、嬉しいの? すごい尻尾振ってるね?」
ハルが隣で、チワワの子犬に甘ったるい声で話しかける。すると、ここぞとばかりに若い女性の店員が近寄ってきた。
「よかったら抱っこしてみますか?」
「え、いいですか?」
すかさずハルが食いつく。店員に促されるまま、私たちは近くのソファに並んで座り、膝に毛布をあてがわれた。裏に戻った店員がショーケースのなかに現れ、さっきの子犬を抱えて戻ってくる。彼女は、ハルの太ももの上にそっと子犬を乗せてくれた。
「この子はモモちゃんっていうんです。生後二ヶ月なんですよ」
「そうなんですねー」
ハルは店員に愛想良く相槌を打つと、さっそく目の前の子犬に向き直り、その名前を呼んだ。
「モモちゃん!」
呼ばれたのに気がついたのだろうか。モモちゃんは、ハァハァと舌を出し、まん丸な黒目でじっとハルを見つめる。
「ああ、どうしよ。ほんと可愛い」
ハルはモモちゃんの背を撫でながら、大袈裟なリアクションとともに顔を綻ばせる。
「ポメがいいんじゃなかったっけ?」
なぜだかモモちゃんに対して嫉妬心湧いてきた私は、わざと水を差してやった。
「そうなんだよね。でも、実際ここ来てこの子見たらビビっときちゃった。運命だよ」
「何度も言うようだけどさ、うちではペット飼えないんだからね? 今日は見に来ただけなんでしょ?」
ハルはぷくっと頬を膨らませ、瞳を潤ませた。
「そんな顔してもだめ」
いつもハルの我儘に押し負けてきた私だけれど、今回ばかりは絶対に許容できない。費用だって馬鹿にならないし、長年の責任が伴うことだし、何よりこの子に愛情を注げる自信がない。
「どうされますか?」
傍で私たちのやり取りを見ていた店員が、 ハルの方だけに視線をやって、問いかけてくる。
私はハルが何か言おうとする気配を感じ取って、すぐに口を開いた。
「すみません。もう少し考えます」
未だガラス越しの小動物たちに食いつくハルを引きずるようにして、私はペットショップを離れた。
その後私たちは、お手洗いを済ませ、フードコートで簡単な食事を摂り、ディナーの時間まで暇をつぶすことにした。夜はハルの希望で、駅前のホテルの最上階にある高級なビュッフェのプランを奮発して予約したのだ。
気になる店舗を一通り巡って(主にハルのための)洋服や雑貨を物色し、ゲーセンでクレーンゲームに興じた。「どうせ確率機だよ」と私が忠告するのも聞かず、ハルは目当てのぬいぐるみを狙い続けた。そして、私の財布からは予算外の五千円が散った。
ハルはまだ遊び足りずに、ゲーセンの隅に設けられたカプセルトイを回している。ビーズをあしらった女児向けのアクセサリー。
「あー、ダブっちゃった」
ハルがカプセルを開くと、またさっきと同じビーズのブレスレット。
「ねえ、もう懲りたでしょ?」
私がため息を吐くと、ハルは笑顔でこちらにブレスレットを差しだした。
「あげる。お揃いだね?」
「ん、そうね」
私は渋々といった感じで、安っぽいブレスレットを手首につける。
かっちりしたジャケットに不似合いなそれが、どうしようもなく愛しい。
***
スケルトンのエレベーターで一気に最上階まで上がる。受付に予約の旨を伝えると、スムーズになかへ通された。
軽いドレスコートの注意はあったものの、店内には案外ラフな格好の客が多くて安心する。
窓際の予約席に案内された私たちは、向かい合わせに座る。すぐ横にはライトアップされた綺麗な夜景。ビル群の隙間を縫うように、テールランプの明かりが流れている。
やってきたウエイトレスに、アルコールの注文を聞かれ、せっかくだからと白ワインを頼む。
二時間のビュッフェ。私たちはテーブル下の籠に鞄を置き、一緒に料理を取りにいく。
しっかりサラダから取る私に対して、ハルはもうメイン料理のコーナーにいた。ピザやパスタやチキン、フライドポテトなど好きなものだけをプレートに載せている。そんな彼女を横目に見ながら、早死にしそうだよなあ、とか思う。
一通り食べたいものを取って、互いに席に戻り、私たちは手を合わせる。ちょうどウエイトレスが冷えたワインをワゴンに載せてやってきて、それぞれのグラスに注いでくれた。
慣れない乾杯。下手なグラスの持ち方をするハルに庇護欲が湧く。
「このパスタ美味しいよ」
「うん」
「志乃さんも食べてね」
「うん」
アルコールで、ハルの肌がまだらに赤くなる。呼気が僅かに荒くなっているのが分かる。
「ここ高かったしちゃんと元取ろうね」と言い合って、私たちは周りの目も気にせず、もくもくと食べ進めていった。ハルは、小さな口に見合わない量を詰め込んだせいで、ハムスターみたいに頬が膨れている。
ふと、「時々考えるんだよね」と私は口を滑らせてしまう。酔いにやられたということにしてほしい。「なあに」とハルが聞くから、後悔するも手遅れで、私はくだらない思考をそのまま零す。「結婚できない、セックスもしない私たちは、何のために一緒にいるんだろうって」
ハルは興味もなさそうに頬杖をついて、夜景を眺めている。
「なにそれ。志乃さん、頭でも打っちゃった?」
「だって、そうでしょ? 私たちを繋いでるものって、言えば二十歳の時に交わした脆い約束に過ぎないわけじゃない?」
「えーと、なんか約束……したっけ?」
傷心するのを自覚しながら、私は気丈に振る舞う。
「……忘れたの? ハルが言ったんだよ。自分の傍からいなくならないでくれって。私はそれに渋々頷いて、だから今があるんでしょ」
私の言葉に、あはは、とハルが可笑しそうに笑った。
「学生時代のうわ言に深い意味なんかないって。あたしたちもういい歳だよ? 志乃さんってやっぱり面白いね?」
もういい歳だなんて、どの口が言うんだよ。胸に募った怒りの感情は、もちろん声に出せない。出しちゃいけない。
「ごめん。私、酔ってると思う」
「分かってる。大丈夫だよ」
ハルがデザートを取りに行き、皿にタルトやケーキ、シュークリーム、マカロンその他諸々を山盛りにして戻ってきた。
案の定と言うべきだろう。最初こそ美味しそうに食べていた彼女だけれど、途中でぱたんとフォークをもつ手を止めてしまった。
「食べれるぶんだけ取らなきゃ」と今更に私は言う。
「だって食べれると思ったもん」
「ねえ、残しちゃだめ」
「じゃあ志乃さん食べてよ」
「うん」
ハルがこちらに皿ごと押しやる。
デザートはぐちゃぐちゃに混ざりあい、食べかけのシフォンのスポンジには、ピンクのグロスがついていた。
フォークでまとめて串刺しにして、無理やり呑み込む。甘すぎて気持ち悪い。吐き気がする。苦味が欲しくてワインを呷る。
次にハルに目線をやった時、彼女はうたた寝していた。
***
やりがいの感じられない事務の仕事は一日八時間、週五日。そして寝るだけの土曜日と、ハルと遊びに興じる日曜日。
ずっとその繰り返し。ただ日々を積み重ねていくだけ。まあ、人生ってそんなものなのかもしれないけれど。
ハルと出会わなかった世界線の私がいるとするなら、もっと消極的な日々を送っていることだろう。
四月の日曜は残り三回あって、私はその全部をハルに捧げた。ピクニックに行きたいと言いだした彼女に付き合って朝早くからサンドイッチを作ったし、脱出ゲームに参加して苦手な謎解きに頭をつかったし、水族館に行ってライトアップされたクラゲのエリアで写真を撮った。
やがて、憂鬱な五月がやってくる。すでに梅雨入りの気配がしていた。心做しか、街全体が色褪せて見えた。
五月は毎年気分が沈むから、私はこの時期が嫌いだ。五月病という言葉があるくらいだし、自殺率も高いらしいし、上手く外向きの表情が繕えなくても許してほしい。
今日も私はハルのだる絡みを受け流し、重たい足を引きずりながら、どうにか駅のプラットホームまで辿り着く。
ホームに入ってきた列車が停車する。満杯の車内に体をすべりこませる。例のごとく途中駅で、通勤の人々がどっと乗り込んできて、私は壁にぐっと押しやられる。
脳内を空っぽにして圧迫感に耐えていると、不意に、内腿に何かが当たった。少なくとも人の手ではない。硬い物質。恐らくは誰かの鞄。不快ではあったけれど、状況的に仕方がない。
私はどうにか首を捻って、車内に設置されたディスプレイを見あげる。この列車は急行だから、次の駅に止まるまでにはまだ時間があった。
数秒後、私は内腿の不快感が明確な悪意によるものだと知る。後ろに立つ誰かが、太腿に差し込んだ通勤鞄を、ぐりぐりと上方にやっている。それで、タイトスカートの裾がずりあがる。
身の毛もよだつ恐怖で、もうそちらに目を向けられない。太い指がストッキング越しに私の足を撫でるのが分かる。気持ち悪い。どうしよう。いや分かってる。今すぐにその汚らわしい手を引っ掴み、「痴漢です!」と叫ぶべきだ。
……けれど、私の手は動かない。さっきから幾度も脳内でイメージトレーニングをしているのに、実際に行動には移せない。
動悸が早くなり、目に涙が滲む。訳も分からない悔しさで、唇を噛み締める。
誰も私の苦しみに気がついてくれない。私と同様に、気づいていても行動に移せないだけなのかもしれない。だとすれば、私はそんな誰かを責められない。
みんな自分が一番大事だ。分かってる。分かってるよ。他人のことなんかどうでもいいよな。私だってそうだよ。
途方もなく長い時間に感じられた。次の停車駅で私はすぐに車内から降りた。もちろん会社の最寄りではない。ただ、あの場から一刻も早く離れたかった。
電波を確保するために、地下鉄のホームから外に出る。
もう出勤時刻には間に合わないけれど、仕方ない。今からすぐに遅刻の連絡を入れよう。でも、なんて? 素直に痴漢されましたって言う? 同僚にはどう思われるだろう? どうして自らを辱めなくちゃいけないんだ?
私は思い直し、スマホの電源を切った。まだ内腿には耐えがたい不快さが残っていた。人生全てが馬鹿馬鹿しい。なんで私、生きてるんだろう。
何だか家に帰る気にはなれなかった。たぶん私は、ハルに仕事を飛んだことを知られたくなかった。幻滅されるんじゃないかと怖かった。
だから、そのまま意味もなく知らない土地を彷徨う。人気のない路地で電柱を蹴飛ばしてみる。普通に痛い。後でトイレで確認したら、足の爪が内出血を起こして黒ずんでいた。
近くのデパートに立ち寄って、来月のことなんか考えずにカードを切る。ほとんどがハルへのお土産だった。返済できずに困ったら? 死ねばいい。それで万事解決でしょ?
***
何だか電車に乗るのが怖くなってしまって、馬鹿みたいな距離を徒歩で帰宅した。足の筋肉が痙攣を起こしている。
帰りが遅れた言い訳を考えながら、私は部屋の扉を開けた。
「ただいま」
返事がない。玄関で靴を脱ぎ、リビングに直行する。いない。寝室の扉を開ける。
あ、いた。
ハルは、寝室の隅につくったゲーミングスペースにいた。電気は点いておらず、パソコンのキーボードとファンが放つ虹色の光がチカチカして目に痛い。
彼女は耳にヘッドフォンをつけ、手にコントローラーをもち、最近ハマっているらしいFPSゲームに熱中していた。誰かと話している様子だった。前に言ってたネッ友だろう。
彼女は楽しそうに喋りながら銃を乱射して、時折思いだしたように、机上に置かれたエナドリ缶を片手にストローで吸う。未だ、こちらに気づく様子がない。よほど熱中しているらしい。
「ねえ、ハル」
試しに呼びかけてみるけれど、気づかない。
「ただいま」
まだ気づかない。
「ねえってば!」
たまらずハルの肩を揺する。それで彼女はびくっと体を震わせ、「ちょっとごめん」と言ってからヘッドフォンを外す。
「なんだ、志乃さんいたの。おかえり」
敵の銃弾でハルが死ぬ。画面が真っ暗になって、リスポーン地点に戻る。
私は衝動的に、ヘッドフォンのコードを引き抜いた。
「今すぐそいつと縁切って」
「え?」
「え、じゃなくてさ。縁切れって言ってる」
ハルが一瞬眉根を寄せる。それからすぐ、傷ついたように笑う。
「どうしたの? 普段そんなこと言わないじゃん」
「煩いな。ずっと思ってたよ。我慢してただけ」
私は喉奥の熱を呑み込んで、泣きそうになるのを堪えた。
「私だけでいいじゃん。なにが不満なの? ずっとハルのために尽くしてきたのに、こんなのってないよ!」
「いやいや、なにが? ねえ意味分かんない。今の志乃さん変だよ」
ハルが私を否定している。どうして? 分からない。私には結局、彼女の考えていることなんて何も分からない。でも。
「ハルはいいよね」
ぽろりと言葉が零れた。一度口にしてしまえば、もう手遅れだった。次から次に残虐な思いが溢れだして止まらなくなる。
「悩みとかなさそうじゃん。生きづらさとか感じたことないんでしょ? どんな思いで私が毎日働いて、あんたを養ってきたと思う? 私が朝起きてまず、決まって脳裏に過ぎるのは、会社に欠勤の連絡を入れようかってことなんだよ。今日くらい仮病で休んでも許されるよね、って私のなかの悪魔が囁くの。でもね、一度そうやって甘えると、二度目三度目って歯止めが効かなくなるし、そうしたら日々の生活が立ちいかなくなる。だから私はその誘惑になんとか抗って、布団から這いでるわけ。億劫な朝の準備を済ませて、外に出て、他人に圧迫されて、小さなミスを引きずってるうちに取り返しのつかないことになって、自分より年下の子の方がずっと優秀で、情けなくなって、へとへとで帰宅したらすぐに明日が来る。生き地獄だよ。生きてる全部が苦しいんだよ。ねえ、あんたばっか楽してずるい。他人の善意を搾取するくらいしか能がないくせに、生きやすそうでずるい」
早口に捲し立てたせいで、軽い息切れを起こす。
本当は、こんなことが言いたいわけじゃない。ハルに私を必要としてほしいだけだ。こんな私にも存在価値があるんだって、だから生きていてもいいんだって、ちゃんと、私自身に分からせてほしいだけだ。
「なにそれ。じゃあ、あたしのこと追いだせば?」
ハルが事もなげに言う。いつものふわふわした甘さは見る影もなく、彼女の伏せられた目はこちらを軽蔑しているようだった。
「……は?」
予想外の返事に面食らって、苛立ちが募った。
怒りと悲しみは似ているな、と思う。発露される方法が違うだけで、その本質はきっと同じ場所にある。
「この家にあたしを置いてるのは志乃さんでしょ?」とハルが乾いた声音で続けた。「ほら、早く言いなよ。あたしに出てけって。そうすれば気が済むんでしょ?」
「違うよ、ハル。ただ、私の辛さを分かってもらいたくて。生きるのが辛いのはお互い様でしょ? ねえ一緒に頑張ろうよ。せめて家事くらいはしてほしい。ちゃんとまともに生きてほしい」
ハルが口もとだけで笑う。それは嘲っているようにも、悲しんでいるようにも見える。確かなのは、彼女が今この瞬間、私に幻滅したらしいこと。
「あー、そう。よく分かったよ。志乃さんは、あたしがなんも考えずにふらふら生きてるだけだと思ってんだ? 怠けてるだけだって」
「別にそんなつもりじゃ……。私はただ――」
私の言葉を遮って、ハルはほとんど叫ぶみたいに言った。
「志乃さんはあたしのなにを知ってんの? 自分一人が苦しいみたいな顔してさ、被害者意識ばっか強いのうざすぎ。そんなん言われるなら、あたし死ぬわ。志乃さん曰く、あたしは他人の善意を踏みにじる害悪なんだもんね? こんなのが生きてたって社会のお荷物だもんね?」
「やめてよ、ハル。違うよ」
ガタン、と乱暴な音が鳴る。ハルはパソコンの電源を落とし、ゲーミングチェアから立ちあがる。壁のスイッチを押して照明をつけ、次に彼女は部屋のクローゼットからキャリーケースを取りだす。
「……なにしてるの?」
ハルは私の質問を無視して、床にケースを広げると、そのなかに自分の持ち物を次々に投げ込み始めた。
「これ以上迷惑かけないし、安心して? あたしたち十年近く一緒にいたけどさ、結婚してるわけでもないし、この家から出てけばどうせ他人だからね」
身体に寒気が走る。現状に頭が追いついていかなくて、心臓がドクドクと鳴って、胸がキリキリと痛む。
このまま、呆然と立ち尽くしていいのか? 私は自問する。
ううん、いい訳がない。ふわふわと続いてきた私たちの関係性だけれど、こんなに痛ましい終わり方をするなんて嫌だ。
いつもはマイペースなハルが、せっせと私物を詰めていく。リビングと脱衣所を行き来して、最低限のパッキングを済ませる。
「ちょっと待ってよ」
ハルはキャリーケースを引きずりながら、すたすたと玄関に向かってしまう。素足のままミュールに足を入れ、ドアの取っ手を掴む。
ここが瀬戸際だった。
「ねえ、お願い。私が全部悪かったから、ごめん。行かないで」
私はみっともなく彼女に縋る。その背中にしがみついて、涙を溢れさせる。
「うん、知ってる」
ハルがすっと、ノブにかけていた手を放した。それから、こちらを振り返る。なぜだか口角が緩やかに上がっていた。細められた目はどこまでも優しい。
「へ?」
私は安堵と困惑で、腑抜けた声を出す。
くずおれる私を、華奢な腕が支える。ハルがすぐ隣でにこやかに笑う。
「志乃さんは、ぜったいあたしから離れられないんだって知ってる」
続くハルの言葉が、真っ直ぐに私を捉えた。次いで、呪いみたいに脳裏から離れなくなった。
「ごめんね? 冗談だからね。あたし怒ってないよ?」
ああ、救われた。涙が止まらない。
「そっか。私こそごめんね。ひどいこと、たくさん言った」
「ううん。大丈夫。あたしはいつだって、志乃さんの全部を許したげる」
ハルの手が背中に回る。彼女の腕のなかはあまりに脆い。
「この荷物は?」
ハルが私に問う。
玄関の周りには、帰宅した時に投げ出した買い物袋が散らばっていた。
「ハルが喜ぶと思って……コスメとか洋服とかいろいろ買ってきた。安かったんだよ。すごく。ほんとに」
「え、これ全部? 嬉しい。ありがとね」
「うん」
私たちは長い間、玄関で抱きしめあった。ハルが優しく頭を撫でてくれる。甘い声が、耳をくすぐる。
「志乃さん、愛してるよ」
「うん……私も」
***
翌日も早朝に起床した。
昨夜の気恥しさで、まともにハルと顔を合わせられないまま、私はスーツを着て外に出た。
会社の番号は着拒済みで、たぶんもう二度と行けない。いつかちゃんとハルにも伝えなくてはならないと分かっているけれど、臆病な私はこうしてしばらく出勤を装い続けるのかもしれない。
家の周辺を無駄に歩き回って、カフェに立ち寄り時間を潰す。
***
日が暮れる。そろそろ頃合いだ。私はマンションの自宅に足を向ける。何もしていない、という虚しさが胸を痛ませる。
帰宅した途端、パン! と弾けるようなクラッカー音に迎え入れられた。
うわあ、と私の口から驚きで情けない声が漏れる。
玄関に立ち尽くしていると、ハルに「本日の主役」というふざけたタスキをかけられた。そのまま頭にもおもちゃの冠を被せられる。
「志乃さん! 誕生日おめでとー!」
「え?」
脳内カレンダーで今日の日付を思いだす。五月二日。そうだ、私はこんな最低な時期に生まれてきたのだった。
「私、疲れててさ。ちょっと寝ていいかな……」
「だめだめ。一年に一回しかない記念すべき日でしょ? 覚悟しな。今夜は寝かさないぜ?」
ハルがおどけた口調で言いながら、私の腕を強引に引っ張っていく。
誕生日なんかめでたくも何ともないのに、微かに胸が踊っている。今年もまたハルとこの日を過ごせることが、結局は嬉しいのだと思う。
ハルに促されるままリビングに入る。盛大に散らかった室内に、私は思わず苦笑した。
今日私がいない間に準備したのだろう。カーテンレールやら照明やらにモールが巻きつけられ、床のあちこちに風船が落ちている。
毎年手作りのミサンガをくれたり、私の似顔絵を書いてくれたり、何だかんだ祝ってもらっていたけれど、こんなに本格的なのは今回が初めてかもしれない。
テーブルの上には、ワンホールのチョコレートケーキがあった。元は完成された市販のケーキだっただろうに、ハルが施したお菓子のデコレーションのせいで台無しになっている。
「ねえ、頑張ったの。食べてみてよ」
「うん」
テーブルに着く。用意されたフォークで一口食べる。
ああ、甘いな。
やっぱり甘いものは苦手だ。お菓子とクリームまみれのケーキも、何から何まで完璧に可愛いハルのことも、等しく苦手だ。
「どう? 楽しい?」
私は再び昨夜のことを思いだしていた。これはハルなりの励ましなのかもしれない。
「うん。最高の気分」
途端、今しかない、と私は思う。ちゃんとハルに伝えなければ。
「私、今の仕事辞めるね」
「なんで急に?」
「遠くに引っ越そうよ。気分転換にさ。犬は飼えないけど、ここより広いとこ」
「え、ほんと?」
「うん。まじで」
改めて現状を把握するために、辺りを見回す。
テーブルに散らかる食べ物の残骸も、部屋中を彩る百均の飾りつけも、きっと明日には全部ゴミになる。そうして、いつかは今日という日も、取るに足らない過去のワンシーンに成り果てる。
ハルと過ごしてきた十年ばかりの歳月が、私にとってあまりに重くて、甘くて、愛おしくて、そのことが切実なまでに悔しい。
「ねえ志乃さん」
「ん?」
何度も繰り返されてきたやり取り。
ハルは上目遣いに私を見あげると、お得意の愛らしい笑みを浮かべて言った。
「次の休みはどこに行こっか?」
時間にルーズで、なくし物が多くて、社会性の欠片もない。そんな彼女との同棲は大学時代に始まり、もう十年目になる。
きっかけは、「お願い、今から泊めて!」という切実な言葉だった。泣き縋るような声音に抗えなかった記憶がある。
あの時は確か、深夜三時を回っていた。私は枕もとのスマホから発される耳障りなコール音に、気分の悪い目覚めを経験した。
暗い部屋で淡白な光を放つ画面には、「ハル」の名前。
うんざりしながら、いやいや緊急事態かもしれないじゃないか、と無理に自分を納得させてから電話に出た。
「あの、もしもし?」
「やっと出たー! 遅いよ、もう」
掴みどころのない、ふわふわした甘い声。
どうしてこちらが責められているのかは全くもって分からない。
「ねえ、今の時間分かってる? 私になんの用?」
一瞬間が空く。通話越しに車の走行音が響く。それで、ハルはこんな夜中にもかかわらず、外にいるのだと気づく。
「ちょっと返事してよ! まさか馬鹿なこと考えてないよね、ねえ?」
「志乃さん……」
ハルが妙に深刻そうな調子で私を呼ぶ。
「お願い、今から泊めて!」
続けて、彼女の口から紡がれたのは、何ともふざけた要求だった。
途端、私に連絡を寄越してきたのはそういうことか、と合点がいった。この付近に一人暮らしをしている人間は、学内でも限られている。
「そんな急に言われても、私だって困る。とりあえず事情を説明して」
私が強めの口調で返すと、ハルは怒られた子どもみたいに「うん、そだよね」と、あからさまに落ち込んで見せる。計算し尽くされたやり口だ。
「家、なくなっちゃって……志乃さんしか頼れないの」
「はあ? なくなった?」
訳が分からずに聞き返す。
長い話になりそうな予感があって、私は眠たい目を擦りながら体を起こし、布団の上で胡座をかく。
「彼氏と喧嘩して、家から追いだされちゃった」
「こんな夜中に? でも、そんなの一時的なもんでしょ?」
ハルは社会人の年上男性と交際していて、少し前に同棲を始めていた。あれだけ愛の深さを語っておいてこのざまかよ。
「とりあえず、泊めてってば! 志乃さんはあたしが路上で野垂れ死んでもいいんだ?」
「別にいいけど。なにを大袈裟な」
「嘘だよ! ぜったい後悔するんだから!」
「はあ……」
「可愛い友達の頼みでしょ? 今晩だけでいいよ、ね?」
私はため息を吐いた。通話越しにもちゃんと聞こえるように。
でもそれはまあ、形式上のものであって、内心は受け入れてあげてもいいか、とは思っている。大事なのはあくまで、私は嫌がっているんですよ、というスタンスであって、そういう私の本質まで見抜かれているのだとしたら、こちらは白旗をあげるしかない。
「分かったよ。ほんと今晩だけだからね」
「ありがと。志乃さん、大好きだよ」
量産されているであろう大好きをもらって、通話は途切れた。
ちなみにハルは私のことを名前にさん付けするかたちで志乃さんと呼ぶけれど、同じ年の生まれであり、学年も変わらない。たぶん甘えん坊キャラを死守するために、日頃から誰にでもさん付けをしているのだと思われる。
五分後、アパートの部屋のベルが鳴った。まさかと思ってドアスコープをのぞくと、派手なピンクのハーフツインが見える。ハルだった。
いくら何でも早すぎる。こいつ、確認を取る前から私の家に向かっていたに違いない。
ロックを外して扉を開けてやるなり、ハルは私に向かって突進してきた。抱きつかれて、そのまま玄関に二人して倒れ込む。ガチャン、と扉の閉まる音がする。
「ねえ、重い。最悪」
「ひどいこと言わないでよー」
「声でかい。響くから」
「あ、ごめん……」
私は自分に被さるハルの体を押し退ける。
彼女は腕にコンビニのレジ袋を提げていて、それを私の前に掲げた。
「軽く飲もう、付き合って。そんで話聞いて」
「仕方ないな」
「待って! その前にシャワー浴びたい」
「え、あー、うん」
ハルに促されるまま、私はカラーボックスから高校時代のジャージ上下を取りだし、彼女に手渡す。私はこれと今身につけているグレーのスウェットを、交互に着回している。
「ありがと。あたしがお風呂入ってる間に寝るのナシね!」
「うん。分かったから、早く行け」
「ぜったいね!」
嵐のような、という比喩はきっと彼女のためにあるのだろう。
私はハルが脱衣所に姿を消すと、ささやかな晩酌のための準備に取りかかった。
補強したダンボール箱に布地をかけただけの粗末なテーブルに、買い溜めてあったスナック菓子を広げる。次に、彼女から受け取ったビニール袋をのぞくと、フルーツの絵が載った缶パッケージが目につく。
甘いのばっかだな、とラインナップに独りで愚痴を零しながら、とりあえず互いの分を一本ずつ用意して並べた。
「ごめんごめん、あがったー」
ようやくハルがお風呂からあがってきた時、私は壁にスクリーンを映しだすために、投影機の設定をいじっていた。
通販サイトでセール時に購入した安物だ。開封が面倒で放置していたのだけれど、せっかくなのでこの際に使ってみることにした。
「志乃さん、なにしてんの?」
「これ買ったんだ。宅飲みしながら、大きな画面で映画観るのってちょっと夢じゃない?」
「ふーん」
「え、てかなにその格好」
「下、サイズ合わんかったー」
濡れた髪から水滴を垂らし、私にもたれかかってくるハルは、小柄な体に上着だけを纏っている。露出した生足が、何というか、目に毒だ。
私は意識を他に追いやろうとして、ひとまず彼女から視線を外す。
「もしかして志乃さん、照れてんの?」
「なわけない」
ハルは一向に髪を乾かそうとしない。それどころか、鬱陶しくらいこちらに頭を擦り寄せてくる。そのせいで、グレーのスウェットに染みができる。
彼女はいよいよ、私の膝の上に頭を乗せてきた。寝転がったまま缶チューハイに手を伸ばして、私にクレームをつけてくる。
「余計な買い物ばっかしてさあ、いい加減テーブルくらい買いなよ」
「うるさいな」
ハルが寝そべったままの姿勢で、缶のプルタブを開け、口もとに持っていく。「危ないよ」という私の忠告も虚しく、彼女の口の端からお酒が伝って零れる。
「なんかどうでもよくなっちゃったなあ」
不意に、ハルが天井をじっと見つめながら呟いた。
「なにが?」
「ここ向かってる時はさ、志乃さんにいっぱい喋りたいことあって、全部受け止めてもらおうと思ってたのに、今はもう言葉が出ないの。志乃さんの傍にいるとさ、誰に傷つけられたとか、裏切られたとか、そういうの全部大したことじゃないんだなって思うよ」
熱い何かが、喉もとに込みあげた。それで私は、今この瞬間に泣きだしたいような、笑いだしたいような、相反する感情に冒された。
「ねえ、志乃さん」
「ん?」
「あたし、いつも大事な人に捨てられちゃうの。でも、志乃さんだけはいなくならないもんね?」
ずるいな、と思う。頼むから、そんなふうに私に縋らないでくれ。
「まあ、そうね」
たちまち、間違った優越感が私を満たす。
平静を装ったはずの声はいやに掠れていて、自分が情けなかった。
明くる日、私たちは講義をサボって、一日中家で映画を観ながら過ごした。
恋愛映画の途中で突然ハルが号泣し、それがいつまでもやみそうにないから、わりと焦って、気分転換にホラー映画を再生して、あまりの怖さに二人して本気でビビって、一つの布団に身を寄せあって。たぶん、幸せってこういうことをいうのだと思う。
次の日もハルは家に泊まった。その次の日も、また次の日も。
そうやって一日ずつ、たくさんの言い訳を並べながら、彼女の滞在を許容していって。気がつけば、長い月日が経っていた。
二十歳に出会った私たちは、今年で三十になる。
***
「ねえ、志乃さん! あたし犬飼いたい」
平日の朝はとにかく時間がない。出勤までの道のりを、どれだけ短縮できるかが勝負となる。
すっかり昼夜逆転した生活を送っているハルは、毎朝飽きもせずにだる絡みしてくる。もはやルーティンの一部となりつつあるそのイベントを、私は華麗に無視して、せっせとタスクをこなしていく。
キッチンに立って、棚からマグカップを取りだし、天然水を注いだそれにビタミンCの錠剤を溶かす。無理にご飯を詰め込むと、通勤の列車のなかで吐き気を催すことは目に見えているから、朝はこれだけで済ませるのが習慣になっている。
堅苦しいスーツを着るのは最後にして、次にメイクとヘアセット。
ドレッサーの前に腰かけたところに、隣からハルの腕が伸びてくる。
「見てよこれ! めっちゃ可愛くない?」
彼女の手に握られたスマホの画面に映るのは、ポメラニアンが飼い主とじゃれあっている様子を撮った、ショートムービー。
「動画で見るぶんにはね」
「そんなことないって! こんな子が家にいたらさ、すっごく癒されると思わない? 志乃さんだって、もっと仕事頑張れるかもだよ」
私は大仰にため息を吐く。ハルの衝動性には、幾度となく振り回されてきた。
少なくとも、一時の感情に踊らされて選択するべきことではないと思うし、どうせ毎日の散歩は私の役目になることだろう。
「うちのマンションはペット駄目でしょ?」
私は苛つきながら、もっともな指摘をする。忘れたとは言わせない。
「なら、また引っ越せばいいじゃない」
ハルは臆する様子もなく、当然のようにそう言った。軽薄な態度が、さらに私の苛立ちに拍車をかける。
「そう簡単に言わないでよ。今のところ予定はないし、次に引っ越す時があったなら、それはあんたとの別離を示してる」
「つまんない冗談やめてよね。もう何度も聞いたって、それ」
そうだ、これも。もう何度も交わしたやり取り。ハルからすれば、私が示す拒絶は、わざわざ気に留める必要もないくらい日常に浸透してしまったのだ。
「次の休みはさ、ペットショップに行こうよ。とりあえず見るだけでいいから! ね?」
ハルがめげずに話しかけてくる。
私は「ん、そうね」と適当にあしらって、鏡に映る憂鬱な顔をした自分を見つめた。
下地を塗って、ファンデーションを叩いて、ペンシルで眉毛を描く。簡潔に化粧を済ませると、最後に着替えをする。いつも着ているシンプルなスーツ。指先で摘んだストッキングをみじめに引きあげているこの時間が、何よりも億劫だと思う。
全ての身支度を終えた私は、玄関でパンプスを履きながら、これまた定型になった台詞を吐いた。
「じゃあ行ってくるから、留守番お願いね」
「はーい」と間延びした返事を受けて、私は扉の外に出た。
最寄り駅まで徒歩十五分。プラットホームで列車を待つ。四月の生温い風が肌を撫でる。
数分後に到着した列車に乗り込む。通勤の満員電車は何年経験しようが慣れないし、慣れたくもない。
車体が揺れて、誰かの靴を思わず踏んでしまって、「すみません」と小声で謝る。車内を満たす熱気。伝わる他人の憂鬱。抑鬱気分。最低な一日の始まり。
息苦しいな、と私は思う。
そうして次に、家で寛いでいるだろうハルのことを思う。
彼女は今まで一度も働いたことがない。大学四年時に就活で挫折したらしく、それ以来バイトも何もしていない。
私がさり気なく就職について促す度、「今は少し、難しい時期なの」とハルは言った。案の定、その難しい時期とやらは十年経っても続いている。
そういえば、私の学生時代の夢は専業主婦だった。早くに結婚して、社会から距離を置いて、家庭のことに専念したかった。
むろん家事を軽んじているわけではないけれど、それでも他人の心情を図りながら、社会のなかで生きていく方がよほど難儀に感じていた。
なんでこうなってしまったのだろう。どうして、ハルのポジションにいるのが私でないのだろう。
途中駅で列車の扉が開いて、多くの人が乗り込んできた。車内はより圧迫し、他人の体に触れざるを得ないほどになる。
ああ、息苦しいな。また一つ、私の胸中のわだかまりが増えていく。毎日、毎日毎日毎日毎日毎日。同じことの繰り返しで。憂鬱で、気怠い。水で薄めたような、漠然とした死にたさがいつまでも消えない。
***
日曜日。
私とハルは、大型モールの一角にあるペットショップの前にいた。
ハルがガラス越しの子犬に駆け寄っていく。まるで子どもみたいに。ウェーブをかけたピンク髪がゆらゆらと揺れる。彼女は週一で美容院に通い、綺麗なハイトーンを維持している。
改めて外でハルのことを見ていると、彼女は本当に老けないなと思う。制服を着れば、余裕で高校生に見えそうなくらい。幼い顔の造形も、滑らかな肌も、出会った頃から何も変わらない。それに比べて私は……。
「わぁー、かわいいー!」
ハルが感嘆の声をあげて、私に手招きする。周りの視線が痛い。仕方なく重い足を動かす。
「なあに、嬉しいの? すごい尻尾振ってるね?」
ハルが隣で、チワワの子犬に甘ったるい声で話しかける。すると、ここぞとばかりに若い女性の店員が近寄ってきた。
「よかったら抱っこしてみますか?」
「え、いいですか?」
すかさずハルが食いつく。店員に促されるまま、私たちは近くのソファに並んで座り、膝に毛布をあてがわれた。裏に戻った店員がショーケースのなかに現れ、さっきの子犬を抱えて戻ってくる。彼女は、ハルの太ももの上にそっと子犬を乗せてくれた。
「この子はモモちゃんっていうんです。生後二ヶ月なんですよ」
「そうなんですねー」
ハルは店員に愛想良く相槌を打つと、さっそく目の前の子犬に向き直り、その名前を呼んだ。
「モモちゃん!」
呼ばれたのに気がついたのだろうか。モモちゃんは、ハァハァと舌を出し、まん丸な黒目でじっとハルを見つめる。
「ああ、どうしよ。ほんと可愛い」
ハルはモモちゃんの背を撫でながら、大袈裟なリアクションとともに顔を綻ばせる。
「ポメがいいんじゃなかったっけ?」
なぜだかモモちゃんに対して嫉妬心湧いてきた私は、わざと水を差してやった。
「そうなんだよね。でも、実際ここ来てこの子見たらビビっときちゃった。運命だよ」
「何度も言うようだけどさ、うちではペット飼えないんだからね? 今日は見に来ただけなんでしょ?」
ハルはぷくっと頬を膨らませ、瞳を潤ませた。
「そんな顔してもだめ」
いつもハルの我儘に押し負けてきた私だけれど、今回ばかりは絶対に許容できない。費用だって馬鹿にならないし、長年の責任が伴うことだし、何よりこの子に愛情を注げる自信がない。
「どうされますか?」
傍で私たちのやり取りを見ていた店員が、 ハルの方だけに視線をやって、問いかけてくる。
私はハルが何か言おうとする気配を感じ取って、すぐに口を開いた。
「すみません。もう少し考えます」
未だガラス越しの小動物たちに食いつくハルを引きずるようにして、私はペットショップを離れた。
その後私たちは、お手洗いを済ませ、フードコートで簡単な食事を摂り、ディナーの時間まで暇をつぶすことにした。夜はハルの希望で、駅前のホテルの最上階にある高級なビュッフェのプランを奮発して予約したのだ。
気になる店舗を一通り巡って(主にハルのための)洋服や雑貨を物色し、ゲーセンでクレーンゲームに興じた。「どうせ確率機だよ」と私が忠告するのも聞かず、ハルは目当てのぬいぐるみを狙い続けた。そして、私の財布からは予算外の五千円が散った。
ハルはまだ遊び足りずに、ゲーセンの隅に設けられたカプセルトイを回している。ビーズをあしらった女児向けのアクセサリー。
「あー、ダブっちゃった」
ハルがカプセルを開くと、またさっきと同じビーズのブレスレット。
「ねえ、もう懲りたでしょ?」
私がため息を吐くと、ハルは笑顔でこちらにブレスレットを差しだした。
「あげる。お揃いだね?」
「ん、そうね」
私は渋々といった感じで、安っぽいブレスレットを手首につける。
かっちりしたジャケットに不似合いなそれが、どうしようもなく愛しい。
***
スケルトンのエレベーターで一気に最上階まで上がる。受付に予約の旨を伝えると、スムーズになかへ通された。
軽いドレスコートの注意はあったものの、店内には案外ラフな格好の客が多くて安心する。
窓際の予約席に案内された私たちは、向かい合わせに座る。すぐ横にはライトアップされた綺麗な夜景。ビル群の隙間を縫うように、テールランプの明かりが流れている。
やってきたウエイトレスに、アルコールの注文を聞かれ、せっかくだからと白ワインを頼む。
二時間のビュッフェ。私たちはテーブル下の籠に鞄を置き、一緒に料理を取りにいく。
しっかりサラダから取る私に対して、ハルはもうメイン料理のコーナーにいた。ピザやパスタやチキン、フライドポテトなど好きなものだけをプレートに載せている。そんな彼女を横目に見ながら、早死にしそうだよなあ、とか思う。
一通り食べたいものを取って、互いに席に戻り、私たちは手を合わせる。ちょうどウエイトレスが冷えたワインをワゴンに載せてやってきて、それぞれのグラスに注いでくれた。
慣れない乾杯。下手なグラスの持ち方をするハルに庇護欲が湧く。
「このパスタ美味しいよ」
「うん」
「志乃さんも食べてね」
「うん」
アルコールで、ハルの肌がまだらに赤くなる。呼気が僅かに荒くなっているのが分かる。
「ここ高かったしちゃんと元取ろうね」と言い合って、私たちは周りの目も気にせず、もくもくと食べ進めていった。ハルは、小さな口に見合わない量を詰め込んだせいで、ハムスターみたいに頬が膨れている。
ふと、「時々考えるんだよね」と私は口を滑らせてしまう。酔いにやられたということにしてほしい。「なあに」とハルが聞くから、後悔するも手遅れで、私はくだらない思考をそのまま零す。「結婚できない、セックスもしない私たちは、何のために一緒にいるんだろうって」
ハルは興味もなさそうに頬杖をついて、夜景を眺めている。
「なにそれ。志乃さん、頭でも打っちゃった?」
「だって、そうでしょ? 私たちを繋いでるものって、言えば二十歳の時に交わした脆い約束に過ぎないわけじゃない?」
「えーと、なんか約束……したっけ?」
傷心するのを自覚しながら、私は気丈に振る舞う。
「……忘れたの? ハルが言ったんだよ。自分の傍からいなくならないでくれって。私はそれに渋々頷いて、だから今があるんでしょ」
私の言葉に、あはは、とハルが可笑しそうに笑った。
「学生時代のうわ言に深い意味なんかないって。あたしたちもういい歳だよ? 志乃さんってやっぱり面白いね?」
もういい歳だなんて、どの口が言うんだよ。胸に募った怒りの感情は、もちろん声に出せない。出しちゃいけない。
「ごめん。私、酔ってると思う」
「分かってる。大丈夫だよ」
ハルがデザートを取りに行き、皿にタルトやケーキ、シュークリーム、マカロンその他諸々を山盛りにして戻ってきた。
案の定と言うべきだろう。最初こそ美味しそうに食べていた彼女だけれど、途中でぱたんとフォークをもつ手を止めてしまった。
「食べれるぶんだけ取らなきゃ」と今更に私は言う。
「だって食べれると思ったもん」
「ねえ、残しちゃだめ」
「じゃあ志乃さん食べてよ」
「うん」
ハルがこちらに皿ごと押しやる。
デザートはぐちゃぐちゃに混ざりあい、食べかけのシフォンのスポンジには、ピンクのグロスがついていた。
フォークでまとめて串刺しにして、無理やり呑み込む。甘すぎて気持ち悪い。吐き気がする。苦味が欲しくてワインを呷る。
次にハルに目線をやった時、彼女はうたた寝していた。
***
やりがいの感じられない事務の仕事は一日八時間、週五日。そして寝るだけの土曜日と、ハルと遊びに興じる日曜日。
ずっとその繰り返し。ただ日々を積み重ねていくだけ。まあ、人生ってそんなものなのかもしれないけれど。
ハルと出会わなかった世界線の私がいるとするなら、もっと消極的な日々を送っていることだろう。
四月の日曜は残り三回あって、私はその全部をハルに捧げた。ピクニックに行きたいと言いだした彼女に付き合って朝早くからサンドイッチを作ったし、脱出ゲームに参加して苦手な謎解きに頭をつかったし、水族館に行ってライトアップされたクラゲのエリアで写真を撮った。
やがて、憂鬱な五月がやってくる。すでに梅雨入りの気配がしていた。心做しか、街全体が色褪せて見えた。
五月は毎年気分が沈むから、私はこの時期が嫌いだ。五月病という言葉があるくらいだし、自殺率も高いらしいし、上手く外向きの表情が繕えなくても許してほしい。
今日も私はハルのだる絡みを受け流し、重たい足を引きずりながら、どうにか駅のプラットホームまで辿り着く。
ホームに入ってきた列車が停車する。満杯の車内に体をすべりこませる。例のごとく途中駅で、通勤の人々がどっと乗り込んできて、私は壁にぐっと押しやられる。
脳内を空っぽにして圧迫感に耐えていると、不意に、内腿に何かが当たった。少なくとも人の手ではない。硬い物質。恐らくは誰かの鞄。不快ではあったけれど、状況的に仕方がない。
私はどうにか首を捻って、車内に設置されたディスプレイを見あげる。この列車は急行だから、次の駅に止まるまでにはまだ時間があった。
数秒後、私は内腿の不快感が明確な悪意によるものだと知る。後ろに立つ誰かが、太腿に差し込んだ通勤鞄を、ぐりぐりと上方にやっている。それで、タイトスカートの裾がずりあがる。
身の毛もよだつ恐怖で、もうそちらに目を向けられない。太い指がストッキング越しに私の足を撫でるのが分かる。気持ち悪い。どうしよう。いや分かってる。今すぐにその汚らわしい手を引っ掴み、「痴漢です!」と叫ぶべきだ。
……けれど、私の手は動かない。さっきから幾度も脳内でイメージトレーニングをしているのに、実際に行動には移せない。
動悸が早くなり、目に涙が滲む。訳も分からない悔しさで、唇を噛み締める。
誰も私の苦しみに気がついてくれない。私と同様に、気づいていても行動に移せないだけなのかもしれない。だとすれば、私はそんな誰かを責められない。
みんな自分が一番大事だ。分かってる。分かってるよ。他人のことなんかどうでもいいよな。私だってそうだよ。
途方もなく長い時間に感じられた。次の停車駅で私はすぐに車内から降りた。もちろん会社の最寄りではない。ただ、あの場から一刻も早く離れたかった。
電波を確保するために、地下鉄のホームから外に出る。
もう出勤時刻には間に合わないけれど、仕方ない。今からすぐに遅刻の連絡を入れよう。でも、なんて? 素直に痴漢されましたって言う? 同僚にはどう思われるだろう? どうして自らを辱めなくちゃいけないんだ?
私は思い直し、スマホの電源を切った。まだ内腿には耐えがたい不快さが残っていた。人生全てが馬鹿馬鹿しい。なんで私、生きてるんだろう。
何だか家に帰る気にはなれなかった。たぶん私は、ハルに仕事を飛んだことを知られたくなかった。幻滅されるんじゃないかと怖かった。
だから、そのまま意味もなく知らない土地を彷徨う。人気のない路地で電柱を蹴飛ばしてみる。普通に痛い。後でトイレで確認したら、足の爪が内出血を起こして黒ずんでいた。
近くのデパートに立ち寄って、来月のことなんか考えずにカードを切る。ほとんどがハルへのお土産だった。返済できずに困ったら? 死ねばいい。それで万事解決でしょ?
***
何だか電車に乗るのが怖くなってしまって、馬鹿みたいな距離を徒歩で帰宅した。足の筋肉が痙攣を起こしている。
帰りが遅れた言い訳を考えながら、私は部屋の扉を開けた。
「ただいま」
返事がない。玄関で靴を脱ぎ、リビングに直行する。いない。寝室の扉を開ける。
あ、いた。
ハルは、寝室の隅につくったゲーミングスペースにいた。電気は点いておらず、パソコンのキーボードとファンが放つ虹色の光がチカチカして目に痛い。
彼女は耳にヘッドフォンをつけ、手にコントローラーをもち、最近ハマっているらしいFPSゲームに熱中していた。誰かと話している様子だった。前に言ってたネッ友だろう。
彼女は楽しそうに喋りながら銃を乱射して、時折思いだしたように、机上に置かれたエナドリ缶を片手にストローで吸う。未だ、こちらに気づく様子がない。よほど熱中しているらしい。
「ねえ、ハル」
試しに呼びかけてみるけれど、気づかない。
「ただいま」
まだ気づかない。
「ねえってば!」
たまらずハルの肩を揺する。それで彼女はびくっと体を震わせ、「ちょっとごめん」と言ってからヘッドフォンを外す。
「なんだ、志乃さんいたの。おかえり」
敵の銃弾でハルが死ぬ。画面が真っ暗になって、リスポーン地点に戻る。
私は衝動的に、ヘッドフォンのコードを引き抜いた。
「今すぐそいつと縁切って」
「え?」
「え、じゃなくてさ。縁切れって言ってる」
ハルが一瞬眉根を寄せる。それからすぐ、傷ついたように笑う。
「どうしたの? 普段そんなこと言わないじゃん」
「煩いな。ずっと思ってたよ。我慢してただけ」
私は喉奥の熱を呑み込んで、泣きそうになるのを堪えた。
「私だけでいいじゃん。なにが不満なの? ずっとハルのために尽くしてきたのに、こんなのってないよ!」
「いやいや、なにが? ねえ意味分かんない。今の志乃さん変だよ」
ハルが私を否定している。どうして? 分からない。私には結局、彼女の考えていることなんて何も分からない。でも。
「ハルはいいよね」
ぽろりと言葉が零れた。一度口にしてしまえば、もう手遅れだった。次から次に残虐な思いが溢れだして止まらなくなる。
「悩みとかなさそうじゃん。生きづらさとか感じたことないんでしょ? どんな思いで私が毎日働いて、あんたを養ってきたと思う? 私が朝起きてまず、決まって脳裏に過ぎるのは、会社に欠勤の連絡を入れようかってことなんだよ。今日くらい仮病で休んでも許されるよね、って私のなかの悪魔が囁くの。でもね、一度そうやって甘えると、二度目三度目って歯止めが効かなくなるし、そうしたら日々の生活が立ちいかなくなる。だから私はその誘惑になんとか抗って、布団から這いでるわけ。億劫な朝の準備を済ませて、外に出て、他人に圧迫されて、小さなミスを引きずってるうちに取り返しのつかないことになって、自分より年下の子の方がずっと優秀で、情けなくなって、へとへとで帰宅したらすぐに明日が来る。生き地獄だよ。生きてる全部が苦しいんだよ。ねえ、あんたばっか楽してずるい。他人の善意を搾取するくらいしか能がないくせに、生きやすそうでずるい」
早口に捲し立てたせいで、軽い息切れを起こす。
本当は、こんなことが言いたいわけじゃない。ハルに私を必要としてほしいだけだ。こんな私にも存在価値があるんだって、だから生きていてもいいんだって、ちゃんと、私自身に分からせてほしいだけだ。
「なにそれ。じゃあ、あたしのこと追いだせば?」
ハルが事もなげに言う。いつものふわふわした甘さは見る影もなく、彼女の伏せられた目はこちらを軽蔑しているようだった。
「……は?」
予想外の返事に面食らって、苛立ちが募った。
怒りと悲しみは似ているな、と思う。発露される方法が違うだけで、その本質はきっと同じ場所にある。
「この家にあたしを置いてるのは志乃さんでしょ?」とハルが乾いた声音で続けた。「ほら、早く言いなよ。あたしに出てけって。そうすれば気が済むんでしょ?」
「違うよ、ハル。ただ、私の辛さを分かってもらいたくて。生きるのが辛いのはお互い様でしょ? ねえ一緒に頑張ろうよ。せめて家事くらいはしてほしい。ちゃんとまともに生きてほしい」
ハルが口もとだけで笑う。それは嘲っているようにも、悲しんでいるようにも見える。確かなのは、彼女が今この瞬間、私に幻滅したらしいこと。
「あー、そう。よく分かったよ。志乃さんは、あたしがなんも考えずにふらふら生きてるだけだと思ってんだ? 怠けてるだけだって」
「別にそんなつもりじゃ……。私はただ――」
私の言葉を遮って、ハルはほとんど叫ぶみたいに言った。
「志乃さんはあたしのなにを知ってんの? 自分一人が苦しいみたいな顔してさ、被害者意識ばっか強いのうざすぎ。そんなん言われるなら、あたし死ぬわ。志乃さん曰く、あたしは他人の善意を踏みにじる害悪なんだもんね? こんなのが生きてたって社会のお荷物だもんね?」
「やめてよ、ハル。違うよ」
ガタン、と乱暴な音が鳴る。ハルはパソコンの電源を落とし、ゲーミングチェアから立ちあがる。壁のスイッチを押して照明をつけ、次に彼女は部屋のクローゼットからキャリーケースを取りだす。
「……なにしてるの?」
ハルは私の質問を無視して、床にケースを広げると、そのなかに自分の持ち物を次々に投げ込み始めた。
「これ以上迷惑かけないし、安心して? あたしたち十年近く一緒にいたけどさ、結婚してるわけでもないし、この家から出てけばどうせ他人だからね」
身体に寒気が走る。現状に頭が追いついていかなくて、心臓がドクドクと鳴って、胸がキリキリと痛む。
このまま、呆然と立ち尽くしていいのか? 私は自問する。
ううん、いい訳がない。ふわふわと続いてきた私たちの関係性だけれど、こんなに痛ましい終わり方をするなんて嫌だ。
いつもはマイペースなハルが、せっせと私物を詰めていく。リビングと脱衣所を行き来して、最低限のパッキングを済ませる。
「ちょっと待ってよ」
ハルはキャリーケースを引きずりながら、すたすたと玄関に向かってしまう。素足のままミュールに足を入れ、ドアの取っ手を掴む。
ここが瀬戸際だった。
「ねえ、お願い。私が全部悪かったから、ごめん。行かないで」
私はみっともなく彼女に縋る。その背中にしがみついて、涙を溢れさせる。
「うん、知ってる」
ハルがすっと、ノブにかけていた手を放した。それから、こちらを振り返る。なぜだか口角が緩やかに上がっていた。細められた目はどこまでも優しい。
「へ?」
私は安堵と困惑で、腑抜けた声を出す。
くずおれる私を、華奢な腕が支える。ハルがすぐ隣でにこやかに笑う。
「志乃さんは、ぜったいあたしから離れられないんだって知ってる」
続くハルの言葉が、真っ直ぐに私を捉えた。次いで、呪いみたいに脳裏から離れなくなった。
「ごめんね? 冗談だからね。あたし怒ってないよ?」
ああ、救われた。涙が止まらない。
「そっか。私こそごめんね。ひどいこと、たくさん言った」
「ううん。大丈夫。あたしはいつだって、志乃さんの全部を許したげる」
ハルの手が背中に回る。彼女の腕のなかはあまりに脆い。
「この荷物は?」
ハルが私に問う。
玄関の周りには、帰宅した時に投げ出した買い物袋が散らばっていた。
「ハルが喜ぶと思って……コスメとか洋服とかいろいろ買ってきた。安かったんだよ。すごく。ほんとに」
「え、これ全部? 嬉しい。ありがとね」
「うん」
私たちは長い間、玄関で抱きしめあった。ハルが優しく頭を撫でてくれる。甘い声が、耳をくすぐる。
「志乃さん、愛してるよ」
「うん……私も」
***
翌日も早朝に起床した。
昨夜の気恥しさで、まともにハルと顔を合わせられないまま、私はスーツを着て外に出た。
会社の番号は着拒済みで、たぶんもう二度と行けない。いつかちゃんとハルにも伝えなくてはならないと分かっているけれど、臆病な私はこうしてしばらく出勤を装い続けるのかもしれない。
家の周辺を無駄に歩き回って、カフェに立ち寄り時間を潰す。
***
日が暮れる。そろそろ頃合いだ。私はマンションの自宅に足を向ける。何もしていない、という虚しさが胸を痛ませる。
帰宅した途端、パン! と弾けるようなクラッカー音に迎え入れられた。
うわあ、と私の口から驚きで情けない声が漏れる。
玄関に立ち尽くしていると、ハルに「本日の主役」というふざけたタスキをかけられた。そのまま頭にもおもちゃの冠を被せられる。
「志乃さん! 誕生日おめでとー!」
「え?」
脳内カレンダーで今日の日付を思いだす。五月二日。そうだ、私はこんな最低な時期に生まれてきたのだった。
「私、疲れててさ。ちょっと寝ていいかな……」
「だめだめ。一年に一回しかない記念すべき日でしょ? 覚悟しな。今夜は寝かさないぜ?」
ハルがおどけた口調で言いながら、私の腕を強引に引っ張っていく。
誕生日なんかめでたくも何ともないのに、微かに胸が踊っている。今年もまたハルとこの日を過ごせることが、結局は嬉しいのだと思う。
ハルに促されるままリビングに入る。盛大に散らかった室内に、私は思わず苦笑した。
今日私がいない間に準備したのだろう。カーテンレールやら照明やらにモールが巻きつけられ、床のあちこちに風船が落ちている。
毎年手作りのミサンガをくれたり、私の似顔絵を書いてくれたり、何だかんだ祝ってもらっていたけれど、こんなに本格的なのは今回が初めてかもしれない。
テーブルの上には、ワンホールのチョコレートケーキがあった。元は完成された市販のケーキだっただろうに、ハルが施したお菓子のデコレーションのせいで台無しになっている。
「ねえ、頑張ったの。食べてみてよ」
「うん」
テーブルに着く。用意されたフォークで一口食べる。
ああ、甘いな。
やっぱり甘いものは苦手だ。お菓子とクリームまみれのケーキも、何から何まで完璧に可愛いハルのことも、等しく苦手だ。
「どう? 楽しい?」
私は再び昨夜のことを思いだしていた。これはハルなりの励ましなのかもしれない。
「うん。最高の気分」
途端、今しかない、と私は思う。ちゃんとハルに伝えなければ。
「私、今の仕事辞めるね」
「なんで急に?」
「遠くに引っ越そうよ。気分転換にさ。犬は飼えないけど、ここより広いとこ」
「え、ほんと?」
「うん。まじで」
改めて現状を把握するために、辺りを見回す。
テーブルに散らかる食べ物の残骸も、部屋中を彩る百均の飾りつけも、きっと明日には全部ゴミになる。そうして、いつかは今日という日も、取るに足らない過去のワンシーンに成り果てる。
ハルと過ごしてきた十年ばかりの歳月が、私にとってあまりに重くて、甘くて、愛おしくて、そのことが切実なまでに悔しい。
「ねえ志乃さん」
「ん?」
何度も繰り返されてきたやり取り。
ハルは上目遣いに私を見あげると、お得意の愛らしい笑みを浮かべて言った。
「次の休みはどこに行こっか?」