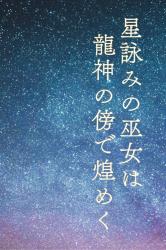「クローズ作業って、クソだりぃっすね」
バイト終わり、俺はバックヤードで愚痴を吐く。白無地のTシャツに着替えた片岡さんは、苦笑いを浮かべながら頷いた。
「分かる。やること多いもんね。終わらないと帰れないし」
「そうなんすよ。店長も早く帰りたがっているから、急かしてくるし」
うちのアイスクリーム屋は20時閉店だけど、すぐに帰れるわけではない。閉店後は、洗い物や清掃、レジ締めなどの雑務が待ち構えている。その作業が結構面倒くさいのだ。細かな手順も決まっているから、覚えるのも一苦労だった。
「20時閉店だと、高校生バイトでもクローズに入れられるもんね」
「ですね。片岡さんとクローズで一緒になること多いですもん」
「主婦パートさんは、夜はなかなかシフトに入れないからね。必然的に学生バイトが入ることが多くなるんだよ、うちの場合」
「なるほどー……」
クローズばかり任されているのは、そういう事情があったのか。確かに主婦パートさんなら、夕食の支度もあるだろうから夜に働くのは難しそうだ。それなら仕方がないのかもしれない。
クローズ作業は面倒だけど、嫌な事ばかりではない。クローズで入れば、バイト終わりは片岡さんと一緒に帰れる。店から駅まで喋りながら帰るのも、俺にとっては密かな楽しみだったりする。
「ほら、流星も早く着替えておいで」
「うぃっす」
片岡さんを待たせるわけにはいかない。俺は急いでアイスクリーム屋の制服を脱いだ。
◇
店長に小言を言われてから、俺と片岡さんは店を出る。外の空気は昼間の熱気を残しているせいで、むわっとしていた。冷房の効いた店内から外に出ると、余計に暑く感じる。じっとりと背中に汗をかきながら、賑やかな駅前の大通りを歩いた。
駅までは徒歩3分。普通に歩いたらすぐについてしまう。なるべく時間を引き延ばしたくて、わざとゆっくり歩いてみた。不自然なほどにちんたら歩いているのに、片岡さんは文句ひとつ言わずに歩幅を合わせてくれる。俺のしょうもない行動にも付き合ってくれるのは嬉しかった。
「あ」
コンビニの看板が視界に入ると、あることを思い出す。
「今日、親いないから飯買って帰らないといけないんだった」
「そうなんだ、仕事?」
「月に一度のデートっす。うちの親、俺から見ても引くほどラブラブで、月に一度は二人で出掛けてるんですよ」
「へぇ、素敵な夫婦だね」
片岡さんは、穏やかに微笑んだ。こういう時、揶揄われたり、引かれたりしないのは、結構嬉しい。口では「引くほど」なんて貶しているが、内心では誇らしく思っている。年を取っても仲が良いのは素敵なことだ。
「片岡さんちは、どんな感じなんですか?」
「あー、うちは母親と二人暮らしなんだー」
さらっと軽く告げられる。余計なことを言ってしまったようだ。
「なんか、すいません……」
「なんで謝るの? 今時、片親なんて珍しくもないでしょう」
俯く俺を、いつも通りの口調でフォローする。本当に気にしていないのか、平静を装っているのかは分からない。片岡さんの横顔からは、感情が読み取れなかった。
俺だけが気まずい空気を背負いながら歩いていると、あっという間に駅に着く。階段を登って、改札まで辿り着いたら、そこでお別れだ。気まずい空気のまま解散すると考えると、申し訳なくなった。
「じゃあね、流星。次シフト被るのは、一週間後かな?」
改札前で片岡さんがひらひらと手を振る。そこでハッと気付く。明後日から家族旅行だから、しばらくバイトを休むんだった。
「気を付けて帰るんだよ~」
爽やかな笑顔を向けられると、切なさが溢れ返る。一週間なんて、大した期間ではない。旅行に行ったら、あっという間に過ぎていくだろう。頭ではそう分かっているはずなのに、しばらく片岡さんの笑顔を見られないと思うと、胸の奥がぎゅうぎゅうと締め付けられた。
嫌だ。まだ帰りたくない。離れがたいと思うあまり、片岡さんのTシャツの裾を掴んでいた。
「流星?」
戸惑いを含んだ声が飛んでくる。自分でも驚いている。俺は一体何をしているんだ?
恥ずかしくて、顔を上げることすらできない。それでも、周囲の人々が改札前で立ち止まる俺達を、邪魔くさそうに避けていることには気付いた。
歩行者の邪魔にならないように、壁際まで片岡さんを押していく。おかしな行動だが、片岡さんは俺の誘導するままに足を進めた。壁際まで追い詰めると、顔を上げる。片岡さんは、驚いたようにこちらを凝視していた。
壁際で向かい合う俺達を見て、周囲の人々がひそひそと話す。「やだぁ、喧嘩?」「絡まれてるの? 可哀そう」なんて非難の声が飛んできた。傍から見れば、俺が片岡さんを恐喝しているように見えるのだろう。
どうしていつも誤解されてしまうんだ。本当はそんなつもりはないのに。恥ずかしさと情けなさが入り交じって泣きそうになった。
だけど、片岡さんだけは分かってくれた。俺を見つめる瞳は、温かかった。
「どうしたの?」
まるで子供から話を聞き出すように、優しく尋ねられる。そんな聞き方をされたら、否が応でも引きずり出されてしまう。
「なんか、もう少し、一緒にいたいなって……」
こんなことを言ったら、困らせてしまうのは分かっている。視線を落として、感情を読み取るのを遅らせた。
賑やかな駅にいるはずなのに、俺達だけが何もない空間に弾き飛ばされたようだ。周囲の音も視線も気にならない。それくらい頭がぼーっとしていた。顔を上げられずにいると、意外な言葉が降ってくる。
「それなら、うち来る? 今日、親夜勤でいないから」
◇
もう少し一緒にいたいと言ったものの、自宅に招かれるとは思わなかった。俺はガチガチに緊張しながら、片岡家の玄関に足を踏み入れる。
「お邪魔しまーす……」
蚊の鳴くような声で挨拶をすると、片岡さんに笑われた。
「そんなにかしこまらなくていいから。楽にしてて」
そうは言われたって、余所の家に来ることなんて滅多にないのだ。かしこまってしまうのも無理はない。俺はロボットのような動きで靴を脱ぎ、玄関の隅に揃えた。
片岡さんの家は、駅から徒歩10分の場所にある比較的新しい七階建てマンションだ。エントランスも綺麗だったが、玄関もすっきり片付いていた。生真面目な家主の性格が伺える。
「どうぞ入って」
「失礼しまーす……」
片岡さんに続いて、おっかなびっくり廊下を歩く。突き当りの部屋に通されると、背筋がグッと伸びた。白を基調としたダイニングキッチンは、すっきりと片付いている。テーブルに手紙やチラシが散乱していることもない。物自体も少ないように感じた。
帰ってきたばかりだから、部屋の中は蒸している。片岡さんが冷房のリモコンを操作する姿を、じっと眺めていた。
成り行きでついて来てしまったけど、これからどうしよう? 余所の家では、どう振舞うべきなのか分からなかった。
「そんな隅っこにいないで、ソファーにでも座ってて」
「はいっ」
言われるがまま部屋の奥にある布張りのソファーに腰掛ける。背筋を伸ばして置物のように固まっていると、片岡さんに再び笑われた。
「ホント、楽にしてていいから。そうだ、腹減ってるでしょ? 夕飯作るから待ってて」
「どええ!?」
予想外の言葉でおかしな声を上げてしまった。まさか夕飯までご馳走してくれるとは思わなかった。しかも、片岡さんのお手製だ。……食べたい。めっちゃ食べたいっ!
「ありがたくご相伴に預かりいたしつかまつり」
「だからかしこまり過ぎだってっ! 作るって言っても大したものじゃないから、期待しないでね」
いやいや、客人に料理を振舞えるだけでも凄いことだ。俺の作れる料理といえば、カップ麺かカップ焼きそばくらいなのだから。うん、料理ですらないな。
片岡さんは、手を洗ってから黒無地のエプロンを身につける。エプロン姿も様になっていて、思わず見入ってしまった。
「そんなに見つめられると、やりにくいなぁ」
「……お気になさらず」
俺は空気になることにした。キッチンに立つ片岡さんが、とん、とん、野菜を切ったり、じゅう、じゅう、肉を炒めたりする様子をぼーっと眺める。作業に無駄がない。これは普段から作り慣れている証拠だな。
トマトソースの香りに包まれると食欲が刺激されて、ぐうぅと腹の虫が鳴いた。フライパンの火を止めたタイミングで、電子レンジの音が鳴る。冷凍ご飯も、ほくほくに温まったようだ。深皿に盛りつけると、出来立ての料理がダイニングテーブルに運ばれてくる。俺は餌につられた犬のように、テーブルに駆け寄った。
「はい、できたよ。ミートご飯」
「ミート……ご飯!?」
聞き慣れない料理名に首を傾げる。深皿には、ひき肉と玉ねぎをトマトソースで炒めたものが乗っている。紛れもなくミートソースパスタの具だ。しかしその下に隠れていたのは白米だった。
「パスタじゃなくて、米なんすね」
「うん。俺、パスタより米派だから」
意外な組み合わせだが、なかなか美味しそうだ。スプーンを用意されると、向かい合わせに座って手を合わせた。
「いただきまーす」
「どうぞ、食べて、食べてー」
ミートソースと白米を一緒に掬って口に運ぶ。トマトソースの酸味とひき肉の肉汁が口の中で溶け合って「ん~っ」と唸った。
「めっちゃ美味いっす! ミートソースって、米にも合うんですね! パスタより、こっちの方が食べ応えがある」
「でしょ? パスタってすぐ腹減るから、こっちの方が食べた気がするんだよね。簡単だし、一人の時はよく作ってるんだ。大量に作っておけば、次の日の弁当にも使いまわせるし」
「なるほど!」
確かにこれなら、食べ盛りの男子高校生の腹も満たせる。パスタのように固くなってしまうこともないから、弁当にももってこいだ。ミートソースに新たな可能性に気付いた瞬間だった。
「ちなみにスライスチーズを乗せると、もっと美味くなるよ」
「マジすか?」
「マジマジ。やってみる?」
「お願いします!」
皿を差し出すと、片岡さんに回収される。冷蔵庫からスライスチーズを取り出してミートソースの上に乗せると、チーズを溶かすために電子レンジに入れた。
美味しいご飯までご馳走してもらい至れり尽くせりだ。俺は、ふぅと溜息をついた。
「それにしても、片岡さんって何でもできるんですね。仕事もできるし、頼りがいもあるし、優しいし、その上料理までできる。完璧じゃないっすか」
「そんなことないよー」
片岡さんは、かぶりを振りながら謙遜する。謙虚な振る舞いもポイントを上げた。
こういうの、なんて言うんだっけ? 片岡さんみたいなタイプを指す言葉があった気がする。すぐには思い出せず、うんうんと考え込んでいると、ハッと思い出す。
「そう、スパダリ! 片岡さん、スパダリじゃないですか! 俺、片岡さんの嫁になりたいくらいです!」
興奮気味に伝えたところで、電子レンジの音が鳴った。しかし、片岡さんは後ろを向いただけで、扉を開けることはなかった。
沈黙が走る。掛け時計の秒針だけが、時が動いていることを証明するように響き渡った。
ヤバイ。気に障るようなことを言ってしまったのかもしれない。片岡さんの表情が見えないからこそ、感情が読めなかった。とりあえず謝ろうとしたところで、片岡さんが先に言葉を発する。
「そういうこと、俺の前では言わない方がいいよ」
後ろを向いたまま、冷めた声で指摘される。その声色は、怒っているというよりは、諭されているように感じた。
どうしてそんな反応をされるのか分からない。呆然と固まっていると、片岡さんは振り返ることなく言葉を続けた。
「俺さ、男の人が好きなんだ」
え、と喉の奥から声が漏れる。その告白は、即座に飲み込めるようなものではなかった。手に持っていたスプーンをテーブルに落とす。けたたましい音が響くと、片岡さんはようやく振り返った。
「だからさ、あんまり気を持たせるようなこと言わない方がいいよ。俺みたいのに好かれたって困るでしょ?」
片岡さんは、笑っている。だけど、全然笑っているようには見えなかった。
笑っている時の顔は、とても正直だ。相手の感情がダイレクトに伝わって来る。ぎこちなく笑う片岡さんの表情からは、痛みのようなものが滲んでいた。
俺は、バイト先での片岡さんしか知らない。アイスクリーム屋の外に出た彼が、どんな人生を歩んでいるのか想像もつかなかった。そこに自分が立ち入る権利があるのかどうかも分からない。友達でも、家族でも、ましてや恋人でもない関係は、とてつもなく薄っぺらいものに感じた。
片岡さんの言葉を飲み込むには、十分すぎるほどの時間を与えられた。電子レンジのセンサーが反応して、再び音が鳴り響く。そこでようやく時間が動き出した。
「突然こんな話をされても困るよね。ごめん、忘れて」
痛々しい笑顔を浮かべたまま、話を終わらせようとする。これ以上立ち入るなと、線引きされたような気がした。
俺は、片岡さんの笑顔が見たくてバイトを始めた。一緒に働けているだけでも十分幸せだった。このまま何事もなかったかのように受け流せば、いつも通りバイト先でしょうもない話をする関係に戻れる。
だけど、それでいいのか? 今、片岡さんは、アイスクリーム屋では見せることのない表情を見せてくれた。勇気を振り絞ったのか、はたまた口が滑ったのかは分からないが、今の表情は誰にでも見せるものではない。俺だけに見せてくれたのだ。ここで曖昧な反応をしたら、もう二度と近付けなくなるような気がした。
俺は、片岡さんの笑顔が好きだ。もっと、ずっと、彼の笑顔を見ていたい。その笑顔の裏側に隠れているものも知りたかった。
「話を聞かせてくれませんか?」
片岡さんの笑顔が引っ込む。信じられないものを前にしたかのように目を見開いていた。ここで怯んではいけない。不安そうに揺らぐ瞳を真っすぐ捉えながら、想いを口にした。
「片岡さんのこと、もっと知りたいんです」
俺の見てきた世界は、とてつもなく狭いものだ。だからこそ、彼の世界を教えてほしかった。寄り添って、交わって、それでもなお一緒にいられたら、これほどまでに嬉しいことはない。
◇
ミートソースの上で溶けたチーズはとても美味しそうだったが、正直味はよく分からなかった。食事よりも、片岡さんの話に集中していた。
片岡さんは、俺と出会う前の出来事を明かしてくれた。初めて好きになった人が、男性の保育士さんだったこと。小学校高学年になって、自分は他の人と違うと気付いたこと。以降、誰を好きになっても想いを封じ込めてきたこと。話を聞いている中でも、片岡さんの葛藤が伝わってきた。
真っ白な羊の群れに、一匹だけ黒い羊が交っていたら警戒される。そう話す片岡さんの気持ちは、痛いほどよく分かった。
中学までは何事もなく群れに交じっていられたが、高一の夏に事件が起きた。バスケ部のチームメイトにふざけ半分でスマホの履歴を見られてしまったそうだ。そこで自分の性癖が明るみになった。何を見られたのかは話してくれなかったけど、内容はある程度察しがついた。
それ以降、チームメイトとの間で大きな溝ができてしまった。表立って揶揄われたり、拒絶されたりしたわけではない。そういう人が一定数いることは、みんなも理解していた。それでも、見えない何かで線引きをされたように感じた。今までは、しょうもない話をしながら笑っていたチームメイトから、ぎこちない笑顔を向けられる度に血の気が引いていった。
「俺と仲良くなったら、惚れられると思ったのかもね。そんなわけないのにね。別に男だからって、だれかれ構わず好きになるわけじゃない」
そう話す片岡さんは、やっぱり痛々しい笑顔を浮かべていた。俺は言葉を返すことができなかった。チームメイトと気まずくなってしまった結果、夏休みが終わる頃には部活を辞めた。
だけど部活を辞めたからといって、すべてが解決したわけでもない。バスケ部での出来事がどこまで広まっているのか分からなかった。クラスメイトから向けられる笑顔の裏に別の感情が含まれていると想像すると、目を見て話すことができなくなったそうだ。
居心地が悪くなった結果、学校以外の場所へ居場所を求めるようになった。それがアイスクリーム屋だった。バイト先としてアイスクリーム屋を選んだ理由は、家からも学校からも近かったからという理由があるが、それだけではない。女性が多い職場なら、誰かを好きになる心配がないと思ったからだ。
新しい居場所ができたことで、ようやく人と目を見て話せるようになった。だけど油断はできない。もう二度と居場所を失わないように、バイト先では完璧に振舞った。仕事の手順を頭に叩き込み、アイスクリームの種類を覚え、足手まといにならないようにしたそうだ。
何でもできると思っていた片岡さんが、莫大な時間をかけて完璧であろうとしていた事実を知って、心底驚いた。自宅や学校でバイトのことを考えている間も時給換算したら、ゲームでも服でも好きなだけ買えるほどの報酬が手に入ったに違いない。追い詰められた彼の気持ちを想像すると、胸が締め付けられた。
「……って、こんな話したら、また気まずくなっちゃうね。失敗したなぁ」
片岡さんは、相変わらず笑っている。だけどその裏では、叱られるのを待つ子供のように怯えて見えた。そんな彼を、今すぐ安心させてあげたい。
「俺は、距離取ったりしませんよ。これまで通り、片岡さんとしょうもない話をしていたいです」
嘘ではない。戸惑いがないといえば嘘になるけど、そんなことが原因で片岡さんとの間に溝を作りたくなかった。
生まれ持ったものが違うだけで社会から爪弾きにされてしまうことは、これまでの経験上よく分かっている。集団の中では、みんなと同じ色をしていないと警戒されてしまうのだ。そのせいで、散々嫌な思いをしてきた。多分、片岡さんも同じなのだろう。
そんなこと、なのだ。人より明るい髪色だって、同性を好きになることだって、些細なことだ。そんなことは、溝を作る原因にはならない。
「優しいね、流星は」
椅子から立ち上がった片岡さんが、食器をシンクに運ぶ。こちらには一切視線を向けてくれないから、感情が読み取れなかった。蛇口から水を出し、皿に溜める。水音が響く中、片岡さんは視線を落としたまま言葉を続けた。
「だけどもし、俺が流星のことを気になってるって言ったら?」
片岡さんの感情は相変わらず読み取れないが、冗談を言っているような口ぶりではなかった。
気になっている。
話の流れから、恋愛対象としてという意味だろう。理解するには幾分時間がかかった。
思いもよらぬ相手から恋心を打ち明けられたら、戸惑うのが普通の反応だ。相手が同性なら尚更。体のいい断り文句を探していたとしても不思議ではない。
だけど、俺の中に芽生えた感情は違った。
生まれて初めて好意を伝えられた。相手はずっと憧れていた人だ。自覚した瞬間、身体の奥底からエネルギーが沸き上がり、天まで飛んでいきそうな気分になった。
「そんなの、嬉しいに決まってるじゃないですか」
もう、誤魔化す必要なんてない。片岡さんの瞳を見据えながら、心の内を明かした。
「俺、片岡さんの笑顔に一目惚れして、アイスクリーム屋に通うようになったんです。バイトを始めたのも、無料で笑顔が見られるからです。片岡さんが俺のことを好きになってくれたら、もっとたくさん笑顔を見せてくれるってことですよね? そんなの最高じゃないですか」
大好きな笑顔を一番近くで見られる。これほどまでに喜ばしいことはない。
「だから、安心して好きになってくれていいですよ」
偽りのない笑顔で告げる。これまでは片岡さんとどうなりたいのか分からなかったが、今ならはっきり分かる。俺は、片岡さんの笑顔を見ていたいんだ。バイトの先輩後輩という枠を超えて、もっと近い存在になりたい。
片岡さんは、驚いたようにこちらを凝視している。告白紛いの言葉に戸惑っているのだろう。大きすぎる感情は、すぐには飲み込めない。長い時間をかけて、片岡さんは俺の言葉を飲み込んだ。
「ほんっとに……流星は……」
片岡さんは右腕で目元を隠している。泣いているようだけど、口元は笑っていた。多分、想いは伝わったのだろう。安堵したのも束の間、片岡さんが泣いているなんてただならぬ事態だと気付く。
「ティッシュ! ティッシュを持ってきますね!」
ローテーブルに置かれたティッシュを箱ごと掴んで、片岡さんに差し出す。ティッシュで目元を押さえている様子をソワソワと見守っていると、不意に目が合った。
「ありがとう、流星」
片岡さんは、笑っていた。その笑顔を目の当たりにした瞬間、またしても息の仕方を忘れた。緩く弧を描いた口元に、ほんのり上気した頬。瞳の奥には明らかに熱が宿っていた。その笑顔の正体に、ようやく気付いた。
身体が熱くて仕方がない。片岡さんの笑顔に、どんどん甘く溶かされていくようだ。恥ずかしいけど、目が離せない。それは向こうも同じようだった。
笑顔を引っ込めると、熱い眼差しだけが残る。まるで磁石に引き寄せられるように、片岡さんが距離を縮めてきた。
心臓が暴れまわって仕方がない。クーラーが効いた部屋にいるはずなのに、炎天下で立ち尽くしているかのようにびっしょりと汗をかいていた。浅い呼吸を繰り返していると、片岡さんの大きな手が俺の後頭部を包み込む。至近距離で瞳の奥を覗き込まれた途端、彼が何をしたいのか察した。
反射的に目を瞑る。男の人とキスをするなんて考えたことすらない。だけど片岡さんが相手なら、してみてもいいと思っていた。
身を固くして待っていたものの、いつまで経っても唇に触れる感触は伝わってこない。恐る恐る目を開くと、耳元に熱い吐息が触れた。
「もう遅いから帰りな。駅まで送ってく」
バイト終わり、俺はバックヤードで愚痴を吐く。白無地のTシャツに着替えた片岡さんは、苦笑いを浮かべながら頷いた。
「分かる。やること多いもんね。終わらないと帰れないし」
「そうなんすよ。店長も早く帰りたがっているから、急かしてくるし」
うちのアイスクリーム屋は20時閉店だけど、すぐに帰れるわけではない。閉店後は、洗い物や清掃、レジ締めなどの雑務が待ち構えている。その作業が結構面倒くさいのだ。細かな手順も決まっているから、覚えるのも一苦労だった。
「20時閉店だと、高校生バイトでもクローズに入れられるもんね」
「ですね。片岡さんとクローズで一緒になること多いですもん」
「主婦パートさんは、夜はなかなかシフトに入れないからね。必然的に学生バイトが入ることが多くなるんだよ、うちの場合」
「なるほどー……」
クローズばかり任されているのは、そういう事情があったのか。確かに主婦パートさんなら、夕食の支度もあるだろうから夜に働くのは難しそうだ。それなら仕方がないのかもしれない。
クローズ作業は面倒だけど、嫌な事ばかりではない。クローズで入れば、バイト終わりは片岡さんと一緒に帰れる。店から駅まで喋りながら帰るのも、俺にとっては密かな楽しみだったりする。
「ほら、流星も早く着替えておいで」
「うぃっす」
片岡さんを待たせるわけにはいかない。俺は急いでアイスクリーム屋の制服を脱いだ。
◇
店長に小言を言われてから、俺と片岡さんは店を出る。外の空気は昼間の熱気を残しているせいで、むわっとしていた。冷房の効いた店内から外に出ると、余計に暑く感じる。じっとりと背中に汗をかきながら、賑やかな駅前の大通りを歩いた。
駅までは徒歩3分。普通に歩いたらすぐについてしまう。なるべく時間を引き延ばしたくて、わざとゆっくり歩いてみた。不自然なほどにちんたら歩いているのに、片岡さんは文句ひとつ言わずに歩幅を合わせてくれる。俺のしょうもない行動にも付き合ってくれるのは嬉しかった。
「あ」
コンビニの看板が視界に入ると、あることを思い出す。
「今日、親いないから飯買って帰らないといけないんだった」
「そうなんだ、仕事?」
「月に一度のデートっす。うちの親、俺から見ても引くほどラブラブで、月に一度は二人で出掛けてるんですよ」
「へぇ、素敵な夫婦だね」
片岡さんは、穏やかに微笑んだ。こういう時、揶揄われたり、引かれたりしないのは、結構嬉しい。口では「引くほど」なんて貶しているが、内心では誇らしく思っている。年を取っても仲が良いのは素敵なことだ。
「片岡さんちは、どんな感じなんですか?」
「あー、うちは母親と二人暮らしなんだー」
さらっと軽く告げられる。余計なことを言ってしまったようだ。
「なんか、すいません……」
「なんで謝るの? 今時、片親なんて珍しくもないでしょう」
俯く俺を、いつも通りの口調でフォローする。本当に気にしていないのか、平静を装っているのかは分からない。片岡さんの横顔からは、感情が読み取れなかった。
俺だけが気まずい空気を背負いながら歩いていると、あっという間に駅に着く。階段を登って、改札まで辿り着いたら、そこでお別れだ。気まずい空気のまま解散すると考えると、申し訳なくなった。
「じゃあね、流星。次シフト被るのは、一週間後かな?」
改札前で片岡さんがひらひらと手を振る。そこでハッと気付く。明後日から家族旅行だから、しばらくバイトを休むんだった。
「気を付けて帰るんだよ~」
爽やかな笑顔を向けられると、切なさが溢れ返る。一週間なんて、大した期間ではない。旅行に行ったら、あっという間に過ぎていくだろう。頭ではそう分かっているはずなのに、しばらく片岡さんの笑顔を見られないと思うと、胸の奥がぎゅうぎゅうと締め付けられた。
嫌だ。まだ帰りたくない。離れがたいと思うあまり、片岡さんのTシャツの裾を掴んでいた。
「流星?」
戸惑いを含んだ声が飛んでくる。自分でも驚いている。俺は一体何をしているんだ?
恥ずかしくて、顔を上げることすらできない。それでも、周囲の人々が改札前で立ち止まる俺達を、邪魔くさそうに避けていることには気付いた。
歩行者の邪魔にならないように、壁際まで片岡さんを押していく。おかしな行動だが、片岡さんは俺の誘導するままに足を進めた。壁際まで追い詰めると、顔を上げる。片岡さんは、驚いたようにこちらを凝視していた。
壁際で向かい合う俺達を見て、周囲の人々がひそひそと話す。「やだぁ、喧嘩?」「絡まれてるの? 可哀そう」なんて非難の声が飛んできた。傍から見れば、俺が片岡さんを恐喝しているように見えるのだろう。
どうしていつも誤解されてしまうんだ。本当はそんなつもりはないのに。恥ずかしさと情けなさが入り交じって泣きそうになった。
だけど、片岡さんだけは分かってくれた。俺を見つめる瞳は、温かかった。
「どうしたの?」
まるで子供から話を聞き出すように、優しく尋ねられる。そんな聞き方をされたら、否が応でも引きずり出されてしまう。
「なんか、もう少し、一緒にいたいなって……」
こんなことを言ったら、困らせてしまうのは分かっている。視線を落として、感情を読み取るのを遅らせた。
賑やかな駅にいるはずなのに、俺達だけが何もない空間に弾き飛ばされたようだ。周囲の音も視線も気にならない。それくらい頭がぼーっとしていた。顔を上げられずにいると、意外な言葉が降ってくる。
「それなら、うち来る? 今日、親夜勤でいないから」
◇
もう少し一緒にいたいと言ったものの、自宅に招かれるとは思わなかった。俺はガチガチに緊張しながら、片岡家の玄関に足を踏み入れる。
「お邪魔しまーす……」
蚊の鳴くような声で挨拶をすると、片岡さんに笑われた。
「そんなにかしこまらなくていいから。楽にしてて」
そうは言われたって、余所の家に来ることなんて滅多にないのだ。かしこまってしまうのも無理はない。俺はロボットのような動きで靴を脱ぎ、玄関の隅に揃えた。
片岡さんの家は、駅から徒歩10分の場所にある比較的新しい七階建てマンションだ。エントランスも綺麗だったが、玄関もすっきり片付いていた。生真面目な家主の性格が伺える。
「どうぞ入って」
「失礼しまーす……」
片岡さんに続いて、おっかなびっくり廊下を歩く。突き当りの部屋に通されると、背筋がグッと伸びた。白を基調としたダイニングキッチンは、すっきりと片付いている。テーブルに手紙やチラシが散乱していることもない。物自体も少ないように感じた。
帰ってきたばかりだから、部屋の中は蒸している。片岡さんが冷房のリモコンを操作する姿を、じっと眺めていた。
成り行きでついて来てしまったけど、これからどうしよう? 余所の家では、どう振舞うべきなのか分からなかった。
「そんな隅っこにいないで、ソファーにでも座ってて」
「はいっ」
言われるがまま部屋の奥にある布張りのソファーに腰掛ける。背筋を伸ばして置物のように固まっていると、片岡さんに再び笑われた。
「ホント、楽にしてていいから。そうだ、腹減ってるでしょ? 夕飯作るから待ってて」
「どええ!?」
予想外の言葉でおかしな声を上げてしまった。まさか夕飯までご馳走してくれるとは思わなかった。しかも、片岡さんのお手製だ。……食べたい。めっちゃ食べたいっ!
「ありがたくご相伴に預かりいたしつかまつり」
「だからかしこまり過ぎだってっ! 作るって言っても大したものじゃないから、期待しないでね」
いやいや、客人に料理を振舞えるだけでも凄いことだ。俺の作れる料理といえば、カップ麺かカップ焼きそばくらいなのだから。うん、料理ですらないな。
片岡さんは、手を洗ってから黒無地のエプロンを身につける。エプロン姿も様になっていて、思わず見入ってしまった。
「そんなに見つめられると、やりにくいなぁ」
「……お気になさらず」
俺は空気になることにした。キッチンに立つ片岡さんが、とん、とん、野菜を切ったり、じゅう、じゅう、肉を炒めたりする様子をぼーっと眺める。作業に無駄がない。これは普段から作り慣れている証拠だな。
トマトソースの香りに包まれると食欲が刺激されて、ぐうぅと腹の虫が鳴いた。フライパンの火を止めたタイミングで、電子レンジの音が鳴る。冷凍ご飯も、ほくほくに温まったようだ。深皿に盛りつけると、出来立ての料理がダイニングテーブルに運ばれてくる。俺は餌につられた犬のように、テーブルに駆け寄った。
「はい、できたよ。ミートご飯」
「ミート……ご飯!?」
聞き慣れない料理名に首を傾げる。深皿には、ひき肉と玉ねぎをトマトソースで炒めたものが乗っている。紛れもなくミートソースパスタの具だ。しかしその下に隠れていたのは白米だった。
「パスタじゃなくて、米なんすね」
「うん。俺、パスタより米派だから」
意外な組み合わせだが、なかなか美味しそうだ。スプーンを用意されると、向かい合わせに座って手を合わせた。
「いただきまーす」
「どうぞ、食べて、食べてー」
ミートソースと白米を一緒に掬って口に運ぶ。トマトソースの酸味とひき肉の肉汁が口の中で溶け合って「ん~っ」と唸った。
「めっちゃ美味いっす! ミートソースって、米にも合うんですね! パスタより、こっちの方が食べ応えがある」
「でしょ? パスタってすぐ腹減るから、こっちの方が食べた気がするんだよね。簡単だし、一人の時はよく作ってるんだ。大量に作っておけば、次の日の弁当にも使いまわせるし」
「なるほど!」
確かにこれなら、食べ盛りの男子高校生の腹も満たせる。パスタのように固くなってしまうこともないから、弁当にももってこいだ。ミートソースに新たな可能性に気付いた瞬間だった。
「ちなみにスライスチーズを乗せると、もっと美味くなるよ」
「マジすか?」
「マジマジ。やってみる?」
「お願いします!」
皿を差し出すと、片岡さんに回収される。冷蔵庫からスライスチーズを取り出してミートソースの上に乗せると、チーズを溶かすために電子レンジに入れた。
美味しいご飯までご馳走してもらい至れり尽くせりだ。俺は、ふぅと溜息をついた。
「それにしても、片岡さんって何でもできるんですね。仕事もできるし、頼りがいもあるし、優しいし、その上料理までできる。完璧じゃないっすか」
「そんなことないよー」
片岡さんは、かぶりを振りながら謙遜する。謙虚な振る舞いもポイントを上げた。
こういうの、なんて言うんだっけ? 片岡さんみたいなタイプを指す言葉があった気がする。すぐには思い出せず、うんうんと考え込んでいると、ハッと思い出す。
「そう、スパダリ! 片岡さん、スパダリじゃないですか! 俺、片岡さんの嫁になりたいくらいです!」
興奮気味に伝えたところで、電子レンジの音が鳴った。しかし、片岡さんは後ろを向いただけで、扉を開けることはなかった。
沈黙が走る。掛け時計の秒針だけが、時が動いていることを証明するように響き渡った。
ヤバイ。気に障るようなことを言ってしまったのかもしれない。片岡さんの表情が見えないからこそ、感情が読めなかった。とりあえず謝ろうとしたところで、片岡さんが先に言葉を発する。
「そういうこと、俺の前では言わない方がいいよ」
後ろを向いたまま、冷めた声で指摘される。その声色は、怒っているというよりは、諭されているように感じた。
どうしてそんな反応をされるのか分からない。呆然と固まっていると、片岡さんは振り返ることなく言葉を続けた。
「俺さ、男の人が好きなんだ」
え、と喉の奥から声が漏れる。その告白は、即座に飲み込めるようなものではなかった。手に持っていたスプーンをテーブルに落とす。けたたましい音が響くと、片岡さんはようやく振り返った。
「だからさ、あんまり気を持たせるようなこと言わない方がいいよ。俺みたいのに好かれたって困るでしょ?」
片岡さんは、笑っている。だけど、全然笑っているようには見えなかった。
笑っている時の顔は、とても正直だ。相手の感情がダイレクトに伝わって来る。ぎこちなく笑う片岡さんの表情からは、痛みのようなものが滲んでいた。
俺は、バイト先での片岡さんしか知らない。アイスクリーム屋の外に出た彼が、どんな人生を歩んでいるのか想像もつかなかった。そこに自分が立ち入る権利があるのかどうかも分からない。友達でも、家族でも、ましてや恋人でもない関係は、とてつもなく薄っぺらいものに感じた。
片岡さんの言葉を飲み込むには、十分すぎるほどの時間を与えられた。電子レンジのセンサーが反応して、再び音が鳴り響く。そこでようやく時間が動き出した。
「突然こんな話をされても困るよね。ごめん、忘れて」
痛々しい笑顔を浮かべたまま、話を終わらせようとする。これ以上立ち入るなと、線引きされたような気がした。
俺は、片岡さんの笑顔が見たくてバイトを始めた。一緒に働けているだけでも十分幸せだった。このまま何事もなかったかのように受け流せば、いつも通りバイト先でしょうもない話をする関係に戻れる。
だけど、それでいいのか? 今、片岡さんは、アイスクリーム屋では見せることのない表情を見せてくれた。勇気を振り絞ったのか、はたまた口が滑ったのかは分からないが、今の表情は誰にでも見せるものではない。俺だけに見せてくれたのだ。ここで曖昧な反応をしたら、もう二度と近付けなくなるような気がした。
俺は、片岡さんの笑顔が好きだ。もっと、ずっと、彼の笑顔を見ていたい。その笑顔の裏側に隠れているものも知りたかった。
「話を聞かせてくれませんか?」
片岡さんの笑顔が引っ込む。信じられないものを前にしたかのように目を見開いていた。ここで怯んではいけない。不安そうに揺らぐ瞳を真っすぐ捉えながら、想いを口にした。
「片岡さんのこと、もっと知りたいんです」
俺の見てきた世界は、とてつもなく狭いものだ。だからこそ、彼の世界を教えてほしかった。寄り添って、交わって、それでもなお一緒にいられたら、これほどまでに嬉しいことはない。
◇
ミートソースの上で溶けたチーズはとても美味しそうだったが、正直味はよく分からなかった。食事よりも、片岡さんの話に集中していた。
片岡さんは、俺と出会う前の出来事を明かしてくれた。初めて好きになった人が、男性の保育士さんだったこと。小学校高学年になって、自分は他の人と違うと気付いたこと。以降、誰を好きになっても想いを封じ込めてきたこと。話を聞いている中でも、片岡さんの葛藤が伝わってきた。
真っ白な羊の群れに、一匹だけ黒い羊が交っていたら警戒される。そう話す片岡さんの気持ちは、痛いほどよく分かった。
中学までは何事もなく群れに交じっていられたが、高一の夏に事件が起きた。バスケ部のチームメイトにふざけ半分でスマホの履歴を見られてしまったそうだ。そこで自分の性癖が明るみになった。何を見られたのかは話してくれなかったけど、内容はある程度察しがついた。
それ以降、チームメイトとの間で大きな溝ができてしまった。表立って揶揄われたり、拒絶されたりしたわけではない。そういう人が一定数いることは、みんなも理解していた。それでも、見えない何かで線引きをされたように感じた。今までは、しょうもない話をしながら笑っていたチームメイトから、ぎこちない笑顔を向けられる度に血の気が引いていった。
「俺と仲良くなったら、惚れられると思ったのかもね。そんなわけないのにね。別に男だからって、だれかれ構わず好きになるわけじゃない」
そう話す片岡さんは、やっぱり痛々しい笑顔を浮かべていた。俺は言葉を返すことができなかった。チームメイトと気まずくなってしまった結果、夏休みが終わる頃には部活を辞めた。
だけど部活を辞めたからといって、すべてが解決したわけでもない。バスケ部での出来事がどこまで広まっているのか分からなかった。クラスメイトから向けられる笑顔の裏に別の感情が含まれていると想像すると、目を見て話すことができなくなったそうだ。
居心地が悪くなった結果、学校以外の場所へ居場所を求めるようになった。それがアイスクリーム屋だった。バイト先としてアイスクリーム屋を選んだ理由は、家からも学校からも近かったからという理由があるが、それだけではない。女性が多い職場なら、誰かを好きになる心配がないと思ったからだ。
新しい居場所ができたことで、ようやく人と目を見て話せるようになった。だけど油断はできない。もう二度と居場所を失わないように、バイト先では完璧に振舞った。仕事の手順を頭に叩き込み、アイスクリームの種類を覚え、足手まといにならないようにしたそうだ。
何でもできると思っていた片岡さんが、莫大な時間をかけて完璧であろうとしていた事実を知って、心底驚いた。自宅や学校でバイトのことを考えている間も時給換算したら、ゲームでも服でも好きなだけ買えるほどの報酬が手に入ったに違いない。追い詰められた彼の気持ちを想像すると、胸が締め付けられた。
「……って、こんな話したら、また気まずくなっちゃうね。失敗したなぁ」
片岡さんは、相変わらず笑っている。だけどその裏では、叱られるのを待つ子供のように怯えて見えた。そんな彼を、今すぐ安心させてあげたい。
「俺は、距離取ったりしませんよ。これまで通り、片岡さんとしょうもない話をしていたいです」
嘘ではない。戸惑いがないといえば嘘になるけど、そんなことが原因で片岡さんとの間に溝を作りたくなかった。
生まれ持ったものが違うだけで社会から爪弾きにされてしまうことは、これまでの経験上よく分かっている。集団の中では、みんなと同じ色をしていないと警戒されてしまうのだ。そのせいで、散々嫌な思いをしてきた。多分、片岡さんも同じなのだろう。
そんなこと、なのだ。人より明るい髪色だって、同性を好きになることだって、些細なことだ。そんなことは、溝を作る原因にはならない。
「優しいね、流星は」
椅子から立ち上がった片岡さんが、食器をシンクに運ぶ。こちらには一切視線を向けてくれないから、感情が読み取れなかった。蛇口から水を出し、皿に溜める。水音が響く中、片岡さんは視線を落としたまま言葉を続けた。
「だけどもし、俺が流星のことを気になってるって言ったら?」
片岡さんの感情は相変わらず読み取れないが、冗談を言っているような口ぶりではなかった。
気になっている。
話の流れから、恋愛対象としてという意味だろう。理解するには幾分時間がかかった。
思いもよらぬ相手から恋心を打ち明けられたら、戸惑うのが普通の反応だ。相手が同性なら尚更。体のいい断り文句を探していたとしても不思議ではない。
だけど、俺の中に芽生えた感情は違った。
生まれて初めて好意を伝えられた。相手はずっと憧れていた人だ。自覚した瞬間、身体の奥底からエネルギーが沸き上がり、天まで飛んでいきそうな気分になった。
「そんなの、嬉しいに決まってるじゃないですか」
もう、誤魔化す必要なんてない。片岡さんの瞳を見据えながら、心の内を明かした。
「俺、片岡さんの笑顔に一目惚れして、アイスクリーム屋に通うようになったんです。バイトを始めたのも、無料で笑顔が見られるからです。片岡さんが俺のことを好きになってくれたら、もっとたくさん笑顔を見せてくれるってことですよね? そんなの最高じゃないですか」
大好きな笑顔を一番近くで見られる。これほどまでに喜ばしいことはない。
「だから、安心して好きになってくれていいですよ」
偽りのない笑顔で告げる。これまでは片岡さんとどうなりたいのか分からなかったが、今ならはっきり分かる。俺は、片岡さんの笑顔を見ていたいんだ。バイトの先輩後輩という枠を超えて、もっと近い存在になりたい。
片岡さんは、驚いたようにこちらを凝視している。告白紛いの言葉に戸惑っているのだろう。大きすぎる感情は、すぐには飲み込めない。長い時間をかけて、片岡さんは俺の言葉を飲み込んだ。
「ほんっとに……流星は……」
片岡さんは右腕で目元を隠している。泣いているようだけど、口元は笑っていた。多分、想いは伝わったのだろう。安堵したのも束の間、片岡さんが泣いているなんてただならぬ事態だと気付く。
「ティッシュ! ティッシュを持ってきますね!」
ローテーブルに置かれたティッシュを箱ごと掴んで、片岡さんに差し出す。ティッシュで目元を押さえている様子をソワソワと見守っていると、不意に目が合った。
「ありがとう、流星」
片岡さんは、笑っていた。その笑顔を目の当たりにした瞬間、またしても息の仕方を忘れた。緩く弧を描いた口元に、ほんのり上気した頬。瞳の奥には明らかに熱が宿っていた。その笑顔の正体に、ようやく気付いた。
身体が熱くて仕方がない。片岡さんの笑顔に、どんどん甘く溶かされていくようだ。恥ずかしいけど、目が離せない。それは向こうも同じようだった。
笑顔を引っ込めると、熱い眼差しだけが残る。まるで磁石に引き寄せられるように、片岡さんが距離を縮めてきた。
心臓が暴れまわって仕方がない。クーラーが効いた部屋にいるはずなのに、炎天下で立ち尽くしているかのようにびっしょりと汗をかいていた。浅い呼吸を繰り返していると、片岡さんの大きな手が俺の後頭部を包み込む。至近距離で瞳の奥を覗き込まれた途端、彼が何をしたいのか察した。
反射的に目を瞑る。男の人とキスをするなんて考えたことすらない。だけど片岡さんが相手なら、してみてもいいと思っていた。
身を固くして待っていたものの、いつまで経っても唇に触れる感触は伝わってこない。恐る恐る目を開くと、耳元に熱い吐息が触れた。
「もう遅いから帰りな。駅まで送ってく」