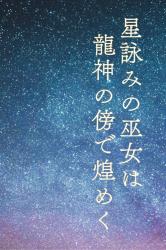「片岡さん、プレート書くの上手くないっすか?」
「そう?」
チョコペンを持った片岡さんが、小首を傾げながら微笑む。手元には、アイスケーキに乗せるチョコプレートがあった。表面には丸みを帯びた文字で「ゆみちゃん」と書かれている。後ろには、にこちゃんマークも描き添えられていた。
うちのアイスクリーム屋では、お誕生日用のアイスケーキも販売しており、チョコプレートは従業員が手作りしている。予約時にプレートに書く名前を伺い、引き渡し時までに作成するのだ。
ちなみに、「ゆみちゃん」へのバースデイケーキの予約は俺が受けた。小学校低学年の可愛らしい女の子が、うきうきしながらケーキを選んでいたのを覚えている。
「ケーキ開けて、このプレート見たら、絶対喜びますよ」
「うん、そうだといいね」
片岡さんは、目を細めながら微笑んでいる。きっとケーキを受け取る「ゆみちゃん」を想像しているのだろう。お客さんを思いながら丁寧に仕事をするのも、片岡さんの素敵なところだ。
出来上がったプレートを、ケーキにそっと乗せると、華やかなバースデイケーキが完成した。あとは冷凍庫で保管をして、お客さんが引き取りに来るのを待つだけだ。一仕事終えてホッとしていると、目の前にチョコペンが差し出される。
「せっかくだし、流星も書いてみる?」
「え? 俺が!?」
まさかそういう展開になるとは思わなかった。これは困ったことになったぞ。何を隠そう、俺は美術が2だ。字だって上手い方ではない。自信なんてなかった。チョコペンを凝視して警戒していると、片岡さんは肩をすくませながら笑う。
「無理強いはしないけどさ、流星だっていずれプレートを書くだろうから、今のうちに練習しておいた方がいいんじゃない?」
それは一理ある。いずれやって来るプレートデビューに備えて、練習しておくに越したことはない。おっかない店長の前で罵倒されながらデビューするよりは、優しい片岡さんの前で練習しておいた方が良さそうだ。
「分かりました。やってみます」
「本物のプレートを使うわけにはいかないから、ペーパータオルの上で練習してね」
「ういっす」
意気込みを見せて、チョコペンを受け取る。いざ、書こうとしたものの手が止まった。
「なんて書けばいいですか?」
「んー、そうだねぇ……。じゃあ、ひろとくんで」
「誰っすか?」
「俺の名前だよ!」
片岡さんって、ひろとくんっていうのか! 知らなかった! 片岡さんの名前となれば、手を抜くわけにはいかない。気合を入れて、チョコペンを握り直した。
◇
数分後。俺はまたしても、自分の無能さを思い知ることとなる。
「こりゃ酷いな……」
「あー、うーん……。そうだね……」
いつもはフォローしてくれる片岡さんですら、今回ばかりは残念そうに目を細めていた。無理もない。ペーパータオルに描かれた文字は、風に吹かれたようにヘロヘロ。文字の大きさもまちまち。にこちゃんマークなんて、狂気に満ちていた。
「片岡さんのバースデイケーキにこのプレートが付いていたら、どう思いますか?」
「ちょっと悲しくなるかな」
「ですよね……」
俺だって、バースデイケーキにこのプレートが付いていたら悲しくなる。つくづく自分のダメさ加減を思い知らされた。
「俺って、本当に使えないですね……」
プレートに限った話ではない。バイトを始めて一ヶ月が経とうとしているが、店長にはいまだに怒られてばかりだ。片岡さんにも迷惑ばかりかけている。最近の仕事ぶりを思い返すと、情けなくなった。
「そんな落ち込まないで。使えないなんてことないって。流星、最近はスクープも上手くなったし、確実に成長してるよ」
そう言われると、ちょっと救われる。確かに最初の頃よりは、スクープに慣れてきたように思える。以前のように、何度も掬ったり削ったりを繰り返してグラム調整をすることもなくなった。そんな変化を見ていてくれていたなんて驚きだ。
「俺のこと、ちゃんと見ていてくれたんですね」
「そりゃあ、そうだよ。大事な後輩だからね」
顔を覗き込まれながら、ふわりと微笑みかけられる。優しい笑顔を目の当たりにして、胸の奥がジーンと熱くなった。
「ありがとうございます。ひろとくん」
何気なく下の名前で呼んでみると、キョトンとした視線を向けられる。数秒の沈黙が流れた後、片岡さんは耳まで真っ赤にして照れ始めた。
「ど、どっ、どうしたの急に!?」
「片岡さんこそ、どうしたんすか?」
名前で呼んだだけなのに、なぜそこまで照れるのか。片岡さんは、頭を抱えながら「うー」だの「あー」だの訳の分からないことを口にしていた。名前で呼ばれたのが、そんなに嬉しかったのか?
取り乱している様子をしばらく見守っていると、片岡さんはショーケースを開けて、レモンシャーベットをスプーンで掬った。
「ねえ、もう一回言って?」
シャーベットを差し出しながら、おかわりを要求する。顔は相変わらず真っ赤で、瞳の奥には熱が宿っていた。
いくらテイスティングとはいえ、自らの欲のために店のアイスを利用するのはいかがなものか。文句を言いたくなったが、スプーンに乗ったアイスが溶けてきたため、こっちが折れることになった。
「……ひろとくん」
名前を呼ぶと、口にアイスを突っ込まれる。甘酸っぱくて美味しい。さっぱりとしたレモンの風味で口の中がいっぱいになった。目の前にいる片岡さんが蕩けたような顔をしているから、余計にアイスの味が甘くなったように感じる。やっぱり名前で呼ばれるのは嬉しいようだ。俺も片岡さんから「流星」と呼ばれた時は、嬉しさのあまりスキップをしていたから、人のことはとやかく言えないけど。
とはいえ、片岡さんの周りには名前で呼んでくれる女子もいるだろう。爽やかイケメンな上に、優しくて気遣いもできるのだ。女子が放っておくはずがない。
「片岡さんって、彼女いるんですか?」
「うん、いるよー」
「はあああ!? どこのどいつだ!」
いけない。うっかり罵声を浴びせてしまった。取り乱した姿を見て、片岡さんはふふっと吹き出した。
「ごめん、嘘。本当はいない」
「な、なんだ。嘘っすかぁ……」
嘘だと知って、ホッとしている自分がいる。片岡さんに彼女がいようが俺には関係ないはずなのに。感情の波に戸惑っていると、片岡さんからも質問される。
「流星は? 彼女とかいるの?」
「俺っすか? ないない、生まれてこのかたできたことないです」
「えー、流星、面白いし、綺麗な顔しているからモテそうなのに」
面白い? それに綺麗? 俺が? そんなことを言ってくれるのは片岡さんくらいだ。学校では怖い人扱いされ、ろくに話しかけられることすらないのに。
「全然モテませんから。そもそも俺の場合は、この外見のせいでみんなから怖がられているんで」
正直に学校での惨状を白状すると、片岡さんは納得するように頷いた。
「あーあ……まあ、それは分かる気がするな。流星って、圧があるからね」
ほら、片岡さんにも怖いって思われていた。仕方のないことだけど、直接言われると少なからずショックを受けている自分がいる。だけど片岡さんの話は、そこでは終わらなかった。
「でも、流星と話すようになってからは、怖いとは思わなくなったよ。一緒にいると楽しいし、頑張り屋だし、優しい子だってちゃんと分かったから」
ああ、この人はどうして俺の欲しいものを、こうも的確に差し出してくれるのだろう。そんな風に言われたら、どんどん好きになっちゃうじゃんか。学校では怖がられていても、ここに来れば受け入れてもらえる。そう思うだけで心が軽くなった。
「それに……」
「それに?」
片岡さんは言葉に詰まらせる。聞き返したものの、わざとらしくはぐらかされた。
「やっぱこれは内緒」
「なんでですか?! 気になるじゃないっすか!」
はぐらかされると余計に気になる。追求すべく、胸ぐらを掴んでジリジリと壁に追い詰めた。
「何を言おうとしたんですか?」
「内緒だって!」
「さっさと白状してください」
押し問答を繰り広げていると、カウンターにやってきた三上さんにギョッとした目で見られる。
「うっわ……ミントくんが片岡くんを恐喝してる」
「してないです!」
慌てて胸ぐらから手を離す。解放された片岡さんは、ホッと胸を撫で下ろした。依然として白い目を向けてくる三上さんに弁解する。
「俺はただ、片岡さんの口を割らせようと思っただけで」
「それを恐喝っていうんだよ」
「そうじゃなくて!」
両手を忙しなく動かしながら無罪を主張していると、片岡さんが声を押し殺しながら笑い始めた。
「やっぱ流星って、面白い」
どうやらツボに入ったらしい。肩を振るわせながら笑っている姿を見ると、こちらも表情が緩んだ。
片岡さんの笑っている顔は好きだ。この顔が見たくて、俺はバイトを始めたんだ。この一ヶ月で、十分すぎるほどの報酬を貰った気がする。楽しそうに笑っている片岡さんをしみじみと眺めていると、不意に目が合う。すると、先ほどまでとは違う笑い方をされた。
「俺は、好きだよ。ここで流星としょうもない話をしているの。学校にいる時よりもずっと楽しい」
その表情を見た瞬間、俺は息の仕方を忘れた。緩く弧を描いた口元に、ほんのり上気させた頬。瞳の奥には僅かに熱が宿っている。その表情を向けられたのは二度目だ。あの時と同じように、俺の心臓は激しく鼓動していた。
なんだこれは? 身体が熱くて仕方がない。笑顔一つでこんなにも心をかき乱されるなんて、俺はおかしいのかもしれない。
「お、俺も、片岡さんと話すの楽しいです……」
視線を泳がせながら、返事をする。恥ずかしくて片岡さんの顔が見られなくなった。俯いていると、蚊帳の外になっていた三上さんが口を開く。
「なに、この甘酸っぱい空気……」
そんな恋の始まりみたいな言い方をするのは、やめていただきたい。恥ずかしいし、片岡さんにも失礼だ。
俺は片岡さんが大好きだけど、片岡さんからすれば俺なんてただの後輩だ。男同士なんだし、恋に発展するはずがない。そう自覚しているはずなのに、受け止めきれない自分がいた。
なんだこれ? どうしてこんなにもどかしいんだ? これまでは誰かを好きになっても、その先の関係になりたいとは思わなかった。それなのに、今はバイトの先輩後輩という関係では物足りなくなっている。もっと近い存在になって、片岡さんの笑顔を独占したかった。
もやもやして仕方がない。さっき口に突っ込まれたレモンシャーベットのようなものを身体が欲している。さっぱりとしたものを摂取しないと、身体が茹ってしまいそうだ。
「あーあ、コンビニでサクレレモンでも買って帰るか」
「「……なんで?」」
何の脈絡のない発言に、二人から突っ込みが入ったのは言うまでもない。
「そう?」
チョコペンを持った片岡さんが、小首を傾げながら微笑む。手元には、アイスケーキに乗せるチョコプレートがあった。表面には丸みを帯びた文字で「ゆみちゃん」と書かれている。後ろには、にこちゃんマークも描き添えられていた。
うちのアイスクリーム屋では、お誕生日用のアイスケーキも販売しており、チョコプレートは従業員が手作りしている。予約時にプレートに書く名前を伺い、引き渡し時までに作成するのだ。
ちなみに、「ゆみちゃん」へのバースデイケーキの予約は俺が受けた。小学校低学年の可愛らしい女の子が、うきうきしながらケーキを選んでいたのを覚えている。
「ケーキ開けて、このプレート見たら、絶対喜びますよ」
「うん、そうだといいね」
片岡さんは、目を細めながら微笑んでいる。きっとケーキを受け取る「ゆみちゃん」を想像しているのだろう。お客さんを思いながら丁寧に仕事をするのも、片岡さんの素敵なところだ。
出来上がったプレートを、ケーキにそっと乗せると、華やかなバースデイケーキが完成した。あとは冷凍庫で保管をして、お客さんが引き取りに来るのを待つだけだ。一仕事終えてホッとしていると、目の前にチョコペンが差し出される。
「せっかくだし、流星も書いてみる?」
「え? 俺が!?」
まさかそういう展開になるとは思わなかった。これは困ったことになったぞ。何を隠そう、俺は美術が2だ。字だって上手い方ではない。自信なんてなかった。チョコペンを凝視して警戒していると、片岡さんは肩をすくませながら笑う。
「無理強いはしないけどさ、流星だっていずれプレートを書くだろうから、今のうちに練習しておいた方がいいんじゃない?」
それは一理ある。いずれやって来るプレートデビューに備えて、練習しておくに越したことはない。おっかない店長の前で罵倒されながらデビューするよりは、優しい片岡さんの前で練習しておいた方が良さそうだ。
「分かりました。やってみます」
「本物のプレートを使うわけにはいかないから、ペーパータオルの上で練習してね」
「ういっす」
意気込みを見せて、チョコペンを受け取る。いざ、書こうとしたものの手が止まった。
「なんて書けばいいですか?」
「んー、そうだねぇ……。じゃあ、ひろとくんで」
「誰っすか?」
「俺の名前だよ!」
片岡さんって、ひろとくんっていうのか! 知らなかった! 片岡さんの名前となれば、手を抜くわけにはいかない。気合を入れて、チョコペンを握り直した。
◇
数分後。俺はまたしても、自分の無能さを思い知ることとなる。
「こりゃ酷いな……」
「あー、うーん……。そうだね……」
いつもはフォローしてくれる片岡さんですら、今回ばかりは残念そうに目を細めていた。無理もない。ペーパータオルに描かれた文字は、風に吹かれたようにヘロヘロ。文字の大きさもまちまち。にこちゃんマークなんて、狂気に満ちていた。
「片岡さんのバースデイケーキにこのプレートが付いていたら、どう思いますか?」
「ちょっと悲しくなるかな」
「ですよね……」
俺だって、バースデイケーキにこのプレートが付いていたら悲しくなる。つくづく自分のダメさ加減を思い知らされた。
「俺って、本当に使えないですね……」
プレートに限った話ではない。バイトを始めて一ヶ月が経とうとしているが、店長にはいまだに怒られてばかりだ。片岡さんにも迷惑ばかりかけている。最近の仕事ぶりを思い返すと、情けなくなった。
「そんな落ち込まないで。使えないなんてことないって。流星、最近はスクープも上手くなったし、確実に成長してるよ」
そう言われると、ちょっと救われる。確かに最初の頃よりは、スクープに慣れてきたように思える。以前のように、何度も掬ったり削ったりを繰り返してグラム調整をすることもなくなった。そんな変化を見ていてくれていたなんて驚きだ。
「俺のこと、ちゃんと見ていてくれたんですね」
「そりゃあ、そうだよ。大事な後輩だからね」
顔を覗き込まれながら、ふわりと微笑みかけられる。優しい笑顔を目の当たりにして、胸の奥がジーンと熱くなった。
「ありがとうございます。ひろとくん」
何気なく下の名前で呼んでみると、キョトンとした視線を向けられる。数秒の沈黙が流れた後、片岡さんは耳まで真っ赤にして照れ始めた。
「ど、どっ、どうしたの急に!?」
「片岡さんこそ、どうしたんすか?」
名前で呼んだだけなのに、なぜそこまで照れるのか。片岡さんは、頭を抱えながら「うー」だの「あー」だの訳の分からないことを口にしていた。名前で呼ばれたのが、そんなに嬉しかったのか?
取り乱している様子をしばらく見守っていると、片岡さんはショーケースを開けて、レモンシャーベットをスプーンで掬った。
「ねえ、もう一回言って?」
シャーベットを差し出しながら、おかわりを要求する。顔は相変わらず真っ赤で、瞳の奥には熱が宿っていた。
いくらテイスティングとはいえ、自らの欲のために店のアイスを利用するのはいかがなものか。文句を言いたくなったが、スプーンに乗ったアイスが溶けてきたため、こっちが折れることになった。
「……ひろとくん」
名前を呼ぶと、口にアイスを突っ込まれる。甘酸っぱくて美味しい。さっぱりとしたレモンの風味で口の中がいっぱいになった。目の前にいる片岡さんが蕩けたような顔をしているから、余計にアイスの味が甘くなったように感じる。やっぱり名前で呼ばれるのは嬉しいようだ。俺も片岡さんから「流星」と呼ばれた時は、嬉しさのあまりスキップをしていたから、人のことはとやかく言えないけど。
とはいえ、片岡さんの周りには名前で呼んでくれる女子もいるだろう。爽やかイケメンな上に、優しくて気遣いもできるのだ。女子が放っておくはずがない。
「片岡さんって、彼女いるんですか?」
「うん、いるよー」
「はあああ!? どこのどいつだ!」
いけない。うっかり罵声を浴びせてしまった。取り乱した姿を見て、片岡さんはふふっと吹き出した。
「ごめん、嘘。本当はいない」
「な、なんだ。嘘っすかぁ……」
嘘だと知って、ホッとしている自分がいる。片岡さんに彼女がいようが俺には関係ないはずなのに。感情の波に戸惑っていると、片岡さんからも質問される。
「流星は? 彼女とかいるの?」
「俺っすか? ないない、生まれてこのかたできたことないです」
「えー、流星、面白いし、綺麗な顔しているからモテそうなのに」
面白い? それに綺麗? 俺が? そんなことを言ってくれるのは片岡さんくらいだ。学校では怖い人扱いされ、ろくに話しかけられることすらないのに。
「全然モテませんから。そもそも俺の場合は、この外見のせいでみんなから怖がられているんで」
正直に学校での惨状を白状すると、片岡さんは納得するように頷いた。
「あーあ……まあ、それは分かる気がするな。流星って、圧があるからね」
ほら、片岡さんにも怖いって思われていた。仕方のないことだけど、直接言われると少なからずショックを受けている自分がいる。だけど片岡さんの話は、そこでは終わらなかった。
「でも、流星と話すようになってからは、怖いとは思わなくなったよ。一緒にいると楽しいし、頑張り屋だし、優しい子だってちゃんと分かったから」
ああ、この人はどうして俺の欲しいものを、こうも的確に差し出してくれるのだろう。そんな風に言われたら、どんどん好きになっちゃうじゃんか。学校では怖がられていても、ここに来れば受け入れてもらえる。そう思うだけで心が軽くなった。
「それに……」
「それに?」
片岡さんは言葉に詰まらせる。聞き返したものの、わざとらしくはぐらかされた。
「やっぱこれは内緒」
「なんでですか?! 気になるじゃないっすか!」
はぐらかされると余計に気になる。追求すべく、胸ぐらを掴んでジリジリと壁に追い詰めた。
「何を言おうとしたんですか?」
「内緒だって!」
「さっさと白状してください」
押し問答を繰り広げていると、カウンターにやってきた三上さんにギョッとした目で見られる。
「うっわ……ミントくんが片岡くんを恐喝してる」
「してないです!」
慌てて胸ぐらから手を離す。解放された片岡さんは、ホッと胸を撫で下ろした。依然として白い目を向けてくる三上さんに弁解する。
「俺はただ、片岡さんの口を割らせようと思っただけで」
「それを恐喝っていうんだよ」
「そうじゃなくて!」
両手を忙しなく動かしながら無罪を主張していると、片岡さんが声を押し殺しながら笑い始めた。
「やっぱ流星って、面白い」
どうやらツボに入ったらしい。肩を振るわせながら笑っている姿を見ると、こちらも表情が緩んだ。
片岡さんの笑っている顔は好きだ。この顔が見たくて、俺はバイトを始めたんだ。この一ヶ月で、十分すぎるほどの報酬を貰った気がする。楽しそうに笑っている片岡さんをしみじみと眺めていると、不意に目が合う。すると、先ほどまでとは違う笑い方をされた。
「俺は、好きだよ。ここで流星としょうもない話をしているの。学校にいる時よりもずっと楽しい」
その表情を見た瞬間、俺は息の仕方を忘れた。緩く弧を描いた口元に、ほんのり上気させた頬。瞳の奥には僅かに熱が宿っている。その表情を向けられたのは二度目だ。あの時と同じように、俺の心臓は激しく鼓動していた。
なんだこれは? 身体が熱くて仕方がない。笑顔一つでこんなにも心をかき乱されるなんて、俺はおかしいのかもしれない。
「お、俺も、片岡さんと話すの楽しいです……」
視線を泳がせながら、返事をする。恥ずかしくて片岡さんの顔が見られなくなった。俯いていると、蚊帳の外になっていた三上さんが口を開く。
「なに、この甘酸っぱい空気……」
そんな恋の始まりみたいな言い方をするのは、やめていただきたい。恥ずかしいし、片岡さんにも失礼だ。
俺は片岡さんが大好きだけど、片岡さんからすれば俺なんてただの後輩だ。男同士なんだし、恋に発展するはずがない。そう自覚しているはずなのに、受け止めきれない自分がいた。
なんだこれ? どうしてこんなにもどかしいんだ? これまでは誰かを好きになっても、その先の関係になりたいとは思わなかった。それなのに、今はバイトの先輩後輩という関係では物足りなくなっている。もっと近い存在になって、片岡さんの笑顔を独占したかった。
もやもやして仕方がない。さっき口に突っ込まれたレモンシャーベットのようなものを身体が欲している。さっぱりとしたものを摂取しないと、身体が茹ってしまいそうだ。
「あーあ、コンビニでサクレレモンでも買って帰るか」
「「……なんで?」」
何の脈絡のない発言に、二人から突っ込みが入ったのは言うまでもない。