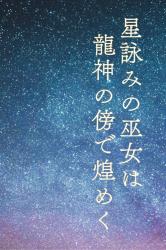「この店って、アイスの種類多すぎじゃないですか?」
お客さんの波が落ち着いた頃、俺はショーケースを恨めし気に眺めながら訴える。プラスチックスプーンの補充をしていた片岡さんは、手を止めて振り返った。
「30種類あるからね。定番が25種類で、期間限定が5種類」
「いや、多すぎでしょ」
フレーバーの種類が豊富なことが、この店のウリであることは分かっている。だけど新人バイトには、30種類のアイスは脅威でしかない。バイトを始めて三週間が経とうとしているが、いまだに全種類は把握していなかった。
頻繁に注文の入るフレーバーはすぐに分かるが、マイナーなフレーバーを注文されると時が止まる。お客さんの発した言葉を頼りに、目的のアイスを探す作業は毎回ヒヤヒヤものだ。いつまでも見つけられずにいると、お客さんの目も冷ややかになっていくから余計に怖い。後ろに列が形成されていようものなら目も当てられない。ショーケースだけでなく、店内が冷え冷えになった。そうなる前に片岡さんが助けてくれることがほとんどなのだけれど。
最近は、片岡さんとセットでシフトに入れられることが多くなった。店長が、俺の教育係に片岡さんを任命したからだ。店長は相変わらずおっかない人だけど、その点だけは感謝している。
「そう言えば、この前期間限定のトロピカルカーニバルの味を聞かれてテンパっていたよね?」
不意に前回の失敗を蒸し返されて、俺は顔をしかめる。30種類のアイスに迷ってしまうのは、お客さんも同様だ。悩んだ末、従業員に味を尋ねることも珍しくない。前回シフトに入った時は、運悪く俺が聞かれてしまったのだ。
「あの時、なんて答えてたんだっけ?」
「……陽気な感じで、とにかく美味いっすって」
「そうだった。お客さん、キョトンとしてたね」
まるで不思議な生き物と遭遇したかのようにこちらを見つめるお客さんの顔を思い出すと、申しわけなさで一杯になった。あの回答は0点だろう。
「流星もさ、ちゃんとおすすめできるようになった方が良いよ。いつもチョコミントしか食べないから、味が分かんないだよ」
「だって、好きなんですもん、チョコミント」
「他のアイスを頼もうとは思わないの?」
「あんまり」
他の味も嫌いではないけど、ショーケースの中でチョコミントを見つけると、つい選んでしまう。万人受けする味ではないとは分かっているけど、俺は好きだった。
「流星はこだわりが強いんだね」
「一途なんです」
ふん、と鼻息を荒くして答える。今の流れでは、全然誇れることではないけど。
「そういう片岡さんは、お客さんからアイスの味を聞かれても困らないんですか?」
「俺は一通り食べてるから、普通に答えられるよ」
「全部の味を知ってるんですか?」
「うん」
当たり前のことのように答えているが、30種類のアイスをすべて食べたことがあるなんて驚きだ。
「この浮気者がっ」
「なんでそうなるんだよっ」
わざとらしく罵倒すると、片岡さんはくくくっと喉の奥で笑う。その笑顔で、俺の頬も緩んだ。笑いが収まったところで、片岡さんの新情報が飛び込んでくる。
「俺の場合は、各フレーバーの特徴をノートにまとめてるよ」
「ノートに!?」
まさかノートにまとめるほど熱心に研究しているとは思わなかった。俺が想像していた以上に、片岡さんは真面目な性格なのかもしれない。
「そのノート、見せてくれませんか?」
じりじりと距離を詰めると、片岡さんは後退りする。
「目が怖いって! 今、持ってくるから待ってて!」
そう言い残すと、片岡さんは逃げるようにバックヤードに走った。数十秒後、A5サイズのノートを持って戻ってくる。表紙には、『フレーバーノート』と丁寧な文字で書かれていた。
「はい、どうぞ」
「あざっす」
さっそく拝読すると、まあ驚いた。1ページごとに各フレーバーの特徴がびっしり書かれていた。味の特徴、使われている材料、アレルギーの有無、ショーケース内での位置まで事細かに記されている。さらには色鉛筆で書かれたイラストまで添えられていた。
「片岡さん、ここに就職する気ですか? もしくは店長の座を狙ってるとか……」
尊敬を通り越して脅威を感じていると、片岡さんは苦笑いを浮かべながら両手を振る。
「違う、違う。やるからにはちゃんとやりたいだけだよ」
ただのバイトがここまでやるものなのか? このノートを作るために費やした時間を想像すると、ゾッとした。俺には到底真似できない。
「流石にここまでやれとは言わないけどさ、流星もアイスの味くらい知っていても良いんじゃない?」
「そっすかねぇ……」
「そうだよ。そういうわけだから、はい、あーん」
片岡さんはプラスチックスプーンでトロピカルカーニバルを掬い取ると、俺の前に差し出す。お言葉に甘えて、スプーンを口に含んだ。
「どう?」
「んまあ、美味いっす」
「もっと具体的に」
「……マンゴーとパインの味がして、甘酸っぱい感じ?」
何とか感想を捻り出すと、片岡さんの表情に笑顔が浮かぶ。
「そうそう! それなら伝わるよ」
正解を導き出せたようで、ホッとした。
「でも、チョコミントの方が美味いっす」
「ブレないなぁ、流星は」
片岡さんは、くくくっと喉の奥で笑った。またしてもツボに入ったらしい。俺のしょうもない発言が、片岡さんの笑顔に繋がるなら本望だ。
「流星、にやにやしてて怖いよ」
煩悩が顔に出てしまったようだ。いかん、いかん。きゅっと頬に力を入れて、にやけ顔を封じた。
「そういえば、片岡さんはバイトを始めてどれくらいなんですか?」
わざとらしく話題を逸らしたものの、とくに怪しまれることなく会話が進んでいく。
「10ヶ月くらいかな? 去年の秋ごろから始めたから」
「へぇ、もっと長くやっているのかと思いました」
仕事にも慣れているから、てっきり1年以上はやっているのかと思っていた。10ヶ月後には、俺も片岡さんと同等レベルに仕事ができるようになっているのだろうか? いや、難しいだろうな。尊敬の眼差しを向けていると、片岡さんは言葉を続ける。
「高一の夏までは部活やってたからね」
「何部だったんです?」
「バスケ部」
「あー、ぽいわー」
片岡さんは背が高いから、バスケをやっている姿は容易に想像がつく。運動神経も良さそうだし、活躍していたに違いない。
「なんで辞めちゃったんですか?」
何気なく尋ねたものの、返事はない。不審に思って表情を伺うと、片岡さんは眉を下げながら苦笑いを浮かべていた。
「んー、色々あってね」
これは、あまり踏み込んでほしくない時の反応だ。片岡さんの言う「色々」が何を指すのかは分からないが、興味本位で立ち入ってはいけないような気がした。
「そっすかぁ」
それ以上は追求しなかった。
最近は片岡さんと打ち解けてきたように思えたが、バイト以外での姿は何も知らない。俺はあくまでバイトの後輩で、友達なわけではない。そう自覚すると、ちょっと寂しくなった。
お客さんの波が落ち着いた頃、俺はショーケースを恨めし気に眺めながら訴える。プラスチックスプーンの補充をしていた片岡さんは、手を止めて振り返った。
「30種類あるからね。定番が25種類で、期間限定が5種類」
「いや、多すぎでしょ」
フレーバーの種類が豊富なことが、この店のウリであることは分かっている。だけど新人バイトには、30種類のアイスは脅威でしかない。バイトを始めて三週間が経とうとしているが、いまだに全種類は把握していなかった。
頻繁に注文の入るフレーバーはすぐに分かるが、マイナーなフレーバーを注文されると時が止まる。お客さんの発した言葉を頼りに、目的のアイスを探す作業は毎回ヒヤヒヤものだ。いつまでも見つけられずにいると、お客さんの目も冷ややかになっていくから余計に怖い。後ろに列が形成されていようものなら目も当てられない。ショーケースだけでなく、店内が冷え冷えになった。そうなる前に片岡さんが助けてくれることがほとんどなのだけれど。
最近は、片岡さんとセットでシフトに入れられることが多くなった。店長が、俺の教育係に片岡さんを任命したからだ。店長は相変わらずおっかない人だけど、その点だけは感謝している。
「そう言えば、この前期間限定のトロピカルカーニバルの味を聞かれてテンパっていたよね?」
不意に前回の失敗を蒸し返されて、俺は顔をしかめる。30種類のアイスに迷ってしまうのは、お客さんも同様だ。悩んだ末、従業員に味を尋ねることも珍しくない。前回シフトに入った時は、運悪く俺が聞かれてしまったのだ。
「あの時、なんて答えてたんだっけ?」
「……陽気な感じで、とにかく美味いっすって」
「そうだった。お客さん、キョトンとしてたね」
まるで不思議な生き物と遭遇したかのようにこちらを見つめるお客さんの顔を思い出すと、申しわけなさで一杯になった。あの回答は0点だろう。
「流星もさ、ちゃんとおすすめできるようになった方が良いよ。いつもチョコミントしか食べないから、味が分かんないだよ」
「だって、好きなんですもん、チョコミント」
「他のアイスを頼もうとは思わないの?」
「あんまり」
他の味も嫌いではないけど、ショーケースの中でチョコミントを見つけると、つい選んでしまう。万人受けする味ではないとは分かっているけど、俺は好きだった。
「流星はこだわりが強いんだね」
「一途なんです」
ふん、と鼻息を荒くして答える。今の流れでは、全然誇れることではないけど。
「そういう片岡さんは、お客さんからアイスの味を聞かれても困らないんですか?」
「俺は一通り食べてるから、普通に答えられるよ」
「全部の味を知ってるんですか?」
「うん」
当たり前のことのように答えているが、30種類のアイスをすべて食べたことがあるなんて驚きだ。
「この浮気者がっ」
「なんでそうなるんだよっ」
わざとらしく罵倒すると、片岡さんはくくくっと喉の奥で笑う。その笑顔で、俺の頬も緩んだ。笑いが収まったところで、片岡さんの新情報が飛び込んでくる。
「俺の場合は、各フレーバーの特徴をノートにまとめてるよ」
「ノートに!?」
まさかノートにまとめるほど熱心に研究しているとは思わなかった。俺が想像していた以上に、片岡さんは真面目な性格なのかもしれない。
「そのノート、見せてくれませんか?」
じりじりと距離を詰めると、片岡さんは後退りする。
「目が怖いって! 今、持ってくるから待ってて!」
そう言い残すと、片岡さんは逃げるようにバックヤードに走った。数十秒後、A5サイズのノートを持って戻ってくる。表紙には、『フレーバーノート』と丁寧な文字で書かれていた。
「はい、どうぞ」
「あざっす」
さっそく拝読すると、まあ驚いた。1ページごとに各フレーバーの特徴がびっしり書かれていた。味の特徴、使われている材料、アレルギーの有無、ショーケース内での位置まで事細かに記されている。さらには色鉛筆で書かれたイラストまで添えられていた。
「片岡さん、ここに就職する気ですか? もしくは店長の座を狙ってるとか……」
尊敬を通り越して脅威を感じていると、片岡さんは苦笑いを浮かべながら両手を振る。
「違う、違う。やるからにはちゃんとやりたいだけだよ」
ただのバイトがここまでやるものなのか? このノートを作るために費やした時間を想像すると、ゾッとした。俺には到底真似できない。
「流石にここまでやれとは言わないけどさ、流星もアイスの味くらい知っていても良いんじゃない?」
「そっすかねぇ……」
「そうだよ。そういうわけだから、はい、あーん」
片岡さんはプラスチックスプーンでトロピカルカーニバルを掬い取ると、俺の前に差し出す。お言葉に甘えて、スプーンを口に含んだ。
「どう?」
「んまあ、美味いっす」
「もっと具体的に」
「……マンゴーとパインの味がして、甘酸っぱい感じ?」
何とか感想を捻り出すと、片岡さんの表情に笑顔が浮かぶ。
「そうそう! それなら伝わるよ」
正解を導き出せたようで、ホッとした。
「でも、チョコミントの方が美味いっす」
「ブレないなぁ、流星は」
片岡さんは、くくくっと喉の奥で笑った。またしてもツボに入ったらしい。俺のしょうもない発言が、片岡さんの笑顔に繋がるなら本望だ。
「流星、にやにやしてて怖いよ」
煩悩が顔に出てしまったようだ。いかん、いかん。きゅっと頬に力を入れて、にやけ顔を封じた。
「そういえば、片岡さんはバイトを始めてどれくらいなんですか?」
わざとらしく話題を逸らしたものの、とくに怪しまれることなく会話が進んでいく。
「10ヶ月くらいかな? 去年の秋ごろから始めたから」
「へぇ、もっと長くやっているのかと思いました」
仕事にも慣れているから、てっきり1年以上はやっているのかと思っていた。10ヶ月後には、俺も片岡さんと同等レベルに仕事ができるようになっているのだろうか? いや、難しいだろうな。尊敬の眼差しを向けていると、片岡さんは言葉を続ける。
「高一の夏までは部活やってたからね」
「何部だったんです?」
「バスケ部」
「あー、ぽいわー」
片岡さんは背が高いから、バスケをやっている姿は容易に想像がつく。運動神経も良さそうだし、活躍していたに違いない。
「なんで辞めちゃったんですか?」
何気なく尋ねたものの、返事はない。不審に思って表情を伺うと、片岡さんは眉を下げながら苦笑いを浮かべていた。
「んー、色々あってね」
これは、あまり踏み込んでほしくない時の反応だ。片岡さんの言う「色々」が何を指すのかは分からないが、興味本位で立ち入ってはいけないような気がした。
「そっすかぁ」
それ以上は追求しなかった。
最近は片岡さんと打ち解けてきたように思えたが、バイト以外での姿は何も知らない。俺はあくまでバイトの後輩で、友達なわけではない。そう自覚すると、ちょっと寂しくなった。