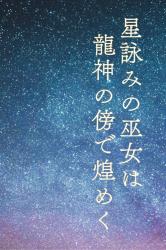アイスクリーム屋でバイトを始めてから、自分がいかに無能であるかを思い知らされた。バイトの面接を受け、採用の連絡を貰ったところまでは良かった。しかし、実際に働き始めてからは波乱の連続だった。
毎度、毎度、店長に怒られてばかり。前髪はキャップにしまえだの、声が小さいだの、敬語は正しく使えだの、おかしな挙動をするなだの……あとはもう、なんだか忘れた。とにかくうんざりするほど怒られた。
初めてのバイトだから仕方がないのかもしれないけど、それにしたって怒られ過ぎだ。店長は、どうにも俺にだけ厳しい気がする。どうせヤンキーだからきつく叱っても構わないと思われているのだろう。小心者の俺からすれば、店長からの罵声がナイフのように突き刺さる。バイトが終わった頃には満身創痍だ。
働くって大変だ。とはいえ、たったの二週間で辞めるわけにもいかない。シフトが入っている今日は、朝から憂鬱だった。出勤は16時から。15時過ぎには重い身体に鞭打って家を出た。
バイト先までは電車で20分ほどかかる。普段から通学で乗り降りしている駅だけど、制服姿の高校生がいない夏休み期間は別の場所のように感じた。重い足取りで駅を出て、賑わう大通りを歩くと、3分ほどで店に着く。パステルピンクの看板を恨めし気に見上げてから、店の自動ドアを通過した。
「おつかれさまっすー……」
カウンターにいる先輩への挨拶もそこそこに、従業員専用のバックヤードに向かう。店の奥にあるバックヤードは、大人が三人入れば身動きが取れなくなるほど狭い空間だった。その中に、勤怠を入力するパソコンやカーテンで仕切られた更衣室がある。店に来て、雑多な箱に収まる度に、うんざりした気分になった。
一つ溜息をついてから扉を開けると、コバルトブルーのキャップを被ったお兄さんと目が合った。その瞬間、ムスッとしていた俺の表情が甘く溶ける。目の前のお兄さんからも、にこっと微笑みかけられた。
「おはよう、流星。今日はシフト一緒だね」
お兄さん、もとい片岡さんだ。純度100%の笑顔を向けられた瞬間、沈んでいた心が一気に跳ね上がった。
「今日は片岡さんと一緒なんですね! 嬉しいですっ」
飼い主を見つけた犬のように飛びかかろうとすると、どうどうと肩を掴まれて静止される。
「喜びすぎだって。今日は店長休みだから、俺が流星の教育係を任されてるんだ」
「店長休みなんすね! よっしゃっ!」
「そこは喜ばないっ」
脳天にチョップを食らう。出勤して早々、怒られてしまった。でも片岡さんからの攻撃ならノーダメだ。
片岡さんがいるなら、今日は乗り切れそうだ。片岡さんとシフトが被ったのは二度目だが、既に絶対的な信頼を寄せている。
片岡さんは、とても面倒見が良い。前回もフォローされっぱなしだった。お客さんから声をかけられるだけでビビり散らす俺に代わって注文を伺い、レジの操作方法が分からずにフリーズした時は颯爽とヘルプに入り、手元が狂ってプラスチックスプーンを床にぶちまけた時は一緒に回収してくれた。その上、バイト終わりにはジュースを奢ってくれたのだ。まさに理想の先輩だ。
すっかり懐いた俺は、帰りもご一緒させてもらった。そこで片岡さんの基本情報も得た。年齢は俺の一個上で、高校二年生。この辺りでは偏差値の高い公立高校に通っている。自宅は駅の反対方向にあるらしく、バイト先には徒歩で通っているそうだ。
これはどうでもいい情報だが、俺が毎日アイスクリーム屋に通っていたせいで、従業員からは密かに「ミントくん」と呼ばれていたらしい。毎回チョコミントしか頼まなかったのが原因だ。知らぬ間にあだ名が付けられていたと知って、恥ずかしいやら腹立たしいやらで、しばらくは顔が上げられなかった。
駅までの道のりで、有益な情報も無益な情報もたくさん得た。もっと話をしたかったが、あっという間に改札に着いてしまう。名残惜しさを感じながらもお別れしようとすると、片岡さんから「バイバイ、流星」と手を振られた。その瞬間、血が湧き立つような興奮に襲われた。
聞き間違いではない。片岡さんは、俺のことを「流星」と呼んだ。店ではずっと「綾瀬くん」だったのに、駅まで向かう3分間で「流星」へとランクアップしたのだ。名前呼びをされたことで、一気に距離が縮まったような気がした。嬉しさのあまりホームでスキップをしていたら、近くにいたお姉さんにギョッとした目で見られたが、それもどうでもいい話だ。
前回の出来事を振り返りながらにまにましていると、片岡さんに背中を押される。
「ぼーっとしてないで、早く着替えておいで。もう時間ないよ」
現在の時刻は15時55分。稼働時間の16時まであと5分しかない。
「やばっ……すぐ着替えます」
更衣室に飛び込んで、Tシャツとハーフパンツを脱ぎ捨てた。アイスクリーム屋の制服に着替えてから鏡を見る。水色のポロシャツに、黒のスラックス。コバルトブルーの腰エプロンとキャップを身につければ、バイト戦士の完成だ。長めの前髪も、きちんとキャップに収めている。これなら文句はないだろう。カーテンを開けると、片岡さんに上から下までチェックをされた。
「ん、オッケー」
「あざっす」
身だしなみチェックをクリアしたところで、タイムカードを切る。よしっ、意気込んでからカウンターに出た。
「いらっしゃいませ-」
「イラッシャイマセ~」
片岡さんに続いて、ぎこちなく挨拶をする。バイト初日に適当な挨拶をしていたら店長に怒られたから、今日は端折らずに口にした。ざっと店内を見渡すと、イートインスペースにお客さんが二組、カウンターには大学生バイトの三上さんがいた。
「片岡くん、ミントくん、おつ~」
ちゅるんとしたグロスを塗った唇を尖らせながら、三上さんがひらひらと手を振る。カラコンを付けているせいか、黒目がやけにデカい。俺は警戒しながら「おつかれっす」と聞こえるか聞こえないか分からない声量で挨拶を返した。
「ねえ、流星。俺のポロシャツ引っ張るのやめて」
反射的に片岡さんを盾にしてしまった。困ったように笑いかけられたことで、慌ててポロシャツの襟から手を離す。
「ミントくん、片岡くんを虐めないでね~」
「……虐めてないです」
ちなみに三上さんは、いまだに俺のことを「ミントくん」と呼ぶ。それはきっと、この人が命名したからに違いない。三上さんは、俺を怖がることはないけど、ヤンキー風な見た目を面白可笑しくイジってくる。悪い人ではないのだろうけど、正直苦手だ。
「ミントくん、目が怖いよ~。まじヤンキー」
「……ヤンキーじゃないですから」
目つきが悪いせいで、また睨んでいると誤解されてしまった。いかん、いかん。眉間を揉み解していると、入り口の自動ドアが開く。真っ先に片岡さんが反応した。
「いらっしゃいませー」
大学生風カップルのご来店だ。カップルは、ショーケースの前でキャッキャウフフとフレーバーを選んだ後、三上さんに声をかけた。オーダーを受けている三上さんをぼんやりと眺めていると、おもむろにメモを渡される。
「ミントくん、頼んだ。どっちもスモールカップで」
「はいっ」
さっそく仕事だ。張り切ってメモを受け取るも、書かれていた文字を見た途端、俺の思考は宇宙の彼方へと飛ばされた。
「Ca……Sr……? カルシウムとストロンチウムですか?」
「はあ?」
お会計をしていた三上さんから、冷ややかな視線を向けられる。「はあ?」はやめてほしい。心臓が凍り付きそうになるから。恐怖のあまりその場で固まっていると、片岡さんがフォローに入る。
「貸して。えーっと、キャラメルハートとストロベリーマーチね」
「そうそう」
「三上さん、流星はまだ慣れてないんで、正式名称で書いてください」
「あー、はい、はーい」
三上さんは間延びした返事をする。どうやらアレは、フレーバーの略称だったようだ。Caはキャラメル、Srはストロベリー……いや、分からんて。お会計を続行する三上さんを恨めし気に見つめていると、アイスを掬い取るデッシャーを持った片岡さんから指示される。
「キャラメルハートは俺がやるから、流星はストロベリーマーチをお願い」
「はいっ」
シャキッと背筋が伸ばして反応する。片岡さんに倣って、スモールサイズのディッシャーを手に取って臨戦態勢に入った。しかし、更なる問題が発生する。
「ストロベリーマーチって、どこ!?」
ショーケースに収まった30種類のフレーバーから、目的のフレーバーを捜し出すのは容易ではない。端から順番に探したものの、なかなか見つからなかった。そうこうしているうちに、三上さんがお会計を済ませる。お客さんを待たせていると思うと、余計に焦りが生まれた。カウンターで右往左往していると、片岡さんの背中に激突する。
「ぐぇ、スミマセン!」
「また場所分かんなくなった? ストロベリーマーチはこっち」
片岡さんは左から三番目のアイスを指さす。そんなところに隠れていたのか、ストロベリーマーチ! 気を取り直して、ディッシャーを握りしめ、ショーケースの扉を開ける。円柱状の紙箱に収まったアイスは、表面がつるんとしていた。まだ一度も削った形跡がない。そこへディッシャーを差し込み、アイスを掬おうとしたが、またしても問題が発生する。
「か、硬い……。なんでこんなに硬いんすか?」
アイスクリーム屋のバイトを始めて分かったことだが、アイスを掬い取る作業は結構力がいる。バイト初日は、右腕だけが筋肉痛になったくらいだ。
硬いことはある程度覚悟していたけど、今格闘しているアイスは尋常じゃなく硬い。悲鳴を上げていると、片岡さんがすぐさま駆けつけてくれた。
「あー、倉庫から出したばっかりだったんだ。その状態だと硬いよね。貸して。俺やるよ」
有無を言わさずディッシャーを奪われる。俺が白旗を上げたストロベリーマーチだったが、片岡さんの上腕二頭筋にかかれば造作もなかった。
片岡さんは細身に見えるが、腕の筋肉は結構付いている。ショベルカーのように平らな面からアイスを掬い取ると、みるみるうちに丸く成形されていった。惚れ惚れするような手捌きだ。掬い取ったアイスをカップに収めると、笑顔で提供する。
「お待たせしました。ストロベリーマーチです。ありがとうございました」
お客さんは軽く会釈するだけだったが、俺は盛大な拍手を送りたい気分になった。店内からキャッキャウフフと出ていくカップルを見送ってから、俺は片岡さんに駆け寄った。
「片岡さぁぁん、助かりました!」
両手を擦り合わせて拝み倒していると、片岡さんは申し訳なさそうに微笑んだ。
「倉庫から出したばかりなの気付かないで頼んじゃってごめんね。最初は難しいよね、スクープ」
スクープとは、アイスを掬い取る作業のことだ。アイスクリーム屋の基本の仕事といえる。この店では、ディッシャーを使ってアイスを丸く成形するのだが、これが案外難しい。小さすぎてもダメだし、大きすぎてもダメ。既定のグラムに収まるまで、何度もやり直す必要があった。バイトを始めて二週間の俺は、まだスクープを習得していない。まあ、今回に至ってはグラム以前の話だったが。
できないのは、スクープに限った話ではない。頼まれたアイスの種類も分からないし、ショーケース内での位置も把握していない。さっきだって、俺は右往左往するばかりで、何の役にも立っていなかった。自分の無能さに呆れてしまう。
「すいません。全然使えなくて……」
戦力どころか邪魔にしかなっていない。これではクビになるのも時間の問題だ。恐る恐る片岡さんの反応を伺うと、目を細めながら小さく息をついた。
呆れられたかもしれない。心臓が縮こまった直後、片岡さんはプラスチックスプーンを手に取って、ショーケースを開けた。何をするのかと観察していると、ストロベリーマーチを掬って俺の前に差し出す。
「流星、あーん」
言われるがまま口を開けると、スプーンを突っ込まれる。
「んぐっ」
ストロベリーの甘酸っぱさと濃厚なミルクの味が広がる。そこにチョコレートのカリッとした食感も加わると、口の中が賑やかになった。
「美味しい?」
にこっと微笑む片岡さんを見て、俺はコクコクと頷く。アイスを飲み込んでから、おずおずと尋ねた。
「良いんですか? 食べちゃって……」
「テイスティングってことにしておけば大丈夫」
片岡さんがそう言うのなら、大丈夫なのだろう。俺はホッと安堵の溜息をつく。
思いがけずアイスを突っ込まれてしまったが、糖分を摂取したおかげでちょっと元気が出た。きっと片岡さんは、俺を元気付けるためにアイスを食べさせてくれたのだろう。その優しさは、とても嬉しい。口元に触れてアイスが付いていないことを確認すると、片岡さんからトンと背中を叩かれる。
「使えないなんて言わないで。これから色々覚えていけばいいから」
晴れやかな笑顔に励まされる。地の底まで沈みかけていた自己肯定感がゆっくり浮上していった。やっぱり片岡さんは優しい。優し過ぎて、泣きそうだ。目を細めて涙を堪えていると、片岡さんの笑顔がみるみると困り顔に変わっていった。
「あの、流星……。そんなに睨まないで?」
「わっ……ミントくんが片岡くんにガン飛ばしてる……こっわ」
二人から指摘されて、自分の目つきの悪さを思い出す。
「ち、違うんです! これは睨んでいるわけではなくてですねぇ!」
片岡さんにまで怖いと思われたら最悪だ。わたわたと忙しなく両手を動かしていると、片岡さんがブフォッと吹き出す。
「店長が言ってたおかしな挙動ってこれか……。確かにピーク時にこれをやられたら、気が散るなぁ」
俺の動きがツボに入ったようだ。笑わせるつもりはなかったから驚いた。顔をくしゃくしゃにして声を抑えながら笑っている姿を見ていると、嬉しくなってくる。カウンター越しの純度100%の笑顔も良いけど、素の笑顔も好きだ。しみじみと眺めていると、再び入り口の自動ドアが開いた。
「いらっしゃいませー」
いまだに笑いが収まっていない片岡さんに代わって、お客さんを出迎える。片岡さんの言う通りだ。今は使えなくても、この先挽回すればいい。今度こそ戦力になれるように、率先して注文を聞きに行った。
「ご注文、お伺いします!」
毎度、毎度、店長に怒られてばかり。前髪はキャップにしまえだの、声が小さいだの、敬語は正しく使えだの、おかしな挙動をするなだの……あとはもう、なんだか忘れた。とにかくうんざりするほど怒られた。
初めてのバイトだから仕方がないのかもしれないけど、それにしたって怒られ過ぎだ。店長は、どうにも俺にだけ厳しい気がする。どうせヤンキーだからきつく叱っても構わないと思われているのだろう。小心者の俺からすれば、店長からの罵声がナイフのように突き刺さる。バイトが終わった頃には満身創痍だ。
働くって大変だ。とはいえ、たったの二週間で辞めるわけにもいかない。シフトが入っている今日は、朝から憂鬱だった。出勤は16時から。15時過ぎには重い身体に鞭打って家を出た。
バイト先までは電車で20分ほどかかる。普段から通学で乗り降りしている駅だけど、制服姿の高校生がいない夏休み期間は別の場所のように感じた。重い足取りで駅を出て、賑わう大通りを歩くと、3分ほどで店に着く。パステルピンクの看板を恨めし気に見上げてから、店の自動ドアを通過した。
「おつかれさまっすー……」
カウンターにいる先輩への挨拶もそこそこに、従業員専用のバックヤードに向かう。店の奥にあるバックヤードは、大人が三人入れば身動きが取れなくなるほど狭い空間だった。その中に、勤怠を入力するパソコンやカーテンで仕切られた更衣室がある。店に来て、雑多な箱に収まる度に、うんざりした気分になった。
一つ溜息をついてから扉を開けると、コバルトブルーのキャップを被ったお兄さんと目が合った。その瞬間、ムスッとしていた俺の表情が甘く溶ける。目の前のお兄さんからも、にこっと微笑みかけられた。
「おはよう、流星。今日はシフト一緒だね」
お兄さん、もとい片岡さんだ。純度100%の笑顔を向けられた瞬間、沈んでいた心が一気に跳ね上がった。
「今日は片岡さんと一緒なんですね! 嬉しいですっ」
飼い主を見つけた犬のように飛びかかろうとすると、どうどうと肩を掴まれて静止される。
「喜びすぎだって。今日は店長休みだから、俺が流星の教育係を任されてるんだ」
「店長休みなんすね! よっしゃっ!」
「そこは喜ばないっ」
脳天にチョップを食らう。出勤して早々、怒られてしまった。でも片岡さんからの攻撃ならノーダメだ。
片岡さんがいるなら、今日は乗り切れそうだ。片岡さんとシフトが被ったのは二度目だが、既に絶対的な信頼を寄せている。
片岡さんは、とても面倒見が良い。前回もフォローされっぱなしだった。お客さんから声をかけられるだけでビビり散らす俺に代わって注文を伺い、レジの操作方法が分からずにフリーズした時は颯爽とヘルプに入り、手元が狂ってプラスチックスプーンを床にぶちまけた時は一緒に回収してくれた。その上、バイト終わりにはジュースを奢ってくれたのだ。まさに理想の先輩だ。
すっかり懐いた俺は、帰りもご一緒させてもらった。そこで片岡さんの基本情報も得た。年齢は俺の一個上で、高校二年生。この辺りでは偏差値の高い公立高校に通っている。自宅は駅の反対方向にあるらしく、バイト先には徒歩で通っているそうだ。
これはどうでもいい情報だが、俺が毎日アイスクリーム屋に通っていたせいで、従業員からは密かに「ミントくん」と呼ばれていたらしい。毎回チョコミントしか頼まなかったのが原因だ。知らぬ間にあだ名が付けられていたと知って、恥ずかしいやら腹立たしいやらで、しばらくは顔が上げられなかった。
駅までの道のりで、有益な情報も無益な情報もたくさん得た。もっと話をしたかったが、あっという間に改札に着いてしまう。名残惜しさを感じながらもお別れしようとすると、片岡さんから「バイバイ、流星」と手を振られた。その瞬間、血が湧き立つような興奮に襲われた。
聞き間違いではない。片岡さんは、俺のことを「流星」と呼んだ。店ではずっと「綾瀬くん」だったのに、駅まで向かう3分間で「流星」へとランクアップしたのだ。名前呼びをされたことで、一気に距離が縮まったような気がした。嬉しさのあまりホームでスキップをしていたら、近くにいたお姉さんにギョッとした目で見られたが、それもどうでもいい話だ。
前回の出来事を振り返りながらにまにましていると、片岡さんに背中を押される。
「ぼーっとしてないで、早く着替えておいで。もう時間ないよ」
現在の時刻は15時55分。稼働時間の16時まであと5分しかない。
「やばっ……すぐ着替えます」
更衣室に飛び込んで、Tシャツとハーフパンツを脱ぎ捨てた。アイスクリーム屋の制服に着替えてから鏡を見る。水色のポロシャツに、黒のスラックス。コバルトブルーの腰エプロンとキャップを身につければ、バイト戦士の完成だ。長めの前髪も、きちんとキャップに収めている。これなら文句はないだろう。カーテンを開けると、片岡さんに上から下までチェックをされた。
「ん、オッケー」
「あざっす」
身だしなみチェックをクリアしたところで、タイムカードを切る。よしっ、意気込んでからカウンターに出た。
「いらっしゃいませ-」
「イラッシャイマセ~」
片岡さんに続いて、ぎこちなく挨拶をする。バイト初日に適当な挨拶をしていたら店長に怒られたから、今日は端折らずに口にした。ざっと店内を見渡すと、イートインスペースにお客さんが二組、カウンターには大学生バイトの三上さんがいた。
「片岡くん、ミントくん、おつ~」
ちゅるんとしたグロスを塗った唇を尖らせながら、三上さんがひらひらと手を振る。カラコンを付けているせいか、黒目がやけにデカい。俺は警戒しながら「おつかれっす」と聞こえるか聞こえないか分からない声量で挨拶を返した。
「ねえ、流星。俺のポロシャツ引っ張るのやめて」
反射的に片岡さんを盾にしてしまった。困ったように笑いかけられたことで、慌ててポロシャツの襟から手を離す。
「ミントくん、片岡くんを虐めないでね~」
「……虐めてないです」
ちなみに三上さんは、いまだに俺のことを「ミントくん」と呼ぶ。それはきっと、この人が命名したからに違いない。三上さんは、俺を怖がることはないけど、ヤンキー風な見た目を面白可笑しくイジってくる。悪い人ではないのだろうけど、正直苦手だ。
「ミントくん、目が怖いよ~。まじヤンキー」
「……ヤンキーじゃないですから」
目つきが悪いせいで、また睨んでいると誤解されてしまった。いかん、いかん。眉間を揉み解していると、入り口の自動ドアが開く。真っ先に片岡さんが反応した。
「いらっしゃいませー」
大学生風カップルのご来店だ。カップルは、ショーケースの前でキャッキャウフフとフレーバーを選んだ後、三上さんに声をかけた。オーダーを受けている三上さんをぼんやりと眺めていると、おもむろにメモを渡される。
「ミントくん、頼んだ。どっちもスモールカップで」
「はいっ」
さっそく仕事だ。張り切ってメモを受け取るも、書かれていた文字を見た途端、俺の思考は宇宙の彼方へと飛ばされた。
「Ca……Sr……? カルシウムとストロンチウムですか?」
「はあ?」
お会計をしていた三上さんから、冷ややかな視線を向けられる。「はあ?」はやめてほしい。心臓が凍り付きそうになるから。恐怖のあまりその場で固まっていると、片岡さんがフォローに入る。
「貸して。えーっと、キャラメルハートとストロベリーマーチね」
「そうそう」
「三上さん、流星はまだ慣れてないんで、正式名称で書いてください」
「あー、はい、はーい」
三上さんは間延びした返事をする。どうやらアレは、フレーバーの略称だったようだ。Caはキャラメル、Srはストロベリー……いや、分からんて。お会計を続行する三上さんを恨めし気に見つめていると、アイスを掬い取るデッシャーを持った片岡さんから指示される。
「キャラメルハートは俺がやるから、流星はストロベリーマーチをお願い」
「はいっ」
シャキッと背筋が伸ばして反応する。片岡さんに倣って、スモールサイズのディッシャーを手に取って臨戦態勢に入った。しかし、更なる問題が発生する。
「ストロベリーマーチって、どこ!?」
ショーケースに収まった30種類のフレーバーから、目的のフレーバーを捜し出すのは容易ではない。端から順番に探したものの、なかなか見つからなかった。そうこうしているうちに、三上さんがお会計を済ませる。お客さんを待たせていると思うと、余計に焦りが生まれた。カウンターで右往左往していると、片岡さんの背中に激突する。
「ぐぇ、スミマセン!」
「また場所分かんなくなった? ストロベリーマーチはこっち」
片岡さんは左から三番目のアイスを指さす。そんなところに隠れていたのか、ストロベリーマーチ! 気を取り直して、ディッシャーを握りしめ、ショーケースの扉を開ける。円柱状の紙箱に収まったアイスは、表面がつるんとしていた。まだ一度も削った形跡がない。そこへディッシャーを差し込み、アイスを掬おうとしたが、またしても問題が発生する。
「か、硬い……。なんでこんなに硬いんすか?」
アイスクリーム屋のバイトを始めて分かったことだが、アイスを掬い取る作業は結構力がいる。バイト初日は、右腕だけが筋肉痛になったくらいだ。
硬いことはある程度覚悟していたけど、今格闘しているアイスは尋常じゃなく硬い。悲鳴を上げていると、片岡さんがすぐさま駆けつけてくれた。
「あー、倉庫から出したばっかりだったんだ。その状態だと硬いよね。貸して。俺やるよ」
有無を言わさずディッシャーを奪われる。俺が白旗を上げたストロベリーマーチだったが、片岡さんの上腕二頭筋にかかれば造作もなかった。
片岡さんは細身に見えるが、腕の筋肉は結構付いている。ショベルカーのように平らな面からアイスを掬い取ると、みるみるうちに丸く成形されていった。惚れ惚れするような手捌きだ。掬い取ったアイスをカップに収めると、笑顔で提供する。
「お待たせしました。ストロベリーマーチです。ありがとうございました」
お客さんは軽く会釈するだけだったが、俺は盛大な拍手を送りたい気分になった。店内からキャッキャウフフと出ていくカップルを見送ってから、俺は片岡さんに駆け寄った。
「片岡さぁぁん、助かりました!」
両手を擦り合わせて拝み倒していると、片岡さんは申し訳なさそうに微笑んだ。
「倉庫から出したばかりなの気付かないで頼んじゃってごめんね。最初は難しいよね、スクープ」
スクープとは、アイスを掬い取る作業のことだ。アイスクリーム屋の基本の仕事といえる。この店では、ディッシャーを使ってアイスを丸く成形するのだが、これが案外難しい。小さすぎてもダメだし、大きすぎてもダメ。既定のグラムに収まるまで、何度もやり直す必要があった。バイトを始めて二週間の俺は、まだスクープを習得していない。まあ、今回に至ってはグラム以前の話だったが。
できないのは、スクープに限った話ではない。頼まれたアイスの種類も分からないし、ショーケース内での位置も把握していない。さっきだって、俺は右往左往するばかりで、何の役にも立っていなかった。自分の無能さに呆れてしまう。
「すいません。全然使えなくて……」
戦力どころか邪魔にしかなっていない。これではクビになるのも時間の問題だ。恐る恐る片岡さんの反応を伺うと、目を細めながら小さく息をついた。
呆れられたかもしれない。心臓が縮こまった直後、片岡さんはプラスチックスプーンを手に取って、ショーケースを開けた。何をするのかと観察していると、ストロベリーマーチを掬って俺の前に差し出す。
「流星、あーん」
言われるがまま口を開けると、スプーンを突っ込まれる。
「んぐっ」
ストロベリーの甘酸っぱさと濃厚なミルクの味が広がる。そこにチョコレートのカリッとした食感も加わると、口の中が賑やかになった。
「美味しい?」
にこっと微笑む片岡さんを見て、俺はコクコクと頷く。アイスを飲み込んでから、おずおずと尋ねた。
「良いんですか? 食べちゃって……」
「テイスティングってことにしておけば大丈夫」
片岡さんがそう言うのなら、大丈夫なのだろう。俺はホッと安堵の溜息をつく。
思いがけずアイスを突っ込まれてしまったが、糖分を摂取したおかげでちょっと元気が出た。きっと片岡さんは、俺を元気付けるためにアイスを食べさせてくれたのだろう。その優しさは、とても嬉しい。口元に触れてアイスが付いていないことを確認すると、片岡さんからトンと背中を叩かれる。
「使えないなんて言わないで。これから色々覚えていけばいいから」
晴れやかな笑顔に励まされる。地の底まで沈みかけていた自己肯定感がゆっくり浮上していった。やっぱり片岡さんは優しい。優し過ぎて、泣きそうだ。目を細めて涙を堪えていると、片岡さんの笑顔がみるみると困り顔に変わっていった。
「あの、流星……。そんなに睨まないで?」
「わっ……ミントくんが片岡くんにガン飛ばしてる……こっわ」
二人から指摘されて、自分の目つきの悪さを思い出す。
「ち、違うんです! これは睨んでいるわけではなくてですねぇ!」
片岡さんにまで怖いと思われたら最悪だ。わたわたと忙しなく両手を動かしていると、片岡さんがブフォッと吹き出す。
「店長が言ってたおかしな挙動ってこれか……。確かにピーク時にこれをやられたら、気が散るなぁ」
俺の動きがツボに入ったようだ。笑わせるつもりはなかったから驚いた。顔をくしゃくしゃにして声を抑えながら笑っている姿を見ていると、嬉しくなってくる。カウンター越しの純度100%の笑顔も良いけど、素の笑顔も好きだ。しみじみと眺めていると、再び入り口の自動ドアが開いた。
「いらっしゃいませー」
いまだに笑いが収まっていない片岡さんに代わって、お客さんを出迎える。片岡さんの言う通りだ。今は使えなくても、この先挽回すればいい。今度こそ戦力になれるように、率先して注文を聞きに行った。
「ご注文、お伺いします!」