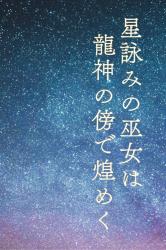綾瀬流星とは、どんな人間か? クラスメイトにそんな質問を投げかければ、こう返ってくるだろう。怖そうな人。
それは大きな誤解だ。俺は人に害を成す人間ではないし、どちらかと言えば小心者だ。それにも関わらず、高校に入学した初日からヤンキーとして恐れられるようになった。
そう思わせてしまう原因は、俺の外見にある。外国の血を引いている俺は、生まれつき色素が薄く、髪色は黄みがかったベージュだ。黒髪の集団の中では、明らかに浮いた存在だった。堀の深い顔立ちをしていれば違和感を持たれることもなかったのかもしれないが、俺の顔はあっさりとした塩顔。おまけにつり目なせいで、目つきは人一倍悪い。平常時でも睨んでいると誤解された。目が合うだけで「ひぃ」と逃げられることすらある。
目立たないようにフードを被り、前髪を伸ばしてみたが、どちらも逆効果だった。陰気なオーラが増して、余計に危ない人になってしまった。
子供の頃は良かった。明るい髪色でも、お人形さんみたいだとチヤホヤされた。だけど高校生になった今は、このザマだ。せめてもの救いは、身長が162センチと比較的小柄なことだ。これで180センチ越えの巨漢だったら、余計に人が寄り付かなくなっていただろう。怖そうなちっちゃいヤンキー。学校では、そう呼ばれていた。
ヤンキーなんて呼ばれているけど、実際には殴り合いの喧嘩をしたことがなければ、夜間にバイクでかっ飛ばしたこともない。授業だって真面目に受けてるし、こう見えて化学部だ。部活の人からもビビられまくっているせいで、部活には顔を出せていないけど。
教室でも部活でも怖い人扱いされ、遠巻きにされている。その一方で、繁華街を歩けば本物のヤンキーに絡まれる始末だ。その度に脱兎のごとく逃げ出していた。
高校デビューに失敗したせいで、学校での居心地は最悪だ。だからこそ、学校の外で居場所を求めていたんだと思う。
一学期最後のHRが終わると、俺は一目散に教室から飛び出す。夏休み前で浮足立った生徒達の間をすり抜けながら昇降口へと急いだ。
今日も学校から抜け出して、アイスクリーム屋に向かう。あの日以来、お兄さんの笑顔を見ることが、俺にとっての唯一の癒しになっていた。
昇降口でスニーカーに履き替えて外に出ると、蒸し風呂のような熱気に襲われる。照り付ける太陽からは攻撃性すら感じた。だけどそんなことでは俺の足は止まらない。正門に向かう生徒達を追い抜いて、駅前のアイスクリーム屋へと走った。
◇
冷房の効いたオアシスに辿り着いたものの、そこに安らぎは存在しなかった。
「お兄さんが、いないだと……」
俺は膝から崩れ落ちそうになった。ショックだが、こればっかりは仕方がない。お兄さんだって毎日シフトに入っているわけではないのだ。会えるのは、せいぜい週に三回。今日はハズレの日だったようだ。
お兄さんがいないと知って、浮かれていた心がずーんと地の底まで沈んでいく。もうアイスクリーム屋には用はないのだけれど、店に入ってしまった以上、注文せずに帰るのは忍びない。渋々カウンターに向かった。
「……チョコミントのスモールカップで」
「380円になります」
一番小さいサイズのアイスを購入する。月5000円のお小遣いでやりくりしている身としては、380円の出費は軽視できない。毎日通っていれば、お小遣いだって底を尽きる。ついに今日、財布の中身が空になった。
「ありがとうございました~」
アイスを受け取った俺は、イートインスペースで項垂れていた。お金がないということは、もうここには来られないということだ。二週間もアイスクリーム屋に通い詰めているのだから無理もない。
「夏休み前なのに、お小遣いゼロ……」
次のお小遣い支給日までは、お兄さんの笑顔はお預けだ。せめて今日、お兄さんがシフトに入っていたらと悔やまれた。隣の席で夏の計画を立てる女子高生達の会話を聞きながら、俺はテーブルに突っ伏していた。そんな時、聞き覚えのある声が耳に届く。
「お疲れ様です」
気持ちのいい挨拶が聞こえる。俺は勢いよくテーブルから起き上がった。店の入り口には、高校の制服を着たお兄さんがいる。その姿を見た瞬間、凍りついていた表情が甘く溶けた。
お兄さんだ! 今日、シフト入ってたんだ! 思いがけず会えたことに歓喜し、俺は静かに星を散らしていた。
お兄さんが高校生だったことにも驚きだ。背が高くて大人びて見えたから、大学生かと思っていた。キャップを被っていない姿も初めて見た。黒髪ショートをセンター分けにした爽やかなスタイルに整えている。もとから顔が良いことは知っていたけど、そんなにイケメンだったなんて聞いてない。穴が開きそうなほど凝視していると、お兄さんと視線がぶつかった。
最初は驚いたように目を見開いていたお兄さんだったが、しばらくするとふわりと柔らかく微笑む。え? 俺に笑いかけているのか? 理解が追い付かずにいると、お兄さんがイートインスペースに近付いてきた。
「いらっしゃい。今日も来てくれたんだね」
きょろきょろと辺りを伺ってみたものの、他に反応している人はいない。どうやら俺に話しかけているようだ。放心したまま固まっていると、お兄さんは申し訳なさそうに目を細めた。
「あ、ごめんね、驚かせちゃって。最近、毎日来ているみたいだから、気になっちゃって」
どうやら顔を覚えられていたらしい。二週間も通い詰めているのだから当然か。アイスのカップを握りしめながら凝視していると、お兄さんがカップの中を覗き込む。
「今日もチョコミント?」
「…………です」
「好きだね。それしか頼まないじゃん」
お兄さんは、くくくっと喉の奥で笑う。その表情はカウンター越しに見る笑顔とは違い、年相応な笑い方だった。
「突然話しかけちゃってごめんね。ごゆっくり~」
お兄さんは、ひらひらと手を振りながら店の奥に歩いていく。嘘だろ? もう行っちゃうの? せっかく話かけてもらえたのに、これで終わりなんて嫌だ。
「あのっ!」
気付いた時には、椅子から立ち上がってお兄さんを呼び止めていた。
「ん?」
お兄さんは小首を傾げながら、にこやかに用件を尋ねる。突然のことにも関わらず、笑顔で応対してくれるのは有り難かった。
引き留めることには成功したものの、ここから先はノープランだ。脳みそは沸騰寸前。心臓は徒競走を終えた直後のように暴れまわっている。無意識でアイスのカップをぎゅうぎゅうと握りしめながら、お兄さんを引き留めるためだけの会話を続けた。
「チョコミントも好きなんです。歯磨き粉の味がするって、馬鹿にされることもあるんですけど」
「お、う、うん……」
何の話をしているんだ? 俺だって分からない。目の前にいるお兄さんは、もっと分からないだろう。にこやかだった表情が、次第に苦笑いに変わっていく。お互い訳が分からないけど、止められなかった。
「だけど、それだけじゃないんです」
頭から湯気が出そうになりながら、無我夢中で訴えた。
「本当はお兄さんの笑顔が見たくて、この店に通っていたんです! だから、今話しかけてもらえて、めちゃくちゃ嬉しいんです!」
最後まで口にした途端、激しく後悔した。やってしまった。今の発言は、どう考えてもヤバイ奴だ。ストーカーだと疑われても仕方がない。サアァと血の気が引いて、頭の中が凍りつきそうになった。
お兄さんは、ぽかんと口を開けたまま固まっている。変な奴だと思われただろう。どうにかフォローして取り繕わなければ。
「あ、の……スイマセン、キモイこと言って……。お小遣いも底を尽きたので、もう来ません。失礼しました」
これ以上、ボロを出さないようにさっさと退散しよう。俺はスクールバックを掴んで椅子から立ち上がった。
「待って」
店から出ようとしたものの、お兄さんに引き留められた。ドン引きされている訳ではなさそうだが、真顔で見つめられるのも怖い。どうしたらいいのか分からずに固まっていると、お兄さんは言葉を続けた。
「えーっと、つまり、俺に会いたくて毎日通っていたってこと?」
客観的に指摘されると、自らの異常さに気付く。だけど既に自供してしまったのだから、誤魔化しようがない。
「まあ、そういうことですね……」
もう、罵倒するなり、ドン引きするなり好きにしてくれ。断頭台に立たされた気分で処遇を待っていると、驚くべき光景が広がった。
「そっか。嬉しい」
お兄さんは、笑っていた。
笑っている時の顔は、とても正直だ。相手の感情がダイレクトに伝わってくる。普段だったらおおよその感情は読み取れるが、今向けられている笑顔だけは分からなかった。
口元は緩く弧を描き、頬はほんのり上気している。細めた目元から覗く瞳には、僅かばかりの熱が籠っていた。その笑顔はなんだ? 見ているだけで心臓が暴れまわる。身体中の血が沸騰して、みるみる体温が上昇していった。
「あのさ」
「はいっ!」
びくんと肩を振るわせながら返事をする。自分の身に何が起こっているのか分からずにパニックになっていると、お兄さんがおもむろに壁のポスターを指さした。
「ミントくん……じゃないや。君さえよければ、うちでバイトしない?」
お兄さんが指さしたのは、バイト募集のポスターだ。時給1200円。営業時間9時~20時。週2~OK。フリーター・大学生・高校生歓迎。この条件が、良いのか悪いのかはよく分からない。だけどこの店で働けば、お兄さんの笑顔を無料で拝める。それだけではない。お小遣いだって手に入るのだ。断る理由がなかった。
「やります! 俺をここで働かせてください! 明日からよろしくお願いします!」
即決だった。深々と頭を下げ、意気込みを伝える。バイトはしたことがないが、この機会を逃すわけにはいかなかった。顔を上げた時、お兄さんが困ったように眉を下げていることに気付く。
「あー、えっと、ごめん。誘っといて悪いんだけど、俺はただのバイトだから採用権限はないんだ。後日、履歴書持って、正式に応募してね」
「……ああ、はい」
脱力して椅子に座る。購入したアイスは、すっかり溶けていた。
それは大きな誤解だ。俺は人に害を成す人間ではないし、どちらかと言えば小心者だ。それにも関わらず、高校に入学した初日からヤンキーとして恐れられるようになった。
そう思わせてしまう原因は、俺の外見にある。外国の血を引いている俺は、生まれつき色素が薄く、髪色は黄みがかったベージュだ。黒髪の集団の中では、明らかに浮いた存在だった。堀の深い顔立ちをしていれば違和感を持たれることもなかったのかもしれないが、俺の顔はあっさりとした塩顔。おまけにつり目なせいで、目つきは人一倍悪い。平常時でも睨んでいると誤解された。目が合うだけで「ひぃ」と逃げられることすらある。
目立たないようにフードを被り、前髪を伸ばしてみたが、どちらも逆効果だった。陰気なオーラが増して、余計に危ない人になってしまった。
子供の頃は良かった。明るい髪色でも、お人形さんみたいだとチヤホヤされた。だけど高校生になった今は、このザマだ。せめてもの救いは、身長が162センチと比較的小柄なことだ。これで180センチ越えの巨漢だったら、余計に人が寄り付かなくなっていただろう。怖そうなちっちゃいヤンキー。学校では、そう呼ばれていた。
ヤンキーなんて呼ばれているけど、実際には殴り合いの喧嘩をしたことがなければ、夜間にバイクでかっ飛ばしたこともない。授業だって真面目に受けてるし、こう見えて化学部だ。部活の人からもビビられまくっているせいで、部活には顔を出せていないけど。
教室でも部活でも怖い人扱いされ、遠巻きにされている。その一方で、繁華街を歩けば本物のヤンキーに絡まれる始末だ。その度に脱兎のごとく逃げ出していた。
高校デビューに失敗したせいで、学校での居心地は最悪だ。だからこそ、学校の外で居場所を求めていたんだと思う。
一学期最後のHRが終わると、俺は一目散に教室から飛び出す。夏休み前で浮足立った生徒達の間をすり抜けながら昇降口へと急いだ。
今日も学校から抜け出して、アイスクリーム屋に向かう。あの日以来、お兄さんの笑顔を見ることが、俺にとっての唯一の癒しになっていた。
昇降口でスニーカーに履き替えて外に出ると、蒸し風呂のような熱気に襲われる。照り付ける太陽からは攻撃性すら感じた。だけどそんなことでは俺の足は止まらない。正門に向かう生徒達を追い抜いて、駅前のアイスクリーム屋へと走った。
◇
冷房の効いたオアシスに辿り着いたものの、そこに安らぎは存在しなかった。
「お兄さんが、いないだと……」
俺は膝から崩れ落ちそうになった。ショックだが、こればっかりは仕方がない。お兄さんだって毎日シフトに入っているわけではないのだ。会えるのは、せいぜい週に三回。今日はハズレの日だったようだ。
お兄さんがいないと知って、浮かれていた心がずーんと地の底まで沈んでいく。もうアイスクリーム屋には用はないのだけれど、店に入ってしまった以上、注文せずに帰るのは忍びない。渋々カウンターに向かった。
「……チョコミントのスモールカップで」
「380円になります」
一番小さいサイズのアイスを購入する。月5000円のお小遣いでやりくりしている身としては、380円の出費は軽視できない。毎日通っていれば、お小遣いだって底を尽きる。ついに今日、財布の中身が空になった。
「ありがとうございました~」
アイスを受け取った俺は、イートインスペースで項垂れていた。お金がないということは、もうここには来られないということだ。二週間もアイスクリーム屋に通い詰めているのだから無理もない。
「夏休み前なのに、お小遣いゼロ……」
次のお小遣い支給日までは、お兄さんの笑顔はお預けだ。せめて今日、お兄さんがシフトに入っていたらと悔やまれた。隣の席で夏の計画を立てる女子高生達の会話を聞きながら、俺はテーブルに突っ伏していた。そんな時、聞き覚えのある声が耳に届く。
「お疲れ様です」
気持ちのいい挨拶が聞こえる。俺は勢いよくテーブルから起き上がった。店の入り口には、高校の制服を着たお兄さんがいる。その姿を見た瞬間、凍りついていた表情が甘く溶けた。
お兄さんだ! 今日、シフト入ってたんだ! 思いがけず会えたことに歓喜し、俺は静かに星を散らしていた。
お兄さんが高校生だったことにも驚きだ。背が高くて大人びて見えたから、大学生かと思っていた。キャップを被っていない姿も初めて見た。黒髪ショートをセンター分けにした爽やかなスタイルに整えている。もとから顔が良いことは知っていたけど、そんなにイケメンだったなんて聞いてない。穴が開きそうなほど凝視していると、お兄さんと視線がぶつかった。
最初は驚いたように目を見開いていたお兄さんだったが、しばらくするとふわりと柔らかく微笑む。え? 俺に笑いかけているのか? 理解が追い付かずにいると、お兄さんがイートインスペースに近付いてきた。
「いらっしゃい。今日も来てくれたんだね」
きょろきょろと辺りを伺ってみたものの、他に反応している人はいない。どうやら俺に話しかけているようだ。放心したまま固まっていると、お兄さんは申し訳なさそうに目を細めた。
「あ、ごめんね、驚かせちゃって。最近、毎日来ているみたいだから、気になっちゃって」
どうやら顔を覚えられていたらしい。二週間も通い詰めているのだから当然か。アイスのカップを握りしめながら凝視していると、お兄さんがカップの中を覗き込む。
「今日もチョコミント?」
「…………です」
「好きだね。それしか頼まないじゃん」
お兄さんは、くくくっと喉の奥で笑う。その表情はカウンター越しに見る笑顔とは違い、年相応な笑い方だった。
「突然話しかけちゃってごめんね。ごゆっくり~」
お兄さんは、ひらひらと手を振りながら店の奥に歩いていく。嘘だろ? もう行っちゃうの? せっかく話かけてもらえたのに、これで終わりなんて嫌だ。
「あのっ!」
気付いた時には、椅子から立ち上がってお兄さんを呼び止めていた。
「ん?」
お兄さんは小首を傾げながら、にこやかに用件を尋ねる。突然のことにも関わらず、笑顔で応対してくれるのは有り難かった。
引き留めることには成功したものの、ここから先はノープランだ。脳みそは沸騰寸前。心臓は徒競走を終えた直後のように暴れまわっている。無意識でアイスのカップをぎゅうぎゅうと握りしめながら、お兄さんを引き留めるためだけの会話を続けた。
「チョコミントも好きなんです。歯磨き粉の味がするって、馬鹿にされることもあるんですけど」
「お、う、うん……」
何の話をしているんだ? 俺だって分からない。目の前にいるお兄さんは、もっと分からないだろう。にこやかだった表情が、次第に苦笑いに変わっていく。お互い訳が分からないけど、止められなかった。
「だけど、それだけじゃないんです」
頭から湯気が出そうになりながら、無我夢中で訴えた。
「本当はお兄さんの笑顔が見たくて、この店に通っていたんです! だから、今話しかけてもらえて、めちゃくちゃ嬉しいんです!」
最後まで口にした途端、激しく後悔した。やってしまった。今の発言は、どう考えてもヤバイ奴だ。ストーカーだと疑われても仕方がない。サアァと血の気が引いて、頭の中が凍りつきそうになった。
お兄さんは、ぽかんと口を開けたまま固まっている。変な奴だと思われただろう。どうにかフォローして取り繕わなければ。
「あ、の……スイマセン、キモイこと言って……。お小遣いも底を尽きたので、もう来ません。失礼しました」
これ以上、ボロを出さないようにさっさと退散しよう。俺はスクールバックを掴んで椅子から立ち上がった。
「待って」
店から出ようとしたものの、お兄さんに引き留められた。ドン引きされている訳ではなさそうだが、真顔で見つめられるのも怖い。どうしたらいいのか分からずに固まっていると、お兄さんは言葉を続けた。
「えーっと、つまり、俺に会いたくて毎日通っていたってこと?」
客観的に指摘されると、自らの異常さに気付く。だけど既に自供してしまったのだから、誤魔化しようがない。
「まあ、そういうことですね……」
もう、罵倒するなり、ドン引きするなり好きにしてくれ。断頭台に立たされた気分で処遇を待っていると、驚くべき光景が広がった。
「そっか。嬉しい」
お兄さんは、笑っていた。
笑っている時の顔は、とても正直だ。相手の感情がダイレクトに伝わってくる。普段だったらおおよその感情は読み取れるが、今向けられている笑顔だけは分からなかった。
口元は緩く弧を描き、頬はほんのり上気している。細めた目元から覗く瞳には、僅かばかりの熱が籠っていた。その笑顔はなんだ? 見ているだけで心臓が暴れまわる。身体中の血が沸騰して、みるみる体温が上昇していった。
「あのさ」
「はいっ!」
びくんと肩を振るわせながら返事をする。自分の身に何が起こっているのか分からずにパニックになっていると、お兄さんがおもむろに壁のポスターを指さした。
「ミントくん……じゃないや。君さえよければ、うちでバイトしない?」
お兄さんが指さしたのは、バイト募集のポスターだ。時給1200円。営業時間9時~20時。週2~OK。フリーター・大学生・高校生歓迎。この条件が、良いのか悪いのかはよく分からない。だけどこの店で働けば、お兄さんの笑顔を無料で拝める。それだけではない。お小遣いだって手に入るのだ。断る理由がなかった。
「やります! 俺をここで働かせてください! 明日からよろしくお願いします!」
即決だった。深々と頭を下げ、意気込みを伝える。バイトはしたことがないが、この機会を逃すわけにはいかなかった。顔を上げた時、お兄さんが困ったように眉を下げていることに気付く。
「あー、えっと、ごめん。誘っといて悪いんだけど、俺はただのバイトだから採用権限はないんだ。後日、履歴書持って、正式に応募してね」
「……ああ、はい」
脱力して椅子に座る。購入したアイスは、すっかり溶けていた。