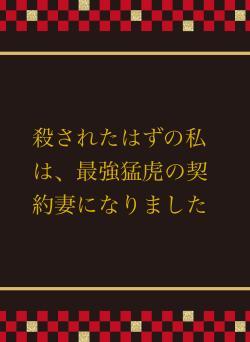バァン!と大きな音と共に、美術室の扉が開け放たれた。
施錠されていないことがわかって、雪がいると確信して顔を上げる。
「あ、おっはよ〜塁くん」
お目当ての雪はやはり美術室にいた。昨日に変わらず満面の笑みで塁を迎える。
その雪に向かって、塁はズカズカと乱暴な足音を立てて一気に近づく。そして目の前に例の絵をバっと開いて見せた。
「なんだこの絵は!」
「何って、昨日僕が描いた最高傑作! 朝イチで掲示板に貼っといた」
塁の圧にも動じない雪が明るく答える。
そこには間違いなく、雪に描かれた塁の横顔があった。
しかし、ただの横顔ではなくて――。
「なんで! いちごオレを! 飲んでんだよ!」
塁は眉根を寄せて頬を真っ赤にしながら、単語ひとつひとつを強調して叫ぶ。
挿し込まれたストローに唇を寄せて、カッコつけた表情で紙パックのいちごオレを飲んでいる横顔だった。
校内の自販機で買えるいちごオレは、パッケージがいかにもラブリーなピンク色。甘くて美味しく女子生徒にも人気。
そんな可愛いイメージの飲み物を、塁のようなヤンキーが飲んでいるという不可解な絵に仕上がっていた。
「塁くんの怖いイメージを覆すには、これかなって思って!」
「はあ⁉︎」
「好きでしょ? いちごオレ」
なんの問題もないという瞳で、含み笑いを続ける雪が腹立たしい。
ただ、塁にはこのいちごオレに心当たりがあった。
「……まさか、見たな」
「ん?」
「だから、俺がいつも昼休みに隠れて飲んでんの、見たんだろ!」
耐え難い恥辱に体を震わせながら、塁が雪を責め立てる。
男が、ましてやヤンキーに間違われるような見た目の自分が、いちごオレを好んで飲んでいる。
それは塁にとってとても恥ずかしいことで、隠したい事実だった。
すると雪は静かに首を振る。
「塁くんを見掛けていたのは、いつも後ろ姿だけだったよ」
「だったら、なんで……」
「だけど、昼休みにコソコソと非常階段に向かうとき――」
言いながら、雪の脳内で当時の記憶が再生される。
昼休みになると、一人で非常階段へと向かう塁を雪は知っていた。
その手には昼食用の菓子パンと、自販機で買ったであろう紙パックのいちごオレ。
実際に飲んでいる姿は見たことがない。けれど、その後ろ姿を毎回見ていた雪は、随分前から確信していた。
ビシッと塁の顔を指差して、自身満々に言い放つ。
「塁くんはいちごオレ好き好きマンだと知ってしまったんだ!」
「…………何言ってんだ」
ふざけているのか真面目なのか。分かりにくい雰囲気で話す雪に、塁の羞恥心も憤りも呆れに変わっていった。
「甘いもの好きに悪い人はいないよ! 塁くんのそんな一面をみんなが知ったら、変わると思ったんだ」
根拠のない持論はさておき、塁との契約を果たすためにしたこと。
得意げに説明する雪に、塁が大きなため息をついて頭を抱えた。
「……俺は、隠しておきたかったんだよ!」
「なんで?」
「揶揄われるだろ、男がこんなもん飲んでたら――」
「僕は好きだよ」
必死に隠したい理由を述べる塁に構うことなく、雪はセリフを被せてきた。
「好きだよ」の言葉が不思議と鮮明に耳に届いて、塁の口も表情も一瞬にして固まる。
同時に、心臓がドクンと大きな音を鳴らし雪の言葉に反応した。
「男も女も関係ない。髪を染める塁くんも、いちごオレ好きな塁くんも、僕は好きだよ」
「な……」
「だから好きなものを否定しないで。隠さなくていい、そのままの塁くんをもっとみんなに知ってもらおうよ」
真っ直ぐに塁だけを見つめ、真っ直ぐな言葉を塁だけに伝える。
どういうつもりで“好き”という言葉を使っているのか、塁は頭の中ではわかっていた。
犬好き、ラーメン好き、旅行好きの感覚。決してラブではないのに、雪の視線がほのかに熱を帯びているように感じた。
そんな勘違いはしてはいけないと言い聞かせて、塁は雪から視線を外す。
変に意識すると心臓の鼓動がさらに速くなりそう。こんな経験は初めてだった塁が、小さなパニックを起こしかけたとき。
雪はいつもの調子に戻って、明るく締めくくった。
「ま、一番好きなのは塁くんの横顔だけどね!」
「…………あ、っそ」
どうせ俺はデッサンの対象物ですよ。という気持ちで、塁が口先を尖らせる。
複雑な感情の中にある、ほんの少しだけ抱いた残念な気持ち。
それをあえて気づかないようにして、塁は髪をくしゃっとした。
*
もうすぐ朝のSHRが始まる時刻。美術室を出た直後の雪が、ふと塁に声をかける。
「これをきっかけに、塁くんと仲良くしたいって人も増えるかもね」
「……すでに何人かに声かけられた」
「え、すごいじゃん! 僕の戦略通りだ!」
早速効果が表れていると知って、雪が自画自賛しながら喜んでいる。
その姿が、一つ上の先輩とは思えないほどはしゃいでいて、塁の口角が少し緩んだ。
塁はこのまま真っ直ぐ廊下を進み、二年生の教室に。雪は二階の三年生の教室に向かうため、階段を降りる。
その別れ際に、雪が意味深なことを口にした。
「じゃ、また今日の放課後よろしくね」
「……は? いや、横顔のモデルは昨日で終わっただろ」
「ふふふ甘いな塁くん、いちごオレより甘いよ。契約書を見てごらん」
ニヤリと笑みを浮かべる雪に腹を立てながら、塁は鞄から契約書を取り出した。
雪の希望も叶えたし、塁の怖いイメージを払拭するという約束も、現在進行形で効果が表れていくだろう。
これにて契約書はお役御免のはずだった。
「僕は“一度だけ”なんて一言も言ってないよ?」
「……それって」
嫌な予感がして塁は眉を引き攣らせる。確かに、この契約の明確な期限は記載されていないし、決めてもいない。
「そう! だから今日の放課後も美術室で待ってるからね〜!」
必ず来るんだよ〜と付け加えて、階段を降りていく雪の姿があっという間に見えなくなった。
その場に呆然と立ち尽くす塁は、絶望感と少しの胸の高鳴りを覚えはじめる。
この混ざり合うことのない思いを抱えながら、ポツリと呟いた。
「騙された……」
なのに、塁はそれほど嫌な顔はしていない。
契約書は再び鞄の中に収め、ため息をつきながら自分の教室へと向かった。
放課後が待ち遠しいなんて気持ちも、そっと知らないふりをして。
fin.