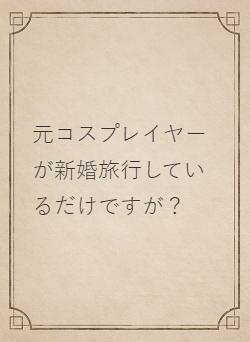・
・【09 好意】
・
今回、この自殺室に入ってきた人は女子生徒だった。
しかし彼女が入ってきても、部屋に変化は無い。
いや、あった。
部屋の中央に白いテーブルが出てきて、錠剤の入った瓶とコップ一杯の水が出現した。
それだけ。
基本的に白い空間のままということは、死にたくないとは思っているけども、死にたい気持ちも少しは持っているみたいな、半々の人なのかもしれない。
ちなみにあの錠剤は、普通の毒薬だと思われる。
何故なら錠剤が瓶の中に一個しか入っていなくて、水も一杯しかないからだ。
それを飲んで終われるみたいだ。
僕は、そんなに苦しんでいるところを見なくて済むんだ、と思って胸をなで下ろしていると、
「あれ、田中信太くん……信太くんだよね?」
と彼女に話し掛けられたので、僕は驚きながら溝渕さんへ向かって、
「あれ? 溝渕さん、僕、姿を現すように念じていないのに見られていますよ」
と言うと、彼女は矢継ぎ早にこう言った。
「信太くん、誰と喋っているの?」
どうやら溝渕さんは見えていないらしい。
一体どういうことなんだろうと、少々挙動不審になっていると、溝渕さんがこう言った。
《田中くん、どうやら今回の人は、君に用がある人みたいだ。僕は黙っているとしよう》
こんなイレギュラーもあるんだと思いつつも、この空間は不可解だらけなんだから、それを受け入れなければ。
僕は一旦深呼吸をしてから、彼女のほうを向いて、
「あの……えっと、君は誰ですか……?」
と、おそるおそる聞いてみると、彼女は優しく微笑みながら、
「私は菅野奈々江。覚えていないかもしれないけども、信太くんと会話したこともあるんだよっ」
しかし僕は正直彼女のことを全然覚えていない。
そりゃそうだ。
きっともっと大切だった光莉のことさえ、脳裏をかすめることなく没頭していたんだから。
ここはちゃんと言ったほうがいいと思って、
「ゴメン、全然覚えていない」
と俯いながら言うと、奈々江さんは当たり前だよという感じに笑いながら、
「そりゃそうだよ、入学の最初だけだもん。それ以降は成績が違うからクラスも違って。でも、こうやって、死ぬ前にまた逢えた……嬉しい……」
そう言って瞳に涙を溜めこんだ。
まさか自分で嬉し泣きをしそうになっている人をみるなんて。
僕なんて全然そんなことされていい人間じゃないのに。
でもそれを謙遜のように否定することも違うので、
「喜んでくれてありがとう」
と言って一礼すると、彼女は首を激しく横に振って、
「フフッ、困った顔しないで。私が一方的に信太くんのこと好きだっただけだからっ」
好き。
そんな短くて単純な言葉に、少し心が動かされた。
自分のことを好いてくれている人がいたなんて、知らなかったから。
僕は少しドギマギしながら、
「そ、そっか、僕のこと好きだったんだ……うん、そう言ってくれて嬉しいよ」
「信太くん、あの頃と一緒で受け答えが優しいね。私も嬉しい……というかもう……死にたいと思っていたけども、信太くんを見たら死にたくなくなってきた……何でいるの、決意が揺らいじゃうよ……」
「あっ、ゴメン……僕も自分ではよく分からないけども、この部屋は・・・」
「いやっでも!」
と、僕がこの部屋と僕について説明をしようとしたところで、彼女は僕の言葉を制止し、喋り始めた。
まるで何かを決心したかのような表情をしている。
一体何をする気なんだろうか。
「もう……いることは受け入れるよ、うん……あのね、だからね、その、信太くん……」
彼女は顔ばかりか体中を紅潮し、こっちを見ながら、こう言った。
「最期に、私の裸、見てくれないかな……」
そう言って服を脱ぎ始めた彼女。
僕はそれを止めようと、彼女の腕を掴もうとしたが、触れることはできなかった。
「やっぱり信太くんには触れられないんだね、なんとなくそう思ったよ。だって信太くん、私と違って透明感があるから」
「そ、それは、君が僕のことを好きだからじゃない、かな」
「ううん、何か違う。ここにいる信太くんは何か違うよ。本当は幻だと思っているよ、私」
そう言いながらも、どんどん服を脱いでいく奈々江さん。
制服のリボンを外し、男子はよく知らないだろう位置のボタンをパチパチと外していく。
あんなところにもボタンがあったんだ、みたいなバカなことを一瞬考えてしまう自分が少し嫌だ。
ブレザーはもう床に落として、シャツとスカートだけになった奈々江さん。
僕はなんとか止めようと思って、喋り始めた。
「いや、幻ではないんだ。僕は今ここで自殺室に入ってきた人を自殺に導く案内人をしているんだ」
すると奈々江さんはフフッと笑ってから、
「何それ、幻だね」
ちょっと脱ぐ手が止まった奈々江さんに僕は畳みかける。
「幻じゃなくて、あの、僕は死にたくても死ねない状況なんだ。この自殺室は死にたい人は死ねなくて、生きたい人が死なないといけなくて」
「じゃあ幻だね、だって生きてるんだもん」
「生きてるから幻じゃないんだけども」
「信太くんは私にとって幻のような存在なの。まあこれは私だけの感覚だから言っても分かんないよね」
確かに僕は幻じゃないと言っているのに、幻だと言い張る奈々江さんに僕は混乱している。
でも奈々江さんの脱ぐ手は止まっているので、このまま喋っていくことにしよう。
「まあ幻云々はどうでもいいとして、この空間は早く自殺しようとしないと、居た堪れない死に方をしてしまうんだ。だから早くその毒薬を飲むべきなんだ」
「そんな急がせないでよ、せっかく最期に信太くんと出会えたのに」
「でも本当に、苦しみがずっと続くような死に方をしてしまうんだ」
「私は別にそれでもいいよ、だって信太くんと会話できる状況でしないほうが苦しいよ」
そう言って自分の胸元をギュッと握った奈々江さん。
真に迫るその表情に、僕はドキッとした。
奈々江さんは続ける。
「というかずっと苦しかったんだ、信太くんとは住む世界が違って。何だか立場も違うような」
「同じ学校なんだから住む世界も立場も全く一緒だよ」
「ううん、違うよ、全然違うよ、ある意味住む世界が同じだからこそ遠さがより分かったよ」
奈々江さんの言う通り、多分クラスが違ったんだろう。
この学校は成績ごとにクラスを分けているので、確かにクラスが違えば交流も基本無い。
その交流が無くなってしまうせいで、僕は光莉のことを忘れてしまったんだ。
いや、クラスのせいにしてはいけない。
僕は注意散漫だった。
光莉は光莉でそれなりに優秀だったので、絶対大丈夫だと思っていた。
そう思ってしまった、そう妄信し、猛進したことが間違いだったんだ。
奈々江さんは少し心配そうな表情をしながら、こう言った。
「何かつらいこと思い出したの? 信太くん」
ハッキリ心の中を見透かされていて、驚いていると、
「好きな人の考えていることくらい、顔を見れば分かるよっ」
じゃあ僕は。
僕は光莉の顔を見て、本当に光莉のことを分かっていたのか。
光莉はいつも笑っていたけども、もしかしたら僕と一緒にいることは苦痛だったのか。
楽しかったのは僕だけだったのか。
僕が『一生一緒にいたい』と言ったから、光莉は無理してこの学校へ入学して。
僕のせいでこうなってしまったんじゃないか。
全部全部僕のせいで、ダメだ、ダメだ、ダメだ、死にたい。
また襲ってきたこの気持ち。
死にたいんだ。
今日も死にたいんだ。
死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだいじょうぶ?
えっ?
「大丈夫?」
気付いた時には奈々江さんが僕を抱き締め、耳元で「大丈夫?」と囁いていた。
今、奈々江さんは僕に触れることができている。
そのことに奈々江さんも驚いているようで、
「ゴメン、信太くん。信太くんって幻じゃなかったんだね、本当に生きているんだね。心臓の鼓動が聞こえるよ」
そう言ってから少し僕から離れて、顔を見せて笑ってくれた奈々江さん。
僕は何を言えばいいのか困惑していると、
「でも良かった。困惑してくれて。困惑って、困って惑わされてってことだもんね。心が私のほうを向いてくれて嬉しい」
「奈々江さん、すみません……今ちょっと他のことを考えていて……本当はもっと奈々江さんのことを考えないといけないんですけども」
「ううん、大丈夫だよ。信太くんの顔が大丈夫になってくれれば大丈夫。正直さっきつらそうだったもん。あんまりつらいことばかり考えないで」
「ありがとう」
そう落ち着きを取り戻そうと、自分に言い聞かすようにそう言うと、奈々江さんはコップを僕に差し出してきた。
「水を飲んで一旦休んで。私は薬を飲むにしても水が無くても大丈夫だから」
僕はその奈々江さんの好意を無下にできないという気持ちが大きくなって、促されるまま水を飲んだ。
水を飲んだコップを白い机の上に置くと、案の定、また水が出現した。
「なるほど、そうなるんだね。面白い空間だね」
そう言ってクスクス笑った奈々江さん。
どこか奈々江さんは余裕がある。
正直僕なんかよりもずっとずっと大きく感じた。
だから、
「何で奈々江さんはそんなに落ち着いていられるんですか?」
「もういいかなと思っているからかな。そりゃ死にたくないけども、死なないともいけないんだな、って」
それがこの白い空間、白い机に、白い錠剤、白いコップなんだろうな。
これなら長いこと、この空間にいても、苦しんで死ぬことはないのかもしれないな。
要素も全然無いし。
いやだからってこれ以上、脱がれても目のやり場に困ってしまうけども、と思ったタイミングで奈々江さんがこう言った。
「じゃあ私、脱ぐね」
そう言ってシャツのボタンにも手を掛け始めたので、僕は慌てながら、
「いやいや! 脱がないで! 脱がないで! というか何で脱ごうと思っているのっ?」
「だって、好きな人に自分の裸見てほしいじゃん」
「いやでも! 急にそんなのは困るよ!」
「困ってくれるのは大好き。いっぱい私のこと考えてほしいんだ」
そう言って、どんどんボタンを外していく奈々江さん。
さっき奈々江さんは僕に触れられたんだからと思って、僕は腕を掴もうとしたが、それはすり抜けてしまった。
それに対して奈々江さんは、
「何だか不思議。ずっと私に有利なように触れられたり触れられなかったり、この空間は天国かもしれないね。澄んだ良い空気だし」
そう話しながら、スルスルと服を脱いでいく奈々江さん。
僕は目を逸らそうと思って、後ろを振り返ろうとしたその時に気付いてしまった。
僕自身、動けなくなっていることに。
というか瞬きもできなくなっている。
まさか動きの制限が僕にも作用するなんて。
硬直しつつ、その場で黙って立っていると、奈々江さんはまた僕の異変に気付いたようで、
「もしかすると動けないの? 視線を動かすこともできないの? なんて私に有利なの……嬉しいなぁ……死にたくないなぁ、ずっとこうしていたいなぁ……」
そして下着姿になった奈々江さんを見て、僕はゾッとしてしまった。
なんと、体中に生傷がたくさんあったからだ。
その多分、ギョッとしてしまった僕を見た奈々江さんはこう言った。
「あっ、そんな顔しないで。傷を見せたいわけじゃないんだ。ただただ裸を見てほしくて。信太くんにえっちな気持ちになってほしくて……でも無理だよね……ゴメン……」
少し俯いてしまった奈々江さんに僕は聞いてもいいかどうか迷ったけども、何だか聞かないと話が進まないような気がして、
「そのケガ、どうしたの?」
奈々江さんは俯きながら喋り始めた。
「この学校の成績下位なんて、みんなこんなもんだよ。いつか死ぬと思って、イジメが横行しているんだ。まあ本当に上位の人たちは自分にしか興味が無いから、信太くんみたいな人は知らなかったと思うけども」
上位の人たちは自分にしか興味が無い。
この言葉を聞いて僕も俯きたいが、今は俯けず、ずっと奈々江さんの下着姿を見ている。
奈々江さんは少し顔を上げて、
「弱肉強食って本当に怖いよね、というかコイツは自分より下だと認識した時の人って本当に怖いよね」
額を抑えながら喋る奈々江さん。
「死にたくないけども、自殺室に来れて良かったなと思うところもちょっとあって。でも今は死にたくないなぁ。だって、信太くんがいるんだもん。ずっと信太くんと一緒にいたいよ……」
そう言ってついには泣き出した彼女。
そうだ。
そういうことだ。
僕が自分を消したくなった理由と繋がる。
彼女はすぐに気付く。
物事に変化があれば、好きな人に異変があれば、すぐに気付いて想うんだ。
でも僕は大切な人を失ったことさえも気付かず、盲目で生きる。
ある日、ふとした瞬間に気付いた時にはもう遅くて。
だから殺したくなったんだ。
でも結局。
今でさえ。
僕のことを大切に想ってくれている人の死ぬ間際にも、何も感じなくなっている部分もある。
服着ていないと寒くないかな、とか、どうでもいいことを考えてしまう自分が嫌だ。
殺したい。
殺したい。
自分を殺したい。
「ゴメンね、ゴメンね、勝手に一人で盛り上がって泣いちゃって、キモいよね、ゴメン、信太くん、ゴメン……」
そう言って涙をボロボロ流す奈々江さん。
僕は首を横に振っているつもりで、
「いや、全然気持ち悪くないよ。むしろその清廉潔白な君が羨ましいよ」
「全然清廉潔白じゃないよ」
「だから、その、服を着てほしいんだ。その状況じゃ、君のことを見づらいよ。君の顔を、君の姿をしっかり僕に見せてほしいんだ」
「私のこと見てくれるの? ホントに?」
そう言って笑った奈々江さん。
僕は頷いたつもりで、
「うん、見るよ。というか君のような人をしっかり見たいよ。だから」
「分かった……」
そう言って服を着た彼女。
一回脱ぐ時に服をくしゃくしゃにしたはずなのに、入ってきた時よりも何だか輝いて見えた。
「あぁーぁ、死にたくないなぁ、ずっと信太くんと一緒にいたいなぁ、でも無理なんでしょ、きっと無理なんでしょ? 分かるよ、なんとなく分かるよ、私」
「うん、僕は死にたくても死ねないし、君は死にたくないから死なないといけないんだ」
「何かあべこべだけど、そういうことだと思う。でも嫌だな、信太くんに死ぬ瞬間を見られるなんて嫌だよ……醜く死ぬところなんて見られたくない……」
醜く死ぬというワードで、僕は、公衆便所の彼や鏡張りの彼がああなって死んだことを思い出し、言葉が詰まる。
奈々江さんは続ける。
「変に泡吹いて死なないといいな……そんなところ信太くんに見せたくないから……でも」
でも、って一体何だろうか。
僕は気になって、そのままオウム返しした。
「……でも?」
「幸せなのかな、とも、ほんの少しだけ思うの……」
理解ができなくて、短絡的な言葉しか出てこない自分に嫌気が差しつつも、
「……何で?」
と聞くと、奈々江さんは切なく微笑みながら、
「だって自分の最期を好きな人に看取ってもらえるんだもん」
正直意味は理解できているけども、どこか理解できなかった。
もし同じ状況なら、僕は死にたくないから。
やっぱりずっと一緒にいたいと思ってしまうから。
と思ったその時だった。
少し自分の体が動いたような気がした。
何か前進して、奈々江さんのほうへ歩き出すような。
そして少し腕に力が宿ったような気がした。
嫌な予感を抱いた。
まさか奈々江さんはこのまま死のうとしなければ、まさか……の、刹那、彼女は錠剤を口に含み、水を飲みこみ、その場に膝から崩れ落ちた。
そして彼女の体は星の砂のようにサラサラと崩れていき、同じように自殺室に出現した白い机も風化され始め、元の自殺室に戻った。
まさかこんな美しい死があるなんて、知らなかった。
こんな風に死にたい、と強く願ったが、強く願うほどに死ねないのだろうな。
そして気配を消していた溝渕さんがアゴを触りながら喋り出した。
「彼女の死を替わってあげたかったよ、俺は。君と彼女でこの自殺室の案内人をすればいいのにと思ったよ」
僕は首を横に振った。
「いや、ダメですよ。僕が奈々江さんを穢してしまいますよ。きっと、そうだ」
「そうかなぁ」
溝渕さんは納得のいっていない表情で相槌を打った。
ところで
「もし、僕が死んでいたら、奈々江さんの自殺室はどうなっていたんでしょうかね」
「きっと本物の君の幻を見たんじゃないかなぁ」
本物の幻。
それこそ存在しない話なんだけども、今の僕よりも、彼女が見る本物の幻のほうが最期に良いことを言った気がした。
僕はダメだ。
何をしても中途半端だ。
だから自殺室に逃げてきたんだ。
そして中途半端に逃げてきたから、自殺室で死ねないんだ。
溝渕さんはまた部屋の隅に体育座りをした。
僕は奈々江さんがいた場所にしゃがんで、ゆっくり目を閉じた。
奈々江さんがいたことを忘れないように。
しっかり記憶するように、目を閉じた。
そして考える。
自分が動き出しそうになっていたことを。
きっと奈々江さんは自殺しなければ、僕が無理やり、力づくで毒薬を飲ませたんだろうな。
そうならなくて良かった。
奈々江さんが自ら死を選んでくれて助かった。
僕が奈々江さんを直接自殺させようとしたら、もっと僕は死にたくなっただろうから。
とか、ほらまただ、すぐ自分のことを考えている。
もうだ。
もう自分のことを考えてしまった。
嫌だ。
こんな自分が嫌いだ。
早く死にたい。
・【09 好意】
・
今回、この自殺室に入ってきた人は女子生徒だった。
しかし彼女が入ってきても、部屋に変化は無い。
いや、あった。
部屋の中央に白いテーブルが出てきて、錠剤の入った瓶とコップ一杯の水が出現した。
それだけ。
基本的に白い空間のままということは、死にたくないとは思っているけども、死にたい気持ちも少しは持っているみたいな、半々の人なのかもしれない。
ちなみにあの錠剤は、普通の毒薬だと思われる。
何故なら錠剤が瓶の中に一個しか入っていなくて、水も一杯しかないからだ。
それを飲んで終われるみたいだ。
僕は、そんなに苦しんでいるところを見なくて済むんだ、と思って胸をなで下ろしていると、
「あれ、田中信太くん……信太くんだよね?」
と彼女に話し掛けられたので、僕は驚きながら溝渕さんへ向かって、
「あれ? 溝渕さん、僕、姿を現すように念じていないのに見られていますよ」
と言うと、彼女は矢継ぎ早にこう言った。
「信太くん、誰と喋っているの?」
どうやら溝渕さんは見えていないらしい。
一体どういうことなんだろうと、少々挙動不審になっていると、溝渕さんがこう言った。
《田中くん、どうやら今回の人は、君に用がある人みたいだ。僕は黙っているとしよう》
こんなイレギュラーもあるんだと思いつつも、この空間は不可解だらけなんだから、それを受け入れなければ。
僕は一旦深呼吸をしてから、彼女のほうを向いて、
「あの……えっと、君は誰ですか……?」
と、おそるおそる聞いてみると、彼女は優しく微笑みながら、
「私は菅野奈々江。覚えていないかもしれないけども、信太くんと会話したこともあるんだよっ」
しかし僕は正直彼女のことを全然覚えていない。
そりゃそうだ。
きっともっと大切だった光莉のことさえ、脳裏をかすめることなく没頭していたんだから。
ここはちゃんと言ったほうがいいと思って、
「ゴメン、全然覚えていない」
と俯いながら言うと、奈々江さんは当たり前だよという感じに笑いながら、
「そりゃそうだよ、入学の最初だけだもん。それ以降は成績が違うからクラスも違って。でも、こうやって、死ぬ前にまた逢えた……嬉しい……」
そう言って瞳に涙を溜めこんだ。
まさか自分で嬉し泣きをしそうになっている人をみるなんて。
僕なんて全然そんなことされていい人間じゃないのに。
でもそれを謙遜のように否定することも違うので、
「喜んでくれてありがとう」
と言って一礼すると、彼女は首を激しく横に振って、
「フフッ、困った顔しないで。私が一方的に信太くんのこと好きだっただけだからっ」
好き。
そんな短くて単純な言葉に、少し心が動かされた。
自分のことを好いてくれている人がいたなんて、知らなかったから。
僕は少しドギマギしながら、
「そ、そっか、僕のこと好きだったんだ……うん、そう言ってくれて嬉しいよ」
「信太くん、あの頃と一緒で受け答えが優しいね。私も嬉しい……というかもう……死にたいと思っていたけども、信太くんを見たら死にたくなくなってきた……何でいるの、決意が揺らいじゃうよ……」
「あっ、ゴメン……僕も自分ではよく分からないけども、この部屋は・・・」
「いやっでも!」
と、僕がこの部屋と僕について説明をしようとしたところで、彼女は僕の言葉を制止し、喋り始めた。
まるで何かを決心したかのような表情をしている。
一体何をする気なんだろうか。
「もう……いることは受け入れるよ、うん……あのね、だからね、その、信太くん……」
彼女は顔ばかりか体中を紅潮し、こっちを見ながら、こう言った。
「最期に、私の裸、見てくれないかな……」
そう言って服を脱ぎ始めた彼女。
僕はそれを止めようと、彼女の腕を掴もうとしたが、触れることはできなかった。
「やっぱり信太くんには触れられないんだね、なんとなくそう思ったよ。だって信太くん、私と違って透明感があるから」
「そ、それは、君が僕のことを好きだからじゃない、かな」
「ううん、何か違う。ここにいる信太くんは何か違うよ。本当は幻だと思っているよ、私」
そう言いながらも、どんどん服を脱いでいく奈々江さん。
制服のリボンを外し、男子はよく知らないだろう位置のボタンをパチパチと外していく。
あんなところにもボタンがあったんだ、みたいなバカなことを一瞬考えてしまう自分が少し嫌だ。
ブレザーはもう床に落として、シャツとスカートだけになった奈々江さん。
僕はなんとか止めようと思って、喋り始めた。
「いや、幻ではないんだ。僕は今ここで自殺室に入ってきた人を自殺に導く案内人をしているんだ」
すると奈々江さんはフフッと笑ってから、
「何それ、幻だね」
ちょっと脱ぐ手が止まった奈々江さんに僕は畳みかける。
「幻じゃなくて、あの、僕は死にたくても死ねない状況なんだ。この自殺室は死にたい人は死ねなくて、生きたい人が死なないといけなくて」
「じゃあ幻だね、だって生きてるんだもん」
「生きてるから幻じゃないんだけども」
「信太くんは私にとって幻のような存在なの。まあこれは私だけの感覚だから言っても分かんないよね」
確かに僕は幻じゃないと言っているのに、幻だと言い張る奈々江さんに僕は混乱している。
でも奈々江さんの脱ぐ手は止まっているので、このまま喋っていくことにしよう。
「まあ幻云々はどうでもいいとして、この空間は早く自殺しようとしないと、居た堪れない死に方をしてしまうんだ。だから早くその毒薬を飲むべきなんだ」
「そんな急がせないでよ、せっかく最期に信太くんと出会えたのに」
「でも本当に、苦しみがずっと続くような死に方をしてしまうんだ」
「私は別にそれでもいいよ、だって信太くんと会話できる状況でしないほうが苦しいよ」
そう言って自分の胸元をギュッと握った奈々江さん。
真に迫るその表情に、僕はドキッとした。
奈々江さんは続ける。
「というかずっと苦しかったんだ、信太くんとは住む世界が違って。何だか立場も違うような」
「同じ学校なんだから住む世界も立場も全く一緒だよ」
「ううん、違うよ、全然違うよ、ある意味住む世界が同じだからこそ遠さがより分かったよ」
奈々江さんの言う通り、多分クラスが違ったんだろう。
この学校は成績ごとにクラスを分けているので、確かにクラスが違えば交流も基本無い。
その交流が無くなってしまうせいで、僕は光莉のことを忘れてしまったんだ。
いや、クラスのせいにしてはいけない。
僕は注意散漫だった。
光莉は光莉でそれなりに優秀だったので、絶対大丈夫だと思っていた。
そう思ってしまった、そう妄信し、猛進したことが間違いだったんだ。
奈々江さんは少し心配そうな表情をしながら、こう言った。
「何かつらいこと思い出したの? 信太くん」
ハッキリ心の中を見透かされていて、驚いていると、
「好きな人の考えていることくらい、顔を見れば分かるよっ」
じゃあ僕は。
僕は光莉の顔を見て、本当に光莉のことを分かっていたのか。
光莉はいつも笑っていたけども、もしかしたら僕と一緒にいることは苦痛だったのか。
楽しかったのは僕だけだったのか。
僕が『一生一緒にいたい』と言ったから、光莉は無理してこの学校へ入学して。
僕のせいでこうなってしまったんじゃないか。
全部全部僕のせいで、ダメだ、ダメだ、ダメだ、死にたい。
また襲ってきたこの気持ち。
死にたいんだ。
今日も死にたいんだ。
死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだ死にたいんだいじょうぶ?
えっ?
「大丈夫?」
気付いた時には奈々江さんが僕を抱き締め、耳元で「大丈夫?」と囁いていた。
今、奈々江さんは僕に触れることができている。
そのことに奈々江さんも驚いているようで、
「ゴメン、信太くん。信太くんって幻じゃなかったんだね、本当に生きているんだね。心臓の鼓動が聞こえるよ」
そう言ってから少し僕から離れて、顔を見せて笑ってくれた奈々江さん。
僕は何を言えばいいのか困惑していると、
「でも良かった。困惑してくれて。困惑って、困って惑わされてってことだもんね。心が私のほうを向いてくれて嬉しい」
「奈々江さん、すみません……今ちょっと他のことを考えていて……本当はもっと奈々江さんのことを考えないといけないんですけども」
「ううん、大丈夫だよ。信太くんの顔が大丈夫になってくれれば大丈夫。正直さっきつらそうだったもん。あんまりつらいことばかり考えないで」
「ありがとう」
そう落ち着きを取り戻そうと、自分に言い聞かすようにそう言うと、奈々江さんはコップを僕に差し出してきた。
「水を飲んで一旦休んで。私は薬を飲むにしても水が無くても大丈夫だから」
僕はその奈々江さんの好意を無下にできないという気持ちが大きくなって、促されるまま水を飲んだ。
水を飲んだコップを白い机の上に置くと、案の定、また水が出現した。
「なるほど、そうなるんだね。面白い空間だね」
そう言ってクスクス笑った奈々江さん。
どこか奈々江さんは余裕がある。
正直僕なんかよりもずっとずっと大きく感じた。
だから、
「何で奈々江さんはそんなに落ち着いていられるんですか?」
「もういいかなと思っているからかな。そりゃ死にたくないけども、死なないともいけないんだな、って」
それがこの白い空間、白い机に、白い錠剤、白いコップなんだろうな。
これなら長いこと、この空間にいても、苦しんで死ぬことはないのかもしれないな。
要素も全然無いし。
いやだからってこれ以上、脱がれても目のやり場に困ってしまうけども、と思ったタイミングで奈々江さんがこう言った。
「じゃあ私、脱ぐね」
そう言ってシャツのボタンにも手を掛け始めたので、僕は慌てながら、
「いやいや! 脱がないで! 脱がないで! というか何で脱ごうと思っているのっ?」
「だって、好きな人に自分の裸見てほしいじゃん」
「いやでも! 急にそんなのは困るよ!」
「困ってくれるのは大好き。いっぱい私のこと考えてほしいんだ」
そう言って、どんどんボタンを外していく奈々江さん。
さっき奈々江さんは僕に触れられたんだからと思って、僕は腕を掴もうとしたが、それはすり抜けてしまった。
それに対して奈々江さんは、
「何だか不思議。ずっと私に有利なように触れられたり触れられなかったり、この空間は天国かもしれないね。澄んだ良い空気だし」
そう話しながら、スルスルと服を脱いでいく奈々江さん。
僕は目を逸らそうと思って、後ろを振り返ろうとしたその時に気付いてしまった。
僕自身、動けなくなっていることに。
というか瞬きもできなくなっている。
まさか動きの制限が僕にも作用するなんて。
硬直しつつ、その場で黙って立っていると、奈々江さんはまた僕の異変に気付いたようで、
「もしかすると動けないの? 視線を動かすこともできないの? なんて私に有利なの……嬉しいなぁ……死にたくないなぁ、ずっとこうしていたいなぁ……」
そして下着姿になった奈々江さんを見て、僕はゾッとしてしまった。
なんと、体中に生傷がたくさんあったからだ。
その多分、ギョッとしてしまった僕を見た奈々江さんはこう言った。
「あっ、そんな顔しないで。傷を見せたいわけじゃないんだ。ただただ裸を見てほしくて。信太くんにえっちな気持ちになってほしくて……でも無理だよね……ゴメン……」
少し俯いてしまった奈々江さんに僕は聞いてもいいかどうか迷ったけども、何だか聞かないと話が進まないような気がして、
「そのケガ、どうしたの?」
奈々江さんは俯きながら喋り始めた。
「この学校の成績下位なんて、みんなこんなもんだよ。いつか死ぬと思って、イジメが横行しているんだ。まあ本当に上位の人たちは自分にしか興味が無いから、信太くんみたいな人は知らなかったと思うけども」
上位の人たちは自分にしか興味が無い。
この言葉を聞いて僕も俯きたいが、今は俯けず、ずっと奈々江さんの下着姿を見ている。
奈々江さんは少し顔を上げて、
「弱肉強食って本当に怖いよね、というかコイツは自分より下だと認識した時の人って本当に怖いよね」
額を抑えながら喋る奈々江さん。
「死にたくないけども、自殺室に来れて良かったなと思うところもちょっとあって。でも今は死にたくないなぁ。だって、信太くんがいるんだもん。ずっと信太くんと一緒にいたいよ……」
そう言ってついには泣き出した彼女。
そうだ。
そういうことだ。
僕が自分を消したくなった理由と繋がる。
彼女はすぐに気付く。
物事に変化があれば、好きな人に異変があれば、すぐに気付いて想うんだ。
でも僕は大切な人を失ったことさえも気付かず、盲目で生きる。
ある日、ふとした瞬間に気付いた時にはもう遅くて。
だから殺したくなったんだ。
でも結局。
今でさえ。
僕のことを大切に想ってくれている人の死ぬ間際にも、何も感じなくなっている部分もある。
服着ていないと寒くないかな、とか、どうでもいいことを考えてしまう自分が嫌だ。
殺したい。
殺したい。
自分を殺したい。
「ゴメンね、ゴメンね、勝手に一人で盛り上がって泣いちゃって、キモいよね、ゴメン、信太くん、ゴメン……」
そう言って涙をボロボロ流す奈々江さん。
僕は首を横に振っているつもりで、
「いや、全然気持ち悪くないよ。むしろその清廉潔白な君が羨ましいよ」
「全然清廉潔白じゃないよ」
「だから、その、服を着てほしいんだ。その状況じゃ、君のことを見づらいよ。君の顔を、君の姿をしっかり僕に見せてほしいんだ」
「私のこと見てくれるの? ホントに?」
そう言って笑った奈々江さん。
僕は頷いたつもりで、
「うん、見るよ。というか君のような人をしっかり見たいよ。だから」
「分かった……」
そう言って服を着た彼女。
一回脱ぐ時に服をくしゃくしゃにしたはずなのに、入ってきた時よりも何だか輝いて見えた。
「あぁーぁ、死にたくないなぁ、ずっと信太くんと一緒にいたいなぁ、でも無理なんでしょ、きっと無理なんでしょ? 分かるよ、なんとなく分かるよ、私」
「うん、僕は死にたくても死ねないし、君は死にたくないから死なないといけないんだ」
「何かあべこべだけど、そういうことだと思う。でも嫌だな、信太くんに死ぬ瞬間を見られるなんて嫌だよ……醜く死ぬところなんて見られたくない……」
醜く死ぬというワードで、僕は、公衆便所の彼や鏡張りの彼がああなって死んだことを思い出し、言葉が詰まる。
奈々江さんは続ける。
「変に泡吹いて死なないといいな……そんなところ信太くんに見せたくないから……でも」
でも、って一体何だろうか。
僕は気になって、そのままオウム返しした。
「……でも?」
「幸せなのかな、とも、ほんの少しだけ思うの……」
理解ができなくて、短絡的な言葉しか出てこない自分に嫌気が差しつつも、
「……何で?」
と聞くと、奈々江さんは切なく微笑みながら、
「だって自分の最期を好きな人に看取ってもらえるんだもん」
正直意味は理解できているけども、どこか理解できなかった。
もし同じ状況なら、僕は死にたくないから。
やっぱりずっと一緒にいたいと思ってしまうから。
と思ったその時だった。
少し自分の体が動いたような気がした。
何か前進して、奈々江さんのほうへ歩き出すような。
そして少し腕に力が宿ったような気がした。
嫌な予感を抱いた。
まさか奈々江さんはこのまま死のうとしなければ、まさか……の、刹那、彼女は錠剤を口に含み、水を飲みこみ、その場に膝から崩れ落ちた。
そして彼女の体は星の砂のようにサラサラと崩れていき、同じように自殺室に出現した白い机も風化され始め、元の自殺室に戻った。
まさかこんな美しい死があるなんて、知らなかった。
こんな風に死にたい、と強く願ったが、強く願うほどに死ねないのだろうな。
そして気配を消していた溝渕さんがアゴを触りながら喋り出した。
「彼女の死を替わってあげたかったよ、俺は。君と彼女でこの自殺室の案内人をすればいいのにと思ったよ」
僕は首を横に振った。
「いや、ダメですよ。僕が奈々江さんを穢してしまいますよ。きっと、そうだ」
「そうかなぁ」
溝渕さんは納得のいっていない表情で相槌を打った。
ところで
「もし、僕が死んでいたら、奈々江さんの自殺室はどうなっていたんでしょうかね」
「きっと本物の君の幻を見たんじゃないかなぁ」
本物の幻。
それこそ存在しない話なんだけども、今の僕よりも、彼女が見る本物の幻のほうが最期に良いことを言った気がした。
僕はダメだ。
何をしても中途半端だ。
だから自殺室に逃げてきたんだ。
そして中途半端に逃げてきたから、自殺室で死ねないんだ。
溝渕さんはまた部屋の隅に体育座りをした。
僕は奈々江さんがいた場所にしゃがんで、ゆっくり目を閉じた。
奈々江さんがいたことを忘れないように。
しっかり記憶するように、目を閉じた。
そして考える。
自分が動き出しそうになっていたことを。
きっと奈々江さんは自殺しなければ、僕が無理やり、力づくで毒薬を飲ませたんだろうな。
そうならなくて良かった。
奈々江さんが自ら死を選んでくれて助かった。
僕が奈々江さんを直接自殺させようとしたら、もっと僕は死にたくなっただろうから。
とか、ほらまただ、すぐ自分のことを考えている。
もうだ。
もう自分のことを考えてしまった。
嫌だ。
こんな自分が嫌いだ。
早く死にたい。