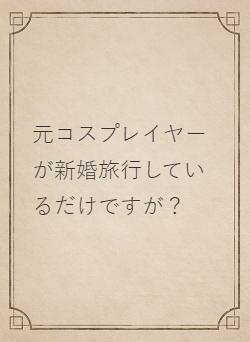・
・【08 想う呟き】
・
僕はふと、
「光莉……」
と声が漏れ出るように呟いてしまった。
自分で言っててキモイと思ってしまったんだけども、溝渕さんは僕の言葉に反応して喋り始めた。
「相当後悔しているんだな」
「していますよ、溝渕さんもそうですよね」
そう自分のキモさをかき消すため、あえて切り返すと、溝渕さんはアゴを触りながら、
「当然だろ。俺も後悔しているよ。どうする? この流れ。田中くんが喋るか、俺が喋るか」
僕はもしかしたら前にいた女子生徒というヤツは、溝渕さんの話を聞いてから死んでいったのかもしれないと思ったので、
「溝渕さんが過去を喋っていいと思うなら、喋ってくれると有難いです」
と答えると、溝渕さんに座ることを促されたので、座り、溝渕さんも近くに座ってから口を改めて開いた。
「元々俺は極貧街の出身で、食べることは勿論、寝ることもままならなかった。ずっと厳しい労働を子供の頃から強いられてな。その時に出会った上流階級の娘、それが俺と一緒にこの高校へ入ることになったカヲルという女子だ」
当たり前だけども、僕とはちょっと違う境遇だ。まあ全部合っているほうがおかしいけども。
溝渕さんは続ける。
「俺は毎日、カヲルからパンをもらっていた。また時間がある時は勉強を教えてもらってな。そこで計算ができるようになって、肉体労働から頭脳労働へ徐々にシフトチェンジできるようになっていったんだ。勿論、どっちにしろ子供が働くのは法律違反だが、そういうことを言ってられる世界観じゃなかったからな」
僕は静かに頷く。
溝渕さんもそれ以上は求めないで、語り続ける。
「そんなある日、カヲルは俺にパンを与え、勉強を教えていることをカヲルの両親に知られたんだ。俺はどうなったと思う?」
急な質問文に少々驚いてしまって、その場に固まってしまうと、
「何、ちょっとクイズ形式であったほうが会話も捗るだろと思っただけだ。でもどうせ暇だろ? ここは俺にとって転機になったところだから、考えてみてくれよ」
そう言って笑った溝渕さん。
なりに、という言葉は上から目線みたいで好きじゃないんだけども、溝渕さんなりに僕へ歩み寄ってきてくれているのかなと思って、僕は、
「分かりました。ちょっと考えてみますね」
と言ってから、無意識に腕を組んでしまい、すぐさま腕を解いてぶらんぶらんとさせた。
それに対して溝渕さんは、
「別に腕くらい組んでいいよ、それ見て偉そうだなとか思わないし。俺が年上かどうかなんて気にしなくていいからな。年齢なんてこの場に相応しくない。あるのは同じ立場だということだけだ」
「同じ立場ですか」
「そうだ、田中くんはスポーツとか観戦するかい?」
「あんまり興味はありませんでしたね」
「でも相手のことを敵とか、敵地と言ったり、アウェイと言ったりすることは知っているだろう」
僕はうんうんと相槌を打ちながら、
「それは知識として知っています」
「でも実際は敵ではないんだよ、同じ立場なだけ。同じ立場だからいがみ合っているようになっているが、本当は全員が全員、共通の話題がある仲間なんだよ」
「何だか平和な考え方ですね、この学校には合わないと思います」
「その通り。なんせ俺もこの考えになったのはこの自殺室に来てからだからな。だから俺は自殺室に来てしまった生徒にはできるだけ安らかに死んでほしいんだ。まあ実際は俺や田中くんとは立場は違うんだが、でもまあ同じと言えば同じだ。同じ仲間として、嘘をついても優しくありたいのさ」
正直こういうところだと思った。
溝渕さんが自殺室で死ねない理由って。
そしてその素養がきっと僕にもあって。
優し過ぎて、自分を殺したくなるから死ねないんだ。
そんなことを考えていると、溝渕さんはふとこう言った。
「でも勝ち負けというものはある。その場合、自殺した生徒が勝ちで俺や田中くんが負けなのか。それとも生きたいのに死んだ生徒が負けで、さらに死にたいのに生きている俺と田中くんも負けなのか。まあ自殺室に来る時点で負けなんだろうな」
「そうですね」
曖昧に頷きが、ここはあえて口に出して返事をした、と、たっぷり意識をしたわけじゃないんだけども、この言葉はさらりと口から流れ出た。
僕の相槌に溝渕さんはフッと笑ってから、
「そういうことだよな」
と一瞬伏し目になってから、
「そうだ、そうだ、田中くん。話は俺のクイズからだったな、シンキングタイムも終了だ。答えは出たかな」
「いやシンキングタイムの話が考えさせられる話でクイズどころじゃなかったですよ」
「そうか、確かにノイズにはなっていたかもな。じゃあ改めて考えてほしい」
さて、じゃあちゃんと思考してみよう。
溝渕さんは結果的にカヲルさんと一緒にこの学校に入っているわけだから、仲違いしたわけではないだろう。
ということは関係は継続していると考えることが自然だろう。
でもここをクイズに出したということは、何か特殊なことが起きた可能性もある。
それか言葉か、関係は継続したけども変わった言葉を言われたというパターンもあるだろう、と思ったところで溝渕さんが、
「今考えている思考を教えてくれないか、競技クイズやクイズ番組でも、答えたあとの感想戦があるけども、今は二人きりだ。思考途中の式を教えてくれないかな?」
僕は今考えていたことをそのまま言葉にすると、溝渕さんはニヤッと笑ってから、
「やっぱり田中くんは賢いな、その方向性で当たりだ。もしかしたら正解しちゃうかもしれないな」
まず合っていたということが嬉しかったし、何だか少し楽しくなった。
だからって生きたくなるほどではないが、正直今はこの答えを聞かずには死にたくない。
やっぱり人と関わるってことは良いことなのかもしれない、そんなことを考えてから僕はもっと深く思考することにした。
言葉、何を言われたか、もしかすると”男女としてお似合い”みたいなことかもしれない。
これは結構意外だと思う。両親から急にこんなこと言われたらビックリするだろうし。
でも溝渕さんの表情を見ると、何だか余裕そうだ。
絶対当たらないだろうみたいな面持ちをしている。
というと、この案はナシか。
言うてもありがちではあるから、男女の関係として褒めるというのは。
そもそも溝渕さんがそんな自慢のようなことを言うとは思えないところもあって。
きっと酷いことを言われたんだろう、でも酷いことを言われた上で関係を継続するってどういうこと?
そうか、分かった。酷いことを言われたけども、それとは別に関係を続けたということだ。
後はどんな酷いことを言われたのか……って、それを思いついたとして口にすることは何か失礼だな、というわけで、
「分かりました。溝渕さん。酷いことを言われたけども、カヲルさんとの関係を継続したということですね」
「じゃあその酷いこととはなんだ?」
「それを言ったら失礼になると思うので、考えてませんでした」
「田中くんは優しい人間だな。そんなに優しいと苦労するぞ」
「まあもうしていますけどね、この自殺室で生きてしまうという苦労を」
「時にはバサッと切り捨てることも大切だけどな、って、先生みたいなことを言ってしまってウザかったな。申し訳ない」
そう言って頭を下げた溝渕さん。
いやいや、
「全然大丈夫ですよ。僕からしたら、いくら立場が同じでも先輩は先輩なので、いろいろ言って頂けるほうが有難いくらいです」
「先輩といっても留年している先輩みたいなもんだけどな」
と言って優しく笑った溝渕さん。
溝渕さんにはずっと温かみがある。
こんな人と、もっと早く、できればこんなところじゃない場所で出会いたかった。
もし生まれ変われるなら僕はこんな先輩と一緒に人生を謳歌したいと思った。
溝渕さんはアゴのあたりを触ってから、
「じゃあ答えを言うかな。あんまりもったいぶっているとハードルが上がってしまうからな」
僕は一丁前にドキドキしてきた。
どんな答えなのか、結構楽しみになってきていたからだ。
溝渕さんは一瞬首をコクンと縦に動かしてから喋り始めた。
「正解は、カヲルの両親から『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』と言われたでしたー」
明るく言い放った溝渕さんとは対照的に僕は背筋が凍った。
『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』なんて、まともな人間の言う台詞ではない。倫理観が完全に崩壊している。
そうか、飼うことはいいことだからそのまま関係を継続するわけか。なんて異常性だ。
僕はきっと張り詰めたような表情をしていたのだろう、溝渕さんは優しく首を横に振ってからこう言った。
「笑ってくれよ、だって異常だっただろ?」
「……笑えませんよ、異常過ぎて」
「笑いって裏切りだろ? 結構な裏切りだっただろう」
「そうですね、ありえないと思いました」
「でもそれが転機になって俺とカヲルは公然の関係になって、勉強も捗ったし、美味しい食事をカヲルの家族に交じって食べることもできるようになった。さらにカヲルの屋敷の使用人にもなれて、生活が安定したんだ」
『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』って言葉、子供のうちからという部分から察するにカヲルさんの両親は人と関わることを”人間を飼う”と考えているんだろう。
全て使用する立場ということ。正直僕とは全然立場が違うと思ったし、もしこの自殺室が見世物小屋ならそういう階級の人間が見ているだろうなと思った。
溝渕さんは一回手を優しく合わせ、改めてといった感じに喋り始めた。
「じゃあ話を続けるか。そして俺とカヲルはこの高校へ一緒に入学することになったんだ。カヲルの家は高校生の年齢になったら必ずこの高校へ入学する習わしだったらしい」
そのことについては何だかもうそうだろうなと思った。
そんな両親なら当然のように卒業生だろうなと思ってしまった。
「最初は俺もカヲルも成績が良かったが、カヲルがあまりにも厳しい環境に体調を崩し、その結果成績も下がっていったんだ。劣悪慣れしていなかったということだな」
そんなものには慣れたくないけども、確かに慣れている慣れていないは大きなターニングポイントではあると思う。
「で、ずっと付きっ切りでカヲルの傍にいたら、カヲルから『まるで私が飼われてるみたいじゃない!』と言われたんだよ。さすがにこれには俺も傷ついてさ」
そう昔を懐かしむように天井のほうを見ながら言った溝渕さん。遠い目をしている。
でも確かにそうだと思う。カヲルさんからも『飼われている』という言葉が出たら、じゃあずっとそうだったのかと思ってしまうから。傷つくということはカヲルさんからは言われたことなかったんだろう。
「俺はさ、やっぱりそういう関係じゃなくて友達だと思っていたから。カヲルから心の奥でそう思われていたことが悔しかったんだよ」
僕が思った通りのことをすぐに言った溝渕さん。
もし僕も光莉から『私が飼ってたから構ってただけ』とか言われたら、心臓が重くなるくらい苦しいだろうな。
「そこから仲違いして俺は成績優秀を一人で維持し。でも気付いた時にはカヲルは自殺室で死んでいたんだ。その時に思ったよ、失敗したって」
全て語り終えたといった感じに、小さく一礼をした溝渕さん。
でもすぐに溝渕さんは口を開き、
「きっと突発的に、思ってもない言葉が出てしまっただけなのかもしれないな、って今は思うよ。思おうとしているだけかもしれないけども」
「いや、実際に思ってもない言葉を言ってしまっただけだと思いますよ。カヲルさんは」
「そう言ってくれて有難う」
溝渕さんは優しく微笑んだ。
あまりにも綺麗な瞳だったので、つい視線を外してしまった。
・【08 想う呟き】
・
僕はふと、
「光莉……」
と声が漏れ出るように呟いてしまった。
自分で言っててキモイと思ってしまったんだけども、溝渕さんは僕の言葉に反応して喋り始めた。
「相当後悔しているんだな」
「していますよ、溝渕さんもそうですよね」
そう自分のキモさをかき消すため、あえて切り返すと、溝渕さんはアゴを触りながら、
「当然だろ。俺も後悔しているよ。どうする? この流れ。田中くんが喋るか、俺が喋るか」
僕はもしかしたら前にいた女子生徒というヤツは、溝渕さんの話を聞いてから死んでいったのかもしれないと思ったので、
「溝渕さんが過去を喋っていいと思うなら、喋ってくれると有難いです」
と答えると、溝渕さんに座ることを促されたので、座り、溝渕さんも近くに座ってから口を改めて開いた。
「元々俺は極貧街の出身で、食べることは勿論、寝ることもままならなかった。ずっと厳しい労働を子供の頃から強いられてな。その時に出会った上流階級の娘、それが俺と一緒にこの高校へ入ることになったカヲルという女子だ」
当たり前だけども、僕とはちょっと違う境遇だ。まあ全部合っているほうがおかしいけども。
溝渕さんは続ける。
「俺は毎日、カヲルからパンをもらっていた。また時間がある時は勉強を教えてもらってな。そこで計算ができるようになって、肉体労働から頭脳労働へ徐々にシフトチェンジできるようになっていったんだ。勿論、どっちにしろ子供が働くのは法律違反だが、そういうことを言ってられる世界観じゃなかったからな」
僕は静かに頷く。
溝渕さんもそれ以上は求めないで、語り続ける。
「そんなある日、カヲルは俺にパンを与え、勉強を教えていることをカヲルの両親に知られたんだ。俺はどうなったと思う?」
急な質問文に少々驚いてしまって、その場に固まってしまうと、
「何、ちょっとクイズ形式であったほうが会話も捗るだろと思っただけだ。でもどうせ暇だろ? ここは俺にとって転機になったところだから、考えてみてくれよ」
そう言って笑った溝渕さん。
なりに、という言葉は上から目線みたいで好きじゃないんだけども、溝渕さんなりに僕へ歩み寄ってきてくれているのかなと思って、僕は、
「分かりました。ちょっと考えてみますね」
と言ってから、無意識に腕を組んでしまい、すぐさま腕を解いてぶらんぶらんとさせた。
それに対して溝渕さんは、
「別に腕くらい組んでいいよ、それ見て偉そうだなとか思わないし。俺が年上かどうかなんて気にしなくていいからな。年齢なんてこの場に相応しくない。あるのは同じ立場だということだけだ」
「同じ立場ですか」
「そうだ、田中くんはスポーツとか観戦するかい?」
「あんまり興味はありませんでしたね」
「でも相手のことを敵とか、敵地と言ったり、アウェイと言ったりすることは知っているだろう」
僕はうんうんと相槌を打ちながら、
「それは知識として知っています」
「でも実際は敵ではないんだよ、同じ立場なだけ。同じ立場だからいがみ合っているようになっているが、本当は全員が全員、共通の話題がある仲間なんだよ」
「何だか平和な考え方ですね、この学校には合わないと思います」
「その通り。なんせ俺もこの考えになったのはこの自殺室に来てからだからな。だから俺は自殺室に来てしまった生徒にはできるだけ安らかに死んでほしいんだ。まあ実際は俺や田中くんとは立場は違うんだが、でもまあ同じと言えば同じだ。同じ仲間として、嘘をついても優しくありたいのさ」
正直こういうところだと思った。
溝渕さんが自殺室で死ねない理由って。
そしてその素養がきっと僕にもあって。
優し過ぎて、自分を殺したくなるから死ねないんだ。
そんなことを考えていると、溝渕さんはふとこう言った。
「でも勝ち負けというものはある。その場合、自殺した生徒が勝ちで俺や田中くんが負けなのか。それとも生きたいのに死んだ生徒が負けで、さらに死にたいのに生きている俺と田中くんも負けなのか。まあ自殺室に来る時点で負けなんだろうな」
「そうですね」
曖昧に頷きが、ここはあえて口に出して返事をした、と、たっぷり意識をしたわけじゃないんだけども、この言葉はさらりと口から流れ出た。
僕の相槌に溝渕さんはフッと笑ってから、
「そういうことだよな」
と一瞬伏し目になってから、
「そうだ、そうだ、田中くん。話は俺のクイズからだったな、シンキングタイムも終了だ。答えは出たかな」
「いやシンキングタイムの話が考えさせられる話でクイズどころじゃなかったですよ」
「そうか、確かにノイズにはなっていたかもな。じゃあ改めて考えてほしい」
さて、じゃあちゃんと思考してみよう。
溝渕さんは結果的にカヲルさんと一緒にこの学校に入っているわけだから、仲違いしたわけではないだろう。
ということは関係は継続していると考えることが自然だろう。
でもここをクイズに出したということは、何か特殊なことが起きた可能性もある。
それか言葉か、関係は継続したけども変わった言葉を言われたというパターンもあるだろう、と思ったところで溝渕さんが、
「今考えている思考を教えてくれないか、競技クイズやクイズ番組でも、答えたあとの感想戦があるけども、今は二人きりだ。思考途中の式を教えてくれないかな?」
僕は今考えていたことをそのまま言葉にすると、溝渕さんはニヤッと笑ってから、
「やっぱり田中くんは賢いな、その方向性で当たりだ。もしかしたら正解しちゃうかもしれないな」
まず合っていたということが嬉しかったし、何だか少し楽しくなった。
だからって生きたくなるほどではないが、正直今はこの答えを聞かずには死にたくない。
やっぱり人と関わるってことは良いことなのかもしれない、そんなことを考えてから僕はもっと深く思考することにした。
言葉、何を言われたか、もしかすると”男女としてお似合い”みたいなことかもしれない。
これは結構意外だと思う。両親から急にこんなこと言われたらビックリするだろうし。
でも溝渕さんの表情を見ると、何だか余裕そうだ。
絶対当たらないだろうみたいな面持ちをしている。
というと、この案はナシか。
言うてもありがちではあるから、男女の関係として褒めるというのは。
そもそも溝渕さんがそんな自慢のようなことを言うとは思えないところもあって。
きっと酷いことを言われたんだろう、でも酷いことを言われた上で関係を継続するってどういうこと?
そうか、分かった。酷いことを言われたけども、それとは別に関係を続けたということだ。
後はどんな酷いことを言われたのか……って、それを思いついたとして口にすることは何か失礼だな、というわけで、
「分かりました。溝渕さん。酷いことを言われたけども、カヲルさんとの関係を継続したということですね」
「じゃあその酷いこととはなんだ?」
「それを言ったら失礼になると思うので、考えてませんでした」
「田中くんは優しい人間だな。そんなに優しいと苦労するぞ」
「まあもうしていますけどね、この自殺室で生きてしまうという苦労を」
「時にはバサッと切り捨てることも大切だけどな、って、先生みたいなことを言ってしまってウザかったな。申し訳ない」
そう言って頭を下げた溝渕さん。
いやいや、
「全然大丈夫ですよ。僕からしたら、いくら立場が同じでも先輩は先輩なので、いろいろ言って頂けるほうが有難いくらいです」
「先輩といっても留年している先輩みたいなもんだけどな」
と言って優しく笑った溝渕さん。
溝渕さんにはずっと温かみがある。
こんな人と、もっと早く、できればこんなところじゃない場所で出会いたかった。
もし生まれ変われるなら僕はこんな先輩と一緒に人生を謳歌したいと思った。
溝渕さんはアゴのあたりを触ってから、
「じゃあ答えを言うかな。あんまりもったいぶっているとハードルが上がってしまうからな」
僕は一丁前にドキドキしてきた。
どんな答えなのか、結構楽しみになってきていたからだ。
溝渕さんは一瞬首をコクンと縦に動かしてから喋り始めた。
「正解は、カヲルの両親から『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』と言われたでしたー」
明るく言い放った溝渕さんとは対照的に僕は背筋が凍った。
『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』なんて、まともな人間の言う台詞ではない。倫理観が完全に崩壊している。
そうか、飼うことはいいことだからそのまま関係を継続するわけか。なんて異常性だ。
僕はきっと張り詰めたような表情をしていたのだろう、溝渕さんは優しく首を横に振ってからこう言った。
「笑ってくれよ、だって異常だっただろ?」
「……笑えませんよ、異常過ぎて」
「笑いって裏切りだろ? 結構な裏切りだっただろう」
「そうですね、ありえないと思いました」
「でもそれが転機になって俺とカヲルは公然の関係になって、勉強も捗ったし、美味しい食事をカヲルの家族に交じって食べることもできるようになった。さらにカヲルの屋敷の使用人にもなれて、生活が安定したんだ」
『子供のうちから人間を飼うことはいいことだ』って言葉、子供のうちからという部分から察するにカヲルさんの両親は人と関わることを”人間を飼う”と考えているんだろう。
全て使用する立場ということ。正直僕とは全然立場が違うと思ったし、もしこの自殺室が見世物小屋ならそういう階級の人間が見ているだろうなと思った。
溝渕さんは一回手を優しく合わせ、改めてといった感じに喋り始めた。
「じゃあ話を続けるか。そして俺とカヲルはこの高校へ一緒に入学することになったんだ。カヲルの家は高校生の年齢になったら必ずこの高校へ入学する習わしだったらしい」
そのことについては何だかもうそうだろうなと思った。
そんな両親なら当然のように卒業生だろうなと思ってしまった。
「最初は俺もカヲルも成績が良かったが、カヲルがあまりにも厳しい環境に体調を崩し、その結果成績も下がっていったんだ。劣悪慣れしていなかったということだな」
そんなものには慣れたくないけども、確かに慣れている慣れていないは大きなターニングポイントではあると思う。
「で、ずっと付きっ切りでカヲルの傍にいたら、カヲルから『まるで私が飼われてるみたいじゃない!』と言われたんだよ。さすがにこれには俺も傷ついてさ」
そう昔を懐かしむように天井のほうを見ながら言った溝渕さん。遠い目をしている。
でも確かにそうだと思う。カヲルさんからも『飼われている』という言葉が出たら、じゃあずっとそうだったのかと思ってしまうから。傷つくということはカヲルさんからは言われたことなかったんだろう。
「俺はさ、やっぱりそういう関係じゃなくて友達だと思っていたから。カヲルから心の奥でそう思われていたことが悔しかったんだよ」
僕が思った通りのことをすぐに言った溝渕さん。
もし僕も光莉から『私が飼ってたから構ってただけ』とか言われたら、心臓が重くなるくらい苦しいだろうな。
「そこから仲違いして俺は成績優秀を一人で維持し。でも気付いた時にはカヲルは自殺室で死んでいたんだ。その時に思ったよ、失敗したって」
全て語り終えたといった感じに、小さく一礼をした溝渕さん。
でもすぐに溝渕さんは口を開き、
「きっと突発的に、思ってもない言葉が出てしまっただけなのかもしれないな、って今は思うよ。思おうとしているだけかもしれないけども」
「いや、実際に思ってもない言葉を言ってしまっただけだと思いますよ。カヲルさんは」
「そう言ってくれて有難う」
溝渕さんは優しく微笑んだ。
あまりにも綺麗な瞳だったので、つい視線を外してしまった。