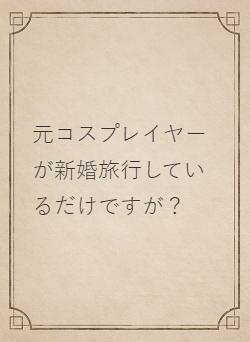・
・【04 最初の生徒】
・
空想の末に眠りかけたその時、突然訪れた。
自殺室のドアが開いた。
男子生徒だ。
彼が入ってきた瞬間、自殺室の光景は一変した。
公衆便所を思わせるような匂い、否、自殺室は公衆便所そのものに変化し、さっきまでの清い色の空間は幻と化した。
あまりの床のタイルの汚さに、僕は勿論、溝渕さんも立ち上がった。
その流れで僕はこの空間を小走りで見渡した。
入ってきた彼よりも、変わった空間のほうがずっと気になったからだ。
公衆便所の内装に、小さな天窓が一つ。
そこからは青空が見えていた。
天窓は高すぎて、人間が手動で開け閉めはできない感じ。
じゃあ公衆便所の”外”にはどこまでいけるのかと思っていたが、外へ通じると思われる場所は扉となって、それ以上は行けなくなっていた。
つまりここは公衆便所の密室といったところだ。
あと気になる箇所と言えば、手洗いをする蛇口のところに薬箱が出現している。
でも公衆便所に変わるということは一体何なんだろうか、何か意味があるのだろうか。
僕は何か知っているかもしれないと思って、溝渕さんの近くに寄って、話し掛けることにした。
正直、聞きたいことは山ほどある。
こういう状況になって、やっと聞きたい事柄が分かった。
今までは聞きたい事柄さえも浮かばなかったけども、こう何かが起こって初めて分かったんだ。
まず入ってきた彼に僕たちの姿が見えているかどうか、空間がこう変わったことに意味があるのか。
まあ焦っても仕方ない。
一つずつ聞いていこう。
《溝渕さん、僕たちの姿は彼に見えているのですか?》
僕は少々興奮を抑えられないような感じでそう言ったけども、溝渕さんは慣れているだけあって、淡々と、
《いや、俺たちが念じない限り、俺たちの姿が彼に見えることは無いよ》
《じゃあ声も聞こえないということですね》
《その通りだ》
自分が喋った時も思ったけども、何だかいつもと比べて溝渕さんも僕も声がおかしい。
まるで言葉にぬめり気が覆っているような。
ちょっとこもっているような不思議な声になっている、とか考えていると、溝渕さんが見透かしているようにこう言った。
《声がおかしかったり、動いている時に妙な動きづらさを感じるだろう、田中くん》
僕はハッとした。
そう言えば、動いている時も何か少し変だった。
あんまり動いていなかったせいで体が鈍っているのかなとすぐに考えて、それ以上の思考は停止していた。
じゃあ
《何か理由があるんですか?》
《誰かが来た時、俺たちには膜が張るんだ。いやまあ俺が勝手に”膜”と呼んでいるだけだがな》
膜。
確かに膜だ。
この感覚は膜でしかない。
溝渕さんは正確に言葉を扱うなぁ、と感心した。
溝渕さんは続ける。
《この膜を破ることによって、この入ってきた彼と会話をしたり、俺たちの姿を見せることができる。やり方は簡単だ。強く念じるだけでいい》
《じゃあ出て行ったほうがいいんですかね》
《いや最初は傍観したほうがいい。それはあくまで俺のやり方だがな。まあすぐに俺たちが出てきたら情報過多でパニックになってしまう。向こうも様子見しているし、こっちも様子見するべきだ》
なるほど、多分経験上仰っているんだなと思った。
でもあれだ。
人が自殺する瞬間を見届けるって苦痛だなと単純に今、そう思った。
さらには死ななかった場合、自殺の手伝いをするとか、そんなことできるのか、と不安になってきた。
いやその前に、まだ聞きたいことがあった。
《何で空間が公衆便所になったんですか?》
少し悩んでいるように、腕を組んだ溝渕さん。
理由が分からないのなら分からないと言ってほしいのにな、と、少しソワソワしながら待っていると、
《まあこの辺はこっちの勝手な予想みたいなところにもなってくるし、ここは言わないことにしておこう》
《何ですか、もったいぶっているんですか?》
《いやそういうことじゃないんだ。でも一つ言えることがあるとしたら、情報過多でパニックになるのは入ってきた彼だけじゃないってことだ》
これは明らかに僕のことを指している言葉だ。
僕が情報過多でパニックになる心配をしているのだ。
でもそれはバカにしているような言いっぷりではなくて、本当に親身になって、言っている感じだと分かった。
そうか、そりゃそうだ、情報過多でパニックになって彼が死ぬことを邪魔してしまったら、どうしようもないもんな。
変に長引いたら、溝渕さんからしたら面倒そのものだろう。
僕は溝渕さんの言葉を受け入れ、静かに見ていることにした。
最初、呆然としていた入ってきた彼は、徐々に何かを口にし始めた。
「おい、何だよ、この部屋、まるで地元の公衆便所みてぇじゃん、何なんだよこれぇ……」
地元の公衆便所。
ということは彼の思い出が出現しているということか?
でもこの公衆便所の汚さから察するに、あんまり良い思い出といった感じでは無さそうだ。
いやそれとも彼はヤンキーみたいなもんで、こういう公衆便所でたむろしていたのかな。
だとしたら友達との記憶といった感じで、良い思い出なのかもしれない。
最後は良い思い出の中で死なせてあげるみたいな話なのかもしれない。
そんなことを考えていると、入ってきた彼は、手洗いする蛇口のところで薬箱に目をやった。
その薬箱は箱が既にパカッと開いていて、中に錠剤の薬が入った瓶がある。
その瓶も、もう口が開いて、蓋の類は薬箱の中に入っている。
錠剤は結構たくさん入っている感じだ。
瓶にラベルは無いが、多分これが毒薬だと思われる。
入ってきた彼はその錠剤に手を掛けた。
《あっ、溝渕さん。彼、錠剤の瓶に手を出しましたね》
と言いながら僕は溝渕さんのほうを見ると、溝渕さんは少し訝し気に、
《……これがそのまま死ねる毒薬ならいいんだけどね……》
とポツリと呟いた。
その憂鬱そうな声に、僕は少し不安になりながら、
《どういうことですか?》
《この空間は、絶対に死にたくない方法で死なないといけない空間なんだ。勿論、本人がそう思っている死にたくない方法で、ね》
一個、情報が出てきた。
溝渕さんは本当にちょっとずつ情報を出してくる。
それが正直煩わしい部分もあるんだけども、その分、一個一個考えることができる。
いや考える必要なんてないのかもしれないけども、やっぱり分析のようなことはしてしまうもので。
本人が死にたくない方法で死なないといけない。
その縛りにどんな意味があるのか。
いや意味は分からないけども、僕が死ねない理由はなんとなく分かった。
死にたくない方法が無いから死ねないんだ。
死にたさ過ぎて、死ねるならなんでもいいと思ってしまったから死ねないんだ。
なんて天邪鬼な空間なんだろうか。
どうせ平等な死が待っているのなら、そんなプライドを折るような死はいらないような気がするんだけども。
それとも何か深い意味があるのだろうか、と思った時、一つ、答えが浮かび上がってきた。
これは誰かが監視しているんだ、と。
監視なら、まだ幸せだが、まさかこの空間を娯楽として喜んでいる富裕層の人間みたいなもんがいるのでは、と。
奴隷を闘わせるコロッセオのように、これで楽しんでいる連中がいるのでは、と考えた時、背筋がゾッとした。
でも考えられる。
この考えられない技術で作られた空間に意味があるのならば。
僕はどうしても気になって、溝渕さんに問いかけた。
《この空間は、もしかすると、大金持ちの娯楽として配信されているんですか?》
僕がそう言うと「おっ」と少し驚いた表情をしてから、こう言った。
《まあそう考えることが妥当だよね。俺も正直そう思っている、が、昔俺と一緒に自殺室に長く居た子は何かに気付いたような顔をして、こっちを見つめてきたのち、何事も無かったように砂になっていき、消えて死んでいったんだ。俺はその時のその子の微笑みが忘れられないんだ。それなりに仲良くしていたことは事実だが、そんな笑うようなことは無くて。もし苦しんで死ぬパフォーマンス劇場なら、その子はあんな顔して死ぬはずがないんだ。いやでも何か特別な例だったのかもしれないけどな》
一応は溝渕さんも僕の意見に賛同してくれたが、特例もあるみたいだ。
まあ長く居た人は特別なことが起こるだけかもしれない。
基本的にはこの方向性で間違っていないんだと思う。
自殺室は見世物小屋。
まさかそんなことが分かってしまうなんて。
月並みだけども、さっきよりも俄然死にたくなってしまった。
・【04 最初の生徒】
・
空想の末に眠りかけたその時、突然訪れた。
自殺室のドアが開いた。
男子生徒だ。
彼が入ってきた瞬間、自殺室の光景は一変した。
公衆便所を思わせるような匂い、否、自殺室は公衆便所そのものに変化し、さっきまでの清い色の空間は幻と化した。
あまりの床のタイルの汚さに、僕は勿論、溝渕さんも立ち上がった。
その流れで僕はこの空間を小走りで見渡した。
入ってきた彼よりも、変わった空間のほうがずっと気になったからだ。
公衆便所の内装に、小さな天窓が一つ。
そこからは青空が見えていた。
天窓は高すぎて、人間が手動で開け閉めはできない感じ。
じゃあ公衆便所の”外”にはどこまでいけるのかと思っていたが、外へ通じると思われる場所は扉となって、それ以上は行けなくなっていた。
つまりここは公衆便所の密室といったところだ。
あと気になる箇所と言えば、手洗いをする蛇口のところに薬箱が出現している。
でも公衆便所に変わるということは一体何なんだろうか、何か意味があるのだろうか。
僕は何か知っているかもしれないと思って、溝渕さんの近くに寄って、話し掛けることにした。
正直、聞きたいことは山ほどある。
こういう状況になって、やっと聞きたい事柄が分かった。
今までは聞きたい事柄さえも浮かばなかったけども、こう何かが起こって初めて分かったんだ。
まず入ってきた彼に僕たちの姿が見えているかどうか、空間がこう変わったことに意味があるのか。
まあ焦っても仕方ない。
一つずつ聞いていこう。
《溝渕さん、僕たちの姿は彼に見えているのですか?》
僕は少々興奮を抑えられないような感じでそう言ったけども、溝渕さんは慣れているだけあって、淡々と、
《いや、俺たちが念じない限り、俺たちの姿が彼に見えることは無いよ》
《じゃあ声も聞こえないということですね》
《その通りだ》
自分が喋った時も思ったけども、何だかいつもと比べて溝渕さんも僕も声がおかしい。
まるで言葉にぬめり気が覆っているような。
ちょっとこもっているような不思議な声になっている、とか考えていると、溝渕さんが見透かしているようにこう言った。
《声がおかしかったり、動いている時に妙な動きづらさを感じるだろう、田中くん》
僕はハッとした。
そう言えば、動いている時も何か少し変だった。
あんまり動いていなかったせいで体が鈍っているのかなとすぐに考えて、それ以上の思考は停止していた。
じゃあ
《何か理由があるんですか?》
《誰かが来た時、俺たちには膜が張るんだ。いやまあ俺が勝手に”膜”と呼んでいるだけだがな》
膜。
確かに膜だ。
この感覚は膜でしかない。
溝渕さんは正確に言葉を扱うなぁ、と感心した。
溝渕さんは続ける。
《この膜を破ることによって、この入ってきた彼と会話をしたり、俺たちの姿を見せることができる。やり方は簡単だ。強く念じるだけでいい》
《じゃあ出て行ったほうがいいんですかね》
《いや最初は傍観したほうがいい。それはあくまで俺のやり方だがな。まあすぐに俺たちが出てきたら情報過多でパニックになってしまう。向こうも様子見しているし、こっちも様子見するべきだ》
なるほど、多分経験上仰っているんだなと思った。
でもあれだ。
人が自殺する瞬間を見届けるって苦痛だなと単純に今、そう思った。
さらには死ななかった場合、自殺の手伝いをするとか、そんなことできるのか、と不安になってきた。
いやその前に、まだ聞きたいことがあった。
《何で空間が公衆便所になったんですか?》
少し悩んでいるように、腕を組んだ溝渕さん。
理由が分からないのなら分からないと言ってほしいのにな、と、少しソワソワしながら待っていると、
《まあこの辺はこっちの勝手な予想みたいなところにもなってくるし、ここは言わないことにしておこう》
《何ですか、もったいぶっているんですか?》
《いやそういうことじゃないんだ。でも一つ言えることがあるとしたら、情報過多でパニックになるのは入ってきた彼だけじゃないってことだ》
これは明らかに僕のことを指している言葉だ。
僕が情報過多でパニックになる心配をしているのだ。
でもそれはバカにしているような言いっぷりではなくて、本当に親身になって、言っている感じだと分かった。
そうか、そりゃそうだ、情報過多でパニックになって彼が死ぬことを邪魔してしまったら、どうしようもないもんな。
変に長引いたら、溝渕さんからしたら面倒そのものだろう。
僕は溝渕さんの言葉を受け入れ、静かに見ていることにした。
最初、呆然としていた入ってきた彼は、徐々に何かを口にし始めた。
「おい、何だよ、この部屋、まるで地元の公衆便所みてぇじゃん、何なんだよこれぇ……」
地元の公衆便所。
ということは彼の思い出が出現しているということか?
でもこの公衆便所の汚さから察するに、あんまり良い思い出といった感じでは無さそうだ。
いやそれとも彼はヤンキーみたいなもんで、こういう公衆便所でたむろしていたのかな。
だとしたら友達との記憶といった感じで、良い思い出なのかもしれない。
最後は良い思い出の中で死なせてあげるみたいな話なのかもしれない。
そんなことを考えていると、入ってきた彼は、手洗いする蛇口のところで薬箱に目をやった。
その薬箱は箱が既にパカッと開いていて、中に錠剤の薬が入った瓶がある。
その瓶も、もう口が開いて、蓋の類は薬箱の中に入っている。
錠剤は結構たくさん入っている感じだ。
瓶にラベルは無いが、多分これが毒薬だと思われる。
入ってきた彼はその錠剤に手を掛けた。
《あっ、溝渕さん。彼、錠剤の瓶に手を出しましたね》
と言いながら僕は溝渕さんのほうを見ると、溝渕さんは少し訝し気に、
《……これがそのまま死ねる毒薬ならいいんだけどね……》
とポツリと呟いた。
その憂鬱そうな声に、僕は少し不安になりながら、
《どういうことですか?》
《この空間は、絶対に死にたくない方法で死なないといけない空間なんだ。勿論、本人がそう思っている死にたくない方法で、ね》
一個、情報が出てきた。
溝渕さんは本当にちょっとずつ情報を出してくる。
それが正直煩わしい部分もあるんだけども、その分、一個一個考えることができる。
いや考える必要なんてないのかもしれないけども、やっぱり分析のようなことはしてしまうもので。
本人が死にたくない方法で死なないといけない。
その縛りにどんな意味があるのか。
いや意味は分からないけども、僕が死ねない理由はなんとなく分かった。
死にたくない方法が無いから死ねないんだ。
死にたさ過ぎて、死ねるならなんでもいいと思ってしまったから死ねないんだ。
なんて天邪鬼な空間なんだろうか。
どうせ平等な死が待っているのなら、そんなプライドを折るような死はいらないような気がするんだけども。
それとも何か深い意味があるのだろうか、と思った時、一つ、答えが浮かび上がってきた。
これは誰かが監視しているんだ、と。
監視なら、まだ幸せだが、まさかこの空間を娯楽として喜んでいる富裕層の人間みたいなもんがいるのでは、と。
奴隷を闘わせるコロッセオのように、これで楽しんでいる連中がいるのでは、と考えた時、背筋がゾッとした。
でも考えられる。
この考えられない技術で作られた空間に意味があるのならば。
僕はどうしても気になって、溝渕さんに問いかけた。
《この空間は、もしかすると、大金持ちの娯楽として配信されているんですか?》
僕がそう言うと「おっ」と少し驚いた表情をしてから、こう言った。
《まあそう考えることが妥当だよね。俺も正直そう思っている、が、昔俺と一緒に自殺室に長く居た子は何かに気付いたような顔をして、こっちを見つめてきたのち、何事も無かったように砂になっていき、消えて死んでいったんだ。俺はその時のその子の微笑みが忘れられないんだ。それなりに仲良くしていたことは事実だが、そんな笑うようなことは無くて。もし苦しんで死ぬパフォーマンス劇場なら、その子はあんな顔して死ぬはずがないんだ。いやでも何か特別な例だったのかもしれないけどな》
一応は溝渕さんも僕の意見に賛同してくれたが、特例もあるみたいだ。
まあ長く居た人は特別なことが起こるだけかもしれない。
基本的にはこの方向性で間違っていないんだと思う。
自殺室は見世物小屋。
まさかそんなことが分かってしまうなんて。
月並みだけども、さっきよりも俄然死にたくなってしまった。