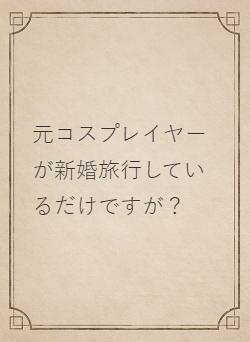・
・【02 はじまりのおわり】
・
僕は目を覚ますと、目の前には自分と同じ学生服を着ているが、明らかに見た目が生徒と言える年齢ではない男が僕の顔を覗き込むようにしゃがんでいた。大学生四年生くらいか、もう社会人になりたてくらいだろうか。
というか目を覚ますと、ということは、と僕が喋りだそうと思ったところで、その男が先に口を開いた。
「珍しい生徒がいたもんだ。まあ大体分かっていたがな」
そう言いながらアゴを触る男。
加齢した顔の割にはヒゲが生えていないな、とか、妙に冷静なことを考えている自分に気付き、少し自己嫌悪した。
いやいやそんなことよりも、そう思いながら僕は
「……ここが地獄ですか?」
と聞くと、その男は首を横に振りながら、
「いや、自殺室だよ」
あっけらかんとそう答えた男は、ゆっくりと屈伸するように立ち上がった。
「……死ねなかったのか……」
僕はそうポツリと呟くと、男は何だか少し鼻で笑いながら、見下すように、そして物理的にも見下しながら、こう言った。
「君、自分のこと殴っていたよね、その程度じゃ気絶が関の山だよ」
えっ?
「見ていたんですか?」
「うん、なんせ俺は自殺室の番人だからね」
「番人ということは、貴方を倒さないと死ねないということですか?」
と僕が疑問を投げかけたところで、男はニヤァと笑みを浮かべながら、
「君は珍しいね。その言動間違いない。君は何の疑問も持たず、死のうとしているよね?」
と言ってきたので、僕は聞かれるがままに、
「はい、テストで最下位でしたから」
その返答に対して、男は間髪入れずにこう言った。
「それはわざとだろう?」
僕はドキッとした。
でもここで怯んでは値踏みされると思って、すぐに、
「いや、実力です」
と答えると、その男は「ハッ」と掠れた笑いをしてから、
「まあ最下位をとった理由はなんでもいいんだ、今は」
その後から付けたような”今は”が妙に気になって、
「今は?」
と聞き返すと、男は少々面倒臭そうに、
「しかし君が死にたいという願望を持っていることはダメなんだ」
「いやでも、自殺室行きになったのですから、僕は死にたいんです」
ハッキリそう答えると、男はやれやれといったような感じで、
「違うんだよ。自殺室行きになった人間は生きていたいと思わなければ死ねないんだよ、何故なら罰としての死だからね」
なんとなく理解はできているが、もっと情報がほしいので、
「どういうことですか?」
と掘り進めると、男は淡々と説明し始めた。
「君は心の底から死にたいと思っている。この自殺室は入ってきた生徒の心理状態を表しているんだ」
「死にたいのならば、もっと禍々しい感じになるべきなんじゃないんですか?」
「いや、君の死にたい気持ちは高潔なんだ。だからこんな美しい部屋になっているんだ。本来、この部屋はもっと禍々しく変化するし、死ぬための道具だって出てくる。でも君はダメだ。死ねないね」
死ねない、つまり、
「ということは、元の学校生活に戻るということですか?」
それに対しては、ゆっくり首を横に振って、少し間を持ってから、こう言った。
「いや違う。この自殺室で次にやって来る生徒たちの自殺を手伝う係として、俺と一緒に生きてもらう」
「じゃあその時に出現した死ぬための道具で死ねばいいんですね」
「いや、きっと君は、死ぬための道具に触れた時に、その死ぬための道具は消えてしまうだろうね。状況にもよるが、基本は触れられないと思う」
何から何まで否定するその男に内心イライラしてきた僕は、ちょっと声を荒上げながら、
「でもやってみないと分からないじゃないですか」
と言うと、その男は僕と反比例するかのように、澄んだ瞳になって、
「分かるよ」
「どうしてですか?」
「俺がそうだから」
「……えっ?」
徐々に高鳴っていた心臓が、ここにきてより強くなった。
この展開じゃいけない、と思っても、そうならざる得ない展開が聞こえてきそうで。
男は冷静にこう言った。
「俺は前に……今までやって来た人数から察するに、一年間三十六人×三学年分だから……七年前に自殺室へ入ったこの高校の生徒だ。君がやろうとするようなことは、きっと全てやり尽くした」
状況から見ても、直感的にも、この男が言っていることは真実だということは分かった。
でも、それでも、どこか反抗したくて、僕は、
「どうやって生きているんですか、食べ物とか、どうしているんですか?」
「知らない。ただ生きているんだ。ただし、これだけは変わらずあるモノがある」
僕は生唾を飲みこんだ。
聞いていいものかどうか、一瞬躊躇した。
でも聞かないと進まない。
ここまで聞いてしまったらもう最後まで聞かないといけない。
そういう思いに駆られて、僕は声を出した。
「……なんですか?」
「死にたいという気持ちだ」
全てを理解した。
男の気持ちも手に取るように分かったような気がした。
僕は妙に落ち着いた。
そして男のやり場のない怒りを汲み取るように、僕は喋りだした。
「貴方も僕と同じで、死にたい気持ちを持って自殺室に入ったんですね」
「あぁ、そうだ、ずっと死にたいし、きっと死ねないだろうな。この自殺室での手伝いというモノは、あまりにも死にたすぎる作業だからね。でも」
とってつけたような”でも”に違和感を抱き、僕は素のまま聞き返した。
「でも?」
「君が来る前にいた、一人の女生徒は急に死んだよ。だからまあ人によっては生きたくなるのかなぁ。分かんないけども。なんせ俺はずっと死ねていないからね」
――そして僕の自殺室での生活が始まった。
食べなくても寝なくても生きている謎の空間。
・【02 はじまりのおわり】
・
僕は目を覚ますと、目の前には自分と同じ学生服を着ているが、明らかに見た目が生徒と言える年齢ではない男が僕の顔を覗き込むようにしゃがんでいた。大学生四年生くらいか、もう社会人になりたてくらいだろうか。
というか目を覚ますと、ということは、と僕が喋りだそうと思ったところで、その男が先に口を開いた。
「珍しい生徒がいたもんだ。まあ大体分かっていたがな」
そう言いながらアゴを触る男。
加齢した顔の割にはヒゲが生えていないな、とか、妙に冷静なことを考えている自分に気付き、少し自己嫌悪した。
いやいやそんなことよりも、そう思いながら僕は
「……ここが地獄ですか?」
と聞くと、その男は首を横に振りながら、
「いや、自殺室だよ」
あっけらかんとそう答えた男は、ゆっくりと屈伸するように立ち上がった。
「……死ねなかったのか……」
僕はそうポツリと呟くと、男は何だか少し鼻で笑いながら、見下すように、そして物理的にも見下しながら、こう言った。
「君、自分のこと殴っていたよね、その程度じゃ気絶が関の山だよ」
えっ?
「見ていたんですか?」
「うん、なんせ俺は自殺室の番人だからね」
「番人ということは、貴方を倒さないと死ねないということですか?」
と僕が疑問を投げかけたところで、男はニヤァと笑みを浮かべながら、
「君は珍しいね。その言動間違いない。君は何の疑問も持たず、死のうとしているよね?」
と言ってきたので、僕は聞かれるがままに、
「はい、テストで最下位でしたから」
その返答に対して、男は間髪入れずにこう言った。
「それはわざとだろう?」
僕はドキッとした。
でもここで怯んでは値踏みされると思って、すぐに、
「いや、実力です」
と答えると、その男は「ハッ」と掠れた笑いをしてから、
「まあ最下位をとった理由はなんでもいいんだ、今は」
その後から付けたような”今は”が妙に気になって、
「今は?」
と聞き返すと、男は少々面倒臭そうに、
「しかし君が死にたいという願望を持っていることはダメなんだ」
「いやでも、自殺室行きになったのですから、僕は死にたいんです」
ハッキリそう答えると、男はやれやれといったような感じで、
「違うんだよ。自殺室行きになった人間は生きていたいと思わなければ死ねないんだよ、何故なら罰としての死だからね」
なんとなく理解はできているが、もっと情報がほしいので、
「どういうことですか?」
と掘り進めると、男は淡々と説明し始めた。
「君は心の底から死にたいと思っている。この自殺室は入ってきた生徒の心理状態を表しているんだ」
「死にたいのならば、もっと禍々しい感じになるべきなんじゃないんですか?」
「いや、君の死にたい気持ちは高潔なんだ。だからこんな美しい部屋になっているんだ。本来、この部屋はもっと禍々しく変化するし、死ぬための道具だって出てくる。でも君はダメだ。死ねないね」
死ねない、つまり、
「ということは、元の学校生活に戻るということですか?」
それに対しては、ゆっくり首を横に振って、少し間を持ってから、こう言った。
「いや違う。この自殺室で次にやって来る生徒たちの自殺を手伝う係として、俺と一緒に生きてもらう」
「じゃあその時に出現した死ぬための道具で死ねばいいんですね」
「いや、きっと君は、死ぬための道具に触れた時に、その死ぬための道具は消えてしまうだろうね。状況にもよるが、基本は触れられないと思う」
何から何まで否定するその男に内心イライラしてきた僕は、ちょっと声を荒上げながら、
「でもやってみないと分からないじゃないですか」
と言うと、その男は僕と反比例するかのように、澄んだ瞳になって、
「分かるよ」
「どうしてですか?」
「俺がそうだから」
「……えっ?」
徐々に高鳴っていた心臓が、ここにきてより強くなった。
この展開じゃいけない、と思っても、そうならざる得ない展開が聞こえてきそうで。
男は冷静にこう言った。
「俺は前に……今までやって来た人数から察するに、一年間三十六人×三学年分だから……七年前に自殺室へ入ったこの高校の生徒だ。君がやろうとするようなことは、きっと全てやり尽くした」
状況から見ても、直感的にも、この男が言っていることは真実だということは分かった。
でも、それでも、どこか反抗したくて、僕は、
「どうやって生きているんですか、食べ物とか、どうしているんですか?」
「知らない。ただ生きているんだ。ただし、これだけは変わらずあるモノがある」
僕は生唾を飲みこんだ。
聞いていいものかどうか、一瞬躊躇した。
でも聞かないと進まない。
ここまで聞いてしまったらもう最後まで聞かないといけない。
そういう思いに駆られて、僕は声を出した。
「……なんですか?」
「死にたいという気持ちだ」
全てを理解した。
男の気持ちも手に取るように分かったような気がした。
僕は妙に落ち着いた。
そして男のやり場のない怒りを汲み取るように、僕は喋りだした。
「貴方も僕と同じで、死にたい気持ちを持って自殺室に入ったんですね」
「あぁ、そうだ、ずっと死にたいし、きっと死ねないだろうな。この自殺室での手伝いというモノは、あまりにも死にたすぎる作業だからね。でも」
とってつけたような”でも”に違和感を抱き、僕は素のまま聞き返した。
「でも?」
「君が来る前にいた、一人の女生徒は急に死んだよ。だからまあ人によっては生きたくなるのかなぁ。分かんないけども。なんせ俺はずっと死ねていないからね」
――そして僕の自殺室での生活が始まった。
食べなくても寝なくても生きている謎の空間。