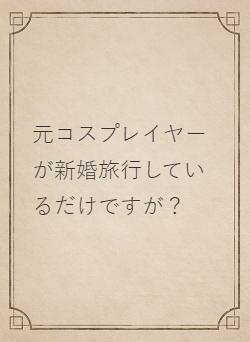・
・【19 樹海】
・
溝渕さんがいなくなってから、もう十人以上の生徒が入ってきた。
もう溝渕さんのいない日々のほうが日常だ。
溝渕さんがいなくなっても、僕と陽菜の関係が変わることは無く……いやでもより距離が近くなったような気がする。
それは心も物理的にも。
陽菜はやけにベタベタ僕にくっつくようになってきた。
まるで本当に光莉みたいに。
それに対して、僕も正直全然嫌じゃない。
そういう距離で会話することは光莉で慣れていたし、特にそれで何か考えるようなことも無かった。
いや、でも、どこか、何かが引っかかる思いは感じている。
それは棘とかじゃなくて、何だか不思議と温かいモノだった。
そんなことを時折考えながら、この自殺室で暮らしていったある時、また男子生徒が入ってきた。
また空間は一変し、樹海のように木々が生い茂る空間になった。
そしてこれ見よがしに空間の中央には首吊り用の縄に、台が置かれた。
今回は導くにしても簡単だし、そんなに苦しんでいるところを見なくてもいいかもしれない。
男子生徒の彼は呟く。
「何なんだ、ここは……こんな虫がいそうなところ……汚らしい……」
それに対して陽菜が言う。
《虫が苦手なんだな、コイツは》
《まあ基本みんな好きじゃないけどね》
《アタシは結構好きだけどな、カッコイイし》
そう言いながら腕を組んで頷いた陽菜。
まあ確かに
《カブトムシとかクワガタはカッコイイかもしれないけども》
僕がそう相槌を打つと、陽菜は首を横に振って、
《いや蚊》
と言い切ったので、僕は驚いてしまい、生返事のオウム返しをし、
《蚊ぁっ?》
と語尾も何だか妙に上げてしまった。
ちょっと恥ずかしい声になっちゃったな、と思っていたけども、陽菜はそんなこと気にせず、喋る。
《血を吸うとか、かなりイカしてるじゃん。しかもバレずに吸っておいて、最後は痒みで吸ったことバラすって。仕事は冷静、でも最後の勝負は正々堂々と情熱みたいな》
《いや痒みは別に正々堂々勝負したいからじゃないよ、痒みのある液を体内に流し込むことによって血液の凝固を防いでいるだけで》
《だからって痒みのある液にする必要無いじゃん、やっぱりあえて痒みのある成分を入れて流し込んでいるとしか思えないね、カッコイイよ、蚊は》
《そうかなぁ》
独特な感性だなと思いつつも、それがまあ陽菜かと思って納得した。
男子生徒の彼は周りの様子を見て叫び声を上げる。
「どうせならもっと都会で死にてぇよ! こんな虫、虫! 虫ぃっ!」
僕は分析をする。
《この彼の死にたくない状況って、虫が多い状況ということなのかもしれないね》
それに対して陽菜は小首を傾げながら、
《虫なんて天国の一種じゃん》
《天国の一種ではないと思うけども》
そんなどうでもいいやり取りをしたところで、陽菜は首を回しながら、こう言った。
《というわけで、そろそろ姿を現すかなぁ。あんまり発展しそうにないもんなぁ》
《陽菜って入ってきた生徒を助けようとするよね、最近特にまた》
《それは信太だって一緒だろ? アタシは悪いヤツ以外は全員助けたいんだよ! というか変えたいんだよ、きっとアタシたちはこの人たちの運命を変えるためにいるんだよ》
《そう言って助けられた試しはまだ一度も無いけどね》
そう一度も。
あれから幾度となく自殺室に生徒が入ってきたが、ことごとく生徒を助けられたことはない。
《でも今度こそやってやるんだからな! まあいいヤツならだけどな!》
そう言って、陽菜は姿を現した。
僕も頃合いを見て、出ることにしよう。
姿を現した陽菜を見て、彼は戦々恐々しながらこう言った。
「……オマエ、深山陽菜か……何故こんなところに……」
「アンタがいいヤツなら助けてやるぜ!」
陽菜は今日、一段と気合いが入っているような気がした。
いや、陽菜は日に日に意気込みが増していっている。
普通こんな空間にいたら、どんどん気持ちが落ち込んでいきそうだけども、陽菜はどんどん上昇していく。
特に、あの川の一件から陽菜は変わった。
より明るくなったと思う。
陽菜が言うところの独善的な明るさから、本当に全てを助けたい、喜ばせたいといったような明るさ。
どんどん周りを、というか特に僕を鼓舞していくようになった。
とはいえ、やって来た生徒を助けられた例なんて一個も無いし、極悪と言ってもいい所業をやらかしていた生徒には陽菜の気持ちが反転して、そういう生徒と喧嘩になったこともあるんだけども。
この気合いの入りすぎが、悪いほうにいかなきゃいいんだけど。
要は入ってきた生徒と喧嘩しないでほしい。
そうなると無駄に長引いてしまうから。
入ってきた彼は手を合わせて喜びながら、
「マジかっ! ありがとう!」
と言った。
いやいや、と思いながら、
「陽菜、あんまり期待するようなことを言っちゃダメだから。今まで助けられた生徒なんていないんだからさ……」
そう言いながら僕も姿を現すと、この彼は陽菜の時と違い、体を硬直させた。
いやでも僕にはこの彼には見覚えが無い。
しかしこの彼は明らかに、僕に怯えている。
どういうことだ?
そしてその彼はポツリと呟いた。
「木島光莉の……」
それこそ僕が硬直した。
木島光莉。
それは、僕の幼馴染の光莉のフルネームだ。
まさか。
コイツが。
光莉を……!
「死ねぇぇぇええええええ!」
我を失うってこういうことだと、この彼を殴った時に気付いた。
いやこの彼に触れることはできなかったから、殴れなかったんだけども。
そんな僕に陽菜は慌てながら、
「ちょっ! 信太! 急にどうしたんだよぉっ!」
僕は呼吸を整えた。
否、整わない。
どんどん息が荒くなる。
許せない。
許せない。
光莉は、光莉は、こんなヤツに……、
「オマエか……オマエがっ! 光莉のことをイジメていたのはっ!」
僕がそう叫ぶと、彼はぶるぶると震えながら、
「……いや……オレは……最初は、止めようとして……」
「最初は? じゃあイジメに加担していたということだなぁっ!」
「いや……まあ……なんというか……えっ、それが原因? オマエが自殺室に行ったのっ?」
それ?
光莉のイジメが、それ?
何だその言い方。
馬鹿にしてんのか。
光莉のことを馬鹿にしてんのか! クソっ!
「あぁぁぁぁぁああああああああああああああああああああああああああああ!」
と僕が叫んだところで、僕の目の前で猫だましをした陽菜。
僕はつい目を閉じた瞬間、ハッとなんとか気を取り戻した。
でもまたすぐこうなるだろう。
だって光莉を、光莉をあんな目に遭わせた張本人が……と思ったところで、陽菜が僕の肩を掴んで、
「らしくなぁっい! らしくないぞ! 信太! 叫ぶのはアタシの役目だろうがぁっ!」
僕よりもデカい声を上げた陽菜は続ける。
「信太! 何があったか簡潔に話してほしい! それで決めるから!」
別に陽菜に何がどうか決めてほしいわけではないけども、話さずにはいられなかった。
「木島光莉は僕の幼馴染で、僕が好きだった女性だ……一緒に入学した光莉は、元々は上位だったんだけども、このシステムにどんどん憂鬱になり、徐々に成績を落としていった……そして中位になると、精神的なダメージを与えてもっと順位を下げようとしてくれる連中からイジメられるようになり……成績的にはまだ大丈夫だったんだけど、自殺室のドアの前で自殺した……という話……」
「……という話?」
「そう……僕は全てそれらの話をあとから聞いたんだ……光莉が死んだあとに、ね……光莉がそんな状況になっていることに気付いていなくて、僕は自分のことでずっと必死で」
陽菜は真剣な瞳で小さく頷く。
僕は続ける。
「光莉ともっと密にコミュニケーションをとっていれば……自分の順位ならイジメだって止めさせることができたはずなのに……貼りだされた成績を見れば、卒業まで自殺室に行くことは無かった成績だし……もっと心のケアを自分がすることができれば……あと」
「あと?」
「光莉を失って初めて好きだったということにも気付いたんだ……ダメだよね、全然ダメだよね、僕……こんなヤツ、死ねばいいんだよ、早く死ねばいいんだよ……死にたい……死にたいよ……」
「つまり、じゃあ、コイツが、信太の仇というわけね……おい! オマエ! さっさと死ねぇぇ! ……えっ?」
と彼のほうを見た陽菜は何かに驚愕した。
一体何なんだろうと思いながら彼がいたはずの方向を見ると、そこに彼はいなくて、じゃあどこだと思って首吊り台のほうを見ると、既に自殺を試みていた。
その彼は多分、僕が喋っている間に台の上にあがったみたいだ。
僕と同じ空間にいることが、つらすぎたようで。
しかし、まだ死ねていない。
ずっと足がバタバタと空を切り、口から泡を吹き出し、目玉が飛び出そうになりながら、ずっと、ずっと首を吊られた状態で苦しんでいた。
普通、今までなら、こういう死の時になったら、彼自身は砂状になり、空間も風化していくのに、全然変わらない。
「ふぬぬぬぬぅぬぬぬぬぅぬぬぬぬぬぬぅぅぅううう!」
声にならない声が空間をこだましている。
彼は一向に変わらないが、空間の様子は少しずつ変貌していった。
樹海にいた虫たちが彼の死臭を感じ取り、どんどん彼の体に張り付いていった。
中には彼の口の中に入っていく虫もいて、何なら虫で窒息するくらいの勢いだ。
「あががががががががぁぁぁぁぁああああああああああああああああああぅぅうううううううう!」
彼の断末魔は終わらない。
どういうことだ。
僕は呆然としながら、ただただその彼のことを見ていると、陽菜は囁いた。
「死にたくなったから死ねないんだ……信太の言葉を聞いて死にたくなったから、死ねないんだ……」
ゾワァッとした。
ということはこの男子生徒はこの状況でずっと生き続けるということか?
死ぬような思いをしながら、ずっと死ねずに、このままで。
僕はたまらず声を出した。
「生きたいと思え! そうすれば生きられるんだ! 実は! だって生きたいだろ! こんな状況でいたくないだろ! 本心だ! 本心を心の中で叫べ! こんなところにいないで楽しく生活していたいって! 生きたいって思うんだよ!」
その言葉が届いたのか、男子生徒は悶え苦しむことをやめ、体が砂状になり、そして空間が風化し、元の真っ白い空間に戻った。
どうやらちゃんと死ねたらしい。
生きたいと思えば死ねる空間だから。
僕は胸をなで下ろしていると、陽菜が聞いてきた。
「ねぇ、信太、仇なんでしょ? 何で楽になるようなことを言ったの?」
「だって……あんなのつらいじゃないか……」
そう言って僕は俯くと、それ以上に暗そうな声で陽菜が、
「そんな……信太のほうがつらいじゃん……仇討ちじゃん……あんなヤツに同情する余地無いじゃん……」
「いやいいんだよ、もう」
そう言って僕は顔を上げて、陽菜のほうをしっかり見た。
陽菜は一息ついてから、
「……まあいいだったら、もういいけどなぁ」
そう言ってその場に座り込んだので、僕も隣に座った。
僕は一つ浮かんだ言葉がある。
だから、
「一つ思ったことがあるんだけど、聞いていい?」
「何? アタシで良ければ何でも聞くけどっ」
「陽菜は今も、死にたいんだよね。だから死ねないで今もここにいるんだよね」
「うん、ハッキリ言えば死にてぇ、それだけ」
そう少し面倒臭そうに言った陽菜。
僕は続ける。
「でも入ってきた生徒の運命を変えたいとは今、思うんだね」
「そりゃ思う。まあ大体はもうクズばっかで、運命変えなくていいかなって途中で思うんだけどな」
「入ってきた生徒の運命を変えるために生きていたい、とは、思わないんだね」
「いやそれは思わないな、そんなことよりは死にてぇ。でもそれも叶わないなら、せめて助けたいだけ。結局ただの暇潰しかもな。勝手だよな、アタシって。やっぱり独善的なままだよな」
そう言って切なげに笑った陽菜。
そんな陽菜に追い打ちをかけるようで悪いんだけども、僕は自分の聞きたい言葉を優先させた。
「何で自殺室に来たの?」
少し空いた間。
陽菜は絞り出すように喋りだした。
「……似たようなもんだと思うよ、その光莉って人とね。もうこのシステムで生きることが嫌なんだ。だからいっそのこと死にたい。それだけ。でも自分では死ねず、自殺室に助けを求めたってわけ。その結果、自殺室に死なせてもらえていないだけ」
「じゃあやっぱり似た者同士だね、僕たち」
「そうだな、何だかんだで全くの一緒、一致しているのかもな」
一致。
全くの一致。
何だか。
何だか。
同じなら。
と、深く思考しようとしたその時だった。
「なぁ、信太、せっかくだからしりとりでもしようぜ!」
そう言って明朗に笑った陽菜。
「いや何で急にしりとりをするの」
「いいじゃん! とにかくまずは、しりとりの”か”な!」
「しりとりには”か”は勿論、か行すら無いよ」
僕はとりあえず普通にツッコミを入れた。
それに対して陽菜は嬉しそうに、
「カニ食べ放題で貝ばっかり食う! はい!」
「いや禁じ手の文章を早くも使ってる。どういうこと」
「どういうこととか、そういうのいいだろ! とにかく、しりとりするんだよ!」
何だか陽菜は、どこか少し焦っているような気がした。
何でこのタイミングで、とかは思ったけども、僕は改めて言うことにした。
「陽菜、僕は相変わらず死にたいから、すぐには死なないよ。一人ぼっちで寂しくはならないから大丈夫だよ」
「別に急に寂しくなったわけじゃないから! ただ遊びたいだけだから!」
もしかしたら陽菜は一瞬、溝渕さんのことを考えてしまったのかもしれない。
それを紛らわすために、こんな突発的に言い出したのかもしれない。
僕もいろいろなことを考えるし、陽菜も様々なことを考えるだろうし。
まあそういうことだろう。
いや待て。
それともさっきの樹海で気落ちしていると思われる僕への配慮か。
とにかく、
「今は遊びたい気分じゃないんだ。もう休むよ、僕」
それに対して陽菜はムスっとしながら、
「……何で遊んでくれないんだよぉ……もー……」
「逆に何でそんなに遊びたいの? 今はもう休もうよ、疲れたよ」
「だって、アタシ、信太のこと……」
と言ったところで黙って俯いた陽菜。
僕は本当に今すぐ休みたかったので、早く会話を終わらせようと、ちょっと冷徹な感じで、
「何?」
と言うと、陽菜は急に大きな声を上げた。
「やめた! やめた! 回りくどいことやめた! アタシらしくねぇわ!」
「何か企んでいたわけだ、何を企んでいたの?」
と僕は少々イライラしながら、そう言うと、陽菜は僕の顔をじっと見ながら、
「じゃあ言うわ。アタシは信太と一緒に死にたい! 今すぐに信太と一緒に死にたい!」
「……何で僕と一緒なの? そんなに寂しいのっ?」
「違う! アタシは信太のことが好きになったから!」
一瞬僕の何かが揺れ動いたような気がした。
陽菜は軽快に続ける。
「いつも冷静にアタシのこと思ってくれたり! アタシのボケにもちゃんとツッコんでくれたり!」
僕の頭の中は徐々に真っ白になっていく。
まるでこの空間のように。
「冷静なのは冷めているだけだし、ボケとかは流れ上、処理するしかないじゃん」
いや。
いやいや。
陽菜が、僕のことを、好き……?
そんなこと、考えもしなかった。
ただの友達だと思っていたから。
いやむしろ、僕が……あっ。
ダメだ。
僕。
死ぬわ。
いや死んでいいんだけど。
死んでいいだけどもダメなんだ。
あぁ、そういうことか……溝渕さんは、僕たちを見て、気付いたのか。
溝渕さんは僕たちを見て、僕よりも前にいた人との関係を思い出し、そして気付いたのか。
客観的に見れて感謝って、僕と陽菜の関係を見て、自分がこうだったんだと気付いたんだ。
『そのままでいい』は余計なことを言って今の関係を邪魔しないため、何も言わないようにして、あの『一緒に』は俺みたいに一人で相方のような存在を死なせるな、一緒に死ねということか……あぁ、言わないと。
最期に言わないと。
「……僕も、好きだよ、陽菜」
「えぇっ! 本当にっ? よっしゃぁぁぁああああああ!」
そう言ってガッツポーズをした陽菜。
いや、
「情緒が無いな。いやでもそれが陽菜か……陽菜、君は何だか、僕にとっての光だよ」
「光莉って、信太の好きだった女性のこと? それくらい好きってこと? いやそれは複雑だなぁ」
「そうじゃなくて、闇とか光のほうの、光だよ」
「あぁ、そっちねぇ」
そう言ってホッとしたような表情をした陽菜。
僕は続ける。
「君が来て、僕の心は照らされたんだ。熱くて陽射しが痛い時もあるけども、君の言葉が僕を焦がすんだ」
「何それ、詩人?」
「死びと、かもね」
「えっ、死ぬの? ちょっ! 何で! 死にたいんじゃないのっ! というかアタシと一緒に死のうよ! 信太!」
陽菜が僕の手を握る。
でも僕の手は徐々に砂状になっていくので、陽菜はもっと、手首のほうを握る。
僕は言う。
「ううん、違う、陽菜……」
「……何……」
「僕、陽菜と一緒に生きたいんだ、ずっとずっと生きたいんだ」
「……あっ」
僕はどんどん砂になっていく。
その最中に見えた。
陽菜も砂になっていくところが。
生きたかった。
もっと陽菜と、ずっと生きたかった。
こんな自殺室という空間でもいいから、ずっと陽菜と生きたかった。
でもそれも、もう、叶わないんだなぁ。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・【19 樹海】
・
溝渕さんがいなくなってから、もう十人以上の生徒が入ってきた。
もう溝渕さんのいない日々のほうが日常だ。
溝渕さんがいなくなっても、僕と陽菜の関係が変わることは無く……いやでもより距離が近くなったような気がする。
それは心も物理的にも。
陽菜はやけにベタベタ僕にくっつくようになってきた。
まるで本当に光莉みたいに。
それに対して、僕も正直全然嫌じゃない。
そういう距離で会話することは光莉で慣れていたし、特にそれで何か考えるようなことも無かった。
いや、でも、どこか、何かが引っかかる思いは感じている。
それは棘とかじゃなくて、何だか不思議と温かいモノだった。
そんなことを時折考えながら、この自殺室で暮らしていったある時、また男子生徒が入ってきた。
また空間は一変し、樹海のように木々が生い茂る空間になった。
そしてこれ見よがしに空間の中央には首吊り用の縄に、台が置かれた。
今回は導くにしても簡単だし、そんなに苦しんでいるところを見なくてもいいかもしれない。
男子生徒の彼は呟く。
「何なんだ、ここは……こんな虫がいそうなところ……汚らしい……」
それに対して陽菜が言う。
《虫が苦手なんだな、コイツは》
《まあ基本みんな好きじゃないけどね》
《アタシは結構好きだけどな、カッコイイし》
そう言いながら腕を組んで頷いた陽菜。
まあ確かに
《カブトムシとかクワガタはカッコイイかもしれないけども》
僕がそう相槌を打つと、陽菜は首を横に振って、
《いや蚊》
と言い切ったので、僕は驚いてしまい、生返事のオウム返しをし、
《蚊ぁっ?》
と語尾も何だか妙に上げてしまった。
ちょっと恥ずかしい声になっちゃったな、と思っていたけども、陽菜はそんなこと気にせず、喋る。
《血を吸うとか、かなりイカしてるじゃん。しかもバレずに吸っておいて、最後は痒みで吸ったことバラすって。仕事は冷静、でも最後の勝負は正々堂々と情熱みたいな》
《いや痒みは別に正々堂々勝負したいからじゃないよ、痒みのある液を体内に流し込むことによって血液の凝固を防いでいるだけで》
《だからって痒みのある液にする必要無いじゃん、やっぱりあえて痒みのある成分を入れて流し込んでいるとしか思えないね、カッコイイよ、蚊は》
《そうかなぁ》
独特な感性だなと思いつつも、それがまあ陽菜かと思って納得した。
男子生徒の彼は周りの様子を見て叫び声を上げる。
「どうせならもっと都会で死にてぇよ! こんな虫、虫! 虫ぃっ!」
僕は分析をする。
《この彼の死にたくない状況って、虫が多い状況ということなのかもしれないね》
それに対して陽菜は小首を傾げながら、
《虫なんて天国の一種じゃん》
《天国の一種ではないと思うけども》
そんなどうでもいいやり取りをしたところで、陽菜は首を回しながら、こう言った。
《というわけで、そろそろ姿を現すかなぁ。あんまり発展しそうにないもんなぁ》
《陽菜って入ってきた生徒を助けようとするよね、最近特にまた》
《それは信太だって一緒だろ? アタシは悪いヤツ以外は全員助けたいんだよ! というか変えたいんだよ、きっとアタシたちはこの人たちの運命を変えるためにいるんだよ》
《そう言って助けられた試しはまだ一度も無いけどね》
そう一度も。
あれから幾度となく自殺室に生徒が入ってきたが、ことごとく生徒を助けられたことはない。
《でも今度こそやってやるんだからな! まあいいヤツならだけどな!》
そう言って、陽菜は姿を現した。
僕も頃合いを見て、出ることにしよう。
姿を現した陽菜を見て、彼は戦々恐々しながらこう言った。
「……オマエ、深山陽菜か……何故こんなところに……」
「アンタがいいヤツなら助けてやるぜ!」
陽菜は今日、一段と気合いが入っているような気がした。
いや、陽菜は日に日に意気込みが増していっている。
普通こんな空間にいたら、どんどん気持ちが落ち込んでいきそうだけども、陽菜はどんどん上昇していく。
特に、あの川の一件から陽菜は変わった。
より明るくなったと思う。
陽菜が言うところの独善的な明るさから、本当に全てを助けたい、喜ばせたいといったような明るさ。
どんどん周りを、というか特に僕を鼓舞していくようになった。
とはいえ、やって来た生徒を助けられた例なんて一個も無いし、極悪と言ってもいい所業をやらかしていた生徒には陽菜の気持ちが反転して、そういう生徒と喧嘩になったこともあるんだけども。
この気合いの入りすぎが、悪いほうにいかなきゃいいんだけど。
要は入ってきた生徒と喧嘩しないでほしい。
そうなると無駄に長引いてしまうから。
入ってきた彼は手を合わせて喜びながら、
「マジかっ! ありがとう!」
と言った。
いやいや、と思いながら、
「陽菜、あんまり期待するようなことを言っちゃダメだから。今まで助けられた生徒なんていないんだからさ……」
そう言いながら僕も姿を現すと、この彼は陽菜の時と違い、体を硬直させた。
いやでも僕にはこの彼には見覚えが無い。
しかしこの彼は明らかに、僕に怯えている。
どういうことだ?
そしてその彼はポツリと呟いた。
「木島光莉の……」
それこそ僕が硬直した。
木島光莉。
それは、僕の幼馴染の光莉のフルネームだ。
まさか。
コイツが。
光莉を……!
「死ねぇぇぇええええええ!」
我を失うってこういうことだと、この彼を殴った時に気付いた。
いやこの彼に触れることはできなかったから、殴れなかったんだけども。
そんな僕に陽菜は慌てながら、
「ちょっ! 信太! 急にどうしたんだよぉっ!」
僕は呼吸を整えた。
否、整わない。
どんどん息が荒くなる。
許せない。
許せない。
光莉は、光莉は、こんなヤツに……、
「オマエか……オマエがっ! 光莉のことをイジメていたのはっ!」
僕がそう叫ぶと、彼はぶるぶると震えながら、
「……いや……オレは……最初は、止めようとして……」
「最初は? じゃあイジメに加担していたということだなぁっ!」
「いや……まあ……なんというか……えっ、それが原因? オマエが自殺室に行ったのっ?」
それ?
光莉のイジメが、それ?
何だその言い方。
馬鹿にしてんのか。
光莉のことを馬鹿にしてんのか! クソっ!
「あぁぁぁぁぁああああああああああああああああああああああああああああ!」
と僕が叫んだところで、僕の目の前で猫だましをした陽菜。
僕はつい目を閉じた瞬間、ハッとなんとか気を取り戻した。
でもまたすぐこうなるだろう。
だって光莉を、光莉をあんな目に遭わせた張本人が……と思ったところで、陽菜が僕の肩を掴んで、
「らしくなぁっい! らしくないぞ! 信太! 叫ぶのはアタシの役目だろうがぁっ!」
僕よりもデカい声を上げた陽菜は続ける。
「信太! 何があったか簡潔に話してほしい! それで決めるから!」
別に陽菜に何がどうか決めてほしいわけではないけども、話さずにはいられなかった。
「木島光莉は僕の幼馴染で、僕が好きだった女性だ……一緒に入学した光莉は、元々は上位だったんだけども、このシステムにどんどん憂鬱になり、徐々に成績を落としていった……そして中位になると、精神的なダメージを与えてもっと順位を下げようとしてくれる連中からイジメられるようになり……成績的にはまだ大丈夫だったんだけど、自殺室のドアの前で自殺した……という話……」
「……という話?」
「そう……僕は全てそれらの話をあとから聞いたんだ……光莉が死んだあとに、ね……光莉がそんな状況になっていることに気付いていなくて、僕は自分のことでずっと必死で」
陽菜は真剣な瞳で小さく頷く。
僕は続ける。
「光莉ともっと密にコミュニケーションをとっていれば……自分の順位ならイジメだって止めさせることができたはずなのに……貼りだされた成績を見れば、卒業まで自殺室に行くことは無かった成績だし……もっと心のケアを自分がすることができれば……あと」
「あと?」
「光莉を失って初めて好きだったということにも気付いたんだ……ダメだよね、全然ダメだよね、僕……こんなヤツ、死ねばいいんだよ、早く死ねばいいんだよ……死にたい……死にたいよ……」
「つまり、じゃあ、コイツが、信太の仇というわけね……おい! オマエ! さっさと死ねぇぇ! ……えっ?」
と彼のほうを見た陽菜は何かに驚愕した。
一体何なんだろうと思いながら彼がいたはずの方向を見ると、そこに彼はいなくて、じゃあどこだと思って首吊り台のほうを見ると、既に自殺を試みていた。
その彼は多分、僕が喋っている間に台の上にあがったみたいだ。
僕と同じ空間にいることが、つらすぎたようで。
しかし、まだ死ねていない。
ずっと足がバタバタと空を切り、口から泡を吹き出し、目玉が飛び出そうになりながら、ずっと、ずっと首を吊られた状態で苦しんでいた。
普通、今までなら、こういう死の時になったら、彼自身は砂状になり、空間も風化していくのに、全然変わらない。
「ふぬぬぬぬぅぬぬぬぬぅぬぬぬぬぬぬぅぅぅううう!」
声にならない声が空間をこだましている。
彼は一向に変わらないが、空間の様子は少しずつ変貌していった。
樹海にいた虫たちが彼の死臭を感じ取り、どんどん彼の体に張り付いていった。
中には彼の口の中に入っていく虫もいて、何なら虫で窒息するくらいの勢いだ。
「あががががががががぁぁぁぁぁああああああああああああああああああぅぅうううううううう!」
彼の断末魔は終わらない。
どういうことだ。
僕は呆然としながら、ただただその彼のことを見ていると、陽菜は囁いた。
「死にたくなったから死ねないんだ……信太の言葉を聞いて死にたくなったから、死ねないんだ……」
ゾワァッとした。
ということはこの男子生徒はこの状況でずっと生き続けるということか?
死ぬような思いをしながら、ずっと死ねずに、このままで。
僕はたまらず声を出した。
「生きたいと思え! そうすれば生きられるんだ! 実は! だって生きたいだろ! こんな状況でいたくないだろ! 本心だ! 本心を心の中で叫べ! こんなところにいないで楽しく生活していたいって! 生きたいって思うんだよ!」
その言葉が届いたのか、男子生徒は悶え苦しむことをやめ、体が砂状になり、そして空間が風化し、元の真っ白い空間に戻った。
どうやらちゃんと死ねたらしい。
生きたいと思えば死ねる空間だから。
僕は胸をなで下ろしていると、陽菜が聞いてきた。
「ねぇ、信太、仇なんでしょ? 何で楽になるようなことを言ったの?」
「だって……あんなのつらいじゃないか……」
そう言って僕は俯くと、それ以上に暗そうな声で陽菜が、
「そんな……信太のほうがつらいじゃん……仇討ちじゃん……あんなヤツに同情する余地無いじゃん……」
「いやいいんだよ、もう」
そう言って僕は顔を上げて、陽菜のほうをしっかり見た。
陽菜は一息ついてから、
「……まあいいだったら、もういいけどなぁ」
そう言ってその場に座り込んだので、僕も隣に座った。
僕は一つ浮かんだ言葉がある。
だから、
「一つ思ったことがあるんだけど、聞いていい?」
「何? アタシで良ければ何でも聞くけどっ」
「陽菜は今も、死にたいんだよね。だから死ねないで今もここにいるんだよね」
「うん、ハッキリ言えば死にてぇ、それだけ」
そう少し面倒臭そうに言った陽菜。
僕は続ける。
「でも入ってきた生徒の運命を変えたいとは今、思うんだね」
「そりゃ思う。まあ大体はもうクズばっかで、運命変えなくていいかなって途中で思うんだけどな」
「入ってきた生徒の運命を変えるために生きていたい、とは、思わないんだね」
「いやそれは思わないな、そんなことよりは死にてぇ。でもそれも叶わないなら、せめて助けたいだけ。結局ただの暇潰しかもな。勝手だよな、アタシって。やっぱり独善的なままだよな」
そう言って切なげに笑った陽菜。
そんな陽菜に追い打ちをかけるようで悪いんだけども、僕は自分の聞きたい言葉を優先させた。
「何で自殺室に来たの?」
少し空いた間。
陽菜は絞り出すように喋りだした。
「……似たようなもんだと思うよ、その光莉って人とね。もうこのシステムで生きることが嫌なんだ。だからいっそのこと死にたい。それだけ。でも自分では死ねず、自殺室に助けを求めたってわけ。その結果、自殺室に死なせてもらえていないだけ」
「じゃあやっぱり似た者同士だね、僕たち」
「そうだな、何だかんだで全くの一緒、一致しているのかもな」
一致。
全くの一致。
何だか。
何だか。
同じなら。
と、深く思考しようとしたその時だった。
「なぁ、信太、せっかくだからしりとりでもしようぜ!」
そう言って明朗に笑った陽菜。
「いや何で急にしりとりをするの」
「いいじゃん! とにかくまずは、しりとりの”か”な!」
「しりとりには”か”は勿論、か行すら無いよ」
僕はとりあえず普通にツッコミを入れた。
それに対して陽菜は嬉しそうに、
「カニ食べ放題で貝ばっかり食う! はい!」
「いや禁じ手の文章を早くも使ってる。どういうこと」
「どういうこととか、そういうのいいだろ! とにかく、しりとりするんだよ!」
何だか陽菜は、どこか少し焦っているような気がした。
何でこのタイミングで、とかは思ったけども、僕は改めて言うことにした。
「陽菜、僕は相変わらず死にたいから、すぐには死なないよ。一人ぼっちで寂しくはならないから大丈夫だよ」
「別に急に寂しくなったわけじゃないから! ただ遊びたいだけだから!」
もしかしたら陽菜は一瞬、溝渕さんのことを考えてしまったのかもしれない。
それを紛らわすために、こんな突発的に言い出したのかもしれない。
僕もいろいろなことを考えるし、陽菜も様々なことを考えるだろうし。
まあそういうことだろう。
いや待て。
それともさっきの樹海で気落ちしていると思われる僕への配慮か。
とにかく、
「今は遊びたい気分じゃないんだ。もう休むよ、僕」
それに対して陽菜はムスっとしながら、
「……何で遊んでくれないんだよぉ……もー……」
「逆に何でそんなに遊びたいの? 今はもう休もうよ、疲れたよ」
「だって、アタシ、信太のこと……」
と言ったところで黙って俯いた陽菜。
僕は本当に今すぐ休みたかったので、早く会話を終わらせようと、ちょっと冷徹な感じで、
「何?」
と言うと、陽菜は急に大きな声を上げた。
「やめた! やめた! 回りくどいことやめた! アタシらしくねぇわ!」
「何か企んでいたわけだ、何を企んでいたの?」
と僕は少々イライラしながら、そう言うと、陽菜は僕の顔をじっと見ながら、
「じゃあ言うわ。アタシは信太と一緒に死にたい! 今すぐに信太と一緒に死にたい!」
「……何で僕と一緒なの? そんなに寂しいのっ?」
「違う! アタシは信太のことが好きになったから!」
一瞬僕の何かが揺れ動いたような気がした。
陽菜は軽快に続ける。
「いつも冷静にアタシのこと思ってくれたり! アタシのボケにもちゃんとツッコんでくれたり!」
僕の頭の中は徐々に真っ白になっていく。
まるでこの空間のように。
「冷静なのは冷めているだけだし、ボケとかは流れ上、処理するしかないじゃん」
いや。
いやいや。
陽菜が、僕のことを、好き……?
そんなこと、考えもしなかった。
ただの友達だと思っていたから。
いやむしろ、僕が……あっ。
ダメだ。
僕。
死ぬわ。
いや死んでいいんだけど。
死んでいいだけどもダメなんだ。
あぁ、そういうことか……溝渕さんは、僕たちを見て、気付いたのか。
溝渕さんは僕たちを見て、僕よりも前にいた人との関係を思い出し、そして気付いたのか。
客観的に見れて感謝って、僕と陽菜の関係を見て、自分がこうだったんだと気付いたんだ。
『そのままでいい』は余計なことを言って今の関係を邪魔しないため、何も言わないようにして、あの『一緒に』は俺みたいに一人で相方のような存在を死なせるな、一緒に死ねということか……あぁ、言わないと。
最期に言わないと。
「……僕も、好きだよ、陽菜」
「えぇっ! 本当にっ? よっしゃぁぁぁああああああ!」
そう言ってガッツポーズをした陽菜。
いや、
「情緒が無いな。いやでもそれが陽菜か……陽菜、君は何だか、僕にとっての光だよ」
「光莉って、信太の好きだった女性のこと? それくらい好きってこと? いやそれは複雑だなぁ」
「そうじゃなくて、闇とか光のほうの、光だよ」
「あぁ、そっちねぇ」
そう言ってホッとしたような表情をした陽菜。
僕は続ける。
「君が来て、僕の心は照らされたんだ。熱くて陽射しが痛い時もあるけども、君の言葉が僕を焦がすんだ」
「何それ、詩人?」
「死びと、かもね」
「えっ、死ぬの? ちょっ! 何で! 死にたいんじゃないのっ! というかアタシと一緒に死のうよ! 信太!」
陽菜が僕の手を握る。
でも僕の手は徐々に砂状になっていくので、陽菜はもっと、手首のほうを握る。
僕は言う。
「ううん、違う、陽菜……」
「……何……」
「僕、陽菜と一緒に生きたいんだ、ずっとずっと生きたいんだ」
「……あっ」
僕はどんどん砂になっていく。
その最中に見えた。
陽菜も砂になっていくところが。
生きたかった。
もっと陽菜と、ずっと生きたかった。
こんな自殺室という空間でもいいから、ずっと陽菜と生きたかった。
でもそれも、もう、叶わないんだなぁ。
・
・
・
・
・
・
・
・
・