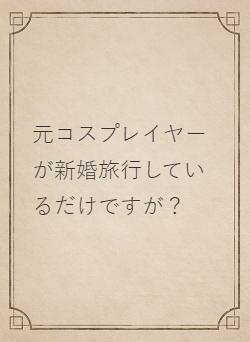・
・【15 おびき寄せる】
・
一人の女子生徒が入ってきた。
自殺室はまた一変し、前回のような人間が多い雑踏の光景になった。
陽菜はすぐさま平坦に《あーっ》と声を出したと思ったら、こんなことを言った。
《入室と同時に声に膜が張るよな。便利というかなんというか》
《確かに。来る前は別に、普通に会話できるもんね》
《この膜が張っている感じは何か嫌なんだよな。自分がいないみたいで》
《でも実際僕には見えているから大丈夫だよ》
僕が普通にそう言っただけなのに、何だか陽菜は少し嬉しそうに笑ってから、
《そうだな、信太に見えているだけで十分かもなっ》
何だかその表情にドギマギしてしまった。
何だろう、この感情。
不思議なような、新しいような、懐かしいような。
そんなことを考えていると陽菜が、
《それにしてもまた人混みって、爆竹?》
《そんなことは無いんじゃないかな、まあ様子を見てみよう》
《ただ全員で打ち上げ花火を見るだけならいいんだけどな》
《河川敷とかならまだしも、ここ都会っぽいから違うんじゃないかな》
と僕がツッコむと、まるで陽菜が僕にツッコミを入れているようなテンションで僕の肩を叩きながら、
《まあ確かにそうだなぁ! 都会で打ち上げ花火は危ないからな! ハッハッハ!》
と、やけに快活に笑った。
何がそこまでおかしいのかはちょっと分からなかったけども、楽しそうで何よりだ。
僕と陽菜はこんな他愛も無い会話をすることがどんどん多くなっていった。
だけど僕と陽菜の会話が増える度に、溝渕さんの言葉数は減っていった。
実際、陽菜が溝渕さんのことをお客さん扱いしているから会話する機会自体が少ないだけなんだけども。
溝渕さんの表情を見ていると、こっちの会話を聞いて優しく笑っていると思ったら、急に思い詰めたような表情をしている時があって。
ふと溝渕さんが言っていた『直子は俺のことを憎んでいたのでは』というような言葉が脳内で再生される。
溝渕さんは何か僕と陽菜に文句があるのだろうか。
いや確かに陽菜から一方的にお客さん扱いされたら嫌かもしれない。突っぱねられている感じもするし。
でもそんなことで嫌な気持ちになるような人じゃないだろうと思うこともあって。
いやいやそんなことより今はまずこの女子生徒の動きを注視しよう。
さて、そろそろ女子生徒の言動も何か出てくる頃だろうと思っているんだけども、この女子生徒は反応が薄い。
まだ一言も喋っていない。
でも何も動じていないわけでは無さそうだ。
何故なら何か思案しているような面持ちはしているからだ。
そしてついにこの女子生徒は口を開いた。
「何で地元だし?」
どうやらここは地元の風景らしい。
今回は思い出の中で何かあったパターンだ。
胸糞の悪い話じゃないように、と心の中で願ったが、公衆便所のことを思い出し、きっと良くない話なんだろうな、と思ってしまった。
そんな僕は、きっと不安そうな顔をしていたのだろう。
僕の顔を覗き込んで陽菜が、
《どうしたの? これヤバイ感じなの?》
《自分の地元が、思い出が出てくる時に良いパターンは無かったかな》
と僕が言ったその時だった。
部屋の真ん中に机が出現した。
その机の形状は奈々江さんの時とは全然違った。
奈々江さんの時の机は、真っ白い色に丸い机だった。
しかしこの女子生徒の前に出現した机は、真っ黒い色に角が鋭い三角形の机。
さらにその机の上にはラベル付きの液体が入った瓶。
陽菜はすぐさまそのラベルを見に行き、
《これ硫酸だ! ヤバイ!》
硫酸。
硫酸を被って死ぬなんて、どう考えても苦しむしかない。
ということはこの女子生徒は良くないことをしていたことが確定した、と言っていいだろう。
だから、とりあえず僕は陽菜にそのことを伝えた。
《苦しんで死ぬ可能性が高い時は、きっとこの女子生徒は良くないことをしていたんだと思う》
《何それ! 腹立つな! すぐに出てってやる!》
《いやちょっと待って、陽菜。もう少し様子を見よう。周りの光景は変わることがあるんだって……そうですよね、溝渕さん》
そう言って僕はまだ座っている溝渕さんに同意を求めると、溝渕さんは小さく頷きながら、
《そうだ。俺の経験上、これから周りの風景は変わっていくだろう。まるで周りの風景だけが動いていくようにな》
陽菜は今にも飛び出しそうな雰囲気から、一旦落ち着いた感じになって、とりあえずは傍観する流れになった。
「何? 帰ってこれたの? でもあの黒い机何? あんなんあったっけ?」
女子生徒も黒い机に近付き、ラベルを確認した。
「硫酸? 何これ? これで死ねってこと? いやいや、意味分かんないし。ここ中央通りじゃないの?」
何だか話の進みも遅そうだし、そろそろ出ないといけないかなと思っていると、その女子生徒は急に大きな声を上げた。
「誰だ! 急に男が出てきたし!」
痺れを切らした溝渕さんが出てきたのかな、と思ったら、存在がクリアになっているのは僕だった。
何で、念じていないのに、いやでもこんな経験は一度ある。
奈々江さんの時だ。
あの時は念じていなくても僕が出現した。
じゃあこの彼女は僕に何か用がある人なのか?
《信太! 急にどうしたんだよ! まだ見ていく流れだっただろ!》
「たまにこういうことがあるんだよ。念じていないのに出てしまうパターンが」
《何だそれ! いろいろあって分かんないな! この空間は! じゃあアタシも今行く! ……あれ? 何か出られない!》
「えっ? その膜から? じゃあ本当に僕だけなんだっ」
と声を出しながら、溝渕さんのほうも見ると、溝渕さんもコクンと頷き、どうやら溝渕さんも出られないようだった。
挙動不審のようにキョロキョロしていると、彼女が喋り出した。
「いや誰と話してんの? というか誰? 地元のダチじゃないしさ、普通このタイミングなら地元のダチじゃね?」
……あれ? 僕に関係している人じゃない?
それなのに僕が出現してしまった、って、一体どういうことなのだろうか。
もしかしたら逆に、僕がこの彼女に関係しているのか。
いやいや全然見覚えが無い……わけでもない?
何故かどこかで見たことあるような。
僕は割と記憶がいいほうだと自負している。
そんな僕がどこかで見たことあるのならば、僕は見たことあるんだ。
そもそもこの彼女がいったこの場所”中央通り”は、中学三年生の時に何だか行ったことがあるような。
古本を探して大きな街へ行った時、こんな場所があったような。
と、じっくり考えたいんだけども、彼女はどんどん喋ってくる。
「いやマジ誰? イミフなんですけど。ここ中央通り? それとも自殺室? どっちなん?」
ここはまず彼女の質問に答えないといけないな。
「僕は自殺室を司る死神です。ここは自殺室です。この自殺室は貴方の心の中とリンクして、死ぬ時のシチュエーションが決まります。貴方はここ、中央通りに強い思い出があるのでしょう」
「死神て。こんな普通の男子生徒みたいな感じが? ウケんね。何か死にきれなかったガキみたいな感じじゃん」
多分偶然だろうけども、死にきれなかったガキは合っている。
でもその説明は省いていいだろう。
僕は続ける。
「この自殺室では自分が最も死にたくない、屈辱的な死に方をしなければいけません。貴方は自分の容姿が気に入っているのでしょう。だからこの硫酸を被って死ななければならないのです」
「マジかよ……硫酸ってドロドロにただれるヤツだろ? そんなん絶対嫌だし。私は結構今盛れてるし」
「だからこそです。その容姿を失うような死に方をしないといけないんです」
「クソみてぇな罰だし。罰を受けるべきはオマエのような凡人顔の男だし。つまんねぇ顔、硫酸で溶かして整えろや」
ヘラヘラ笑って人を見下しているような言い方。
僕はこの空間を理解している側だから、正直そんなに気にならなかったけども、陽菜が叫び声を上げた。
《何言ってんだよ! 信太が優しく言ってんだから従えよ! バカ!》
「まあまあ」
と僕が陽菜のほうを見ながら声を出したところで彼女が、
「他に誰かいるん? 死神って群れてるんだ。ウケんね。連れション死神とかあるんだ」
卑しく笑う彼女に僕はハッキリと言うことにした。
「何でそんなに余裕なのかは分かりませんが、自分で死のうとしないと、最も苦しむ方法で死なないといけなくなるんです。だからまだ意識があるうちに、硫酸をかぶって自殺して下さい」
「そんなんするわけねぇじゃん、誰がオマエの言うこと鵜呑みにするかよ。というかその制服、ウチの学校の制服じゃん。オマエ、もしかすると自殺室へ先に入った生徒か? 普通に死なずに生きてるし。じゃあ私も生きるから安心するし」
どうやら勘は良いみたいだ。
仕方ない、ちゃんと説明するか。
「この自殺室は生きたい人は死んで、死にたい人は生きてしまう部屋。確かに僕は死神ではなくて、この自殺室で死ねなかった人間です」
「嘘ついてたし! というか死にたいってマ? 死にたいヤツは勝手に死ねばいいし! ウケんね! マジで!」
「僕の話はこの際どうでもいいじゃないですか。今は貴方の話が重要です。この状況、何か見覚えがあるんじゃないんですか?」
と僕が言ったところで、彼女は何かに気付いたような表情をしながら、
「この状況に見覚え?」
と言った。
何に気付いたのだろうか。
やっぱり僕と彼女はどこかに接点があったのだろうか。
いやでもイマイチ思い出せない。
ちょっとすれ違ったくらいなんじゃないかな。
でもそれだと学校にいた生徒はほぼ全員そうなるだろうし。
それこそ、何か状況に関係しているのか、とか思っていると、彼女はこう言った。
「なるほどね、じゃあオマエにこれをやってやればいいんじゃね? そうしたら仲間も出てくるんじゃね?」
そう言って悪知恵が働いている人のような笑みを浮かべた。
一体何をやるんだろうと思って、身構えていると、
「ねぇ、お兄さぁん。ちょっと私と楽しいことしないぃ?」
急に甘ったるい声を上げて、ブリッコのように僕へ近付いてきた彼女。
何だこれ。
何なんだこれ。
めちゃくちゃ既視感がある。
その時に僕は思い出してしまい、思わず声を出した。
「あの時の逆ナンの人だ!」
その言葉に一瞬ビクついた彼女は、ブリッコのような雰囲気を止め、少し嫌悪感のある目つきでこちらを見ながら、
「えっ、アンタ一回私に引っかかったことあんの? マジウケるしぃ」
「いや、断ったというか、しつこかったから逃げ出したけども」
「あーっ、じゃあ引っかかってないほうのヤツかぁ。確かに写真に残ってねぇと思うしなぁ」
僕は浮かんだことを率直に聞くことにした。
自分の中で激しく嫌悪感を抱き始めているので、自然と言葉もぶっきらぼうになる。
「そうやって逆ナンして遊んでいたのか?」
「そうそう、めちゃくちゃ遊んでやってたしぃ、どう? 慈善事業っしょ」
そう怪しくニタァと笑った彼女。
これは違う。
ただ二人で何かしていただけではない、何故なら
「仲間も出てくるってさっき言っていたけども、君に逆ナンされてついていったら、その部屋に君の仲間がいてボコボコにされるってことだな」
「ボコボコて。ウケるし。暴力だけじゃねぇし。まあなんというか、蹂躙プレイって感じぃ?」
暴力だけじゃない、ということは、暴力だってあるということだ。
さらに蹂躙だなんて、多分想像もしたくないようなことをするんだろうな。
だから想像なんてする必要無い。
する必要があることと言えば……と、改めて冷静な気持ちを自分の中に入れてから、
「今すぐ硫酸で死んで下さい。貴方はきっと醜い死に方をしてしまうだろうから」
「醜いのはあんな蹂躙されても女子が裸になったら反応してしまう男子のほうじゃね? ハハッ」
「何の話か分かりませんが、今すぐ自殺して下さい」
「嫌だし。自殺室でも生きる道があるって分かったから、このまま生きてやるし。そうしたらマジで遊んでやってもいいけどぉ? 悪くない取引じゃねぇ?」
僕は正直、醜い死に方をすればいいと思ってしまっている。
だからもうこれ以上、何か言うことは止めようかなと思い始めてきた。
チラリと溝渕さんのほうを見れば、大きな溜息をついて、呆れた表情をし、陽菜のほうを見れば顔まで真っ赤にして怒っている。
いや陽菜が何でそんなに怒っているかは分からないけども、もう今回はこのまま行くしかないみたいだ。
溝渕さんは正直分からないけども、陽菜はどう考えても、あの膜を破ろうとしても破れないみたいだし。
「じゃあ君は死ぬ気が無いんだね。じゃあそのまま自分が思うままに動いているといいよ」
「男なんかに命令されなくてもそうするし。というわけで! お兄さぁん、私と一緒に楽しいことしようよぉ?」
また甘ったるい声を出しているが、最初と違って邪悪に満ちている。
僕はただただ黙って立っていると、周りの光景が動き出した。
まるでプロジェクションマッピングのように、周りだけが動いて、真ん中の黒い机はそのまま。
その光景を見た彼女は、
「うわっ、進みだしたし! ていうかマジで私たちのアジトに向かってる感じじゃん! ウケんね! オマエ、行く気無いみたいな顔しといて私についてく気満々だったんじゃん! アソコは正直じゃん! ハハッ!」
あくまでこれは彼女の物語だ。
僕の気持ちは作用せず、彼女の物語が進行している。
でも少し気になってはいる。
果たして仲間はいるのか。
一体どんな自殺が待っているのか。
依然、プロジェクションマッピングのような移動は行なわれている。
勿論、自分たちが動いているわけじゃないので、歩いてはいない。
でもまるで歩いているような錯覚を受けてしまうのは、きっとこの風と香りのせいだ。
歩行している時のような向かい風を浴びて、雑居ビル群のところへやって来ると、カビくさい香りがした。
そして風景は階段を上がり始めて、とあるアパートの一室に来た。
「じゃあここで楽しいこといぃっぱぁいぃしましょうねぇ、お兄さぁん」
物語の中に入っているような彼女はニッコリと微笑んだ。
その時だった。
今まではあくまで映像を投影しているような感じだったのに、壁に、本物の扉が現れたのだ。
その扉の登場に彼女も一瞬怯む。
「何この扉、全然違うし」
その扉は鉄の扉で、全体的に腐食していた。
まるで硫酸をぶちまけられた扉のように。
あまりの禍々しさに、言葉を失う僕たち。
彼女は急に後ずさりし始めた刹那、彼女はその場に尻もちをついた。
腰が抜けたのかな、と思っていると、彼女は声を震わせながらこう言った。
「うまく動けないし……何これ……どういうこと……」
彼女が震える度に、黒い机が彼女の揺れのせいで(というように)動いていき、ついには黒い机が彼女の頭上あたりまでやって来た。当然、黒い机に乗っている硫酸の瓶も揺れている。
このタイミング。
この場所。
そうか、彼女の体が大きくブレたその時に、上にある硫酸の瓶が倒れて、彼女に偶然のように降り注いで死ぬんだ。
僕はそう思っていると、鉄の扉が開く音がした。
きっとここで何か驚かすようなモノが出てきて、そして彼女は体を強く揺らすんだと思っているので、何が出てきても驚かないつもりでいたが、僕は鉄の扉から出てきた存在に心臓が止まるかと思った。
その存在は、硫酸でただれ、ゾンビのような見た目になった人間たちなんだけども、全員目玉と両腕が無かった。
そんな人間が徐々に彼女に近付いていく。
「嫌だし……助けて! おい! オマエ! 助けてくれぇぇぇええええええええええええ!」
そう言って僕のほうを見そうだけども、彼女は首を動かせなくなっていることがなんとなく分かった。
「助けろよ! 男だろ! ……うわぁぁぁあああ! 何だよ! ここで普通の人間ってどういうことだよ!」
えっ、と思いながら、陽菜のほうを見ると、なんと陽菜の見た目が一段階クリアになっていた。
さらに多分この彼女は気付いていないと思うけども、後方で体育座りをしていた溝渕さんも姿を現した状態になっている。
その時に気付いた。
僕たちが彼女を見る側なんだと。
この部屋に彼女が僕を連れてきたんじゃなくて、僕が彼女をこの部屋に連れてきたんだ。
そして僕の仲間がいる陽菜と溝渕さんの部屋にやって来て、彼女がいわゆる蹂躙されていくところを見るんだ。
嫌だ。
見たくない。
そう思った時に気付いた。
僕は体が動けなくなっていた。
それはどうやら陽菜も一緒らしく、全然動いていない。
瞼も閉じることはできず、僕たちはこの光景を見るしかないんだ。
果たしてこの光景とは。
彼女に近付いていくゾンビのような人間たちは、徐々にスピードを上げ、ゼロ距離になったところで、ゾンビのような人間たちはしゃがんだり、倒れたりして、彼女へ覆い被さっていった。
自分の体についた硫酸をこすりつけるのかな、と思っていると、そのゾンビのような人間たちはなんと彼女の体中を舐め始めたのだ。
「やめてくれぇぇぇぇえええええええええええええええええええええええええ!」
断末魔に似た叫び声を上げる彼女。
しかし舐める行為は止めない。
まるで今まで彼女が人のことを舐めていた分だけ舐めているように。
そして彼女が舐められた箇所は、まるで硫酸を浴びたように溶け出していった。
「あぁぁぁあああああああああああああつつつつつつっつつつついぃぃいいいいいいいいいいいいいいい!」
一気に死なないように、徐々に、徐々に、蝕ませていく。
言いようもない臭気とただれた皮膚を見ていると吐き気を催すが、何か出るようなモノは僕の体内には無い。
地獄だ。
単純にそう思った。
「見ないでくれ! 見ないでくれ! ぁぁぁぁああああああああああああああああ!」
彼女がそう叫んだ時、急に彼女は動き出し、黒い机の上にあった硫酸の瓶を手に取った。
「体が勝手にぃぃいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい!」
でもきっと、あの硫酸の瓶を浴びれば死ねるんだ、と思って見ることしかできずにいると、彼女は硫酸の瓶を口と鼻の間に掛け始めた。
硫酸の瓶からは瓶のサイズ以上の硫酸が溢れ出る。
いくら硫酸が流れ落ちても、どんどん沸いてくる。
「あばあばばばばばばばああああああばばばばばばばああああああああああああああああばばばばばあああああああああ!」
彼女は硫酸で溶けるというよりも、硫酸で窒息死するように死んでいった。
そしてやっと彼女は砂状になっていき、空間も、ゾンビのような人間たちも風化して、元の真っ白い空間に戻った。
戻った瞬間に陽菜が、
「おぉぉおおおおおおおおおおおおぇぇぇぇぇええええええええ!」
と叫んだ。
勿論何も出していないけども、陽菜はその場に跪き、うなだれた。
今まで見た自殺というか、もはやこれはもう自殺なんかじゃない。
一体何なんだ、この部屋は。
いや忘れよう。
こんな死に方はすぐに忘れよう。
僕は陽菜の背中をさすりながら、ゆっくり、ゆっくりと、
「大丈夫、大丈夫だから、陽菜、落ち着いて」
と、ずっと言っていた。
・【15 おびき寄せる】
・
一人の女子生徒が入ってきた。
自殺室はまた一変し、前回のような人間が多い雑踏の光景になった。
陽菜はすぐさま平坦に《あーっ》と声を出したと思ったら、こんなことを言った。
《入室と同時に声に膜が張るよな。便利というかなんというか》
《確かに。来る前は別に、普通に会話できるもんね》
《この膜が張っている感じは何か嫌なんだよな。自分がいないみたいで》
《でも実際僕には見えているから大丈夫だよ》
僕が普通にそう言っただけなのに、何だか陽菜は少し嬉しそうに笑ってから、
《そうだな、信太に見えているだけで十分かもなっ》
何だかその表情にドギマギしてしまった。
何だろう、この感情。
不思議なような、新しいような、懐かしいような。
そんなことを考えていると陽菜が、
《それにしてもまた人混みって、爆竹?》
《そんなことは無いんじゃないかな、まあ様子を見てみよう》
《ただ全員で打ち上げ花火を見るだけならいいんだけどな》
《河川敷とかならまだしも、ここ都会っぽいから違うんじゃないかな》
と僕がツッコむと、まるで陽菜が僕にツッコミを入れているようなテンションで僕の肩を叩きながら、
《まあ確かにそうだなぁ! 都会で打ち上げ花火は危ないからな! ハッハッハ!》
と、やけに快活に笑った。
何がそこまでおかしいのかはちょっと分からなかったけども、楽しそうで何よりだ。
僕と陽菜はこんな他愛も無い会話をすることがどんどん多くなっていった。
だけど僕と陽菜の会話が増える度に、溝渕さんの言葉数は減っていった。
実際、陽菜が溝渕さんのことをお客さん扱いしているから会話する機会自体が少ないだけなんだけども。
溝渕さんの表情を見ていると、こっちの会話を聞いて優しく笑っていると思ったら、急に思い詰めたような表情をしている時があって。
ふと溝渕さんが言っていた『直子は俺のことを憎んでいたのでは』というような言葉が脳内で再生される。
溝渕さんは何か僕と陽菜に文句があるのだろうか。
いや確かに陽菜から一方的にお客さん扱いされたら嫌かもしれない。突っぱねられている感じもするし。
でもそんなことで嫌な気持ちになるような人じゃないだろうと思うこともあって。
いやいやそんなことより今はまずこの女子生徒の動きを注視しよう。
さて、そろそろ女子生徒の言動も何か出てくる頃だろうと思っているんだけども、この女子生徒は反応が薄い。
まだ一言も喋っていない。
でも何も動じていないわけでは無さそうだ。
何故なら何か思案しているような面持ちはしているからだ。
そしてついにこの女子生徒は口を開いた。
「何で地元だし?」
どうやらここは地元の風景らしい。
今回は思い出の中で何かあったパターンだ。
胸糞の悪い話じゃないように、と心の中で願ったが、公衆便所のことを思い出し、きっと良くない話なんだろうな、と思ってしまった。
そんな僕は、きっと不安そうな顔をしていたのだろう。
僕の顔を覗き込んで陽菜が、
《どうしたの? これヤバイ感じなの?》
《自分の地元が、思い出が出てくる時に良いパターンは無かったかな》
と僕が言ったその時だった。
部屋の真ん中に机が出現した。
その机の形状は奈々江さんの時とは全然違った。
奈々江さんの時の机は、真っ白い色に丸い机だった。
しかしこの女子生徒の前に出現した机は、真っ黒い色に角が鋭い三角形の机。
さらにその机の上にはラベル付きの液体が入った瓶。
陽菜はすぐさまそのラベルを見に行き、
《これ硫酸だ! ヤバイ!》
硫酸。
硫酸を被って死ぬなんて、どう考えても苦しむしかない。
ということはこの女子生徒は良くないことをしていたことが確定した、と言っていいだろう。
だから、とりあえず僕は陽菜にそのことを伝えた。
《苦しんで死ぬ可能性が高い時は、きっとこの女子生徒は良くないことをしていたんだと思う》
《何それ! 腹立つな! すぐに出てってやる!》
《いやちょっと待って、陽菜。もう少し様子を見よう。周りの光景は変わることがあるんだって……そうですよね、溝渕さん》
そう言って僕はまだ座っている溝渕さんに同意を求めると、溝渕さんは小さく頷きながら、
《そうだ。俺の経験上、これから周りの風景は変わっていくだろう。まるで周りの風景だけが動いていくようにな》
陽菜は今にも飛び出しそうな雰囲気から、一旦落ち着いた感じになって、とりあえずは傍観する流れになった。
「何? 帰ってこれたの? でもあの黒い机何? あんなんあったっけ?」
女子生徒も黒い机に近付き、ラベルを確認した。
「硫酸? 何これ? これで死ねってこと? いやいや、意味分かんないし。ここ中央通りじゃないの?」
何だか話の進みも遅そうだし、そろそろ出ないといけないかなと思っていると、その女子生徒は急に大きな声を上げた。
「誰だ! 急に男が出てきたし!」
痺れを切らした溝渕さんが出てきたのかな、と思ったら、存在がクリアになっているのは僕だった。
何で、念じていないのに、いやでもこんな経験は一度ある。
奈々江さんの時だ。
あの時は念じていなくても僕が出現した。
じゃあこの彼女は僕に何か用がある人なのか?
《信太! 急にどうしたんだよ! まだ見ていく流れだっただろ!》
「たまにこういうことがあるんだよ。念じていないのに出てしまうパターンが」
《何だそれ! いろいろあって分かんないな! この空間は! じゃあアタシも今行く! ……あれ? 何か出られない!》
「えっ? その膜から? じゃあ本当に僕だけなんだっ」
と声を出しながら、溝渕さんのほうも見ると、溝渕さんもコクンと頷き、どうやら溝渕さんも出られないようだった。
挙動不審のようにキョロキョロしていると、彼女が喋り出した。
「いや誰と話してんの? というか誰? 地元のダチじゃないしさ、普通このタイミングなら地元のダチじゃね?」
……あれ? 僕に関係している人じゃない?
それなのに僕が出現してしまった、って、一体どういうことなのだろうか。
もしかしたら逆に、僕がこの彼女に関係しているのか。
いやいや全然見覚えが無い……わけでもない?
何故かどこかで見たことあるような。
僕は割と記憶がいいほうだと自負している。
そんな僕がどこかで見たことあるのならば、僕は見たことあるんだ。
そもそもこの彼女がいったこの場所”中央通り”は、中学三年生の時に何だか行ったことがあるような。
古本を探して大きな街へ行った時、こんな場所があったような。
と、じっくり考えたいんだけども、彼女はどんどん喋ってくる。
「いやマジ誰? イミフなんですけど。ここ中央通り? それとも自殺室? どっちなん?」
ここはまず彼女の質問に答えないといけないな。
「僕は自殺室を司る死神です。ここは自殺室です。この自殺室は貴方の心の中とリンクして、死ぬ時のシチュエーションが決まります。貴方はここ、中央通りに強い思い出があるのでしょう」
「死神て。こんな普通の男子生徒みたいな感じが? ウケんね。何か死にきれなかったガキみたいな感じじゃん」
多分偶然だろうけども、死にきれなかったガキは合っている。
でもその説明は省いていいだろう。
僕は続ける。
「この自殺室では自分が最も死にたくない、屈辱的な死に方をしなければいけません。貴方は自分の容姿が気に入っているのでしょう。だからこの硫酸を被って死ななければならないのです」
「マジかよ……硫酸ってドロドロにただれるヤツだろ? そんなん絶対嫌だし。私は結構今盛れてるし」
「だからこそです。その容姿を失うような死に方をしないといけないんです」
「クソみてぇな罰だし。罰を受けるべきはオマエのような凡人顔の男だし。つまんねぇ顔、硫酸で溶かして整えろや」
ヘラヘラ笑って人を見下しているような言い方。
僕はこの空間を理解している側だから、正直そんなに気にならなかったけども、陽菜が叫び声を上げた。
《何言ってんだよ! 信太が優しく言ってんだから従えよ! バカ!》
「まあまあ」
と僕が陽菜のほうを見ながら声を出したところで彼女が、
「他に誰かいるん? 死神って群れてるんだ。ウケんね。連れション死神とかあるんだ」
卑しく笑う彼女に僕はハッキリと言うことにした。
「何でそんなに余裕なのかは分かりませんが、自分で死のうとしないと、最も苦しむ方法で死なないといけなくなるんです。だからまだ意識があるうちに、硫酸をかぶって自殺して下さい」
「そんなんするわけねぇじゃん、誰がオマエの言うこと鵜呑みにするかよ。というかその制服、ウチの学校の制服じゃん。オマエ、もしかすると自殺室へ先に入った生徒か? 普通に死なずに生きてるし。じゃあ私も生きるから安心するし」
どうやら勘は良いみたいだ。
仕方ない、ちゃんと説明するか。
「この自殺室は生きたい人は死んで、死にたい人は生きてしまう部屋。確かに僕は死神ではなくて、この自殺室で死ねなかった人間です」
「嘘ついてたし! というか死にたいってマ? 死にたいヤツは勝手に死ねばいいし! ウケんね! マジで!」
「僕の話はこの際どうでもいいじゃないですか。今は貴方の話が重要です。この状況、何か見覚えがあるんじゃないんですか?」
と僕が言ったところで、彼女は何かに気付いたような表情をしながら、
「この状況に見覚え?」
と言った。
何に気付いたのだろうか。
やっぱり僕と彼女はどこかに接点があったのだろうか。
いやでもイマイチ思い出せない。
ちょっとすれ違ったくらいなんじゃないかな。
でもそれだと学校にいた生徒はほぼ全員そうなるだろうし。
それこそ、何か状況に関係しているのか、とか思っていると、彼女はこう言った。
「なるほどね、じゃあオマエにこれをやってやればいいんじゃね? そうしたら仲間も出てくるんじゃね?」
そう言って悪知恵が働いている人のような笑みを浮かべた。
一体何をやるんだろうと思って、身構えていると、
「ねぇ、お兄さぁん。ちょっと私と楽しいことしないぃ?」
急に甘ったるい声を上げて、ブリッコのように僕へ近付いてきた彼女。
何だこれ。
何なんだこれ。
めちゃくちゃ既視感がある。
その時に僕は思い出してしまい、思わず声を出した。
「あの時の逆ナンの人だ!」
その言葉に一瞬ビクついた彼女は、ブリッコのような雰囲気を止め、少し嫌悪感のある目つきでこちらを見ながら、
「えっ、アンタ一回私に引っかかったことあんの? マジウケるしぃ」
「いや、断ったというか、しつこかったから逃げ出したけども」
「あーっ、じゃあ引っかかってないほうのヤツかぁ。確かに写真に残ってねぇと思うしなぁ」
僕は浮かんだことを率直に聞くことにした。
自分の中で激しく嫌悪感を抱き始めているので、自然と言葉もぶっきらぼうになる。
「そうやって逆ナンして遊んでいたのか?」
「そうそう、めちゃくちゃ遊んでやってたしぃ、どう? 慈善事業っしょ」
そう怪しくニタァと笑った彼女。
これは違う。
ただ二人で何かしていただけではない、何故なら
「仲間も出てくるってさっき言っていたけども、君に逆ナンされてついていったら、その部屋に君の仲間がいてボコボコにされるってことだな」
「ボコボコて。ウケるし。暴力だけじゃねぇし。まあなんというか、蹂躙プレイって感じぃ?」
暴力だけじゃない、ということは、暴力だってあるということだ。
さらに蹂躙だなんて、多分想像もしたくないようなことをするんだろうな。
だから想像なんてする必要無い。
する必要があることと言えば……と、改めて冷静な気持ちを自分の中に入れてから、
「今すぐ硫酸で死んで下さい。貴方はきっと醜い死に方をしてしまうだろうから」
「醜いのはあんな蹂躙されても女子が裸になったら反応してしまう男子のほうじゃね? ハハッ」
「何の話か分かりませんが、今すぐ自殺して下さい」
「嫌だし。自殺室でも生きる道があるって分かったから、このまま生きてやるし。そうしたらマジで遊んでやってもいいけどぉ? 悪くない取引じゃねぇ?」
僕は正直、醜い死に方をすればいいと思ってしまっている。
だからもうこれ以上、何か言うことは止めようかなと思い始めてきた。
チラリと溝渕さんのほうを見れば、大きな溜息をついて、呆れた表情をし、陽菜のほうを見れば顔まで真っ赤にして怒っている。
いや陽菜が何でそんなに怒っているかは分からないけども、もう今回はこのまま行くしかないみたいだ。
溝渕さんは正直分からないけども、陽菜はどう考えても、あの膜を破ろうとしても破れないみたいだし。
「じゃあ君は死ぬ気が無いんだね。じゃあそのまま自分が思うままに動いているといいよ」
「男なんかに命令されなくてもそうするし。というわけで! お兄さぁん、私と一緒に楽しいことしようよぉ?」
また甘ったるい声を出しているが、最初と違って邪悪に満ちている。
僕はただただ黙って立っていると、周りの光景が動き出した。
まるでプロジェクションマッピングのように、周りだけが動いて、真ん中の黒い机はそのまま。
その光景を見た彼女は、
「うわっ、進みだしたし! ていうかマジで私たちのアジトに向かってる感じじゃん! ウケんね! オマエ、行く気無いみたいな顔しといて私についてく気満々だったんじゃん! アソコは正直じゃん! ハハッ!」
あくまでこれは彼女の物語だ。
僕の気持ちは作用せず、彼女の物語が進行している。
でも少し気になってはいる。
果たして仲間はいるのか。
一体どんな自殺が待っているのか。
依然、プロジェクションマッピングのような移動は行なわれている。
勿論、自分たちが動いているわけじゃないので、歩いてはいない。
でもまるで歩いているような錯覚を受けてしまうのは、きっとこの風と香りのせいだ。
歩行している時のような向かい風を浴びて、雑居ビル群のところへやって来ると、カビくさい香りがした。
そして風景は階段を上がり始めて、とあるアパートの一室に来た。
「じゃあここで楽しいこといぃっぱぁいぃしましょうねぇ、お兄さぁん」
物語の中に入っているような彼女はニッコリと微笑んだ。
その時だった。
今まではあくまで映像を投影しているような感じだったのに、壁に、本物の扉が現れたのだ。
その扉の登場に彼女も一瞬怯む。
「何この扉、全然違うし」
その扉は鉄の扉で、全体的に腐食していた。
まるで硫酸をぶちまけられた扉のように。
あまりの禍々しさに、言葉を失う僕たち。
彼女は急に後ずさりし始めた刹那、彼女はその場に尻もちをついた。
腰が抜けたのかな、と思っていると、彼女は声を震わせながらこう言った。
「うまく動けないし……何これ……どういうこと……」
彼女が震える度に、黒い机が彼女の揺れのせいで(というように)動いていき、ついには黒い机が彼女の頭上あたりまでやって来た。当然、黒い机に乗っている硫酸の瓶も揺れている。
このタイミング。
この場所。
そうか、彼女の体が大きくブレたその時に、上にある硫酸の瓶が倒れて、彼女に偶然のように降り注いで死ぬんだ。
僕はそう思っていると、鉄の扉が開く音がした。
きっとここで何か驚かすようなモノが出てきて、そして彼女は体を強く揺らすんだと思っているので、何が出てきても驚かないつもりでいたが、僕は鉄の扉から出てきた存在に心臓が止まるかと思った。
その存在は、硫酸でただれ、ゾンビのような見た目になった人間たちなんだけども、全員目玉と両腕が無かった。
そんな人間が徐々に彼女に近付いていく。
「嫌だし……助けて! おい! オマエ! 助けてくれぇぇぇええええええええええええ!」
そう言って僕のほうを見そうだけども、彼女は首を動かせなくなっていることがなんとなく分かった。
「助けろよ! 男だろ! ……うわぁぁぁあああ! 何だよ! ここで普通の人間ってどういうことだよ!」
えっ、と思いながら、陽菜のほうを見ると、なんと陽菜の見た目が一段階クリアになっていた。
さらに多分この彼女は気付いていないと思うけども、後方で体育座りをしていた溝渕さんも姿を現した状態になっている。
その時に気付いた。
僕たちが彼女を見る側なんだと。
この部屋に彼女が僕を連れてきたんじゃなくて、僕が彼女をこの部屋に連れてきたんだ。
そして僕の仲間がいる陽菜と溝渕さんの部屋にやって来て、彼女がいわゆる蹂躙されていくところを見るんだ。
嫌だ。
見たくない。
そう思った時に気付いた。
僕は体が動けなくなっていた。
それはどうやら陽菜も一緒らしく、全然動いていない。
瞼も閉じることはできず、僕たちはこの光景を見るしかないんだ。
果たしてこの光景とは。
彼女に近付いていくゾンビのような人間たちは、徐々にスピードを上げ、ゼロ距離になったところで、ゾンビのような人間たちはしゃがんだり、倒れたりして、彼女へ覆い被さっていった。
自分の体についた硫酸をこすりつけるのかな、と思っていると、そのゾンビのような人間たちはなんと彼女の体中を舐め始めたのだ。
「やめてくれぇぇぇぇえええええええええええええええええええええええええ!」
断末魔に似た叫び声を上げる彼女。
しかし舐める行為は止めない。
まるで今まで彼女が人のことを舐めていた分だけ舐めているように。
そして彼女が舐められた箇所は、まるで硫酸を浴びたように溶け出していった。
「あぁぁぁあああああああああああああつつつつつつっつつつついぃぃいいいいいいいいいいいいいいい!」
一気に死なないように、徐々に、徐々に、蝕ませていく。
言いようもない臭気とただれた皮膚を見ていると吐き気を催すが、何か出るようなモノは僕の体内には無い。
地獄だ。
単純にそう思った。
「見ないでくれ! 見ないでくれ! ぁぁぁぁああああああああああああああああ!」
彼女がそう叫んだ時、急に彼女は動き出し、黒い机の上にあった硫酸の瓶を手に取った。
「体が勝手にぃぃいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい!」
でもきっと、あの硫酸の瓶を浴びれば死ねるんだ、と思って見ることしかできずにいると、彼女は硫酸の瓶を口と鼻の間に掛け始めた。
硫酸の瓶からは瓶のサイズ以上の硫酸が溢れ出る。
いくら硫酸が流れ落ちても、どんどん沸いてくる。
「あばあばばばばばばばああああああばばばばばばばああああああああああああああああばばばばばあああああああああ!」
彼女は硫酸で溶けるというよりも、硫酸で窒息死するように死んでいった。
そしてやっと彼女は砂状になっていき、空間も、ゾンビのような人間たちも風化して、元の真っ白い空間に戻った。
戻った瞬間に陽菜が、
「おぉぉおおおおおおおおおおおおぇぇぇぇぇええええええええ!」
と叫んだ。
勿論何も出していないけども、陽菜はその場に跪き、うなだれた。
今まで見た自殺というか、もはやこれはもう自殺なんかじゃない。
一体何なんだ、この部屋は。
いや忘れよう。
こんな死に方はすぐに忘れよう。
僕は陽菜の背中をさすりながら、ゆっくり、ゆっくりと、
「大丈夫、大丈夫だから、陽菜、落ち着いて」
と、ずっと言っていた。