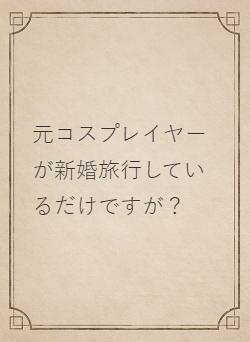・
・【12 他愛も無い会話】
・
また陽菜が僕に話し掛けてきた。
絶対全く意味の無い会話に決まっている。
「私さ、まだ未成年だけどもお酒飲んだことあるんだ。凄すぎるだろ、凄すぎるスキルだろ」
そう、えっへんといった感じにふんぞり返ってきた陽菜。
いや、
「全然ダメだよ、そういうことは人に言って自慢することももっとダメだよ」
「でも正月だったから、正月は無礼講だろ? それに信太だって親戚の集まりで一回くらいビールを味見したことくらいあるだろ?」
「いや僕に親戚の集まりとかないから」
そう、僕には親戚なんてモノは無い。
だからここを今から陽菜に掘り下げられたら面倒だなと思っていると、陽菜はこう言った。
「じゃあこっから私のターン! ビールって不味いんだぜ!」
良かった、自分の言いたいことを一方的に喋る人で。いや本来会話としては良くないけども。
「結局お酒って不味いんだと思う!」
「いやでも大人は喜んで飲んでいるから美味しいんじゃないのかな」
「でもさ! ワインってあるじゃん! ワインは知ってるっ?」
「知ってるよ、味は知らないけどもモノはちゃんと知っているから」
「あれって結局ぶどうジュースの部分が美味しいんだと思うんだよね! 果汁というかさ!」
何か熱弁を振るっている。
相槌を打つことも正直面倒だけども、まあこれで陽菜が楽しくなって生きたくなって死んでくれたら、また平穏が訪れるからここは我慢だ。
いや本当は死にたくて、死ねない平穏なんて本当はいらないんだけども。
「まあワインの味はよく知らないけども、ぶどうの果汁が美味しいことは分かるよ」
と一応答えておくと、陽菜は輪をかけてデカい声で、
「結局ワインってぶどうジュースにアルコールを入れたもんなんだよ! 絶対に!」
「そんな単純な足し算ではないと思うけども、近いは近いと思うよ」
ここを反論すると話が長くなりそうなので、一応同意はしておく。
陽菜は楽しそうに続ける。いやもうコイツ、すぐに死ぬんじゃないの?
「で! 信太はさぁ! アルコールランプのアルコールを飲もうと思ったことあるぅっ?」
「無いよ、絶対飲まないよ、あんなもの」
「そうなんだよ! アルコールは美味しくないんだよ! 美味しくないモノをぶどうジュースに入れて美味しく飲んだらもはやぶどうジュースが美味しいだけじゃん!」
「いやアルコールランプのアルコールとお酒のアルコールって違うんじゃないの?」
「元素は一緒でしょ!」
まあ確かに言いたいことは分かった。
ウォッカとかアルコールそのものだみたいな言い方もするし、全くその論が正しいとは思わないけども、近いということは確かなのかもしれない。
「つまり、陽菜はどう考えているの?」
「お酒はアルコールが邪魔なんじゃないかって! そしてアルコールなんていらないんじゃないかって!」
「でも大人は酔えるからいいって言う人もいるじゃないか」
「だからそれはもうただの麻薬なんだよ! 合法麻薬! 取り締まるべきだと思う!」
「陽菜はお酒に酔った人に何か暴力を振るわれたことでもあるのっ?」
「一切無い! でもそういうことが起きる前に取り締まるべきだぁ!」
そう言って拳を強く握った陽菜。
何でこんな熱量が出るんだと思って、ちょっと吹き出してしまうと、
「えっ? 面白すぎて生きたいと思ったっ? あちゃー、先越されちゃったぜ!」
と言ってから、てへぺろをした。
いやいや全然面白くはないけども、何か勢いがすごいなと思ってしまっただけだけども。
でも、
「まあ、勢いは面白かったよ。勢いだけだけども」
「やっぱりね、漫才の大会でも一回戦は声が出てないと落とされるからね」
「いやあんまり褒めたつもりでそう言ったわけじゃないけども」
「でも実際、まずは勢いが無いと、元気が無いと一回戦で落とされるから」
「そんな漫才の大会の定石みたいなこと言われても、全然褒めていなかったから僕」
と冷たく言い放つように言っているんだけども、陽菜は何かめちゃくちゃ嬉しそうに、
「褒められるって嬉しいし! 何これー! 抱かれるのー!」
と言いながらおでこに手を当てて、仰け反りながら笑っている。
ダメだ、コイツ、電波すぎる。
どうしようも無いヤツだ。
こんなヤツとずっと一緒なんて気が重い。
こんなんじゃなおさら死ねないと思う。
もうどうすればいいんだ……と思いつつも、何だか懐かしい気持ちにもなっていた。
陽菜はまるで光莉みたいだから。
光莉もこんな感じの一方的な人間だった。
特に初期はこんな感じだった。
まるで一から光莉と会話しているような感覚。
いや光莉はもっとまともだったような気がするけども。
・【12 他愛も無い会話】
・
また陽菜が僕に話し掛けてきた。
絶対全く意味の無い会話に決まっている。
「私さ、まだ未成年だけどもお酒飲んだことあるんだ。凄すぎるだろ、凄すぎるスキルだろ」
そう、えっへんといった感じにふんぞり返ってきた陽菜。
いや、
「全然ダメだよ、そういうことは人に言って自慢することももっとダメだよ」
「でも正月だったから、正月は無礼講だろ? それに信太だって親戚の集まりで一回くらいビールを味見したことくらいあるだろ?」
「いや僕に親戚の集まりとかないから」
そう、僕には親戚なんてモノは無い。
だからここを今から陽菜に掘り下げられたら面倒だなと思っていると、陽菜はこう言った。
「じゃあこっから私のターン! ビールって不味いんだぜ!」
良かった、自分の言いたいことを一方的に喋る人で。いや本来会話としては良くないけども。
「結局お酒って不味いんだと思う!」
「いやでも大人は喜んで飲んでいるから美味しいんじゃないのかな」
「でもさ! ワインってあるじゃん! ワインは知ってるっ?」
「知ってるよ、味は知らないけどもモノはちゃんと知っているから」
「あれって結局ぶどうジュースの部分が美味しいんだと思うんだよね! 果汁というかさ!」
何か熱弁を振るっている。
相槌を打つことも正直面倒だけども、まあこれで陽菜が楽しくなって生きたくなって死んでくれたら、また平穏が訪れるからここは我慢だ。
いや本当は死にたくて、死ねない平穏なんて本当はいらないんだけども。
「まあワインの味はよく知らないけども、ぶどうの果汁が美味しいことは分かるよ」
と一応答えておくと、陽菜は輪をかけてデカい声で、
「結局ワインってぶどうジュースにアルコールを入れたもんなんだよ! 絶対に!」
「そんな単純な足し算ではないと思うけども、近いは近いと思うよ」
ここを反論すると話が長くなりそうなので、一応同意はしておく。
陽菜は楽しそうに続ける。いやもうコイツ、すぐに死ぬんじゃないの?
「で! 信太はさぁ! アルコールランプのアルコールを飲もうと思ったことあるぅっ?」
「無いよ、絶対飲まないよ、あんなもの」
「そうなんだよ! アルコールは美味しくないんだよ! 美味しくないモノをぶどうジュースに入れて美味しく飲んだらもはやぶどうジュースが美味しいだけじゃん!」
「いやアルコールランプのアルコールとお酒のアルコールって違うんじゃないの?」
「元素は一緒でしょ!」
まあ確かに言いたいことは分かった。
ウォッカとかアルコールそのものだみたいな言い方もするし、全くその論が正しいとは思わないけども、近いということは確かなのかもしれない。
「つまり、陽菜はどう考えているの?」
「お酒はアルコールが邪魔なんじゃないかって! そしてアルコールなんていらないんじゃないかって!」
「でも大人は酔えるからいいって言う人もいるじゃないか」
「だからそれはもうただの麻薬なんだよ! 合法麻薬! 取り締まるべきだと思う!」
「陽菜はお酒に酔った人に何か暴力を振るわれたことでもあるのっ?」
「一切無い! でもそういうことが起きる前に取り締まるべきだぁ!」
そう言って拳を強く握った陽菜。
何でこんな熱量が出るんだと思って、ちょっと吹き出してしまうと、
「えっ? 面白すぎて生きたいと思ったっ? あちゃー、先越されちゃったぜ!」
と言ってから、てへぺろをした。
いやいや全然面白くはないけども、何か勢いがすごいなと思ってしまっただけだけども。
でも、
「まあ、勢いは面白かったよ。勢いだけだけども」
「やっぱりね、漫才の大会でも一回戦は声が出てないと落とされるからね」
「いやあんまり褒めたつもりでそう言ったわけじゃないけども」
「でも実際、まずは勢いが無いと、元気が無いと一回戦で落とされるから」
「そんな漫才の大会の定石みたいなこと言われても、全然褒めていなかったから僕」
と冷たく言い放つように言っているんだけども、陽菜は何かめちゃくちゃ嬉しそうに、
「褒められるって嬉しいし! 何これー! 抱かれるのー!」
と言いながらおでこに手を当てて、仰け反りながら笑っている。
ダメだ、コイツ、電波すぎる。
どうしようも無いヤツだ。
こんなヤツとずっと一緒なんて気が重い。
こんなんじゃなおさら死ねないと思う。
もうどうすればいいんだ……と思いつつも、何だか懐かしい気持ちにもなっていた。
陽菜はまるで光莉みたいだから。
光莉もこんな感じの一方的な人間だった。
特に初期はこんな感じだった。
まるで一から光莉と会話しているような感覚。
いや光莉はもっとまともだったような気がするけども。