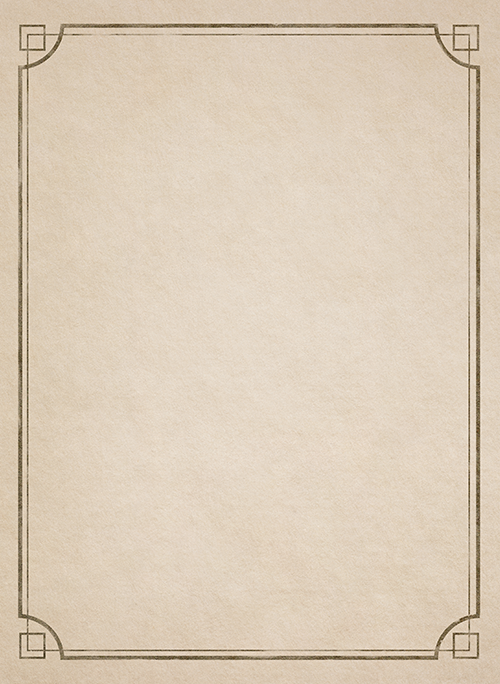第五話
私は手芸部の部室にいた。
私とハナちゃんしか、人がない手芸部。
そこで私とハナちゃんは、ビーズで刺繍を作りながら、おしゃべりをしている。
ハナちゃんの手元にあるのは、ヒマワリのような刺繍だ。
私の手元にあるのは、赤いバラのように見える刺繍だ。
どちらも、ビーズを布に縫い付けることで、そう見えるようにした刺繍。
そして、手芸部としての作品だ。
「ええーっ。アイリちゃん、クラス委員をやるの!」
ハナちゃんが驚いたように私にいった。
「それで、藤原さんと一緒にクラス委員をすることになったの。」
「カリンちゃん?」
「そう。」
「ふーん。仲良くなれるといいね!」
ハナちゃんはニコニコとした様子でいった。
「そうね。今まで藤原さんとは話したことが無いから、仲良くなれればいいんだけど。」
「大丈夫だよ。アイリちゃんなら、誰とでも仲良くなれると思うよ。」
「頑張ってみるわ。」
私は、先生から話された真の目的については話さなかった。
それを周囲に言いふらすと、カリンちゃんとは仲良くなれない気がした。
先生から言われて、友達をやっている。
それは良くないことだ、と私は判断する。
「クラス委員って、日ごろ、何をやっているのかなぁ?」
ハナちゃんは、そういって考え始めた。
私も詳しい説明は、後日なのだ。
実はまだ、良く分かっていない。
「うーん。なんだっけ。そういえば、朝のホームルームで号令をかけているのクラス委員だっけ。」
ポツリポツリと思い出しながら、ハナちゃんがクラス委員のやっていることを出していく。
「そうね。でも、私も実は、クラス委員の仕事、詳しいことをまだ、聞いていないの。」
「へっー、じゃあ、良く分かってないけど、クラス委員をするの?大変だね。」
ハナちゃんは、まるで自分のことかのように、困っている表情を浮かべている。
「大丈夫、詳しいことは今度、先生から聞くことになっているの。」
「あっ、そうなんだ。じゃあ、安心だね。」
そう言って、ハナちゃんの表情が明るくなる。
そんな可愛い友達の様子に、私は心がほっこりした。
私は、その後もハナちゃんと話しながら、自分のことも考える。
まず、友達のハナちゃんや、ヒナコちゃんとの関係は、クラス委員になっても特に変わりないだろう。
では、それ以外の生徒から、クラス委員となった私が、どう見られるか。
…たぶん、これまでと変わらない。
私がクラス委員になっても、大多数の生徒が、『へっー、そうなんだ。』と思うだけに違いない。
だとすれば、やっぱり問題は、カリンちゃんとうまく関係を築けるか、なのだ。
ハナちゃんと話ながら、私は思索に耽っていた。
そして、その手は延々とビーズ刺繍を作成している。
平和なひと時。
そんな心地の良い時間が過ぎていった。
そして、気が付くと、下校を告げるチャイムが校内に響いた。
「あっ、もう部活も終わりだね。」
「そうね。片付けましょうか。」
私とハナちゃんはそう言って、作業をキリの良いところで終える。
私とハナちゃんは、それぞれの作業台の上に散らばったビーズや布、針などを丁寧に片付け始めた。
ハナちゃんは小さな声で鼻歌を歌いながら、カラフルなビーズを種類ごとに小さな容器に分けていく。
上機嫌で片付けを行っている姿には、どこか子供っぽさがある。
そんなハナちゃんを私は、愛らしく思えた。
「ねえ、アイリちゃん。今日、刺繍作業がうまく進んだんだよ。」
ハナちゃんが突然話しかけてきた。
「ハナちゃんのヒマワリの刺繍ね?」
「そう!あと、ちょっとで完成なんだよ。」
「それは楽しみね。」
確かに、ハナちゃんの作品は彼女らしい明るさが感じられてとても良い。
完成まで、あと少し。
「アイリちゃんのも、あと少しだよね。」
「そうね。もう少し。」
私たちは、そんな会話をしながら、部室の片付けを続ける。
私は効率よく作業を進めながら、部室を見る。
棚の上に置かれている他の部員たちの作品。
少し埃のたまった棚。
そして窓から差し込む夕陽。
放課後という感じがした。
「あ!アイリちゃん。これどこから出したんだっけ?」
ハナちゃんが手に持っていたのは、一番、太い刺繍糸だった。
ああ、でも。
それは。
「それは棚の一番上よ。でも、ハナちゃん、背は届く?」
「うーん、ちょっと届かないかも…」
ハナちゃんが困ったみたいにじっと、棚の上を見た。
「じゃあ、私がしまっておくわ。」
私は、ハナちゃんから刺繍糸を受け取った。
そして、その刺繍糸を棚の上から取り出したときと同じように置いた。
「ありがとう!アイリちゃん。」
「いいえ。どういたしまして。」
そんなことをしていると、やがて片付けが終わる。
部室の鍵を閉める。
途中で、職員室へ鍵を預けてから、私たちは昇降口へと向かう。
私とハナちゃんは、廊下を進んでいた。
「明日は、陸上部に見学かー。」
廊下を進みながら、隣にいるハナちゃんが自由奔放な言葉を放つ。
「そうね。楽しみね。」
私はハナちゃんの言葉に頷く。
そして、前にもハナちゃんと一緒に、陸上部へ行ったことを思い出していた。
そう、あれは確か…。
新学期が始まって間もない頃だった。
ヒナコちゃんに誘われて、今回みたいに、見学に行ったのだ。
あの日も放課後。
私とハナちゃんは、陸上部の活動場所である校庭へと向かった。
校庭に着くと、すでに何人かの部員たちがウォーミングアップを始めていた。
その中にヒナコちゃんの姿も見えた。
彼女は私たちに気づくと、笑顔で手を振ってきた。
「アイリちゃん、ハナちゃん、来てくれたんだ!」
ヒナコちゃんの声には嬉しさが溢れていた。
しばらくすると、顧問の先生が現れ、本格的な練習が始まった。
短距離走、長距離走、そしてフィールド競技と、様々な種目の練習を見学させてもらった。
その中で、特に印象に残っているのは、ヒナコちゃんの走る姿だった。
陸上のユニフォームに身を包んだヒナコちゃんは、いつもの学校生活での姿とは全く違っていた。
真剣な表情で、全身の筋肉を駆使しながら走る姿は、まるで別人のようだった。
ハナちゃんは目を輝かせながら、友達の走る姿を見つめていた。
「すごいね、ヒナコちゃん。かっこいい!」
ハナちゃんの素直な感想を聞きながら、私は頷いた。
確かに、ヒナコちゃんの走りには人を惹きつける何かがあった。
それは単純な速さだけではなく、彼女の持つ強い意志のようなものが感じられた。
練習の合間に、ヒナコちゃんが私たちのところへ来た。
汗で髪が額に張り付き、息も荒かったが、その目は充実感に満ちていた。
その日の見学では、陸上部の雰囲気、部員たちの関係性、そしてヒナコちゃんの部活動での立ち位置が見えた。
そして明日、再び、私とハナちゃんは陸上部を見に行くことになった。
なんだかんだいって、ヒナコちゃんが所属しているので、見に行く機会はあるのだ。
私が思考を巡らせながら歩いていると、やがて、昇降口が見えてきた。
下駄箱。
ちらほらと生徒が見える。
彼らも部活を終えて、帰る途中に違いない。
「お疲れ!」
ヒナコちゃんの声だ。
部活を終えたらしい、彼女が私たちに声をかけてきていた。
ちょうど、同じタイミングで下駄箱に到着したらしい。
「お疲れ様、ヒナコちゃん。」
私は、ヒナコちゃんに話しかけた。
「ああ、アイリ。特に今日の練習は、いい汗をかいた気がしたんだよ!」
ヒナコちゃんは、私たちに何かを伝えたいように話してきた。
その様子を見ていると、陸上競技や陸上部への愛着が伝わってきた。
「へぇ、すごい!ヒナコちゃん。」
ハナちゃんが感心したように言う。
「ああ、明日は、一緒に練習しようぜ、ヒナ。」
「うん。分かった!」
ハナちゃんと、ヒナコちゃんが二人で話を続けていた。
二人の会話を邪魔しないように、私は聞き耳を立てながらついていく。
そして、私たちは昇降口にある下駄箱から自分たちの靴を取り出して、履き替えた。
私たちは、上履きから、学校指定のローファーへと履き替える。
そして、私たちは昇降口から歩き出した。
学校の校舎から出て、校門へ向けて歩き出す。
「しゅっぱつ!」
ハナちゃんが、元気よくそう言った。
「あはは、ハナ。これから、家へ帰るだけなのに、楽しそうだな。」
「えへへ。だって、一緒に帰るの楽しいんだもん。」
私たちは横に広がって歩いていた。
周囲にも私たちのような生徒がちらほらと見える。
これが青春みたいな。
そう、平和なひととき。
これから私たちは、学校周辺の何の変哲もない通学路を三人一緒に帰っていく。
私は、話し合っている二人の様子や、通り過ぎた学校の正門を見ながら、しみじみとそう思った。
「あれ?アイリちゃん?何かあった?」
ハナちゃんがこちらに聞いてきた。
「ああ、ごめんなさい。」
「アイリ、何かあったか?」
二人がこちらに聞いてきた。
正直、私が勝手にしみじみとした感情を抱いて、静かにしていただけなので、何もない。
「いえ。特に何もないわ。」
「ええっ?本当、アイリちゃん?なにか、悩んでいるように見えたけど。」
ハナちゃんは、私のことを気にかけているようだ。
いや、しかし、本当になんでもないのだ。
「そうね、でも、今日みたいな日が続くといいなぁ、と思ったのよ。」
私は無難な答えを述べた。
とりあえず、二人に心配させないように、と思ったのだ。
「あはは、アイリはそういう所あるからな。」
何か頷きながら、ヒナコちゃんが納得している。
その間も、私たちは通学路を進んでいた。
「あっ、そうだ、そうだ。聞いてよ、ヒナコちゃん!」
ふと、思い出したかのように。
ハナちゃんは、ヒナコちゃんへ唐突に別の話を始めた。
「ん?なんだ?」
「えっと…。」
ハナちゃんはヒナコちゃんに話しかけている。
ハナちゃんは、たぶん、あの話を話そうとしている。
それは、クラス委員の話だ、と私は思った。
私たちは、自然と歩くスピードを緩める。
ヒナコちゃんも、ハナちゃんがゆっくりと思い出すように話を始めたので、しっかりと話を聞こうとしている。
「アイリちゃんが、クラス委員になるの。」
「えっ?そうなのか、アイリ?」
ヒナコちゃんが私の方を向いた。
「ああ、それね。実は…」
私は少し間を置いた。
「さっき、部活が始まる前に担任の先生から言われたの。」
「それでさっき悩んでたのか!」
ヒナコちゃんは、勝手に思い込んでいる。
実際はそうではないのだけれど。
「…ちょっと、思う所はあるわ。」
私は、含みのある言い方でヒナコちゃんに答えた。
まあ、全てを説明するのは面倒なのだ。
「もう、なんだよ。それなら、早く言えよぉ!」
ヒナコちゃんらしい励ましの言葉だと、私は思った。
「ええ。でも、大丈夫。今回のクラス委員は二人らしいの。」
「へぇーそうなんだ。もう一人は誰なんだ?」
「藤原さんと一緒にやることになったわ。」
「藤原?あの、いつも一人でいる子?」
そう言って、ヒナコちゃんは思い出そうとしているようだ。
「カリンちゃん!いい子だと思うよ!」
これまで、話に入ってこなかったハナちゃんは隣でそう言った。
「へぇ、でも。面白い組み合わせだな。でも二人って、何か理由があるのか?」
ヒナコちゃんは、私に聞いてきた。
クラス委員が増員される理由を聞きたいようだった。
たしかに、これまでの話を聞くと、その理由は聞きたくなるだろう。
「詳しいことはまだ聞いていないの。これから説明があるみたい。」
私は適当に誤魔化した。
いつも、カリンちゃんが一人だから、私とカリンちゃんが友達になるために、クラス委員になった、とは言えない。
そもそも、その理由を話すと、カリンちゃんと友達になるって目的から遠ざかる気もするし。
「そっか。でも、アイリちゃんとカリンちゃんか…。」
ヒナコちゃんは、少し心配そうな表情を浮かべる。
「大丈夫。アイリちゃんなら大丈夫だよ!」
「そうかな。まあ、そうか。」
ヒナコちゃんは、どこか完全に納得してはないようだった。
しかし、ハナちゃんにそう言われて、しぶしぶ、納得したようだ。
「アイリ、なんかあったらすぐに相談してくれ!」
「もちろんよ。何かあったら助けてね。ヒナコちゃん。」
「私もだよ!」
「ハナちゃんもね。」
私たちは、そんな会話を交わしながら、夕暮れの街を歩いていた。
やがて、私と二人の帰り道が分かれる交差点に差し掛かった。
「じゃあ、今日はここまでね。また、明日。」
私は、ハナちゃんとヒナコちゃんにそういってから、手をふった。
「アイリちゃん、さよならー!」
「じゃあな、アイリ。」
手をブンブンと振っているハナちゃん。
その横で、クールにも見える様子のヒナコちゃん。
相変わらずな二人。
その姿を見て、ほっこりした。
私はそのまま、二人の姿が見えなくなるまで見送った。
そして、一人になった瞬間、私だけの空間が訪れる。
明日は今日よりも良くなればいいな。
そう心の底から私は願った
私は手芸部の部室にいた。
私とハナちゃんしか、人がない手芸部。
そこで私とハナちゃんは、ビーズで刺繍を作りながら、おしゃべりをしている。
ハナちゃんの手元にあるのは、ヒマワリのような刺繍だ。
私の手元にあるのは、赤いバラのように見える刺繍だ。
どちらも、ビーズを布に縫い付けることで、そう見えるようにした刺繍。
そして、手芸部としての作品だ。
「ええーっ。アイリちゃん、クラス委員をやるの!」
ハナちゃんが驚いたように私にいった。
「それで、藤原さんと一緒にクラス委員をすることになったの。」
「カリンちゃん?」
「そう。」
「ふーん。仲良くなれるといいね!」
ハナちゃんはニコニコとした様子でいった。
「そうね。今まで藤原さんとは話したことが無いから、仲良くなれればいいんだけど。」
「大丈夫だよ。アイリちゃんなら、誰とでも仲良くなれると思うよ。」
「頑張ってみるわ。」
私は、先生から話された真の目的については話さなかった。
それを周囲に言いふらすと、カリンちゃんとは仲良くなれない気がした。
先生から言われて、友達をやっている。
それは良くないことだ、と私は判断する。
「クラス委員って、日ごろ、何をやっているのかなぁ?」
ハナちゃんは、そういって考え始めた。
私も詳しい説明は、後日なのだ。
実はまだ、良く分かっていない。
「うーん。なんだっけ。そういえば、朝のホームルームで号令をかけているのクラス委員だっけ。」
ポツリポツリと思い出しながら、ハナちゃんがクラス委員のやっていることを出していく。
「そうね。でも、私も実は、クラス委員の仕事、詳しいことをまだ、聞いていないの。」
「へっー、じゃあ、良く分かってないけど、クラス委員をするの?大変だね。」
ハナちゃんは、まるで自分のことかのように、困っている表情を浮かべている。
「大丈夫、詳しいことは今度、先生から聞くことになっているの。」
「あっ、そうなんだ。じゃあ、安心だね。」
そう言って、ハナちゃんの表情が明るくなる。
そんな可愛い友達の様子に、私は心がほっこりした。
私は、その後もハナちゃんと話しながら、自分のことも考える。
まず、友達のハナちゃんや、ヒナコちゃんとの関係は、クラス委員になっても特に変わりないだろう。
では、それ以外の生徒から、クラス委員となった私が、どう見られるか。
…たぶん、これまでと変わらない。
私がクラス委員になっても、大多数の生徒が、『へっー、そうなんだ。』と思うだけに違いない。
だとすれば、やっぱり問題は、カリンちゃんとうまく関係を築けるか、なのだ。
ハナちゃんと話ながら、私は思索に耽っていた。
そして、その手は延々とビーズ刺繍を作成している。
平和なひと時。
そんな心地の良い時間が過ぎていった。
そして、気が付くと、下校を告げるチャイムが校内に響いた。
「あっ、もう部活も終わりだね。」
「そうね。片付けましょうか。」
私とハナちゃんはそう言って、作業をキリの良いところで終える。
私とハナちゃんは、それぞれの作業台の上に散らばったビーズや布、針などを丁寧に片付け始めた。
ハナちゃんは小さな声で鼻歌を歌いながら、カラフルなビーズを種類ごとに小さな容器に分けていく。
上機嫌で片付けを行っている姿には、どこか子供っぽさがある。
そんなハナちゃんを私は、愛らしく思えた。
「ねえ、アイリちゃん。今日、刺繍作業がうまく進んだんだよ。」
ハナちゃんが突然話しかけてきた。
「ハナちゃんのヒマワリの刺繍ね?」
「そう!あと、ちょっとで完成なんだよ。」
「それは楽しみね。」
確かに、ハナちゃんの作品は彼女らしい明るさが感じられてとても良い。
完成まで、あと少し。
「アイリちゃんのも、あと少しだよね。」
「そうね。もう少し。」
私たちは、そんな会話をしながら、部室の片付けを続ける。
私は効率よく作業を進めながら、部室を見る。
棚の上に置かれている他の部員たちの作品。
少し埃のたまった棚。
そして窓から差し込む夕陽。
放課後という感じがした。
「あ!アイリちゃん。これどこから出したんだっけ?」
ハナちゃんが手に持っていたのは、一番、太い刺繍糸だった。
ああ、でも。
それは。
「それは棚の一番上よ。でも、ハナちゃん、背は届く?」
「うーん、ちょっと届かないかも…」
ハナちゃんが困ったみたいにじっと、棚の上を見た。
「じゃあ、私がしまっておくわ。」
私は、ハナちゃんから刺繍糸を受け取った。
そして、その刺繍糸を棚の上から取り出したときと同じように置いた。
「ありがとう!アイリちゃん。」
「いいえ。どういたしまして。」
そんなことをしていると、やがて片付けが終わる。
部室の鍵を閉める。
途中で、職員室へ鍵を預けてから、私たちは昇降口へと向かう。
私とハナちゃんは、廊下を進んでいた。
「明日は、陸上部に見学かー。」
廊下を進みながら、隣にいるハナちゃんが自由奔放な言葉を放つ。
「そうね。楽しみね。」
私はハナちゃんの言葉に頷く。
そして、前にもハナちゃんと一緒に、陸上部へ行ったことを思い出していた。
そう、あれは確か…。
新学期が始まって間もない頃だった。
ヒナコちゃんに誘われて、今回みたいに、見学に行ったのだ。
あの日も放課後。
私とハナちゃんは、陸上部の活動場所である校庭へと向かった。
校庭に着くと、すでに何人かの部員たちがウォーミングアップを始めていた。
その中にヒナコちゃんの姿も見えた。
彼女は私たちに気づくと、笑顔で手を振ってきた。
「アイリちゃん、ハナちゃん、来てくれたんだ!」
ヒナコちゃんの声には嬉しさが溢れていた。
しばらくすると、顧問の先生が現れ、本格的な練習が始まった。
短距離走、長距離走、そしてフィールド競技と、様々な種目の練習を見学させてもらった。
その中で、特に印象に残っているのは、ヒナコちゃんの走る姿だった。
陸上のユニフォームに身を包んだヒナコちゃんは、いつもの学校生活での姿とは全く違っていた。
真剣な表情で、全身の筋肉を駆使しながら走る姿は、まるで別人のようだった。
ハナちゃんは目を輝かせながら、友達の走る姿を見つめていた。
「すごいね、ヒナコちゃん。かっこいい!」
ハナちゃんの素直な感想を聞きながら、私は頷いた。
確かに、ヒナコちゃんの走りには人を惹きつける何かがあった。
それは単純な速さだけではなく、彼女の持つ強い意志のようなものが感じられた。
練習の合間に、ヒナコちゃんが私たちのところへ来た。
汗で髪が額に張り付き、息も荒かったが、その目は充実感に満ちていた。
その日の見学では、陸上部の雰囲気、部員たちの関係性、そしてヒナコちゃんの部活動での立ち位置が見えた。
そして明日、再び、私とハナちゃんは陸上部を見に行くことになった。
なんだかんだいって、ヒナコちゃんが所属しているので、見に行く機会はあるのだ。
私が思考を巡らせながら歩いていると、やがて、昇降口が見えてきた。
下駄箱。
ちらほらと生徒が見える。
彼らも部活を終えて、帰る途中に違いない。
「お疲れ!」
ヒナコちゃんの声だ。
部活を終えたらしい、彼女が私たちに声をかけてきていた。
ちょうど、同じタイミングで下駄箱に到着したらしい。
「お疲れ様、ヒナコちゃん。」
私は、ヒナコちゃんに話しかけた。
「ああ、アイリ。特に今日の練習は、いい汗をかいた気がしたんだよ!」
ヒナコちゃんは、私たちに何かを伝えたいように話してきた。
その様子を見ていると、陸上競技や陸上部への愛着が伝わってきた。
「へぇ、すごい!ヒナコちゃん。」
ハナちゃんが感心したように言う。
「ああ、明日は、一緒に練習しようぜ、ヒナ。」
「うん。分かった!」
ハナちゃんと、ヒナコちゃんが二人で話を続けていた。
二人の会話を邪魔しないように、私は聞き耳を立てながらついていく。
そして、私たちは昇降口にある下駄箱から自分たちの靴を取り出して、履き替えた。
私たちは、上履きから、学校指定のローファーへと履き替える。
そして、私たちは昇降口から歩き出した。
学校の校舎から出て、校門へ向けて歩き出す。
「しゅっぱつ!」
ハナちゃんが、元気よくそう言った。
「あはは、ハナ。これから、家へ帰るだけなのに、楽しそうだな。」
「えへへ。だって、一緒に帰るの楽しいんだもん。」
私たちは横に広がって歩いていた。
周囲にも私たちのような生徒がちらほらと見える。
これが青春みたいな。
そう、平和なひととき。
これから私たちは、学校周辺の何の変哲もない通学路を三人一緒に帰っていく。
私は、話し合っている二人の様子や、通り過ぎた学校の正門を見ながら、しみじみとそう思った。
「あれ?アイリちゃん?何かあった?」
ハナちゃんがこちらに聞いてきた。
「ああ、ごめんなさい。」
「アイリ、何かあったか?」
二人がこちらに聞いてきた。
正直、私が勝手にしみじみとした感情を抱いて、静かにしていただけなので、何もない。
「いえ。特に何もないわ。」
「ええっ?本当、アイリちゃん?なにか、悩んでいるように見えたけど。」
ハナちゃんは、私のことを気にかけているようだ。
いや、しかし、本当になんでもないのだ。
「そうね、でも、今日みたいな日が続くといいなぁ、と思ったのよ。」
私は無難な答えを述べた。
とりあえず、二人に心配させないように、と思ったのだ。
「あはは、アイリはそういう所あるからな。」
何か頷きながら、ヒナコちゃんが納得している。
その間も、私たちは通学路を進んでいた。
「あっ、そうだ、そうだ。聞いてよ、ヒナコちゃん!」
ふと、思い出したかのように。
ハナちゃんは、ヒナコちゃんへ唐突に別の話を始めた。
「ん?なんだ?」
「えっと…。」
ハナちゃんはヒナコちゃんに話しかけている。
ハナちゃんは、たぶん、あの話を話そうとしている。
それは、クラス委員の話だ、と私は思った。
私たちは、自然と歩くスピードを緩める。
ヒナコちゃんも、ハナちゃんがゆっくりと思い出すように話を始めたので、しっかりと話を聞こうとしている。
「アイリちゃんが、クラス委員になるの。」
「えっ?そうなのか、アイリ?」
ヒナコちゃんが私の方を向いた。
「ああ、それね。実は…」
私は少し間を置いた。
「さっき、部活が始まる前に担任の先生から言われたの。」
「それでさっき悩んでたのか!」
ヒナコちゃんは、勝手に思い込んでいる。
実際はそうではないのだけれど。
「…ちょっと、思う所はあるわ。」
私は、含みのある言い方でヒナコちゃんに答えた。
まあ、全てを説明するのは面倒なのだ。
「もう、なんだよ。それなら、早く言えよぉ!」
ヒナコちゃんらしい励ましの言葉だと、私は思った。
「ええ。でも、大丈夫。今回のクラス委員は二人らしいの。」
「へぇーそうなんだ。もう一人は誰なんだ?」
「藤原さんと一緒にやることになったわ。」
「藤原?あの、いつも一人でいる子?」
そう言って、ヒナコちゃんは思い出そうとしているようだ。
「カリンちゃん!いい子だと思うよ!」
これまで、話に入ってこなかったハナちゃんは隣でそう言った。
「へぇ、でも。面白い組み合わせだな。でも二人って、何か理由があるのか?」
ヒナコちゃんは、私に聞いてきた。
クラス委員が増員される理由を聞きたいようだった。
たしかに、これまでの話を聞くと、その理由は聞きたくなるだろう。
「詳しいことはまだ聞いていないの。これから説明があるみたい。」
私は適当に誤魔化した。
いつも、カリンちゃんが一人だから、私とカリンちゃんが友達になるために、クラス委員になった、とは言えない。
そもそも、その理由を話すと、カリンちゃんと友達になるって目的から遠ざかる気もするし。
「そっか。でも、アイリちゃんとカリンちゃんか…。」
ヒナコちゃんは、少し心配そうな表情を浮かべる。
「大丈夫。アイリちゃんなら大丈夫だよ!」
「そうかな。まあ、そうか。」
ヒナコちゃんは、どこか完全に納得してはないようだった。
しかし、ハナちゃんにそう言われて、しぶしぶ、納得したようだ。
「アイリ、なんかあったらすぐに相談してくれ!」
「もちろんよ。何かあったら助けてね。ヒナコちゃん。」
「私もだよ!」
「ハナちゃんもね。」
私たちは、そんな会話を交わしながら、夕暮れの街を歩いていた。
やがて、私と二人の帰り道が分かれる交差点に差し掛かった。
「じゃあ、今日はここまでね。また、明日。」
私は、ハナちゃんとヒナコちゃんにそういってから、手をふった。
「アイリちゃん、さよならー!」
「じゃあな、アイリ。」
手をブンブンと振っているハナちゃん。
その横で、クールにも見える様子のヒナコちゃん。
相変わらずな二人。
その姿を見て、ほっこりした。
私はそのまま、二人の姿が見えなくなるまで見送った。
そして、一人になった瞬間、私だけの空間が訪れる。
明日は今日よりも良くなればいいな。
そう心の底から私は願った