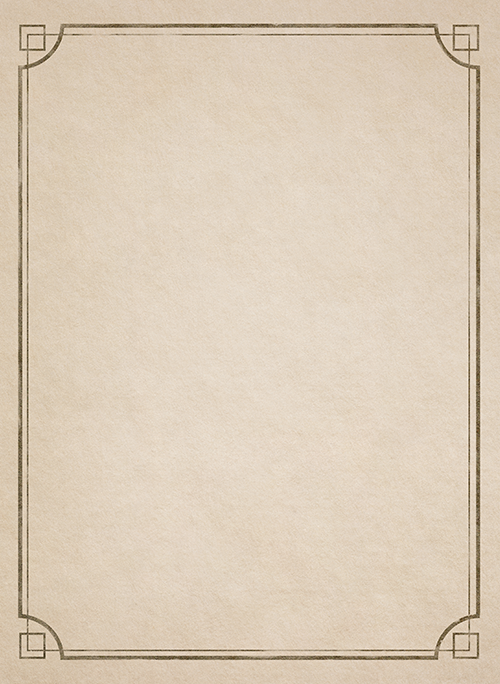第四話
午後の授業は特筆すべきことはなかった。
淡々と進んで、いつの間にか部活の時間となっていた。
「アイリちゃーん。」
ハナちゃんが私を呼んでいる。
「分かったわ。ハナちゃん。一緒に行きましょう。」
そうだ、今日は彼女も手芸部に来るのだ。
私は、ハナちゃんに返事をする。
そして、一緒に手芸部の部室へと向かうために、ハナちゃんの後について、私は教室を出ようとしたときだった。
「桔梗さん?ちょっといいかしら?」
担任の先生の声が、私の耳に届いた。
振り返ると、先生は優しい笑顔で私を見ていた。
その表情には、何か重要な話がありそうな感じがする。
「はい、先生。何でしょうか?」
私は丁寧に答えた。
教室を出ようとしていた足を止め、先生の方へ向き直る。
私の隣でハナちゃんは、私と先生を見ている。
「桔梗さん。これからちょっと話があるだけども、これから職員室で私と話をするのはダメかしら?」
「えっと。」
それはいいのだけれども。
ただ、私は、ハナちゃんを先に部室へ行かせようと思った。
「じゃ、アイリちゃん。話、あるようだから、私、先に行ってるよー!」
ハナちゃんは、先生と私が話をする雰囲気を察したみたいだ。
「ありがとう、ハナちゃん。」
私は、ハナちゃんにそう言った。
ハナちゃんは、元気よく先に進みだした。
ちょっと小柄な彼女のその様子を見ると微笑ましく思える。
「ごめんね。」
先生は、申し訳なさそうにそういった。
「いいえ。」
「では、ちょっとね。」
私は先生について職員室へ向かう。
「桔梗さんは、手芸部でしたっけ?」
「はい、そうです。」
「茨木さんも手芸部だから、一緒に部活なのね。」
「はい。」
私は意図せず、淡々と返事をしてしまった。
「話はすぐに終わるから、安心してね。」
先生は、私の調子になにかを考えたのか。
安心させるような感じでそう言った。
どうやら、先生は、ハナちゃんと私が一緒にいた雰囲気を壊したことに対して、悪いと思っているようだ。
しかし、そこまでのことではない、と私は思っていた。
「いいえ。大丈夫です。手芸部の活動は毎日あるので。」
「そう?ならいいんだけど。」
先生は私の返答に対して、気を使って、話を進めている。
そんな先生と私は、まったく関係のない話をしながら廊下を進んだ。
一方で私は、これからどんな話が始まるのだろうか、と思っていた。
私がなにか粗相をした記憶はない。
それに、そのような場合は生徒指導室へ直行するだろう、と推測している。
それでは、担任の先生から私へ話すこと、とはなんだろうか?
例えば、何かをお願いする場合。
委員とか?
私は推測を重ねていった。
もちろん、それを確認するようなことを今の段階では聞かない。
それは職員室の中でたっぷりと聞けるからだ。
私と先生は、廊下を進み終わった。
そして、そのまま職員室の中に入る。
職員室には、先生たちがいる。
放課後ともなれば、だいたいの先生たちはいるのだろう。
見知った顔の先生たちが見える。
私は、挨拶をしながら、先生たちの集団の間を進んでいった。
「桔梗さん、ここを使いましょう。」
私を先導する先生は、そう言って進む。
目の前にあるのは、パーティションに区切られた一角。
会議室みたいな場所だ。
その小部屋のような空間にはふかふかとしたソファー、テーブルが置かれている。
中央にテーブル、それを挟んで対面するようにソファーだ。
応接室として使用しているのだろうか?
「桔梗さん、座って。」
「はい。」
私は、先生に言われたようにソファーに座った。
先生も私の前にあるソファーに座る。
「忙しいところ、ごめんなさいね。」
先生はまず、私に謝ってきた。
「いいえ。忙しくはないので、大丈夫です。」
私は適当に話を合わせた。
「そう?それで、桔梗さんに相談というのは…。実は、クラス委員のことなの。」
先生はそう言って、話を続けた。
「桔梗さんと藤原さんに、クラス委員を務めてもらいたいんだけど、どうかな?」
藤原さん?
私は一瞬、驚きを隠せなかった。
藤原カリン。
彼女は、いつも一人で過ごしている女の子だ。
クラスの中で、最も存在感の薄い生徒の一人かもしれない。
「私と藤原さんですか?」
確認するように、私は尋ねた。
「そうよ。」
「あの、今、クラス委員をやっている子は?」
私は、記憶にあるクラス委員の子を思い描いていた。
「実は、その子も忙しくなっちゃってね。今、次の子を探しているところなのよ。」
「なるほどですね。」
内心、私は引き受ける気でいた。
しかし、なぜ私とカリンちゃんなんだろう。
それだけがちょっと気になったのだ。
「えっと。私はいいですけど、藤原ちゃんの方はどうなんでしょうか?」
「それはね。実はまだ、この話は桔梗さんだけしか話していないの。」
「そうなんですか。」
「クラス委員ってこれまでは各クラスに一人だけ、だったのよ。」
先生が言った言葉に、私も同意した。
そうだ。これまでクラス委員ってクラスに一人だけだったはず。
今回は二人なんだ。
ということは、私とカリンちゃんという組み合わせに意味があるのだろうか。
先生は、私の雰囲気を察したのか、話を始めた。
「実はね。私は藤原さんのことが少し心配なのよ。ちょっとクラスで孤立気味だから。」
そういって事情を話し始めた。
「…だから、どちらかといえば、クラス委員の仕事というよりも、二人で一緒に仕事をしてもらいたいのよ。」
その言葉を聞きながら、私は頷く。
ようやく先生の狙いが見えてきた。
「うーん。そうですか。」
先生から、私がどう見えているのは分からなかったが、そうなんだ、と思った。
「どうかしら?」
「私は構いません。」
そして、私は心の中で付け加えた。
カリンちゃんがどんな人物なのか、たしかに少しだけ、気になっていたのだ、と。
「そう?本当に?」
「はい。」
「ありがとう。じゃあ、二人でクラス委員をやってもらえるかしら」
「あの、藤原さんへは…。」
私は確認するように、先生へそう言った。
「藤原さんへは、既にクラス委員の話はしているから、大丈夫よ。」
「分かりました。喜んでお引き受けします。」
私は礼儀正しく、そう言った。
「ありがとう、桔梗さん。あなたなら、きっと藤原さんとも上手くやっていけると思うわ。」
先生の言葉に、私は軽く頭を下げた。
「いいえ、桔梗さん。頭を下げるのはこちらのほうよ。」
先生は、そう言って私にウインクをした。
ほかの先生とは違って、それは様になっていた。
「では、クラス委員の話はまた、後日、藤原さんと一緒の時にするから。今日は、本当にありがとう。」
そういって、私と先生の話は終わった。
午後の授業は特筆すべきことはなかった。
淡々と進んで、いつの間にか部活の時間となっていた。
「アイリちゃーん。」
ハナちゃんが私を呼んでいる。
「分かったわ。ハナちゃん。一緒に行きましょう。」
そうだ、今日は彼女も手芸部に来るのだ。
私は、ハナちゃんに返事をする。
そして、一緒に手芸部の部室へと向かうために、ハナちゃんの後について、私は教室を出ようとしたときだった。
「桔梗さん?ちょっといいかしら?」
担任の先生の声が、私の耳に届いた。
振り返ると、先生は優しい笑顔で私を見ていた。
その表情には、何か重要な話がありそうな感じがする。
「はい、先生。何でしょうか?」
私は丁寧に答えた。
教室を出ようとしていた足を止め、先生の方へ向き直る。
私の隣でハナちゃんは、私と先生を見ている。
「桔梗さん。これからちょっと話があるだけども、これから職員室で私と話をするのはダメかしら?」
「えっと。」
それはいいのだけれども。
ただ、私は、ハナちゃんを先に部室へ行かせようと思った。
「じゃ、アイリちゃん。話、あるようだから、私、先に行ってるよー!」
ハナちゃんは、先生と私が話をする雰囲気を察したみたいだ。
「ありがとう、ハナちゃん。」
私は、ハナちゃんにそう言った。
ハナちゃんは、元気よく先に進みだした。
ちょっと小柄な彼女のその様子を見ると微笑ましく思える。
「ごめんね。」
先生は、申し訳なさそうにそういった。
「いいえ。」
「では、ちょっとね。」
私は先生について職員室へ向かう。
「桔梗さんは、手芸部でしたっけ?」
「はい、そうです。」
「茨木さんも手芸部だから、一緒に部活なのね。」
「はい。」
私は意図せず、淡々と返事をしてしまった。
「話はすぐに終わるから、安心してね。」
先生は、私の調子になにかを考えたのか。
安心させるような感じでそう言った。
どうやら、先生は、ハナちゃんと私が一緒にいた雰囲気を壊したことに対して、悪いと思っているようだ。
しかし、そこまでのことではない、と私は思っていた。
「いいえ。大丈夫です。手芸部の活動は毎日あるので。」
「そう?ならいいんだけど。」
先生は私の返答に対して、気を使って、話を進めている。
そんな先生と私は、まったく関係のない話をしながら廊下を進んだ。
一方で私は、これからどんな話が始まるのだろうか、と思っていた。
私がなにか粗相をした記憶はない。
それに、そのような場合は生徒指導室へ直行するだろう、と推測している。
それでは、担任の先生から私へ話すこと、とはなんだろうか?
例えば、何かをお願いする場合。
委員とか?
私は推測を重ねていった。
もちろん、それを確認するようなことを今の段階では聞かない。
それは職員室の中でたっぷりと聞けるからだ。
私と先生は、廊下を進み終わった。
そして、そのまま職員室の中に入る。
職員室には、先生たちがいる。
放課後ともなれば、だいたいの先生たちはいるのだろう。
見知った顔の先生たちが見える。
私は、挨拶をしながら、先生たちの集団の間を進んでいった。
「桔梗さん、ここを使いましょう。」
私を先導する先生は、そう言って進む。
目の前にあるのは、パーティションに区切られた一角。
会議室みたいな場所だ。
その小部屋のような空間にはふかふかとしたソファー、テーブルが置かれている。
中央にテーブル、それを挟んで対面するようにソファーだ。
応接室として使用しているのだろうか?
「桔梗さん、座って。」
「はい。」
私は、先生に言われたようにソファーに座った。
先生も私の前にあるソファーに座る。
「忙しいところ、ごめんなさいね。」
先生はまず、私に謝ってきた。
「いいえ。忙しくはないので、大丈夫です。」
私は適当に話を合わせた。
「そう?それで、桔梗さんに相談というのは…。実は、クラス委員のことなの。」
先生はそう言って、話を続けた。
「桔梗さんと藤原さんに、クラス委員を務めてもらいたいんだけど、どうかな?」
藤原さん?
私は一瞬、驚きを隠せなかった。
藤原カリン。
彼女は、いつも一人で過ごしている女の子だ。
クラスの中で、最も存在感の薄い生徒の一人かもしれない。
「私と藤原さんですか?」
確認するように、私は尋ねた。
「そうよ。」
「あの、今、クラス委員をやっている子は?」
私は、記憶にあるクラス委員の子を思い描いていた。
「実は、その子も忙しくなっちゃってね。今、次の子を探しているところなのよ。」
「なるほどですね。」
内心、私は引き受ける気でいた。
しかし、なぜ私とカリンちゃんなんだろう。
それだけがちょっと気になったのだ。
「えっと。私はいいですけど、藤原ちゃんの方はどうなんでしょうか?」
「それはね。実はまだ、この話は桔梗さんだけしか話していないの。」
「そうなんですか。」
「クラス委員ってこれまでは各クラスに一人だけ、だったのよ。」
先生が言った言葉に、私も同意した。
そうだ。これまでクラス委員ってクラスに一人だけだったはず。
今回は二人なんだ。
ということは、私とカリンちゃんという組み合わせに意味があるのだろうか。
先生は、私の雰囲気を察したのか、話を始めた。
「実はね。私は藤原さんのことが少し心配なのよ。ちょっとクラスで孤立気味だから。」
そういって事情を話し始めた。
「…だから、どちらかといえば、クラス委員の仕事というよりも、二人で一緒に仕事をしてもらいたいのよ。」
その言葉を聞きながら、私は頷く。
ようやく先生の狙いが見えてきた。
「うーん。そうですか。」
先生から、私がどう見えているのは分からなかったが、そうなんだ、と思った。
「どうかしら?」
「私は構いません。」
そして、私は心の中で付け加えた。
カリンちゃんがどんな人物なのか、たしかに少しだけ、気になっていたのだ、と。
「そう?本当に?」
「はい。」
「ありがとう。じゃあ、二人でクラス委員をやってもらえるかしら」
「あの、藤原さんへは…。」
私は確認するように、先生へそう言った。
「藤原さんへは、既にクラス委員の話はしているから、大丈夫よ。」
「分かりました。喜んでお引き受けします。」
私は礼儀正しく、そう言った。
「ありがとう、桔梗さん。あなたなら、きっと藤原さんとも上手くやっていけると思うわ。」
先生の言葉に、私は軽く頭を下げた。
「いいえ、桔梗さん。頭を下げるのはこちらのほうよ。」
先生は、そう言って私にウインクをした。
ほかの先生とは違って、それは様になっていた。
「では、クラス委員の話はまた、後日、藤原さんと一緒の時にするから。今日は、本当にありがとう。」
そういって、私と先生の話は終わった。