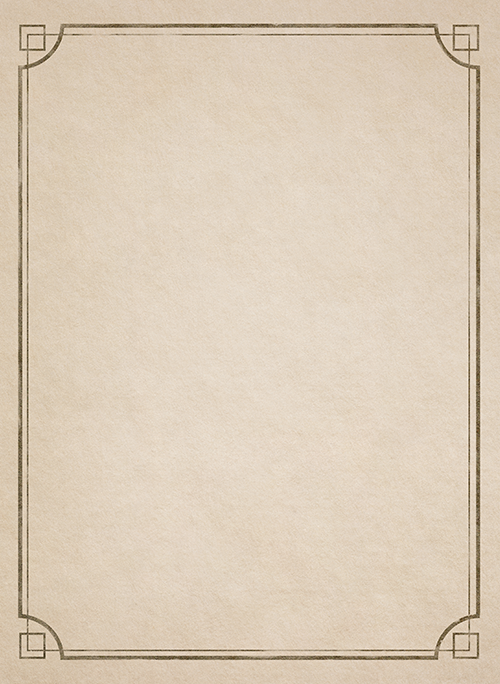第二話
やがて、教師が教室に入ってきた。
中年の神経質そうな男性教師。
彼の担当教科は数学だ。
数学の教師は教卓に着くと、資料を置いて準備を始めていた。
さて彼は、今、どんな事を考えているのだろうか?
私は、少し想像をしてみた。
材料となるのは、とある女子生徒からの情報だ。
その情報によれば、今、目の前にいる教師は、つい先週から妻と別居しているらしい。
…どこから、そんな情報を?
と、私は思ったけれど。
一方的にその子は、私にその話をしてきたのだ。
おそらく、離婚。
それに準じる状況に近い。
そして、その動揺が職場でも少しずつ生じてくる。
疲労や周囲への無神経など。
とはいえ、この教師は真面目そうに見える。
性格も外見通りだ。
その彼はこれから振る舞いになるだろうか?
私は教師の様子を静かに観察する。
彼の動きは、ぱっと見る限り、いつも通りでなんら変化がない。
淡々と授業の準備を進めている。
ただ、先ほどの情報に照らし合わせて、改めて私は考える。
教師は機械的に、慣れた動作をこなしているだけのようにも見えた。
チャイムがなった。
これから授業が始まるのだ。
「はい、皆さん。これから授業を始めます。」
教師は授業を始めた。
なんら、これまでと変わらない様子だ。
しかし、私には読めた。
これまでと同じように振舞っているだけ、だと。
恒常性バイアス?
いや、違う。
同じように振る舞うことが楽なのだ。
いや、むしろ心が死んでいる人間には、それしかできないのだろう。
クラスメイトたちは、特に変わった様子もなく教科書を開いていく。
彼らには、教師の微妙な変化は見えていないのだろう。
私は、ゆっくりと教科書を開きながら、その観点から注意深く観察し続ける。
「今日は前回の続きから始めます。」
滑らかに授業が進んでいく。
長年にわたる教師としてのキャリアが人間らしい思考を塗りつぶしている。
おそらく、今の彼は、なにも考えていない。
長年に染み付いた習慣によってのみ、彼は動作している。
授業が進む中、私は観察を続ける。
彼の声の抑揚、黒板に文字を書く速度、生徒に問いかける際の間の取り方。
全てが、普段と変わらないように見える。
しかし、その『変わらなさ』こそが、彼の内面の激しい動揺を物語っているのだ。
ふと、教師の目が私と合った。
私はにっこりと微笑んだ。
普段の私なら、たぶんしないタイミングでのいい笑顔だ。
すると、その瞬間、彼の動作が停止した。
少しだけ、授業に空白ができる。
教室が静まり返った。
「…桔梗さん、この問題を解いてくれますか?」
突然の指名だった。
おそらく、授業の進行が止まったから、間に合わせなのだろう。
「はい、分かりました」
私は言われたように静かに立ち上がり、黒板の前に立つ。
しかし黒板に書かれている問題が、分からない。
周囲の生徒が私と教師を黙って見ていた。
「すいません。この問題、まだやっていないので、私には分かりません。」
「ああ、ごめんごめん。これから説明するところだった、桔梗さん。席に戻っても大丈夫です。」
普段の彼なら、とてもありえないミスだ。
もちろん、私も知っていて、わざと黒板まで進んだということもあるのだが。
教室の誰かが笑った。
それに釣られて、みんなが笑い出した。
私も笑顔で自分の席へと戻る。
「あ、みんな、ごめんごめん。桔梗さんも。」
そう言って教師は、自分を取り戻したかのように軽薄な様子で謝っていた。
そして、いつもの教室の雰囲気へと戻っていく。
席に着いた私は、実験結果から推理を進める。
しかし、なぜ、先ほど教師は授業の進行を止めたのだろうか?と。
その理由は私にはなんとなく分かった。
おそらく彼は、止めざるを得なかったのだ。
そして、その後のミスという要素。
これらは、もちろん、私の笑顔という予想外の出来事で、いつもの習慣が出来なくなったから、が原因だと思われた。
そう。長年の習慣以外のことが起きた。
そして、ふと自分の思考を取り戻したとき、彼は何も対処ができなくなったのだ。
今の彼は、普段通り授業を進めている。
まるでこれまでに染み付いた慣習のみによって動く、生ける屍。
私は、その様子をじっと見た。
そして、私は思った。
私にも衝撃的なことが起これば、ああなってしまうのだろうか?と。
私も周囲からは、なんら変わっていない、と見られつつも内部の自分が枯れたまま青春を送るのだろうか?
それは分からない。
そんなことを考えていた。
やがて、授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。
休み時間になった。
クラスメイトたちは、いつものように賑やかに話し始める。
その中で、私は静かに教師の後ろ姿を見つめていた。
彼は少し肩を落として教室を出ていく。
そこへ、ハナちゃんが近づいてきた。
「アイリちゃん、さっきの先生おかしかったね」
彼女の明るい声に、私は優しく微笑む。
「あの先生にしては、珍しいミスだったわね。」
「でも、アイリちゃんの対応がすごかった!冷静だったよ」
ハナちゃんは心底、感心しているような様子だ。
「別に、大したことじゃないわ」
「そうかなぁ?」
「そうよ。」
私は、ハナちゃんが冷静になるような回答をする。
「うーん。でも、あの先生、最近なんか元気なかったよね?」
ハナちゃんは、私の言葉や態度をようやく察したのか、ハナちゃんが話す内容が少し変わった。
「そうかしら?いつも通りに見えたけど。」
私は、ハナちゃんに答えながらも、少し驚いた。
能天気そうなハナちゃんにも、あの先生が奥に秘めたものが見えているだろうか、と。
私は、ハナちゃんの直感の鋭さに舌を巻いた。
「じゃあ、私の気のせいかな。」
私の答えを聞いたハナちゃんは、すぐに別の話題に移っていった。
無邪気なハナちゃんは、それ以上、この件について話をしてこなかった。
そうやってハナちゃんと会話を続けていると、チャイムが鳴った。
「じゃ、また!」
「ハナちゃんも。」
ハナちゃんは、自分の席へと戻っていった。
しばらくすると、教師が教師が入ってきた。
次の授業は、私たちのクラス担任の先生が持っている授業だった。
英語の授業だ。
「皆さん!始めますよ。」
軽快な声が教室に響き渡った。
若い女性教師。
とはいえ、新米というわけではない。
教師としての経験もあり、まだ20代で若々しい。
とても理想的な立ち位置の英語教師だ。
クラスのみんなは、そのクラス担任でもある先生の方を向き始める。
私もクラスのみんなと同じように顔を上げ、教壇に立つ先生を見た。
彼女は、今日もきちんとしたスーツを着こなしている。
濃紺のジャケットに白いブラウス、膝丈のスカート。
その姿は知的で洗練されている。
先生の黒髪は肩まで伸びていて、さらさらとして生命力が溢れているかのようだ。
それが彼女の整った顔立ちをより引き立てている。
大きな瞳、通った鼻筋、そして優しく微笑む唇。
男子生徒からはもちろん、同性の私たちからもその魅力は見て取れる。
そんな美人の先生に、クラスのみんなは自然と従ってしまう。
その自信に裏打ちされているのか、彼女の声には、いつもの活気が満ちている。
「では、教科書の92ページを開いてください。」
先生の声に合わせて、教室中でページをめくる音が響く。
先生は黒板に向かい、すらりとした指で白いチョークを握る。
続いて、先生の流暢な英語が教室に響き渡った。
「Today, we're going to learn about environmental issues.」
先生の声は、張りがあって聞き取りやすい。
彼女が話し始めると、教室全体が静まり返る。
みんな、先生の一言一句を聞き逃すまいと耳を傾けている。
時折、難しい単語が出てくると、先生はジェスチャーを交えて説明する。
その典型的なジェスチャー。
しかし、彼女がするだけで、何かとても洗練された動作に見えた。
黒板には、先生の美しい文字で「Global Warming」「Deforestation」「Pollution」といった環境問題に関する単語が英語で整理されていく。
その説明は分かりやすく、時折ユーモアを交えながら進められる。
英語では有賀、その先生の洒落た雰囲気と語りかけに、クラスメイトたちから笑いが起こる。
おそらく、クラスの半数は先生が何を言っているのか理解できていない。
しかし、いつも彼女の持つ雰囲気は、日本語や英語といった言葉の壁を突破して、いつも楽しい雰囲気にクラスを変えてしまう。
私は、先生の話に耳を傾けながらも、ふと周りを見回した。
男子生徒たちは、美しい先生が主導するテンポの良い授業を熱心に聞いている。
それは女子生徒も、同じのようだ。
その目にあるのは、憧れのまなざし。
スタイリッシュでかっこいい。
みんな催眠術にかかっているかのように、授業に参加している。
その中で、私はノートを取り続けた。
おそらく、先生の魅力は、単に外見や英語力だけではない。
その知性と教養、そして生徒たちへの優しさ。
英語が苦手な生徒にも、丁寧にフォローする姿勢。
それらが相まって、彼女は誰からも慕われる存在なのだ。
授業が進む中、私は観察を進める。
完璧な発音、豊富な表現力、そして生徒を引き付ける雰囲気。
まるで海外のドラマに出てくるような理想的な英語教師。
でも、私の目は自然と別の方向へ向かっていた。
藤原 カリン。
どこか熱に浮かれた雰囲気の教室。
しかし、カリンちゃんの周囲だけは死んだように静かな雰囲気が漂っている。
私は、カリンちゃんの姿を不自然にならないように見つめた。
まるで教室という熱狂の中に浮かぶ一人小島のようだ。
もし、心の熱量というものが表示されるサーマルゴーグルのようなものがあるとすれば、カリンちゃんの周りだけ熱源がないように表示されるだろう。
そんな静けさを私は感じていた。
カリンの孤独な姿を見ていると、不思議と私は安心した。
なぜだろう。
もしかしたら、私も同じような役割だからかもしれない。
それは、クラスの中心を引き立てる役。
もし、違いがあるとすれば、私には少なくともハナちゃんという話し相手がいる。
しかし、カリンちゃんには、誰もいないようだ。
カリンは、真面目に授業を聞いているようだ。
でも、心なしかその表情には何か寂しさが漂っているようにも見えた。
私は、そんなカリンの様子を観察しながら、静かにノートを取り続けた。
「Okay, that's all for today. Don't forget your homework!」
先生の声が、私の思考を現実に引き戻した。
英語の授業が終わったようだ。
次の瞬間、いきなり生徒たちの声が教室中に満ち始めた。
これまで溜まっていた水が一気に放出されたような、そんな活気に満ち溢れ始めた。
やがて、教師が教室に入ってきた。
中年の神経質そうな男性教師。
彼の担当教科は数学だ。
数学の教師は教卓に着くと、資料を置いて準備を始めていた。
さて彼は、今、どんな事を考えているのだろうか?
私は、少し想像をしてみた。
材料となるのは、とある女子生徒からの情報だ。
その情報によれば、今、目の前にいる教師は、つい先週から妻と別居しているらしい。
…どこから、そんな情報を?
と、私は思ったけれど。
一方的にその子は、私にその話をしてきたのだ。
おそらく、離婚。
それに準じる状況に近い。
そして、その動揺が職場でも少しずつ生じてくる。
疲労や周囲への無神経など。
とはいえ、この教師は真面目そうに見える。
性格も外見通りだ。
その彼はこれから振る舞いになるだろうか?
私は教師の様子を静かに観察する。
彼の動きは、ぱっと見る限り、いつも通りでなんら変化がない。
淡々と授業の準備を進めている。
ただ、先ほどの情報に照らし合わせて、改めて私は考える。
教師は機械的に、慣れた動作をこなしているだけのようにも見えた。
チャイムがなった。
これから授業が始まるのだ。
「はい、皆さん。これから授業を始めます。」
教師は授業を始めた。
なんら、これまでと変わらない様子だ。
しかし、私には読めた。
これまでと同じように振舞っているだけ、だと。
恒常性バイアス?
いや、違う。
同じように振る舞うことが楽なのだ。
いや、むしろ心が死んでいる人間には、それしかできないのだろう。
クラスメイトたちは、特に変わった様子もなく教科書を開いていく。
彼らには、教師の微妙な変化は見えていないのだろう。
私は、ゆっくりと教科書を開きながら、その観点から注意深く観察し続ける。
「今日は前回の続きから始めます。」
滑らかに授業が進んでいく。
長年にわたる教師としてのキャリアが人間らしい思考を塗りつぶしている。
おそらく、今の彼は、なにも考えていない。
長年に染み付いた習慣によってのみ、彼は動作している。
授業が進む中、私は観察を続ける。
彼の声の抑揚、黒板に文字を書く速度、生徒に問いかける際の間の取り方。
全てが、普段と変わらないように見える。
しかし、その『変わらなさ』こそが、彼の内面の激しい動揺を物語っているのだ。
ふと、教師の目が私と合った。
私はにっこりと微笑んだ。
普段の私なら、たぶんしないタイミングでのいい笑顔だ。
すると、その瞬間、彼の動作が停止した。
少しだけ、授業に空白ができる。
教室が静まり返った。
「…桔梗さん、この問題を解いてくれますか?」
突然の指名だった。
おそらく、授業の進行が止まったから、間に合わせなのだろう。
「はい、分かりました」
私は言われたように静かに立ち上がり、黒板の前に立つ。
しかし黒板に書かれている問題が、分からない。
周囲の生徒が私と教師を黙って見ていた。
「すいません。この問題、まだやっていないので、私には分かりません。」
「ああ、ごめんごめん。これから説明するところだった、桔梗さん。席に戻っても大丈夫です。」
普段の彼なら、とてもありえないミスだ。
もちろん、私も知っていて、わざと黒板まで進んだということもあるのだが。
教室の誰かが笑った。
それに釣られて、みんなが笑い出した。
私も笑顔で自分の席へと戻る。
「あ、みんな、ごめんごめん。桔梗さんも。」
そう言って教師は、自分を取り戻したかのように軽薄な様子で謝っていた。
そして、いつもの教室の雰囲気へと戻っていく。
席に着いた私は、実験結果から推理を進める。
しかし、なぜ、先ほど教師は授業の進行を止めたのだろうか?と。
その理由は私にはなんとなく分かった。
おそらく彼は、止めざるを得なかったのだ。
そして、その後のミスという要素。
これらは、もちろん、私の笑顔という予想外の出来事で、いつもの習慣が出来なくなったから、が原因だと思われた。
そう。長年の習慣以外のことが起きた。
そして、ふと自分の思考を取り戻したとき、彼は何も対処ができなくなったのだ。
今の彼は、普段通り授業を進めている。
まるでこれまでに染み付いた慣習のみによって動く、生ける屍。
私は、その様子をじっと見た。
そして、私は思った。
私にも衝撃的なことが起これば、ああなってしまうのだろうか?と。
私も周囲からは、なんら変わっていない、と見られつつも内部の自分が枯れたまま青春を送るのだろうか?
それは分からない。
そんなことを考えていた。
やがて、授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。
休み時間になった。
クラスメイトたちは、いつものように賑やかに話し始める。
その中で、私は静かに教師の後ろ姿を見つめていた。
彼は少し肩を落として教室を出ていく。
そこへ、ハナちゃんが近づいてきた。
「アイリちゃん、さっきの先生おかしかったね」
彼女の明るい声に、私は優しく微笑む。
「あの先生にしては、珍しいミスだったわね。」
「でも、アイリちゃんの対応がすごかった!冷静だったよ」
ハナちゃんは心底、感心しているような様子だ。
「別に、大したことじゃないわ」
「そうかなぁ?」
「そうよ。」
私は、ハナちゃんが冷静になるような回答をする。
「うーん。でも、あの先生、最近なんか元気なかったよね?」
ハナちゃんは、私の言葉や態度をようやく察したのか、ハナちゃんが話す内容が少し変わった。
「そうかしら?いつも通りに見えたけど。」
私は、ハナちゃんに答えながらも、少し驚いた。
能天気そうなハナちゃんにも、あの先生が奥に秘めたものが見えているだろうか、と。
私は、ハナちゃんの直感の鋭さに舌を巻いた。
「じゃあ、私の気のせいかな。」
私の答えを聞いたハナちゃんは、すぐに別の話題に移っていった。
無邪気なハナちゃんは、それ以上、この件について話をしてこなかった。
そうやってハナちゃんと会話を続けていると、チャイムが鳴った。
「じゃ、また!」
「ハナちゃんも。」
ハナちゃんは、自分の席へと戻っていった。
しばらくすると、教師が教師が入ってきた。
次の授業は、私たちのクラス担任の先生が持っている授業だった。
英語の授業だ。
「皆さん!始めますよ。」
軽快な声が教室に響き渡った。
若い女性教師。
とはいえ、新米というわけではない。
教師としての経験もあり、まだ20代で若々しい。
とても理想的な立ち位置の英語教師だ。
クラスのみんなは、そのクラス担任でもある先生の方を向き始める。
私もクラスのみんなと同じように顔を上げ、教壇に立つ先生を見た。
彼女は、今日もきちんとしたスーツを着こなしている。
濃紺のジャケットに白いブラウス、膝丈のスカート。
その姿は知的で洗練されている。
先生の黒髪は肩まで伸びていて、さらさらとして生命力が溢れているかのようだ。
それが彼女の整った顔立ちをより引き立てている。
大きな瞳、通った鼻筋、そして優しく微笑む唇。
男子生徒からはもちろん、同性の私たちからもその魅力は見て取れる。
そんな美人の先生に、クラスのみんなは自然と従ってしまう。
その自信に裏打ちされているのか、彼女の声には、いつもの活気が満ちている。
「では、教科書の92ページを開いてください。」
先生の声に合わせて、教室中でページをめくる音が響く。
先生は黒板に向かい、すらりとした指で白いチョークを握る。
続いて、先生の流暢な英語が教室に響き渡った。
「Today, we're going to learn about environmental issues.」
先生の声は、張りがあって聞き取りやすい。
彼女が話し始めると、教室全体が静まり返る。
みんな、先生の一言一句を聞き逃すまいと耳を傾けている。
時折、難しい単語が出てくると、先生はジェスチャーを交えて説明する。
その典型的なジェスチャー。
しかし、彼女がするだけで、何かとても洗練された動作に見えた。
黒板には、先生の美しい文字で「Global Warming」「Deforestation」「Pollution」といった環境問題に関する単語が英語で整理されていく。
その説明は分かりやすく、時折ユーモアを交えながら進められる。
英語では有賀、その先生の洒落た雰囲気と語りかけに、クラスメイトたちから笑いが起こる。
おそらく、クラスの半数は先生が何を言っているのか理解できていない。
しかし、いつも彼女の持つ雰囲気は、日本語や英語といった言葉の壁を突破して、いつも楽しい雰囲気にクラスを変えてしまう。
私は、先生の話に耳を傾けながらも、ふと周りを見回した。
男子生徒たちは、美しい先生が主導するテンポの良い授業を熱心に聞いている。
それは女子生徒も、同じのようだ。
その目にあるのは、憧れのまなざし。
スタイリッシュでかっこいい。
みんな催眠術にかかっているかのように、授業に参加している。
その中で、私はノートを取り続けた。
おそらく、先生の魅力は、単に外見や英語力だけではない。
その知性と教養、そして生徒たちへの優しさ。
英語が苦手な生徒にも、丁寧にフォローする姿勢。
それらが相まって、彼女は誰からも慕われる存在なのだ。
授業が進む中、私は観察を進める。
完璧な発音、豊富な表現力、そして生徒を引き付ける雰囲気。
まるで海外のドラマに出てくるような理想的な英語教師。
でも、私の目は自然と別の方向へ向かっていた。
藤原 カリン。
どこか熱に浮かれた雰囲気の教室。
しかし、カリンちゃんの周囲だけは死んだように静かな雰囲気が漂っている。
私は、カリンちゃんの姿を不自然にならないように見つめた。
まるで教室という熱狂の中に浮かぶ一人小島のようだ。
もし、心の熱量というものが表示されるサーマルゴーグルのようなものがあるとすれば、カリンちゃんの周りだけ熱源がないように表示されるだろう。
そんな静けさを私は感じていた。
カリンの孤独な姿を見ていると、不思議と私は安心した。
なぜだろう。
もしかしたら、私も同じような役割だからかもしれない。
それは、クラスの中心を引き立てる役。
もし、違いがあるとすれば、私には少なくともハナちゃんという話し相手がいる。
しかし、カリンちゃんには、誰もいないようだ。
カリンは、真面目に授業を聞いているようだ。
でも、心なしかその表情には何か寂しさが漂っているようにも見えた。
私は、そんなカリンの様子を観察しながら、静かにノートを取り続けた。
「Okay, that's all for today. Don't forget your homework!」
先生の声が、私の思考を現実に引き戻した。
英語の授業が終わったようだ。
次の瞬間、いきなり生徒たちの声が教室中に満ち始めた。
これまで溜まっていた水が一気に放出されたような、そんな活気に満ち溢れ始めた。