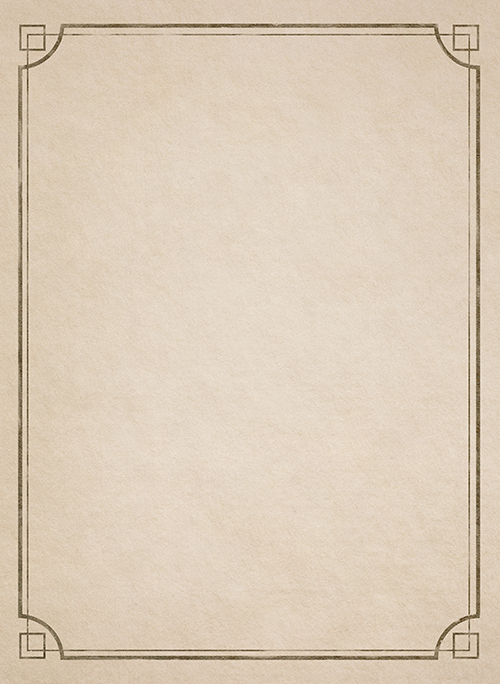第十五話
私の作品が壊された事件。
それ以降、私たちの間では、その話はしないことが暗黙の了解になっていた。
どこか、ヒナコちゃんもハナちゃんも何か思う所はあるようだった。
…その犯人が誰にしろ、である。
そして、その日は、私の作品が壊されて何日か経過しているある日だった。
朝、私が教室のドアを開けると、カリンちゃんの姿があった。
彼女は自席に座っていた。
私の心は、彼女と会話するように囁いた。
それに従って、カリンちゃんへ適度な距離に近づく。
私はできるだけ自然に振る舞おうと心掛けた。
「おはよう、カリンちゃん。」
私は、なるべく普通の声で挨拶をした。
カリンちゃんは、一瞬こちらを見たが、すぐに目をそらした。
しかし、今日はいつもと違う。
「うるさい。気持ち悪い。」
カリンちゃんは、珍しく言葉を返してきた。
カリンちゃんの言葉には、相変わらずの冷たさが込められていた。
しかし、これまで大きく違うのは、カリンちゃんが完全なる無視をしていない、ということだ。
会話ができる以上、何か前に進むことが出来る、私はそう思った。
「私、カリンちゃんに嫌われる理由が分からないのよ。」
私の言葉を聞いたカリンちゃんの目に一瞬、虚をつかれた様子で固まった。
続いて、驚きの色が浮かんだ。
しかし、すぐにその表情は怒りに変わった。
「お前!よくも、そんな白々しいことを!」
カリンちゃんの大声が、周囲に届く。
怒りしか感じられない。
だけど、このまま会話を続けるほかにない。
「カリンちゃん、私たち、最初はうまくいってたじゃない…」
私が言いかけると、カリンちゃんは更に声を荒げた。
「お前、いい子ぶりやがって…」
もはや、カリンちゃんは、まったく私の言葉を聞いていない。
その代わりに、まるで呪詛のように、なにかを繰り返し小さな声で発している。
カリンちゃんは、相当、頭に来ているようだ。
私は言葉を慎重に選ばなければならない。
ここで間違えれば、全てが台無しになってしまう。
そう思いながら、私は静かに口を開いた。
「そんなつもりはないわ。ねえ、カリンちゃん?」
私はゆっくりと話しかけた。
そのとき、カリンちゃんは自席から立ち上がった。
「黙れ!」
カリンちゃんは大声で一喝した。
彼女は、とても感情的になっている。
そして、カリンちゃんは、私の方へ近づいてきた。
彼女は、かつてないほどの憎しみに囚われていた。
「殺してやる!」
よく見ると、カリンちゃんの手には、カッターナイフが握られていた。
どうやら、私から見えないところで、彼女はそれを持っていたようだ。
おもわず、その様子を見た私は、後ずさる。
カリンちゃんは、尋常でない様子だ。
逃げないと!
私の頭の中で警報が鳴り響く。
「死ね!」
彼女はそう言って、こちらに向かってきた。
「やめて!」
私は、思わず叫ぶ。
そして、反射的に教室を飛び出した。
廊下を全力で走る。
間違いなく後ろから、カリンちゃんが走ってきている。
私の耳に、彼女の荒い息遣いが聞こえるかのような。
もし捕まれば、ただでは済まないだろう。
そう思うと、恐怖が込み上げてきた。
全力疾走。
逃げながら、私は、陸上部の見学の時に走った時を思い出す。
あのときと、違うのは、失敗が許されないことだ。
ああ、あの時は良かった。
なにしろ、あの時、隣にはハナちゃんがいたのだ。
廊下を走る。
私は、後ろを振り返った。
夜叉の如き表情をした、カリンちゃんが凶器を手に走ってきている。
逃げるしかない。
しかし、このまま逃げ続けても、逃げ切れる気はしない。
彼女との距離は、今の所、詰まられることはないが
このまま、引き離すほど、私の足は速くない。
どうすればいいの?
私は、人が多いところに逃げるべきと考えた。
そうだ!
職員室。
私は、それを実行に移す。
廊下を走る。
私は、後ろから追跡してくる彼女か確認しながら、職員室へ向かう。
息が上がり、足が重くなってきた。
でも、止まるわけにはいかない。
職員室の扉が見えた。
後ろの彼女までの距離は、扉を開くくらいの余裕はありそうだ。
希望が見えた気がした。
「あああああああああああ!!!!」
半狂乱となっているカリンちゃんの声。
職員室に入らないと!
扉に手を掛けて、一気に開ける。
ドンッ!
そして、飛び込むように、職員室へ入った。
想像以上の物音がした。
先生たちが私を見る。
しかし、それを気にする余裕はない。
扉を閉めないと!
目と鼻の先に彼女がいた。
それは殺気を感じるほどの。
彼女も私の後に続いて、室内へ入ろうとしていた。
ドンッ!
私は、一気に職員室の扉を閉めた。
ドンドンドン!
扉をたたく音。
「開けろ!死ね!殺すぞ!」
罵声。
カリンちゃんの声。
ドンドンドン!
彼女は職員室の扉を開けようとしている。
私は扉を開けられないように、抑える。
もちろん全体重を扉に掛ける。
「おい!うるさいぞ!」
「ちょっと!あなたたち!ここは職員室です!静かにしてください!」
「静かにしろ!」
職員にいた先生たちから檄が飛んだ。
どうやら、私たちがふざけている、と先生たちは勘違いしているようだ。
「助けてください!」
扉を抑えながら、私が叫ぶ。
その尋常でない様子に、先生たちが集まってきた。
先生たちが私の周囲に集まってくればくるほど、職員室の扉の向こうは静かになっていた。
そして、廊下にいる彼女の気配が消えた。
職員室前の廊下で、あれほど騒いでいるのだ。
もしかしたら、彼女は先生に捕まったのかもしれない。
「先生…カリンさんが…私を…。」
扉を抑えている私は、言葉が途切れ途切れになる。
騒ぎを聞きつけた担任の先生が、驚いた様子で駆け寄ってきた。
「落ち着いて。ゆっくり話してくれる?」
まるで先生の声が、遠くから聞こえてくるようだった。
私を殺そうとしているカリンちゃんは、もう廊下にいないようだった。
その状況になって、ようやく私は扉を抑えることをやめた。
緊張から解かれた私は、ヘナヘナと、職員室の一角へ力なく座り込む。
そして、ゆっくりと私は状況を説明しはじめた。
カリンちゃんとの対立、そして今朝の出来事。
言葉が混乱し、うまく伝わっているか分からなかったが、担任の先生は真剣な表情で私の話を聞いていた。
「分かりました。桔梗さん、立てる?」
「はい。」
私はようやく、自分の足で立った。
先ほどまで、命を狙われていたのだ。
ちょっとだけ落ち着いたとはいえ、まだ、完全ではない。
先生が、職員室にある会議室のソファーへ、私を座らせる。
パーティションで区切られた小さなスペースだ。
「桔梗さん、こっちでちょっと、待っていてね。」
「はい、分かりました。」
担任の先生は、他の教師たちと相談をするようだ。
私はソファーに座って、待つ。
少しづつ、落ち着きを取り戻しつつある私は、周囲を見た。
そこは奇しくも、私がクラス委員の仕事を命じられた場所だった。
しばらく待つと、担任の先生が戻ってきた。
「桔梗さん。あとは、私たちが対応します。」
「えっと。カリンちゃんは、どうなったんですか?」
私は、先生に聞く。
「それは…。これから対応を決めるところよ。」
担任の先生は、深刻そうな表情でそう言った。
「そうですか。」
「ああ、それで…桔梗さん?それでこれから、授業を受けられるかしら?もう少し休んだ方がいいなら…。」
担任の先生は、私に気を使っているようだ。
私は、どう答えようかと考えていた。
その時だった。
私と先生が話し合っている会議室。
そのパーティションの向こう側から、ガヤガヤとした雰囲気が感じられた。
足音や話し声からすると、ヒナコちゃんとハナちゃんみたいだ。
ヒナコちゃんとハナちゃんは、ひょっこり、この小部屋へ入ってきた。
「アイリ!大丈夫か?」
「アイリちゃん!」
二人は、騒ぎを聞きつけてここに来たようだ。
狭い会議室に、先生も入れて4人もいる。
「ヒナコちゃん、ハナちゃん…」
私が説明をしようとした。
その様子を見た先生は、何かを思いついたようだった。
「山吹さん、茨木さん。桔梗さんを保健室へ連れて行ってあげてください。」
先生は、話を進める。
「はい。」
「はーい。」
ハナちゃんとヒナコちゃんが先生にそう答えた。
「えっと。はい、分かりました。」
「桔梗さん。次の授業の先生には、私から伝えておくから。」
「…ありがとうございます。」
私が先生に礼をいうと、彼女は会議室から出て行った。
その様子を見た後で、二人が私に話しかけてきた。
「で、アイリ。何があったんだ?」
ヒナコちゃんが、真剣な表情で尋ねてきた。
私は、もう一度状況を説明した。
二人は、黙って私の話を聞いていた。
「そうか…。」
目を閉じて、何か考える雰囲気。
そんな凛々しい様子のヒナコちゃんは、そう静かに言った。
「ひどいよ!」
ハナちゃんはそう言って、私を慰めるようにいう。
そのあと私は、ヒナコちゃんとハナちゃんに付き添われながら、保健室へ向かった。
私とヒナコちゃん、ハナちゃんは授業が始まる時間まで、一緒に居た。
しかし、さすがに始業のチャイムが鳴ると二人は、教室へと向かった。
私は、先生が気を使ってくれていることもあって、1時間目の授業は休むことにした。
そいて、ベッドに横たわりながら、私は天井を見つめていた。
保健室の天井は、いつもの教室とは違う。
周囲に生徒がいないからか、どこか落ち着く雰囲気に満ちていた。
しばらくすると、担任の先生が保健室に入ってきた。
先生の表情は、とても深刻だった。
「桔梗さん、大丈夫?」
先生のほうが疲れを感じされる、そんな声だった。
「はい、大丈夫です。」
「学校側で話し合いをしました。その結果…藤原さんは、即日の停学処分となりました。」
「そうですか…。」
私は、そう答えるほかになかった。
「桔梗さん、このあとの授業はどう?出れそうかしら?」
先生は私に問いかけてきた。
私は少し考える。
「はい、2時間目からなら大丈夫です。」
「そう、分かったわ。無理はしないでね。」
私の言葉に、先生は少し安堵したようだった。
私は軽く会釈をして、先生の言葉に応えた。
そして、それを以て私の人生でも一か二を争うほどに、とんでもない出来事に一区切りがついたのだった。
保健室のベッドに横たわりながら、私は天井を見つめていた。
白い天井には、微かなシミがいくつか見えた。
それを数えながら、私は今日の出来事を思い返していた。
カリンちゃんの冷たい目線。
彼女の手に握られたカッターナイフ。
殺気だった様子で、私を追いかけてくるカリンちゃん。
とんでもない経験だった。
しかし、この保健室にいると、それらは出来の悪い悪夢の中の出来事だったかのようで。
まるで、今日の出来事が現実ではないかのようだ。
ふうっ。
私は一息ついて、ベッドから身を起こす。
そして、できるだけ普段通りの表情を作って、私は保健室を後にした。
その日、その後。
ヒナコちゃんとハナちゃんは、とても心配していたけれど。
私は、何事もなかったかのように学校生活を送った。
そして、放課後。
私とヒナコちゃん、ハナちゃんは一緒に、学校から家へ帰っていた。
「アイリちゃん、本当に大丈夫?」
ハナちゃんが、心配そうに尋ねてきた。
「うん、大丈夫よ。」
私はハナちゃんにそう答えた。
一方、ヒナコちゃんは先ほどからずっと黙って歩いていた。
なにかを彼女は何かを考えているようだった。
「もしかしたら、何か理由があったのかも…」
突然、ヒナコちゃんがそう言い出した。
その言葉に、ハナちゃんが驚いたように振り返る。
「え?それ、どういうこと、ヒナコちゃん?」
「いや、ただ…。」
ヒナコちゃんは言葉を選んでいるようだった。
「アイリちゃんがあんな目に遭ったのに!」
ハナちゃんが、ヒナコちゃんの言葉を遮るように声を上げた。
「あのな、ハナ、そうじゃなくて…。」
「どう考えてもカリンちゃんが悪いんだよ!」
ハナちゃんの声は大きくなっていく。
ヒナコちゃんも負けじと言い返す。
「しかしだな。理由もなく、こんなことするなんて…。」
「だからって、アイリちゃんを殺そうとするなんて!絶対におかしいよ!」
二人の言い合いは、どんどんエスカレートしていく。
「二人とも…私のことで喧嘩しないで。」
私は、小さな声で言った。
でも、二人の言い争いは収まらない。
気がつけば、私たちはいつもの別れ道に着いていた。
「じゃあ、私はここで…。」
その私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんの言い合いが止まった。
「ごめんね、アイリちゃん。つい…。」
ハナちゃんが、申し訳なさそうに言った。
「いや、ごめん。」
ヒナコちゃんも、俯いて言った。
「大丈夫よ。ありがとう、二人とも。」
私はそういって二人から距離を取るように、ささっと別れた。
それはどこか、ぎこちない雰囲気だった。
カリンちゃんの怒りに満ちた顔。
ハナちゃんとヒナコちゃんの言い争い。
どこまで行っても、争いの種は絶えない。
そんなことを思っていると、自宅が見えて来ていた。
ようやく、忙しかった一日が終わるのだ。
そう思った。
私の作品が壊された事件。
それ以降、私たちの間では、その話はしないことが暗黙の了解になっていた。
どこか、ヒナコちゃんもハナちゃんも何か思う所はあるようだった。
…その犯人が誰にしろ、である。
そして、その日は、私の作品が壊されて何日か経過しているある日だった。
朝、私が教室のドアを開けると、カリンちゃんの姿があった。
彼女は自席に座っていた。
私の心は、彼女と会話するように囁いた。
それに従って、カリンちゃんへ適度な距離に近づく。
私はできるだけ自然に振る舞おうと心掛けた。
「おはよう、カリンちゃん。」
私は、なるべく普通の声で挨拶をした。
カリンちゃんは、一瞬こちらを見たが、すぐに目をそらした。
しかし、今日はいつもと違う。
「うるさい。気持ち悪い。」
カリンちゃんは、珍しく言葉を返してきた。
カリンちゃんの言葉には、相変わらずの冷たさが込められていた。
しかし、これまで大きく違うのは、カリンちゃんが完全なる無視をしていない、ということだ。
会話ができる以上、何か前に進むことが出来る、私はそう思った。
「私、カリンちゃんに嫌われる理由が分からないのよ。」
私の言葉を聞いたカリンちゃんの目に一瞬、虚をつかれた様子で固まった。
続いて、驚きの色が浮かんだ。
しかし、すぐにその表情は怒りに変わった。
「お前!よくも、そんな白々しいことを!」
カリンちゃんの大声が、周囲に届く。
怒りしか感じられない。
だけど、このまま会話を続けるほかにない。
「カリンちゃん、私たち、最初はうまくいってたじゃない…」
私が言いかけると、カリンちゃんは更に声を荒げた。
「お前、いい子ぶりやがって…」
もはや、カリンちゃんは、まったく私の言葉を聞いていない。
その代わりに、まるで呪詛のように、なにかを繰り返し小さな声で発している。
カリンちゃんは、相当、頭に来ているようだ。
私は言葉を慎重に選ばなければならない。
ここで間違えれば、全てが台無しになってしまう。
そう思いながら、私は静かに口を開いた。
「そんなつもりはないわ。ねえ、カリンちゃん?」
私はゆっくりと話しかけた。
そのとき、カリンちゃんは自席から立ち上がった。
「黙れ!」
カリンちゃんは大声で一喝した。
彼女は、とても感情的になっている。
そして、カリンちゃんは、私の方へ近づいてきた。
彼女は、かつてないほどの憎しみに囚われていた。
「殺してやる!」
よく見ると、カリンちゃんの手には、カッターナイフが握られていた。
どうやら、私から見えないところで、彼女はそれを持っていたようだ。
おもわず、その様子を見た私は、後ずさる。
カリンちゃんは、尋常でない様子だ。
逃げないと!
私の頭の中で警報が鳴り響く。
「死ね!」
彼女はそう言って、こちらに向かってきた。
「やめて!」
私は、思わず叫ぶ。
そして、反射的に教室を飛び出した。
廊下を全力で走る。
間違いなく後ろから、カリンちゃんが走ってきている。
私の耳に、彼女の荒い息遣いが聞こえるかのような。
もし捕まれば、ただでは済まないだろう。
そう思うと、恐怖が込み上げてきた。
全力疾走。
逃げながら、私は、陸上部の見学の時に走った時を思い出す。
あのときと、違うのは、失敗が許されないことだ。
ああ、あの時は良かった。
なにしろ、あの時、隣にはハナちゃんがいたのだ。
廊下を走る。
私は、後ろを振り返った。
夜叉の如き表情をした、カリンちゃんが凶器を手に走ってきている。
逃げるしかない。
しかし、このまま逃げ続けても、逃げ切れる気はしない。
彼女との距離は、今の所、詰まられることはないが
このまま、引き離すほど、私の足は速くない。
どうすればいいの?
私は、人が多いところに逃げるべきと考えた。
そうだ!
職員室。
私は、それを実行に移す。
廊下を走る。
私は、後ろから追跡してくる彼女か確認しながら、職員室へ向かう。
息が上がり、足が重くなってきた。
でも、止まるわけにはいかない。
職員室の扉が見えた。
後ろの彼女までの距離は、扉を開くくらいの余裕はありそうだ。
希望が見えた気がした。
「あああああああああああ!!!!」
半狂乱となっているカリンちゃんの声。
職員室に入らないと!
扉に手を掛けて、一気に開ける。
ドンッ!
そして、飛び込むように、職員室へ入った。
想像以上の物音がした。
先生たちが私を見る。
しかし、それを気にする余裕はない。
扉を閉めないと!
目と鼻の先に彼女がいた。
それは殺気を感じるほどの。
彼女も私の後に続いて、室内へ入ろうとしていた。
ドンッ!
私は、一気に職員室の扉を閉めた。
ドンドンドン!
扉をたたく音。
「開けろ!死ね!殺すぞ!」
罵声。
カリンちゃんの声。
ドンドンドン!
彼女は職員室の扉を開けようとしている。
私は扉を開けられないように、抑える。
もちろん全体重を扉に掛ける。
「おい!うるさいぞ!」
「ちょっと!あなたたち!ここは職員室です!静かにしてください!」
「静かにしろ!」
職員にいた先生たちから檄が飛んだ。
どうやら、私たちがふざけている、と先生たちは勘違いしているようだ。
「助けてください!」
扉を抑えながら、私が叫ぶ。
その尋常でない様子に、先生たちが集まってきた。
先生たちが私の周囲に集まってくればくるほど、職員室の扉の向こうは静かになっていた。
そして、廊下にいる彼女の気配が消えた。
職員室前の廊下で、あれほど騒いでいるのだ。
もしかしたら、彼女は先生に捕まったのかもしれない。
「先生…カリンさんが…私を…。」
扉を抑えている私は、言葉が途切れ途切れになる。
騒ぎを聞きつけた担任の先生が、驚いた様子で駆け寄ってきた。
「落ち着いて。ゆっくり話してくれる?」
まるで先生の声が、遠くから聞こえてくるようだった。
私を殺そうとしているカリンちゃんは、もう廊下にいないようだった。
その状況になって、ようやく私は扉を抑えることをやめた。
緊張から解かれた私は、ヘナヘナと、職員室の一角へ力なく座り込む。
そして、ゆっくりと私は状況を説明しはじめた。
カリンちゃんとの対立、そして今朝の出来事。
言葉が混乱し、うまく伝わっているか分からなかったが、担任の先生は真剣な表情で私の話を聞いていた。
「分かりました。桔梗さん、立てる?」
「はい。」
私はようやく、自分の足で立った。
先ほどまで、命を狙われていたのだ。
ちょっとだけ落ち着いたとはいえ、まだ、完全ではない。
先生が、職員室にある会議室のソファーへ、私を座らせる。
パーティションで区切られた小さなスペースだ。
「桔梗さん、こっちでちょっと、待っていてね。」
「はい、分かりました。」
担任の先生は、他の教師たちと相談をするようだ。
私はソファーに座って、待つ。
少しづつ、落ち着きを取り戻しつつある私は、周囲を見た。
そこは奇しくも、私がクラス委員の仕事を命じられた場所だった。
しばらく待つと、担任の先生が戻ってきた。
「桔梗さん。あとは、私たちが対応します。」
「えっと。カリンちゃんは、どうなったんですか?」
私は、先生に聞く。
「それは…。これから対応を決めるところよ。」
担任の先生は、深刻そうな表情でそう言った。
「そうですか。」
「ああ、それで…桔梗さん?それでこれから、授業を受けられるかしら?もう少し休んだ方がいいなら…。」
担任の先生は、私に気を使っているようだ。
私は、どう答えようかと考えていた。
その時だった。
私と先生が話し合っている会議室。
そのパーティションの向こう側から、ガヤガヤとした雰囲気が感じられた。
足音や話し声からすると、ヒナコちゃんとハナちゃんみたいだ。
ヒナコちゃんとハナちゃんは、ひょっこり、この小部屋へ入ってきた。
「アイリ!大丈夫か?」
「アイリちゃん!」
二人は、騒ぎを聞きつけてここに来たようだ。
狭い会議室に、先生も入れて4人もいる。
「ヒナコちゃん、ハナちゃん…」
私が説明をしようとした。
その様子を見た先生は、何かを思いついたようだった。
「山吹さん、茨木さん。桔梗さんを保健室へ連れて行ってあげてください。」
先生は、話を進める。
「はい。」
「はーい。」
ハナちゃんとヒナコちゃんが先生にそう答えた。
「えっと。はい、分かりました。」
「桔梗さん。次の授業の先生には、私から伝えておくから。」
「…ありがとうございます。」
私が先生に礼をいうと、彼女は会議室から出て行った。
その様子を見た後で、二人が私に話しかけてきた。
「で、アイリ。何があったんだ?」
ヒナコちゃんが、真剣な表情で尋ねてきた。
私は、もう一度状況を説明した。
二人は、黙って私の話を聞いていた。
「そうか…。」
目を閉じて、何か考える雰囲気。
そんな凛々しい様子のヒナコちゃんは、そう静かに言った。
「ひどいよ!」
ハナちゃんはそう言って、私を慰めるようにいう。
そのあと私は、ヒナコちゃんとハナちゃんに付き添われながら、保健室へ向かった。
私とヒナコちゃん、ハナちゃんは授業が始まる時間まで、一緒に居た。
しかし、さすがに始業のチャイムが鳴ると二人は、教室へと向かった。
私は、先生が気を使ってくれていることもあって、1時間目の授業は休むことにした。
そいて、ベッドに横たわりながら、私は天井を見つめていた。
保健室の天井は、いつもの教室とは違う。
周囲に生徒がいないからか、どこか落ち着く雰囲気に満ちていた。
しばらくすると、担任の先生が保健室に入ってきた。
先生の表情は、とても深刻だった。
「桔梗さん、大丈夫?」
先生のほうが疲れを感じされる、そんな声だった。
「はい、大丈夫です。」
「学校側で話し合いをしました。その結果…藤原さんは、即日の停学処分となりました。」
「そうですか…。」
私は、そう答えるほかになかった。
「桔梗さん、このあとの授業はどう?出れそうかしら?」
先生は私に問いかけてきた。
私は少し考える。
「はい、2時間目からなら大丈夫です。」
「そう、分かったわ。無理はしないでね。」
私の言葉に、先生は少し安堵したようだった。
私は軽く会釈をして、先生の言葉に応えた。
そして、それを以て私の人生でも一か二を争うほどに、とんでもない出来事に一区切りがついたのだった。
保健室のベッドに横たわりながら、私は天井を見つめていた。
白い天井には、微かなシミがいくつか見えた。
それを数えながら、私は今日の出来事を思い返していた。
カリンちゃんの冷たい目線。
彼女の手に握られたカッターナイフ。
殺気だった様子で、私を追いかけてくるカリンちゃん。
とんでもない経験だった。
しかし、この保健室にいると、それらは出来の悪い悪夢の中の出来事だったかのようで。
まるで、今日の出来事が現実ではないかのようだ。
ふうっ。
私は一息ついて、ベッドから身を起こす。
そして、できるだけ普段通りの表情を作って、私は保健室を後にした。
その日、その後。
ヒナコちゃんとハナちゃんは、とても心配していたけれど。
私は、何事もなかったかのように学校生活を送った。
そして、放課後。
私とヒナコちゃん、ハナちゃんは一緒に、学校から家へ帰っていた。
「アイリちゃん、本当に大丈夫?」
ハナちゃんが、心配そうに尋ねてきた。
「うん、大丈夫よ。」
私はハナちゃんにそう答えた。
一方、ヒナコちゃんは先ほどからずっと黙って歩いていた。
なにかを彼女は何かを考えているようだった。
「もしかしたら、何か理由があったのかも…」
突然、ヒナコちゃんがそう言い出した。
その言葉に、ハナちゃんが驚いたように振り返る。
「え?それ、どういうこと、ヒナコちゃん?」
「いや、ただ…。」
ヒナコちゃんは言葉を選んでいるようだった。
「アイリちゃんがあんな目に遭ったのに!」
ハナちゃんが、ヒナコちゃんの言葉を遮るように声を上げた。
「あのな、ハナ、そうじゃなくて…。」
「どう考えてもカリンちゃんが悪いんだよ!」
ハナちゃんの声は大きくなっていく。
ヒナコちゃんも負けじと言い返す。
「しかしだな。理由もなく、こんなことするなんて…。」
「だからって、アイリちゃんを殺そうとするなんて!絶対におかしいよ!」
二人の言い合いは、どんどんエスカレートしていく。
「二人とも…私のことで喧嘩しないで。」
私は、小さな声で言った。
でも、二人の言い争いは収まらない。
気がつけば、私たちはいつもの別れ道に着いていた。
「じゃあ、私はここで…。」
その私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんの言い合いが止まった。
「ごめんね、アイリちゃん。つい…。」
ハナちゃんが、申し訳なさそうに言った。
「いや、ごめん。」
ヒナコちゃんも、俯いて言った。
「大丈夫よ。ありがとう、二人とも。」
私はそういって二人から距離を取るように、ささっと別れた。
それはどこか、ぎこちない雰囲気だった。
カリンちゃんの怒りに満ちた顔。
ハナちゃんとヒナコちゃんの言い争い。
どこまで行っても、争いの種は絶えない。
そんなことを思っていると、自宅が見えて来ていた。
ようやく、忙しかった一日が終わるのだ。
そう思った。