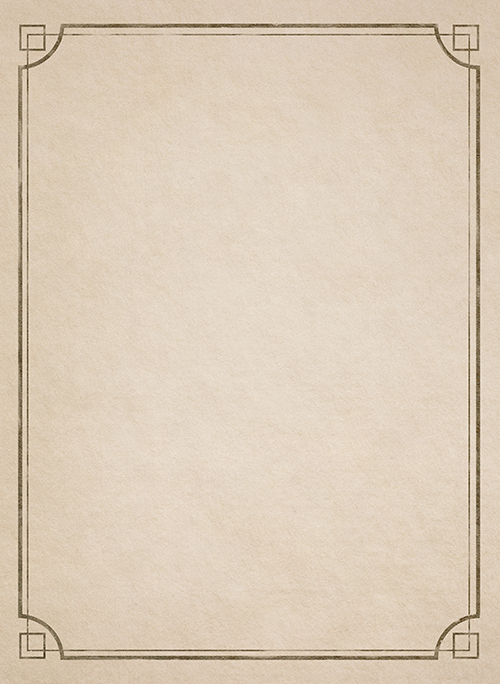第十四話
私とカリンちゃんとのすれ違い。
最終的に、それはあの日のことにつながった。
あの日の放課後に、起きてしまったちょっとした騒動。
それは、ハナちゃん、ヒナコちゃん、そして、担任の先生を巻き込んでしまった。
あの後、先生とカリンちゃんは何かを話したのだろうか?
私は、そのことについて先生から説明を受けていない。
そんな感じだから、もちろん、カリンちゃんとの関係も改善などしていない。
いや、率直にいって、私とカリンちゃんのわだかまりは解消されることはなく、広がっていく一方だった。
これでいいのだろうか?
けれども、一人で考えても何も変わることはない。
だから、その日も何ら状況が変わることなく、私は学校へ登校していた。
教室に入ると、カリンちゃんの姿はなかった。
カリンちゃんは、あの日以来、学校に来ない日も多くなった。
でも、もし仮に彼女が学校にいても、私への敵意は変わらないのだ。
一緒に何かを話すこともない。
何かが修復したり、発展することはない。
そんなことを思い返しながら私は、自分の席に着いた。
カリンちゃんの空席を見つめる。
休みがちな彼女。
学校を休んでいるときには何をするんだろう。
何を考えているんだろう。
…さすがに完全に理解不能だ。
だけども、私はクラス委員なのだ。
カリンちゃんと二人で。
だから、せめて彼女には毎日、学校に来てほしかった。
そんなことを考えていると、ハナちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリちゃん」
そう言って、ハナちゃんはカリンちゃんの席を見た。
「おはよう、ハナちゃん」
「カリンちゃん、今日、来てないね…。」
ハナちゃんが、小さな声で呟いた。
「ええ…」
私は、ため息をつきそうになるのを抑える。
そうして、私たちの日常は始まった。
時間は進む。
放課後となった。
私は一人でクラス委員の仕事を行っていた。
そして、黒板の予定を明日のモノへと書き換える。
チョークを動かしながら、ふと思った。
今日はヒナコちゃんが、手芸部に来るそうだ。
…珍しい。
正直な感想はそうだ。
なんでも、珍しく今日は陸上部の練習が無いらしい。
暇を持て余した彼女は、うちの部活を見学という名で遊びに来るのだ。
そんなことを思い返していると、クラス委員の仕事は終わった。
今、ハナちゃんとヒナコちゃんは、部室で先に何かをしていることだろう。
私は、その様子を思いながら、クスッと笑った。
手芸部の部室へと向かっていく。
部室に到着する、そして、いつものように部室の扉を開けた。
しかし、部室のドアを開けた私には、予想外の光景が広がっていた。
ハナちゃんとヒナコちゃんが、何かをじっと見ていたのだ。
どこか緊迫した雰囲気が感じられた。
二人は、私に気がついた。
アイリちゃんと、ヒナちゃんがこちらを見る。
その表情は優れない。
「どうしたの?二人とも」
私は、少し首を傾げながら尋ねた。
「あ、アイリちゃん!」
ハナちゃんは、少し慌てた様子だ。
「アイリ!その、大変なんだよ…。」
ヒナコちゃんも、SОS信号を発するかのような感じで話し始めるが。
言葉がそこで詰まっている。
さて、一体何だろう?
「どうしたの、ハナちゃん、ヒナコちゃん?」
私は、不安な気持ちを隠せない。
「これだよ。」
ヒナコちゃんは、棚に置いてある私の作品を見ていた。
私は、その視線の先を追う。
作品を置いてある棚だ。
手芸部の先輩方から、私たちの作品までが置かれている。
私の刺繍作品が、ズタズタになっていた。
布にビーズを縫い付けることで赤いバラを表現する私の作品。
生地がズタズタに切り裂かれていて、もはや原型が無い。
これでは作り直しだ。
「ひどいよ。」
いつも元気なハナちゃんが、力なく声を出す。
私は、じっと自分の作品を見つめていた。
これまでの努力が、一瞬にして無に帰してしまったのだ。
「誰がこんなことを…」
ヒナコちゃんの声には、怒りが込められていた。
私は、ゆっくりと裂かれた刺繍に手を伸ばした。
指先で触れると、糸によって止められていた赤いビーズがボロボロと落ちた。
それはまるで作品が流している血の涙のように見えた。
「アイリちゃん…」
ハナちゃんはそれだけ言って、言葉が詰まる。
私も同じように何も言えなかった。
しばし、沈黙が続いていた。
「もしかして…カリンちゃん?」
私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんは驚いた表情を浮かべた。
「まさか…。」
ハナちゃんが、信じられないという顔をした。
「いや、しかし、でも…。」
ヒナコちゃんの言葉が、途中で止まった。
私たちは、お互いの顔を見合わせた。
誰も、その可能性を否定できなかった。
「でも、なんでカリンちゃんがそんなことを…」
ハナちゃんの声が震えていた。
「分からないわ。」
私は、小さく呟いた。
「とりあえず、先生に報告しよう。」
ヒナコちゃんが、冷静に言った。
私とハナちゃんは、黙って頷いた。
私たちは、部室から職員室へと移動する。
もちろん、先生に相談するのだ。
事情を知っている、担任の先生へ。
廊下を歩く、私たちはいつになく静かだった。
話しかけづらい雰囲気がある。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、小さな声で話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「本当に…カリンちゃんがやったと思う?」
ハナちゃんの目には、不安と悲しみが浮かんでいた。
「私にも…分からないわ」
私は、正直に答えた。
「でも、カリンじゃない可能性だってあるだろ。」
ヒナコちゃんが、どこか思いつめた表情で言った。
「そうだよね…。」
私は、小さく頷いた。
そして、言葉を続けた。
「きっと、私に非があったんだわ。」
私は、思わず口に出してしまった。
「そんなことないよ!」
ハナちゃんが、涙ぐみながら言った。
「そうだ。アイリ、お前は何も悪くない。」
ヒナコちゃんも、強く言った。
二人の言葉に、私は少し心が和らいだ。
でも、まだ胸の奥には何かの感情が残っている。
私はそれを解消しなければならない、と思う。
それがなくなる日は来るのだろうか。
それは分からない。
職員室へ着いた、私たちは担任の先生に報告した。
先生は、深刻な表情で私たちの話を聞いていた。
「分かりました。調査します。」
どこか疲れたような様子の先生。
その言葉に、私たちは小さく頷くほかなかった。
それから、私たちは部活どころではなかった。
そのまま、家に帰ることにした。
私とハナちゃん、ヒナコちゃん。
三人で家に帰る。
隣にいる二人。
その様子は暗い。
あんなことがあったのだ、仕方がない。
だけど、私にはこの二人がいてくれて、良かったと思った。
「アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然、私に声をかけてきた。
「何?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「私たち、一緒に頑張ろうね。」
ハナちゃんの目には、優しさがある。
「そうだな。私たちは親友だからな。」
ヒナコちゃんも、力強く言った。
「ええ、もちろんよ。」
私は、二人の言葉の言葉に感謝しながら、そう答える。
そして、私は思った。
これから三人が帰る家は違うけれど、今、この瞬間の私たちは同じ道を歩んでいるんだ、と。
私は、その事実を思い返しながら、一緒に帰る道を進んでいった。
私とカリンちゃんとのすれ違い。
最終的に、それはあの日のことにつながった。
あの日の放課後に、起きてしまったちょっとした騒動。
それは、ハナちゃん、ヒナコちゃん、そして、担任の先生を巻き込んでしまった。
あの後、先生とカリンちゃんは何かを話したのだろうか?
私は、そのことについて先生から説明を受けていない。
そんな感じだから、もちろん、カリンちゃんとの関係も改善などしていない。
いや、率直にいって、私とカリンちゃんのわだかまりは解消されることはなく、広がっていく一方だった。
これでいいのだろうか?
けれども、一人で考えても何も変わることはない。
だから、その日も何ら状況が変わることなく、私は学校へ登校していた。
教室に入ると、カリンちゃんの姿はなかった。
カリンちゃんは、あの日以来、学校に来ない日も多くなった。
でも、もし仮に彼女が学校にいても、私への敵意は変わらないのだ。
一緒に何かを話すこともない。
何かが修復したり、発展することはない。
そんなことを思い返しながら私は、自分の席に着いた。
カリンちゃんの空席を見つめる。
休みがちな彼女。
学校を休んでいるときには何をするんだろう。
何を考えているんだろう。
…さすがに完全に理解不能だ。
だけども、私はクラス委員なのだ。
カリンちゃんと二人で。
だから、せめて彼女には毎日、学校に来てほしかった。
そんなことを考えていると、ハナちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリちゃん」
そう言って、ハナちゃんはカリンちゃんの席を見た。
「おはよう、ハナちゃん」
「カリンちゃん、今日、来てないね…。」
ハナちゃんが、小さな声で呟いた。
「ええ…」
私は、ため息をつきそうになるのを抑える。
そうして、私たちの日常は始まった。
時間は進む。
放課後となった。
私は一人でクラス委員の仕事を行っていた。
そして、黒板の予定を明日のモノへと書き換える。
チョークを動かしながら、ふと思った。
今日はヒナコちゃんが、手芸部に来るそうだ。
…珍しい。
正直な感想はそうだ。
なんでも、珍しく今日は陸上部の練習が無いらしい。
暇を持て余した彼女は、うちの部活を見学という名で遊びに来るのだ。
そんなことを思い返していると、クラス委員の仕事は終わった。
今、ハナちゃんとヒナコちゃんは、部室で先に何かをしていることだろう。
私は、その様子を思いながら、クスッと笑った。
手芸部の部室へと向かっていく。
部室に到着する、そして、いつものように部室の扉を開けた。
しかし、部室のドアを開けた私には、予想外の光景が広がっていた。
ハナちゃんとヒナコちゃんが、何かをじっと見ていたのだ。
どこか緊迫した雰囲気が感じられた。
二人は、私に気がついた。
アイリちゃんと、ヒナちゃんがこちらを見る。
その表情は優れない。
「どうしたの?二人とも」
私は、少し首を傾げながら尋ねた。
「あ、アイリちゃん!」
ハナちゃんは、少し慌てた様子だ。
「アイリ!その、大変なんだよ…。」
ヒナコちゃんも、SОS信号を発するかのような感じで話し始めるが。
言葉がそこで詰まっている。
さて、一体何だろう?
「どうしたの、ハナちゃん、ヒナコちゃん?」
私は、不安な気持ちを隠せない。
「これだよ。」
ヒナコちゃんは、棚に置いてある私の作品を見ていた。
私は、その視線の先を追う。
作品を置いてある棚だ。
手芸部の先輩方から、私たちの作品までが置かれている。
私の刺繍作品が、ズタズタになっていた。
布にビーズを縫い付けることで赤いバラを表現する私の作品。
生地がズタズタに切り裂かれていて、もはや原型が無い。
これでは作り直しだ。
「ひどいよ。」
いつも元気なハナちゃんが、力なく声を出す。
私は、じっと自分の作品を見つめていた。
これまでの努力が、一瞬にして無に帰してしまったのだ。
「誰がこんなことを…」
ヒナコちゃんの声には、怒りが込められていた。
私は、ゆっくりと裂かれた刺繍に手を伸ばした。
指先で触れると、糸によって止められていた赤いビーズがボロボロと落ちた。
それはまるで作品が流している血の涙のように見えた。
「アイリちゃん…」
ハナちゃんはそれだけ言って、言葉が詰まる。
私も同じように何も言えなかった。
しばし、沈黙が続いていた。
「もしかして…カリンちゃん?」
私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんは驚いた表情を浮かべた。
「まさか…。」
ハナちゃんが、信じられないという顔をした。
「いや、しかし、でも…。」
ヒナコちゃんの言葉が、途中で止まった。
私たちは、お互いの顔を見合わせた。
誰も、その可能性を否定できなかった。
「でも、なんでカリンちゃんがそんなことを…」
ハナちゃんの声が震えていた。
「分からないわ。」
私は、小さく呟いた。
「とりあえず、先生に報告しよう。」
ヒナコちゃんが、冷静に言った。
私とハナちゃんは、黙って頷いた。
私たちは、部室から職員室へと移動する。
もちろん、先生に相談するのだ。
事情を知っている、担任の先生へ。
廊下を歩く、私たちはいつになく静かだった。
話しかけづらい雰囲気がある。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、小さな声で話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「本当に…カリンちゃんがやったと思う?」
ハナちゃんの目には、不安と悲しみが浮かんでいた。
「私にも…分からないわ」
私は、正直に答えた。
「でも、カリンじゃない可能性だってあるだろ。」
ヒナコちゃんが、どこか思いつめた表情で言った。
「そうだよね…。」
私は、小さく頷いた。
そして、言葉を続けた。
「きっと、私に非があったんだわ。」
私は、思わず口に出してしまった。
「そんなことないよ!」
ハナちゃんが、涙ぐみながら言った。
「そうだ。アイリ、お前は何も悪くない。」
ヒナコちゃんも、強く言った。
二人の言葉に、私は少し心が和らいだ。
でも、まだ胸の奥には何かの感情が残っている。
私はそれを解消しなければならない、と思う。
それがなくなる日は来るのだろうか。
それは分からない。
職員室へ着いた、私たちは担任の先生に報告した。
先生は、深刻な表情で私たちの話を聞いていた。
「分かりました。調査します。」
どこか疲れたような様子の先生。
その言葉に、私たちは小さく頷くほかなかった。
それから、私たちは部活どころではなかった。
そのまま、家に帰ることにした。
私とハナちゃん、ヒナコちゃん。
三人で家に帰る。
隣にいる二人。
その様子は暗い。
あんなことがあったのだ、仕方がない。
だけど、私にはこの二人がいてくれて、良かったと思った。
「アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然、私に声をかけてきた。
「何?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「私たち、一緒に頑張ろうね。」
ハナちゃんの目には、優しさがある。
「そうだな。私たちは親友だからな。」
ヒナコちゃんも、力強く言った。
「ええ、もちろんよ。」
私は、二人の言葉の言葉に感謝しながら、そう答える。
そして、私は思った。
これから三人が帰る家は違うけれど、今、この瞬間の私たちは同じ道を歩んでいるんだ、と。
私は、その事実を思い返しながら、一緒に帰る道を進んでいった。