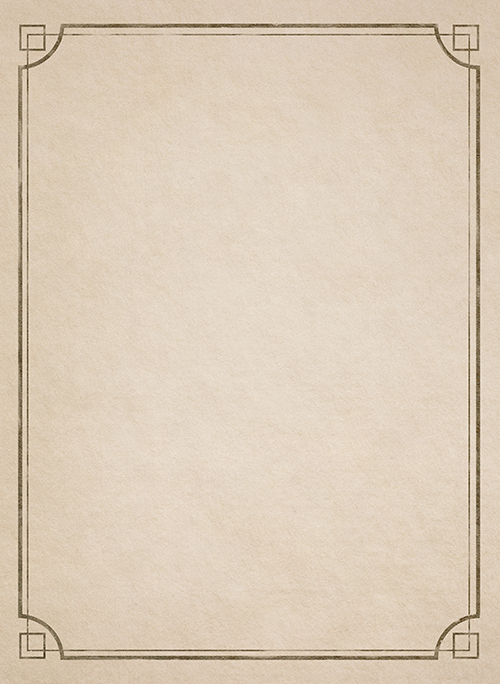第十三話
次の日。
いつものように私は校門をくぐる。
教室のドアを開けると、すでにカリンちゃんの姿があった。
なんだかんだ言って、彼女はクラス委員になってから早い時間で投稿しているようだ。
彼女は窓際の席で、外を眺めていた。
「おはよう、カリンちゃん。」
私は、できるだけ普通の声で挨拶をした。
しかし、カリンちゃんの反応は相変わらずだった。
彼女は一瞬だけこちらを見る。
しかし、その後は、完全に私がいないものかのような態度だ。
私は、少し躊躇いながらも自分の席に向かった。
カリンちゃんとの距離感を感じた。
しばらくすると、生徒たちが教室に入ってくる。
徐々に教室内が騒がしくなっていく。
私は、その中で一人、自席についていた。
今日は、小説を読む気にはならない。
教室に入ってくる生徒、カリンちゃんを観察する。
そんなことをしていると、ヒナコちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリ。」
ヒナコちゃんが、いつもの調子で声をかけてきた。
「おはよう、ヒナコちゃん。」
私は、笑みを作ってから返事をした。
「ちょっと、アイリ。」
そういうと、ヒナコちゃんが耳打ちをしてきた。
私は、聞く態勢に入る。
「…さっき、先生と話してきたぞ。」
ヒナコちゃんが、小声で言った。
「え?何て言われたの?」
「先生も心配しているらしい。カリンの様子がおかしいってさ。」
ヒナコちゃんの言葉。
それによれば、カリンちゃんの変化は、先生の目にも映っているようだ。
「それで、どうなるの?」
私は、続きを尋ねる。
「先生が、それとなくカリンと話をしてみるって。でも、まずは様子を見るそうだ。」
ヒナコちゃんの言葉に、私は小さく頷いた。
そのとき、ハナちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリちゃん、ヒナコちゃん!」
ハナちゃんの明るい声が、教室に響いた。
「おはよう、ハナちゃん」
私とヒナコちゃんは、同時に返事をした。
ハナちゃんは、昨日からの話を思い出しているようだ。
そして、二人でコソコソと話しているかのような雰囲気を察したのか。
「二人とも、どうしたいの?」
ハナちゃんは聞いてきた。
「うん。なんでもないわ。」
私は、できるだけ明るく答えた。
「そう?」
ハナちゃんは、そう言って、それ以上は聞いてこなかった。
それにハナちゃんは手芸部で話せる。
私はそう思った。
それから、私たちはいつもの雰囲気を取り戻した。
なんとかいつものように、適当な話題を話す。
すると、チャイムが鳴った。
授業が始まる合図だ。
私たちは、それぞれの席に着いた。
授業中、私は何度もカリンちゃんの方を見てしまう。
彼女は、相変わらず無表情で前を向いていた。
昼休み。
私たちは、一緒に昼食を取っていた。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然声をかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「カリンちゃんのこと、私にも何かできることない?」
ハナちゃんは純粋にそう質問をしているようだ。
「ハナちゃん…」
私は、言葉につまった。
なんて言えばいいのか、分からない。
「でも、今はカリンを刺激しない方がいいかもしれない。」
隣でヒナコちゃんが、冷静に言った。
「そっか…」
ハナちゃんは、少し寂しそうな顔をする。
そして、ハナちゃんはヒナコちゃんと話をし始めた。
私は、二人の会話を聞きながら、カリンちゃんの方を見た。
彼女は今日も一人で昼食を取っていた。
その姿を見ていると、何か思う所はあった。
そして、特に事態が変わらないまま時間は流れる。
放課後となる。
つまり、私はカリンちゃんと一緒に仕事をするのだ。
さて、今日はどうなるのか。
先生が何かをしたのだろうか?
…分からない。
私は、少し緊張しながらカリンちゃんの席に近づいた。
クラス委員の仕事がある。
たとえ彼女が冷たくても、私は諦めるわけにはいかない。
「カリンちゃん、今日の仕事を…。」
私の言葉が途中で止まった。
カリンちゃんが、突然一方的に話し始めた。
「あんた、みんなの前でいい子ぶってさ。本当は違うんでしょ?」
カリンちゃんの声には、明確な敵意がある。
「え?」
そう言われた私は、驚いた声を上げる。
「カリン!」
ヒナコちゃんの声が、教室に響いた。
彼女が、私たちの間に立った。
「何を言ってるんだ?アイリが何をしたって言うんだ?」
ヒナコちゃんは、カリンちゃんに怒っている。
私を守ろうとしているのだ。
「ヒナコちゃん…」
私は、ヒナコちゃんがそれ以上、カリンちゃんへ強い言葉をかけることを止めようとした。
ヒナコちゃんの怒りが、カリンちゃんの心には、どのように作用するのか分からない。
「偽善者!」
カリンちゃんが、突然叫んだ。
その声に、教室にいた数人の生徒が驚いて振り返った。
「カリンちゃん、落ち着いて」
するとハナちゃんも、カリンちゃんに近づこうとした。
「私に近づかないで!」
カリンちゃんの声が、さらに大きくなった。
私は、その光景を見ていることしかできない。
「カリンさん、どうしたの?」
担任の先生が、教室に入ってきた。
先生の声に、カリンちゃんは一瞬硬直した。
そして、次の瞬間。
カリンちゃんは、教室を飛び出していった。
「カリンちゃん!」
私は、思わず声を上げた。
でも、彼女の姿はもう見えなかった。
「アイリちゃん、大丈夫?」
ハナちゃんが、私の肩に手を置いた。
「え?ええ…」
私は、ハナちゃんへそう答えた。
「みんな、落ち着いて」
先生が、クラスの生徒たちに声をかけた。
「桔梗さん、大丈夫?結局、何があったの?」
先生が、優しく尋ねてきた。
「えっと。私も…よく分からなくて…。」
私は、状況を説明したかった。
…しかし、先生にはそう説明するしかなかった。
「山吹さんから、桔梗さんと藤原さんについて聞いているわ。」
先生は、私に話しかけてきた。
「えっと。見ての通りなんです。」
「そうですか。」
状況を理解した先生は、どこか遠い目をした。
「アイリ…。」
ヒナコちゃんが、心配そうに私を見ていた。
教室には、重苦しい空気が漂っていた。
何かあったことを察した周囲の生徒は、教室からさっさと抜けていく。
その教室の中で私は、これからどうすればいいのか考える。
人間関係は刺繍のようにはいかないのだ。
…ただ、一つだけ確かなことがあった。
私は、カリンちゃんとの関係を上手く…したいということだ。
たとえ、それがどれほど難しくても。
「…先生、私はカリンちゃんともう少し頑張ってみます。」
「…。」
先生は、答えてこない。
「その、こうなってしまった、何か…。原因があるはずです。」
「分かったわ、でも何かあったらすぐに報告する事。それが条件よ。」
先生は私にそう言って、教室から出て行った。
たぶん、カリンちゃんを探しにでも言ったのだろう。
「アイリ、それで良かったのか?」
「ええ。私は…。ごめんなさい。ハナちゃん、ヒナコちゃん。」
私はヒナコちゃんとハナちゃんに謝る。
「そんなことはないぞ。私たち、親友だろ。」
「そうだよ、アイリちゃん!」
二人は努めて歩く答えているようだ。
「ありがとう。」
私はそんな二人にお礼をいう他になかった。
次の日。
いつものように私は校門をくぐる。
教室のドアを開けると、すでにカリンちゃんの姿があった。
なんだかんだ言って、彼女はクラス委員になってから早い時間で投稿しているようだ。
彼女は窓際の席で、外を眺めていた。
「おはよう、カリンちゃん。」
私は、できるだけ普通の声で挨拶をした。
しかし、カリンちゃんの反応は相変わらずだった。
彼女は一瞬だけこちらを見る。
しかし、その後は、完全に私がいないものかのような態度だ。
私は、少し躊躇いながらも自分の席に向かった。
カリンちゃんとの距離感を感じた。
しばらくすると、生徒たちが教室に入ってくる。
徐々に教室内が騒がしくなっていく。
私は、その中で一人、自席についていた。
今日は、小説を読む気にはならない。
教室に入ってくる生徒、カリンちゃんを観察する。
そんなことをしていると、ヒナコちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリ。」
ヒナコちゃんが、いつもの調子で声をかけてきた。
「おはよう、ヒナコちゃん。」
私は、笑みを作ってから返事をした。
「ちょっと、アイリ。」
そういうと、ヒナコちゃんが耳打ちをしてきた。
私は、聞く態勢に入る。
「…さっき、先生と話してきたぞ。」
ヒナコちゃんが、小声で言った。
「え?何て言われたの?」
「先生も心配しているらしい。カリンの様子がおかしいってさ。」
ヒナコちゃんの言葉。
それによれば、カリンちゃんの変化は、先生の目にも映っているようだ。
「それで、どうなるの?」
私は、続きを尋ねる。
「先生が、それとなくカリンと話をしてみるって。でも、まずは様子を見るそうだ。」
ヒナコちゃんの言葉に、私は小さく頷いた。
そのとき、ハナちゃんが教室に入ってきた。
「おはよう、アイリちゃん、ヒナコちゃん!」
ハナちゃんの明るい声が、教室に響いた。
「おはよう、ハナちゃん」
私とヒナコちゃんは、同時に返事をした。
ハナちゃんは、昨日からの話を思い出しているようだ。
そして、二人でコソコソと話しているかのような雰囲気を察したのか。
「二人とも、どうしたいの?」
ハナちゃんは聞いてきた。
「うん。なんでもないわ。」
私は、できるだけ明るく答えた。
「そう?」
ハナちゃんは、そう言って、それ以上は聞いてこなかった。
それにハナちゃんは手芸部で話せる。
私はそう思った。
それから、私たちはいつもの雰囲気を取り戻した。
なんとかいつものように、適当な話題を話す。
すると、チャイムが鳴った。
授業が始まる合図だ。
私たちは、それぞれの席に着いた。
授業中、私は何度もカリンちゃんの方を見てしまう。
彼女は、相変わらず無表情で前を向いていた。
昼休み。
私たちは、一緒に昼食を取っていた。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然声をかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「カリンちゃんのこと、私にも何かできることない?」
ハナちゃんは純粋にそう質問をしているようだ。
「ハナちゃん…」
私は、言葉につまった。
なんて言えばいいのか、分からない。
「でも、今はカリンを刺激しない方がいいかもしれない。」
隣でヒナコちゃんが、冷静に言った。
「そっか…」
ハナちゃんは、少し寂しそうな顔をする。
そして、ハナちゃんはヒナコちゃんと話をし始めた。
私は、二人の会話を聞きながら、カリンちゃんの方を見た。
彼女は今日も一人で昼食を取っていた。
その姿を見ていると、何か思う所はあった。
そして、特に事態が変わらないまま時間は流れる。
放課後となる。
つまり、私はカリンちゃんと一緒に仕事をするのだ。
さて、今日はどうなるのか。
先生が何かをしたのだろうか?
…分からない。
私は、少し緊張しながらカリンちゃんの席に近づいた。
クラス委員の仕事がある。
たとえ彼女が冷たくても、私は諦めるわけにはいかない。
「カリンちゃん、今日の仕事を…。」
私の言葉が途中で止まった。
カリンちゃんが、突然一方的に話し始めた。
「あんた、みんなの前でいい子ぶってさ。本当は違うんでしょ?」
カリンちゃんの声には、明確な敵意がある。
「え?」
そう言われた私は、驚いた声を上げる。
「カリン!」
ヒナコちゃんの声が、教室に響いた。
彼女が、私たちの間に立った。
「何を言ってるんだ?アイリが何をしたって言うんだ?」
ヒナコちゃんは、カリンちゃんに怒っている。
私を守ろうとしているのだ。
「ヒナコちゃん…」
私は、ヒナコちゃんがそれ以上、カリンちゃんへ強い言葉をかけることを止めようとした。
ヒナコちゃんの怒りが、カリンちゃんの心には、どのように作用するのか分からない。
「偽善者!」
カリンちゃんが、突然叫んだ。
その声に、教室にいた数人の生徒が驚いて振り返った。
「カリンちゃん、落ち着いて」
するとハナちゃんも、カリンちゃんに近づこうとした。
「私に近づかないで!」
カリンちゃんの声が、さらに大きくなった。
私は、その光景を見ていることしかできない。
「カリンさん、どうしたの?」
担任の先生が、教室に入ってきた。
先生の声に、カリンちゃんは一瞬硬直した。
そして、次の瞬間。
カリンちゃんは、教室を飛び出していった。
「カリンちゃん!」
私は、思わず声を上げた。
でも、彼女の姿はもう見えなかった。
「アイリちゃん、大丈夫?」
ハナちゃんが、私の肩に手を置いた。
「え?ええ…」
私は、ハナちゃんへそう答えた。
「みんな、落ち着いて」
先生が、クラスの生徒たちに声をかけた。
「桔梗さん、大丈夫?結局、何があったの?」
先生が、優しく尋ねてきた。
「えっと。私も…よく分からなくて…。」
私は、状況を説明したかった。
…しかし、先生にはそう説明するしかなかった。
「山吹さんから、桔梗さんと藤原さんについて聞いているわ。」
先生は、私に話しかけてきた。
「えっと。見ての通りなんです。」
「そうですか。」
状況を理解した先生は、どこか遠い目をした。
「アイリ…。」
ヒナコちゃんが、心配そうに私を見ていた。
教室には、重苦しい空気が漂っていた。
何かあったことを察した周囲の生徒は、教室からさっさと抜けていく。
その教室の中で私は、これからどうすればいいのか考える。
人間関係は刺繍のようにはいかないのだ。
…ただ、一つだけ確かなことがあった。
私は、カリンちゃんとの関係を上手く…したいということだ。
たとえ、それがどれほど難しくても。
「…先生、私はカリンちゃんともう少し頑張ってみます。」
「…。」
先生は、答えてこない。
「その、こうなってしまった、何か…。原因があるはずです。」
「分かったわ、でも何かあったらすぐに報告する事。それが条件よ。」
先生は私にそう言って、教室から出て行った。
たぶん、カリンちゃんを探しにでも言ったのだろう。
「アイリ、それで良かったのか?」
「ええ。私は…。ごめんなさい。ハナちゃん、ヒナコちゃん。」
私はヒナコちゃんとハナちゃんに謝る。
「そんなことはないぞ。私たち、親友だろ。」
「そうだよ、アイリちゃん!」
二人は努めて歩く答えているようだ。
「ありがとう。」
私はそんな二人にお礼をいう他になかった。