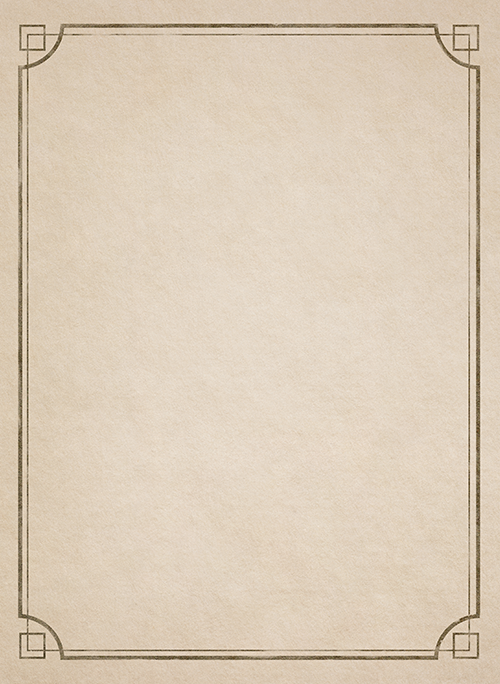第一話
私は、休み時間の教室にいた。
周囲は喧騒に包まれ、クラスメイトたちの楽しげな笑い声や話し声が環境に満ち満ちている。
彼らは、まるで鳥たちが囀るかのように、その存在を示していた。
一言でいうならば、これこそが青春というものだろう。
生命力にあふれた、正の力めいたもの。
しかし、私にはそれらが遠くから聞こえてくるような気がしていた。
もちろん、その情景には私も含まれている。
そんな私は、ごく一般的な女子高生だ。
この教室にいるのだから、当然といえば当然だ。
ここは部外者立ち入り禁止の空間。
まるで青春を送るものにしか、入ることが許されない場所のようだ。
その中で、私は微妙な距離感を保っている。
クラスメイトたちと同じ制服を着て、同じ教室で授業を受け、同じ空気を吸っている。
けれど、どこか一線を引いているような感覚がある。
私はこの高校に所属し、学校に通い、クラスに属している。
教室では自分の机が与えられ、学校の規則に従う。
この喧騒の中で、私一人だけが浮いているように感じるが、それは決して不快ではない。
むしろ、この距離感が心地よいとさえ思える。
私には私の距離感があるのだ。
それは私の持つ感性、そしてこれまでの学校での振る舞いの結果なのかもしれない。
ただ、一つだけ確実なのは、私もまた青春の真っ只中にいるということだ。
もしこの状況を絵画で例えるならば、私は背景に描かれている無名な人物の一人だろう。
それは、絵の中心で輝く主役たちの存在とは対照的だ。
しかし、中心が輝くのは背景があるからこそ。
彼らが光り輝けば輝くほど、私の存在は薄く陰っていく。
ただ、それらは陰と陽の関係のように、決してお互いがなくなることはない。
お互いが存在するからこそ、この教室という小さな宇宙のバランスが保たれているのだ。
その陰の部分を担う存在として、私は自分の役割を果たしている。
私の目や耳は、自然と教室の隅々の情報を収集していく。
クラスメイトたちの一つ一つの仕草、表情の変化、言葉の抑揚。
それらの情報が私の中で溜まっていく。
暇を持て余している私は、それらを心の中で分析していく。
観察から得た情報から、私は周囲の状況を推測する。
誰がどんな性格で、誰と誰が仲が良くて、誰が誰のことをどう考えているのか。
人間関係の綾を、私は頭の中で推測を進めていくのだ。
そんなひと時。
ふと、教室の後ろの方に目をやると、藤原カリンの姿が目に入った。
彼女もまた、この賑やかな空間の中で一人静かにしている。
私たちの役割は似たようなものなのかもしれない、ふと、私はそんなことを考えた。
窓際の席に座った私は、静かに本を開いていた。
ページをめくる音さえ、この騒がしい空間では飲み込まれてしまいそうだ。
それでも、私は気にせず読書に没頭していた。
読んでいる本は、人間関係の機微を描いた青春小説だ。
登場人物たちが織りなす複雑な関係性に、私は引き込まれていく。
彼らの悩み、喜び、葛藤。
それらはどこか滑稽で、同時に痛々しい。
それはまるで現実のつまらないところを無くしてしまったような。
濃度100%の還元ジュースのようなもの。
それは、ドロドロに煮詰まった現実のようで、ある意味、現実よりも現実らしい。
そんな現実の塊を読み流しながら、私は思った。
これが私の現実でなくて良かった、と。
「アイリちゃん、また本、読んでるの?」
突然、明るい声が耳元に届いた。
その声には、私の名前である、アイリという名が含まれている。
…私を呼んでいる。
顔を上げると、茨木ハナが私の机の前に立っていた。
茨木ハナは、私と同じクラス、同じ部活に所属する女子生徒だ。
同世代と比べると、ちょっと小柄な体型だけど。
それがまたハナちゃんらしい。
ハナちゃんというのは、彼女への呼び名だ。
だから、というのはおかしいけれど。
そんなハナちゃんと私は、友達だ。
そう、友達なのだ。
桔梗アイリと茨木ハナは同じ手芸部に所属する、友達。
この教室において、間違いなく私たちはそういう関係だった。
友達である私たちは、普段、休み時間や部活動中に話をする。
そして、一緒に学校から帰るときもある。
だから、私は知っている。
ハナちゃんは、底抜けに明るい。
前向きで、ひたむきで。
こちらを覗き込んでくるハナちゃんの笑顔は、まるで太陽のように輝いている。
「ええ。だって、面白いわよ?この本?」
私は、ハナちゃんにそう返事をしながら、本をパタンと閉じた。
「ふーん?それ、どんな本なの?」
「人間関係を描いた小説。友情や恋愛、そういったものがテーマになってるの」
「へぇー、アイリちゃんらしい!」
私の前にいるハナちゃんは、何かに感心したように続ける。
「私は本を読まないから、難しいな、って。」
「そんなことはないわ。この前の国語のテスト、ハナちゃんと私の点数、同じだったよね?」
「うーん?そうだけど。そうだけどさ。」
ハナちゃんは、なんて言っていいのか分からないみたい。
「小説読むの、難しいもん。」
「そうかしら?」
私は、ハナちゃんに、なんて言えばいいのか思案した。
簡単?
いや、そんな説明じゃダメだろうな。
「人の心って、複雑で面白いと思うの」
「うん?そうだね?」
私の言葉に、ハナちゃんは首を傾げた。
「この読んでいる本にはね、そういう人の考えていることが書かれているの。」
「そうなんだ。」
「だから、読んでいるとすぐに面白さがわかるわ。」
私は、ハナちゃんに説明をする。
この説明でどうだろうか?
「…うーん?そうかなー?」
あまり、共感されなかったみたいだ。
「ハナちゃんだって、噂話とか好きでしょ?」
「えー。まー、そのー。明るい話なら…好きかな?」
モジモジとしながら、ハナちゃんが同意する。
実際、ハナちゃんはゴシップが大好きだ。
…確かに、それを自ら大っぴらに認めるのは、確かにどうかと思う。
それが今の態度に現れている。
「…でも、本当にアイリちゃんって、いろいろな話を聞いているよね。私なんて、周りのことなんてあまり気にしないのに。」
「そうかしら?ハナちゃんの方が、私よりも話している人が幅広いと思うけど。」
私は、話を広がらないように、そう返事をする。
「そんなことないよ!」
「そう?」
「だって、アイリちゃんがこの間、言っていたこと。私、知らなかったもん!」
えっと、それってなんだっけ?
私は思い起こす。
一緒に帰ったときのこと?
いや、違う。
…ああ、そうか。
先週の出来事のことを言っているのね。
「ああ、あれのこと?あの二人が付き合い始めたって話?」
ハナちゃんは目を丸くした。
「そう!それ、それ!アイリちゃん、どうやって知ったの?」
「ただの偶然なのよ。だって、二人が図書室で話しているのを聞いちゃっただけ」
それはそう、本当に偶然だった。
小声で、とはいえ。
そんな場所でそんなことを話す、二人もどうかと思うんだけど。
「ふーん。なるほど。やっぱり、アイリちゃんは凄いね!」
ハナちゃんは感心したように言った。
…そう。
それは、あの静かな雰囲気の図書室で。
二人の話し声が聞こえないはずがないのだ。
あの二人にとっての問題は、周囲に私がいたことを確認していなかったことだろうけども。
「でも、あの二人はアイリちゃんへ相談したりはしなかったんだね!」
「え?どういうこと?」
ハナちゃんの言葉に、私は少し考え込んだ。
いやいや?
ある意味、盗み聞いていたようなものだから!
どこかハナちゃんが勘違いしているような?
「あのね?」
私が弁解しようとしたとき。
ハナちゃんは自分の世界に入ったように、うっとりとした表情で私を見ていた。
「えっと?ハナちゃん?」
「アイリちゃん!やっぱり、アイリちゃんは凄い!」
???
私は首を傾げる。
「だって、二人のキューピットになったんでしょ?」
「えっと?」
「私ならできないよー。」
論理の飛躍。
どうやら、ハナちゃんの中では、私が二人を引き合わせたことになったらしい。
「あのね。ハナちゃん。あの二人はね。私が知った時には付き合っていたのよ?」
「えー?でも、アイリちゃんっていつも誰かの相談に乗ってるイメージだよ?」
「そうかしら?」
確かに私は、人の愚痴を聞くのは得意なのだ。
もちろん、それは私の役目によるようなもので。
特に解決もしない。
打ち明ける相手もどうでもいい愚痴しか私には、話してこない。
深い悩みを打ち明けられるほど、私は誰とも親しくはないのだ。
「そうね。ただ、ちょっとだけ、人の話を聞くのが得意なだけよ」
そう言いながら、私は内心で考えていた。
人々の悩みを聞き、その心の機微を理解すること。
その奥にある真の悩みを推察すること。
それが青春という舞台から、私へ与えられた役目なのかもしれない、と。
「そうかな?」
ハナちゃんは少し納得がいかないような表情を浮かべた。
その様子を見て、私は話題を変えることにした。
「そういえば、ハナちゃん。今日の手芸部はどうするの?」
「え?ああ、そうだった!」
ハナちゃんの表情が変わった。
「一緒に手芸部に行かないと。」
「そうね。一緒に行きましょ?」
「うん。終わったら一緒に行こう!」
おっちょこちょいなハナちゃん。
今日は手芸部に来るらしい。
それは楽しみだ。
ハナちゃんも私も手芸部という部に所属している。
その手芸部には、名簿上には十数人いるはず、なのだけど。
主に部室に来ているのは、私とハナちゃんがほとんどだ。
時々、他の部員も来るのだけれど、そこまで常連というわけでもない。
それに部長って誰だろう?
ってくらいに存在感が無い。
もしかしたら、私が実質的に部を仕切っているのかもしれない。
少なくとも、部活動の出席順位では私が一番だろうな、と思った。
手芸部では、私は教室で挨拶するかのように、様々な女子生徒から話を聞いている。
お互いの名前すら怪しい表面上の関係。
しかし、だからこそ、どうでもいい話が聞ける。
それは聞き役の私にとって、願ったりかなったりだ。
やっぱり、部活動を楽しんでいるのは、私だ。
そう思った。
予鈴のチャイムが鳴った。
「じゃあ、また!」
「うん。ハナちゃん。」
ハナちゃんが私の机から離れていく。
その様子を見ながら、私は今日の部活動は華やかだな、と感じた。
私は、休み時間の教室にいた。
周囲は喧騒に包まれ、クラスメイトたちの楽しげな笑い声や話し声が環境に満ち満ちている。
彼らは、まるで鳥たちが囀るかのように、その存在を示していた。
一言でいうならば、これこそが青春というものだろう。
生命力にあふれた、正の力めいたもの。
しかし、私にはそれらが遠くから聞こえてくるような気がしていた。
もちろん、その情景には私も含まれている。
そんな私は、ごく一般的な女子高生だ。
この教室にいるのだから、当然といえば当然だ。
ここは部外者立ち入り禁止の空間。
まるで青春を送るものにしか、入ることが許されない場所のようだ。
その中で、私は微妙な距離感を保っている。
クラスメイトたちと同じ制服を着て、同じ教室で授業を受け、同じ空気を吸っている。
けれど、どこか一線を引いているような感覚がある。
私はこの高校に所属し、学校に通い、クラスに属している。
教室では自分の机が与えられ、学校の規則に従う。
この喧騒の中で、私一人だけが浮いているように感じるが、それは決して不快ではない。
むしろ、この距離感が心地よいとさえ思える。
私には私の距離感があるのだ。
それは私の持つ感性、そしてこれまでの学校での振る舞いの結果なのかもしれない。
ただ、一つだけ確実なのは、私もまた青春の真っ只中にいるということだ。
もしこの状況を絵画で例えるならば、私は背景に描かれている無名な人物の一人だろう。
それは、絵の中心で輝く主役たちの存在とは対照的だ。
しかし、中心が輝くのは背景があるからこそ。
彼らが光り輝けば輝くほど、私の存在は薄く陰っていく。
ただ、それらは陰と陽の関係のように、決してお互いがなくなることはない。
お互いが存在するからこそ、この教室という小さな宇宙のバランスが保たれているのだ。
その陰の部分を担う存在として、私は自分の役割を果たしている。
私の目や耳は、自然と教室の隅々の情報を収集していく。
クラスメイトたちの一つ一つの仕草、表情の変化、言葉の抑揚。
それらの情報が私の中で溜まっていく。
暇を持て余している私は、それらを心の中で分析していく。
観察から得た情報から、私は周囲の状況を推測する。
誰がどんな性格で、誰と誰が仲が良くて、誰が誰のことをどう考えているのか。
人間関係の綾を、私は頭の中で推測を進めていくのだ。
そんなひと時。
ふと、教室の後ろの方に目をやると、藤原カリンの姿が目に入った。
彼女もまた、この賑やかな空間の中で一人静かにしている。
私たちの役割は似たようなものなのかもしれない、ふと、私はそんなことを考えた。
窓際の席に座った私は、静かに本を開いていた。
ページをめくる音さえ、この騒がしい空間では飲み込まれてしまいそうだ。
それでも、私は気にせず読書に没頭していた。
読んでいる本は、人間関係の機微を描いた青春小説だ。
登場人物たちが織りなす複雑な関係性に、私は引き込まれていく。
彼らの悩み、喜び、葛藤。
それらはどこか滑稽で、同時に痛々しい。
それはまるで現実のつまらないところを無くしてしまったような。
濃度100%の還元ジュースのようなもの。
それは、ドロドロに煮詰まった現実のようで、ある意味、現実よりも現実らしい。
そんな現実の塊を読み流しながら、私は思った。
これが私の現実でなくて良かった、と。
「アイリちゃん、また本、読んでるの?」
突然、明るい声が耳元に届いた。
その声には、私の名前である、アイリという名が含まれている。
…私を呼んでいる。
顔を上げると、茨木ハナが私の机の前に立っていた。
茨木ハナは、私と同じクラス、同じ部活に所属する女子生徒だ。
同世代と比べると、ちょっと小柄な体型だけど。
それがまたハナちゃんらしい。
ハナちゃんというのは、彼女への呼び名だ。
だから、というのはおかしいけれど。
そんなハナちゃんと私は、友達だ。
そう、友達なのだ。
桔梗アイリと茨木ハナは同じ手芸部に所属する、友達。
この教室において、間違いなく私たちはそういう関係だった。
友達である私たちは、普段、休み時間や部活動中に話をする。
そして、一緒に学校から帰るときもある。
だから、私は知っている。
ハナちゃんは、底抜けに明るい。
前向きで、ひたむきで。
こちらを覗き込んでくるハナちゃんの笑顔は、まるで太陽のように輝いている。
「ええ。だって、面白いわよ?この本?」
私は、ハナちゃんにそう返事をしながら、本をパタンと閉じた。
「ふーん?それ、どんな本なの?」
「人間関係を描いた小説。友情や恋愛、そういったものがテーマになってるの」
「へぇー、アイリちゃんらしい!」
私の前にいるハナちゃんは、何かに感心したように続ける。
「私は本を読まないから、難しいな、って。」
「そんなことはないわ。この前の国語のテスト、ハナちゃんと私の点数、同じだったよね?」
「うーん?そうだけど。そうだけどさ。」
ハナちゃんは、なんて言っていいのか分からないみたい。
「小説読むの、難しいもん。」
「そうかしら?」
私は、ハナちゃんに、なんて言えばいいのか思案した。
簡単?
いや、そんな説明じゃダメだろうな。
「人の心って、複雑で面白いと思うの」
「うん?そうだね?」
私の言葉に、ハナちゃんは首を傾げた。
「この読んでいる本にはね、そういう人の考えていることが書かれているの。」
「そうなんだ。」
「だから、読んでいるとすぐに面白さがわかるわ。」
私は、ハナちゃんに説明をする。
この説明でどうだろうか?
「…うーん?そうかなー?」
あまり、共感されなかったみたいだ。
「ハナちゃんだって、噂話とか好きでしょ?」
「えー。まー、そのー。明るい話なら…好きかな?」
モジモジとしながら、ハナちゃんが同意する。
実際、ハナちゃんはゴシップが大好きだ。
…確かに、それを自ら大っぴらに認めるのは、確かにどうかと思う。
それが今の態度に現れている。
「…でも、本当にアイリちゃんって、いろいろな話を聞いているよね。私なんて、周りのことなんてあまり気にしないのに。」
「そうかしら?ハナちゃんの方が、私よりも話している人が幅広いと思うけど。」
私は、話を広がらないように、そう返事をする。
「そんなことないよ!」
「そう?」
「だって、アイリちゃんがこの間、言っていたこと。私、知らなかったもん!」
えっと、それってなんだっけ?
私は思い起こす。
一緒に帰ったときのこと?
いや、違う。
…ああ、そうか。
先週の出来事のことを言っているのね。
「ああ、あれのこと?あの二人が付き合い始めたって話?」
ハナちゃんは目を丸くした。
「そう!それ、それ!アイリちゃん、どうやって知ったの?」
「ただの偶然なのよ。だって、二人が図書室で話しているのを聞いちゃっただけ」
それはそう、本当に偶然だった。
小声で、とはいえ。
そんな場所でそんなことを話す、二人もどうかと思うんだけど。
「ふーん。なるほど。やっぱり、アイリちゃんは凄いね!」
ハナちゃんは感心したように言った。
…そう。
それは、あの静かな雰囲気の図書室で。
二人の話し声が聞こえないはずがないのだ。
あの二人にとっての問題は、周囲に私がいたことを確認していなかったことだろうけども。
「でも、あの二人はアイリちゃんへ相談したりはしなかったんだね!」
「え?どういうこと?」
ハナちゃんの言葉に、私は少し考え込んだ。
いやいや?
ある意味、盗み聞いていたようなものだから!
どこかハナちゃんが勘違いしているような?
「あのね?」
私が弁解しようとしたとき。
ハナちゃんは自分の世界に入ったように、うっとりとした表情で私を見ていた。
「えっと?ハナちゃん?」
「アイリちゃん!やっぱり、アイリちゃんは凄い!」
???
私は首を傾げる。
「だって、二人のキューピットになったんでしょ?」
「えっと?」
「私ならできないよー。」
論理の飛躍。
どうやら、ハナちゃんの中では、私が二人を引き合わせたことになったらしい。
「あのね。ハナちゃん。あの二人はね。私が知った時には付き合っていたのよ?」
「えー?でも、アイリちゃんっていつも誰かの相談に乗ってるイメージだよ?」
「そうかしら?」
確かに私は、人の愚痴を聞くのは得意なのだ。
もちろん、それは私の役目によるようなもので。
特に解決もしない。
打ち明ける相手もどうでもいい愚痴しか私には、話してこない。
深い悩みを打ち明けられるほど、私は誰とも親しくはないのだ。
「そうね。ただ、ちょっとだけ、人の話を聞くのが得意なだけよ」
そう言いながら、私は内心で考えていた。
人々の悩みを聞き、その心の機微を理解すること。
その奥にある真の悩みを推察すること。
それが青春という舞台から、私へ与えられた役目なのかもしれない、と。
「そうかな?」
ハナちゃんは少し納得がいかないような表情を浮かべた。
その様子を見て、私は話題を変えることにした。
「そういえば、ハナちゃん。今日の手芸部はどうするの?」
「え?ああ、そうだった!」
ハナちゃんの表情が変わった。
「一緒に手芸部に行かないと。」
「そうね。一緒に行きましょ?」
「うん。終わったら一緒に行こう!」
おっちょこちょいなハナちゃん。
今日は手芸部に来るらしい。
それは楽しみだ。
ハナちゃんも私も手芸部という部に所属している。
その手芸部には、名簿上には十数人いるはず、なのだけど。
主に部室に来ているのは、私とハナちゃんがほとんどだ。
時々、他の部員も来るのだけれど、そこまで常連というわけでもない。
それに部長って誰だろう?
ってくらいに存在感が無い。
もしかしたら、私が実質的に部を仕切っているのかもしれない。
少なくとも、部活動の出席順位では私が一番だろうな、と思った。
手芸部では、私は教室で挨拶するかのように、様々な女子生徒から話を聞いている。
お互いの名前すら怪しい表面上の関係。
しかし、だからこそ、どうでもいい話が聞ける。
それは聞き役の私にとって、願ったりかなったりだ。
やっぱり、部活動を楽しんでいるのは、私だ。
そう思った。
予鈴のチャイムが鳴った。
「じゃあ、また!」
「うん。ハナちゃん。」
ハナちゃんが私の机から離れていく。
その様子を見ながら、私は今日の部活動は華やかだな、と感じた。