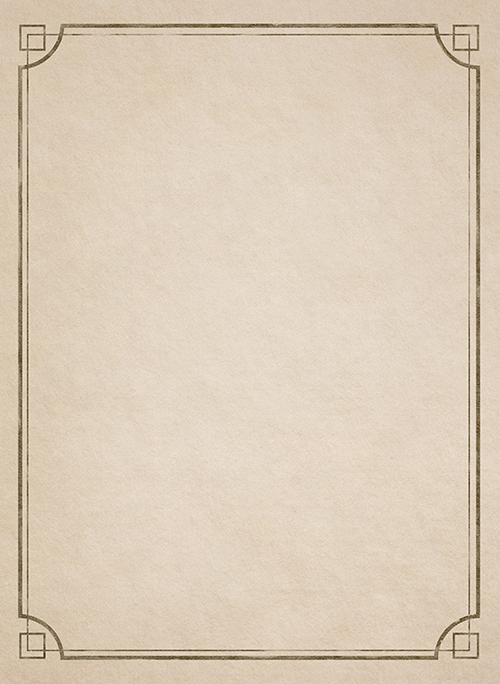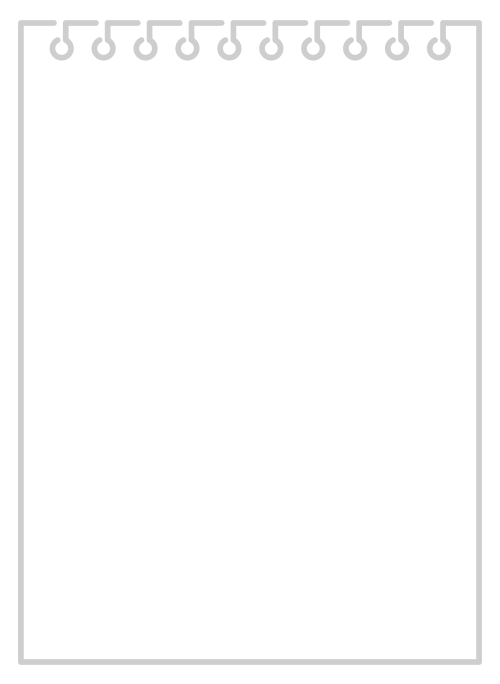今までとは違い、少し出すのを躊躇うように顔を顰めて私の前にそれを差し出した。
真っ白な紙に黒い文字が横に連なっている。
「お前の、妹は、殺した。陽炎の中に、眠る」
『かげろう』
声出した瞬間、恐怖のようなものが体の内から這い上がってきた。唾を飲み込んで私は咄嗟にそれを裏返して見えないようにする。
この連なる文字がどういう意味かも理解していないのに、だ。自分でもよく分からない。
「お前、本当に記憶なくしてんのか」
「…どういうことですか」
「警察が動かない理由はもう一つあると俺は思う」
ひっくり返した紙を私の視界に入るように再び表にしたその男は『殺した』と並んでいる文字を人差し指でさらりと撫でる。
「大きな権力が阻んでる、とかな」
「意味が分かりません」
「お前は失踪中、知ってはいけないことを知ってしまって記憶喪失のフリをしてる」
向けられた人差し指。
そんなわけないのに。記憶をなくしたことでどれだけ不安で、毎日どんな思いで生きているかなんてこの男には分からないだろう。分かって欲しいなんて思っていない。
「っていう憶測。フリーライターっぽい思想だろ」
「…私は失踪直前のこと、失踪中のことは何も覚えていません。もういいですか」
「まあ待てや、これについて気にならないのか」
紙をヒラヒラと揺らして私にそう問う男。
私は小さく息をはく。
肯定も否定もしない私に痺れを切らせた男は勝手に話し始めた。
「俺の妹は1年前に失踪してる」
低く怒りを押し殺すような声を放ったその男。この紙に書かれている『妹』というのは彼の妹ということなのだろう。
つまり、この紙に書かれていることが本当なら。
「失踪する前、メールが届いた『今までありがとうお兄ちゃん。自分の力で生きてみます』ってな」
「でも、」
「そう、自分の力で生きた妹は殺されたかもしれない。この手紙は2週間前に届いたものだ」
「警察には行ったんですか」
これを見せれば事件性を疑って絶対に動いてくれるはずなのに。
「やつらは動かねえよ。妹が失踪した時にそれは思い知らされた」
「で、でも、これは、」
「死んでねえ」
「泉さん」
「妹は、実里は、死んでねえ。俺はこの手紙を送ったやつを突き止めてぶっ殺して、そんで妹も探し出す」
大切な人が生きていないかもしれないという恐怖や不安を怒りに変えるように男は拳を握りしめた。
何も言えなくなった私に男は紙や記事をカバンの中に入れると、小さく息をつく。
テーブルに運ばれてきたナポリタンを男は視界に入れた。
フォークを握りしめて、その先を私に向ける。
「本題に入ろう。お前の失踪のことについてだ」
「待ってください。妹さんと私の失踪はそもそも関係していない可能性はありませんか」
「まあそうかもな」とナポリタンを一口頬張った男。
「そもそも俺の妹は失踪した時ハタチだ。女子高生ではない」
「じゃあなんで」
「お前が発見された河原と俺の妹が最後に目撃されたところが近いから」
「それだけですか」
「それだけだ」
思わずため息をつけば、男は舌打ちをもらす。
「言ったろ、こうやって連続して若い女が失踪してる中、お前は帰ってきてる。俺にとっては藁にもすがる思いなんだよ」
確かに同情はするけれど、私は何も役にたてないだろう。どうやってもこの人のために、そしてこの人の妹のために私は何もできない。
「私は、今、自分のことで手一杯なんです。申し訳ないですが…」
「お前、自分のことを知りたいって思わないのか」
鞄を掴みかけた手がとまる。
知りたい、なんて、思わない。
だって、記憶が消えた理由はそれほどの嫌な出来事があったからで
私はそれをわざわざ思い出したくはない。絶対に。
無駄に傷つくだけじゃない。
「言い方を変える。お前の記憶が妹の手がかりになるかもしれないんだ」
「ごめんなさい、おそらく力にはなれないと思う」
私は男の顔を見ないまま、早口でそう言って逃げるようにその場を去った。