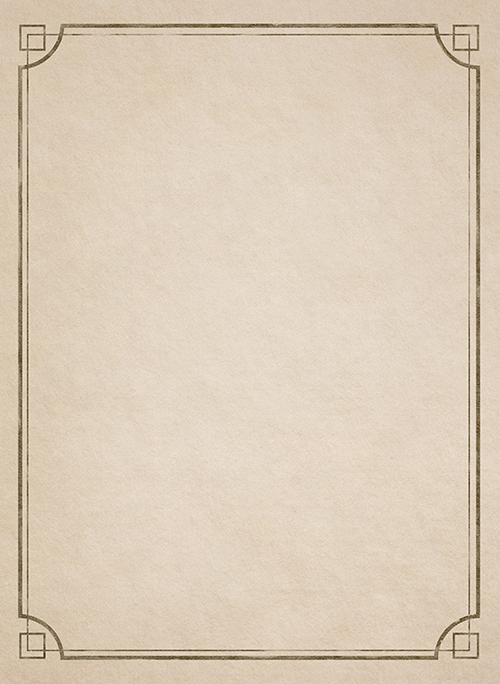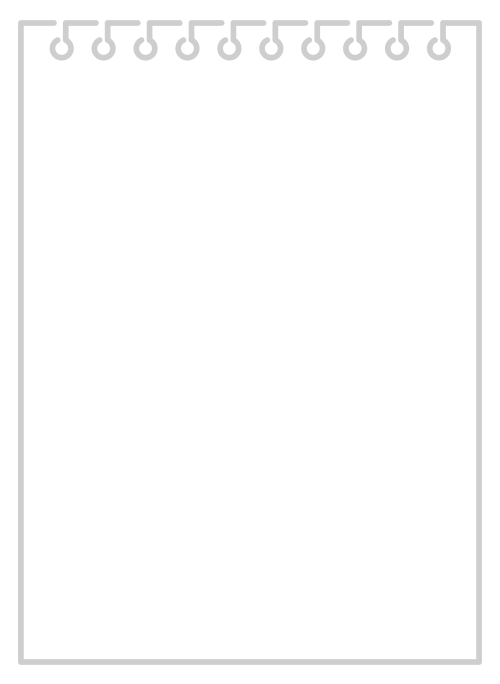「っ!」
目を開けた。
一瞬みた走馬灯のようなもの。
夢の中の光景のように思えたが、時間は一瞬だった。
周りを見渡す。原島先輩、久松先生、そして廊下に飾られている花瓶。
私は立ち上がって花瓶を掴んで、地面に叩きつけた。
「なにやって!」
原島先輩が驚いたように私に手を伸ばすが私はそれを花瓶の破片を掴んで振り回し、そのまま自分の太ももに突き刺す。
痛さで、なんとか意識を冴えさせた。
太ももから血が滲んでいく。
「萌香ちゃん何を考えてるの、言ったでしょ、あなたは例のものの場所を教えてくれさえすれば助かるのよ?」
そう言った久松先生。
泉さんを思い出した。こういう時こそ不敵に笑い、余裕の笑みを浮かべる。
悪役のように。
原島先輩の腕を掴み、そのまま首に手を伸ばして血のついた花瓶の破片を突きつけた。
「…要は、カヨラの教祖は久松先生で、記憶で人を陥れている主が原島先輩ってことね」
「萌香ちゃん…」
「人質をとるなら、原島先輩が正解ですね」
手に力をこめる。
原島先輩が苦しそうに手を上げた。
「立見さんに、僕は殺せない。君はどうやっても地獄におちる覚悟なんてないだろ」
「やってみないと、分からない」
原島先輩の首から一筋の血が流れていく。
久松先生はその状況を見て、慌てたように私に近づく。
「近づかないで!殺しますよ、本当に」
周りには、信者たちが騒ぎをききつけ集まっていた。
ーーー自分は、『天使』か『悪魔』か。
調べ始めてそんなことを思い悩んだことがある。
もう、どうでもよくなった。
誰かによっては私は『悪魔』であり、誰かによっては私は『天使』にもなる。
外から見た自分がどうなろうと、もう、どうだっていい。私は今、私自身の正義でここに立っているんだから。
「萌香ちゃん、落ち着いて」
「落ち着いてますよ、教祖ではなく原島先輩を人質にするくらいにはね。現に、あなたたちは私に手を出せなくなってる」
「っ」
「原島先輩がいなくなれば、記憶を消去することも書き換えることもできなくなりますもんね」
久松先生や、他の信者たちが青ざめていく。この人たちにとって私は幸せを奪う悪魔のような存在なのだろう。上等だ。
周りを見渡した。
取り囲んでいる信者の中、再び上に挙げられた銃。私の視界に入った瞬間それは降ろされた。
ーーーいる、私の味方。
「私の要求は、ここでおこなわれている売春を公にすること!」
息を呑む人もいる中で何も知らない人たちが「どういこと?」と騒ぎ立てる。
久松先生は、「静まりなさい」と声を出すが騒ぎはおさまらなかった。
そして、久松先生はため息をついた。
「もういいわ」と。
そして、服の中を探りゆっくりと取り出したそれ。
「私は、あくまで何も手を加えていない、汚れのない教祖でいたかったけれど、ここを守るには仕方がないわね」
銃口がこちらに向けられる。
原島先輩を突き出すようにして、私は手に力を加えた。
「原島先輩も死にますよ」
「そうなったら、そうねえ、時間はかかるけど、もう1人原島くんのような人を作り上げるしかないわね」
眉間に皺をよせる。原島先輩が「そんなのバカげてる」と掠れたような声を出した。絶望の声色だった。
カチャリと銃の音が鳴る。
私は、目を瞑らなかった。
死んでも、実里さんが、泉さんがきっとやってくれると思ったから。
すべてがスローモーションのようにみえる。
放たれた銃弾、耳や目を塞いだ周りの人たち。
一度の銃声のあと、紛れるように聴こえたもう一つの銃声。
「っ!」
私は誰かに強く引き寄せられて地面に転がった。
あちこちは痛いものの、死ぬほどのものではないことを悟って、ゆっくりと目を開ける。
私に覆い被さるようにして私を見下ろしたその人。
「泉さん!」
名前を呼べば、私の体を守るように頭に手を回したあと、周りを見渡して声を出す。
「久松は!」
「確保!」
返事をしたのは、高橋さんだった。
泉さんの腕の間から見えたのは、久松先生が肩を抑えて倒れ込んでおり、高橋さんがそれを捕まえている様子だった。
そしてもう1つの銃弾は、壁に穴を開けており高橋さんが久松先生の肩を捉えたのが幾分か先だったことが伺える。
再び泉さんの方に顔を向けると、泉さんは気まずそうに私を見て顔を逸らした。
「高橋は、潜入調査が得意だからな。お前がカヨラに連れていかれたとふんで、急いで来たんだ。俺も、こうやって」
白い服を軽く持ち上げてそう言った泉さん。
私は吹き出すように笑った。
「似合わないですね、白」
「うるせえよ」
泉さんは、体勢を変えないまま項垂れるように私の首元に顔を埋めた。
「…悪かった、お前を疑ったのは本心じゃない」
「分かってます」
「腕、ごめんな」
「大丈夫です」
「お前、大した度胸だよ、これでカヨラを潰せる」
その言葉は、すべてが終わったことを示唆していた。
高橋さんに手錠をかけられ、連れていかれる久松先生。
私たちは体をおこして、それを見つめていた。
そしてしばらくして、私は慌てて泉さんの腕を掴む。
「実里さんとは?」
「ああ、走って外にいく姿をみた。おそらく外で警察に保護されてる」
よかった、と安堵する。
実里さんも無事だ。
血だらけになっている足を泉さんに止血してもらい、
なんとか立ち上がって外に出る。
外では、蝉が鳴き夏を知らせるような太陽が照りつけていた。
そして警察に保護されて、心配そうな目で中を伺っていた実里さんが私たちに気づいてこちらに駆け出してきた。
「お兄ちゃん!萌香ちゃん!」
まとめて抱きしめられ、私たちは苦笑いを浮かべる。
「よかった、無事で」
「実里こそ」
「うん、ありがとうお兄ちゃん」
微笑みあっている兄妹をみて、ああ本当によかった、やっと、終わったと安堵する。
ここから先は私だけで充分だ。
「泉さん」
「ん?」
「ポケットに入っているもの、一度私に貸してくれませんか」