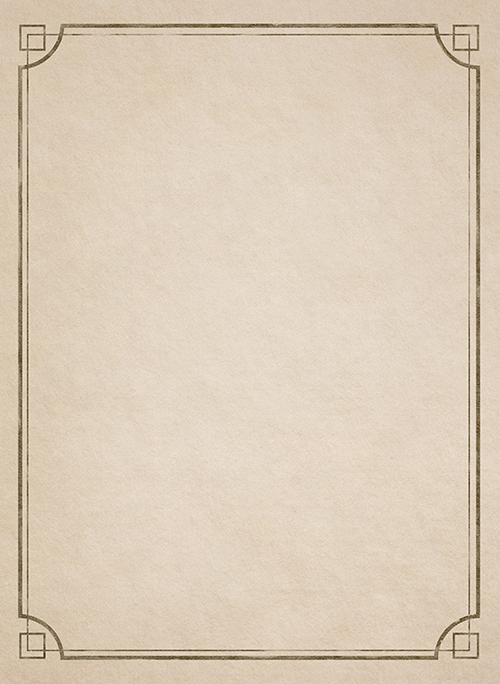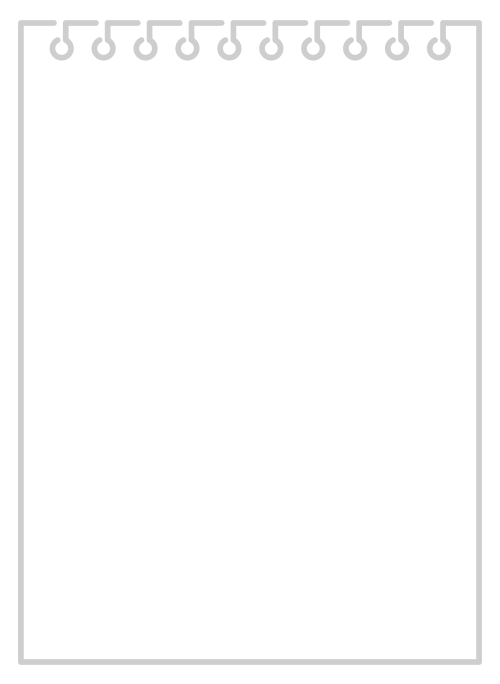「記憶がないのに、自分を調べあげるなんてたいしたものだね、立見さん」
原島先輩がそう言って、私に近づく。
実里さんを守るようにして私は原島先輩を睨みつけた。
「やっぱりあなたはカヨラの人間」
「あはは!甘いね、何度も言ってるけど僕は『記憶』しか興味がない。いわば君たちは僕の実験体に他ならないってことだよ」
「っ、どういうこと」
「記憶を消去して改ざんする、僕は人間の未知な可能性を研究したいだけ。その大事な研究場所が君たちの無駄な告発で潰されたくないだけなんだよ」
原島先輩はそう言って私に手を差し伸べる。
もう、絶対に何も失わない。記憶も、大事な人も、すべて。
「僕以外の人たちは、ちゃーんとカヨラを信仰して、人々が救われるように清き心で日々を生きているんだよ、分かる?」
何が清き心だ。
と、サラと久松先生を睨みつけた。
「売春させて、記憶を消して、無理矢理カヨラにいれようとしたの奴らの何が『救い』よ、笑わせないで」
そう言えば、サラは片手を口元にもっていき小さく笑った。
「何がおかしいの」
「無理矢理ってひどい言われようね、私は求められたから答えただけだよ、真由も、広菜も、自分から頼んできた」
だからって人の弱さを利用するなんて絶対に間違っている。
実里さんが後ろで小さく震えていた。その手を握る。
ーーー次は離さないように。
原島先輩の後ろの人たちが私たちを捕まえるためにゆっくりとこちらに近づいてきた。
実里さんだけでもいい。きっとこの人たちは私が証拠がある場所をはくまで、私を殺しやしない。
もう一度記憶を失っても、泉さんがきっと私の前にやってくる。大丈夫、きっと、大丈夫だから。
そうだよね、広菜。
走り出そうとした、その瞬間だった。
大きな銃声が響き渡る。
それは、原島先輩でもサラでも、久松先生でもない。
もっと、後ろの方で聞こえた。
姿は見えない。ただ、複数の中の1人の銃を持った手が上に掲げられていた。
その銃口が原島先輩に向く。
「裏切り者は、あちら側だけにいるとは限らないよ、原島くん」
そう言って出てきたこの人。
私は、その人を知っていた。
暴力に耐えていた彼。
私は、2度、彼を助けたことがある。
「いじめられた記憶は失ったけれど、不思議と助けられた記憶は消えなかったんだよね」
裏庭。私は彼に暴力をはたらいたやつの背中にリンゴジュースのパックを投げた。
1度は、広菜と2人で、2度目は記憶を失った私が。
「あの時はありがとう。よく覚えてないんだけどさ、俺も、君みたいに強くなりたいって、その気持ちは忘れてないよ」
その先輩が私を見つめてそう言った。
銃がカチャリと鳴る。
原島先輩に向けられたそれに、周りは身動きが取れなくなっていた。
そして、もう一度銃を上に向けて放った。
スタート合図のように。
「行って!はやく!」
銃を持った先輩がそう私に叫んだ。
私は、実里さんの手を掴んだまま走り出す。
白い扉を抜けて、迷路のような場所を一気に駆け抜けていく。
「実里さん、何があっても外に出て、ここに、縛られちゃだめだよ」
「萌香ちゃんは!」
「私と一緒にいると絶対につかまっちゃう!あいつらは、私がつかんでる証拠を探してるんだよ!
大丈夫、泉さんがきっと実里さんをむかえにくる!!」
「ダメだよ、一緒に」
足に力が入らなくなり、私は地面に転がった。
「っ、萌香ちゃん!」
視界がゆらゆらと揺れていく。
自ら目を覚ますように頭を振るがそれはなおらない。
実里さんの手を離して私は、地面に手をついて力を振り絞る。ここで倒れたら絶対にダメだ。
まだ、やるべきことが残っている。
「まさか原島さんに薬を飲まされたの!?」
「わ、からない」
「とりあえず外に出よう!はやくしないと、」
「大丈夫だから、実里さん、いって、お願い」
実里さんは涙で顔をぐちゃぐちゃにしながら、私の腕を掴む。首を横に振って「嫌だ!」と子供のように叫んでいた。
「広菜ちゃんも助けられなかった!次は絶対に助ける!!」
そう言った実里さんに、私は腕を振り払った。
なんとか足に力を入れて、実里さんに背中を向ける。
「萌香ちゃん!」
「大丈夫、次は何も失わない」
近くまで原島先輩が来ていた。手には血がついている。
両手を広げた。
「実里さん、行って!!」
実里さんは、私の背中で泣きじゃくりながら走り出した。
笑顔でこちらに近寄ってくる原島先輩が揺れている。
自分が真っ直ぐに立っているのかも分からない。
「意外と手こずらせるね、君は」
地面に膝がつく。
近くに来た原島先輩は私に目線を合わせるようにしゃがんだ。
「ただ、満尾広菜が残したものがどこにあるかを教えてくれればいいんだ」
「っ、」
「そしたら、すべて忘れて楽になるんだよ」
冷たい手のひらが私の顔に添えられる。
荒くなる呼吸。
視界がシャットアウトしないように私は自らの舌を強く噛んだ。
「あの美術室で、君は徳田サラに復讐しようとしたのが間違いだったね。
ただ、満尾広菜が残したものを手に持っていればよかった。そしたら、地獄で満尾広菜に会えたのに」
やっぱりあの時、私は捕まってここにまた連れてこられたあと記憶を消された。
原島先輩の腕の傷は私が最後まで争った跡なのだろう。
原島先輩はゆっくりと立ち上がる。
「はやく気を失いなよ、その薬結構強力だよ?」
「っ、いや、だ」
「強情だなあ、ね、教祖様どうする?この子」
原島先輩が振り返った。
後ろからやってきたのは、久松先生だ。
そして、いつも私に向けていた穏やかな笑みの仮面を貼り付けて私の前に座る。
「もう、楽になったら?」
私は、目を瞑った。