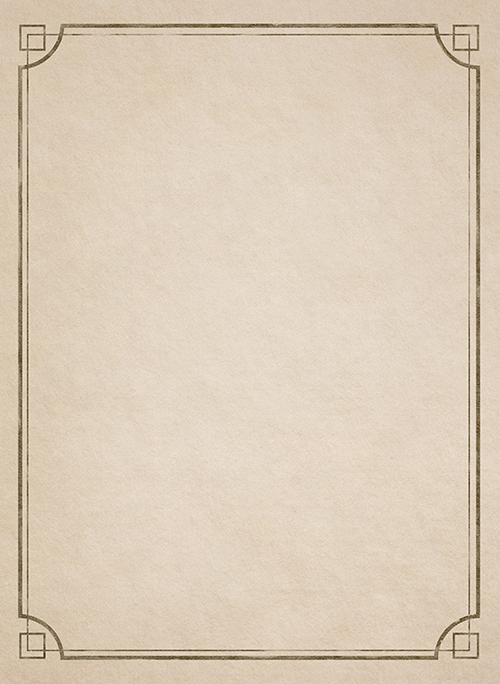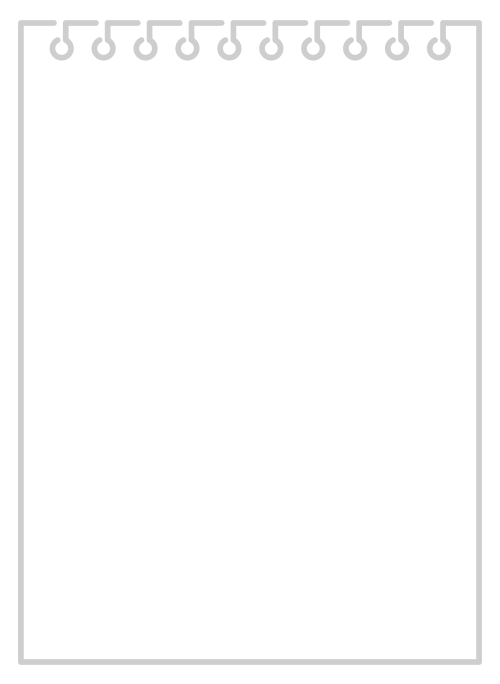でも、広菜はあてたあの手紙だけは真実だって信じたい。カヨラは最低最悪の組織。
しばらく走ったあと私の手を離し、息を整えた原島先輩。
「いやー、久々に走った」
そう言って私に笑いかける。
「危なかったね」
と、涙と汗のせいで頬にへばりついた私の髪を指先でゆっくりと耳にかけた。
触れた指先が冷たくて、身を一歩引く。
「あなたは、カヨラの人間ですよね、原島先輩」
「…違うと言っても君は信じないでしょ」
「っ、だって、記憶の話をしてたじゃない」
原島先輩は近くにあったベンチに、「まあ座りなよ」と手を差し出した。
自身を落ち着けるように息を吐いて、私はベンチに腰を下ろす。
「飲み物買ってくるから、ちょっと待ってて」
そう言って原島先輩が近くの自販機までかけだしていく。そんな背中姿を見つめながら私は、また溢れ出す涙を手の甲で拭う。
地面に倒れ込んだ泉さんの姿が焼きついて離れない。戻りたい。
私は実里さんを傷つけたかもしれないけれど、私は、私は。
スマホが振動する。
泉さんかもしれないと、画面をみればそこに表示されたのは『高橋さん』だった。
「…もしもし」
「萌香ちゃん、よかった繋がって、すぐるとは一緒?」
高橋さんは、あの犯行文の筆跡のことをしらない。
「うっ…」と堪えられなくなった泣き声が口からもれた。
「泉さんとは、一緒じゃないです」
「家にはいる?」
「いえ、外で」
「そっか」と高橋さんの声が低くなる。
なんでそんなことを聞くんだろう。
「君が調べて欲しいって言っていた美術室に残された『血』なんだけど」
戻ってきている原島先輩に背を向ける形で私は声を顰めた。
「何か分かりましたか」
私の問いかけに高橋さんは「うん」と、そして、息を吸った。
「原島 蓮のものだと分かった」
あの美術室で私が復讐しようとしていたのは、サラと、もう1人いたかもしれないと思った。それが真由なのか、晴美なのか分からなかった。
小さく飛び散った血が、誰のものか分かれば少しでも真実につながる。
あの場にいたのが原島先輩だとしたら、なぜ。
「立見さん」
「っ」
振り返った瞬間。
スマホが地面に転がる。
視界は、真っ暗になった。