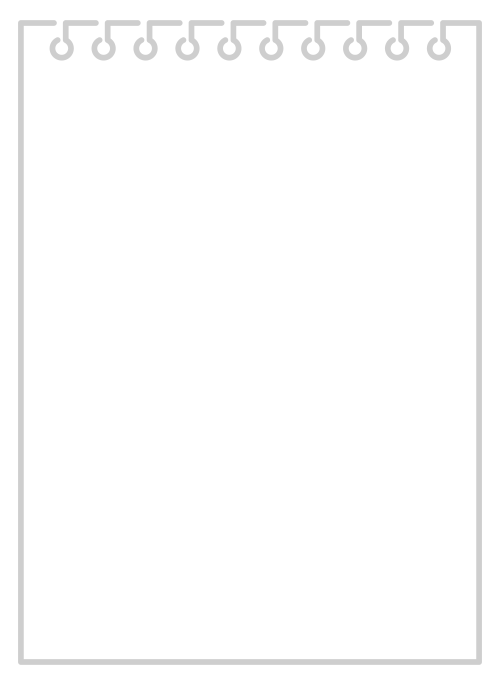夢に出て来る知らない少女。
帰ってきた娘に過保護なお母さんとお父さん。
無事に学校に来た私をみて泣いて喜んでくれたサラたち。
私の知らない記憶を知っているかのように煽ってきた見ず知らずの先輩、原島。
頭の中で彼らを順番に思い出していく。
重々しいため息をついた。
「疲れた」
吐かれた息とともにそんな言葉が空中で散っていく。
今日はもう一つ、試練があった。
スマホで時間を確認する。急がないといけない。
そして、少し歩みを早めた時に気づいた。
「っ」
誰かにつけられている。
足を止めて振り返るが誰もいない。
落ち着け、落ち着け。と何度も自分に言い聞かせるが恐怖で心臓が大きく音をたてる。
耐えきれなくなって私は走り出した。
後ろからついてくる足音も合わせて走り出す。
本当に気のせいじゃなかったのだと気づいた時私は額から頬に伝う汗をそのままに、無我夢中で走った。
ーーーもう、消えたくない。
走りながら、私はスマホを取り出して画面をつけたが、上手く力が入らず個体が地面に転がった。
こういう時の自分の不甲斐なさに怒りを覚える。
転がったスマホを拾い上げようとしたが、足が絡まって自分自身も地面に手をついた。
もういっそのこと、次は殺してほしい。
なぜか分からないけれどそう思った。
「おい」
「ひっ」
スマホを拾い上げたものの、体は恐怖で起き上がれずに私は短く悲鳴をあげた。
目の前にいたのはフードを被った男だ。
私はこの男に連れ去られたんだろうか。そして私が逃げ出したから連れ戻しに来た、とか。
「騒ぐなよ、黙ってついてこい」
私の前にしゃがんだ男が私にそう言う。
もう逃げられないと思った。次は殺される。この人が私を連れ去って、監禁していたんだ、きっとそう。
ほら、失った記憶なんてあっけないものである。
腕を掴み、私の体を起き上がらせる。
悔しさから涙が出そうになったけれど、唇を噛んで耐えた。
しばらくして着いたその場所に私は思わず「は?」と声がもれる。
ファミレスの扉を開ければ男がフードをとった。
私の気持ちなんて知ったことかと店員が「いらっしゃいませ。何名様ですか?」と笑いかける。
「座れ」
「…」
「座れって」
荒々しく私を椅子に座らせた後、男は私の正面に座った。
フードをとりあらわになった顔は自分が想像していた姿より若かった。20代だろうか。
「手荒なことをするつもりはなかったが、こっちも必死なんだ、許せ。なんか頼むか」
「誰ですか、あなた」
開かれたメニューを端に追いやり、私は目の前の男を睨みつける。
「警戒するよな、そりゃあ失踪してたんだし。
安心しろよ、お前をどうにかしようとしてたらこんな人がいっぱいいるところなんて来ねえだろ」
「っ、なんで」
何者かも分からないこの人は、なぜ私は失踪をしていたことを知っていて、なんで私をつけたのだろうか。
男はコップ一杯の水を全て飲み干し、テーブルの上に置いた後、ふっと鼻で小さく笑う。
そして私の目の前に投げ捨てるように紙を滑らせた。
1枚の名刺だった。名前は『泉 すぐる』
「…フリーライター」
「そう」
男は私の反応なんて興味がないかのように店員を呼ぶボタンをおした。簡易な音がそこに響く。
「近辺の連続失踪、今巷でよくきくだろ、それを追ってる」
「ナポリタン」と語尾に付け加えられたのはちょうど店員がテーブルに来たからだった。
「お前、何にするんだ。安心しろ奢ってやっから」
「…大丈夫です、以上で」
呑気なものだ。素性もしれない人と一緒にごはんを食べるだなんて絶対無理。帰りたい、吐きそう。
店員が「かしこまりました」と間延びした返事をしてテーブルを去っていけばそこに沈黙がうまれた。
そして男はため息をついて、黒い鞄から何かを取り出してテーブルの上に置く。
男が私の前に差し出したのは数枚の記事だった。
ところどころ赤ペンで何かを書きなぐっている。
「今回の騒ぎ、警察は積極的に動いていない」
「なんでですか」
「お前だって身をもって体験してんだろ、まあ記憶喪失のやつに何か聞いたところで情報はでてきやしないんだろうが」
吐き捨てられたその言葉に私はむっとして男を睨みつけた。じゃあなぜこの男は私を引っ捕まえてここに座らせているんだろうか。
時間をみれば、すでに予定の時間は過ぎており私はテーブルの下でメールをうった。
『すみません、少し遅れます』
「騒いでいるのは、世間だけだ。SNSや面白おかしく噂で連続失踪事件などと言われてるが世の中に行方不明者なんてごまんといるだろ。
警察的は家出だと断定して腰を上げないのが現実」
「なぜそう言い切れるの」
「実際にこいつらは、失踪する前に家族や友人に何かしら家出の意思を伝えている」
広げられた記事を人差し指で軽く叩きながらそう言った男はため息をついて「というのは一般論だがな」と呟く。
「なんでそんな話を私にするの」
「そりゃあ、この一連の騒動で唯一生き残って帰ってきてんだからライターとしては取材しないと気が済まないだろ。
しかも失踪中の記憶がないなんて、読者の好奇心くすぐるに決まってんじゃん」
私は立ち上がってその場を去ろうとする。
シニカルな笑みを浮かべていたその男は慌てたように私の腕を掴んだ。
「よく考えろよ、一緒にお前の記憶を探してやるって言ってんだ」
「メリットはありません」
「ちゃんと話すから座れって」
強制的に再び椅子に座らせられたあと、男は鞄からまた何かを取り出した。